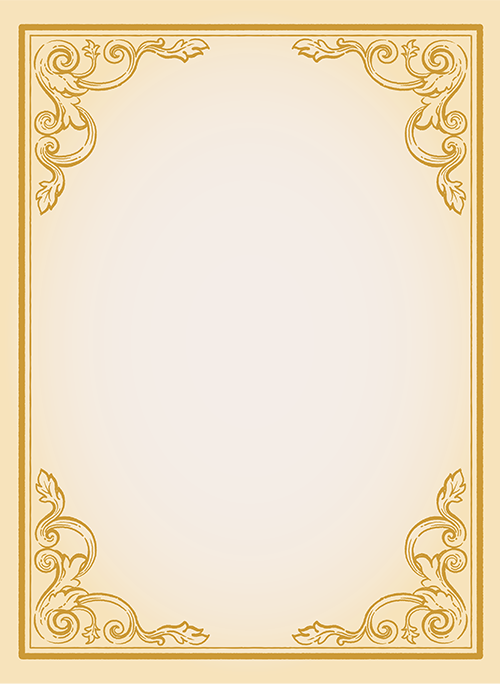進路希望調査票が配られたのは、火曜日の6限目だった。
担任の先生が淡々と説明する間、
教室の空気は重たく沈んでいた。
紙の上には、志望校と志望理由を書く欄がある。
その空白が、わたしの胸をずしりと押しつけてくる。
(第一志望校……)
ペンを握った手が震えそうになる。
わたしは、どこに行きたいのだろう。
いや、そもそも――何になりたいのだろう。
「水野さん、明日までに提出してね」
帰りがけに先生にそう言われて、
「はい」と答えるしかなかった。
家に帰ると、ダイニングには母が座っていた。
ノートパソコンを開いたまま、
すぐにわたしのかばんの中身に目を留める。
「それ、希望調査?」
「……うん」
「いつまでに出すの?」
「明日……」
母は「ふうん」と言って、再び画面に視線を戻した。
その横顔を、わたしはそっと盗み見る。
母の視線は、鋭くて迷いがない。
キャリアウーマンとしての自信にあふれている。
そんな人に、わたしの「夢」は、どんなふうに映るのだろう。
(言えるわけ、ないよ)
そう心の中でつぶやいた。
わたしの成績では、第一志望どころか、
母の思い描く進学ルートからも遠ざかっている。
漫画家になりたい――なんて、絶対に笑われる。
夢よりも現実を。
努力よりも結果を。
母はいつも、そうやってわたしを「正しく」導こうとしてきた。
でも、その「正しさ」に、わたしはもう、窒息しそうだった。
その日の夕飯は、父が作った炒め物と味噌汁だった。
「いただきます」
母と向かい合って座りながら、
わたしは、無意識に背筋を伸ばしていた。
食卓に並ぶ湯気の向こうで、
母は静かに箸を動かしている。
沈黙が怖くて、わたしが口を開く前に、
母のほうが切り出した。
「希望調査、志望校は前と同じでいいわよね?」
その言い方は、まるで確認だった。
わたしに「選ぶ」という余地はないように聞こえた。
「……ちょっと、迷ってて」
そう返した瞬間、母の手が止まる。
わたしは、急いで弁解を重ねた。
「まだ書き出してるだけで……でも、別に変えるって決めたわけじゃなくて……」
「どうして迷うの?」
母は、ごく自然な口調でそう尋ねた。
でもその声は、やっぱり冷たく聞こえた。
「成績が落ちてるから?
それとも、ほかにやりたいことができたの?」
そう聞かれて、わたしは言葉を詰まらせた。
やりたいこと。――ある。
でも、言えない。
夢を口にすることは、わたしにとって、
それ以外のすべてを捨てるくらいの勇気が必要だった。
「……ううん、なんでもない」
そう言って、わたしはご飯を口に運んだ。
母はもうそれ以上、何も言わなかった。
けれど、その沈黙が、いちばん堪えた。
「わたしの気持ち」は、やっぱりこの家では小さすぎる。
スカーフをぴんと結び直すような、
そんな気持ちで、わたしはスプーンを強く握った。
部屋に戻ると、制服のままベッドに倒れ込んだ。
ため息が、シーツの上に落ちる。
夕飯の間、ずっと息を止めていた気がした。
母と話すたび、わたしの声はどこかへ小さくなっていく。
(言いたかったのに)
言えなかった言葉が、胸の奥に残って、
重たく膨らんでいる。
進路希望票は、まだかばんの中にある。
空欄のままの第一志望欄を思い出すだけで、
心臓が音を立てる。
(わたしは、本当は……)
その続きを、声に出すのがこわい。
スマホが震えた。
アリサからのメッセージだった。
「提出って明日だっけ? 書けた?」
「てか、お母さんとなんかあったでしょ?」
心を見透かされたみたいで、思わず笑ってしまった。
「なんにも言えなかった。
また『がっかりした』って顔されるのがこわかった」
「でも、ほんとは……描いていたいって思ってる」
返したあと、スマホを抱えたまま、しばらく動けなかった。
アリサからの返信は、思ったよりすぐに届いた。
「いいじゃん、それ。描いていたいって思えるって、めっちゃすごいことだよ」
いつものアリサの笑顔が浮かんで、涙がぽとり、一粒こぼれる。
わたし、描いていたいよ。
自分の声が、心の中で響いていた。
夜、机に向かってノートを開いた。
ペンを持つ手はまだ少し震えていたけれど、
それでも、描きはじめてみた。
いつものように、無言のまま線を重ねる。
でも今夜の線は、いつもと少しちがっていた。
そのコマの中の女の子は、制服を着ていた。
けれど、そのスカーフは、きゅうくつじゃなくて、
少しゆるんで、風になびいていた。
彼女は、誰かに言おうとしている。
「わたし、描いていたいんだ」
「わたし、これがすきなんだ」
わたしの手は、そのセリフを吹き出しに書いたあと、ふと止まった。
(ほんとうに、言えるのかな)
ページの上では堂々と夢を語る女の子。
でも、わたしはまだ、母に一言も言えていない。
描くことでしか、自分の想いを伝えられない自分が、
少し悔しくて、でも少し、いとおしかった。
机の上のランプの光に照らされながら、
わたしは、描いたページを見つめた。
その子は笑っていた。
ちゃんと、前を向いていた。
(わたしも……)
心の中で、そうつぶやいて、もう一枚、ページをめくる。
誰にも見せなくていい。
誰にも認められなくてもいい。
まずは、自分で、自分の気持ちを認めてあげるために。
わたしは、ペンを持ち直した。
小さな決意の音が、紙の上にすうっと走った。
進路希望調査票は、まだかばんの奥に入ったままだった。
次の日の朝も、提出はしなかった。
勇気がなかったわけじゃない。
ただ、まだ言葉にできる準備が、できていなかっただけだ。
母は何も言わなかった。
提出日が過ぎても、何も聞いてこなかった。
けれどその沈黙が、逆にプレッシャーになって、
胸の中に小さな波紋を広げていた。
アリサと会ったのは、放課後の電車の中だった。
「どう? 書けた?」
ノートを見せながらそう聞かれて、
わたしは、首を横にふった。
「……まだ、ちょっと怖い」
「うん、わかる。でもさ、描いてたでしょ? 昨日」
「え?」
「LINEで『描いてたい』って言ったあと、絶対描いてたでしょ。
なんかそういう顔してる」
わたしは笑った。
「……ばれてるんだね、やっぱり」
「描いてるときの顔って、なんか光ってるんだよ。
ちゃんと『好き』って顔になるの」
アリサは、ふわっと笑った。
「だから、大丈夫。
まだ言えなくても、夢はそこにあるし、
みのりが大事にしてるなら、それで十分」
ノートの中に描いた女の子の笑顔と、
アリサのまなざしが、重なって見えた。
担任の先生が淡々と説明する間、
教室の空気は重たく沈んでいた。
紙の上には、志望校と志望理由を書く欄がある。
その空白が、わたしの胸をずしりと押しつけてくる。
(第一志望校……)
ペンを握った手が震えそうになる。
わたしは、どこに行きたいのだろう。
いや、そもそも――何になりたいのだろう。
「水野さん、明日までに提出してね」
帰りがけに先生にそう言われて、
「はい」と答えるしかなかった。
家に帰ると、ダイニングには母が座っていた。
ノートパソコンを開いたまま、
すぐにわたしのかばんの中身に目を留める。
「それ、希望調査?」
「……うん」
「いつまでに出すの?」
「明日……」
母は「ふうん」と言って、再び画面に視線を戻した。
その横顔を、わたしはそっと盗み見る。
母の視線は、鋭くて迷いがない。
キャリアウーマンとしての自信にあふれている。
そんな人に、わたしの「夢」は、どんなふうに映るのだろう。
(言えるわけ、ないよ)
そう心の中でつぶやいた。
わたしの成績では、第一志望どころか、
母の思い描く進学ルートからも遠ざかっている。
漫画家になりたい――なんて、絶対に笑われる。
夢よりも現実を。
努力よりも結果を。
母はいつも、そうやってわたしを「正しく」導こうとしてきた。
でも、その「正しさ」に、わたしはもう、窒息しそうだった。
その日の夕飯は、父が作った炒め物と味噌汁だった。
「いただきます」
母と向かい合って座りながら、
わたしは、無意識に背筋を伸ばしていた。
食卓に並ぶ湯気の向こうで、
母は静かに箸を動かしている。
沈黙が怖くて、わたしが口を開く前に、
母のほうが切り出した。
「希望調査、志望校は前と同じでいいわよね?」
その言い方は、まるで確認だった。
わたしに「選ぶ」という余地はないように聞こえた。
「……ちょっと、迷ってて」
そう返した瞬間、母の手が止まる。
わたしは、急いで弁解を重ねた。
「まだ書き出してるだけで……でも、別に変えるって決めたわけじゃなくて……」
「どうして迷うの?」
母は、ごく自然な口調でそう尋ねた。
でもその声は、やっぱり冷たく聞こえた。
「成績が落ちてるから?
それとも、ほかにやりたいことができたの?」
そう聞かれて、わたしは言葉を詰まらせた。
やりたいこと。――ある。
でも、言えない。
夢を口にすることは、わたしにとって、
それ以外のすべてを捨てるくらいの勇気が必要だった。
「……ううん、なんでもない」
そう言って、わたしはご飯を口に運んだ。
母はもうそれ以上、何も言わなかった。
けれど、その沈黙が、いちばん堪えた。
「わたしの気持ち」は、やっぱりこの家では小さすぎる。
スカーフをぴんと結び直すような、
そんな気持ちで、わたしはスプーンを強く握った。
部屋に戻ると、制服のままベッドに倒れ込んだ。
ため息が、シーツの上に落ちる。
夕飯の間、ずっと息を止めていた気がした。
母と話すたび、わたしの声はどこかへ小さくなっていく。
(言いたかったのに)
言えなかった言葉が、胸の奥に残って、
重たく膨らんでいる。
進路希望票は、まだかばんの中にある。
空欄のままの第一志望欄を思い出すだけで、
心臓が音を立てる。
(わたしは、本当は……)
その続きを、声に出すのがこわい。
スマホが震えた。
アリサからのメッセージだった。
「提出って明日だっけ? 書けた?」
「てか、お母さんとなんかあったでしょ?」
心を見透かされたみたいで、思わず笑ってしまった。
「なんにも言えなかった。
また『がっかりした』って顔されるのがこわかった」
「でも、ほんとは……描いていたいって思ってる」
返したあと、スマホを抱えたまま、しばらく動けなかった。
アリサからの返信は、思ったよりすぐに届いた。
「いいじゃん、それ。描いていたいって思えるって、めっちゃすごいことだよ」
いつものアリサの笑顔が浮かんで、涙がぽとり、一粒こぼれる。
わたし、描いていたいよ。
自分の声が、心の中で響いていた。
夜、机に向かってノートを開いた。
ペンを持つ手はまだ少し震えていたけれど、
それでも、描きはじめてみた。
いつものように、無言のまま線を重ねる。
でも今夜の線は、いつもと少しちがっていた。
そのコマの中の女の子は、制服を着ていた。
けれど、そのスカーフは、きゅうくつじゃなくて、
少しゆるんで、風になびいていた。
彼女は、誰かに言おうとしている。
「わたし、描いていたいんだ」
「わたし、これがすきなんだ」
わたしの手は、そのセリフを吹き出しに書いたあと、ふと止まった。
(ほんとうに、言えるのかな)
ページの上では堂々と夢を語る女の子。
でも、わたしはまだ、母に一言も言えていない。
描くことでしか、自分の想いを伝えられない自分が、
少し悔しくて、でも少し、いとおしかった。
机の上のランプの光に照らされながら、
わたしは、描いたページを見つめた。
その子は笑っていた。
ちゃんと、前を向いていた。
(わたしも……)
心の中で、そうつぶやいて、もう一枚、ページをめくる。
誰にも見せなくていい。
誰にも認められなくてもいい。
まずは、自分で、自分の気持ちを認めてあげるために。
わたしは、ペンを持ち直した。
小さな決意の音が、紙の上にすうっと走った。
進路希望調査票は、まだかばんの奥に入ったままだった。
次の日の朝も、提出はしなかった。
勇気がなかったわけじゃない。
ただ、まだ言葉にできる準備が、できていなかっただけだ。
母は何も言わなかった。
提出日が過ぎても、何も聞いてこなかった。
けれどその沈黙が、逆にプレッシャーになって、
胸の中に小さな波紋を広げていた。
アリサと会ったのは、放課後の電車の中だった。
「どう? 書けた?」
ノートを見せながらそう聞かれて、
わたしは、首を横にふった。
「……まだ、ちょっと怖い」
「うん、わかる。でもさ、描いてたでしょ? 昨日」
「え?」
「LINEで『描いてたい』って言ったあと、絶対描いてたでしょ。
なんかそういう顔してる」
わたしは笑った。
「……ばれてるんだね、やっぱり」
「描いてるときの顔って、なんか光ってるんだよ。
ちゃんと『好き』って顔になるの」
アリサは、ふわっと笑った。
「だから、大丈夫。
まだ言えなくても、夢はそこにあるし、
みのりが大事にしてるなら、それで十分」
ノートの中に描いた女の子の笑顔と、
アリサのまなざしが、重なって見えた。