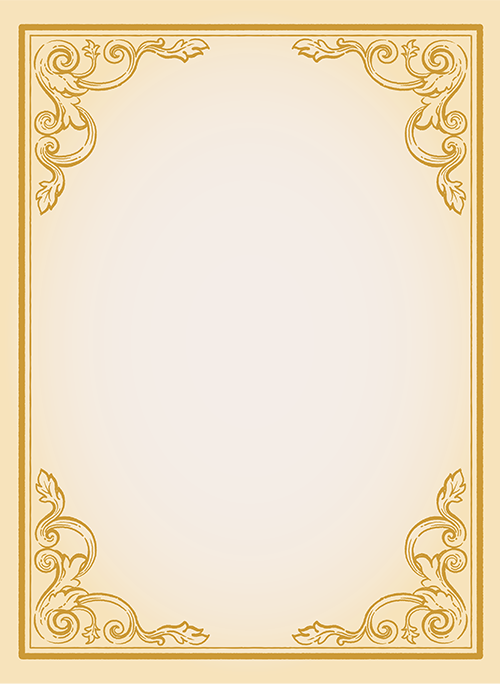アリサが制服のことを話してくれたのは、
あのカフェでの寄り道から数日後のことだった。
いつものように電車でノートを見せ合って、
ふたりして笑いながら、ありもしない恋愛展開にツッコミを入れていた帰り道。
「……ねえ、みのりってさ。制服、好き?」
不意にアリサが言った。
「え?」
唐突な質問に驚いて顔を向けると、アリサは窓の外を見ていた。
「いや、別に深い意味はないんだけどさ。
わたし、制服見ると、いまだにちょっとだけ気分悪くなるんだよね」
わたしは、胸の奥がきゅっとなるのを感じた。
アリサは続けた。
「でもさ、みのりがそれ着てるの、
……わたし、そこまでイヤじゃないんだよね。変でしょ?」
その言葉に、顔を上げた。
アリサの目は、どこか遠くを見ているようで、
でも、まっすぐにわたしに向いていた。
「みのりの制服姿、なんか、ちゃんとしてていいんだよ」
アリサがそう言った。
「ちゃんとしてる……?」
「うん。あたしがいた学校って、外見では何も判断しませんって言いながら、
けっきょく、『ちゃんとできる子』しか受け入れられなかった」
わたしはそっと、自分のスカートの裾をなぞった。
「でも、みのりはちゃんと、ちゃんとしようとしてる感じがするんだよね。
誰かに押しつけられたっていうより、自分でこうしなきゃって思ってるみたいな」
ドキリとした。
まさにその通りだったから。
わたしは、誰よりも「まじめ」でいようとしてきた。
母に叱られないように。
学校で浮かないように。
失敗しないように。
嫌われないように。
だから、制服はわたしの殻だった。
「でも、もしね。もし、いつか制服を脱いでも、
みのりの『まじめ』が残ってたら、それってほんとにすごいと思う」
「……それって、いいこと?」
「わかんない。
でも、みのりは『まじめ』を使って、自分を守ってきたんだろうなって思うからさ。
それって、ちょっとカッコいいじゃん」
カッコいいなんて、言われたことがなかった。
不器用で、要領もよくなくて、
人より遅れてばかりで、
それでもまじめにノートをとるしかなかったわたしが。
「ありがとう」
小さな声でそう言うと、
アリサは「どーいたしまして」と、ふわりと笑った。
その笑顔が、あたたかくて、
制服のスカーフの締めつけさえ、
少しだけやわらいだ気がした。
「あたし――」
アリサは、電車の窓の外に目を向けながら、言葉を続けた。
「やっぱり、夢はあきらめたくないんだよね。
自由な学校を作りたいって気持ち」
その声は、ふだんの明るさとは違って、静かで、まっすぐだった。
「たぶんさ。制服でいっぱい傷ついたからこそ、
こんどは誰かを守れる制服を作りたいのかも」
誰かを守れる制服。
その言葉を聞いたとき、
わたしの胸の奥で、何かがゆっくりと動いた。
制服は、ずっとわたしにとって「守られる側」の象徴だった。
きちんとしていれば叱られない。
まじめにしていれば居場所がある。
それが、わたしにとっての制服の意味だった。
でもアリサは、逆のことを考えている。
制服を選ばされるものじゃなくて、
選べるものに変えたいって思ってる。
それは、わたしにはなかった視点だった。
「アリサは、すごいよ」
思わず、繰り返しそう言ってしまう。
アリサは笑って、首を振った。
「ううん、全然。
だって、いまも自分のこと、ちょっとは信じきれてないもん。
ただ……みのりみたいな子が漫画描いてるって言ってくれたとき、
なんか、救われたんだよね」
「わたしが……?」
「うん。『まじめ』の中にも、こんなに光ってる子がいるんだって思って」
それは、照れくさくて、でもほんとうにうれしい言葉だった。
わたしの「小さな夢」が、アリサにとっての「希望」になれたなんて――
そんなこと、これまでの人生で一度もなかった。
「……わたし、自分のこと光ってるなんて思ったこと、一度もなかったよ」
わたしは、電車の窓にうつる自分の顔を見ながらつぶやいた。
アリサがくるりとこちらを向く。
「うそ。だって、描いてるときの顔、めっちゃキラキラしてるよ?」
「えっ……してない、してない!」
「してるって。あれ、隠せないやつ。
好きなことしてるときの顔って、バレるもんだよ」
好きなこと。
その言葉を聞いたとき、
わたしの胸にじわりと熱いものが広がった。
小学校のころ。
中学受験の塾で、ひとりの子がこっそり見せてくれた少女漫画。
漫画禁止のうちでは、決して見られない世界だった。
どこも全部、きらきらしてて、とってもかわいくて。
ページをめくるたびに、ドキドキ、わくわくして。
わたしは「この世界に行きたい」って、強く思った。
でも――
そんなことを言ったら、怒られると思った。
無駄だって言われると思った。
どうせわたしなんかにできるわけないって、思ってた。
だから、誰にも言わなかった。
誰にも見せなかった。
ひとりきりでノートに描き続けることでしか、
夢をつないでこれなかった。
「でもさ」
アリサが、わたしのノートをそっと指でつついた。
「それでも、やめなかったじゃん。
誰にも見せなくても、あんた、ずっと描いてたんでしょ?
それって、ほんとの『好き』じゃん」
その言葉が、心に深く染みこんだ。
電車が、アリサの降りる駅に近づいてきた。
アナウンスの声にかき消されるようにして、
車内がざわめきはじめる。
それでも、ふたりの間には、静かな温度が流れていた。
「……ありがとね、みのり」
「え?」
「なんか、話せてよかった。
制服のことも、夢のことも。
前までは、人に話すなんて、無理だと思ってたから」
アリサはそう言って、軽く目を伏せる。
その横顔が、夕方の光に照らされて、
どこか大人っぽく見えた。
「わたしのほうこそ、ありがとう。
アリサが聞いてくれたから……
わたし、自分の気持ちに気づけたんだと思う」
「そっか」
アリサは、ふっと息を吐いて、ドアの前に立つ。
電車がゆるやかにブレーキをかける。
「じゃ、またね」
「うん。また、電車で」
そのやりとりは、いつもと同じなのに、
今日は、少しだけ特別に感じた。
あのカフェでの寄り道から数日後のことだった。
いつものように電車でノートを見せ合って、
ふたりして笑いながら、ありもしない恋愛展開にツッコミを入れていた帰り道。
「……ねえ、みのりってさ。制服、好き?」
不意にアリサが言った。
「え?」
唐突な質問に驚いて顔を向けると、アリサは窓の外を見ていた。
「いや、別に深い意味はないんだけどさ。
わたし、制服見ると、いまだにちょっとだけ気分悪くなるんだよね」
わたしは、胸の奥がきゅっとなるのを感じた。
アリサは続けた。
「でもさ、みのりがそれ着てるの、
……わたし、そこまでイヤじゃないんだよね。変でしょ?」
その言葉に、顔を上げた。
アリサの目は、どこか遠くを見ているようで、
でも、まっすぐにわたしに向いていた。
「みのりの制服姿、なんか、ちゃんとしてていいんだよ」
アリサがそう言った。
「ちゃんとしてる……?」
「うん。あたしがいた学校って、外見では何も判断しませんって言いながら、
けっきょく、『ちゃんとできる子』しか受け入れられなかった」
わたしはそっと、自分のスカートの裾をなぞった。
「でも、みのりはちゃんと、ちゃんとしようとしてる感じがするんだよね。
誰かに押しつけられたっていうより、自分でこうしなきゃって思ってるみたいな」
ドキリとした。
まさにその通りだったから。
わたしは、誰よりも「まじめ」でいようとしてきた。
母に叱られないように。
学校で浮かないように。
失敗しないように。
嫌われないように。
だから、制服はわたしの殻だった。
「でも、もしね。もし、いつか制服を脱いでも、
みのりの『まじめ』が残ってたら、それってほんとにすごいと思う」
「……それって、いいこと?」
「わかんない。
でも、みのりは『まじめ』を使って、自分を守ってきたんだろうなって思うからさ。
それって、ちょっとカッコいいじゃん」
カッコいいなんて、言われたことがなかった。
不器用で、要領もよくなくて、
人より遅れてばかりで、
それでもまじめにノートをとるしかなかったわたしが。
「ありがとう」
小さな声でそう言うと、
アリサは「どーいたしまして」と、ふわりと笑った。
その笑顔が、あたたかくて、
制服のスカーフの締めつけさえ、
少しだけやわらいだ気がした。
「あたし――」
アリサは、電車の窓の外に目を向けながら、言葉を続けた。
「やっぱり、夢はあきらめたくないんだよね。
自由な学校を作りたいって気持ち」
その声は、ふだんの明るさとは違って、静かで、まっすぐだった。
「たぶんさ。制服でいっぱい傷ついたからこそ、
こんどは誰かを守れる制服を作りたいのかも」
誰かを守れる制服。
その言葉を聞いたとき、
わたしの胸の奥で、何かがゆっくりと動いた。
制服は、ずっとわたしにとって「守られる側」の象徴だった。
きちんとしていれば叱られない。
まじめにしていれば居場所がある。
それが、わたしにとっての制服の意味だった。
でもアリサは、逆のことを考えている。
制服を選ばされるものじゃなくて、
選べるものに変えたいって思ってる。
それは、わたしにはなかった視点だった。
「アリサは、すごいよ」
思わず、繰り返しそう言ってしまう。
アリサは笑って、首を振った。
「ううん、全然。
だって、いまも自分のこと、ちょっとは信じきれてないもん。
ただ……みのりみたいな子が漫画描いてるって言ってくれたとき、
なんか、救われたんだよね」
「わたしが……?」
「うん。『まじめ』の中にも、こんなに光ってる子がいるんだって思って」
それは、照れくさくて、でもほんとうにうれしい言葉だった。
わたしの「小さな夢」が、アリサにとっての「希望」になれたなんて――
そんなこと、これまでの人生で一度もなかった。
「……わたし、自分のこと光ってるなんて思ったこと、一度もなかったよ」
わたしは、電車の窓にうつる自分の顔を見ながらつぶやいた。
アリサがくるりとこちらを向く。
「うそ。だって、描いてるときの顔、めっちゃキラキラしてるよ?」
「えっ……してない、してない!」
「してるって。あれ、隠せないやつ。
好きなことしてるときの顔って、バレるもんだよ」
好きなこと。
その言葉を聞いたとき、
わたしの胸にじわりと熱いものが広がった。
小学校のころ。
中学受験の塾で、ひとりの子がこっそり見せてくれた少女漫画。
漫画禁止のうちでは、決して見られない世界だった。
どこも全部、きらきらしてて、とってもかわいくて。
ページをめくるたびに、ドキドキ、わくわくして。
わたしは「この世界に行きたい」って、強く思った。
でも――
そんなことを言ったら、怒られると思った。
無駄だって言われると思った。
どうせわたしなんかにできるわけないって、思ってた。
だから、誰にも言わなかった。
誰にも見せなかった。
ひとりきりでノートに描き続けることでしか、
夢をつないでこれなかった。
「でもさ」
アリサが、わたしのノートをそっと指でつついた。
「それでも、やめなかったじゃん。
誰にも見せなくても、あんた、ずっと描いてたんでしょ?
それって、ほんとの『好き』じゃん」
その言葉が、心に深く染みこんだ。
電車が、アリサの降りる駅に近づいてきた。
アナウンスの声にかき消されるようにして、
車内がざわめきはじめる。
それでも、ふたりの間には、静かな温度が流れていた。
「……ありがとね、みのり」
「え?」
「なんか、話せてよかった。
制服のことも、夢のことも。
前までは、人に話すなんて、無理だと思ってたから」
アリサはそう言って、軽く目を伏せる。
その横顔が、夕方の光に照らされて、
どこか大人っぽく見えた。
「わたしのほうこそ、ありがとう。
アリサが聞いてくれたから……
わたし、自分の気持ちに気づけたんだと思う」
「そっか」
アリサは、ふっと息を吐いて、ドアの前に立つ。
電車がゆるやかにブレーキをかける。
「じゃ、またね」
「うん。また、電車で」
そのやりとりは、いつもと同じなのに、
今日は、少しだけ特別に感じた。