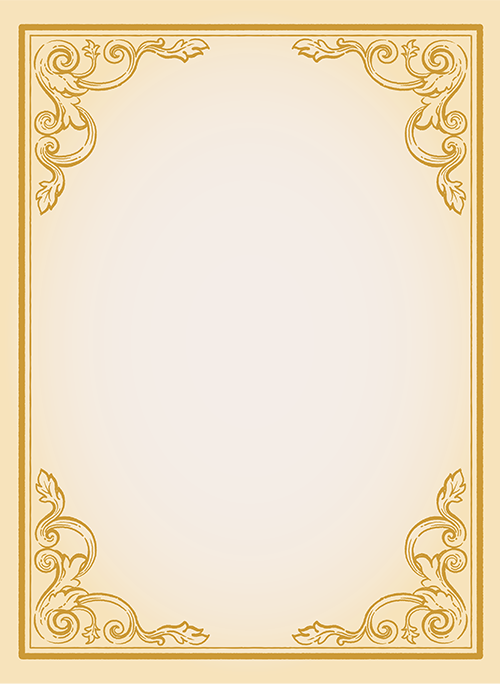放課後にまっすぐ帰らない日が来るなんて、
数週間前のわたしには想像もできなかった。
それは金曜日のことだった。
アリサから「今週、描けてる?」とLINEが来て、
「まだ途中だけど……」と返したら、すぐに「じゃ、放課後行こう」と返ってきた。
「行こう」――つまり、「寄り道しよう」ってことだ。
わたしは、制服の襟を見つめながら、
(ほんとうに大丈夫かな)と何度も心の中で問い直した。
でも、不思議と、罪悪感はあまりなかった。
学校が終わって、駅へ急ぐ足取りは、
どこか浮き足立っていた。
今日のカフェは、この前と違うお店だった。
アリサが「新しくできたばっかで、めっちゃ映えるの」と言って案内してくれた。
ガラス張りの店内は明るくて、
ドライフラワーが吊るされた天井と、
淡い色のクッションが置かれたベンチソファがかわいらしい。
「どう? 制服でも入りやすいでしょ?」
「うん……すごく、いい感じ……」
「でしょー!女子高生っぽいことしようぜ!」
アリサのテンションに引っぱられて、
わたしの口元にも自然と笑みがこぼれる。
店内は放課後らしいお客さんで賑わっていたけど、
そのざわめきが、どこかやさしく感じた。
学校でも家でもない場所で、
制服のままおしゃべりして、甘いものを食べて、漫画を描いて――
そんな時間を過ごしている自分が、
まるで違う世界の住人みたいだった。
「ほらほら、描いて〜。わたし、今日ストーリーの展開予想してきたから!」
「ちょ、ちょっと待って……!」
わたしの放課後が、静かに変わりはじめていた。
「てかさ、前回のラスト、絶対キスすると思ったのに……」
「しないってば!あそこは、まだ我慢のとこ!」
「えー、じれったい〜。読者としては、そこはキスしてほしかった〜!」
「うぅ……そ、それは次回のお楽しみ……かも」
わたしがごにょごにょ言うと、アリサはにんまり笑って、
クリームが山盛りのパンケーキをすくって口に運んだ。
その無防備な横顔を見て、
わたしはふっと、今が不思議な時間の中にいるような気がした。
アリサは、ほんとうにいろんな表情を見せてくれる。
無邪気に笑ったかと思えば、
ふとしたときに遠くを見るような顔をする。
だけど、誰よりも言葉がストレートで、
ごまかさない。
それが、まぶしくて、少しだけうらやましかった。
「……ねえ、アリサって、将来なにかやりたいことあるの?」
わたしはふと思って、そんな質問を口にしていた。
アリサはスプーンを止めて、目を丸くする。
「うん。あるよ」
「ほんと?」
「うん。あたしね――
将来、日本で“自由な学校”を作りたいの」
「自由な……学校?」
「うん。制服も、髪型も、メイクも、スカート丈も、
そーゆーの一切なし。生徒が自分で決められる学校」
その言葉に、わたしの心がひゅっと揺れた。
まるで、それはわたしがずっと夢見ていた世界だった。
「自由な学校って……どうして、そんな学校を作りたいって思ったの?」
わたしがたずねると、アリサはちょっとだけ口元を引き結んだ。
さっきまでパンケーキの山を攻めていた手が止まり、
静かに、テーブルの端をなぞるように指が動く。
「……あたし、金鳳花女子にいたころね」
金鳳花女子。
それは今、わたしが通っている学校の名前だった。
「髪の色がどうとか、スカートの長さがどうとか。
わたし、けっこう規則きっちり守ってたのに、
それでも『あの子だけなんか違う』って言われた」
アリサの声は、どこか遠い場所を見つめているみたいだった。
「それでね、思ったの。
『正しさ』って、誰かが決めるもんじゃないんだって。
だから、自分で選べる学校を作りたいって思ったの。
髪の色も、服も、言葉も、ぜんぶ、
『自分で決めていい』って場所」
その言葉に、わたしはなにも言えなくなった。
だって、わたしは逆だったから。
校則の中にいることでしか、自分の価値を見いだせなかった。
誰かが決めたルールに従うことでしか、ちゃんとしている自分を保てなかった。
「すごいね、アリサは」
やっとの思いで、そう言うと、
アリサはふっと微笑んだ。
「ううん、すごくないよ。
むしろ、怖がりなんだと思う。
ふつうに縛られるのが、こわいだけ」
その言葉が、わたしの胸に、深く沈んでいった。
アリサの話を聞いていたら、
ずっと胸の奥にしまっていた言葉が、
少しずつ、うずうずと動き出していた。
「……わたしもね、ほんとは」
声に出すと、自分でも驚くほどかすれていた。
アリサがこちらを見た。
そのまなざしは、急かさず、でもまっすぐで。
だから、わたしも少しだけ、言ってみることにした。
「わたし……漫画家になりたいって、思ってるの」
言った瞬間、心臓がドクンと跳ねた。
夢、なんて言葉。
自分にいちばん似合わないと思っていた言葉。
それを口にしてしまった、という事実が、
恥ずかしくて、でも、どこかすっきりしていた。
「ふーん……」
アリサは、ゆっくりうなずいた。
「やっぱ、そういう顔してたもんね」
「え?」
「好きなことの話してるときの顔って、ばれやすいんだよ。
目がね、きらきらするの。あんたの目、よく光る」
「うそ……」
「ほんと。
てか、わたしも結構うれしいよ。
なんか……仲間ができたって感じ?」
仲間――その言葉は、あたたかくて、
まるでカフェの窓から差しこむ光みたいだった。
「描き続けてよ、ちゃんと。
わたし、ずっと読みたいし。
……あんたの描く世界、好きだもん」
その一言で、わたしはもうだめだった。
涙が出そうになるのを、必死でこらえながら、
「ありがとう」とだけ、小さな声で返した。
日が傾いて、カフェの窓から差し込む光が、
すこしオレンジ色に染まりはじめていた。
数週間前のわたしには想像もできなかった。
それは金曜日のことだった。
アリサから「今週、描けてる?」とLINEが来て、
「まだ途中だけど……」と返したら、すぐに「じゃ、放課後行こう」と返ってきた。
「行こう」――つまり、「寄り道しよう」ってことだ。
わたしは、制服の襟を見つめながら、
(ほんとうに大丈夫かな)と何度も心の中で問い直した。
でも、不思議と、罪悪感はあまりなかった。
学校が終わって、駅へ急ぐ足取りは、
どこか浮き足立っていた。
今日のカフェは、この前と違うお店だった。
アリサが「新しくできたばっかで、めっちゃ映えるの」と言って案内してくれた。
ガラス張りの店内は明るくて、
ドライフラワーが吊るされた天井と、
淡い色のクッションが置かれたベンチソファがかわいらしい。
「どう? 制服でも入りやすいでしょ?」
「うん……すごく、いい感じ……」
「でしょー!女子高生っぽいことしようぜ!」
アリサのテンションに引っぱられて、
わたしの口元にも自然と笑みがこぼれる。
店内は放課後らしいお客さんで賑わっていたけど、
そのざわめきが、どこかやさしく感じた。
学校でも家でもない場所で、
制服のままおしゃべりして、甘いものを食べて、漫画を描いて――
そんな時間を過ごしている自分が、
まるで違う世界の住人みたいだった。
「ほらほら、描いて〜。わたし、今日ストーリーの展開予想してきたから!」
「ちょ、ちょっと待って……!」
わたしの放課後が、静かに変わりはじめていた。
「てかさ、前回のラスト、絶対キスすると思ったのに……」
「しないってば!あそこは、まだ我慢のとこ!」
「えー、じれったい〜。読者としては、そこはキスしてほしかった〜!」
「うぅ……そ、それは次回のお楽しみ……かも」
わたしがごにょごにょ言うと、アリサはにんまり笑って、
クリームが山盛りのパンケーキをすくって口に運んだ。
その無防備な横顔を見て、
わたしはふっと、今が不思議な時間の中にいるような気がした。
アリサは、ほんとうにいろんな表情を見せてくれる。
無邪気に笑ったかと思えば、
ふとしたときに遠くを見るような顔をする。
だけど、誰よりも言葉がストレートで、
ごまかさない。
それが、まぶしくて、少しだけうらやましかった。
「……ねえ、アリサって、将来なにかやりたいことあるの?」
わたしはふと思って、そんな質問を口にしていた。
アリサはスプーンを止めて、目を丸くする。
「うん。あるよ」
「ほんと?」
「うん。あたしね――
将来、日本で“自由な学校”を作りたいの」
「自由な……学校?」
「うん。制服も、髪型も、メイクも、スカート丈も、
そーゆーの一切なし。生徒が自分で決められる学校」
その言葉に、わたしの心がひゅっと揺れた。
まるで、それはわたしがずっと夢見ていた世界だった。
「自由な学校って……どうして、そんな学校を作りたいって思ったの?」
わたしがたずねると、アリサはちょっとだけ口元を引き結んだ。
さっきまでパンケーキの山を攻めていた手が止まり、
静かに、テーブルの端をなぞるように指が動く。
「……あたし、金鳳花女子にいたころね」
金鳳花女子。
それは今、わたしが通っている学校の名前だった。
「髪の色がどうとか、スカートの長さがどうとか。
わたし、けっこう規則きっちり守ってたのに、
それでも『あの子だけなんか違う』って言われた」
アリサの声は、どこか遠い場所を見つめているみたいだった。
「それでね、思ったの。
『正しさ』って、誰かが決めるもんじゃないんだって。
だから、自分で選べる学校を作りたいって思ったの。
髪の色も、服も、言葉も、ぜんぶ、
『自分で決めていい』って場所」
その言葉に、わたしはなにも言えなくなった。
だって、わたしは逆だったから。
校則の中にいることでしか、自分の価値を見いだせなかった。
誰かが決めたルールに従うことでしか、ちゃんとしている自分を保てなかった。
「すごいね、アリサは」
やっとの思いで、そう言うと、
アリサはふっと微笑んだ。
「ううん、すごくないよ。
むしろ、怖がりなんだと思う。
ふつうに縛られるのが、こわいだけ」
その言葉が、わたしの胸に、深く沈んでいった。
アリサの話を聞いていたら、
ずっと胸の奥にしまっていた言葉が、
少しずつ、うずうずと動き出していた。
「……わたしもね、ほんとは」
声に出すと、自分でも驚くほどかすれていた。
アリサがこちらを見た。
そのまなざしは、急かさず、でもまっすぐで。
だから、わたしも少しだけ、言ってみることにした。
「わたし……漫画家になりたいって、思ってるの」
言った瞬間、心臓がドクンと跳ねた。
夢、なんて言葉。
自分にいちばん似合わないと思っていた言葉。
それを口にしてしまった、という事実が、
恥ずかしくて、でも、どこかすっきりしていた。
「ふーん……」
アリサは、ゆっくりうなずいた。
「やっぱ、そういう顔してたもんね」
「え?」
「好きなことの話してるときの顔って、ばれやすいんだよ。
目がね、きらきらするの。あんたの目、よく光る」
「うそ……」
「ほんと。
てか、わたしも結構うれしいよ。
なんか……仲間ができたって感じ?」
仲間――その言葉は、あたたかくて、
まるでカフェの窓から差しこむ光みたいだった。
「描き続けてよ、ちゃんと。
わたし、ずっと読みたいし。
……あんたの描く世界、好きだもん」
その一言で、わたしはもうだめだった。
涙が出そうになるのを、必死でこらえながら、
「ありがとう」とだけ、小さな声で返した。
日が傾いて、カフェの窓から差し込む光が、
すこしオレンジ色に染まりはじめていた。