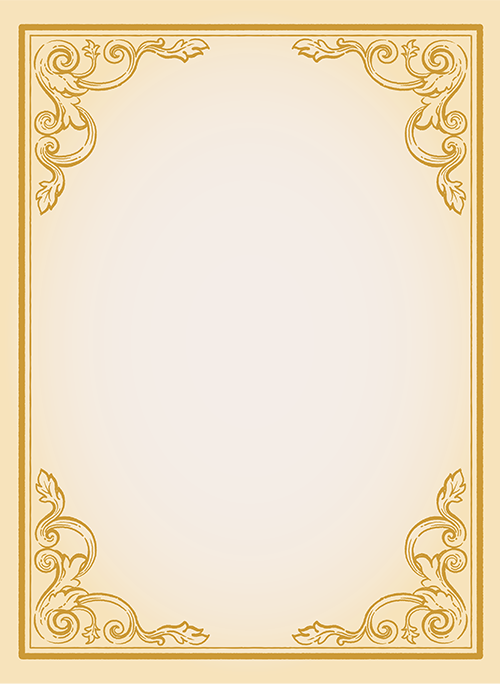「放課後、ちょっと寄り道してみない?」
そう言ったのは、アリサのほうだった。
電車の中で漫画の続きを見せた帰り道、
駅の階段をのぼりながらぽつりと。
「寄り道……?」
わたしの足がぴたりと止まった。
寄り道――それは、わたしの辞書に存在しない言葉だった。
校則で禁止されているし、母にも「まっすぐ帰宅」と言われている。
ルール違反だと、わたしの中の警報が鳴る。
でも、アリサは軽い口調のまま続ける。
「ちょっとだけでいいじゃん。
いつも電車で描いた漫画見せてもらってるし、
今日はカフェで描いてるとこ見てみたいなって思って」
「……描いてるとこ?」
「うん。てか、みのりがどんな顔して漫画描くのか、気になってる」
「えええ、そんな……」
「だいじょぶだって。別に見ててニヤニヤするわけじゃないし。
てか、カフェ行くのもだめ?」
「だめっていうか……その、怒られるかも……」
「親?」
「うん……」
アリサは、少しだけ顔をしかめて、でも怒ったわけじゃなく、
まぶしそうにわたしを見て言った。
「ふうん。じゃあさ、
『怒られない時間までに帰る』ってのはどう?」
「……!」
その発想は、なかった。
“寄り道=即アウト”だと思ってたわたしには、
そんなふうに“ルールの間”を見つける考え方は、まるで魔法みたいだった。
「……少しだけ、なら」
そう答えたとき、心のどこかがふわっと軽くなった気がした。
駅を出て、少し歩いた先の、
こぢんまりしたカフェにアリサは案内してくれた。
入り口のドアに吊るされた小さな黒板には、
「本日のおすすめ:いちごミルクと気まぐれタルト」と書かれていて、
見た瞬間、なんだか胸がときめいた。
「ここね、Wi-Fiあるし、うるさすぎなくて好きなんだよね」
「へぇ……」
制服姿でカフェに入るのは初めてだった。
まわりの目が気になるかと思ったけど、
店内はあたたかい照明に包まれていて、
席もほどよく離れていて、居心地がよかった。
アリサはソファ席に腰を下ろして、
「飲みもん何にする?」とメニューを広げる。
「いちごミルク……に、しようかな」
「お、いいね。じゃあおそろいにしよ」
その一言が、ちょっとうれしかった。
注文を終えて、わたしたちは向かい合わせに座った。
机の上に、ノートとシャーペンを出す。
アリサが、目をきらきらさせてそれをのぞきこむ。
「じゃ、描いて?」
「えっ、今?」
「今でしょ。ライブペイントってやつ?知らんけど」
「む、むりむり、見られながらなんて描けないよ……」
「だいじょぶ、ガン見はしないから。
てか、さっき『ちょっとだけ』って言ったよね?描くって言ってたよね?」
「うう……ずるい」
「ずるくない、見たいだけ。誠意ある読者として」
そう言って、アリサはにやりと笑った。
わたしは少し恥ずかしくなりながらも、
ゆっくりとシャーペンを走らせ始めた。
紙の上に線を描く感覚は、いつもより少しぎこちないけど、
でも不思議と悪くなかった。
だって、隣で誰かが「楽しみにしてくれてる」って思うだけで、
漫画を描く時間が、もっと特別なものに思えたから。
シャーペンの芯が紙をこする音だけが、静かに響いていた。
わたしは、視線を意識しすぎないようにしながら、
キャラクターの横顔を描いていく。
いつもより、ちょっと手が震える。
でも、アリサはほんとうに見守るだけだった。
騒がないし、急かさないし、ただ、待っていてくれる。
「……なんか、さ」
不意に、アリサが言った。
「みのりって、見た目はまじめで地味だけど、
描いてる漫画の女の子、すごい芯が強いよね」
「……え?」
「なんか、セリフもストレートだし。
『あなたのことが好きなの。だってあなたは、私のヒーローだったから』……とかさ」
「うわぁ、それ読まないでぇ……!」
「なんで? めっちゃいいセリフじゃん。泣きそうになったし」
「うそ……」
「ほんとだって。
てか、まじめで生きてる子の中にも、
こういうストレートな言葉、ちゃんと眠ってんだなーって」
アリサは、ストローでいちごミルクをくるくるかき混ぜながら、
まっすぐわたしを見た。
なんだか、見透かされているみたいだった。
「アリサは……強いから、いいなって思う。
自分の意見、ちゃんと言えるし」
ぽつりと、そう言った。
アリサは、くつくつと笑った。
「そんなふうに見える? やっば、演技うまいな、あたし」
「え?」
「強くなきゃ、生きてけなかっただけだよ」
その言葉に、ふっと冷たい風が吹いたような気がした。
アリサの目が、ほんの少しだけ、伏せられる。
その一瞬に、何か深いものが隠れているような気がして、
わたしは何も言えなかった。
「……私、制服見るの、ちょっと苦手なんだよね」
いちごミルクのグラスを半分ほど空けたあと、
アリサがぽつりと言った。
わたしはペンを止めて、顔を上げる。
アリサの表情は、いつもの明るい笑顔とは少し違っていた。
「中学んときさ、めっちゃ頭よくて有名な学校に入ったんだけど、
あたし、そこですっごい浮いてたの」
「……うん」
「成績よすぎて、妬まれて。
んで、いろんなウワサ流されたり、先生にチクられたりして」
わたしは、何も言えなかった。
目の前にいるこの子が、そんな思いをしたなんて想像もできなかったから。
「で、ある日、『万引きした』って言われてさ」
「……えっ」
「してないよ。そんなの。
でも証拠もないし、学校も事を荒立てたくないって感じでさ。
そのまま辞めた」
「…………」
アリサの声は静かだった。
静かすぎて、余計に痛かった。
「だからね、いまでも制服を見ると――
あの学校のこと、全部思い出しちゃうんだよ。
廊下の空気とか、ざわざわした視線とか、誰も信じてくれなかったときの気持ちとか。
それで……たまに、気持ち悪くなっちゃう」
わたしは、制服の襟元を思わず手で押さえた。
それは、わたしを守る盾みたいなものだった。
でも――
アリサにとっては、傷の記憶を引きずる、見たくもない過去だったのかもしれない。
「だから、ごめんね。あのとき『うっさい』って言ったの。
あれ、みのりが悪いわけじゃなかったのに」
「……ううん」
わたしは小さく首を振った。
「言ってくれて、ありがとう」
アリサは、ほんのすこし、微笑んだ。
その笑顔が、泣きそうなくらいやさしくて、
わたしの胸の奥まで、じんわり染みこんできた。
アリサと歩く帰り道。
知らない場所、知らない時間。
なのに、不思議と、落ち着いていた。
まるで、ここがわたしの「ほんとうの居場所」みたいに感じられた。
ふと、アリサが言った。
「ねえ、次さ。放課後のカフェ、また一緒に行こうよ」
「えっ……でも、寄り道って……」
「怒られない時間に帰ればいい。でしょ?」
わたしは、ふっと笑ってしまった。
「あは……うん、そうだね」
うなずいたわたしの顔を見て、
アリサは「よっしゃ」と、子どもみたいに小さくガッツポーズをした。
それがなんだかおかしくて、
わたしは今日いちばんの声で、笑った。
そう言ったのは、アリサのほうだった。
電車の中で漫画の続きを見せた帰り道、
駅の階段をのぼりながらぽつりと。
「寄り道……?」
わたしの足がぴたりと止まった。
寄り道――それは、わたしの辞書に存在しない言葉だった。
校則で禁止されているし、母にも「まっすぐ帰宅」と言われている。
ルール違反だと、わたしの中の警報が鳴る。
でも、アリサは軽い口調のまま続ける。
「ちょっとだけでいいじゃん。
いつも電車で描いた漫画見せてもらってるし、
今日はカフェで描いてるとこ見てみたいなって思って」
「……描いてるとこ?」
「うん。てか、みのりがどんな顔して漫画描くのか、気になってる」
「えええ、そんな……」
「だいじょぶだって。別に見ててニヤニヤするわけじゃないし。
てか、カフェ行くのもだめ?」
「だめっていうか……その、怒られるかも……」
「親?」
「うん……」
アリサは、少しだけ顔をしかめて、でも怒ったわけじゃなく、
まぶしそうにわたしを見て言った。
「ふうん。じゃあさ、
『怒られない時間までに帰る』ってのはどう?」
「……!」
その発想は、なかった。
“寄り道=即アウト”だと思ってたわたしには、
そんなふうに“ルールの間”を見つける考え方は、まるで魔法みたいだった。
「……少しだけ、なら」
そう答えたとき、心のどこかがふわっと軽くなった気がした。
駅を出て、少し歩いた先の、
こぢんまりしたカフェにアリサは案内してくれた。
入り口のドアに吊るされた小さな黒板には、
「本日のおすすめ:いちごミルクと気まぐれタルト」と書かれていて、
見た瞬間、なんだか胸がときめいた。
「ここね、Wi-Fiあるし、うるさすぎなくて好きなんだよね」
「へぇ……」
制服姿でカフェに入るのは初めてだった。
まわりの目が気になるかと思ったけど、
店内はあたたかい照明に包まれていて、
席もほどよく離れていて、居心地がよかった。
アリサはソファ席に腰を下ろして、
「飲みもん何にする?」とメニューを広げる。
「いちごミルク……に、しようかな」
「お、いいね。じゃあおそろいにしよ」
その一言が、ちょっとうれしかった。
注文を終えて、わたしたちは向かい合わせに座った。
机の上に、ノートとシャーペンを出す。
アリサが、目をきらきらさせてそれをのぞきこむ。
「じゃ、描いて?」
「えっ、今?」
「今でしょ。ライブペイントってやつ?知らんけど」
「む、むりむり、見られながらなんて描けないよ……」
「だいじょぶ、ガン見はしないから。
てか、さっき『ちょっとだけ』って言ったよね?描くって言ってたよね?」
「うう……ずるい」
「ずるくない、見たいだけ。誠意ある読者として」
そう言って、アリサはにやりと笑った。
わたしは少し恥ずかしくなりながらも、
ゆっくりとシャーペンを走らせ始めた。
紙の上に線を描く感覚は、いつもより少しぎこちないけど、
でも不思議と悪くなかった。
だって、隣で誰かが「楽しみにしてくれてる」って思うだけで、
漫画を描く時間が、もっと特別なものに思えたから。
シャーペンの芯が紙をこする音だけが、静かに響いていた。
わたしは、視線を意識しすぎないようにしながら、
キャラクターの横顔を描いていく。
いつもより、ちょっと手が震える。
でも、アリサはほんとうに見守るだけだった。
騒がないし、急かさないし、ただ、待っていてくれる。
「……なんか、さ」
不意に、アリサが言った。
「みのりって、見た目はまじめで地味だけど、
描いてる漫画の女の子、すごい芯が強いよね」
「……え?」
「なんか、セリフもストレートだし。
『あなたのことが好きなの。だってあなたは、私のヒーローだったから』……とかさ」
「うわぁ、それ読まないでぇ……!」
「なんで? めっちゃいいセリフじゃん。泣きそうになったし」
「うそ……」
「ほんとだって。
てか、まじめで生きてる子の中にも、
こういうストレートな言葉、ちゃんと眠ってんだなーって」
アリサは、ストローでいちごミルクをくるくるかき混ぜながら、
まっすぐわたしを見た。
なんだか、見透かされているみたいだった。
「アリサは……強いから、いいなって思う。
自分の意見、ちゃんと言えるし」
ぽつりと、そう言った。
アリサは、くつくつと笑った。
「そんなふうに見える? やっば、演技うまいな、あたし」
「え?」
「強くなきゃ、生きてけなかっただけだよ」
その言葉に、ふっと冷たい風が吹いたような気がした。
アリサの目が、ほんの少しだけ、伏せられる。
その一瞬に、何か深いものが隠れているような気がして、
わたしは何も言えなかった。
「……私、制服見るの、ちょっと苦手なんだよね」
いちごミルクのグラスを半分ほど空けたあと、
アリサがぽつりと言った。
わたしはペンを止めて、顔を上げる。
アリサの表情は、いつもの明るい笑顔とは少し違っていた。
「中学んときさ、めっちゃ頭よくて有名な学校に入ったんだけど、
あたし、そこですっごい浮いてたの」
「……うん」
「成績よすぎて、妬まれて。
んで、いろんなウワサ流されたり、先生にチクられたりして」
わたしは、何も言えなかった。
目の前にいるこの子が、そんな思いをしたなんて想像もできなかったから。
「で、ある日、『万引きした』って言われてさ」
「……えっ」
「してないよ。そんなの。
でも証拠もないし、学校も事を荒立てたくないって感じでさ。
そのまま辞めた」
「…………」
アリサの声は静かだった。
静かすぎて、余計に痛かった。
「だからね、いまでも制服を見ると――
あの学校のこと、全部思い出しちゃうんだよ。
廊下の空気とか、ざわざわした視線とか、誰も信じてくれなかったときの気持ちとか。
それで……たまに、気持ち悪くなっちゃう」
わたしは、制服の襟元を思わず手で押さえた。
それは、わたしを守る盾みたいなものだった。
でも――
アリサにとっては、傷の記憶を引きずる、見たくもない過去だったのかもしれない。
「だから、ごめんね。あのとき『うっさい』って言ったの。
あれ、みのりが悪いわけじゃなかったのに」
「……ううん」
わたしは小さく首を振った。
「言ってくれて、ありがとう」
アリサは、ほんのすこし、微笑んだ。
その笑顔が、泣きそうなくらいやさしくて、
わたしの胸の奥まで、じんわり染みこんできた。
アリサと歩く帰り道。
知らない場所、知らない時間。
なのに、不思議と、落ち着いていた。
まるで、ここがわたしの「ほんとうの居場所」みたいに感じられた。
ふと、アリサが言った。
「ねえ、次さ。放課後のカフェ、また一緒に行こうよ」
「えっ……でも、寄り道って……」
「怒られない時間に帰ればいい。でしょ?」
わたしは、ふっと笑ってしまった。
「あは……うん、そうだね」
うなずいたわたしの顔を見て、
アリサは「よっしゃ」と、子どもみたいに小さくガッツポーズをした。
それがなんだかおかしくて、
わたしは今日いちばんの声で、笑った。