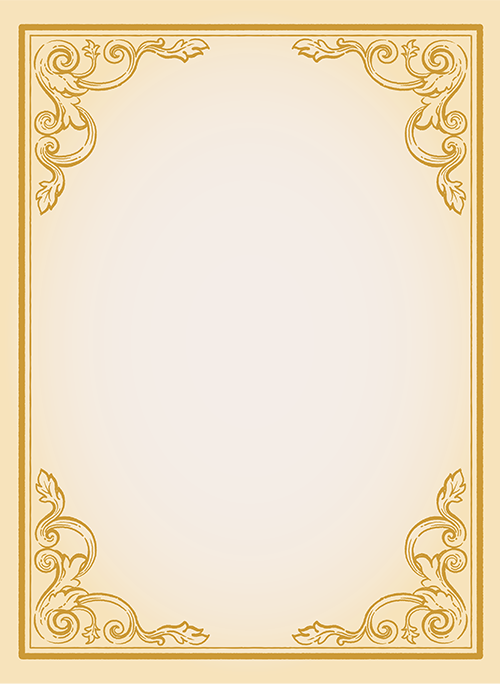朝の電車は、苦手だった。
揺れるし、ぎゅうぎゅうだし、眠いし、
ときどきおなかが痛くなるし、
何より、周りにいる人たちの無言の圧が、重たくて。
だけど最近――電車に乗るのが、少しだけ楽しみになっていた。
あの子と、また会えるかもしれない。
名前も、学校も、なにも知らない。
だけど、わたしの漫画を「おもしろい」って言ってくれた、
あの、金髪の、不思議な子。
彼女がノートを返してくれたあの日から、
なんとなく意識するようになっていた。
(「続き見せてよ」って、ほんとに言ってくれたんだよね)
わたしは、家でこっそり新しいページを描き足していた。
授業中じゃない。
帰ってから、宿題を終えて、誰も見ていない夜の机で。
シャーペンを握りながら、彼女の顔を思い出す。
あのとき、「面白い」って言われたときの、心臓のどくん、どくん。
誰かに見てもらいたいって、
思ったのなんて、たぶん初めてだった。
駅のホームに立っていると、ふと風が吹いて、
制服の襟元がそよいだ。
わたしはその手で、首元を押さえながら、辺りを見回す。
彼女の姿はなかった。
今日はいないのかも。
でも、それはそれでいい。
また会えるかもしれないっていうだけで、
昨日よりちょっとだけ、心が軽くなる。
「電車に乗る理由がもうひとつできるなんて、
ちょっとだけ、大人になったみたいだなあ……」
小さく、つぶやいてみる。
それは、だれにも聞かせたくない、
わたしだけの、小さな秘密だった。
次にあの子に会ったのは、三日後の放課後だった。
今日はたまたま、授業が早く終わって、
一本早い電車に乗れた。
座れるかもしれないと思っていたのに、
車内は意外と混んでいて、立ったままつり革をつかむ。
足元の感覚をたしかめながら、バッグに手を伸ばして、
いつものように、英語の問題集を出そうとした――
そのときだった。
「おー、いた」
軽い声が、耳に飛びこんできた。
反射的に顔を上げると、すぐ目の前に、あの子がいた。
金髪の、少しふわっとした髪。
パーカーの袖からのぞく細い指先。
イヤホンの片耳を外して、わたしを見ている。
「この前の……」
「漫画の子でしょ? わたし、あれけっこう気に入ってるんだよね」
「え、ええと……ありがとう」
どきどきして、何を言えばいいのかわからなかった。
目の前にいるのに、なんだか現実じゃないみたいだった。
(話しかけてくれた……わたしのこと、覚えてたんだ)
「ちなみに、続きは? 描いた?」
「……うん。少しだけ」
「見たい!」
即答だった。
わたしはバッグの中を探って、ノートをそっと取り出す。
手がちょっと震えていたけど、見せたかった。
ノートを開いたとたん、彼女の顔がぐっと近づいた。
「うわ……マジでちゃんと描いてるじゃん。
やば、てかこれ、次のコマ、絶対キスするやつじゃん!」
「し、しないから!」
「しないの!? しようよ! しちゃおうよ!」
「だ、だめだよ!まだ心の準備が!」
電車の中なのに、ふたりでわちゃわちゃ言い合って、
わたしの顔は真っ赤だった。
だけどそのとき、ふと思った。
こんなふうに、誰かと笑いながら話すの――
どれくらい、ぶりだろう。
「……てか、あんた、名前なんて言うの?」
ページをめくりながら、彼女が言った。
その瞬間、心臓がひとつ跳ねた気がした。
(名前……そうだ。わたし、名乗ってなかった)
「み、水野です。水野みのり」
「あー、みのり。オーケー、みのりね」
あっさりと呼び捨てにされて、すこし驚いた。
でも、不思議と嫌じゃなかった。
「じゃ、わたしは白石アリサ。よろしくー」
「白石……アリサさん……」
「“さん”とかつけなくていいし。アリサでいいよ」
「えっ、でも……」
「つけたら怒るから」
そう言って、ウインクしてくる。
まるでマンガの中のキャラみたいだった。
わたしの描く登場人物よりずっと自由で、まぶしくて、
でもちゃんと目の前に存在していて――
ああ、わたし、この人のこと、
もっと知りたいって、思ってるんだ。
「アリサさん……じゃなくて、アリサは、学生?」
「一応、高校生。二年」
「えっ、そうなんだ」
「うん。通信制だからあんまり通わないけどね」
「そうなんだ……」
「毎週、この英会話スクールに来るときだけ、電車乗ってんの。だから、ここであんたに会えるの、まあまあ運命だと思ってる」
さらっとそんなこと言うから、心臓が忙しい。
「う、運命って……」
「だって、漫画の続きを楽しみにしてる読者って、けっこうレアでしょ?」
「えっ……」
「わたし、読者第一号だし」
アリサは、ふふんと胸を張った。
ほんの少しだけ、照れた顔をしていた気がした。
その笑顔に、また一歩、距離が縮んだような気がした。
「てか、みのりの描く女の子、髪型ちょっと自分に似てない?」
アリサが笑いながら言った。
その指は、わたしのノートの中――
くるくるした髪の、自由奔放な女の子を指している。
「……うん。たぶん、ちょっと影響されてる」
「へえ? え、なに、わたしのこと好きなの?」
「ち、ちがうっ……! ちがうけど……」
「けど?」
「ちょっとだけ……憧れてる……かも」
口にした瞬間、自分でびっくりした。
こんなこと、言うつもりじゃなかったのに。
でも、それは本当の気持ちだった。
校則も、親の目も、成績も関係なく、
好きな服を着て、言いたいことを言って、
自分の足で歩いているように見える、アリサ。
わたしには持っていない“何か”を、
彼女は自然に持っている気がした。
アリサは、しばらく黙ってわたしを見ていた。
そして、ちょっとだけ、視線をそらしてつぶやいた。
「……あたしのこと、憧れられるような人間じゃないけどね」
その声は、いつもの調子とは少し違っていた。
明るさの奥に、何か冷たいものがあるみたいな――
そんな声だった。
「でもさ、憧れられたからには、もうちょいカッコよく生きなきゃな」
そう言って、今度はいつもの調子に戻って笑う。
その笑顔を見て、わたしはまた思った。
この人のこと、もっと知りたい。
アリサが、どんなふうに笑って、どんなときに黙るのか。
その全部が、わたしの知らない“自由”みたいで、まぶしかった。
その日から、わたしのノートには、
“アリサに見せる漫画”という新しい意味が加わった。
もともとは、誰にも見せるつもりのなかったひみつのノート。
でも今は、放課後のカフェで描いたページを、
次に電車で会ったときに見せるのが、楽しみになっていた。
アリサは、どのページにもちゃんと感想をくれる。
「ここ最高」「このセリフ、刺さる」「もうちょっとツンデレ味足してよ」とか、
ときにはストーリーに口出ししてきたりするけれど――
それが、うれしかった。
まるで、自分の中の“好き”を、
「ちゃんと見てるよ」って言ってもらえるような感覚。
電車の中は、相変わらず揺れるし、ぎゅうぎゅうだし、
眠いし、おなかも痛くなるときがあるけれど、
今は――少し、違って見える。
イヤなことばかりだった帰り道が、
アリサに出会ってから、ちょっとだけ好きになった。
車内アナウンスが、次の停車駅を告げる。
アリサは、ノートをとじながら言った。
「今日もありがと。次、描けたらまた見せてよ」
「うん、描く。たぶん、もっとたくさん」
「期待してっから」
彼女が手を振って、ドアが開く。
そのまま、スニーカーの音を響かせて、人の波に紛れていった。
電車のドアが閉まり、静かになる。
ノートを抱きしめるみたいに持ちながら、
わたしは、もう一度、彼女のいた方を見た。
ほんの数週間前まで、誰にも見せなかったものが、
今は、誰かに届けたくてたまらない。
こんな気持ちを知ってしまったら、
もう前みたいには戻れないかもしれない。
でも――それで、いいかもしれない。
そんな気が、少しだけした。
揺れるし、ぎゅうぎゅうだし、眠いし、
ときどきおなかが痛くなるし、
何より、周りにいる人たちの無言の圧が、重たくて。
だけど最近――電車に乗るのが、少しだけ楽しみになっていた。
あの子と、また会えるかもしれない。
名前も、学校も、なにも知らない。
だけど、わたしの漫画を「おもしろい」って言ってくれた、
あの、金髪の、不思議な子。
彼女がノートを返してくれたあの日から、
なんとなく意識するようになっていた。
(「続き見せてよ」って、ほんとに言ってくれたんだよね)
わたしは、家でこっそり新しいページを描き足していた。
授業中じゃない。
帰ってから、宿題を終えて、誰も見ていない夜の机で。
シャーペンを握りながら、彼女の顔を思い出す。
あのとき、「面白い」って言われたときの、心臓のどくん、どくん。
誰かに見てもらいたいって、
思ったのなんて、たぶん初めてだった。
駅のホームに立っていると、ふと風が吹いて、
制服の襟元がそよいだ。
わたしはその手で、首元を押さえながら、辺りを見回す。
彼女の姿はなかった。
今日はいないのかも。
でも、それはそれでいい。
また会えるかもしれないっていうだけで、
昨日よりちょっとだけ、心が軽くなる。
「電車に乗る理由がもうひとつできるなんて、
ちょっとだけ、大人になったみたいだなあ……」
小さく、つぶやいてみる。
それは、だれにも聞かせたくない、
わたしだけの、小さな秘密だった。
次にあの子に会ったのは、三日後の放課後だった。
今日はたまたま、授業が早く終わって、
一本早い電車に乗れた。
座れるかもしれないと思っていたのに、
車内は意外と混んでいて、立ったままつり革をつかむ。
足元の感覚をたしかめながら、バッグに手を伸ばして、
いつものように、英語の問題集を出そうとした――
そのときだった。
「おー、いた」
軽い声が、耳に飛びこんできた。
反射的に顔を上げると、すぐ目の前に、あの子がいた。
金髪の、少しふわっとした髪。
パーカーの袖からのぞく細い指先。
イヤホンの片耳を外して、わたしを見ている。
「この前の……」
「漫画の子でしょ? わたし、あれけっこう気に入ってるんだよね」
「え、ええと……ありがとう」
どきどきして、何を言えばいいのかわからなかった。
目の前にいるのに、なんだか現実じゃないみたいだった。
(話しかけてくれた……わたしのこと、覚えてたんだ)
「ちなみに、続きは? 描いた?」
「……うん。少しだけ」
「見たい!」
即答だった。
わたしはバッグの中を探って、ノートをそっと取り出す。
手がちょっと震えていたけど、見せたかった。
ノートを開いたとたん、彼女の顔がぐっと近づいた。
「うわ……マジでちゃんと描いてるじゃん。
やば、てかこれ、次のコマ、絶対キスするやつじゃん!」
「し、しないから!」
「しないの!? しようよ! しちゃおうよ!」
「だ、だめだよ!まだ心の準備が!」
電車の中なのに、ふたりでわちゃわちゃ言い合って、
わたしの顔は真っ赤だった。
だけどそのとき、ふと思った。
こんなふうに、誰かと笑いながら話すの――
どれくらい、ぶりだろう。
「……てか、あんた、名前なんて言うの?」
ページをめくりながら、彼女が言った。
その瞬間、心臓がひとつ跳ねた気がした。
(名前……そうだ。わたし、名乗ってなかった)
「み、水野です。水野みのり」
「あー、みのり。オーケー、みのりね」
あっさりと呼び捨てにされて、すこし驚いた。
でも、不思議と嫌じゃなかった。
「じゃ、わたしは白石アリサ。よろしくー」
「白石……アリサさん……」
「“さん”とかつけなくていいし。アリサでいいよ」
「えっ、でも……」
「つけたら怒るから」
そう言って、ウインクしてくる。
まるでマンガの中のキャラみたいだった。
わたしの描く登場人物よりずっと自由で、まぶしくて、
でもちゃんと目の前に存在していて――
ああ、わたし、この人のこと、
もっと知りたいって、思ってるんだ。
「アリサさん……じゃなくて、アリサは、学生?」
「一応、高校生。二年」
「えっ、そうなんだ」
「うん。通信制だからあんまり通わないけどね」
「そうなんだ……」
「毎週、この英会話スクールに来るときだけ、電車乗ってんの。だから、ここであんたに会えるの、まあまあ運命だと思ってる」
さらっとそんなこと言うから、心臓が忙しい。
「う、運命って……」
「だって、漫画の続きを楽しみにしてる読者って、けっこうレアでしょ?」
「えっ……」
「わたし、読者第一号だし」
アリサは、ふふんと胸を張った。
ほんの少しだけ、照れた顔をしていた気がした。
その笑顔に、また一歩、距離が縮んだような気がした。
「てか、みのりの描く女の子、髪型ちょっと自分に似てない?」
アリサが笑いながら言った。
その指は、わたしのノートの中――
くるくるした髪の、自由奔放な女の子を指している。
「……うん。たぶん、ちょっと影響されてる」
「へえ? え、なに、わたしのこと好きなの?」
「ち、ちがうっ……! ちがうけど……」
「けど?」
「ちょっとだけ……憧れてる……かも」
口にした瞬間、自分でびっくりした。
こんなこと、言うつもりじゃなかったのに。
でも、それは本当の気持ちだった。
校則も、親の目も、成績も関係なく、
好きな服を着て、言いたいことを言って、
自分の足で歩いているように見える、アリサ。
わたしには持っていない“何か”を、
彼女は自然に持っている気がした。
アリサは、しばらく黙ってわたしを見ていた。
そして、ちょっとだけ、視線をそらしてつぶやいた。
「……あたしのこと、憧れられるような人間じゃないけどね」
その声は、いつもの調子とは少し違っていた。
明るさの奥に、何か冷たいものがあるみたいな――
そんな声だった。
「でもさ、憧れられたからには、もうちょいカッコよく生きなきゃな」
そう言って、今度はいつもの調子に戻って笑う。
その笑顔を見て、わたしはまた思った。
この人のこと、もっと知りたい。
アリサが、どんなふうに笑って、どんなときに黙るのか。
その全部が、わたしの知らない“自由”みたいで、まぶしかった。
その日から、わたしのノートには、
“アリサに見せる漫画”という新しい意味が加わった。
もともとは、誰にも見せるつもりのなかったひみつのノート。
でも今は、放課後のカフェで描いたページを、
次に電車で会ったときに見せるのが、楽しみになっていた。
アリサは、どのページにもちゃんと感想をくれる。
「ここ最高」「このセリフ、刺さる」「もうちょっとツンデレ味足してよ」とか、
ときにはストーリーに口出ししてきたりするけれど――
それが、うれしかった。
まるで、自分の中の“好き”を、
「ちゃんと見てるよ」って言ってもらえるような感覚。
電車の中は、相変わらず揺れるし、ぎゅうぎゅうだし、
眠いし、おなかも痛くなるときがあるけれど、
今は――少し、違って見える。
イヤなことばかりだった帰り道が、
アリサに出会ってから、ちょっとだけ好きになった。
車内アナウンスが、次の停車駅を告げる。
アリサは、ノートをとじながら言った。
「今日もありがと。次、描けたらまた見せてよ」
「うん、描く。たぶん、もっとたくさん」
「期待してっから」
彼女が手を振って、ドアが開く。
そのまま、スニーカーの音を響かせて、人の波に紛れていった。
電車のドアが閉まり、静かになる。
ノートを抱きしめるみたいに持ちながら、
わたしは、もう一度、彼女のいた方を見た。
ほんの数週間前まで、誰にも見せなかったものが、
今は、誰かに届けたくてたまらない。
こんな気持ちを知ってしまったら、
もう前みたいには戻れないかもしれない。
でも――それで、いいかもしれない。
そんな気が、少しだけした。