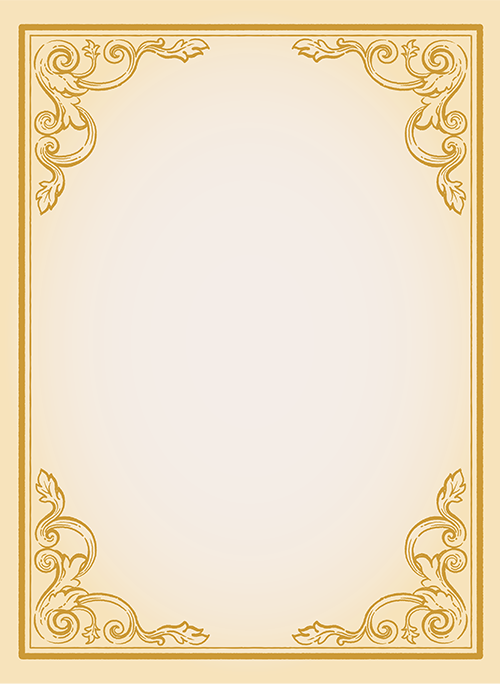あれから、五日が経った。
毎日、電車に乗るたびに、わたしは無意識に車両を見回していた。
もしかしたら、また会えるかもしれない。
いや、もう二度と会いたくない。
そのふたつの気持ちが、心の中で行ったり来たりしていた。
あのギャルの子は、いったい誰だったんだろう。
「水野さん、理科のノート見せてもらえる?」
お昼休み、クラスメイトの中島さんが、声をかけてきた。
「あ、うん。……これ」
わたしはおそるおそるノートを渡す。
中島さんはぺらぺらとページをめくって、
「へえ、字きれいだね」と言った。
「そう、かな……ありがとう」
お礼を言ったけれど、
それ以上話は広がらなかった。
ノートを返されたあと、いつものように、静かな時間が流れていく。
(このままで、いいんだよね)
誰にも迷惑をかけず、目立たず、校則を守って。
この学校で生き残るには、それがいちばん安全な方法だった。
それでも心のどこかで、
「うっさい!」って言い放った、あの強い声が、
ずっと耳の奥に残っていた。
その日も、帰りの電車は満員だった。
吊り革をつかんで立っていると、
つり革の列のちょうど向こう側に――見覚えのある髪色が見えた。
金色、というにはやわらかくて、
でも光の下ではさらっと光る、あの髪。
わたしは思わず、背筋を正した。
(いる……)
声をかけようかどうしようか、迷った。
でも、何を話せばいいのか、わからなかった。
彼女は、わたしに気づいていないふうで、スマホを見ていた。
黒いパーカーに、ショートパンツ。
耳には大きめのイヤホン。
指先には、うっすらと水色のネイルが光っていた。
やっぱり、わたしの世界とはぜんぜん違う。
お母さんが見たら、絶対に「目を合わせちゃだめ」って言いそうな子だ。
でも、わたしは、なぜだか目が離せなかった。
彼女がちらりと顔を上げたとき、
ばちん、と目が合った。
一瞬、体がこわばる。
だけど彼女は、何の感情もないみたいに、ふいっと視線を外した。
まるで、知らない人を見るように。
そっけないというよりも、まるで――忘れられてるみたいな感じだった。
電車が次の駅に着くと、彼女は降りていった。
わたしは、ただ立ちつくしていた。
声をかけたかったのに。
……やっぱり、何もできなかった。
(このまま、また会えなくなったら……)
そう思ったとき、胸の奥がきゅうっと痛んだ。
「水野さん、最近、なんかぼーっとしてる?」
放課後、教室でノートをまとめていたら、
クラスメイトの中島さんがちらっと言った。
「えっ……そうかな?」
「うん、なんか、顔に『気になってることあります』って書いてある」
冗談っぽく笑って、彼女は自分の席に戻っていった。
わたしは、ぼーっとしていたつもりはなかった。
ただ、気づいたら、またあの子のことを考えていた。
たぶん、何かが気になって仕方がないのは、たしかだった。
それから数日。
わたしは、何度かあの子と同じ電車に乗り合わせた。
だけど、いつも一駅だけで降りてしまう。
声をかけようとするたび、心臓がどくどくして、結局何も言えずに終わる。
(タイミングがあったら、ちゃんと謝りたい)
(ちゃんと、あのときのこと、言いたい)
そんな気持ちだけが、心の中で積もっていく。
その日も、変わらない帰り道だった。
駅の改札を通って、階段をのぼって、プラットホームへ。
でも、わたしはまだ気づいていなかった。
その日だけは、少しだけ特別な日になるということを。
電車のドアが開いた瞬間、
いつものように、スマホを見ながら乗り込んできた、金髪の彼女。
今日は、ミニスカートじゃなくて、
ちょっとだけ丈の長いワンピースみたいな服を着ていた。
そしてその手には――見覚えのあるものがあった。
黒いゴムのバンドでとめられた、ノート。
表紙の角がすこしめくれていて、隅っこに、わたしの名前。
(えっ……)
わたしの、漫画のノート――!
「それ、わたしの……!」
思わず声が出た。
彼女がぱっと顔を上げ、わたしを見た。
眉をすこし上げて、目を細める。
「……あんたか。これ、落としたっしょ」
ノートを軽く掲げて見せながら、少しだけ唇をゆるめる。
「まじでびっくりした。落書き帳かと思ったら、がっつり漫画じゃん。しかも、めっちゃ続き気になるんだけど」
「えっ……!」
驚きすぎて、声が裏返った。
(読んだの!?全部!?全部あの恥ずかしいやつ!?)
「や、あの、それは、その……」
「でさ、あの女の子がさ、次にどうなるの?告白するの?てか、相手の男、実は双子ってマジ?」
「わ、わああ、やめてえええええ!!」
わたしは両手で顔を覆った。
耳まで熱くて、声が震えてた。
なのに彼女は――
くすっと、小さく笑った。
「あは。なんでそんな恥ずかしがってんの。普通に、おもしろかったし」
「うそ……」
「うそじゃないって。わたし、漫画好きだし。
てか、これ、自分で描いてんの?下描きなし?」
「え、うん……ペン入れしてないだけで、シャーペンで……」
「すげえじゃん。才能あるんじゃね?」
その言葉は、まるで反則みたいだった。
誰にも見せたことがなかったノート。
ただ、描きたい気持ちにまかせて、机のすみに隠れて描いてたやつ。
それを、こんなふうに言われるなんて、思ってなかった。
わたしは、黙ってノートを受け取った。
心臓がばくばくして、
でも、ほんの少しだけ――あったかかった。
ノートを胸に抱えながら、
わたしは彼女――アリサ、という名前だとあとで知る――の隣に立っていた。
彼女はそれ以上、あれこれ詮索してこなかった。
ただ、「漫画、続き描けたらまた見せてよ」とだけ言った。
電車の窓に映る自分の顔が、少しだけいつもと違って見えた。
ほっぺたが、ほんのり赤くて。
目元が、なぜか少しきらきらしていた。
わたしの中で、「まじめ」は盾みたいなものだった。
それがあれば叱られないし、
失望されないし、
正しい自分でいられると思っていた。
だけど、あの子はその盾を、まるで紙みたいに軽々とめくってきた。
恥ずかしいノートを読まれて、怒られるかと思ったのに、
まっすぐに「面白かった」と言った。
そんなの、ずるい。
ずるいのに――
ちょっと、うれしかった。
彼女が降りる駅が近づいて、ドアの前に立った。
わたしはその背中を見て、思い切って聞いた。
「……あのとき、『うっさい』って言ったの、なんでだったんですか?」
彼女はぴたりと立ち止まった。
一瞬だけ、振り向いて、笑わなかった顔で言った。
「さあ。なんでだろうね」
そのまま、何も言わずに電車を降りていった。
毎日、電車に乗るたびに、わたしは無意識に車両を見回していた。
もしかしたら、また会えるかもしれない。
いや、もう二度と会いたくない。
そのふたつの気持ちが、心の中で行ったり来たりしていた。
あのギャルの子は、いったい誰だったんだろう。
「水野さん、理科のノート見せてもらえる?」
お昼休み、クラスメイトの中島さんが、声をかけてきた。
「あ、うん。……これ」
わたしはおそるおそるノートを渡す。
中島さんはぺらぺらとページをめくって、
「へえ、字きれいだね」と言った。
「そう、かな……ありがとう」
お礼を言ったけれど、
それ以上話は広がらなかった。
ノートを返されたあと、いつものように、静かな時間が流れていく。
(このままで、いいんだよね)
誰にも迷惑をかけず、目立たず、校則を守って。
この学校で生き残るには、それがいちばん安全な方法だった。
それでも心のどこかで、
「うっさい!」って言い放った、あの強い声が、
ずっと耳の奥に残っていた。
その日も、帰りの電車は満員だった。
吊り革をつかんで立っていると、
つり革の列のちょうど向こう側に――見覚えのある髪色が見えた。
金色、というにはやわらかくて、
でも光の下ではさらっと光る、あの髪。
わたしは思わず、背筋を正した。
(いる……)
声をかけようかどうしようか、迷った。
でも、何を話せばいいのか、わからなかった。
彼女は、わたしに気づいていないふうで、スマホを見ていた。
黒いパーカーに、ショートパンツ。
耳には大きめのイヤホン。
指先には、うっすらと水色のネイルが光っていた。
やっぱり、わたしの世界とはぜんぜん違う。
お母さんが見たら、絶対に「目を合わせちゃだめ」って言いそうな子だ。
でも、わたしは、なぜだか目が離せなかった。
彼女がちらりと顔を上げたとき、
ばちん、と目が合った。
一瞬、体がこわばる。
だけど彼女は、何の感情もないみたいに、ふいっと視線を外した。
まるで、知らない人を見るように。
そっけないというよりも、まるで――忘れられてるみたいな感じだった。
電車が次の駅に着くと、彼女は降りていった。
わたしは、ただ立ちつくしていた。
声をかけたかったのに。
……やっぱり、何もできなかった。
(このまま、また会えなくなったら……)
そう思ったとき、胸の奥がきゅうっと痛んだ。
「水野さん、最近、なんかぼーっとしてる?」
放課後、教室でノートをまとめていたら、
クラスメイトの中島さんがちらっと言った。
「えっ……そうかな?」
「うん、なんか、顔に『気になってることあります』って書いてある」
冗談っぽく笑って、彼女は自分の席に戻っていった。
わたしは、ぼーっとしていたつもりはなかった。
ただ、気づいたら、またあの子のことを考えていた。
たぶん、何かが気になって仕方がないのは、たしかだった。
それから数日。
わたしは、何度かあの子と同じ電車に乗り合わせた。
だけど、いつも一駅だけで降りてしまう。
声をかけようとするたび、心臓がどくどくして、結局何も言えずに終わる。
(タイミングがあったら、ちゃんと謝りたい)
(ちゃんと、あのときのこと、言いたい)
そんな気持ちだけが、心の中で積もっていく。
その日も、変わらない帰り道だった。
駅の改札を通って、階段をのぼって、プラットホームへ。
でも、わたしはまだ気づいていなかった。
その日だけは、少しだけ特別な日になるということを。
電車のドアが開いた瞬間、
いつものように、スマホを見ながら乗り込んできた、金髪の彼女。
今日は、ミニスカートじゃなくて、
ちょっとだけ丈の長いワンピースみたいな服を着ていた。
そしてその手には――見覚えのあるものがあった。
黒いゴムのバンドでとめられた、ノート。
表紙の角がすこしめくれていて、隅っこに、わたしの名前。
(えっ……)
わたしの、漫画のノート――!
「それ、わたしの……!」
思わず声が出た。
彼女がぱっと顔を上げ、わたしを見た。
眉をすこし上げて、目を細める。
「……あんたか。これ、落としたっしょ」
ノートを軽く掲げて見せながら、少しだけ唇をゆるめる。
「まじでびっくりした。落書き帳かと思ったら、がっつり漫画じゃん。しかも、めっちゃ続き気になるんだけど」
「えっ……!」
驚きすぎて、声が裏返った。
(読んだの!?全部!?全部あの恥ずかしいやつ!?)
「や、あの、それは、その……」
「でさ、あの女の子がさ、次にどうなるの?告白するの?てか、相手の男、実は双子ってマジ?」
「わ、わああ、やめてえええええ!!」
わたしは両手で顔を覆った。
耳まで熱くて、声が震えてた。
なのに彼女は――
くすっと、小さく笑った。
「あは。なんでそんな恥ずかしがってんの。普通に、おもしろかったし」
「うそ……」
「うそじゃないって。わたし、漫画好きだし。
てか、これ、自分で描いてんの?下描きなし?」
「え、うん……ペン入れしてないだけで、シャーペンで……」
「すげえじゃん。才能あるんじゃね?」
その言葉は、まるで反則みたいだった。
誰にも見せたことがなかったノート。
ただ、描きたい気持ちにまかせて、机のすみに隠れて描いてたやつ。
それを、こんなふうに言われるなんて、思ってなかった。
わたしは、黙ってノートを受け取った。
心臓がばくばくして、
でも、ほんの少しだけ――あったかかった。
ノートを胸に抱えながら、
わたしは彼女――アリサ、という名前だとあとで知る――の隣に立っていた。
彼女はそれ以上、あれこれ詮索してこなかった。
ただ、「漫画、続き描けたらまた見せてよ」とだけ言った。
電車の窓に映る自分の顔が、少しだけいつもと違って見えた。
ほっぺたが、ほんのり赤くて。
目元が、なぜか少しきらきらしていた。
わたしの中で、「まじめ」は盾みたいなものだった。
それがあれば叱られないし、
失望されないし、
正しい自分でいられると思っていた。
だけど、あの子はその盾を、まるで紙みたいに軽々とめくってきた。
恥ずかしいノートを読まれて、怒られるかと思ったのに、
まっすぐに「面白かった」と言った。
そんなの、ずるい。
ずるいのに――
ちょっと、うれしかった。
彼女が降りる駅が近づいて、ドアの前に立った。
わたしはその背中を見て、思い切って聞いた。
「……あのとき、『うっさい』って言ったの、なんでだったんですか?」
彼女はぴたりと立ち止まった。
一瞬だけ、振り向いて、笑わなかった顔で言った。
「さあ。なんでだろうね」
そのまま、何も言わずに電車を降りていった。