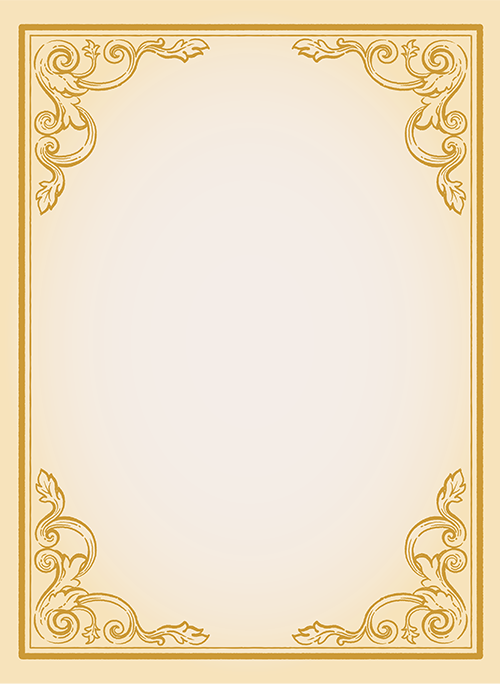朝の教室は、いつも音が薄い。
同じ制服、同じ髪型、同じ表情。
机に座っている子たちは、みんな静かに単語帳をめくっていて、
まるで、同じ工場で作られた人形みたいだった。
その中に、わたし――水野みのりも、ちゃんと収まっていた。
黒髪を一つに結び、ひざ下のスカートをきっちり整えて。
机の上に広げるのは、先生が配ったプリントの問題集。
B列12番、窓側。
定位置。
「水野さん、朝テストのプリント、回してくれる?」
前の席の子が、無表情に手を伸ばす。
「あ、うん」
わたしは、小さく返事してプリントを回す。
声が、小さかったかな。聞こえたかな。
でも、相手は何も言わずにプリントを受け取って、くるっと前を向いた。
それで終わり。
返事がなくても、悪口を言われるわけじゃない。
いじめられているわけでもない。
ただ、透明な壁みたいなものがある。
その壁の向こうから、わたしはそっと覗いているだけだ。
(わたし、今日もちゃんと「まじめ」になれてるかな)
そう心の中で問いかけながら、制服の襟元をさわる。
しっかり形が整っているか、何度も指先でなぞるのが、朝の習慣だった。
校則に違反しなければ、叱られない。
叱られなければ、母に睨まれない。
睨まれなければ、安心できる。
安心できれば――今日も、ちゃんと「わたし」でいられる。
それが、わたしの「ふつう」だった。
その日の放課後、わたしは電車の中で勉強をしていた。
帰り道の、乗り換え前のたった二駅。
でもこの短い時間すら無駄にしたくない。
……というより、成績が落ちて、母に呼び出されたくなかった。
「D組の成績、これ以上下がったらどうなるか、わかってるわよね」
そう言われたのが、つい先週。
「すみません」としか言えなかったけど、
本当は『どうなるんだろう』なんて、聞かなくても知ってる。
お母さんの目が、わたしを「がっかりなもの」として見ているときの、あの静かな絶望感。
その目を向けられるくらいなら、居眠りなんて絶対にしない。
だからわたしは、混み合う電車の座席で、膝にノートを広げていた。
英語のイディオム、あと10個は覚えたい。
「by and large」は……ええと、たいてい、一般的に……。
ペン先がページを滑る音だけに集中していた、そのとき。
「ねえ、妊婦さんに席ゆずってくんない?」
声がして、はっと顔を上げた。
すぐ隣に、立っていた。
大きなおなかをかばうようにして、両手でつり革を握っている妊婦さんが。
その妊婦さんの後ろで、しゃがれた声の主――ギャルみたいな女の子が、わたしをじっと見ていた。
金髪のような、でもどこか柔らかい色の髪。
濃いめのメイク。まつげが長くて、リップがつやつやしてる。
制服じゃない。黒のパーカーに、チェックのミニスカート。
脚が、長くて細くて――
一瞬、テレビの中から出てきたみたいに思えた。
その子が、すこし眉をひそめて、もう一度言った。
「席、譲れるでしょ?」
「す、すみません……!」
あわてて立ち上がって、妊婦さんにぺこりと頭を下げた。
妊婦さんは少し驚いた顔をしながら、
「ありがとう」と言って腰をおろす。
足元の重心をゆっくり移して、ほっとしたように小さく笑った。
その横顔を見ながら、わたしの胸はぎゅっと締めつけられていた。
どうしてすぐに気づけなかったんだろう。
どうして、譲れなかったんだろう。
わたしはずっと目の前のページに集中していた。
「勉強している自分」に必死だった。
席を譲ることより、英単語を一つでも多く覚えることにしがみついていた。
「まじめ」でいないといけない――
そう思っていたのに、それはただの独りよがりだったんじゃないかって、急に足元がぐらついた。
「あの……ありがとう、教えてくれて……」
後ろを振り返って、お礼を言おうとした。
だけどその子――さっきのギャルは、なんだか苦しそうな顔で立っていた。
彼女の顔色は、さっきよりずっと悪い。
唇が白っぽくなっていて、額に汗が浮いている。
「だ、大丈夫ですか?」
わたしが声をかけたそのとき――
「……うっさい!」
その一言は針のように鋭くて、
胸にすっと突き刺さった。
ギャルの子は、わたしを一瞥して、
まるで逃げるように電車を降りていった。
何が起きたのかわからなかった。
ただ、わたしは呆然とドアの外を見つめていた。
その日の帰り道、わたしはずっと胸の奥がざわざわしていた。
席を譲れなかったこと。
気づけなかったこと。
声をかけたのに「うっさい」と言われたこと。
どれが一番気になってるのか、自分でもよくわからなかった。
だけど、あの子の顔――電車を降りる直前の、あの苦しそうな顔が、ずっと脳裏にこびりついて離れなかった。
家に帰ると、父がキッチンでお弁当の下ごしらえをしていた。
「おかえり」と笑いかけてくれるその笑顔も、
どこか上滑りして感じるのは、わたしの気のせいだろうか。
リビングには母の姿がなかった。
たぶん、仕事部屋で資料か英語のプレゼンでも作ってるんだろう。
「成績表、机の上に置いてあるから。見ておいて」
そう言ったきり、朝から口をきいていない。
今月の中間テスト、化学が平均点を割った。
次、数学が落ちたら、また呼び出される。
先生じゃなくて、母に。
翌朝。
いつもより早く家を出た。
理由は特にない。ただ、なんとなく――「同じ電車に乗るかもしれない」と思ったのだ。
わたしは駅のホームで、電車が来るのを待ちながら、制服の袖をそっと引っ張った。
白いセーラー。きちんとした襟。清潔なスカートのひだ。
この制服を着ていると、誰にも文句を言われない。
間違っていないって、自分で自分を守っていられる。
だけど。
昨日の電車の中では――「ちゃんとしているわたし」は、だれかを傷つけたのかもしれなかった。
電車が来て、わたしは乗り込む。
目で、まわりを探してしまう。
あの子はいなかった。
そりゃそうだ。
名前も知らない。学校も違う。
きっと、もう会うことはない。
でも、胸の奥で何かがちくりと疼いた。
「もう会えなくてもいい」って言い切れないくらい、あの子は不思議な存在だった。
授業中も、英単語を覚えているときも、
ふとした瞬間に、思い出す。
「うっさい」って言ったあの子の顔。
そして、それ以上に――
席を譲れなかった自分のことを、思い出す。
たった一言で、たった数秒で、
なにかが変わってしまった気がした。
だけどそれが、「いいこと」なのか「悪いこと」なのか、
わたしには、まだよくわからなかった。
同じ制服、同じ髪型、同じ表情。
机に座っている子たちは、みんな静かに単語帳をめくっていて、
まるで、同じ工場で作られた人形みたいだった。
その中に、わたし――水野みのりも、ちゃんと収まっていた。
黒髪を一つに結び、ひざ下のスカートをきっちり整えて。
机の上に広げるのは、先生が配ったプリントの問題集。
B列12番、窓側。
定位置。
「水野さん、朝テストのプリント、回してくれる?」
前の席の子が、無表情に手を伸ばす。
「あ、うん」
わたしは、小さく返事してプリントを回す。
声が、小さかったかな。聞こえたかな。
でも、相手は何も言わずにプリントを受け取って、くるっと前を向いた。
それで終わり。
返事がなくても、悪口を言われるわけじゃない。
いじめられているわけでもない。
ただ、透明な壁みたいなものがある。
その壁の向こうから、わたしはそっと覗いているだけだ。
(わたし、今日もちゃんと「まじめ」になれてるかな)
そう心の中で問いかけながら、制服の襟元をさわる。
しっかり形が整っているか、何度も指先でなぞるのが、朝の習慣だった。
校則に違反しなければ、叱られない。
叱られなければ、母に睨まれない。
睨まれなければ、安心できる。
安心できれば――今日も、ちゃんと「わたし」でいられる。
それが、わたしの「ふつう」だった。
その日の放課後、わたしは電車の中で勉強をしていた。
帰り道の、乗り換え前のたった二駅。
でもこの短い時間すら無駄にしたくない。
……というより、成績が落ちて、母に呼び出されたくなかった。
「D組の成績、これ以上下がったらどうなるか、わかってるわよね」
そう言われたのが、つい先週。
「すみません」としか言えなかったけど、
本当は『どうなるんだろう』なんて、聞かなくても知ってる。
お母さんの目が、わたしを「がっかりなもの」として見ているときの、あの静かな絶望感。
その目を向けられるくらいなら、居眠りなんて絶対にしない。
だからわたしは、混み合う電車の座席で、膝にノートを広げていた。
英語のイディオム、あと10個は覚えたい。
「by and large」は……ええと、たいてい、一般的に……。
ペン先がページを滑る音だけに集中していた、そのとき。
「ねえ、妊婦さんに席ゆずってくんない?」
声がして、はっと顔を上げた。
すぐ隣に、立っていた。
大きなおなかをかばうようにして、両手でつり革を握っている妊婦さんが。
その妊婦さんの後ろで、しゃがれた声の主――ギャルみたいな女の子が、わたしをじっと見ていた。
金髪のような、でもどこか柔らかい色の髪。
濃いめのメイク。まつげが長くて、リップがつやつやしてる。
制服じゃない。黒のパーカーに、チェックのミニスカート。
脚が、長くて細くて――
一瞬、テレビの中から出てきたみたいに思えた。
その子が、すこし眉をひそめて、もう一度言った。
「席、譲れるでしょ?」
「す、すみません……!」
あわてて立ち上がって、妊婦さんにぺこりと頭を下げた。
妊婦さんは少し驚いた顔をしながら、
「ありがとう」と言って腰をおろす。
足元の重心をゆっくり移して、ほっとしたように小さく笑った。
その横顔を見ながら、わたしの胸はぎゅっと締めつけられていた。
どうしてすぐに気づけなかったんだろう。
どうして、譲れなかったんだろう。
わたしはずっと目の前のページに集中していた。
「勉強している自分」に必死だった。
席を譲ることより、英単語を一つでも多く覚えることにしがみついていた。
「まじめ」でいないといけない――
そう思っていたのに、それはただの独りよがりだったんじゃないかって、急に足元がぐらついた。
「あの……ありがとう、教えてくれて……」
後ろを振り返って、お礼を言おうとした。
だけどその子――さっきのギャルは、なんだか苦しそうな顔で立っていた。
彼女の顔色は、さっきよりずっと悪い。
唇が白っぽくなっていて、額に汗が浮いている。
「だ、大丈夫ですか?」
わたしが声をかけたそのとき――
「……うっさい!」
その一言は針のように鋭くて、
胸にすっと突き刺さった。
ギャルの子は、わたしを一瞥して、
まるで逃げるように電車を降りていった。
何が起きたのかわからなかった。
ただ、わたしは呆然とドアの外を見つめていた。
その日の帰り道、わたしはずっと胸の奥がざわざわしていた。
席を譲れなかったこと。
気づけなかったこと。
声をかけたのに「うっさい」と言われたこと。
どれが一番気になってるのか、自分でもよくわからなかった。
だけど、あの子の顔――電車を降りる直前の、あの苦しそうな顔が、ずっと脳裏にこびりついて離れなかった。
家に帰ると、父がキッチンでお弁当の下ごしらえをしていた。
「おかえり」と笑いかけてくれるその笑顔も、
どこか上滑りして感じるのは、わたしの気のせいだろうか。
リビングには母の姿がなかった。
たぶん、仕事部屋で資料か英語のプレゼンでも作ってるんだろう。
「成績表、机の上に置いてあるから。見ておいて」
そう言ったきり、朝から口をきいていない。
今月の中間テスト、化学が平均点を割った。
次、数学が落ちたら、また呼び出される。
先生じゃなくて、母に。
翌朝。
いつもより早く家を出た。
理由は特にない。ただ、なんとなく――「同じ電車に乗るかもしれない」と思ったのだ。
わたしは駅のホームで、電車が来るのを待ちながら、制服の袖をそっと引っ張った。
白いセーラー。きちんとした襟。清潔なスカートのひだ。
この制服を着ていると、誰にも文句を言われない。
間違っていないって、自分で自分を守っていられる。
だけど。
昨日の電車の中では――「ちゃんとしているわたし」は、だれかを傷つけたのかもしれなかった。
電車が来て、わたしは乗り込む。
目で、まわりを探してしまう。
あの子はいなかった。
そりゃそうだ。
名前も知らない。学校も違う。
きっと、もう会うことはない。
でも、胸の奥で何かがちくりと疼いた。
「もう会えなくてもいい」って言い切れないくらい、あの子は不思議な存在だった。
授業中も、英単語を覚えているときも、
ふとした瞬間に、思い出す。
「うっさい」って言ったあの子の顔。
そして、それ以上に――
席を譲れなかった自分のことを、思い出す。
たった一言で、たった数秒で、
なにかが変わってしまった気がした。
だけどそれが、「いいこと」なのか「悪いこと」なのか、
わたしには、まだよくわからなかった。