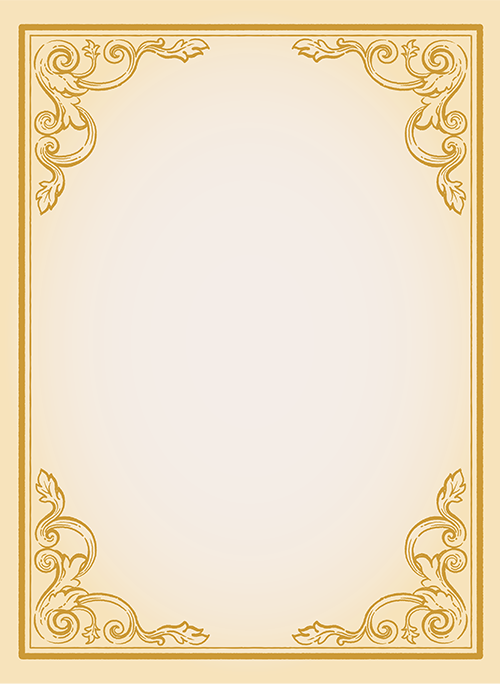次の日、放課後のカフェで、アリサと向かい合った。
二人で並んで座っているだけなのに、
胸の奥がずっとあたたかかった。
「これ、昨日描いたやつ」
わたしは、ノートをそっと差し出した。
アリサはぱらぱらとページをめくる。
途中、笑ったり、眉をひそめたり、じっと見入ったり。
その反応を見ているだけで、胸がくすぐったくなる。
「……なんか、表情が変わったね。前より」
「え?」
「キャラの顔。迷ってない顔してる。いいじゃん、これ」
「ほんと?」
「うん。あんた、ほんとに戻ってきたんだなって思った」
うれしかった。
褒められたことももちろんだけど、
「戻ってきた」って言ってもらえたのが、一番うれしかった。
わたしが、自分の「好き」を捨てずにいられたことが、
ちゃんと誰かに伝わってる。
それだけで、心がぽかぽかした。
「アリサはさ、いつ夢を『これにする』って決めたの?」
「んー、たぶん、ちゃんと決めたのは……金鳳花やめてからかな」
「え?」
「それまでは、できることの中から選んでた。
英語得意だから海外行こうかな、とか、
数学好きだから理系もアリかな、とか。
でも、やりたいかって言われると、なんか違っててさ」
「……うん」
「退学して、空っぽになってからやっと気づいたんだよね。
あたし、本当は、自分が楽しかった学校に行きたかったんだって。
それで、自分でそういう学校つくろうって、思ったの」
わたしは目を見開いた。
「自分で……?」
「うん。自由で、居場所のある学校。
ちゃんと『好き』が肯定されるようなとこ。……なんか、欲張りかな?」
アリサは照れくさそうに笑った。
でも、その目は、少しも曇っていなかった。
あたし、この人のこと、
ほんとうにかっこいいって思う。
「アリサって、すごいね」
わたしはそう言った。
本心だった。
「自分のやりたいこと、ちゃんとわかってて、言葉にできてて」
「んー、でも、わたしも時間かかったよ」
アリサはストローを指でくるくる回しながら、わたしを見た。
「みのりは? いま、『やりたい』って思ってること、ちゃんとあるでしょ?」
「……ある」
わたしはうなずいた。
「描くこと。……わたし、漫画、ずっと描いてたい」
その言葉を口に出したとき、
胸の奥がぽっと灯ったみたいに、あたたかくなった。
「プロとか、仕事とか、そういうのはまだわからないけど……
でも、ずっと描いてたいって思うの。
描いてるときの自分が、いちばん『わたし』な気がするから」
アリサは、にっと笑った。
「それでいいんだよ。夢って、最初は『好き』だけで充分だから」
「……うん」
わたしは、そっとノートを閉じた。
「わたしさ」
アリサが言った。
「たぶん、学校が変わってなかったら、みのりと出会わなかったよね」
「うん……そうかも」
「変わっちゃったこと、最初はすごく悔しかったけど、
でも、変わったから会えた人がいるって思えたら、
ちょっとだけ、救われる気がするんだ」
その言葉に、わたしは心の奥で静かにうなずいた。
「ねえ、みのり」
アリサがふいに、まっすぐな声で言った。
「これから、どんな道に進んでもさ。
あんた、描くのはやめないでよね」
その言葉が、心にまっすぐ刺さった。
「……うん。やめない。絶対」
わたしは、すぐにそう言えた。
「それ、約束」
アリサが小指を出す。
「約束」
わたしも小指を差し出して、絡めた。
わたしたちは笑い合った。
「じゃあさ、十年後」
アリサが目を細めた。
「わたし、日本で学校つくってると思う。たぶん。
でもまだ、現場に立つ準備してる途中かな」
「うん」
「で、みのりは?」
「え?」
「十年後、なにしてる?」
わたしは少しだけ考えてから、答えた。
「出版社とかで働いてるといいな。
漫画に関われる場所で。……そしたら、誰かの『描きたい』を応援できる気がするから」
「いいじゃん、それ」
「……で、自分の作品も、こっそり描き続けてる。たぶん」
アリサが笑う。
「こっそりじゃなくて、堂々とやりなよ」
「そのときは、アリサの学校の壁に貼ってよ」
「えー、校長の許可が要るけど、わたしか。よし、検討します!」
ふたりで声を立てて笑った。
あの日の不安も、涙も、あの沈黙も。
全部この笑いの中で、遠くなっていく気がした。
カフェを出ると、空はすっかり夜になっていた。
街灯の下を、制服姿のわたしとミニスカートのアリサが並んで歩く。
笑い合ったあとの沈黙は、まるで安心の証みたいに、心地よく続いた。
「ねえ、アリサ」
「なに?」
「ありがとう」
アリサは、ふっと笑ってわたしの頭を軽くたたいた。
「礼なんかいいって。あんたもわたしの背中押してくれたんだから。
……こういうの、持ちつ持たれつって言うんでしょ?」
「……うん」
笑いながら、胸の奥がぽっとあたたかくなる。
わたしたちは、互いの夢に光を灯し合った。
わたしたちは、それぞれの『好き』を選んだ。
わたし、ちゃんと、生きてるよ。
夜空にぽっかり浮かぶ月が、私たちを照らしていた。
二人で並んで座っているだけなのに、
胸の奥がずっとあたたかかった。
「これ、昨日描いたやつ」
わたしは、ノートをそっと差し出した。
アリサはぱらぱらとページをめくる。
途中、笑ったり、眉をひそめたり、じっと見入ったり。
その反応を見ているだけで、胸がくすぐったくなる。
「……なんか、表情が変わったね。前より」
「え?」
「キャラの顔。迷ってない顔してる。いいじゃん、これ」
「ほんと?」
「うん。あんた、ほんとに戻ってきたんだなって思った」
うれしかった。
褒められたことももちろんだけど、
「戻ってきた」って言ってもらえたのが、一番うれしかった。
わたしが、自分の「好き」を捨てずにいられたことが、
ちゃんと誰かに伝わってる。
それだけで、心がぽかぽかした。
「アリサはさ、いつ夢を『これにする』って決めたの?」
「んー、たぶん、ちゃんと決めたのは……金鳳花やめてからかな」
「え?」
「それまでは、できることの中から選んでた。
英語得意だから海外行こうかな、とか、
数学好きだから理系もアリかな、とか。
でも、やりたいかって言われると、なんか違っててさ」
「……うん」
「退学して、空っぽになってからやっと気づいたんだよね。
あたし、本当は、自分が楽しかった学校に行きたかったんだって。
それで、自分でそういう学校つくろうって、思ったの」
わたしは目を見開いた。
「自分で……?」
「うん。自由で、居場所のある学校。
ちゃんと『好き』が肯定されるようなとこ。……なんか、欲張りかな?」
アリサは照れくさそうに笑った。
でも、その目は、少しも曇っていなかった。
あたし、この人のこと、
ほんとうにかっこいいって思う。
「アリサって、すごいね」
わたしはそう言った。
本心だった。
「自分のやりたいこと、ちゃんとわかってて、言葉にできてて」
「んー、でも、わたしも時間かかったよ」
アリサはストローを指でくるくる回しながら、わたしを見た。
「みのりは? いま、『やりたい』って思ってること、ちゃんとあるでしょ?」
「……ある」
わたしはうなずいた。
「描くこと。……わたし、漫画、ずっと描いてたい」
その言葉を口に出したとき、
胸の奥がぽっと灯ったみたいに、あたたかくなった。
「プロとか、仕事とか、そういうのはまだわからないけど……
でも、ずっと描いてたいって思うの。
描いてるときの自分が、いちばん『わたし』な気がするから」
アリサは、にっと笑った。
「それでいいんだよ。夢って、最初は『好き』だけで充分だから」
「……うん」
わたしは、そっとノートを閉じた。
「わたしさ」
アリサが言った。
「たぶん、学校が変わってなかったら、みのりと出会わなかったよね」
「うん……そうかも」
「変わっちゃったこと、最初はすごく悔しかったけど、
でも、変わったから会えた人がいるって思えたら、
ちょっとだけ、救われる気がするんだ」
その言葉に、わたしは心の奥で静かにうなずいた。
「ねえ、みのり」
アリサがふいに、まっすぐな声で言った。
「これから、どんな道に進んでもさ。
あんた、描くのはやめないでよね」
その言葉が、心にまっすぐ刺さった。
「……うん。やめない。絶対」
わたしは、すぐにそう言えた。
「それ、約束」
アリサが小指を出す。
「約束」
わたしも小指を差し出して、絡めた。
わたしたちは笑い合った。
「じゃあさ、十年後」
アリサが目を細めた。
「わたし、日本で学校つくってると思う。たぶん。
でもまだ、現場に立つ準備してる途中かな」
「うん」
「で、みのりは?」
「え?」
「十年後、なにしてる?」
わたしは少しだけ考えてから、答えた。
「出版社とかで働いてるといいな。
漫画に関われる場所で。……そしたら、誰かの『描きたい』を応援できる気がするから」
「いいじゃん、それ」
「……で、自分の作品も、こっそり描き続けてる。たぶん」
アリサが笑う。
「こっそりじゃなくて、堂々とやりなよ」
「そのときは、アリサの学校の壁に貼ってよ」
「えー、校長の許可が要るけど、わたしか。よし、検討します!」
ふたりで声を立てて笑った。
あの日の不安も、涙も、あの沈黙も。
全部この笑いの中で、遠くなっていく気がした。
カフェを出ると、空はすっかり夜になっていた。
街灯の下を、制服姿のわたしとミニスカートのアリサが並んで歩く。
笑い合ったあとの沈黙は、まるで安心の証みたいに、心地よく続いた。
「ねえ、アリサ」
「なに?」
「ありがとう」
アリサは、ふっと笑ってわたしの頭を軽くたたいた。
「礼なんかいいって。あんたもわたしの背中押してくれたんだから。
……こういうの、持ちつ持たれつって言うんでしょ?」
「……うん」
笑いながら、胸の奥がぽっとあたたかくなる。
わたしたちは、互いの夢に光を灯し合った。
わたしたちは、それぞれの『好き』を選んだ。
わたし、ちゃんと、生きてるよ。
夜空にぽっかり浮かぶ月が、私たちを照らしていた。