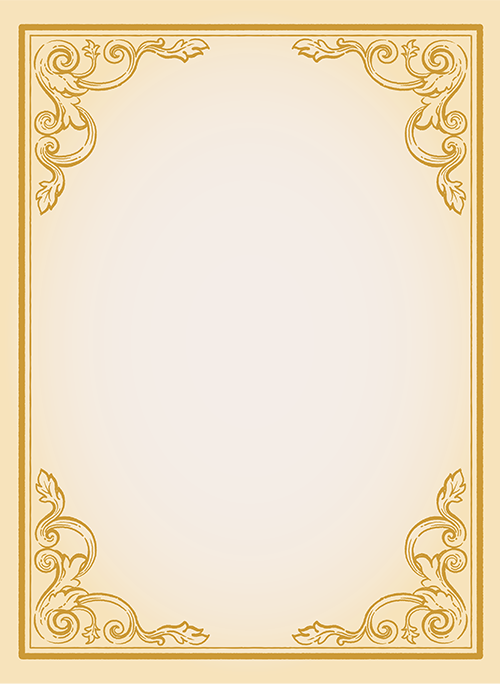「成績、このままでいいと思ってるの?」
日曜の朝、朝食の食卓にて。
母はトーストをかじる手を止めずに、
そう言った。
わたしの顔は見なかった。
でも、その声は鋭かった。
「……別に、よくないけど」
「『よくないけど』? あなたね、少しは危機感持ってるの?」
「持ってるよ。でも……」
わたしの声が、途中でかすれる。
言葉が喉で引っかかる感覚。
心臓がどくどくする。
でも、もう逃げないって決めたんだ。
描くことを、夢を、自分の「好き」を。
「わたし、描きたいの。漫画。
自由に、もっと好きなことやって生きていきたい」
母のフォークが、皿の上でカチンと音を立てた。
顔を上げた母の表情は、想像していたよりずっと冷たい。
「いいかげんにして」
その言葉が、わたしの胸をぐらぐら揺らす。
「あなたは高校生なの。
『自由に生きたい』なんて、そんなの社会に出てから言いなさい」
「じゃあ、高校生は夢見ちゃいけないの?」
声が大きくなった。
「わたし、好きなことすら言っちゃいけないの?」
母の顔がこわばった。
わたしも、怖かった。
でも、この言葉だけは、言いたかった。
「わたし、本当は――」
言葉が唇にかかった瞬間、父が入ってきた。
空気が一気に冷える。
わたしは、それでも続けた。
「わたし、遊びたい。自由になりたい。……漫画家になりたい!」
声が少し震えた。
でも、言い終えた瞬間、胸の奥がすうっと軽くなった。
両親は、何も言わなかった。
ただ、沈黙があった。
わたしにとって、それが答えだった。
沈黙は、予想以上に長かった。
母はわたしを見たまま、ひとことも発しなかった。
父も同じだった。
いつものように「まあまあ」と笑って間を埋めることもなかった。
ただ、ふたりの目が、まるで何かを確認するように、じっとわたしを見つめていた。
怖くなかったといえば、嘘になる。
でも、叫んだあとのわたしの胸の中には、
確かな「すっきり」が残っていた。
ようやく言えた。
ほんとうに言いたかったこと。
ずっと言えなかったのは、
夢を壊されるのが怖かったから。
でも今はちがう。
言えたことで、ようやく自分が自分に戻れた気がした。
「……ごちそうさま」
わたしは食べかけのトーストを置いて、立ち上がった。
自分の部屋に戻ると、ドアを閉めて背中を預けた。
それから数日間、わたしたち家族の間に会話はなかった。
朝は「いってきます」と「いってらっしゃい」だけ。
夕食の時間も、テレビの音だけが部屋に響いていた。
母は相変わらず忙しそうで、
帰宅してもわたしの部屋の前を素通りする。
父は気まずそうに、でもどこかあきらめたような空気をまとっていた。
そんな静かな家の中で、
わたしの心だけが、少しずつ変わっていた。
夕暮れどき、机に向かってノートを開く。
迷わずペンをとるのは、久しぶりだった。
キャラクターたちは、わたしの手の中でゆっくりと動き出す。
泣いていた子が笑い、うつむいていた子が前を向く。
それは、まるで今のわたしそのものだった。
誰にも見せなくても、
誰にも認められなくても、
この時間だけは、ほんとうに自由だった。
(アリサ……会いたいな)
ふと、そう思った。
わたしはスマホを手に取り、
画面を見つめながら、そっとメッセージを打った。
「元気にしてる? 少しだけ、話したいことがあるんだ」
送信ボタンを押したあとの胸の高鳴りは、
夢を語るときのそれと、きっと同じだった。
メッセージを送ったあとの数時間は、永遠のように長かった。
スマホを何度も確認しては、画面を伏せて、また手に取る。
その繰り返しの中で、わたしは自分の呼吸を整えるように、ゆっくりノートを開いた。
線を引くたび、心の奥にしまい込んでいた“わたし”が、すこしずつ戻ってくる。
あの日、アリサに言われたあの言葉。
「ばかなのは、あんただよ」
あの言葉には、
「信じてたのに」って気持ちが込められていた。
信じてくれてたから、怒ったんだ。
だからこそ、わたしも今――ちゃんと向き合いたい。
夢に。
そして、アリサに。
スマホが震えた。
一瞬、鼓動が止まる。
アリサからだった。
「話したいこと、って何?」
「今から会える?」
わたしは目を見開いて、その画面を見つめた。
心臓が高鳴る。
でも、こわくない。
もう、伝えたいことが決まってるから。
わたしは深呼吸をして、返信した。
「うん。伝えたいこと、ちゃんとあるから」
ページの上では、主人公の女の子が前を向いていた。
わたし自身も、その続きを描ける気がしていた。
駅前の小さなカフェ。
ドアを開けると、アリサがいた。
窓際の席に、肘をついてこちらを見ている。
目が合うと、ふっと視線を外した。
でも、その表情が怒っていないことに、少しだけ安心した。
「ひさしぶり」
「……うん」
ぎこちないけど、それでも、わたしたちは目を見て話せた。
カフェラテを前に、沈黙が落ちる。
わたしは、自分の指先を見ながら、少しずつ言葉を探した。
「この前……ごめん」
アリサは、何も言わない。
「夢、やめたって言ったけど、やっぱりうそだった。
ほんとは、あきらめきれなかった。……描いてる。今も」
言いながら、胸の奥がじんとあたたかくなった。
やっと言えた。ちゃんと、自分の言葉で。
「ばからしいって、自分で言って、
そのあと、すごく苦しくなって。
だから、もう一度描いてみたの。そしたら……」
わたしはアリサの目を見て、笑った。
「やっぱり、すきだった」
アリサは、わたしをまっすぐ見つめたまま、ぽつりと言った。
「……ふーん」
わたしは、何か言われるのを待った。
怒られるかもしれない。呆れられるかもしれない。
でも、その次の瞬間、アリサの口元がふっとゆるんだ。
「――あんた、よくやったよ」
その言葉に、胸の奥が、じんわりと熱くなった。
涙が出そうになるのをこらえて、わたしはうなずいた。
「ありがと」
ほんとうに、心からそう思った。
窓の外は夕焼けで、空がにじんでいた。
ふたりで見る景色が、少しだけ違って見えた。
日曜の朝、朝食の食卓にて。
母はトーストをかじる手を止めずに、
そう言った。
わたしの顔は見なかった。
でも、その声は鋭かった。
「……別に、よくないけど」
「『よくないけど』? あなたね、少しは危機感持ってるの?」
「持ってるよ。でも……」
わたしの声が、途中でかすれる。
言葉が喉で引っかかる感覚。
心臓がどくどくする。
でも、もう逃げないって決めたんだ。
描くことを、夢を、自分の「好き」を。
「わたし、描きたいの。漫画。
自由に、もっと好きなことやって生きていきたい」
母のフォークが、皿の上でカチンと音を立てた。
顔を上げた母の表情は、想像していたよりずっと冷たい。
「いいかげんにして」
その言葉が、わたしの胸をぐらぐら揺らす。
「あなたは高校生なの。
『自由に生きたい』なんて、そんなの社会に出てから言いなさい」
「じゃあ、高校生は夢見ちゃいけないの?」
声が大きくなった。
「わたし、好きなことすら言っちゃいけないの?」
母の顔がこわばった。
わたしも、怖かった。
でも、この言葉だけは、言いたかった。
「わたし、本当は――」
言葉が唇にかかった瞬間、父が入ってきた。
空気が一気に冷える。
わたしは、それでも続けた。
「わたし、遊びたい。自由になりたい。……漫画家になりたい!」
声が少し震えた。
でも、言い終えた瞬間、胸の奥がすうっと軽くなった。
両親は、何も言わなかった。
ただ、沈黙があった。
わたしにとって、それが答えだった。
沈黙は、予想以上に長かった。
母はわたしを見たまま、ひとことも発しなかった。
父も同じだった。
いつものように「まあまあ」と笑って間を埋めることもなかった。
ただ、ふたりの目が、まるで何かを確認するように、じっとわたしを見つめていた。
怖くなかったといえば、嘘になる。
でも、叫んだあとのわたしの胸の中には、
確かな「すっきり」が残っていた。
ようやく言えた。
ほんとうに言いたかったこと。
ずっと言えなかったのは、
夢を壊されるのが怖かったから。
でも今はちがう。
言えたことで、ようやく自分が自分に戻れた気がした。
「……ごちそうさま」
わたしは食べかけのトーストを置いて、立ち上がった。
自分の部屋に戻ると、ドアを閉めて背中を預けた。
それから数日間、わたしたち家族の間に会話はなかった。
朝は「いってきます」と「いってらっしゃい」だけ。
夕食の時間も、テレビの音だけが部屋に響いていた。
母は相変わらず忙しそうで、
帰宅してもわたしの部屋の前を素通りする。
父は気まずそうに、でもどこかあきらめたような空気をまとっていた。
そんな静かな家の中で、
わたしの心だけが、少しずつ変わっていた。
夕暮れどき、机に向かってノートを開く。
迷わずペンをとるのは、久しぶりだった。
キャラクターたちは、わたしの手の中でゆっくりと動き出す。
泣いていた子が笑い、うつむいていた子が前を向く。
それは、まるで今のわたしそのものだった。
誰にも見せなくても、
誰にも認められなくても、
この時間だけは、ほんとうに自由だった。
(アリサ……会いたいな)
ふと、そう思った。
わたしはスマホを手に取り、
画面を見つめながら、そっとメッセージを打った。
「元気にしてる? 少しだけ、話したいことがあるんだ」
送信ボタンを押したあとの胸の高鳴りは、
夢を語るときのそれと、きっと同じだった。
メッセージを送ったあとの数時間は、永遠のように長かった。
スマホを何度も確認しては、画面を伏せて、また手に取る。
その繰り返しの中で、わたしは自分の呼吸を整えるように、ゆっくりノートを開いた。
線を引くたび、心の奥にしまい込んでいた“わたし”が、すこしずつ戻ってくる。
あの日、アリサに言われたあの言葉。
「ばかなのは、あんただよ」
あの言葉には、
「信じてたのに」って気持ちが込められていた。
信じてくれてたから、怒ったんだ。
だからこそ、わたしも今――ちゃんと向き合いたい。
夢に。
そして、アリサに。
スマホが震えた。
一瞬、鼓動が止まる。
アリサからだった。
「話したいこと、って何?」
「今から会える?」
わたしは目を見開いて、その画面を見つめた。
心臓が高鳴る。
でも、こわくない。
もう、伝えたいことが決まってるから。
わたしは深呼吸をして、返信した。
「うん。伝えたいこと、ちゃんとあるから」
ページの上では、主人公の女の子が前を向いていた。
わたし自身も、その続きを描ける気がしていた。
駅前の小さなカフェ。
ドアを開けると、アリサがいた。
窓際の席に、肘をついてこちらを見ている。
目が合うと、ふっと視線を外した。
でも、その表情が怒っていないことに、少しだけ安心した。
「ひさしぶり」
「……うん」
ぎこちないけど、それでも、わたしたちは目を見て話せた。
カフェラテを前に、沈黙が落ちる。
わたしは、自分の指先を見ながら、少しずつ言葉を探した。
「この前……ごめん」
アリサは、何も言わない。
「夢、やめたって言ったけど、やっぱりうそだった。
ほんとは、あきらめきれなかった。……描いてる。今も」
言いながら、胸の奥がじんとあたたかくなった。
やっと言えた。ちゃんと、自分の言葉で。
「ばからしいって、自分で言って、
そのあと、すごく苦しくなって。
だから、もう一度描いてみたの。そしたら……」
わたしはアリサの目を見て、笑った。
「やっぱり、すきだった」
アリサは、わたしをまっすぐ見つめたまま、ぽつりと言った。
「……ふーん」
わたしは、何か言われるのを待った。
怒られるかもしれない。呆れられるかもしれない。
でも、その次の瞬間、アリサの口元がふっとゆるんだ。
「――あんた、よくやったよ」
その言葉に、胸の奥が、じんわりと熱くなった。
涙が出そうになるのをこらえて、わたしはうなずいた。
「ありがと」
ほんとうに、心からそう思った。
窓の外は夕焼けで、空がにじんでいた。
ふたりで見る景色が、少しだけ違って見えた。