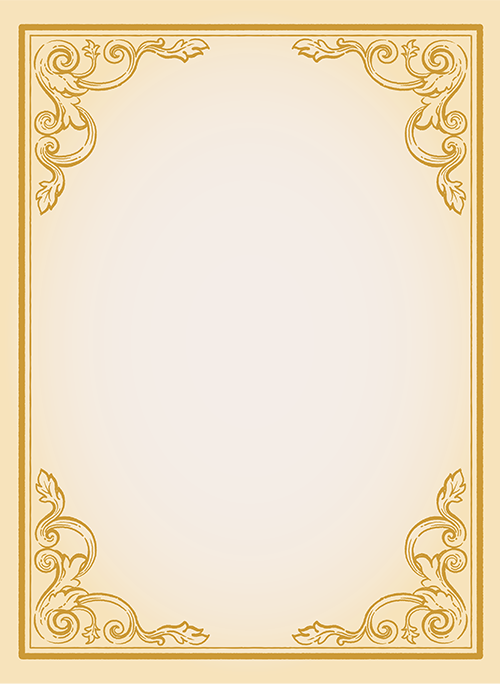アリサからの返信は、来なかった。
既読すらつかないまま、三日が過ぎた。
電車でも、カフェでも、駅のホームでも、姿を見かけることはなかった。
それだけで、わたしの世界は、少し色を失ったような気がした。
わたしは今、アリサに何も言えない。
怖かった。嫌われるのが。
でも、それ以上に怖いのは、
また何も言えないまま、わたしが自分を捨ててしまうことだった。
アリサが言った言葉が、何度もよみがえる。
「そんな簡単にあきらめられる夢には見えなかったけど」
「ばかなのは、あんただよ」
あれは、わたしの夢の姿を一番近くで見てくれていた人のことばだ。
本気だった。信じてくれていた。
それをわたし自身が踏みにじった。
わたしは、ノートの片隅にペンで書いた。
「描きたい。まだ、終わってない」
文字はにじんで、少しゆがんでいた。
でもそれでも、自分の気持ちを自分の手で書いたことで、
胸の奥が、ほんの少しだけ、あたたかくなった。
「お母さん、今日も遅いの?」
そう聞いたのは父だった。
リビングのソファで新聞を読んでいた父は、
わたしの声にちらりと目を向けた。
「会議らしいよ。最近多いね」
「……うん」
それだけの会話が、やけに重たく感じた。
母が家にいない夜。
わたしはほっとする反面、少しだけさびしかった。
さびしいと思ってしまう自分に驚いた。
本当は、話したかったのかもしれない。
母に、怖くても。
わたしがいま何を思っていて、
何を描いていて、
なぜそれを手放したくなかったのか。
でも、あの人の前では、いつも言葉が消えてしまう。
「また漫画、描いてるのか?」
父が不意に言った。
びくっとした。
「……ちょっとだけ」
「お母さんには、言ったのか?」
「言ってない。言えるわけない」
そう返した声が、思ったより強かった。
父はそれ以上、何も言わなかった。
それが優しさなのか、関心のなさなのか、
わたしにはわからなかった。
でも、わたしは立ち上がって、ノートを抱えて自室に戻った。
自分の部屋のドアを閉めた瞬間、
ようやく息ができた。
開いたノートの前で、
「わたし、ちゃんと描いてるよ」と心の中でつぶやいた。
誰にも聞こえなくても、
この言葉だけは、自分に届けておきたかった。
アリサにメッセージを送ってから、もう一週間が過ぎた。
既読はついていたけれど、返事はなかった。
『ちゃんと話したい』って、たったそれだけの言葉が、
こんなにも届かないものなんだと知った。
わたしの手は、毎晩ノートを開いていた。
だけど、ページの半分も埋まらない。
描いては、止まり、
また描いては、消す。
自分の線に、自信が持てなくなっていた。
(わたし、また逃げてるのかな)
母にもまだ何も言えていない。
アリサにはあれ以来、顔すら見せられない。
そして、わたし自身にも――
ほんとうの「やりたいこと」を、まっすぐ認めることが、まだできないでいた。
でも、その気持ちをごまかせない時間がある。
夜。ひとりきりの部屋。
誰にも見られていない場所で、
わたしの心が一番素直になる。
だからこそ、はっきりする。
「やりたい」って気持ちは、まだここにある。
悔しいほど、消えてくれない。
だったらもう一度、ちゃんと見てやろうと思った。
自分の本音を。
自分の弱さを。
そして、自分の『好き』を。
机に置いたスマホの画面を見つめる。
「返信ください」なんて、もう送らない。
でも、アリサに伝えたい言葉はまだ、たくさんある。
その日の夜も、わたしは机に向かっていた。
ノートの前で、ただ一点を見つめる。
鉛筆を握って、何かを描こうとして、手が止まる。
(これって……誰のために描いてるんだろう)
ふと、そんなことを思った。
母に認められたくて。
アリサに応援してもらいたくて。
でも――それだけじゃなかった。
ほんとうは、誰にも見られなくてもよかった。
描いている間だけは、
自分の心に正直でいられる気がしたから。
「ばからしいから、やめた」
あの瞬間、夢を捨てようとした自分を、
いちばん許せていないのは、たぶん――わたしだ。
わたしは、描き始めた。
誰かに見せるためじゃない。
ただ、「わたしのため」に。
ペンを持つ指に力を込めた。
ノートのページに、新しい線が引かれていく。
泣いている女の子が、ページの中に立っていた。
でも、その表情は前よりも少しだけ強かった。
描き終わったあと、深く息を吐いた。
静かな部屋の中で、自分の心の音だけが聞こえる。
あの日、アリサが言ってくれたあの言葉が、
わたしを止めてくれた。
「ばかなのは、あんただよ」
それが、わたしにとっての「本当のはじまり」だった。
まだ何も変わっていない。
だけど――わたしは、もう逃げない。
夢を守るって、
たぶん、こういうことなのかもしれない。
既読すらつかないまま、三日が過ぎた。
電車でも、カフェでも、駅のホームでも、姿を見かけることはなかった。
それだけで、わたしの世界は、少し色を失ったような気がした。
わたしは今、アリサに何も言えない。
怖かった。嫌われるのが。
でも、それ以上に怖いのは、
また何も言えないまま、わたしが自分を捨ててしまうことだった。
アリサが言った言葉が、何度もよみがえる。
「そんな簡単にあきらめられる夢には見えなかったけど」
「ばかなのは、あんただよ」
あれは、わたしの夢の姿を一番近くで見てくれていた人のことばだ。
本気だった。信じてくれていた。
それをわたし自身が踏みにじった。
わたしは、ノートの片隅にペンで書いた。
「描きたい。まだ、終わってない」
文字はにじんで、少しゆがんでいた。
でもそれでも、自分の気持ちを自分の手で書いたことで、
胸の奥が、ほんの少しだけ、あたたかくなった。
「お母さん、今日も遅いの?」
そう聞いたのは父だった。
リビングのソファで新聞を読んでいた父は、
わたしの声にちらりと目を向けた。
「会議らしいよ。最近多いね」
「……うん」
それだけの会話が、やけに重たく感じた。
母が家にいない夜。
わたしはほっとする反面、少しだけさびしかった。
さびしいと思ってしまう自分に驚いた。
本当は、話したかったのかもしれない。
母に、怖くても。
わたしがいま何を思っていて、
何を描いていて、
なぜそれを手放したくなかったのか。
でも、あの人の前では、いつも言葉が消えてしまう。
「また漫画、描いてるのか?」
父が不意に言った。
びくっとした。
「……ちょっとだけ」
「お母さんには、言ったのか?」
「言ってない。言えるわけない」
そう返した声が、思ったより強かった。
父はそれ以上、何も言わなかった。
それが優しさなのか、関心のなさなのか、
わたしにはわからなかった。
でも、わたしは立ち上がって、ノートを抱えて自室に戻った。
自分の部屋のドアを閉めた瞬間、
ようやく息ができた。
開いたノートの前で、
「わたし、ちゃんと描いてるよ」と心の中でつぶやいた。
誰にも聞こえなくても、
この言葉だけは、自分に届けておきたかった。
アリサにメッセージを送ってから、もう一週間が過ぎた。
既読はついていたけれど、返事はなかった。
『ちゃんと話したい』って、たったそれだけの言葉が、
こんなにも届かないものなんだと知った。
わたしの手は、毎晩ノートを開いていた。
だけど、ページの半分も埋まらない。
描いては、止まり、
また描いては、消す。
自分の線に、自信が持てなくなっていた。
(わたし、また逃げてるのかな)
母にもまだ何も言えていない。
アリサにはあれ以来、顔すら見せられない。
そして、わたし自身にも――
ほんとうの「やりたいこと」を、まっすぐ認めることが、まだできないでいた。
でも、その気持ちをごまかせない時間がある。
夜。ひとりきりの部屋。
誰にも見られていない場所で、
わたしの心が一番素直になる。
だからこそ、はっきりする。
「やりたい」って気持ちは、まだここにある。
悔しいほど、消えてくれない。
だったらもう一度、ちゃんと見てやろうと思った。
自分の本音を。
自分の弱さを。
そして、自分の『好き』を。
机に置いたスマホの画面を見つめる。
「返信ください」なんて、もう送らない。
でも、アリサに伝えたい言葉はまだ、たくさんある。
その日の夜も、わたしは机に向かっていた。
ノートの前で、ただ一点を見つめる。
鉛筆を握って、何かを描こうとして、手が止まる。
(これって……誰のために描いてるんだろう)
ふと、そんなことを思った。
母に認められたくて。
アリサに応援してもらいたくて。
でも――それだけじゃなかった。
ほんとうは、誰にも見られなくてもよかった。
描いている間だけは、
自分の心に正直でいられる気がしたから。
「ばからしいから、やめた」
あの瞬間、夢を捨てようとした自分を、
いちばん許せていないのは、たぶん――わたしだ。
わたしは、描き始めた。
誰かに見せるためじゃない。
ただ、「わたしのため」に。
ペンを持つ指に力を込めた。
ノートのページに、新しい線が引かれていく。
泣いている女の子が、ページの中に立っていた。
でも、その表情は前よりも少しだけ強かった。
描き終わったあと、深く息を吐いた。
静かな部屋の中で、自分の心の音だけが聞こえる。
あの日、アリサが言ってくれたあの言葉が、
わたしを止めてくれた。
「ばかなのは、あんただよ」
それが、わたしにとっての「本当のはじまり」だった。
まだ何も変わっていない。
だけど――わたしは、もう逃げない。
夢を守るって、
たぶん、こういうことなのかもしれない。