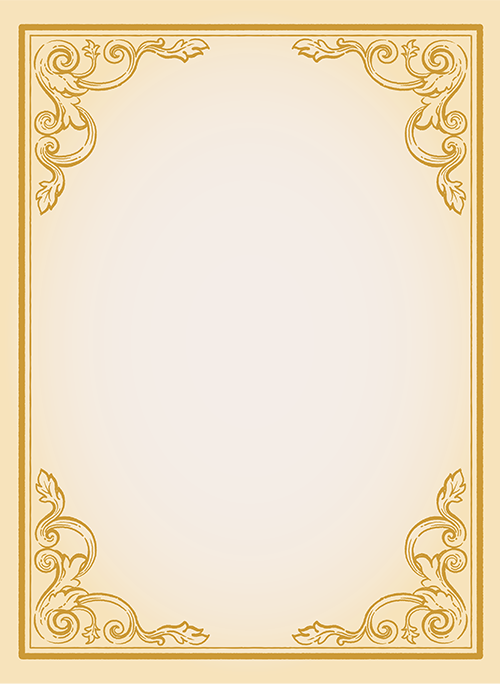廊下の掲示板の前に、人だかりができていた。
成績一覧。中間テストの結果。
貼り出された紙を前に、みんながざわざわと声を交わすなか、
わたしは、その端っこの列に、自分の名前を見つけた。
(……下がってる)
それは、はっきりと「落ちた」と言える順位だった。
(漫画なんて描いてるから……)
頭の中で、母の声が響く。
それはまだ聞いてもいないはずなのに、はっきりとした責め言葉になって、
喉の奥をぎゅっと締めつけた。
放課後、家に帰ると、母はリビングで待っていた。
机の上には、成績通知のコピー。
わたしが部屋に入るのと同時に、
母の視線が、鋭く突き刺さる。
「なに、これ」
第一声は、それだった。
「……ごめんなさい」
「『ごめんなさい』で何とかなる点数じゃないわよ」
静かな怒気を含んだ口調。
「努力の結果がこれ? なにが原因? 言ってみなさい」
わたしは、下を向いたまま答えた。
「……描いてたから。漫画。ちょっとだけ」
次の瞬間、空気が凍った。
「漫画?」
「……うん。でも、もうやめる。……ばからしいって思ったから」
口をついて出たその言葉に、わたし自身が一瞬、驚いた。
(本当にそう思ってる?)
でも、母の目は緩まなかった。
「そう。じゃあ、さっさと勉強に戻りなさい。
もう、無駄なことはしないようにね」
「……うん」
その夜、わたしはノートを開かなかった。
ページの上で止まった線が、今にも泣き出しそうだった。
次の日、アリサと電車でばったり会った。
「おっす」
いつもと変わらない声。
だけどわたしは、なんとなく視線を合わせられなかった。
「昨日、LINEの返事なかったね。元気してた?」
「……うん。まあ」
「てかさ、こないだ描いてた漫画、続き見せてくれるって言ってたじゃん」
「……やめた」
アリサの足が止まる。
「は?」
「描くの、やめた。漫画家になるの、あきらめた。
ばからしいなって思っただけ」
自分で言ったその言葉が、耳の奥で反響する。
胸の奥に何か冷たいものが広がっていく。
でも、もう『夢を持ってる自分』でいるのが苦しかった。
アリサは、しばらく黙っていた。
電車のアナウンスが流れて、乗り込む人たちの声が重なるなか、
その静けさだけが妙にくっきりしていた。
「……そんな簡単に、あきらめられる夢には見えなかったけど?」
低い声だった。
「……」
「ずっと描いてたじゃん。楽しそうだったし、本気だったじゃん。
それを『ばからしい』って、自分で言うの? ほんとに?」
「……だって、親に怒られて、成績も下がって」
「それが理由? だから『やめる』?」
アリサの声が、少しだけ震えていた。
そして、はっきりと。
「ばかなのは、あんただよ」
その一言が、電車の揺れよりずっと強く、わたしの心を突き動かした。
アリサは別の車両に歩いて行った。
何も言い返せなかった。
ずっと黙っていた。
スマホも見られなかったし、ノートも開けなかった。
夢を描くノートは机の上にあるのに、
手が震えて、開けなかった。
アリサの目が頭から離れない。
いつもはきらきらしていて、
明るくて、まっすぐで、まるで太陽みたいな彼女が、
あのときだけは本当に怒っていた。
(わたしのこと、信じてくれてたんだ)
「本気で描いてたくせに、何言ってんの」
って、あの目が言ってた。
わたしは、なにを守ったんだろう。
わたしは、なにを手放したんだろう。
答えが出ないまま、夜が更けていった。
机の上のノートに目をやる。
そこには、まだ最後のページを迎えていない物語がある。
描きかけの主人公の女の子が、
こちらを見ている気がした。
「あなた、ほんとにそれでいいの?」
そう問いかけられているような気がした。
そっと、ページを開く。
ペンを持つ手は、まだ震えている。
でも、線を描き始めたら――すこしだけ、呼吸が整った。
「やっぱり、描きたいよ」
口に出したら、少しだけ涙が出た。
昨日の会話が、胸の奥に残ったままだ。
「ばかなのは、あんただよ」
描くだけじゃなく、
言葉にしなくちゃ――わたしの気持ちを。
通学路を歩きながら、スマホを取り出す。
ゆっくりと、震える指でメッセージを打った。
「アリサ、昨日はごめん。
本当は、まだ描きたい。
ちゃんと話したいから、会える?」
送信ボタンを押すとき、胸がドキドキした。
でも、迷いはなかった。
成績一覧。中間テストの結果。
貼り出された紙を前に、みんながざわざわと声を交わすなか、
わたしは、その端っこの列に、自分の名前を見つけた。
(……下がってる)
それは、はっきりと「落ちた」と言える順位だった。
(漫画なんて描いてるから……)
頭の中で、母の声が響く。
それはまだ聞いてもいないはずなのに、はっきりとした責め言葉になって、
喉の奥をぎゅっと締めつけた。
放課後、家に帰ると、母はリビングで待っていた。
机の上には、成績通知のコピー。
わたしが部屋に入るのと同時に、
母の視線が、鋭く突き刺さる。
「なに、これ」
第一声は、それだった。
「……ごめんなさい」
「『ごめんなさい』で何とかなる点数じゃないわよ」
静かな怒気を含んだ口調。
「努力の結果がこれ? なにが原因? 言ってみなさい」
わたしは、下を向いたまま答えた。
「……描いてたから。漫画。ちょっとだけ」
次の瞬間、空気が凍った。
「漫画?」
「……うん。でも、もうやめる。……ばからしいって思ったから」
口をついて出たその言葉に、わたし自身が一瞬、驚いた。
(本当にそう思ってる?)
でも、母の目は緩まなかった。
「そう。じゃあ、さっさと勉強に戻りなさい。
もう、無駄なことはしないようにね」
「……うん」
その夜、わたしはノートを開かなかった。
ページの上で止まった線が、今にも泣き出しそうだった。
次の日、アリサと電車でばったり会った。
「おっす」
いつもと変わらない声。
だけどわたしは、なんとなく視線を合わせられなかった。
「昨日、LINEの返事なかったね。元気してた?」
「……うん。まあ」
「てかさ、こないだ描いてた漫画、続き見せてくれるって言ってたじゃん」
「……やめた」
アリサの足が止まる。
「は?」
「描くの、やめた。漫画家になるの、あきらめた。
ばからしいなって思っただけ」
自分で言ったその言葉が、耳の奥で反響する。
胸の奥に何か冷たいものが広がっていく。
でも、もう『夢を持ってる自分』でいるのが苦しかった。
アリサは、しばらく黙っていた。
電車のアナウンスが流れて、乗り込む人たちの声が重なるなか、
その静けさだけが妙にくっきりしていた。
「……そんな簡単に、あきらめられる夢には見えなかったけど?」
低い声だった。
「……」
「ずっと描いてたじゃん。楽しそうだったし、本気だったじゃん。
それを『ばからしい』って、自分で言うの? ほんとに?」
「……だって、親に怒られて、成績も下がって」
「それが理由? だから『やめる』?」
アリサの声が、少しだけ震えていた。
そして、はっきりと。
「ばかなのは、あんただよ」
その一言が、電車の揺れよりずっと強く、わたしの心を突き動かした。
アリサは別の車両に歩いて行った。
何も言い返せなかった。
ずっと黙っていた。
スマホも見られなかったし、ノートも開けなかった。
夢を描くノートは机の上にあるのに、
手が震えて、開けなかった。
アリサの目が頭から離れない。
いつもはきらきらしていて、
明るくて、まっすぐで、まるで太陽みたいな彼女が、
あのときだけは本当に怒っていた。
(わたしのこと、信じてくれてたんだ)
「本気で描いてたくせに、何言ってんの」
って、あの目が言ってた。
わたしは、なにを守ったんだろう。
わたしは、なにを手放したんだろう。
答えが出ないまま、夜が更けていった。
机の上のノートに目をやる。
そこには、まだ最後のページを迎えていない物語がある。
描きかけの主人公の女の子が、
こちらを見ている気がした。
「あなた、ほんとにそれでいいの?」
そう問いかけられているような気がした。
そっと、ページを開く。
ペンを持つ手は、まだ震えている。
でも、線を描き始めたら――すこしだけ、呼吸が整った。
「やっぱり、描きたいよ」
口に出したら、少しだけ涙が出た。
昨日の会話が、胸の奥に残ったままだ。
「ばかなのは、あんただよ」
描くだけじゃなく、
言葉にしなくちゃ――わたしの気持ちを。
通学路を歩きながら、スマホを取り出す。
ゆっくりと、震える指でメッセージを打った。
「アリサ、昨日はごめん。
本当は、まだ描きたい。
ちゃんと話したいから、会える?」
送信ボタンを押すとき、胸がドキドキした。
でも、迷いはなかった。