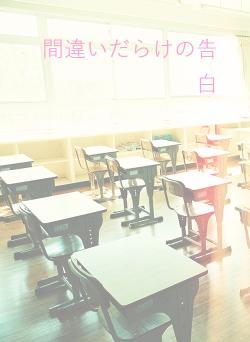葬儀から数日後、夏美の意識が戻ったと担任を通して教えられた。
ただ事故の後遺症のせいで、しばらく学校にはこれなさそうだという。
後遺症などではなく、自分がすでに死んだことにされているという現実に錯乱しているのではないか。
俺にはどうしても、そう思えた。
あの時、俺はどうするべきだったのだろうか。
無言の圧力をかけられても、馬鹿にされても……死んだのは夏美で、今入院しているのは千夏だと言うべきだったのではないか。
もし、などもう有り得もしないのに、どうしても後悔だけが募っていった。
そして目の前には夏美にされた千夏がいる。
どうするべきだったのか。
いや、これからどうすればいいのか。
彼女を見たその瞬間から、答えは一つしかなかった。
「千夏」
俺の言葉に、千夏はさらに顔を歪める。
綺麗な瞳を吊り上がらせ、憎しみを噛みしめるように唇を噛んでいた。
「分かっていたの?」
「ああ」
「分かっていたのなら、なぜ」
「すまない」
「偽善だわ」
謝ったところで、千夏が死んだことにされた事実は変わらない。
千夏の憎しみもそう。
誰一人自分という存在に気付かなかったっこともそうだが、きっとすべてに絶望したのだろう。
「知ってるよ」
睨む彼女に近寄り、その足元に落ちるライターを俺は拾った。
そしてそれをポケットにしまう。
「どういうつもり?」
「君の気が済むまで、一緒に付き合うよ。それが俺の償いさ」
「私はあなたすら殺す気なのかもしれないのに?」
「それならそれでいい。だが、出来れば最後にしてくれ」
俺は千夏をずっと見てきた。
千夏が好きだったから。
だから棺桶の中にいるのが千夏ではなく夏美なのだと気づけたんだ。
だけどそれだけ。
結局何も出来ずに、彼女をただ苦しめてしまった。
協力者になることで、生き延びたいわけではなく、ただ最後まで彼女を見ていたい。
それが最低な俺のエゴだとしても。
「償いって……馬鹿じゃないの」
「そうかな」
千夏は俺から顔を背けた。
俺はそんな彼女の肩に触れる。
「千夏はどうしたい? 復讐か?」
「ええ、そうよ。私を必要としなかった人たちに……。そして私より夏美を選んだ人たちに復讐するの。夏美に殺されるってどんなっ気持ちかしらね」
千夏はこちらを向き、吐き捨てながら笑った。
しかしその瞳からはポロポロと涙がこぼれ落ちる。
「千夏がそうしたいのなら俺は手伝うよ」
まっすぐに千夏を見た。
千夏は俺の目を見たあと、視線を下にそらす。
「でも少し疲れたわ」
そう言いながら千夏は一歩二歩と俺に近づく。
俺はそっと彼女を抱きしめた。
「逃げるか」
俺の言葉に彼女は鼻で笑う。
「せめて逃避行とか、旅行とか。何か言い方はないの?」
「いや、すまん。俺にはそういうレパートリーがなくて」
「まったくもう。山口君らしいわ」
遠くからサイレンの音が聞こえる。
俺たちは手を取り合うと、その場から逃げ出した。
どこまでも降り続く雪が足跡もこの罪も隠してくれるだろう。
もしそうでなくとも構わない。
千夏がいれば……。
罪など怖くはないから――
ただ事故の後遺症のせいで、しばらく学校にはこれなさそうだという。
後遺症などではなく、自分がすでに死んだことにされているという現実に錯乱しているのではないか。
俺にはどうしても、そう思えた。
あの時、俺はどうするべきだったのだろうか。
無言の圧力をかけられても、馬鹿にされても……死んだのは夏美で、今入院しているのは千夏だと言うべきだったのではないか。
もし、などもう有り得もしないのに、どうしても後悔だけが募っていった。
そして目の前には夏美にされた千夏がいる。
どうするべきだったのか。
いや、これからどうすればいいのか。
彼女を見たその瞬間から、答えは一つしかなかった。
「千夏」
俺の言葉に、千夏はさらに顔を歪める。
綺麗な瞳を吊り上がらせ、憎しみを噛みしめるように唇を噛んでいた。
「分かっていたの?」
「ああ」
「分かっていたのなら、なぜ」
「すまない」
「偽善だわ」
謝ったところで、千夏が死んだことにされた事実は変わらない。
千夏の憎しみもそう。
誰一人自分という存在に気付かなかったっこともそうだが、きっとすべてに絶望したのだろう。
「知ってるよ」
睨む彼女に近寄り、その足元に落ちるライターを俺は拾った。
そしてそれをポケットにしまう。
「どういうつもり?」
「君の気が済むまで、一緒に付き合うよ。それが俺の償いさ」
「私はあなたすら殺す気なのかもしれないのに?」
「それならそれでいい。だが、出来れば最後にしてくれ」
俺は千夏をずっと見てきた。
千夏が好きだったから。
だから棺桶の中にいるのが千夏ではなく夏美なのだと気づけたんだ。
だけどそれだけ。
結局何も出来ずに、彼女をただ苦しめてしまった。
協力者になることで、生き延びたいわけではなく、ただ最後まで彼女を見ていたい。
それが最低な俺のエゴだとしても。
「償いって……馬鹿じゃないの」
「そうかな」
千夏は俺から顔を背けた。
俺はそんな彼女の肩に触れる。
「千夏はどうしたい? 復讐か?」
「ええ、そうよ。私を必要としなかった人たちに……。そして私より夏美を選んだ人たちに復讐するの。夏美に殺されるってどんなっ気持ちかしらね」
千夏はこちらを向き、吐き捨てながら笑った。
しかしその瞳からはポロポロと涙がこぼれ落ちる。
「千夏がそうしたいのなら俺は手伝うよ」
まっすぐに千夏を見た。
千夏は俺の目を見たあと、視線を下にそらす。
「でも少し疲れたわ」
そう言いながら千夏は一歩二歩と俺に近づく。
俺はそっと彼女を抱きしめた。
「逃げるか」
俺の言葉に彼女は鼻で笑う。
「せめて逃避行とか、旅行とか。何か言い方はないの?」
「いや、すまん。俺にはそういうレパートリーがなくて」
「まったくもう。山口君らしいわ」
遠くからサイレンの音が聞こえる。
俺たちは手を取り合うと、その場から逃げ出した。
どこまでも降り続く雪が足跡もこの罪も隠してくれるだろう。
もしそうでなくとも構わない。
千夏がいれば……。
罪など怖くはないから――