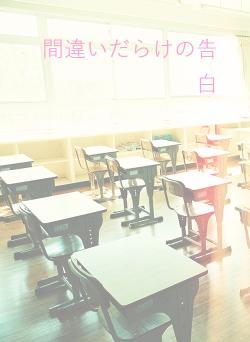その夜、クラスメイトからの緊急連絡を見た瞬間、俺は愕然とした。
街中を走る消防車を帰り道で見てはいたが、それがイコール何に繋がるかなど何も考えていなかったから。
メールには、千夏たちが乗った自動車がカーブを曲がり切れずに崖下へ転落したというもの。
そして翌日の全校集会で、助手席に座っていた千夏が即死。
後部座席に座っていた夏美は重体。母親も重症だという。
皆が咽び泣く体育館で俺は、一つの小さな引っかかりを覚えていた。
葬式は二人の母親の退院を待って、行われた。
夏美の意識はまだ戻らないという。
だからこそ、千夏の死を悲しむと共に、最悪のシナリオにならないことを、誰もが祈っていた。
しかし葬式はどこまでもしめやかに。
あれほど千夏のことを根暗や夏美と全然違うと揶揄していた奴らが泣いている様は、俺にはどうしても滑稽に思えた。
二人の母は、足と手を骨折しており、祭壇の横に置かれた椅子で憔悴しきっていた。
大きな花に囲まれた祭壇の中の千夏の写真。
物静かだが、はにかんように微笑むそれ見た瞬間、俺の中でもやっと人の死というものが実感として湧き上がってくる。
幸い、大事故だったが千夏の顔は綺麗だったという。
だから参列者たちは焼香の後、置かれた棺の中の千夏の顔を見て、皆最後の別れを告げていた。
一人。また一人。
その列はどんどんと進み、見たくないという俺の気持ちなど誰も知らぬうちに、その番は回ってきた。
「千夏?」
物言わぬ一人のその遺体は、綺麗に死に化粧が施されていた。
その顔を見ながら、みんな千夏の名を呼び、涙する。
だが……。千夏じゃない。
俺のあの時感じた小さな違和感は、やはり間違ってなどいなかった。
助手席に乗った千夏が即死。これはどう考えてもあり得なかったから。
千夏は助手席になど絶対に乗らない。
あの家で、千夏はある意味学校よりも空気のような存在だった。
露骨に家族仲が悪いというわけではないが、両親ともに妹の夏美を溺愛していた。
そのため家では、家族との会話などほぼないのだと一度だけ千夏が吐露したことがある。
それに数回、街中で見かけた時も助手席には夏美が座り、母親との会話を楽しんでいた。
つまり――
死んだのは、千夏じゃなくて夏美じゃないか。
焦る気持ちを押さえつつ、辺りを見渡す。
しかし俺と同じようにこの遺体に疑問も持つ者は、この会場には誰一人いなかった。
むしろ両親すら、死亡したのは千夏だと思い込んでいる。
いや、思い込んでいる以上に、もう死亡手続きも終わっているのだろう。
どうしたら……どうすればいいんだ。
今ここで俺が騒いだところでどうにかなるか?
むしろ頭がおかしいヤツと思われるだけじゃないのか?
もしかしたら、本当に頭がおかしくなっただけなのか?
千夏が死んでほしくないと思っていたから。
分からない。分からない。
何が本当で、俺の目の前にいるのが誰なのか。
考えれば考えるほど、分からなくなる。
いや、頭が考えることを拒否していた。
夏美として入院する千夏の意識は、現状まだ戻っていないという。
今ここで騒ぎを起こしたところで、それを証明する術など、俺には何一つなかった。
せめて千夏の意識が戻っていたら……。
そう思いながら、ふと今の現状を考えた。
もしこの葬儀を千夏が知ったら、どう思うのか。
俺だったら耐えられないな。
自分が死んだことにされているだなんて。
「おばさん……千夏は……」
それでも千夏のことを考えれば、俺は声をかけずにいられなかった。
しかし何を言いたいのか、それに気づいたかのように母親は一度俺を睨みつけた後、フラリと立ち上がり棺桶を抱きしめ大声を上げて泣き出した。
母親は分かっている。
分かっていて、それでも死んだのは千夏だとしているのだと俺は理解した。
なんだよ、それ。千夏はまだ生きてるのに。
なんであいつが死んだことにされなきゃいけないんだよ。
まるでその死を望まれているような、そんな重苦しさが込み上げてくる。
しかし周りは皆、俺が彼女たちの母親に何かしたのだろう、というような非難の目を向けていた。
俺はただ血が出るほど強く拳を握りしめ、その場をあとにすることしか出来なかった。
街中を走る消防車を帰り道で見てはいたが、それがイコール何に繋がるかなど何も考えていなかったから。
メールには、千夏たちが乗った自動車がカーブを曲がり切れずに崖下へ転落したというもの。
そして翌日の全校集会で、助手席に座っていた千夏が即死。
後部座席に座っていた夏美は重体。母親も重症だという。
皆が咽び泣く体育館で俺は、一つの小さな引っかかりを覚えていた。
葬式は二人の母親の退院を待って、行われた。
夏美の意識はまだ戻らないという。
だからこそ、千夏の死を悲しむと共に、最悪のシナリオにならないことを、誰もが祈っていた。
しかし葬式はどこまでもしめやかに。
あれほど千夏のことを根暗や夏美と全然違うと揶揄していた奴らが泣いている様は、俺にはどうしても滑稽に思えた。
二人の母は、足と手を骨折しており、祭壇の横に置かれた椅子で憔悴しきっていた。
大きな花に囲まれた祭壇の中の千夏の写真。
物静かだが、はにかんように微笑むそれ見た瞬間、俺の中でもやっと人の死というものが実感として湧き上がってくる。
幸い、大事故だったが千夏の顔は綺麗だったという。
だから参列者たちは焼香の後、置かれた棺の中の千夏の顔を見て、皆最後の別れを告げていた。
一人。また一人。
その列はどんどんと進み、見たくないという俺の気持ちなど誰も知らぬうちに、その番は回ってきた。
「千夏?」
物言わぬ一人のその遺体は、綺麗に死に化粧が施されていた。
その顔を見ながら、みんな千夏の名を呼び、涙する。
だが……。千夏じゃない。
俺のあの時感じた小さな違和感は、やはり間違ってなどいなかった。
助手席に乗った千夏が即死。これはどう考えてもあり得なかったから。
千夏は助手席になど絶対に乗らない。
あの家で、千夏はある意味学校よりも空気のような存在だった。
露骨に家族仲が悪いというわけではないが、両親ともに妹の夏美を溺愛していた。
そのため家では、家族との会話などほぼないのだと一度だけ千夏が吐露したことがある。
それに数回、街中で見かけた時も助手席には夏美が座り、母親との会話を楽しんでいた。
つまり――
死んだのは、千夏じゃなくて夏美じゃないか。
焦る気持ちを押さえつつ、辺りを見渡す。
しかし俺と同じようにこの遺体に疑問も持つ者は、この会場には誰一人いなかった。
むしろ両親すら、死亡したのは千夏だと思い込んでいる。
いや、思い込んでいる以上に、もう死亡手続きも終わっているのだろう。
どうしたら……どうすればいいんだ。
今ここで俺が騒いだところでどうにかなるか?
むしろ頭がおかしいヤツと思われるだけじゃないのか?
もしかしたら、本当に頭がおかしくなっただけなのか?
千夏が死んでほしくないと思っていたから。
分からない。分からない。
何が本当で、俺の目の前にいるのが誰なのか。
考えれば考えるほど、分からなくなる。
いや、頭が考えることを拒否していた。
夏美として入院する千夏の意識は、現状まだ戻っていないという。
今ここで騒ぎを起こしたところで、それを証明する術など、俺には何一つなかった。
せめて千夏の意識が戻っていたら……。
そう思いながら、ふと今の現状を考えた。
もしこの葬儀を千夏が知ったら、どう思うのか。
俺だったら耐えられないな。
自分が死んだことにされているだなんて。
「おばさん……千夏は……」
それでも千夏のことを考えれば、俺は声をかけずにいられなかった。
しかし何を言いたいのか、それに気づいたかのように母親は一度俺を睨みつけた後、フラリと立ち上がり棺桶を抱きしめ大声を上げて泣き出した。
母親は分かっている。
分かっていて、それでも死んだのは千夏だとしているのだと俺は理解した。
なんだよ、それ。千夏はまだ生きてるのに。
なんであいつが死んだことにされなきゃいけないんだよ。
まるでその死を望まれているような、そんな重苦しさが込み上げてくる。
しかし周りは皆、俺が彼女たちの母親に何かしたのだろう、というような非難の目を向けていた。
俺はただ血が出るほど強く拳を握りしめ、その場をあとにすることしか出来なかった。