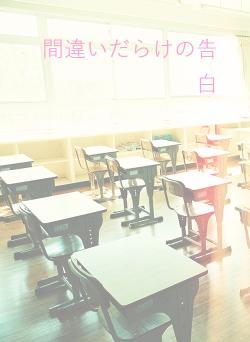「おー山口海斗キャプテンはまだ部活ですか~?」
校庭横の水道前。
そこでタオルを濡らしていた俺に、一人の生徒が声をかけてきた。
見上げれば、彼女は満面の笑みでこちらにやってくる。
大輪のひまわりのようなその笑顔に、俺もつられて笑った。
「おい、なんでフルネームで呼ぶんだよ」
「えー、いいじゃん。なんとなくだよー」
「なんだ夏美はもう帰りか? 俺はまだまだ部活だっていうのに」
「それに何キョロキョロしてるの? 誰を探してるんですかー」
ジト目で睨む彼女から、少し視線をずらす。
気づかれないようにそっと探していたつもりなんだが、こいつにはなぜかバレるんだよな。
まったく目ざとい。
夏美の言う通り、俺は確かに人を探していた。
彼女がいれば、いるはずのもう一人を。
「いや、そのだな……」
「どうせ姉さんでしょ。まさかアタシが声かけたのを残念とか思っていないでしょうね」
「さすがにそれはないわ」
「本当に⁉」
夏美はリスのようにその頬を大きく膨らませた。まぁ、その仕草も表情も可愛いは可愛い。
「なーつみー、もう帰るの~?」
そんな夏美とのやり取りを見つけた他の生徒たちが、集まってきた。
誰にでも優しく平等で気さくな夏美は、この小さな山間の高校では、アイドルなのだ。
「そーなのぉ」
「えー、でもスクールバスの時間まだじゃん」
「今日は用事があって親が迎えに来るんだよー」
「えー。いーなー」
山の上に建つこの高校と、下にある町とは一本の細い道が通っているだけ。
徒歩では到底歩きたくないほど距離があり、生徒は親の送迎かスクールバスで駅まで送迎されていた。
親が迎えに来るってことは、やっぱりセットってことだよな。
夏美に気付かれないように辺りを見渡せば、やや離れた木陰で木に寄りかかりながら本を読む、もう一人の生徒が目に入る。
俺は人だかりになりつつあるこの場を離れ、彼女に近づいた。
「珍しいな。千夏が夏美と帰るなんて」
俺に声をかけられた彼女は、スッと本から視線をこちらに向ける。
長く艶のある黒い髪が風に揺れた。
「親がどうしても用事があるらしくて仕方なくね」
「ああ、もうすぐ冬休みだからな」
「さぁ。私はよく知らないわ」
「知らないって……」
「興味ないの」
素っ気なく答える千夏は、どこか悲しそうな顔をしている。
そんな顔をさせたかったわけではないのに、どうやら俺は質問を間違えてしまったらしい。
双子であることもそうだが、あんまり千夏と家族仲良くないってぽつりと言ってたことがあったけ。
すっかり忘れてた。
まずいこと聞いちゃったな。
「やだぁ、海斗キャプテン、もしかしてうちのお姉ちゃん口説いてるの?」
あれほど人に囲まれていた夏美が、俺と千夏の会話に気づいたのか割って入ってくる。
そしてすかさず千夏の肩にもたれかかり、ニヤリとこちらを見た。
千夏はそんな夏美にうんざりした顔を一瞬だけしたものの、すぐにまた元に戻す。
「べ、別に俺は口説いてなんてないぞ。普通の会話をしていただけで」
「えー。だってアタシと話すより、楽しそうだったじゃない」
夏美の言っていることは、あながち間違いではない。
俺は学校一の人気者と言ってもいい夏美よりも、千夏の方が……。
「二人さぁ、こうやって並ぶと、似てるよね」
気づけばさきほどの人だかりは夏美とともに、ここへ移動してきていた。
その中の一人が何気なしに声を上げる。
「えー。そりゃあ、双子だもーん」
「でも、正反対じゃない? 二人って。性格もだし、いろいろと」
夏美と千夏は双子だ。それも一卵性《いちらんせい》の。
だからパッと見ただけでは、二人を区別するのは難しいらしい。
今は髪型や持ち物、性格などが全く違うから区別画つくというだけ。
昔全く同じ髪型で、一言も発しなかったら誰も区別がつかなかったほどだ。
明るくアイドルで、太陽のような妹の夏美。
物静かで、人を遠ざける月のような千夏。
そんな風に、学校では言われていた。
もちろん、千夏はそう呼ばれる度、心底嫌そうな顔をしていたのを覚えている。
「俺は、顔も性格も全部似てないと思うけどな」
俺は思わず、ぼそりと呟いていた。
なぜだかそう言わずにはいられなかったから。
「ほらやっぱり、お姉ちゃんのコト好きなんでしょう」
「誰もそんなこと言ってないだろ。今のどこを取ったら、そうなるんだよ」
「だってさぁ」
「なんだよ」
別に千夏のことを全面的にかばいたくて言ったわけでもない。
似ているようで、俺にとっては結構二人は似ていないのだ。
目とか、表情、あとは仕草。
声は確かに全く一緒だが、雰囲気も何も全然違う。
これで区別付かないとか、むしろそっちの方はおかしいだろと思うんだが。
「馬鹿な話していないで、迎えが来るわよ」
「えー。あ、ヤバ。お母さんからスマホ鳴ってる」
ややうんざりしたように千夏が言うと、夏美はポケットからスマホを取り出す。
どうやた着信が来ていたようだ。
「じゃあみんな、まーたね」
「さようなら、山口君」
「ああ、気を付けて帰れよ」
やや対照的な二人の背中を見つめながら、俺は見送った。
これがいつもの日常の終わりなど思いもしないで。
校庭横の水道前。
そこでタオルを濡らしていた俺に、一人の生徒が声をかけてきた。
見上げれば、彼女は満面の笑みでこちらにやってくる。
大輪のひまわりのようなその笑顔に、俺もつられて笑った。
「おい、なんでフルネームで呼ぶんだよ」
「えー、いいじゃん。なんとなくだよー」
「なんだ夏美はもう帰りか? 俺はまだまだ部活だっていうのに」
「それに何キョロキョロしてるの? 誰を探してるんですかー」
ジト目で睨む彼女から、少し視線をずらす。
気づかれないようにそっと探していたつもりなんだが、こいつにはなぜかバレるんだよな。
まったく目ざとい。
夏美の言う通り、俺は確かに人を探していた。
彼女がいれば、いるはずのもう一人を。
「いや、そのだな……」
「どうせ姉さんでしょ。まさかアタシが声かけたのを残念とか思っていないでしょうね」
「さすがにそれはないわ」
「本当に⁉」
夏美はリスのようにその頬を大きく膨らませた。まぁ、その仕草も表情も可愛いは可愛い。
「なーつみー、もう帰るの~?」
そんな夏美とのやり取りを見つけた他の生徒たちが、集まってきた。
誰にでも優しく平等で気さくな夏美は、この小さな山間の高校では、アイドルなのだ。
「そーなのぉ」
「えー、でもスクールバスの時間まだじゃん」
「今日は用事があって親が迎えに来るんだよー」
「えー。いーなー」
山の上に建つこの高校と、下にある町とは一本の細い道が通っているだけ。
徒歩では到底歩きたくないほど距離があり、生徒は親の送迎かスクールバスで駅まで送迎されていた。
親が迎えに来るってことは、やっぱりセットってことだよな。
夏美に気付かれないように辺りを見渡せば、やや離れた木陰で木に寄りかかりながら本を読む、もう一人の生徒が目に入る。
俺は人だかりになりつつあるこの場を離れ、彼女に近づいた。
「珍しいな。千夏が夏美と帰るなんて」
俺に声をかけられた彼女は、スッと本から視線をこちらに向ける。
長く艶のある黒い髪が風に揺れた。
「親がどうしても用事があるらしくて仕方なくね」
「ああ、もうすぐ冬休みだからな」
「さぁ。私はよく知らないわ」
「知らないって……」
「興味ないの」
素っ気なく答える千夏は、どこか悲しそうな顔をしている。
そんな顔をさせたかったわけではないのに、どうやら俺は質問を間違えてしまったらしい。
双子であることもそうだが、あんまり千夏と家族仲良くないってぽつりと言ってたことがあったけ。
すっかり忘れてた。
まずいこと聞いちゃったな。
「やだぁ、海斗キャプテン、もしかしてうちのお姉ちゃん口説いてるの?」
あれほど人に囲まれていた夏美が、俺と千夏の会話に気づいたのか割って入ってくる。
そしてすかさず千夏の肩にもたれかかり、ニヤリとこちらを見た。
千夏はそんな夏美にうんざりした顔を一瞬だけしたものの、すぐにまた元に戻す。
「べ、別に俺は口説いてなんてないぞ。普通の会話をしていただけで」
「えー。だってアタシと話すより、楽しそうだったじゃない」
夏美の言っていることは、あながち間違いではない。
俺は学校一の人気者と言ってもいい夏美よりも、千夏の方が……。
「二人さぁ、こうやって並ぶと、似てるよね」
気づけばさきほどの人だかりは夏美とともに、ここへ移動してきていた。
その中の一人が何気なしに声を上げる。
「えー。そりゃあ、双子だもーん」
「でも、正反対じゃない? 二人って。性格もだし、いろいろと」
夏美と千夏は双子だ。それも一卵性《いちらんせい》の。
だからパッと見ただけでは、二人を区別するのは難しいらしい。
今は髪型や持ち物、性格などが全く違うから区別画つくというだけ。
昔全く同じ髪型で、一言も発しなかったら誰も区別がつかなかったほどだ。
明るくアイドルで、太陽のような妹の夏美。
物静かで、人を遠ざける月のような千夏。
そんな風に、学校では言われていた。
もちろん、千夏はそう呼ばれる度、心底嫌そうな顔をしていたのを覚えている。
「俺は、顔も性格も全部似てないと思うけどな」
俺は思わず、ぼそりと呟いていた。
なぜだかそう言わずにはいられなかったから。
「ほらやっぱり、お姉ちゃんのコト好きなんでしょう」
「誰もそんなこと言ってないだろ。今のどこを取ったら、そうなるんだよ」
「だってさぁ」
「なんだよ」
別に千夏のことを全面的にかばいたくて言ったわけでもない。
似ているようで、俺にとっては結構二人は似ていないのだ。
目とか、表情、あとは仕草。
声は確かに全く一緒だが、雰囲気も何も全然違う。
これで区別付かないとか、むしろそっちの方はおかしいだろと思うんだが。
「馬鹿な話していないで、迎えが来るわよ」
「えー。あ、ヤバ。お母さんからスマホ鳴ってる」
ややうんざりしたように千夏が言うと、夏美はポケットからスマホを取り出す。
どうやた着信が来ていたようだ。
「じゃあみんな、まーたね」
「さようなら、山口君」
「ああ、気を付けて帰れよ」
やや対照的な二人の背中を見つめながら、俺は見送った。
これがいつもの日常の終わりなど思いもしないで。