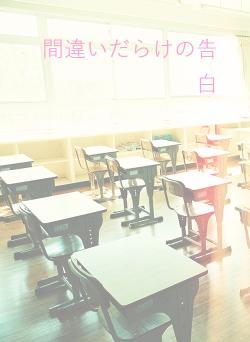それはとても乾燥した冬の日。
彼女が退院したと聞いた俺はいてもたってもいられず、彼女の家へ向かった。
しかしその先で見たものは、白く降り積もっていた雪がかき消されるほど、辺り一面を炎だった。
炎の中心は彼女の家。
もう近づくことも出来ないほどの燃えようで、思わず圧倒されてしまう。
「な、なんだよこれ!」
立ち上がる煙と、何かが燃える異様な匂い。
静かだった冬の空間は、バチバチと燃え上がる炎の音で埋め尽くされていた。
なんだよ、これ。いや、そんなことより、すぐに消防車を呼ばないと!
俺はポケットから慌ててスマホを取り出す。
しかし焦りとかじかんだ手のせいで、スマホはそのまま雪の上に落ちてしまう。
「おわ」
何してるんだよ、俺。
急がなきゃいけないのに。
屈んで雪にやや埋もれたスマホに手を伸ばした俺は、視界の端に炎に包まれる家を眺める彼女を見つけた。
「……」
彼女の周りだけ、空気感が違うようだった。
この惨状の中、彼女はどこまでも幸せそうに笑っていたから。
形の良い赤い唇に、やや高揚した頬。
炎によって巻き上がる風で彼女の長い黒髪が揺れていた。
「なん……で」
なんでこんな時にあんな顔が出来るんだ?
もちろんその疑問に答えられる者など誰もいない。
だからこそ俺は、ついその名を口にしてしまっていた。
「夏美?」
「……山口君も……なの?」
「え? それはどういう……」
名前を呼んだ瞬間、その同級生である夏美の顔は一変した。
真顔というよりも、憎しみがこもったような、そんな表情。
分かってはいたが、どうやら俺は選択を間違えたらしい。
しかしそんな顔も一瞬。
俺の問いかけには何も答えず、夏美はただ形の良い唇を上げた。
その笑みは、今まで見たどんな笑みよりも綺麗だと思えたのに、こんな状況で笑みを浮かべる彼女に、俺は背筋が寒くなったのを覚えている。
俺は本当は知っていた。
彼女が誰なのか。
それなのに罪の意識から、あえて彼女の名前を間違えたのだ。
たぶんこれは罰なのだろう。
俺たち……いや、俺へのか。
あの日、彼女を殺してしまったのはきっと俺だ。
俺は彼女の顔を真っすぐに見ながら、自分の犯した罪を思い出していた――
彼女が退院したと聞いた俺はいてもたってもいられず、彼女の家へ向かった。
しかしその先で見たものは、白く降り積もっていた雪がかき消されるほど、辺り一面を炎だった。
炎の中心は彼女の家。
もう近づくことも出来ないほどの燃えようで、思わず圧倒されてしまう。
「な、なんだよこれ!」
立ち上がる煙と、何かが燃える異様な匂い。
静かだった冬の空間は、バチバチと燃え上がる炎の音で埋め尽くされていた。
なんだよ、これ。いや、そんなことより、すぐに消防車を呼ばないと!
俺はポケットから慌ててスマホを取り出す。
しかし焦りとかじかんだ手のせいで、スマホはそのまま雪の上に落ちてしまう。
「おわ」
何してるんだよ、俺。
急がなきゃいけないのに。
屈んで雪にやや埋もれたスマホに手を伸ばした俺は、視界の端に炎に包まれる家を眺める彼女を見つけた。
「……」
彼女の周りだけ、空気感が違うようだった。
この惨状の中、彼女はどこまでも幸せそうに笑っていたから。
形の良い赤い唇に、やや高揚した頬。
炎によって巻き上がる風で彼女の長い黒髪が揺れていた。
「なん……で」
なんでこんな時にあんな顔が出来るんだ?
もちろんその疑問に答えられる者など誰もいない。
だからこそ俺は、ついその名を口にしてしまっていた。
「夏美?」
「……山口君も……なの?」
「え? それはどういう……」
名前を呼んだ瞬間、その同級生である夏美の顔は一変した。
真顔というよりも、憎しみがこもったような、そんな表情。
分かってはいたが、どうやら俺は選択を間違えたらしい。
しかしそんな顔も一瞬。
俺の問いかけには何も答えず、夏美はただ形の良い唇を上げた。
その笑みは、今まで見たどんな笑みよりも綺麗だと思えたのに、こんな状況で笑みを浮かべる彼女に、俺は背筋が寒くなったのを覚えている。
俺は本当は知っていた。
彼女が誰なのか。
それなのに罪の意識から、あえて彼女の名前を間違えたのだ。
たぶんこれは罰なのだろう。
俺たち……いや、俺へのか。
あの日、彼女を殺してしまったのはきっと俺だ。
俺は彼女の顔を真っすぐに見ながら、自分の犯した罪を思い出していた――