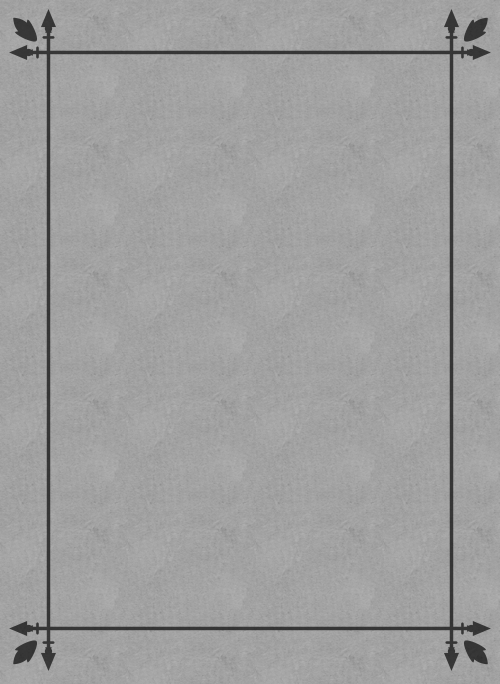季節は、静かに姿を変えていった。
夏の終わりに近づいたころ、未透は病室のベッドにいた。
蝉の声が遠くで揺れ、冷房の効いた廊下をゆっくりと歩く足音だけが、時間の流れを刻んでいた。
秋が来た。手術の日の空は曇っていて。そしてどこか空気が冷たかった。
その日、俺は学校を休んでいた。
未透との約束を果たすため、病院の目の前にある公園でただ一人、夕方になるまでじっとその時を待っていた。
何度も手のひらをこすり合わせ、寒さというより緊張を和らげようとしていた。
その日の昼頃になると、入道雲はすっかり消え、空の色は澄んでいった。
まるで、手術の成功を暗示しているかのような天気の移り変わりだった。
夕方、病院に足を運ぶと、病室のカーテンは開け放たれ、陽の光があたたかく彼女の頬を照らしていた。
彼女の手術は無事に成功した。
経過は順調で、退院までは少し時間がかかったけれど、その間、俺は何度も彼女の病室を訪ねた。
会話をする時間も限られていた。
日によっては声も出せず、ただそばにいるだけで終わる日もあった。
それでも、俺たちはほんの少しずつ言葉を交わし続けた。まるで本のページをめくるように、少しずつ、少しずつ……お互いを知っていった。
その間、彼女のご両親にも何度か顔を合わせた。
俺のことを受け入れてくれて、いつも丁寧にお礼を言ってくれた。
でも、ひとつだけ、彼女は固く口止めしていた。
——わたしの名前だけは絶対に言わないで!
その頼みに、ご両親も静かに頷いた。誰も俺に彼女の本当の名前を伝えなかった。
たぶん、それは彼女自身の“願い”だった。
俺がちゃんと自分の力でその名前に辿り着くように。
誰の声でもなく、俺自身の言葉で呼びかけられるように。
未透——
その偽名のまま、彼女はずっとそこにいてくれた。
名前がわからなくても、気持ちは通じていた。
けれどそれでも、いつかは本当の名前を、きちんと口にしたいと思っていた。
名前を知ることは、記憶に向き合うこと。
彼女が俺に残してくれた、最後の“宿題”のようなものだった。
ことばノートはもう交わしていない。
ことばノートの最後のページは、彼女が退院するときに、そっと閉じられた。
「これで、わたしの“ことば”は全部渡せたから」
そう言ったときの表情を、俺はきっと一生忘れない。
◇◆◇◆◇
春の風が、制服の裾を揺らしていた。
陽射しはやわらかく、けれど確かに温かい。冬の終わりを知らせるように、遠くで鳥のさえずりが響いていた。
俺はいつかの中庭に立っていた。
見慣れたベンチが、同じようにそこにある。
秋には枝だけだった木々が若葉を宿しはじめていて、木漏れ日がリズムよく揺れていた。
約束の時間は、もうすぐだった。
俺は制服の胸ポケットをそっと叩く。
その中には、小さな紙切れが入っている。
手帳の切れ端のような、何気ない紙。でもそこには、彼女が退院の前に残してくれた文字が書かれていた。
——「中庭で待ってて」
たったそれだけ。
でもそれは、俺にとって「再会」を意味する約束だった。
少し風が吹いて、ベンチの隣に置いたカバンのストラップが揺れた。
俺はふと顔を上げた。
中庭の入口に、ひとりの少女が立っていた。
白いブラウスに春色のカーディガン。ローファーに慣れない足取りで、ゆっくりと歩いてくる。
杖こそついているが、彼女は自分の足で地面を踏みしめていた。
綺麗に切り揃えられた黒髪も、少しふっくらしたほっぺたも、入院中とは全然違うから見てるだけで嬉しくなった。
間違えるはずがなかった。
——未透だ。いや、違う。彼女は俺が未透と呼んでいるだけの存在。
俺は静かに立ち上がると、彼女が歩み寄ってくるのを待った。
彼女は、照れたように小さく笑いながら言った。
「久しぶり、陽翔くん」
「……おかえり」
その一言が、ようやく言えた。
病院では何度もあっていたけど、俺たちはまさしく久しぶりの再会だった。こんなやりとりをしなければいけないほどに。
「ふふっ」
彼女は笑った。
季節と一緒に、あの冬を超えてきた笑顔だった。
俺たちはベンチに並んで腰を下ろす。
見上げると、枝の先に小さなつぼみがいくつもついていた。
風がそれを、やさしく揺らしていた。
「春だね」
「うん」
「病院の中からじゃ、季節の変化ってわかりづらくてさ。でも、今日は空気が違うって思った。新しい始まりの匂いがしたの」
彼女の声は、かすかに震えていた。
それは、寒さではなく、きっと“その瞬間”が近づいていることを感じていたから。
俺は、彼女のほうを向いた。
ゆっくりと口を開く。
「ずっと、考えてたんだ……名前のこと」
彼女は目を伏せて、小さくうなずいた。
「わたしも、やっぱり君の口から聞きたかった」
「……ありがとう。待っててくれて」
風がふたりの間を通り過ぎていく。
その静寂の中で、俺は少しだけ呼吸を整えた。
「聞かせて? わたしの名前……」
「うん」
俺は彼女の方を見つめて言った。
「———鈴花さん」
その名前を口にした瞬間、世界が空から強い光が差し込んだ気がした。
同時に、彼女はぱちりと瞬きをした。
そして——
「……そう。やっと、思い出してくれたんだね」
嬉しそうに、でも少し泣きそうな顔で、ゆっくりとうなずいた。
俺は立ち上がり、少し彼女の前に回り込んで、まっすぐに向き合う。
「ごめん。思い出すのが、こんなにも遅くなって」
「ううん。遅くなんてないよ……ちゃんと、君の言葉で思い出してくれたから。それはわたしが望んだことだから」
鈴花の目から涙がこぼれると、春の光がその雫に反射してきらめいた。
「陽翔くんが、ちゃんと声にしてくれて嬉しい」
俺も堪えきれなくなっていた。でも、涙より先に言いたかった言葉がある。
「ありがとう、鈴花さん」
鈴花は何も言わずにうなずいて、ゆっくりと俺に手を差し出した。
その手は少しだけ冷たくて、でも、確かに生きていた。
俺はその手を取った。
かつて名前を呼べなかった日々を、今、ようやく超えることができた。
後悔じゃない。逃げでもない。
言葉で伝えた「ありがとう」と「ごめん」と「また会えてよかった」が、ちゃんと届いた。
風が吹き抜ける中庭で、俺たちは手をつないだまま、しばらく何も言わずに空を見上げていた。
春が、本当に来ていた。
◇◆◇◆◇
数か月前までの寒さは、どこか遠い日のことのようだった。
新学期が始まり、校舎の前には新入生たちの初々しい声が飛び交っている。
教室の窓からは、満開の桜が見えた。
——季節は、冬の終わりから春の始まりへ。
その春の始まりとともに、鈴花が学校へ戻ってきた。
通学にはまだ制限があって、毎日は来られない。
それでも、確かに彼女は“ここにいる”。
ゆっくりと前に進んでいる。
小柄で黒髪がよく似合って、少しだけ人見知りな彼女は、今では自然にクラスの輪に馴染んでいる。
“昔の彼女”を知る人は、もうほとんどいない。
でも、今の彼女を知る人たちは、鈴花のことをちゃんと見ている。
病気でしばらく学校を離れていたと話したとき、
クラスの誰もが驚いたように彼女の話を聞いてくれた。
「あ、そうなんだ。無理しないで、ぼちぼちいこうね」
誰かが言ったそんな何気ない言葉に、彼女は涙をこらえるように小さく笑っていた。
今の彼女は、もう、独りじゃない。
そして俺もまた、あのときの自分とは違っていた。
誰かに言葉をかけることを恐れなくなった。
無理に空気を読もうとしなくなった。
必要なときに、必要な言葉を渡せるようになりたくて——そう思えるようになった。
これまでのように自分を偽ることはやめて、ありのままの姿で接するように心がけた。
そうすると、自然と友人ができた。
俺も鈴花も変わり始めていた。
春の中庭で、俺は彼女を待っていた。
ベンチの上、風に吹かれながらノートを膝に広げていると、ゆっくりと誰かの影が近づいてきた。
「……待った?」
そう言って笑う鈴花の声が、春風に混じって届く。
「いや。今来たとこ」
「ふふっ、ベタな返し」
自然に笑い合えるようになった。
並んで座ると、彼女は鞄の中から何かを取り出した。
小さな鉢植えだった。薄紫の、すずらんの花。
「これ、病室の窓辺に置いてたの。退院するときにね、先生が“持って帰っていいよ”って言ってくれたの」
「すずらん……」
「うん。花言葉、知ってる?」
「……“幸福の再訪”、だったっけ」
「正解……なんか、今のわたしにぴったりでしょ?」
そう言って、鈴花は恥ずかしそうに笑った。
俺はそっとその鉢植えに目をやる。
確かに、今の彼女は“再びここに戻ってきた人”だった。
過去を乗り越えて、もう一度、自分の人生を歩き出した人。
前を向いて再び歩き出した人。
「ぴったりだよ、鈴花」
名前を呼んだとき、彼女はふわりと目を細めた。
「その名前で呼ばれると、今でもなんだかこそばゆい感じする」
「これからは胸を張って呼んでいくからね」
「もう未透なんて言わないでね?」
「当たり前だろ。忘れるわけない」
風が、二人の髪をやさしく撫でた。
「ねえ、はるくん」
「ん?」
「わたしもはるくんも。もう想いが見える力はなくなっちゃったみたいだけど……」
「うん。最近は言葉の声とか不思議な気配とか、全く感じなくなった」
実を言うと、鈴花がまだ未透として入院していたてき、一人で過ごすことが多かった俺は度々想いの声を耳にする機会があった。
俺は彼女とは違い、その声を見て感じて何をするわけでもなかったけど、たくさんの声に触れることで言葉の残響については自然と理解させられた。
彼女からすれば、それがわからなくなったのは辛いかもしれない。
「わたしはそれでよかったと思ってるよ」
「なんで?」
鈴花は少し空を見上げてから、俺の方を見て言った。
「だって、それって、わたしたちがもう“過去”を超えられたってことじゃない?」
俺は、少しだけ目を見開いた。
——たしかに、あの力はもうなくなった。
誰かの“届かなかった想い”を感じることもなくなった。
でも、俺たちの言葉は、ちゃんと“今”に届いている。
見えない力じゃなく、自分たちの言葉で、目の前の誰かを救えるようになった。
「そうだね……もう、見えない力に頼らなくても、伝えられる」
「そう、だから今度は——」
鈴花は、そっと俺のノートを開いた。
何も書かれていない白紙のページに、ペンを差し出してくる。
「書いて、今の“ことば”を。君の言葉で」
「……わかった」
俺はペンを受け取り、ゆっくりと文字を綴る。
『——また、ここから始めよう』
春の風に吹かれながら、
二人は“ことば”で未来を選んでいく。
かつて言えなかった名前も、届けられなかった想いも、
今はもう全部、ここにある。
春は、終わりと始まりの季節だ。
きっとこの一歩が、俺たちの“新しい物語”の第一章になる。
だから、もう後悔はしない。
ちゃんと伝える。ちゃんと名前を呼ぶ。
「——鈴花、ありがとう。これからもよろしく!」
その声は、春の空の下、まっすぐに響いていた。
夏の終わりに近づいたころ、未透は病室のベッドにいた。
蝉の声が遠くで揺れ、冷房の効いた廊下をゆっくりと歩く足音だけが、時間の流れを刻んでいた。
秋が来た。手術の日の空は曇っていて。そしてどこか空気が冷たかった。
その日、俺は学校を休んでいた。
未透との約束を果たすため、病院の目の前にある公園でただ一人、夕方になるまでじっとその時を待っていた。
何度も手のひらをこすり合わせ、寒さというより緊張を和らげようとしていた。
その日の昼頃になると、入道雲はすっかり消え、空の色は澄んでいった。
まるで、手術の成功を暗示しているかのような天気の移り変わりだった。
夕方、病院に足を運ぶと、病室のカーテンは開け放たれ、陽の光があたたかく彼女の頬を照らしていた。
彼女の手術は無事に成功した。
経過は順調で、退院までは少し時間がかかったけれど、その間、俺は何度も彼女の病室を訪ねた。
会話をする時間も限られていた。
日によっては声も出せず、ただそばにいるだけで終わる日もあった。
それでも、俺たちはほんの少しずつ言葉を交わし続けた。まるで本のページをめくるように、少しずつ、少しずつ……お互いを知っていった。
その間、彼女のご両親にも何度か顔を合わせた。
俺のことを受け入れてくれて、いつも丁寧にお礼を言ってくれた。
でも、ひとつだけ、彼女は固く口止めしていた。
——わたしの名前だけは絶対に言わないで!
その頼みに、ご両親も静かに頷いた。誰も俺に彼女の本当の名前を伝えなかった。
たぶん、それは彼女自身の“願い”だった。
俺がちゃんと自分の力でその名前に辿り着くように。
誰の声でもなく、俺自身の言葉で呼びかけられるように。
未透——
その偽名のまま、彼女はずっとそこにいてくれた。
名前がわからなくても、気持ちは通じていた。
けれどそれでも、いつかは本当の名前を、きちんと口にしたいと思っていた。
名前を知ることは、記憶に向き合うこと。
彼女が俺に残してくれた、最後の“宿題”のようなものだった。
ことばノートはもう交わしていない。
ことばノートの最後のページは、彼女が退院するときに、そっと閉じられた。
「これで、わたしの“ことば”は全部渡せたから」
そう言ったときの表情を、俺はきっと一生忘れない。
◇◆◇◆◇
春の風が、制服の裾を揺らしていた。
陽射しはやわらかく、けれど確かに温かい。冬の終わりを知らせるように、遠くで鳥のさえずりが響いていた。
俺はいつかの中庭に立っていた。
見慣れたベンチが、同じようにそこにある。
秋には枝だけだった木々が若葉を宿しはじめていて、木漏れ日がリズムよく揺れていた。
約束の時間は、もうすぐだった。
俺は制服の胸ポケットをそっと叩く。
その中には、小さな紙切れが入っている。
手帳の切れ端のような、何気ない紙。でもそこには、彼女が退院の前に残してくれた文字が書かれていた。
——「中庭で待ってて」
たったそれだけ。
でもそれは、俺にとって「再会」を意味する約束だった。
少し風が吹いて、ベンチの隣に置いたカバンのストラップが揺れた。
俺はふと顔を上げた。
中庭の入口に、ひとりの少女が立っていた。
白いブラウスに春色のカーディガン。ローファーに慣れない足取りで、ゆっくりと歩いてくる。
杖こそついているが、彼女は自分の足で地面を踏みしめていた。
綺麗に切り揃えられた黒髪も、少しふっくらしたほっぺたも、入院中とは全然違うから見てるだけで嬉しくなった。
間違えるはずがなかった。
——未透だ。いや、違う。彼女は俺が未透と呼んでいるだけの存在。
俺は静かに立ち上がると、彼女が歩み寄ってくるのを待った。
彼女は、照れたように小さく笑いながら言った。
「久しぶり、陽翔くん」
「……おかえり」
その一言が、ようやく言えた。
病院では何度もあっていたけど、俺たちはまさしく久しぶりの再会だった。こんなやりとりをしなければいけないほどに。
「ふふっ」
彼女は笑った。
季節と一緒に、あの冬を超えてきた笑顔だった。
俺たちはベンチに並んで腰を下ろす。
見上げると、枝の先に小さなつぼみがいくつもついていた。
風がそれを、やさしく揺らしていた。
「春だね」
「うん」
「病院の中からじゃ、季節の変化ってわかりづらくてさ。でも、今日は空気が違うって思った。新しい始まりの匂いがしたの」
彼女の声は、かすかに震えていた。
それは、寒さではなく、きっと“その瞬間”が近づいていることを感じていたから。
俺は、彼女のほうを向いた。
ゆっくりと口を開く。
「ずっと、考えてたんだ……名前のこと」
彼女は目を伏せて、小さくうなずいた。
「わたしも、やっぱり君の口から聞きたかった」
「……ありがとう。待っててくれて」
風がふたりの間を通り過ぎていく。
その静寂の中で、俺は少しだけ呼吸を整えた。
「聞かせて? わたしの名前……」
「うん」
俺は彼女の方を見つめて言った。
「———鈴花さん」
その名前を口にした瞬間、世界が空から強い光が差し込んだ気がした。
同時に、彼女はぱちりと瞬きをした。
そして——
「……そう。やっと、思い出してくれたんだね」
嬉しそうに、でも少し泣きそうな顔で、ゆっくりとうなずいた。
俺は立ち上がり、少し彼女の前に回り込んで、まっすぐに向き合う。
「ごめん。思い出すのが、こんなにも遅くなって」
「ううん。遅くなんてないよ……ちゃんと、君の言葉で思い出してくれたから。それはわたしが望んだことだから」
鈴花の目から涙がこぼれると、春の光がその雫に反射してきらめいた。
「陽翔くんが、ちゃんと声にしてくれて嬉しい」
俺も堪えきれなくなっていた。でも、涙より先に言いたかった言葉がある。
「ありがとう、鈴花さん」
鈴花は何も言わずにうなずいて、ゆっくりと俺に手を差し出した。
その手は少しだけ冷たくて、でも、確かに生きていた。
俺はその手を取った。
かつて名前を呼べなかった日々を、今、ようやく超えることができた。
後悔じゃない。逃げでもない。
言葉で伝えた「ありがとう」と「ごめん」と「また会えてよかった」が、ちゃんと届いた。
風が吹き抜ける中庭で、俺たちは手をつないだまま、しばらく何も言わずに空を見上げていた。
春が、本当に来ていた。
◇◆◇◆◇
数か月前までの寒さは、どこか遠い日のことのようだった。
新学期が始まり、校舎の前には新入生たちの初々しい声が飛び交っている。
教室の窓からは、満開の桜が見えた。
——季節は、冬の終わりから春の始まりへ。
その春の始まりとともに、鈴花が学校へ戻ってきた。
通学にはまだ制限があって、毎日は来られない。
それでも、確かに彼女は“ここにいる”。
ゆっくりと前に進んでいる。
小柄で黒髪がよく似合って、少しだけ人見知りな彼女は、今では自然にクラスの輪に馴染んでいる。
“昔の彼女”を知る人は、もうほとんどいない。
でも、今の彼女を知る人たちは、鈴花のことをちゃんと見ている。
病気でしばらく学校を離れていたと話したとき、
クラスの誰もが驚いたように彼女の話を聞いてくれた。
「あ、そうなんだ。無理しないで、ぼちぼちいこうね」
誰かが言ったそんな何気ない言葉に、彼女は涙をこらえるように小さく笑っていた。
今の彼女は、もう、独りじゃない。
そして俺もまた、あのときの自分とは違っていた。
誰かに言葉をかけることを恐れなくなった。
無理に空気を読もうとしなくなった。
必要なときに、必要な言葉を渡せるようになりたくて——そう思えるようになった。
これまでのように自分を偽ることはやめて、ありのままの姿で接するように心がけた。
そうすると、自然と友人ができた。
俺も鈴花も変わり始めていた。
春の中庭で、俺は彼女を待っていた。
ベンチの上、風に吹かれながらノートを膝に広げていると、ゆっくりと誰かの影が近づいてきた。
「……待った?」
そう言って笑う鈴花の声が、春風に混じって届く。
「いや。今来たとこ」
「ふふっ、ベタな返し」
自然に笑い合えるようになった。
並んで座ると、彼女は鞄の中から何かを取り出した。
小さな鉢植えだった。薄紫の、すずらんの花。
「これ、病室の窓辺に置いてたの。退院するときにね、先生が“持って帰っていいよ”って言ってくれたの」
「すずらん……」
「うん。花言葉、知ってる?」
「……“幸福の再訪”、だったっけ」
「正解……なんか、今のわたしにぴったりでしょ?」
そう言って、鈴花は恥ずかしそうに笑った。
俺はそっとその鉢植えに目をやる。
確かに、今の彼女は“再びここに戻ってきた人”だった。
過去を乗り越えて、もう一度、自分の人生を歩き出した人。
前を向いて再び歩き出した人。
「ぴったりだよ、鈴花」
名前を呼んだとき、彼女はふわりと目を細めた。
「その名前で呼ばれると、今でもなんだかこそばゆい感じする」
「これからは胸を張って呼んでいくからね」
「もう未透なんて言わないでね?」
「当たり前だろ。忘れるわけない」
風が、二人の髪をやさしく撫でた。
「ねえ、はるくん」
「ん?」
「わたしもはるくんも。もう想いが見える力はなくなっちゃったみたいだけど……」
「うん。最近は言葉の声とか不思議な気配とか、全く感じなくなった」
実を言うと、鈴花がまだ未透として入院していたてき、一人で過ごすことが多かった俺は度々想いの声を耳にする機会があった。
俺は彼女とは違い、その声を見て感じて何をするわけでもなかったけど、たくさんの声に触れることで言葉の残響については自然と理解させられた。
彼女からすれば、それがわからなくなったのは辛いかもしれない。
「わたしはそれでよかったと思ってるよ」
「なんで?」
鈴花は少し空を見上げてから、俺の方を見て言った。
「だって、それって、わたしたちがもう“過去”を超えられたってことじゃない?」
俺は、少しだけ目を見開いた。
——たしかに、あの力はもうなくなった。
誰かの“届かなかった想い”を感じることもなくなった。
でも、俺たちの言葉は、ちゃんと“今”に届いている。
見えない力じゃなく、自分たちの言葉で、目の前の誰かを救えるようになった。
「そうだね……もう、見えない力に頼らなくても、伝えられる」
「そう、だから今度は——」
鈴花は、そっと俺のノートを開いた。
何も書かれていない白紙のページに、ペンを差し出してくる。
「書いて、今の“ことば”を。君の言葉で」
「……わかった」
俺はペンを受け取り、ゆっくりと文字を綴る。
『——また、ここから始めよう』
春の風に吹かれながら、
二人は“ことば”で未来を選んでいく。
かつて言えなかった名前も、届けられなかった想いも、
今はもう全部、ここにある。
春は、終わりと始まりの季節だ。
きっとこの一歩が、俺たちの“新しい物語”の第一章になる。
だから、もう後悔はしない。
ちゃんと伝える。ちゃんと名前を呼ぶ。
「——鈴花、ありがとう。これからもよろしく!」
その声は、春の空の下、まっすぐに響いていた。