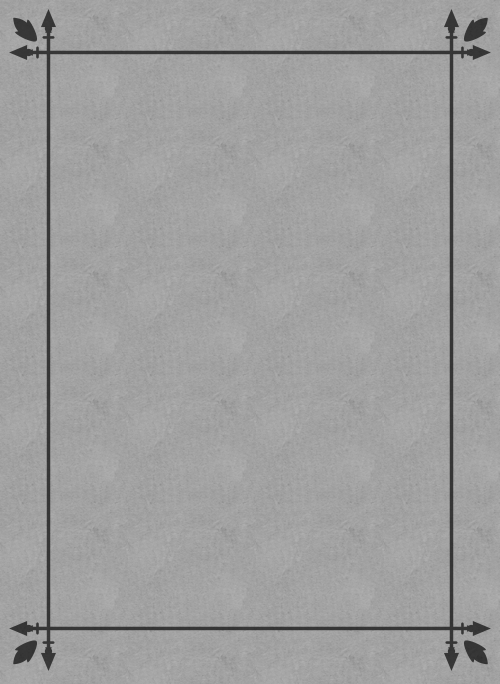夕暮れの街。
空は淡い赤色で、夏の終わりを感じさせる静けさがあった。
自転車のペダルをこぐ足元に、吐いた息が白く流れていく。
きしむチェーンの音が耳障りで、荒みかけた心が刺激される。
「はぁはぁ……」
俺は必死に前に進んでいた。
向かう先は病院だった。
けれど、心の準備はまだできていなかった。
彼女は俺が返したノートを読んでくれているだろうか?
未透から俺に届いた言葉。
俺が返した言葉。
たくさんのやり取りを重ねて、たくさんの言葉を掛け合って、お互いの心には安寧が生まれていた。
俺が勝手に思っているだけかもしれないけど、そのたくさんやり取りや重ねた言葉は、ほんの数十ページなのに何百、何千の言葉よりも重かった。
そして、最後に言葉を綴った瞬間、俺は確かに決めたはずだった。
どんな理由を並べても、言い訳にしかならない。
だから会わなきゃいけない。
今度こそ、ちゃんと伝えなきゃいけない——そう思ったはずだったのに。
俺はまだ、病院へ足を運べていなかった。
雨が降る日、電車の路線を調べては検索履歴を消した。何度も、何度も、家の玄関扉の前に立ったのに、あと一歩が踏み出せなかった。
頭では分かっている。もう迷っている時間はない。
未透の時間は限られている。
それでも、足が動かなかった。
“もし、もう話せなかったら?”
“もし、もう会えない状態だったら?”
そんな恐怖が、俺の意思とは裏腹に体を縛り付けていた。いや、違う。俺の意思も同じく弱気になっていたんだ。前に向いたつもりでも、過去の後悔を嘆くばかりでまともに行動できていない。
また何もできずに終わるんじゃないか。
このままノートだけのやり取りで、終わってしまうんじゃないか。
心の奥に、あのときと同じ影が棲みついていた。
でも、今回はそれに負けたくなかった。
だから、こうして夕暮れを背に家を出た。
目的地も、行き先も、はっきりと決まっている。
ただ、気持ちを追いつかせるために、遠回りをしているだけだ。
俺はハンドルを握る手に力を込めた。
“今度こそ、自分の言葉で彼女に伝える”
あの日の約束を、もう一度、自分に刻み込む。
未透に出会ったことで生まれた言葉がある。
彼女が教えてくれた。
声に出さなきゃ、気持ちは届かないし、想いは伝わらない。
だからこそ、俺は——
ノートに書いた最後の言葉を、もう一度、心の中でなぞる。
“会いにいくよ”——俺の、今のすべて。
病院の前に立つと、思っていた以上に足がすくんだ。
これまでに何度も、あのノートの文字を読んだ。
未透の筆跡。彼女の綴る言葉のあたたかさと静けさに、何度救われただろう。
けれど、その筆跡はだんだん弱々しくなっていた。
まるで、ひと文字ごとに力を振り絞っているかのように。
その変化に気づいていながら、俺はただ“交換”を続けてきた。
ノートの最後に綴った言葉——
『会いにいくね』
それは俺の言葉だった。
本当は、もっと早く伝えるべきだった。
でも、未透の“願い”があのノートには込められていたから、俺はずっとそれを守っていた。
——言葉で、心で、伝え合おうって。
つまり、会わないようにしようって、そういう意味なんだって俺は思っていた。
それが未透の望んだ“形”だった気がして。
未透の言葉の端々から、俺には“そのとき”が近づいているのが分かっていた。
だから、今日は——ちゃんと、会いにいく。
自動ドアの前で一度深呼吸をして、足を踏み入れる。
白く明るいロビーの空気を吸うと、少しだけ喉が渇いた。水が飲みたいわけじゃない。ただ、俺の心には潤いが足りなかった。
「……」
俺が受付に向かおうとしたそのとき、制服姿の俺に気づいた看護師が歩み寄ってきた。
「あの、もしかして——陽翔さんですか?」
「えっ……あ、はい。そうですけど」
突然の声に少し驚いた俺に、その看護師はやわらかく微笑んだ。
「笹山さんがおっしゃられていました。“陽翔くんが来たら、どうか案内してあげてほしい”って」
「ささやま、さん……?」
その名前が告げられた瞬間、鼓動が大きく跳ねた。
笹山——その苗字は、まるで聞き覚えがなかった。
頭のどこかがぐらりと揺れて、思考が一瞬止まる。
でも、次の瞬間にはすべてが繋がっていくのを感じていた。
——未透の苗字は、“笹山”なんだ。
そとそも未透という名前が苗字なのか下の名前なのかもはっきりしない。俺は彼女から聞いた、というただそれだけの理由で彼女の名前が本当なのだと思っていた。その名前が偽物なんだということは気がついていたが、それでもなぜか“未透”という名前には、どこか触れてはいけない感じがした。
そこには触ったら壊れてしまう儚さがあったから、俺はずっとそれを追及しないでいた。いや、正しくは追及できなかった。
「……あの、笹山さんはどこの部屋ですか」
平静を取り繕って尋ねた。
「案内します。ついてきてください」
看護師に続いて、白い廊下を歩き出す。
何もかもが、ゆっくりと過去と未来を混ぜ合わせながら、静かに進んでいく気がした。
俺は今、ようやく“彼女”に会いにいく。
名前を知らなかった彼女に。
想いを伝えてくれた、たったひとりの“君”に。
ノートにはもう書かれていない言葉を、今度は“声”で——
◇◆◇◆◇
看護師が戸を叩いたが、音に応える気配はなかった。
病室のドアが、静かに開かれた。
数秒待って看護師が言った。
「入ってあげてください」
ふわりと微笑んでくれた。未透からどんな話を聞いているのかはわからないけど、その声色は包み込むような優しさがあった。
「失礼します」
俺はゆっくりと病室へ足を踏み入れる。
少しして振り向くと、すでに看護師はいなくなっていた。
静まり返った病室。
白いレースのカーテンが窓の外の光をやわらかく遮っていて、部屋の中の淡い雰囲気を優しく包み込んでいた。
ベッドの上には、静かに眠っている未透がいた。
彼女は夢の中にいるような穏やかな表情をしていた。
だけど、その頬はやせ細り、肌は前よりもずっと白くなっていた。
点滴の管が手の甲に繋がれている。
機械の微かな電子音が、現実を物語っていた。
——これは、現実だ。目の前に見えているのは、俺が目を背け続けてきた光景そのものだった。
俺はそっと歩み寄って、ベッドの脇の椅子に腰を下ろす。彼女を起こさないように、静かな息遣いで。
彼女の枕元には、一冊のノートが置かれていた。
……それは、ことばノートだった。
俺が最後に書いた言葉。
『会いにいくね』
その一文を綴ったノートのページは開いたままになっていた。
ページの端に、小さな折り目があった。
震えるような指先で触れた跡が、そこに残っていた。
もしかしたら、ページを開くのに精一杯で、まだ読めていないのかもしれない。
「未透さん……」
俺は彼女の名を呼んだ。その名前が偽物だったとしても、俺にとって彼女は未透だった。
そんな彼女の病状が気がかりで、俺の心中は穏やかじゃなかった。
俺の心臓は高鳴っていた。
外にも聞こえてしまうんじゃないかって思うくらいだった。
しかし、そんな中でも、窓際に飾られた真白いスズランの花は美しく輝いていた。
花言葉は幸せの再訪。本で読んだことがある。
「スズラン、か」
思わず声が漏れ出たそのときだった。
ふと、声が聞こえてきた。いや、彼女なりに言うなら見えたというべきか、それとも感じたというべきか。
あの感覚がここにきて俺を刺激した。
『おもいだして』
『わたしは、ここにいるよ……?』
『はる……くん?』
そんな消え入りそうな声が俺の頭の中に反響したその瞬間。眠り続けていた未透のまつげがわずかに揺れた。
彼女の瞼がゆっくりと持ち上がる。
眠りの世界から引き戻されたように、未透がこちらを見つめた。
「……えっ? はる、くん……?」
未透が小さく目を見開き、息をのんだのがわかった。
驚きの色がその表情に広がって、やがて、それは少しだけ安堵に変わった。
「……なんでここにいるの」
彼女の声は掠れていて、けれど確かに届いた。
俺は”はるくん”と呼ばれたことへの驚きよりも先に、彼女が目覚めたことを喜んでいた。
「会いにきたよ。それと、未透の想いはちゃんと俺に伝わったよ」
未透の唇が、かすかに動く。
何か言おうとしたようだったが、それよりも先に俺は問いかけた。
「体調は……どう?」
その質問に、彼女はわずかに目を伏せて、小さな声で返した。
「……見ての通りだよ。君から戻ってきたノートも、まだ見れてないくらい。開いた途端に意識なくなっちゃったのかも」
苦笑に近い表情だった。
ノートに目をやると、最後に書いた言葉の上に少しだけ涙の跡が滲んでいた。手のひらで握りつぶしたような跡もあり、一目で彼女のやるせない気持ちが伝わってきた。
「読まなくていいよ、無理しないで」
俺がそう言うと、未透は首を横に振った。
「ううん、読むよ。絶対に、読む。だって……」
そこで言葉を切る。
喉に何かが詰まったようだった。
俺は、彼女がその言葉を取り戻すまで、ただ静かに見守っていた。
多分、10秒くらい経ったと思う。
「……ずっと、待ってたから」
未透は震えた声色でそう口にした。
「ほんとはね……いつか、君が来てくれるって、信じてた」
「だから……あのノートも、宝箱みたいに大事にして、先生と看護師さんには“もし陽翔くんが来たら病室を伝えていいよ”って、お願いしておいたの」
それを聞いた瞬間、胸の奥がぎゅっと締めつけられた。
未透は、ずっと俺を信じてくれていた。
来るかどうかもわからない未来に、希望を託して。
それなのに、俺は——
「……ごめん。もっと、早く来るべきだった」
「そんなこと、ないよ。君はちゃんと来てくれた。むしろ、わたしが遠ざけてたから……」
未透の言葉は、やっぱりあたたかかった。
掠れていても、震えていても、真っ直ぐで優しかった。
ベッドの上、枕元に咲くように微笑む彼女を見ていると、涙がこぼれそうになる。その儚さと今にも消えてしまいそうな弱々しさは、俺が見ないようにしてきた現実だった。
でも、俺は泣かない。
今度こそ、ちゃんと“言葉”で伝えたいから。
声にして、想いを届けたいから。
「未透さん……ありがとう」
その一言に、これまでのすべてを込めた。
未透は、目を閉じるようにして、小さく息を吐いた。
「……ねぇ、陽翔くん」
「うん?」
「もう、気づいてるよね。わたしの本当の名前は……未透じゃないんだよ?」
とっくに気づいていた。でも、言えなかった。思い出せなかった。未透という名前が偽名だとわかっていながらも、俺はそう呼び続けるしかなかった。甘んじるしかなかった。
「知りたい?」
「うん……でも、俺は自分に思い出したい。もう少しでわかる気がするから」
「……わかった」
未透がふわりと微笑むと、窓の外から優しい風が吹き込んできた。
空はもう深い紺色に染まっており、秋が近づいているから風は少し冷たかった。
夜になった病室は妙な静けさを宿していて、中庭や屋上前の踊り場にいるときとは全然違う雰囲気だった。
どこか怖くて、逃げ出したくなってしまう。この場に留まっていると未来が見えてしまうような気がした。
「怖い顔」
「っ……ご、ごめん」
「やっぱり病院は怖いよね」
「未透さんも怖い?」
俺がふと尋ねると、未透はベッドの上で枕に寄りかかるように上体を起こし、少し息を整えながら話し出した。
「……うん。怖いよ。だって——明後日、手術だもん」
静かに、けど、しっかりとした声だった。
俺はほんの一瞬だけ心臓が跳ねるのを感じた。
知っていた。噂で聞いていた。でも、それを未透の口から聞くことで、現実の輪郭がくっきりと浮かび上がった気がした。
「成功率は高いみたい。主治医の先生も、“希望はある”って言ってたから」
「……そうなんだ」
言葉が詰まりそうになるのを、何とかごまかしながら頷く。
未透は、わずかに笑って言った。
「でもね、手術が近づくと、やっぱり……ちょっとだけ不安になるんだよね」
「……うん」
「それでも、こうして君が来てくれたから。もうそれだけで十分だって思えるくらい」
その瞳は、透き通るように優しかった。
俺はベッド脇に置いてあった“ことばノート”に目を落とした。
よくよく見ると、そこかしこに小さく付いた滲みがあった。
それが、未透の涙だったのか、それともインクのシミか、はたまた手が震えていたからかは分からない。でもそれは彼女の怯えを如実に表しているようだった。
「未透さん……」
俺が名前を呼ぶと、彼女はゆっくりとこちらに顔を向けた。
「どうして“未透”って名前を名乗ってたの?」
俺の問いに、彼女はふっと目を細めた。
「……わたしの本当の名前ってね、君にとって、あの日のことを思い出させる引き金になると思ったの。だから、わざと隠したの」
これもまた彼女の優しさだった。中学の時にあれほどの仕打ちを受けたのに、まだ清くて強い優しさを持っている。
「じゃあ、俺のことはずっと知ってたんだね」
「一目でわかったよ。中学からはかなり遠い高校を選んだら、まさか君がいたのは驚いたよ。だからこそ、わたしは自分の名前を偽った」
未透は儚い笑みを浮かべた。
「君が、ちゃんと“自分の言葉”でその記憶と向き合えるようになるまで……わたしの名前を使わずにいてくれるかなって」
涙がこみ上げてきそうになる。
「迷惑かけてごめん。でも、もう思い出せそうなんだ。あと少しで。名前も、あのときの声も、表情も」
俺はことばノートの最後のページをゆっくりとめくった。
「うん。きっと思い出せる。だって君は、ずっと言葉を書いてくれたから。自分と向き合ってくれたから」
未透はゆっくりと頷くと、ノートに目をやった。
真っ白なそのページに、何かを書きたくてたまらなかった。
書かずにはいられない感情が胸に湧き上がっていた。
「……未透さん」
「うん?」
「ありがとう。また出会えて本当によかった」
そう言うと、彼女はまぶたを伏せて、小さな声で答えた。
「こちらこそ。君に“ありがとう”を伝えるために、ここまで来たんだと思う。君はわたしを見捨てたわけじゃない。見守ってくれてたんだよ。悪いのは全部、わたしをいじめた人たちだから、君が気にする必要はない……そうでしょ?」
「……」
未透からの問いかけに対して、俺は何も言えなかった。ここでその言葉に甘えてしまえば、また記憶の中の彼女が遠ざかっていくような気がしたから。
俺は自分の過去に正面から向き合うことを改めて決意した。
「陽翔くん、明日は手術の準備があって時間を作れないから、また明後日のこの時間に来て? 手術が終わったら話そうよ」
未透は枯れた声を明るく取り繕って、綺麗な笑顔を向けてくれた。
「わかった。2日後、また来るよ。またね?」
「うん、またね。“はるくん”」
最後に見た未透の表情は希望に満ちていた。
まるで、最高の明るい未来しか見えていないかのようだった。
明日が、どうなるのかは分からない。
でも、俺はようやくここに立てた。
後悔じゃなく、“言葉”を選べた自分で、ここに。
だから、もう逃げたくない。
過去に向き合って、彼女の名前を見つけ出す。
そして、言葉できちんと伝える。
空は淡い赤色で、夏の終わりを感じさせる静けさがあった。
自転車のペダルをこぐ足元に、吐いた息が白く流れていく。
きしむチェーンの音が耳障りで、荒みかけた心が刺激される。
「はぁはぁ……」
俺は必死に前に進んでいた。
向かう先は病院だった。
けれど、心の準備はまだできていなかった。
彼女は俺が返したノートを読んでくれているだろうか?
未透から俺に届いた言葉。
俺が返した言葉。
たくさんのやり取りを重ねて、たくさんの言葉を掛け合って、お互いの心には安寧が生まれていた。
俺が勝手に思っているだけかもしれないけど、そのたくさんやり取りや重ねた言葉は、ほんの数十ページなのに何百、何千の言葉よりも重かった。
そして、最後に言葉を綴った瞬間、俺は確かに決めたはずだった。
どんな理由を並べても、言い訳にしかならない。
だから会わなきゃいけない。
今度こそ、ちゃんと伝えなきゃいけない——そう思ったはずだったのに。
俺はまだ、病院へ足を運べていなかった。
雨が降る日、電車の路線を調べては検索履歴を消した。何度も、何度も、家の玄関扉の前に立ったのに、あと一歩が踏み出せなかった。
頭では分かっている。もう迷っている時間はない。
未透の時間は限られている。
それでも、足が動かなかった。
“もし、もう話せなかったら?”
“もし、もう会えない状態だったら?”
そんな恐怖が、俺の意思とは裏腹に体を縛り付けていた。いや、違う。俺の意思も同じく弱気になっていたんだ。前に向いたつもりでも、過去の後悔を嘆くばかりでまともに行動できていない。
また何もできずに終わるんじゃないか。
このままノートだけのやり取りで、終わってしまうんじゃないか。
心の奥に、あのときと同じ影が棲みついていた。
でも、今回はそれに負けたくなかった。
だから、こうして夕暮れを背に家を出た。
目的地も、行き先も、はっきりと決まっている。
ただ、気持ちを追いつかせるために、遠回りをしているだけだ。
俺はハンドルを握る手に力を込めた。
“今度こそ、自分の言葉で彼女に伝える”
あの日の約束を、もう一度、自分に刻み込む。
未透に出会ったことで生まれた言葉がある。
彼女が教えてくれた。
声に出さなきゃ、気持ちは届かないし、想いは伝わらない。
だからこそ、俺は——
ノートに書いた最後の言葉を、もう一度、心の中でなぞる。
“会いにいくよ”——俺の、今のすべて。
病院の前に立つと、思っていた以上に足がすくんだ。
これまでに何度も、あのノートの文字を読んだ。
未透の筆跡。彼女の綴る言葉のあたたかさと静けさに、何度救われただろう。
けれど、その筆跡はだんだん弱々しくなっていた。
まるで、ひと文字ごとに力を振り絞っているかのように。
その変化に気づいていながら、俺はただ“交換”を続けてきた。
ノートの最後に綴った言葉——
『会いにいくね』
それは俺の言葉だった。
本当は、もっと早く伝えるべきだった。
でも、未透の“願い”があのノートには込められていたから、俺はずっとそれを守っていた。
——言葉で、心で、伝え合おうって。
つまり、会わないようにしようって、そういう意味なんだって俺は思っていた。
それが未透の望んだ“形”だった気がして。
未透の言葉の端々から、俺には“そのとき”が近づいているのが分かっていた。
だから、今日は——ちゃんと、会いにいく。
自動ドアの前で一度深呼吸をして、足を踏み入れる。
白く明るいロビーの空気を吸うと、少しだけ喉が渇いた。水が飲みたいわけじゃない。ただ、俺の心には潤いが足りなかった。
「……」
俺が受付に向かおうとしたそのとき、制服姿の俺に気づいた看護師が歩み寄ってきた。
「あの、もしかして——陽翔さんですか?」
「えっ……あ、はい。そうですけど」
突然の声に少し驚いた俺に、その看護師はやわらかく微笑んだ。
「笹山さんがおっしゃられていました。“陽翔くんが来たら、どうか案内してあげてほしい”って」
「ささやま、さん……?」
その名前が告げられた瞬間、鼓動が大きく跳ねた。
笹山——その苗字は、まるで聞き覚えがなかった。
頭のどこかがぐらりと揺れて、思考が一瞬止まる。
でも、次の瞬間にはすべてが繋がっていくのを感じていた。
——未透の苗字は、“笹山”なんだ。
そとそも未透という名前が苗字なのか下の名前なのかもはっきりしない。俺は彼女から聞いた、というただそれだけの理由で彼女の名前が本当なのだと思っていた。その名前が偽物なんだということは気がついていたが、それでもなぜか“未透”という名前には、どこか触れてはいけない感じがした。
そこには触ったら壊れてしまう儚さがあったから、俺はずっとそれを追及しないでいた。いや、正しくは追及できなかった。
「……あの、笹山さんはどこの部屋ですか」
平静を取り繕って尋ねた。
「案内します。ついてきてください」
看護師に続いて、白い廊下を歩き出す。
何もかもが、ゆっくりと過去と未来を混ぜ合わせながら、静かに進んでいく気がした。
俺は今、ようやく“彼女”に会いにいく。
名前を知らなかった彼女に。
想いを伝えてくれた、たったひとりの“君”に。
ノートにはもう書かれていない言葉を、今度は“声”で——
◇◆◇◆◇
看護師が戸を叩いたが、音に応える気配はなかった。
病室のドアが、静かに開かれた。
数秒待って看護師が言った。
「入ってあげてください」
ふわりと微笑んでくれた。未透からどんな話を聞いているのかはわからないけど、その声色は包み込むような優しさがあった。
「失礼します」
俺はゆっくりと病室へ足を踏み入れる。
少しして振り向くと、すでに看護師はいなくなっていた。
静まり返った病室。
白いレースのカーテンが窓の外の光をやわらかく遮っていて、部屋の中の淡い雰囲気を優しく包み込んでいた。
ベッドの上には、静かに眠っている未透がいた。
彼女は夢の中にいるような穏やかな表情をしていた。
だけど、その頬はやせ細り、肌は前よりもずっと白くなっていた。
点滴の管が手の甲に繋がれている。
機械の微かな電子音が、現実を物語っていた。
——これは、現実だ。目の前に見えているのは、俺が目を背け続けてきた光景そのものだった。
俺はそっと歩み寄って、ベッドの脇の椅子に腰を下ろす。彼女を起こさないように、静かな息遣いで。
彼女の枕元には、一冊のノートが置かれていた。
……それは、ことばノートだった。
俺が最後に書いた言葉。
『会いにいくね』
その一文を綴ったノートのページは開いたままになっていた。
ページの端に、小さな折り目があった。
震えるような指先で触れた跡が、そこに残っていた。
もしかしたら、ページを開くのに精一杯で、まだ読めていないのかもしれない。
「未透さん……」
俺は彼女の名を呼んだ。その名前が偽物だったとしても、俺にとって彼女は未透だった。
そんな彼女の病状が気がかりで、俺の心中は穏やかじゃなかった。
俺の心臓は高鳴っていた。
外にも聞こえてしまうんじゃないかって思うくらいだった。
しかし、そんな中でも、窓際に飾られた真白いスズランの花は美しく輝いていた。
花言葉は幸せの再訪。本で読んだことがある。
「スズラン、か」
思わず声が漏れ出たそのときだった。
ふと、声が聞こえてきた。いや、彼女なりに言うなら見えたというべきか、それとも感じたというべきか。
あの感覚がここにきて俺を刺激した。
『おもいだして』
『わたしは、ここにいるよ……?』
『はる……くん?』
そんな消え入りそうな声が俺の頭の中に反響したその瞬間。眠り続けていた未透のまつげがわずかに揺れた。
彼女の瞼がゆっくりと持ち上がる。
眠りの世界から引き戻されたように、未透がこちらを見つめた。
「……えっ? はる、くん……?」
未透が小さく目を見開き、息をのんだのがわかった。
驚きの色がその表情に広がって、やがて、それは少しだけ安堵に変わった。
「……なんでここにいるの」
彼女の声は掠れていて、けれど確かに届いた。
俺は”はるくん”と呼ばれたことへの驚きよりも先に、彼女が目覚めたことを喜んでいた。
「会いにきたよ。それと、未透の想いはちゃんと俺に伝わったよ」
未透の唇が、かすかに動く。
何か言おうとしたようだったが、それよりも先に俺は問いかけた。
「体調は……どう?」
その質問に、彼女はわずかに目を伏せて、小さな声で返した。
「……見ての通りだよ。君から戻ってきたノートも、まだ見れてないくらい。開いた途端に意識なくなっちゃったのかも」
苦笑に近い表情だった。
ノートに目をやると、最後に書いた言葉の上に少しだけ涙の跡が滲んでいた。手のひらで握りつぶしたような跡もあり、一目で彼女のやるせない気持ちが伝わってきた。
「読まなくていいよ、無理しないで」
俺がそう言うと、未透は首を横に振った。
「ううん、読むよ。絶対に、読む。だって……」
そこで言葉を切る。
喉に何かが詰まったようだった。
俺は、彼女がその言葉を取り戻すまで、ただ静かに見守っていた。
多分、10秒くらい経ったと思う。
「……ずっと、待ってたから」
未透は震えた声色でそう口にした。
「ほんとはね……いつか、君が来てくれるって、信じてた」
「だから……あのノートも、宝箱みたいに大事にして、先生と看護師さんには“もし陽翔くんが来たら病室を伝えていいよ”って、お願いしておいたの」
それを聞いた瞬間、胸の奥がぎゅっと締めつけられた。
未透は、ずっと俺を信じてくれていた。
来るかどうかもわからない未来に、希望を託して。
それなのに、俺は——
「……ごめん。もっと、早く来るべきだった」
「そんなこと、ないよ。君はちゃんと来てくれた。むしろ、わたしが遠ざけてたから……」
未透の言葉は、やっぱりあたたかかった。
掠れていても、震えていても、真っ直ぐで優しかった。
ベッドの上、枕元に咲くように微笑む彼女を見ていると、涙がこぼれそうになる。その儚さと今にも消えてしまいそうな弱々しさは、俺が見ないようにしてきた現実だった。
でも、俺は泣かない。
今度こそ、ちゃんと“言葉”で伝えたいから。
声にして、想いを届けたいから。
「未透さん……ありがとう」
その一言に、これまでのすべてを込めた。
未透は、目を閉じるようにして、小さく息を吐いた。
「……ねぇ、陽翔くん」
「うん?」
「もう、気づいてるよね。わたしの本当の名前は……未透じゃないんだよ?」
とっくに気づいていた。でも、言えなかった。思い出せなかった。未透という名前が偽名だとわかっていながらも、俺はそう呼び続けるしかなかった。甘んじるしかなかった。
「知りたい?」
「うん……でも、俺は自分に思い出したい。もう少しでわかる気がするから」
「……わかった」
未透がふわりと微笑むと、窓の外から優しい風が吹き込んできた。
空はもう深い紺色に染まっており、秋が近づいているから風は少し冷たかった。
夜になった病室は妙な静けさを宿していて、中庭や屋上前の踊り場にいるときとは全然違う雰囲気だった。
どこか怖くて、逃げ出したくなってしまう。この場に留まっていると未来が見えてしまうような気がした。
「怖い顔」
「っ……ご、ごめん」
「やっぱり病院は怖いよね」
「未透さんも怖い?」
俺がふと尋ねると、未透はベッドの上で枕に寄りかかるように上体を起こし、少し息を整えながら話し出した。
「……うん。怖いよ。だって——明後日、手術だもん」
静かに、けど、しっかりとした声だった。
俺はほんの一瞬だけ心臓が跳ねるのを感じた。
知っていた。噂で聞いていた。でも、それを未透の口から聞くことで、現実の輪郭がくっきりと浮かび上がった気がした。
「成功率は高いみたい。主治医の先生も、“希望はある”って言ってたから」
「……そうなんだ」
言葉が詰まりそうになるのを、何とかごまかしながら頷く。
未透は、わずかに笑って言った。
「でもね、手術が近づくと、やっぱり……ちょっとだけ不安になるんだよね」
「……うん」
「それでも、こうして君が来てくれたから。もうそれだけで十分だって思えるくらい」
その瞳は、透き通るように優しかった。
俺はベッド脇に置いてあった“ことばノート”に目を落とした。
よくよく見ると、そこかしこに小さく付いた滲みがあった。
それが、未透の涙だったのか、それともインクのシミか、はたまた手が震えていたからかは分からない。でもそれは彼女の怯えを如実に表しているようだった。
「未透さん……」
俺が名前を呼ぶと、彼女はゆっくりとこちらに顔を向けた。
「どうして“未透”って名前を名乗ってたの?」
俺の問いに、彼女はふっと目を細めた。
「……わたしの本当の名前ってね、君にとって、あの日のことを思い出させる引き金になると思ったの。だから、わざと隠したの」
これもまた彼女の優しさだった。中学の時にあれほどの仕打ちを受けたのに、まだ清くて強い優しさを持っている。
「じゃあ、俺のことはずっと知ってたんだね」
「一目でわかったよ。中学からはかなり遠い高校を選んだら、まさか君がいたのは驚いたよ。だからこそ、わたしは自分の名前を偽った」
未透は儚い笑みを浮かべた。
「君が、ちゃんと“自分の言葉”でその記憶と向き合えるようになるまで……わたしの名前を使わずにいてくれるかなって」
涙がこみ上げてきそうになる。
「迷惑かけてごめん。でも、もう思い出せそうなんだ。あと少しで。名前も、あのときの声も、表情も」
俺はことばノートの最後のページをゆっくりとめくった。
「うん。きっと思い出せる。だって君は、ずっと言葉を書いてくれたから。自分と向き合ってくれたから」
未透はゆっくりと頷くと、ノートに目をやった。
真っ白なそのページに、何かを書きたくてたまらなかった。
書かずにはいられない感情が胸に湧き上がっていた。
「……未透さん」
「うん?」
「ありがとう。また出会えて本当によかった」
そう言うと、彼女はまぶたを伏せて、小さな声で答えた。
「こちらこそ。君に“ありがとう”を伝えるために、ここまで来たんだと思う。君はわたしを見捨てたわけじゃない。見守ってくれてたんだよ。悪いのは全部、わたしをいじめた人たちだから、君が気にする必要はない……そうでしょ?」
「……」
未透からの問いかけに対して、俺は何も言えなかった。ここでその言葉に甘えてしまえば、また記憶の中の彼女が遠ざかっていくような気がしたから。
俺は自分の過去に正面から向き合うことを改めて決意した。
「陽翔くん、明日は手術の準備があって時間を作れないから、また明後日のこの時間に来て? 手術が終わったら話そうよ」
未透は枯れた声を明るく取り繕って、綺麗な笑顔を向けてくれた。
「わかった。2日後、また来るよ。またね?」
「うん、またね。“はるくん”」
最後に見た未透の表情は希望に満ちていた。
まるで、最高の明るい未来しか見えていないかのようだった。
明日が、どうなるのかは分からない。
でも、俺はようやくここに立てた。
後悔じゃなく、“言葉”を選べた自分で、ここに。
だから、もう逃げたくない。
過去に向き合って、彼女の名前を見つけ出す。
そして、言葉できちんと伝える。