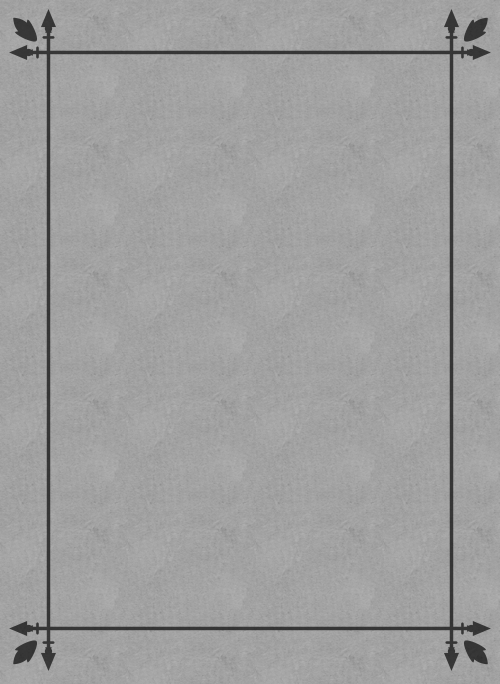再会は、永遠じゃなかった。
学校に未透の姿はない。
今日は一段と乾いた風が吹いていた。それはいつもより少し冷たい風だった。
「またね、って言ったじゃん」
誰にも届かないように、つぶやいた声が風にさらわれた。
朝も、昼も、放課後も。彼女の気配は、どこにもなかった。
無駄だと分かりながら、いつかのように職員室でさりげなく聞いても、
「えーっと……みとうさん? そんな子、いたかしら?」
しらばっくれるだけだった。
「体が弱くて入退院を繰り返してる女の子です」
俺は憤る気持ちを抑えて先生の目を見た。
「入退院を……あぁ、2年生のあの子ね、体調が優れないからしばらくお休みするそうよ。それ以上は詳しく伝えられないわねぇ」
そんな言葉しか返ってこない。
前と同じ、決まりきった曖昧な答えだった。
俺にはそれだけで十分すぎるほどの不安があった。
彼女の体調が“普通じゃない”ということくらい、もうとっくに分かっていた。
それなのに俺は彼女の事情に踏み込めなかった。踏み込んでしまえば、今の関係が壊れてしまうんじゃないかって思ってしまった。
未透は笑顔を見せて言葉をかけてくれるけど、あれは元気を取り繕っているだけなのだと思う。
最初は気づかなかったが、話をするうちにわかるようになった。
——でも、俺には何もできない。何も言えない。
また姿を消してしまうのかもしれない
そう思うたびに、胸が締めつけられた。
未透に会えなかった日々のなかで、俺は少しずつ言葉を綴り始めていた。
白紙のノートに思いの丈をぶつける。
階段の踊り場で。教室の片隅で。自分の部屋の机の上でも。
誰に向けたとも分からない言葉たちを、ノートの白紙の上に静かに書き続けた。
なんの意味があるかは分からない。
ただ、未透の言う通り、言葉は誰かに届けてこそだ。
思ったことを綴れば、それを誰かに届けられれば、何かが変わる。そんな気がしていた。
『また、君に会えたなら——』
気がつけば、その言葉で始まる文章が増えていた。
前までの俺は、“また”という言葉が、こんなにも重いなんて知らなかった。
再会のあと、もう一度失うかもしれない。
そんな恐れが言葉を変えていく。
昨日までの希望は今日の不安にかき消される。
でも、それでも——
「信じたい」と思う気持ちは、どこかで消えずに残っていた。
前みたいに、自分の感情に蓋をしてやりすごすこともできたはずだ。
しかし、今の俺には、それができない。
未透が残してくれた言葉たちが、俺のなかに“色”を灯していたからだ。
誰かの言葉が、ここまで人の心を変える。
それを知ってしまったからこそ、もう何も感じないふりはできなかった。
ある日、帰り支度をしていたときだった。
教室の後ろの方で、ぽつりと誰かの声が聞こえた。
「なんかさ、3組のほうで、ずっと学校来てない子がいるらしいじゃん?」
「え、知ってる。あの……黒髪で色白の子?」
「うん。なんか、体調よくないって。前からたまにしか来てなかったらしいけど、今はもう病院にいるとか……」
「え、マジで?」
その言葉が、俺の時間を止めた。
“黒髪で色白の子”——それが未透でないはずがなかった。
思わず立ち上がりそうになる衝動を、ぎりぎりのところで抑えた。
顔には出さないようにしたけど、内心は荒んで制御できなくなっていた。
彼女の姿が見えなくなってから、ずっと胸の奥にあった不安。
それが現実味を帯びた瞬間だった。
もう3週間も経つ。あまりにも長い。
なぜ、誰も彼女のことを知らなかったのか。
なぜ、誰も彼女の不在を騒がなかったのか。
答えは簡単だった。
“彼女は知られていなかった”からだ。
彼女はずっと、誰の中心にもいなかった。
ただ静かに、そこにいただけだった。
でも、俺にとっては——もう、それだけでは済まされなかった。
家に帰る道すがら、何度も未透の言葉を思い出した。
『言葉って、届かないこともあるけど……でも、誰かがちゃんと受け止めてくれたら、それだけで救われるんだと思う』
あのときの笑顔が、あたたかい風に溶けてゆくように蘇った。
俺は未透から、たくさんの言葉を受け取った。変わるきっかけをもらった。
でも、彼女は——自分の想いを、誰に残しているんだろう。
人にばかり言葉を伝えて、自分の想いは隠しこんでいるんじゃないか?
俺はノートを開いて、書く。
『俺はどうしたらいい? 何をしたらいい?』
自問自答を繰り返しても答えは出てこない。
未透に会えない日々は、続いていた。
でも俺は、もう何もせずにはいられなかった。
とある金曜日の放課後。
陽は傾きかけていて、昇降口に差し込む光が床に長く伸びていた。
俺はゆっくりと靴を履き替え、ふと正面玄関の外を見つめた。
ほんの数週間前まで、あの扉の向こうに、未透がいた。
それが今では、どこにも気配がない。
でも、ただ待っているだけじゃ、何も変わらない。
そう思うようになったのは、自分の“後悔”に向き合いはじめたからだ。
誰かが苦しんでいるのを見て、それでも目を逸らしてしまった過去。
名前を呼べなかった自分。
その後悔を繰り返すくらいなら、今度は、ちゃんと行動しよう——そう思った。
その日、俺は初めて図書室のカウンターで、小さな声を絞り出した。
「あの……3組の未透さんって、今どこにいますか?」
予想していたことだけど、やはり図書委員の先生はすぐに表情を曇らせた。
周りに人がいない状況なら教えてくれると踏んでいた。でも、それは安直な考えだったらしい。
「みとうさん? それは下の名前? 苗字?」
「っ……えーっと、黒髪で肌が白くて、背が小さめの女の子です」
正直言うと、未透という名前が苗字なのかどうかも知らなかった。聞くまでもなく、俺たちは仲を深めていたから。少なくとも俺はそう思っていた。名前なんて知らなくても問題ない、と。
「……私は2年生の担当はしてないからわからないけれど、その子ってあなたと一緒に図書室によく来ていた子よね?」
「はい。何がご存知ですか?」
「うーん、今は訳あって登校できていないのよ。さすがにこれ以上は言えないわね」
先生は一拍おいて、やさしい声で言った。
全く相手にしてくれない。
そんなものだ。当たり前だ。
俺以外の全生徒がそうであるように、先生たちも彼女のことをそういう生徒として認識しているだけなんだ。
「わかりました。ありがとうございます」
俺は小さく頭を下げて図書室を後にした。
何も得られなかったはずのやりとりだったけど、胸の奥には確かに何かが残っていた。
未透に何かを届けたい。
——“言葉”を。
たとえそれが届くか分からなくても、信じてみたい。
信じることを、未透が教えてくれたから。
帰り道、風が頬をなでた。
そのぬるさと冷たさの混じった風が、季節の境界を知らせていた。
俺の中でも、何かが変わろうとしていた。
まだ未透に会えるかは分からない。
でも、あの時とは違う。
今度は、ちゃんと自分の言葉で、想いを届けたい。
ノートを開く。
ページの真ん中に、大きくひとこと。
『探してるよ。君のことを』
そして、その横に、もうひとつ書き加えた。
『また、君に会いたい』
それはこれまでの自問自答ではなく、未透に向けた大切な言葉だった。
『どこにいるのか教えてほしい』
◇◆◇◆◇◆
数週間が流れ、白紙だったノートは未透への言葉で埋まっていた。
今日も一人で悶々と過ごしていると、それは何の前触れもなく訪れた。
頭の中に、いきなり過去の記憶が想起された。
それは、放課後の図書室。
窓際の席には誰もいなかった。
夕焼けの光がページの上に差し込んで、うっすらと影をつくっている。
俺は未透と最後にここに座った日のことを思い出しながら、ただページをめくっていた。
そのときだった。
ふと、ページの白紙の余白に、かつて誰かと一緒に見た文字が浮かんだ気がした。
——きれいな言葉をノートに書いてるの。
その言葉に、胸がひどくざわついた。
あれは、確か……
思い出すよりも先に、脳裏に鮮明な情景がよみがえっていた。
——中学一年の夏。暑さの残る放課後だった。
「ねえねえ、これ見て! きょうの“ことばノート”」
あの子は、笑いながら俺にノートを差し出してきた。
罫線にそって丁寧に並んだ文字たち。そこには、読んだ本の中から好きな言葉がいくつも書き写されていた。
「“ひとりじゃないって思えるだけで、少しだけ、強くなれる”……なんか、いいよね」
俺は横から覗き込んで、黙って頷いた。
言葉の意味が完全に理解できたわけじゃなかったけど、その子がそれを大事にしてることだけは伝わってきた。
「ことばって、ちょっとだけ魔法みたいだと思わない?」
彼女は笑っていた。
小柄で、色白で、黒髪を耳の後ろで結んでいた。
その笑顔を俺は忘れてしまっていた。ただ、やけに鮮明に胸の奥に残っていた。
何度も遊んだ。二人で放課後の教室に残って勉強会を開いたり、帰り道を並んで歩いて笑い合ったり、図書室で静かに本を読みながらも笑顔を見せ合ったり……俺は学校の誰よりも彼女と仲が良かった。
だけど——
その子の名前だけが、どうしても思い出せない。
口元まで来て、何度も喉で止まる。
記憶の中では呼びかけていたはずなのに、いざ声にしようとすると、そこだけが“音”にならない。
——またね、と言ったあのときも。
——いつも隣にいてくれたときも。
思い出せるのは、声の調子、目線、距離、ぬくもり、全部あるのに。
名前だけが、まるで誰かに封じられたように、どうしても出てこない。
「……っく」
唇を噛みしめる。
その子は、俺にとって特別だった。
誰よりも近くて、でも、俺が“踏み込まなかった”相手。
異変に気づきながら、言葉を飲み込んだあの日々。
ある日から、彼女の登校は減っていった。
「最近——さん、来ないね」
ふいに、誰かがぽつりと呟いた。
窓際の席。空になった机。そこに今まで当たり前のようにいたはずの“彼女”の不在が、ようやく誰かの言葉になった。
でも、返事はなかった。
教室はただ、気まずそうな空気に沈黙していた。
視線は交差せず、誰もがどこかを見て見ぬふりをしていた。
俺もまた曖昧に笑って誤魔化していた。
本当は不安だったのに。
胸のどこかがずっと痛かったのに。
でも、そのときの俺には彼女の苦しみに触れる覚悟がなかった。
その痛みに寄り添う強さが、足りなかった。
そして、彼女はいなくなった。
これまでは数週間に一度だけぽつぽつと登校していたのに、いつの日か泡のように消えてしまった。
教室から、学校から、俺の“日常”から消えた。
彼女の名前は、あの日から誰も口にしなくなった。
理由は、分かっていた。
——いじめ。
明確に殴られたり、物を壊されたり、そういうことはなかった。
けれど、言葉の刃は日常のあちこちに無数に散らばっていた。
些細な噂。意味深な笑い声。机への落書き。
廊下ですれ違うときの、わざとらしい肩の当たり方。
何よりも凄惨だったのは、体が弱くて病気がちな彼女を、ウイルスそのものとして扱う空気になっていた。
そして、それを見て見ぬふりをする大多数。
俺もその中の一人だった。
あのとき俺は気づいていた。
彼女の笑顔が、だんだんと引きつったものになっていたこと。
常に誰かの視線に怯えていたこと。
でも、俺は“空気を読んだ”。
気づかないふりをした。
問いかけなかった。「どうしたの?」の一言さえ言えなかった。
怖かったんだ。
俺まで何かを言われるのが。
それまで保っていた曖昧で無難な立ち位置が崩れるのが。
俺が何かを言ったら、彼女がもっと傷つく目に遭うんじゃないかって。でもそれは、きっとくだらない言い訳だ。
俺はずっと彼女の異変に気づいていながら、気づかないふりをしていた……自分にそれが降りかかってくるのが嫌で逃げていたんだ。
彼女がいなくなったあとになって聞いた。
もう中学には通えないらしい、と。
理由は誰もはっきりとは言わなかった。
みんな知っていた。俺も知っていた。
それでも何も言えなかった。
名前も、声も、全部喉の奥で凍っていた。
最後に話したときの彼女の笑顔。
それが、俺の記憶に焼き付いて離れない。
あの時、俺が名前を呼んでいれば。
たった一言でも、何かを言っていたら。
“——”
その名前を、今も俺は口に出せない。
でも、忘れてなどいない。
あの日、何もできなかった自分を、忘れてなどいない。
図書室の中で、俺は目を伏せる。
溢れる涙を指で拭い、平静を取り繕う。
泣きたかったのは彼女のほうだ。同情してただ見るだけしかできなかった俺が涙を流す権利はない。
あれから、何年も経った。
記憶の奥にある風景は少しも色褪せていなかった。
夕暮れの教室、言葉をかけられなかった背中。
名前すら呼べず、ただ見ていることしかできなかった自分。
その悔しさが、未だに胸の奥で静かに燻っていた。
——何か、きっかけさえあれば……
ふと、心の中で声が囁いた。その瞬間、閃いた。
「そうだ……ことばノートだ、ことばノートだよ!」
突如として、未透の声が鮮明に蘇る。
『わたしにとっては、小さな宝箱みたいなものなんだ』
『大切な言葉、うれしかった一言、ふと浮かんだ想い……そういうのを、ぜんぶ書いておくの』
あのときは軽い雑談のように聞いていた。
けれど今、その言葉が脳裏に焼きついたように離れない。
“言葉は残すもの”——未透がそう言っていた意味が、ようやく胸に落ちてくる。
「……俺にも、あるじゃないか」
気づけば、胸ポケットに入れていた自分のノートを握りしめていた。
今まで無意識に何気なく書いていた言葉たち。伝えたいのに伝えられなかった想い。
それはすべて、“届けたかった誰か”へのことばだったのだ。
それなのに、名前も呼べないまま、記憶の中で彼女は“誰か”のまま、立ち尽くしている。
そして今、未透の姿と重なりながら、彼女はまた、俺の前から姿を消そうとしている。
じゃあ、“また同じこと”に繰り返さないために、俺は何ができる?
名前が思い出せなくても、過去はやり直せなくても……今なら伝えられる言葉がある。
——未透に。
そして、あのときの“彼女”に。
俺はゆっくりとノートを開いた。
そして、震える手で、こう綴った。
『——さん。思い出せなくてごめん。でも、忘れてなんかいない』
たった一行のその言葉に、込められるすべてをのせて。
次のページには、こう書いた。
『もう二度と、後悔はしないから』
◇◆◇◆◇
放課後。図書室で借りていた本を返そうとしたら、返却口に小さなノートがぽつんと置かれていた。それを見つけたのは、ほんの偶然だった。
白地に、金色のラインが走った布張りの表紙。何度も開かれた痕跡があって、角が少しだけ丸まっていた。
その表紙の隅に、小さく書かれていた。
——ことばノート
「……!」
無意識に手が勝手に伸びていた。
ノートの裏表紙には、一枚の付箋が貼られていた。そこには、たった一行。
『このノートに、ことばを残してくれたら嬉しいです。差出人はヒミツ。でも、届け先はここです。』
その下に、病院名と、号室が書かれていた。
けれど——名前はなかった。
ページをめくると、見覚えのある文字が並んでいた。
整った文字。少しだけ丸みを帯びた筆跡。
そして、その言葉たちは間違いなく未透のものだった。
『今日の空は、すこし霞んでいました。だけど、君にこの言葉がきっと届くなら、空の色なんて気になりませんでした。』
喉の奥が詰まる。
——未透だ。
確信したのに、それでも俺は、すぐにその住所へ向かおうとは思わなかった。
……いや、思えなかった。
理由は、はっきりしている。
“怖かった”。
彼女の状態が、いま、どれほど悪いのか。
行ってしまえば、現実が突きつけられる。
ここ数週間は俺の想像のなかで生きていた未透という存在が、本当に目の前から消えてしまうかもしれない。
そして何より——
“今の俺が、彼女に会う資格があるのか”という迷い。
名前を呼べなかった、あの過去の自分。
未透に、何も返せなかったまま、ただ寄りかかってきた日々。
いま会えば、きっと泣いてしまう。
言いたいことが、全部こぼれてしまう。
そんな自分が、彼女の前に立ってもいいのか、分からなかった。
けれど、そのノートは——
そんな俺に、もう一度“ことば”をくれた。
自分だけの言葉を綴ることばノートではなくて、これは二人だけの言葉を綴ることができる。
『君の言葉は、とても優しい。だから、いつか……ちゃんと聞かせてね?』
ページの最後にそう綴られていた言葉に、俺は小さく息を吐いた。
これは、未透からの招待状だ。
直接でなくてもいい。まずは、ノートを通して、伝えよう。
こうして、俺たちは、ことばノートの交換日記を始めた。
『こんにちは。ノート、読ませてもらいました。まだ名前も知らないけれど、あなたの言葉が、すごく胸に残ったから』
『本当は、あなたことを知ってる気がする。だけど、それを確かめるのが少しだけ怖いんだ』
『今の俺は、言葉を届けることしかできないけど、それでもよければ、また、返事を書いてもいいかな?』
俺はそれだけ綴って、返却口に戻した。
すると、次の日、ノートはまた図書室のカウンターに戻っていた。
開くと、丁寧な文字が並んでいた。
『お返事、とても嬉しかったよ。ありがとう』
『君が誰なのか、わたしは分かってるつもり。たぶん、同じことを思ってるんじゃないかなって』
『だから、名前はまだ言わないね。今は、お互い“言葉”だけでつながっていたいから』
その優しい文字に、俺は何度もページをなぞった。
不思議だった。文字だけなのに、ちゃんと彼女の声が聞こえる気がした。
未透は元気そうに言葉を綴っていた。
今日見た空のこと、窓辺の花の話、本の中で心に残った台詞。
いつもの彼女そのものだった。
だけど。
だからこそ、俺はどこか、不安になっていた。
『最近のわたしはね、体の調子がすごく良いんだよ。毎日、空の色が綺麗に見えるの』
そんな言葉の裏に、なにかを隠している気がした。
以前、彼女は言っていた。
『調子がいいときほど、逆に怖くなる。終わりが近いんじゃないかって、思っちゃうんだ』
その言葉が、胸に残っていたから。
だから、俺は“すぐに病院へ行く”という選択を取れなかった。
名前がわからない——という理由もある。
でも、それ以上に、彼女の“言葉”がまだ続いている間は、この交換ノートという形を大切にしたかった。
それは、逃げではない。今の俺が届けられる“精一杯”だった。
——言葉だけでつながっている。
それが、かつて俺が何も言えずに失った誰かと、違う形で向き合えている証だと思えたから。
未透との、ことばノートの交換日記を始めてから数十日が経ち、廊下をすれ違うクラスメイトたちの声が、どこか遠く感じられた。
「ねえ、パネルは赤い画用紙でいいんだっけ?」
「えー、じゃあ私はタイトル文字やるよ!」
文化祭前の準備に、校内は少し浮ついた空気に包まれていた。
教室も廊下も、あちこちで段ボールやペンキの匂いが漂っている。
教卓の上には模造紙や資料の山が重ねられ、生徒たちはそれを囲むようにして話していた。
俺はその一角にいた。けれど、輪には入っていなかった。前までの俺なら積極的とは言わずともそれとなく自分を演じていたけど、ここ最近はそれをやめた。
耳に届く会話の内容も、意味を持たない音のように感じる。
——まるで、別の世界にいるみたいだ。
「陽翔くん、この画材、運ぶの手伝ってくれない?」
ふと近くの女子に声をかけられた。でも、やっぱり気が乗らない。やる気がないわけではないし、みんなの邪魔をしたいわけでもない。単純に未透のことが気が気でなくて頭が回っていないのだ。
「……ごめん。今、ちょっと……」
俺は曖昧な笑顔を返すと、彼女は「そっか、ごめんねー」と軽く手を振って去っていった。
その姿が見えなくなったあと、俺は窓際の席に座り、ぼんやりとノートを開いた。
ことばノート——
未透との交換日記。唯一やりとりできるもの。
そこには、今日もまた、彼女の小さな文字が並んでいた。
『文化祭の季節だね。みんな準備でバタバタしてる?』
『陽翔くんは、何を担当してるの? 手伝ってあげられたらよかったのに』
いつの日にか、知らない誰かと誰かの手紙ではなく、俺と未透と手紙になっていた。
あたたかい言葉。どこまでも未透らしい、柔らかな口調。
『今日の空、すごくきれいだったよ。夏が遠ざかっていく音がして、少し寂しかった。』
『この頃、ちょっと疲れやすくなってきたけど、まだだいじょうぶ。ぜったい、まだだいじょうぶだから。』
ページをめくる手が止まった。
その「まだ」は、たぶん、誰に向けてでもない。
だけど、俺にはどうしたって、それが“俺への言葉”に思えてならなかった。
文面の端々からにじみ出る違和感。
いつもよりちょっと丸みのない筆跡。
最近はやたらと短くなった文面。文字が少しかすれていたり、ゆがんでいたりする日もある。
いつの頃からか、毎日だったやりとりが、1日おきになることも増えてきた。
大丈夫って書かれていても、本当に大丈夫だなんて思えなかった。
不安は、膨らむばかりだった。
ひとつひとつの言葉が、まるで誰かに言い聞かせるような響きを持っていた。
そして、何より。
『……会えなくてごめんね。でも、言葉は届くって信じてる。陽翔くんが信じてくれるなら、わたしもだいじょうぶ。』
そこにあるのは、“信じてる”という言葉で自分を支えようとしている彼女の姿だった。
俺は、ノートを胸元に抱える。
そのまま目を閉じると、胸の奥が重くなる。
わかっていた。
未透は、どこかを目指している。
あるいは、何かに向かって進んでいる。
それがどんな場所かは、まだ言葉にされていない。でも、その静かでゆるやかな切実さが、ノートの行間に滲んでいた。
そのことに気づいている自分が情けなかった。
気づいていながら、ただ「会いたい」なんて、軽々しく言えるわけがなかった。
『もう少しだけ、こうしていてもいい?』
——そう締めくくられた未透の手紙の一文が、胸に刺さった。
彼女の願いだ。
真実を隠したままでも、まだ“言葉”を交わせるこの時間が、今の彼女にとってはなにより大切なのだと——そう伝わってきた。
……なら、俺は。
知らないふりをしてでも、応えるしかなかった。
『もちろん。いくらでも、待ってるよ。ずっとでもいい。君の言葉がわかるなら、それでいい』
俺はそう綴ってノートを閉じた。
けれど、指先は少しだけ震えていた。
声に出したら、崩れてしまいそうな想いが、胸の奥に渦を巻いていた。
本当は、いますぐにでも会いにいきたい。直接、顔を見て、声を聞きたい。
だけど——彼女が願った「今のまま」の関係。
それを壊すことが、彼女の“心”にとってどれだけの負担になるかを思うと、俺には踏み込む勇気が出せなかった。
だから俺は何も知らないふりをして、今日もノートに返事を書く。
心のどこかでは気のせいであることを願って。
俺の勘違いであると信じて。
俺がこの耳で本当の言葉を聞いて、本当のことを知るまでは、それが全て嘘なんだと思い込んで。
——そんな俺の逃避を確信に変える出来事が起きたのは、つい数日前のことだった。
昼休み。忘れ物を取りに職員室に向かったときだった。
ドアの手前で、ふと中から声が聞こえてきた。
「3組の子……ほら、あの静かな子。あの子、来週大きな手術があるらしいじゃない」
「うん、けっこう深刻みたいよ。頑張ってたのにねぇ……」
ドアの向こう、聞き慣れた名前が、あまりにも無防備に語られていた。
息が詰まる思いだった。
心臓がどくん、と一度だけ強く鳴って、あとは沈黙。
俺はその場に立ち尽くしたまま、何も言えずに踵を返した。
彼女は——来週、手術を控えている。
それがどれほど重いものなのかは、詳しくは知らない。
でも、その言葉の響きだけで、胸の奥がざわついた。
手紙じゃ間に合わないかもしれない。
声を、直接届けないといけないのかもしれない。
けれど——
「会いにいくことが、彼女の負担になるかもしれない」
未透は直接会うことは避けていた。
病室に見舞いに来られるのを望まないような、そんな言葉も残していた。
少し前のノートにはこんなふうに書かれていた。
“わたしの姿を見たら、陽翔くんがつらくなると思うから”
あれは、病院で起きた笑い話に交えて綴られた冗談のような文面だった。俺にはその意味が痛いほどわかる。
未透は俺と会うことを望んでいないのかもしれない。
だけど——それでも。
俺は、行こうと思った。
直接、言葉を渡しに。
たとえ彼女がそれを望んでいないとしても。
それでも、今度は逃げない。
自分の言葉で、ちゃんと“ありがとう”を伝えるために。
文化祭の準備が進むなか、俺は心の準備をしていた。
ノートに、最後の一行を書き足す。
『——会いにいくね』
学校に未透の姿はない。
今日は一段と乾いた風が吹いていた。それはいつもより少し冷たい風だった。
「またね、って言ったじゃん」
誰にも届かないように、つぶやいた声が風にさらわれた。
朝も、昼も、放課後も。彼女の気配は、どこにもなかった。
無駄だと分かりながら、いつかのように職員室でさりげなく聞いても、
「えーっと……みとうさん? そんな子、いたかしら?」
しらばっくれるだけだった。
「体が弱くて入退院を繰り返してる女の子です」
俺は憤る気持ちを抑えて先生の目を見た。
「入退院を……あぁ、2年生のあの子ね、体調が優れないからしばらくお休みするそうよ。それ以上は詳しく伝えられないわねぇ」
そんな言葉しか返ってこない。
前と同じ、決まりきった曖昧な答えだった。
俺にはそれだけで十分すぎるほどの不安があった。
彼女の体調が“普通じゃない”ということくらい、もうとっくに分かっていた。
それなのに俺は彼女の事情に踏み込めなかった。踏み込んでしまえば、今の関係が壊れてしまうんじゃないかって思ってしまった。
未透は笑顔を見せて言葉をかけてくれるけど、あれは元気を取り繕っているだけなのだと思う。
最初は気づかなかったが、話をするうちにわかるようになった。
——でも、俺には何もできない。何も言えない。
また姿を消してしまうのかもしれない
そう思うたびに、胸が締めつけられた。
未透に会えなかった日々のなかで、俺は少しずつ言葉を綴り始めていた。
白紙のノートに思いの丈をぶつける。
階段の踊り場で。教室の片隅で。自分の部屋の机の上でも。
誰に向けたとも分からない言葉たちを、ノートの白紙の上に静かに書き続けた。
なんの意味があるかは分からない。
ただ、未透の言う通り、言葉は誰かに届けてこそだ。
思ったことを綴れば、それを誰かに届けられれば、何かが変わる。そんな気がしていた。
『また、君に会えたなら——』
気がつけば、その言葉で始まる文章が増えていた。
前までの俺は、“また”という言葉が、こんなにも重いなんて知らなかった。
再会のあと、もう一度失うかもしれない。
そんな恐れが言葉を変えていく。
昨日までの希望は今日の不安にかき消される。
でも、それでも——
「信じたい」と思う気持ちは、どこかで消えずに残っていた。
前みたいに、自分の感情に蓋をしてやりすごすこともできたはずだ。
しかし、今の俺には、それができない。
未透が残してくれた言葉たちが、俺のなかに“色”を灯していたからだ。
誰かの言葉が、ここまで人の心を変える。
それを知ってしまったからこそ、もう何も感じないふりはできなかった。
ある日、帰り支度をしていたときだった。
教室の後ろの方で、ぽつりと誰かの声が聞こえた。
「なんかさ、3組のほうで、ずっと学校来てない子がいるらしいじゃん?」
「え、知ってる。あの……黒髪で色白の子?」
「うん。なんか、体調よくないって。前からたまにしか来てなかったらしいけど、今はもう病院にいるとか……」
「え、マジで?」
その言葉が、俺の時間を止めた。
“黒髪で色白の子”——それが未透でないはずがなかった。
思わず立ち上がりそうになる衝動を、ぎりぎりのところで抑えた。
顔には出さないようにしたけど、内心は荒んで制御できなくなっていた。
彼女の姿が見えなくなってから、ずっと胸の奥にあった不安。
それが現実味を帯びた瞬間だった。
もう3週間も経つ。あまりにも長い。
なぜ、誰も彼女のことを知らなかったのか。
なぜ、誰も彼女の不在を騒がなかったのか。
答えは簡単だった。
“彼女は知られていなかった”からだ。
彼女はずっと、誰の中心にもいなかった。
ただ静かに、そこにいただけだった。
でも、俺にとっては——もう、それだけでは済まされなかった。
家に帰る道すがら、何度も未透の言葉を思い出した。
『言葉って、届かないこともあるけど……でも、誰かがちゃんと受け止めてくれたら、それだけで救われるんだと思う』
あのときの笑顔が、あたたかい風に溶けてゆくように蘇った。
俺は未透から、たくさんの言葉を受け取った。変わるきっかけをもらった。
でも、彼女は——自分の想いを、誰に残しているんだろう。
人にばかり言葉を伝えて、自分の想いは隠しこんでいるんじゃないか?
俺はノートを開いて、書く。
『俺はどうしたらいい? 何をしたらいい?』
自問自答を繰り返しても答えは出てこない。
未透に会えない日々は、続いていた。
でも俺は、もう何もせずにはいられなかった。
とある金曜日の放課後。
陽は傾きかけていて、昇降口に差し込む光が床に長く伸びていた。
俺はゆっくりと靴を履き替え、ふと正面玄関の外を見つめた。
ほんの数週間前まで、あの扉の向こうに、未透がいた。
それが今では、どこにも気配がない。
でも、ただ待っているだけじゃ、何も変わらない。
そう思うようになったのは、自分の“後悔”に向き合いはじめたからだ。
誰かが苦しんでいるのを見て、それでも目を逸らしてしまった過去。
名前を呼べなかった自分。
その後悔を繰り返すくらいなら、今度は、ちゃんと行動しよう——そう思った。
その日、俺は初めて図書室のカウンターで、小さな声を絞り出した。
「あの……3組の未透さんって、今どこにいますか?」
予想していたことだけど、やはり図書委員の先生はすぐに表情を曇らせた。
周りに人がいない状況なら教えてくれると踏んでいた。でも、それは安直な考えだったらしい。
「みとうさん? それは下の名前? 苗字?」
「っ……えーっと、黒髪で肌が白くて、背が小さめの女の子です」
正直言うと、未透という名前が苗字なのかどうかも知らなかった。聞くまでもなく、俺たちは仲を深めていたから。少なくとも俺はそう思っていた。名前なんて知らなくても問題ない、と。
「……私は2年生の担当はしてないからわからないけれど、その子ってあなたと一緒に図書室によく来ていた子よね?」
「はい。何がご存知ですか?」
「うーん、今は訳あって登校できていないのよ。さすがにこれ以上は言えないわね」
先生は一拍おいて、やさしい声で言った。
全く相手にしてくれない。
そんなものだ。当たり前だ。
俺以外の全生徒がそうであるように、先生たちも彼女のことをそういう生徒として認識しているだけなんだ。
「わかりました。ありがとうございます」
俺は小さく頭を下げて図書室を後にした。
何も得られなかったはずのやりとりだったけど、胸の奥には確かに何かが残っていた。
未透に何かを届けたい。
——“言葉”を。
たとえそれが届くか分からなくても、信じてみたい。
信じることを、未透が教えてくれたから。
帰り道、風が頬をなでた。
そのぬるさと冷たさの混じった風が、季節の境界を知らせていた。
俺の中でも、何かが変わろうとしていた。
まだ未透に会えるかは分からない。
でも、あの時とは違う。
今度は、ちゃんと自分の言葉で、想いを届けたい。
ノートを開く。
ページの真ん中に、大きくひとこと。
『探してるよ。君のことを』
そして、その横に、もうひとつ書き加えた。
『また、君に会いたい』
それはこれまでの自問自答ではなく、未透に向けた大切な言葉だった。
『どこにいるのか教えてほしい』
◇◆◇◆◇◆
数週間が流れ、白紙だったノートは未透への言葉で埋まっていた。
今日も一人で悶々と過ごしていると、それは何の前触れもなく訪れた。
頭の中に、いきなり過去の記憶が想起された。
それは、放課後の図書室。
窓際の席には誰もいなかった。
夕焼けの光がページの上に差し込んで、うっすらと影をつくっている。
俺は未透と最後にここに座った日のことを思い出しながら、ただページをめくっていた。
そのときだった。
ふと、ページの白紙の余白に、かつて誰かと一緒に見た文字が浮かんだ気がした。
——きれいな言葉をノートに書いてるの。
その言葉に、胸がひどくざわついた。
あれは、確か……
思い出すよりも先に、脳裏に鮮明な情景がよみがえっていた。
——中学一年の夏。暑さの残る放課後だった。
「ねえねえ、これ見て! きょうの“ことばノート”」
あの子は、笑いながら俺にノートを差し出してきた。
罫線にそって丁寧に並んだ文字たち。そこには、読んだ本の中から好きな言葉がいくつも書き写されていた。
「“ひとりじゃないって思えるだけで、少しだけ、強くなれる”……なんか、いいよね」
俺は横から覗き込んで、黙って頷いた。
言葉の意味が完全に理解できたわけじゃなかったけど、その子がそれを大事にしてることだけは伝わってきた。
「ことばって、ちょっとだけ魔法みたいだと思わない?」
彼女は笑っていた。
小柄で、色白で、黒髪を耳の後ろで結んでいた。
その笑顔を俺は忘れてしまっていた。ただ、やけに鮮明に胸の奥に残っていた。
何度も遊んだ。二人で放課後の教室に残って勉強会を開いたり、帰り道を並んで歩いて笑い合ったり、図書室で静かに本を読みながらも笑顔を見せ合ったり……俺は学校の誰よりも彼女と仲が良かった。
だけど——
その子の名前だけが、どうしても思い出せない。
口元まで来て、何度も喉で止まる。
記憶の中では呼びかけていたはずなのに、いざ声にしようとすると、そこだけが“音”にならない。
——またね、と言ったあのときも。
——いつも隣にいてくれたときも。
思い出せるのは、声の調子、目線、距離、ぬくもり、全部あるのに。
名前だけが、まるで誰かに封じられたように、どうしても出てこない。
「……っく」
唇を噛みしめる。
その子は、俺にとって特別だった。
誰よりも近くて、でも、俺が“踏み込まなかった”相手。
異変に気づきながら、言葉を飲み込んだあの日々。
ある日から、彼女の登校は減っていった。
「最近——さん、来ないね」
ふいに、誰かがぽつりと呟いた。
窓際の席。空になった机。そこに今まで当たり前のようにいたはずの“彼女”の不在が、ようやく誰かの言葉になった。
でも、返事はなかった。
教室はただ、気まずそうな空気に沈黙していた。
視線は交差せず、誰もがどこかを見て見ぬふりをしていた。
俺もまた曖昧に笑って誤魔化していた。
本当は不安だったのに。
胸のどこかがずっと痛かったのに。
でも、そのときの俺には彼女の苦しみに触れる覚悟がなかった。
その痛みに寄り添う強さが、足りなかった。
そして、彼女はいなくなった。
これまでは数週間に一度だけぽつぽつと登校していたのに、いつの日か泡のように消えてしまった。
教室から、学校から、俺の“日常”から消えた。
彼女の名前は、あの日から誰も口にしなくなった。
理由は、分かっていた。
——いじめ。
明確に殴られたり、物を壊されたり、そういうことはなかった。
けれど、言葉の刃は日常のあちこちに無数に散らばっていた。
些細な噂。意味深な笑い声。机への落書き。
廊下ですれ違うときの、わざとらしい肩の当たり方。
何よりも凄惨だったのは、体が弱くて病気がちな彼女を、ウイルスそのものとして扱う空気になっていた。
そして、それを見て見ぬふりをする大多数。
俺もその中の一人だった。
あのとき俺は気づいていた。
彼女の笑顔が、だんだんと引きつったものになっていたこと。
常に誰かの視線に怯えていたこと。
でも、俺は“空気を読んだ”。
気づかないふりをした。
問いかけなかった。「どうしたの?」の一言さえ言えなかった。
怖かったんだ。
俺まで何かを言われるのが。
それまで保っていた曖昧で無難な立ち位置が崩れるのが。
俺が何かを言ったら、彼女がもっと傷つく目に遭うんじゃないかって。でもそれは、きっとくだらない言い訳だ。
俺はずっと彼女の異変に気づいていながら、気づかないふりをしていた……自分にそれが降りかかってくるのが嫌で逃げていたんだ。
彼女がいなくなったあとになって聞いた。
もう中学には通えないらしい、と。
理由は誰もはっきりとは言わなかった。
みんな知っていた。俺も知っていた。
それでも何も言えなかった。
名前も、声も、全部喉の奥で凍っていた。
最後に話したときの彼女の笑顔。
それが、俺の記憶に焼き付いて離れない。
あの時、俺が名前を呼んでいれば。
たった一言でも、何かを言っていたら。
“——”
その名前を、今も俺は口に出せない。
でも、忘れてなどいない。
あの日、何もできなかった自分を、忘れてなどいない。
図書室の中で、俺は目を伏せる。
溢れる涙を指で拭い、平静を取り繕う。
泣きたかったのは彼女のほうだ。同情してただ見るだけしかできなかった俺が涙を流す権利はない。
あれから、何年も経った。
記憶の奥にある風景は少しも色褪せていなかった。
夕暮れの教室、言葉をかけられなかった背中。
名前すら呼べず、ただ見ていることしかできなかった自分。
その悔しさが、未だに胸の奥で静かに燻っていた。
——何か、きっかけさえあれば……
ふと、心の中で声が囁いた。その瞬間、閃いた。
「そうだ……ことばノートだ、ことばノートだよ!」
突如として、未透の声が鮮明に蘇る。
『わたしにとっては、小さな宝箱みたいなものなんだ』
『大切な言葉、うれしかった一言、ふと浮かんだ想い……そういうのを、ぜんぶ書いておくの』
あのときは軽い雑談のように聞いていた。
けれど今、その言葉が脳裏に焼きついたように離れない。
“言葉は残すもの”——未透がそう言っていた意味が、ようやく胸に落ちてくる。
「……俺にも、あるじゃないか」
気づけば、胸ポケットに入れていた自分のノートを握りしめていた。
今まで無意識に何気なく書いていた言葉たち。伝えたいのに伝えられなかった想い。
それはすべて、“届けたかった誰か”へのことばだったのだ。
それなのに、名前も呼べないまま、記憶の中で彼女は“誰か”のまま、立ち尽くしている。
そして今、未透の姿と重なりながら、彼女はまた、俺の前から姿を消そうとしている。
じゃあ、“また同じこと”に繰り返さないために、俺は何ができる?
名前が思い出せなくても、過去はやり直せなくても……今なら伝えられる言葉がある。
——未透に。
そして、あのときの“彼女”に。
俺はゆっくりとノートを開いた。
そして、震える手で、こう綴った。
『——さん。思い出せなくてごめん。でも、忘れてなんかいない』
たった一行のその言葉に、込められるすべてをのせて。
次のページには、こう書いた。
『もう二度と、後悔はしないから』
◇◆◇◆◇
放課後。図書室で借りていた本を返そうとしたら、返却口に小さなノートがぽつんと置かれていた。それを見つけたのは、ほんの偶然だった。
白地に、金色のラインが走った布張りの表紙。何度も開かれた痕跡があって、角が少しだけ丸まっていた。
その表紙の隅に、小さく書かれていた。
——ことばノート
「……!」
無意識に手が勝手に伸びていた。
ノートの裏表紙には、一枚の付箋が貼られていた。そこには、たった一行。
『このノートに、ことばを残してくれたら嬉しいです。差出人はヒミツ。でも、届け先はここです。』
その下に、病院名と、号室が書かれていた。
けれど——名前はなかった。
ページをめくると、見覚えのある文字が並んでいた。
整った文字。少しだけ丸みを帯びた筆跡。
そして、その言葉たちは間違いなく未透のものだった。
『今日の空は、すこし霞んでいました。だけど、君にこの言葉がきっと届くなら、空の色なんて気になりませんでした。』
喉の奥が詰まる。
——未透だ。
確信したのに、それでも俺は、すぐにその住所へ向かおうとは思わなかった。
……いや、思えなかった。
理由は、はっきりしている。
“怖かった”。
彼女の状態が、いま、どれほど悪いのか。
行ってしまえば、現実が突きつけられる。
ここ数週間は俺の想像のなかで生きていた未透という存在が、本当に目の前から消えてしまうかもしれない。
そして何より——
“今の俺が、彼女に会う資格があるのか”という迷い。
名前を呼べなかった、あの過去の自分。
未透に、何も返せなかったまま、ただ寄りかかってきた日々。
いま会えば、きっと泣いてしまう。
言いたいことが、全部こぼれてしまう。
そんな自分が、彼女の前に立ってもいいのか、分からなかった。
けれど、そのノートは——
そんな俺に、もう一度“ことば”をくれた。
自分だけの言葉を綴ることばノートではなくて、これは二人だけの言葉を綴ることができる。
『君の言葉は、とても優しい。だから、いつか……ちゃんと聞かせてね?』
ページの最後にそう綴られていた言葉に、俺は小さく息を吐いた。
これは、未透からの招待状だ。
直接でなくてもいい。まずは、ノートを通して、伝えよう。
こうして、俺たちは、ことばノートの交換日記を始めた。
『こんにちは。ノート、読ませてもらいました。まだ名前も知らないけれど、あなたの言葉が、すごく胸に残ったから』
『本当は、あなたことを知ってる気がする。だけど、それを確かめるのが少しだけ怖いんだ』
『今の俺は、言葉を届けることしかできないけど、それでもよければ、また、返事を書いてもいいかな?』
俺はそれだけ綴って、返却口に戻した。
すると、次の日、ノートはまた図書室のカウンターに戻っていた。
開くと、丁寧な文字が並んでいた。
『お返事、とても嬉しかったよ。ありがとう』
『君が誰なのか、わたしは分かってるつもり。たぶん、同じことを思ってるんじゃないかなって』
『だから、名前はまだ言わないね。今は、お互い“言葉”だけでつながっていたいから』
その優しい文字に、俺は何度もページをなぞった。
不思議だった。文字だけなのに、ちゃんと彼女の声が聞こえる気がした。
未透は元気そうに言葉を綴っていた。
今日見た空のこと、窓辺の花の話、本の中で心に残った台詞。
いつもの彼女そのものだった。
だけど。
だからこそ、俺はどこか、不安になっていた。
『最近のわたしはね、体の調子がすごく良いんだよ。毎日、空の色が綺麗に見えるの』
そんな言葉の裏に、なにかを隠している気がした。
以前、彼女は言っていた。
『調子がいいときほど、逆に怖くなる。終わりが近いんじゃないかって、思っちゃうんだ』
その言葉が、胸に残っていたから。
だから、俺は“すぐに病院へ行く”という選択を取れなかった。
名前がわからない——という理由もある。
でも、それ以上に、彼女の“言葉”がまだ続いている間は、この交換ノートという形を大切にしたかった。
それは、逃げではない。今の俺が届けられる“精一杯”だった。
——言葉だけでつながっている。
それが、かつて俺が何も言えずに失った誰かと、違う形で向き合えている証だと思えたから。
未透との、ことばノートの交換日記を始めてから数十日が経ち、廊下をすれ違うクラスメイトたちの声が、どこか遠く感じられた。
「ねえ、パネルは赤い画用紙でいいんだっけ?」
「えー、じゃあ私はタイトル文字やるよ!」
文化祭前の準備に、校内は少し浮ついた空気に包まれていた。
教室も廊下も、あちこちで段ボールやペンキの匂いが漂っている。
教卓の上には模造紙や資料の山が重ねられ、生徒たちはそれを囲むようにして話していた。
俺はその一角にいた。けれど、輪には入っていなかった。前までの俺なら積極的とは言わずともそれとなく自分を演じていたけど、ここ最近はそれをやめた。
耳に届く会話の内容も、意味を持たない音のように感じる。
——まるで、別の世界にいるみたいだ。
「陽翔くん、この画材、運ぶの手伝ってくれない?」
ふと近くの女子に声をかけられた。でも、やっぱり気が乗らない。やる気がないわけではないし、みんなの邪魔をしたいわけでもない。単純に未透のことが気が気でなくて頭が回っていないのだ。
「……ごめん。今、ちょっと……」
俺は曖昧な笑顔を返すと、彼女は「そっか、ごめんねー」と軽く手を振って去っていった。
その姿が見えなくなったあと、俺は窓際の席に座り、ぼんやりとノートを開いた。
ことばノート——
未透との交換日記。唯一やりとりできるもの。
そこには、今日もまた、彼女の小さな文字が並んでいた。
『文化祭の季節だね。みんな準備でバタバタしてる?』
『陽翔くんは、何を担当してるの? 手伝ってあげられたらよかったのに』
いつの日にか、知らない誰かと誰かの手紙ではなく、俺と未透と手紙になっていた。
あたたかい言葉。どこまでも未透らしい、柔らかな口調。
『今日の空、すごくきれいだったよ。夏が遠ざかっていく音がして、少し寂しかった。』
『この頃、ちょっと疲れやすくなってきたけど、まだだいじょうぶ。ぜったい、まだだいじょうぶだから。』
ページをめくる手が止まった。
その「まだ」は、たぶん、誰に向けてでもない。
だけど、俺にはどうしたって、それが“俺への言葉”に思えてならなかった。
文面の端々からにじみ出る違和感。
いつもよりちょっと丸みのない筆跡。
最近はやたらと短くなった文面。文字が少しかすれていたり、ゆがんでいたりする日もある。
いつの頃からか、毎日だったやりとりが、1日おきになることも増えてきた。
大丈夫って書かれていても、本当に大丈夫だなんて思えなかった。
不安は、膨らむばかりだった。
ひとつひとつの言葉が、まるで誰かに言い聞かせるような響きを持っていた。
そして、何より。
『……会えなくてごめんね。でも、言葉は届くって信じてる。陽翔くんが信じてくれるなら、わたしもだいじょうぶ。』
そこにあるのは、“信じてる”という言葉で自分を支えようとしている彼女の姿だった。
俺は、ノートを胸元に抱える。
そのまま目を閉じると、胸の奥が重くなる。
わかっていた。
未透は、どこかを目指している。
あるいは、何かに向かって進んでいる。
それがどんな場所かは、まだ言葉にされていない。でも、その静かでゆるやかな切実さが、ノートの行間に滲んでいた。
そのことに気づいている自分が情けなかった。
気づいていながら、ただ「会いたい」なんて、軽々しく言えるわけがなかった。
『もう少しだけ、こうしていてもいい?』
——そう締めくくられた未透の手紙の一文が、胸に刺さった。
彼女の願いだ。
真実を隠したままでも、まだ“言葉”を交わせるこの時間が、今の彼女にとってはなにより大切なのだと——そう伝わってきた。
……なら、俺は。
知らないふりをしてでも、応えるしかなかった。
『もちろん。いくらでも、待ってるよ。ずっとでもいい。君の言葉がわかるなら、それでいい』
俺はそう綴ってノートを閉じた。
けれど、指先は少しだけ震えていた。
声に出したら、崩れてしまいそうな想いが、胸の奥に渦を巻いていた。
本当は、いますぐにでも会いにいきたい。直接、顔を見て、声を聞きたい。
だけど——彼女が願った「今のまま」の関係。
それを壊すことが、彼女の“心”にとってどれだけの負担になるかを思うと、俺には踏み込む勇気が出せなかった。
だから俺は何も知らないふりをして、今日もノートに返事を書く。
心のどこかでは気のせいであることを願って。
俺の勘違いであると信じて。
俺がこの耳で本当の言葉を聞いて、本当のことを知るまでは、それが全て嘘なんだと思い込んで。
——そんな俺の逃避を確信に変える出来事が起きたのは、つい数日前のことだった。
昼休み。忘れ物を取りに職員室に向かったときだった。
ドアの手前で、ふと中から声が聞こえてきた。
「3組の子……ほら、あの静かな子。あの子、来週大きな手術があるらしいじゃない」
「うん、けっこう深刻みたいよ。頑張ってたのにねぇ……」
ドアの向こう、聞き慣れた名前が、あまりにも無防備に語られていた。
息が詰まる思いだった。
心臓がどくん、と一度だけ強く鳴って、あとは沈黙。
俺はその場に立ち尽くしたまま、何も言えずに踵を返した。
彼女は——来週、手術を控えている。
それがどれほど重いものなのかは、詳しくは知らない。
でも、その言葉の響きだけで、胸の奥がざわついた。
手紙じゃ間に合わないかもしれない。
声を、直接届けないといけないのかもしれない。
けれど——
「会いにいくことが、彼女の負担になるかもしれない」
未透は直接会うことは避けていた。
病室に見舞いに来られるのを望まないような、そんな言葉も残していた。
少し前のノートにはこんなふうに書かれていた。
“わたしの姿を見たら、陽翔くんがつらくなると思うから”
あれは、病院で起きた笑い話に交えて綴られた冗談のような文面だった。俺にはその意味が痛いほどわかる。
未透は俺と会うことを望んでいないのかもしれない。
だけど——それでも。
俺は、行こうと思った。
直接、言葉を渡しに。
たとえ彼女がそれを望んでいないとしても。
それでも、今度は逃げない。
自分の言葉で、ちゃんと“ありがとう”を伝えるために。
文化祭の準備が進むなか、俺は心の準備をしていた。
ノートに、最後の一行を書き足す。
『——会いにいくね』