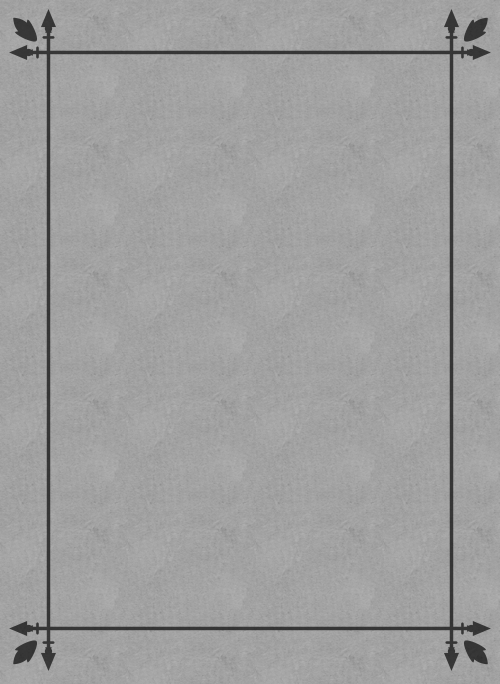夏の終わりも間近だった。それを感じさせるぬくぬくとした陽射しは、どこか淡くて懐かしかった。
午後の授業が終わると同時に、俺は自然と足を動かしていた。
向かう先は、校舎の端にある中庭の小径。
もう何度通ったかわからない場所。
それでも、足は毎回、どこか新しい気持ちで向かっていた。
今日も彼女はいないかもしれない。それでも向かう理由は、ただそこに立ってみたかったから。
けれど、その日は——違った。
曲がり角の先に、風に揺れる黒髪が見えた。
思わず足を止める。声をかけようとしたけれど、喉がすぐには動かなかった。
まるで夢の中の自分のように、言葉にならず言い淀んでしまった。
それでも、彼女のほうから気づいてくれたのか、ゆっくりとこちらを振り返った。
未透だった。
いつかのように、制服のリボンは少し曲がっていたし、袖口には小さなほころびが見えた。
でも、それが彼女らしいと思えた。
「……久しぶり」
そう言ったのは、俺の方だった。
未透は驚いた様子も見せず、ただ静かに笑った。
「うん。久しぶりだね、陽翔くん」
その声を聞いた瞬間、何かが胸の奥でほどけるような感覚があった。
あの日から、言葉にならなかったものが、少しだけ、形を取り始めたような。
「会えない間、ずっと考えてたよ」
「うん」
「なんて言えばいいのかわからなかったけど、でも、また会えたのが嬉しいって……それだけは、ちゃんと伝えたかった」
俺は照れ臭かったがはっきり伝えた。
すると、未透は静かに頷いた。
「また……っていうのは、そういう意味だよね。わかったんだ?」
沈黙が流れる。でも、不思議とそれが心地よかった。
俺はそっと言葉を続けた。
「未透は……ずっと、“言葉”について話してたよね。残る言葉、届かない言葉……そんな想いとか、じっくり考えてみたら、それが少しだけわかった気がしたんだ」
未透の表情が、わずかに変わった。
「言いたかったけど言えなかったことって、時間が経っても消えないんだよね。忘れたつもりでも、ちゃんとそこにあって……いつか、ちゃんと向き合わなきゃって。そう思えるようになった」
「……うん」
「まだ全部は思い出せてない。でも、俺の隣にはあの子がたしかにいた。それだけは、ちゃんと感じられてる」
未透は少しだけ目を伏せて、風の吹く方へと顔を向けた。
その横顔が、どこか寂しげだった。
「陽翔くん」
「なに?」
「誰かの想いって、ほんとはそんなに遠くに行かないんだと思う。ちゃんと受け取ってくれる人がいれば届くんだよ……時間がかかってもね」
その言葉はまるで、あのノートのページから直接こぼれ落ちたようだった。
「だからね、わたし……陽翔くんに、言葉を届けたかった。きっと、君なら受け取ってくれると思ったから」
その瞬間、俺は確信した。
図書室で見つけたノート。あれは未透が、俺のために残してくれたものだったんだと。
偶然なんかじゃなかった。
彼女は、俺がきっと見つけてくれると信じてくれていた。
俺が過去を思い出し、前を向くために、彼女は力を貸してくれたのだ。
「ありがとう」
自然と、そう口にしていた。
「ううん。こちらこそ……届いてよかった」
未透は少しだけ涙ぐんで笑った。
その笑顔が、胸に焼きついた。
彼女の笑顔を見ていると、ふと胸の奥が騒ぎ出す。
それは力を貸してくれた彼女への感謝を示す感情じゃない。これは……既視感だ。彼女を見ていると、やっぱりなんだか初めてじゃない気がした。
声も、話し方も、細い指先も、どこかで知っているような気がしていた。
けれど、その感覚は記憶とは結びつかない。
いや、違う。結びつかないんじゃない。結びつけたくないのかもしれない。
彼女の中に、“あの子”の影を見ていることは、もう自分でも気づいていた。
ノートを読み終えた瞬間にそう感じていた。
でも——名前が、どうしても思い出せない。
目の前に立つ少女の名前は、未透だ。
じゃあ、俺があの時に名前を呼べなかったあの子の名前は?
未透……ではない。何度連呼しても塞ぎ込めてしまった記憶の中枢が刺激されないから間違いない。
「……だめだ」
俺は無意識に頭を抱えて弱音を吐いていた。
その名前を思い出してしまったら、すべてが崩れてしまいそうだった。
あの時、自分が何をしなかったのか、どうして静観することしかできなかったのか。
全部が一度に押し寄せてきて、息ができなくなる。
だから俺は、あの子の名前という最後のピースを、無意識に閉じ込めてしまっている。
未透とこうして話せている今の時間が、本当に嬉しくて、大切で、失いたくなくて——
その思いが強くなればなるほど、過去を認めるのが怖くなる。
もし彼女が“あの子”だとしたら、俺はもう、言い訳なんてできない。
その怖さに、俺はまだ立ち向かえていなかった。
俺は真実から目を逸らして、また俺は未透と彼女を遠ざけようとする。
悩みあぐねいた俺を見かねたのか、はたまた偶然か。未透はおもむろに口を開いた。
「ねぇ、陽翔くんは、探しものを見つけられた? まだだよね?」
「見つけられそうなんだけど……どうしても手が届かない。俺が弱いから、臆病だから、怖がっているから、なかなか一歩踏み出せないでいるんだ」
唐突な問いかけに対して、俺は嘆息を堪えて答えた。
すると、未透は包み込むような優しい表情で応えた。
「君は弱くないよ。臆病でもないし、怖がりでもない。だから、自分を責めないで?」
「……優しいね」
「言葉は残り続けるから焦る必要はない。陽翔くんの中にある言葉と秘めた想いは、必ず相手に届くから」
「じゃあ、もしも拒絶されたらどうしたらいい?」
「拒絶されることはない。それはわたしが約束する。でも、言葉自体は残り続けても、言葉を渡す相手、届けたい相手がいなかったら……もう手遅れになっちゃうからね?」
意味深に笑った彼女はそれだけ告げて踵を返した。
「それって——」
「わたしはきちんと伝えたよ。だから、見つけて? 思い出して? 待ってるから」
俺は呼び止めようとした。しかし、彼女はそのまま静かな足取りで立ち去ろうとする。
まるで、何かから逃げるかのように。
これ以上、強く呼び止めるのは憚られた。だから、俺は最後に彼女に尋ねた。
「また……ここで会えるかな?」
「……うん。わたしは、ここにいるよ。陽翔くんが、ちゃんと見てくれるなら、必ずまた会えるよ」
一見するとそれは約束のようだったが、本当の約束ではなかった。その言葉には不思議な重みがあった。
彼女はきっと長くはここにいない。
そんな予感が、どこかにあった。
でもだからこそ、今ここにいて、言葉を交わしていることが、かけがえのない時間に思えた。
夕焼けが、彼女の姿を静かに染めていた。
俺はその光景を、絶対に忘れないと思った。
◇◆◇◆◇
それから、未透はこれまでの欠席していたのが嘘みたいに何日も連続で登校していた。
なんでも新しい薬のおかげで体調が改善されたらしい。
にこやかに笑う彼女を見ていると、「よかったね」としか言うことができなかった。
その日、俺は未透と二人で図書室にいた。
彼女が突然こちらに向き直った。
「ねえ、陽翔くん」
「ん?」
「こうして二人で図書室にいるの……なんか、変な感じ」
ふいにそんなことを言うから、俺は少し戸惑いながら笑った。
「今さら?」
「もちろん、いい意味でね」
未透はそう言って、手元に開いた文庫本を閉じた。表紙を指先でなぞるようにしてから、俺の方に顔を向ける。
「……一人で本を読むのも好きだけど、誰かと読むのって、こんなに違うんだね」
「違う、って?」
「同じ本でも、君と一緒だと、ちょっとだけ違って見える気がする」
彼女の言葉は、いつだって詩みたいだった。抽象的で、でも不思議とすんなり入ってくる。
「それ、ちょっと嬉しいかも」
「ふふっ……わたしも」
未透が笑った。俺もつられて笑った。
こんな時間がずっと続けばいいのに、なんて、思った。
それから何日も、俺たちは同じように過ごした。
毎日昼休みに顔を合わせて、ささやかな話をしながらお弁当を分け合って。
授業が終わると、どちらからともなく掛け合って、自然と同じ場所へ向かっていた。
誰に何か言われるわけでもなく、気まずさもなかった。
周囲がどう思っていたのかなんて、正直どうでもよかった。
俺にとっては、未透と過ごす時間だけが“ちゃんと生きている”実感を与えてくれた。
でも——
たまに、ほんの少しだけ違和感があった。
未透の歩く速度が急に遅くなったり、何かを話そうとして言葉に詰まったり、座る時にわずかに息を飲んだり。
俺が「大丈夫?」と聞くと、彼女は決まって笑顔で「なんともないよ。お薬の副作用のせいだから」と返した。
時には晴れやかな笑顔でこう言われたこともある。
「わたしはね、調子がいいときほど逆に怖くなるの。終わりが近いんじゃないかって思っちゃうんだろうね。だから、わたしの体調が悪そうに見えるときは全部気のせいなんだよ、陽翔くん」
その言葉を否定するほど、俺は強くなかった。
あの頃の記憶が尾を引いて、うまく言葉をかけられなかった。
本当はもっと彼女を気遣って言葉をかけるべきなのに、臆病な俺は笑ってうなずくしかなかった。
そんなある日、未透が図書室で言った。
「陽翔くんって、優しいよね」
「え? そうかな……?」
「うん。いつもわたしのこと見てくれてるって思う。気づかないふりをしてくれるところとかも」
その言葉に、胸が少しだけ痛んだ。
「……気づいてないわけじゃ、ないんだけど」
「わかってる。だから、ありがとう。放っておいてくれると助かる時もある。それに他人を気にしすぎるのも良くないと思う。みんな自分を一番大切にしないといけないんだよ」
未透の微笑みには、どこか儚さがあった。
まるで、風にさらされて薄くなった羽のように。
「でも、俺は自分を大切にしすぎて、あの子を酷い目に遭わせちゃったから……」
「その子がどう思ってるかは聞いた?」
普段の未透とは違って、珍しく言葉ではなく感情論だった。
「え」
「聞いてないでしょ? 陽翔くんは悪いことをしたと思ってるかもしれないけど、その子が救われたって思ってたらそれはもう気にすることじゃないと思う。でも、陽翔くんが名前を呼べなくて、言葉をかけられなかったのは、その子のことが大切だったから、だよね?」
「……俺が気を遣って名前を呼んだり言葉をかけたら、もっと酷い目に遭っちゃうんじゃないかって思ってたよ。どっちが正解かは分からないけど、結果的にあの子は体も心もボロボロになっていなくなっちゃったから……俺は間違ってたんだよ。声をかけていたら何かが変わっていたかもしれないから」
徐々にあの頃の記憶が鮮明になっていく。
自己保身や言い訳に聞こえるかもしれないけど、俺は単に見捨てたわけではなくて、孤立するあの子のことを助ける術を失っていた。
何をすればいいのか分からなかった。だから、見ることしかできなかった。
残酷なことに、友達を自負していた俺は、いざという時に何の役にも立たなかったんだ。
「その気持ちだけでその子は救われる。その子の名前を思い出せば完璧。心のどこかにずっと言えなかった言葉があると同じで、その子の心のどこかにもずっと聞きたかった言葉があるんだよ」
未透は華奢で冷えた手のひらで、俺の頭を撫でてきた。
全てを知っているかのような、俺の心がわかるかのような、そんなはっきりとした言葉だった。
初めからずっとそうだ。未透は俺の心を手にとるように理解してくれる。なのに俺は彼女に何も返せていない。
「……ごめん、それとありがとう」
俺はそれだけ伝えて彼女に微笑みかけた。
「君は弱くない。それはわたしが保証する」
同時に下校時刻を知らせるチャイムがなると、俺たちは図書室を後にした帰路についた。
図書室の帰り道。
彼女は廊下の窓から外を見ながらぽつりと言った。
「この学校、初めて来たとき、すごく広く感じた」
「……俺も、最初はそうだったかも」
「でも今は……ううん、今は平気。むしろ、狭いって思うくらい」
「狭い?」
「君がいてくれるから、そう感じるんだと思う。隣に誰かがいるのって当たり前のことじゃないから、今はすごく幸せなんだ」
胸が、きゅっと鳴った気がした。
彼女の言葉のすべてが、あたたかくて、でもどこか切ない。
笑っているのに笑えていない。まるで鏡の中の自分を見ているかのような感覚に陥った。彼女は俺に似ている。何かに囚われている。でも、それが俺にはわからない。彼女は俺の全てを知っているかのように振る舞っているけど、俺は彼女のことを何も知らない。
それが辛かった。
だから、明日からはもっと彼女のことを知りたいって思った。表面的なところじゃなくて、もっと心の奥深くの部分……例えば、小さい頃の話とか、将来のこととか、心を通わせた相手にだけ話せる大切な思い出とか……
「また明日」
昇降口での別れのとき、俺とは帰る方向が違う未透は、心底嬉しそうな笑みを浮かべて、
「またね」
それだけ言って歩き去った。
翌日の朝。
未透は学校に来なかった。1日だけ休むものだと勝手に思っていたが、彼女はその日を境にぱったりと姿を消した。
俺は最初こそ「少し体調が悪いのかもしれない」と思っていた。だって、彼女はしきりに「平気」って言っていたから。
でも、いくら待とうと彼女は現れなかった。
少し前の時と同じで、何も言わずにいなくなった。
もしかして、あの日、最後の図書室で交わした言葉が、彼女なりの別れだったんじゃないかと、そんな予感が胸を占め始めていた。
俺はどうしても、それを信じたくなかった。
——まだ、俺は探しものを見つけられていない。
彼女のことを何も知らない。
だから、俺はあの日の言葉を繰り返した。
“またね”
きっと、あれは未透が残した、ささやかな約束だった。
それを信じていい理由が、たった一つでもあれば——俺は、どこまでも探しにいけると思った。
彼女と過ごした時間が、幻じゃなかった証明が、どこかにあると信じたかった。
午後の授業が終わると同時に、俺は自然と足を動かしていた。
向かう先は、校舎の端にある中庭の小径。
もう何度通ったかわからない場所。
それでも、足は毎回、どこか新しい気持ちで向かっていた。
今日も彼女はいないかもしれない。それでも向かう理由は、ただそこに立ってみたかったから。
けれど、その日は——違った。
曲がり角の先に、風に揺れる黒髪が見えた。
思わず足を止める。声をかけようとしたけれど、喉がすぐには動かなかった。
まるで夢の中の自分のように、言葉にならず言い淀んでしまった。
それでも、彼女のほうから気づいてくれたのか、ゆっくりとこちらを振り返った。
未透だった。
いつかのように、制服のリボンは少し曲がっていたし、袖口には小さなほころびが見えた。
でも、それが彼女らしいと思えた。
「……久しぶり」
そう言ったのは、俺の方だった。
未透は驚いた様子も見せず、ただ静かに笑った。
「うん。久しぶりだね、陽翔くん」
その声を聞いた瞬間、何かが胸の奥でほどけるような感覚があった。
あの日から、言葉にならなかったものが、少しだけ、形を取り始めたような。
「会えない間、ずっと考えてたよ」
「うん」
「なんて言えばいいのかわからなかったけど、でも、また会えたのが嬉しいって……それだけは、ちゃんと伝えたかった」
俺は照れ臭かったがはっきり伝えた。
すると、未透は静かに頷いた。
「また……っていうのは、そういう意味だよね。わかったんだ?」
沈黙が流れる。でも、不思議とそれが心地よかった。
俺はそっと言葉を続けた。
「未透は……ずっと、“言葉”について話してたよね。残る言葉、届かない言葉……そんな想いとか、じっくり考えてみたら、それが少しだけわかった気がしたんだ」
未透の表情が、わずかに変わった。
「言いたかったけど言えなかったことって、時間が経っても消えないんだよね。忘れたつもりでも、ちゃんとそこにあって……いつか、ちゃんと向き合わなきゃって。そう思えるようになった」
「……うん」
「まだ全部は思い出せてない。でも、俺の隣にはあの子がたしかにいた。それだけは、ちゃんと感じられてる」
未透は少しだけ目を伏せて、風の吹く方へと顔を向けた。
その横顔が、どこか寂しげだった。
「陽翔くん」
「なに?」
「誰かの想いって、ほんとはそんなに遠くに行かないんだと思う。ちゃんと受け取ってくれる人がいれば届くんだよ……時間がかかってもね」
その言葉はまるで、あのノートのページから直接こぼれ落ちたようだった。
「だからね、わたし……陽翔くんに、言葉を届けたかった。きっと、君なら受け取ってくれると思ったから」
その瞬間、俺は確信した。
図書室で見つけたノート。あれは未透が、俺のために残してくれたものだったんだと。
偶然なんかじゃなかった。
彼女は、俺がきっと見つけてくれると信じてくれていた。
俺が過去を思い出し、前を向くために、彼女は力を貸してくれたのだ。
「ありがとう」
自然と、そう口にしていた。
「ううん。こちらこそ……届いてよかった」
未透は少しだけ涙ぐんで笑った。
その笑顔が、胸に焼きついた。
彼女の笑顔を見ていると、ふと胸の奥が騒ぎ出す。
それは力を貸してくれた彼女への感謝を示す感情じゃない。これは……既視感だ。彼女を見ていると、やっぱりなんだか初めてじゃない気がした。
声も、話し方も、細い指先も、どこかで知っているような気がしていた。
けれど、その感覚は記憶とは結びつかない。
いや、違う。結びつかないんじゃない。結びつけたくないのかもしれない。
彼女の中に、“あの子”の影を見ていることは、もう自分でも気づいていた。
ノートを読み終えた瞬間にそう感じていた。
でも——名前が、どうしても思い出せない。
目の前に立つ少女の名前は、未透だ。
じゃあ、俺があの時に名前を呼べなかったあの子の名前は?
未透……ではない。何度連呼しても塞ぎ込めてしまった記憶の中枢が刺激されないから間違いない。
「……だめだ」
俺は無意識に頭を抱えて弱音を吐いていた。
その名前を思い出してしまったら、すべてが崩れてしまいそうだった。
あの時、自分が何をしなかったのか、どうして静観することしかできなかったのか。
全部が一度に押し寄せてきて、息ができなくなる。
だから俺は、あの子の名前という最後のピースを、無意識に閉じ込めてしまっている。
未透とこうして話せている今の時間が、本当に嬉しくて、大切で、失いたくなくて——
その思いが強くなればなるほど、過去を認めるのが怖くなる。
もし彼女が“あの子”だとしたら、俺はもう、言い訳なんてできない。
その怖さに、俺はまだ立ち向かえていなかった。
俺は真実から目を逸らして、また俺は未透と彼女を遠ざけようとする。
悩みあぐねいた俺を見かねたのか、はたまた偶然か。未透はおもむろに口を開いた。
「ねぇ、陽翔くんは、探しものを見つけられた? まだだよね?」
「見つけられそうなんだけど……どうしても手が届かない。俺が弱いから、臆病だから、怖がっているから、なかなか一歩踏み出せないでいるんだ」
唐突な問いかけに対して、俺は嘆息を堪えて答えた。
すると、未透は包み込むような優しい表情で応えた。
「君は弱くないよ。臆病でもないし、怖がりでもない。だから、自分を責めないで?」
「……優しいね」
「言葉は残り続けるから焦る必要はない。陽翔くんの中にある言葉と秘めた想いは、必ず相手に届くから」
「じゃあ、もしも拒絶されたらどうしたらいい?」
「拒絶されることはない。それはわたしが約束する。でも、言葉自体は残り続けても、言葉を渡す相手、届けたい相手がいなかったら……もう手遅れになっちゃうからね?」
意味深に笑った彼女はそれだけ告げて踵を返した。
「それって——」
「わたしはきちんと伝えたよ。だから、見つけて? 思い出して? 待ってるから」
俺は呼び止めようとした。しかし、彼女はそのまま静かな足取りで立ち去ろうとする。
まるで、何かから逃げるかのように。
これ以上、強く呼び止めるのは憚られた。だから、俺は最後に彼女に尋ねた。
「また……ここで会えるかな?」
「……うん。わたしは、ここにいるよ。陽翔くんが、ちゃんと見てくれるなら、必ずまた会えるよ」
一見するとそれは約束のようだったが、本当の約束ではなかった。その言葉には不思議な重みがあった。
彼女はきっと長くはここにいない。
そんな予感が、どこかにあった。
でもだからこそ、今ここにいて、言葉を交わしていることが、かけがえのない時間に思えた。
夕焼けが、彼女の姿を静かに染めていた。
俺はその光景を、絶対に忘れないと思った。
◇◆◇◆◇
それから、未透はこれまでの欠席していたのが嘘みたいに何日も連続で登校していた。
なんでも新しい薬のおかげで体調が改善されたらしい。
にこやかに笑う彼女を見ていると、「よかったね」としか言うことができなかった。
その日、俺は未透と二人で図書室にいた。
彼女が突然こちらに向き直った。
「ねえ、陽翔くん」
「ん?」
「こうして二人で図書室にいるの……なんか、変な感じ」
ふいにそんなことを言うから、俺は少し戸惑いながら笑った。
「今さら?」
「もちろん、いい意味でね」
未透はそう言って、手元に開いた文庫本を閉じた。表紙を指先でなぞるようにしてから、俺の方に顔を向ける。
「……一人で本を読むのも好きだけど、誰かと読むのって、こんなに違うんだね」
「違う、って?」
「同じ本でも、君と一緒だと、ちょっとだけ違って見える気がする」
彼女の言葉は、いつだって詩みたいだった。抽象的で、でも不思議とすんなり入ってくる。
「それ、ちょっと嬉しいかも」
「ふふっ……わたしも」
未透が笑った。俺もつられて笑った。
こんな時間がずっと続けばいいのに、なんて、思った。
それから何日も、俺たちは同じように過ごした。
毎日昼休みに顔を合わせて、ささやかな話をしながらお弁当を分け合って。
授業が終わると、どちらからともなく掛け合って、自然と同じ場所へ向かっていた。
誰に何か言われるわけでもなく、気まずさもなかった。
周囲がどう思っていたのかなんて、正直どうでもよかった。
俺にとっては、未透と過ごす時間だけが“ちゃんと生きている”実感を与えてくれた。
でも——
たまに、ほんの少しだけ違和感があった。
未透の歩く速度が急に遅くなったり、何かを話そうとして言葉に詰まったり、座る時にわずかに息を飲んだり。
俺が「大丈夫?」と聞くと、彼女は決まって笑顔で「なんともないよ。お薬の副作用のせいだから」と返した。
時には晴れやかな笑顔でこう言われたこともある。
「わたしはね、調子がいいときほど逆に怖くなるの。終わりが近いんじゃないかって思っちゃうんだろうね。だから、わたしの体調が悪そうに見えるときは全部気のせいなんだよ、陽翔くん」
その言葉を否定するほど、俺は強くなかった。
あの頃の記憶が尾を引いて、うまく言葉をかけられなかった。
本当はもっと彼女を気遣って言葉をかけるべきなのに、臆病な俺は笑ってうなずくしかなかった。
そんなある日、未透が図書室で言った。
「陽翔くんって、優しいよね」
「え? そうかな……?」
「うん。いつもわたしのこと見てくれてるって思う。気づかないふりをしてくれるところとかも」
その言葉に、胸が少しだけ痛んだ。
「……気づいてないわけじゃ、ないんだけど」
「わかってる。だから、ありがとう。放っておいてくれると助かる時もある。それに他人を気にしすぎるのも良くないと思う。みんな自分を一番大切にしないといけないんだよ」
未透の微笑みには、どこか儚さがあった。
まるで、風にさらされて薄くなった羽のように。
「でも、俺は自分を大切にしすぎて、あの子を酷い目に遭わせちゃったから……」
「その子がどう思ってるかは聞いた?」
普段の未透とは違って、珍しく言葉ではなく感情論だった。
「え」
「聞いてないでしょ? 陽翔くんは悪いことをしたと思ってるかもしれないけど、その子が救われたって思ってたらそれはもう気にすることじゃないと思う。でも、陽翔くんが名前を呼べなくて、言葉をかけられなかったのは、その子のことが大切だったから、だよね?」
「……俺が気を遣って名前を呼んだり言葉をかけたら、もっと酷い目に遭っちゃうんじゃないかって思ってたよ。どっちが正解かは分からないけど、結果的にあの子は体も心もボロボロになっていなくなっちゃったから……俺は間違ってたんだよ。声をかけていたら何かが変わっていたかもしれないから」
徐々にあの頃の記憶が鮮明になっていく。
自己保身や言い訳に聞こえるかもしれないけど、俺は単に見捨てたわけではなくて、孤立するあの子のことを助ける術を失っていた。
何をすればいいのか分からなかった。だから、見ることしかできなかった。
残酷なことに、友達を自負していた俺は、いざという時に何の役にも立たなかったんだ。
「その気持ちだけでその子は救われる。その子の名前を思い出せば完璧。心のどこかにずっと言えなかった言葉があると同じで、その子の心のどこかにもずっと聞きたかった言葉があるんだよ」
未透は華奢で冷えた手のひらで、俺の頭を撫でてきた。
全てを知っているかのような、俺の心がわかるかのような、そんなはっきりとした言葉だった。
初めからずっとそうだ。未透は俺の心を手にとるように理解してくれる。なのに俺は彼女に何も返せていない。
「……ごめん、それとありがとう」
俺はそれだけ伝えて彼女に微笑みかけた。
「君は弱くない。それはわたしが保証する」
同時に下校時刻を知らせるチャイムがなると、俺たちは図書室を後にした帰路についた。
図書室の帰り道。
彼女は廊下の窓から外を見ながらぽつりと言った。
「この学校、初めて来たとき、すごく広く感じた」
「……俺も、最初はそうだったかも」
「でも今は……ううん、今は平気。むしろ、狭いって思うくらい」
「狭い?」
「君がいてくれるから、そう感じるんだと思う。隣に誰かがいるのって当たり前のことじゃないから、今はすごく幸せなんだ」
胸が、きゅっと鳴った気がした。
彼女の言葉のすべてが、あたたかくて、でもどこか切ない。
笑っているのに笑えていない。まるで鏡の中の自分を見ているかのような感覚に陥った。彼女は俺に似ている。何かに囚われている。でも、それが俺にはわからない。彼女は俺の全てを知っているかのように振る舞っているけど、俺は彼女のことを何も知らない。
それが辛かった。
だから、明日からはもっと彼女のことを知りたいって思った。表面的なところじゃなくて、もっと心の奥深くの部分……例えば、小さい頃の話とか、将来のこととか、心を通わせた相手にだけ話せる大切な思い出とか……
「また明日」
昇降口での別れのとき、俺とは帰る方向が違う未透は、心底嬉しそうな笑みを浮かべて、
「またね」
それだけ言って歩き去った。
翌日の朝。
未透は学校に来なかった。1日だけ休むものだと勝手に思っていたが、彼女はその日を境にぱったりと姿を消した。
俺は最初こそ「少し体調が悪いのかもしれない」と思っていた。だって、彼女はしきりに「平気」って言っていたから。
でも、いくら待とうと彼女は現れなかった。
少し前の時と同じで、何も言わずにいなくなった。
もしかして、あの日、最後の図書室で交わした言葉が、彼女なりの別れだったんじゃないかと、そんな予感が胸を占め始めていた。
俺はどうしても、それを信じたくなかった。
——まだ、俺は探しものを見つけられていない。
彼女のことを何も知らない。
だから、俺はあの日の言葉を繰り返した。
“またね”
きっと、あれは未透が残した、ささやかな約束だった。
それを信じていい理由が、たった一つでもあれば——俺は、どこまでも探しにいけると思った。
彼女と過ごした時間が、幻じゃなかった証明が、どこかにあると信じたかった。