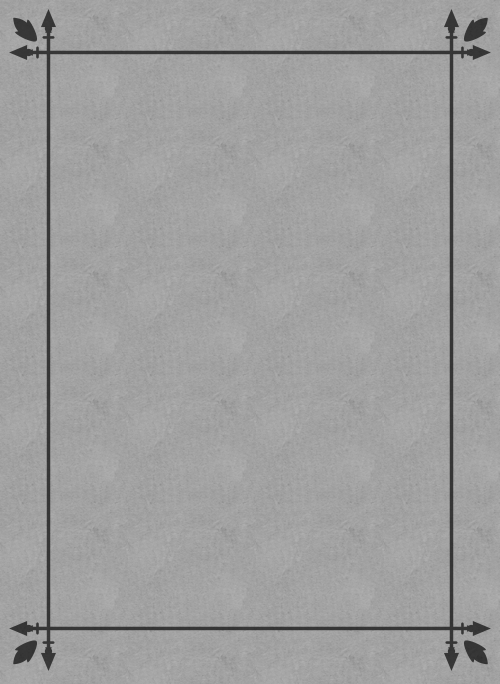未透のいない放課後が、やけに長く感じた。
教室に残っても、図書室の窓際に立っても、グラウンドの周りを歩いてみても、彼女の姿はどこにもなかった。
いるはずがないことは分かっていた。
だけど、「もしかしたら」と思ってしまって、探す意味のない場所をむやみやたらに探してしまう。
それは希望というより、諦めきれない悪癖のようなものだった。
ふとした拍子に机に向かって教科書を開く。
もちろん内容は頭に入らない。文字がただの模様のように見える。
そんな自分に笑えてくる。
今の俺は未透を探すためだけに学校に通っているみたいだ。
廊下のガラスに映る自分が、どこか他人に見えた。
まっすぐ立って歩いているのに、全く芯がない。
腑抜けた顔が馬鹿らしい。死んではないが生きてるだけ、そんな顔つきだった。
表面だけをなぞるように、日々を繰り返している。
まるで出口のない迷路に迷い込んでしまったかのような感覚だ。
でも、それはきっと、前からそうだった。
未透と出会う前の俺は、ずっとそうやって毎日を消化していた。
迷路の壁に突き当たるたびに、無難にやり過ごしては引き返し、また壁に突き当たり、引き返し……ときには立ち止まって無関心を貫いた。
そんなふうに同じ道をぐるぐる回り続けていた。
それは退屈な日常ではあったけど、やることへの不快感や嫌悪はなかった。なぜなら、俺はそれを当然のものとして消化していたから。
ただ、今はその空虚さが、はっきりとわかる。
彼女が、俺に“色”をくれたのだと思う。
今の俺はもう以前までの無難で普遍的な日常では満足できなくなっていた。
壁に突き当たると、壊したい衝動に駆られる。何か変化が欲しいと思うようになる。それこそがきっと彼女と出会って起こった変化なのかもしれない。
その日の昼休み。
階段の踊り場に座った。
閉ざされた屋上の扉。
そこに背中をもたれさせると、ひやりとした金属の冷たさが、制服越しにじんわりと伝わってくる。
ネクタイは少し緩めていた。シャツの襟元も、一つだけボタンを外してある。
誰も来ないこの場所だけが、自分でいられる場所だった。
それだけは変わらなかった。
俺は鞄の中から、くたびれたノートを取り出す。
ページの角が折れて、表紙も少し色褪せている。
何でもないような授業用のノートだったけど、今はなぜかこの中に、自分の“何か”を書きたくなる。
特に意味があるわけでもなく、ただ何かを書きたくなっていた。
制服の胸ポケットから、黒いペンを取り出した。
ペン先を出すとき、わずかに手が震えているのに気がついた。
靴の先を階段の段差に引っかけるようにして、体育座りになる。
膝にノートを置き、ゆっくりとページをめくる。
静かすぎる空気の中で、紙の擦れる音だけが響いた。
白紙のページが目の前に現れた。
それだけで胸の奥がざわついた。
何かを書こうとしても、すぐに手が止まる。
――書けない。
自分の中にあるはずの“言葉”が、どこにも見当たらない。
口に出せない言葉は文字として残せるのではないか、そんな安直な考えは無に帰した。
未透に”色”をもらった今の俺なら書けると思っていたのに、呼べなかった誰かの名前が、喉の奥で詰まったまま出てこない。無理に出そうとすると吐き気がした。体がそれを受け入れてくれない。
しかし、記憶の中には、ふわりとした影だけが残っている。
その子は確かに笑っていた。す隣にいた。楽しい思い出があった。
でも、名前だけが、うまく浮かばない。
思い出そうとするたびに、心の奥がざらついて、背中が縮こまる。
足元のスニーカーが、ぎゅっと階段を鳴らす。
自然と全身に力が入って、自分のことがやるせなくなる。
「……なんで、思い出せないんだよ」
俺は制服の袖を強く握る。
肩が微かに震えていた。
名前を忘れるはずがない。
なぜなら、あれは今の俺を作り出した重要な分岐点だから。
でも、名前を思い出せば、自分が“何をしなかったのか”が全部明らかになる。現実を突きつけられてしまう。情けなく目を背け、逃げてしまった自分に気づかされてしまう。
だから俺は――たぶん、自分で思い出すことを拒んでいる。
ふと、手が動いた。
ノートの片隅に、ひらがなで、ひとつの言葉だけを書いた。
『ごめん』
その三文字が、紙の上にじんわりと沈んでいった。
無意識に綴られたその言葉は俺の本音だった。それも、とても表面的で、その言葉だけでは取り返せない、弱くて情けなくて、言い訳のような言葉だ。
「なんなんだよ……」
俺は乱暴にノートを閉じ、ペンをカバンの中に放り投げた。
感情的になるのは得意じゃないはずなのに、自分に嫌気がさすとこうも理性を失ってしまうのは驚きだ。
だからこそ理解した。
俺の心の中に残っているのは、“名前”じゃなくて、“後悔”だった。
あまりにも大きすぎる後悔が邪魔をして、肝心の名前を思い出せないのだ。
でも、逆に言えば、後悔がある限り、その名前を忘れることはないし、後悔を払拭しなければ、俺は一生このまま停滞し続ける。
「はぁぁ……」
俺がやるせなく座り込んでいると、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
今日も俺は本当の自分を取り戻せなかった。
糸の切れた人形のような、覚束ない足取りで教室へと戻るのだった。
教室に戻ると、誰かが俺を呼んだ。
振り向くと、そこには杉下がいた。クラスのリーダー格で、よく話しかけてくる。
「陽翔」
「なに?」
「お前さ、最近変わったよな」
「……そう?」
「なんか、目が違うっつーか。ちょっと大人っぽくなった?」
「そんなことないと思うけど」
言いながら、俺は自分の声がどこか他人事に思えた。
でも、確かに自分の中に、何かが変わりつつあるのは感じていた。
以前の俺ならここで自分を偽り取り繕っていただろう。
「まあ、大人っぽくなるならいいんじゃね? 俺たちはもう高2だしなぁ」
彼はそれだけ言っていなくなった。
何を伝えたかったのかはわからない。けど、俺は初めて俺らしく自然な会話ができたと思っていた。
周囲に迎合することなく、偽ることなく、本当の自分には程遠いがわずかな自然さを出すことができた。
無理な笑顔も、愛想の良い褒め言葉も、周りを気遣う献身的な姿勢も、今の会話には何一つとしてなかった。
冷たいと言われればそれまでだけど、本来の俺はそれほど明るい性格じゃない。見た目がそうであるように、中身も似たようなものだった。
こんな自分を出せたのも、未透の言葉が俺の中で生きているおかげだ。
言葉を渡されたことで、少しずつ自分を見つけている気がする。
教室の窓から、少しだけ青空がのぞいた。
その青は、どこかで見たような、懐かしい色だった。
◇◆◇◆
その夜、眠りにつくまでに何度も寝返りを打った。
部屋の明かりはとっくに消えていて、時計の秒針だけが一定のリズムで静けさを刻んでいた。
未透がいない日々にはもう慣れたはずだった。
でも、あの静けさだけは、いまだに慣れることができなかった。
布団の中、閉じたまぶたの裏に、いろんな風景が浮かんでは消えた。
裏庭、階段の踊り場、図書室の窓際。
そして——あの子の背中。
思い出そうとすると、いつも曖昧な霞がかかる。
でも、“いた”という確信だけは、ずっと心の奥に残っている。
名前も、顔も、今は思い出せない。
けれどその子が、俺のことをあだ名で呼んでいた記憶だけは、不意に胸に蘇るときがあった。
今では、誰もそう呼ばない。
その呼び名は、記憶の奥底で、ひっそりと沈んだままだった。
そう思った瞬間、まぶたが重くなった。
意識が深いところへ引き込まれていく——
——夢を、見た。
風が吹いていた。
柔らかくて、あたたかくて、でもどこか不安を煽るような、そんな風だった。
俺は中学校の裏庭に立っていた。
懐かしさが過ぎると同時に、そこが現実の場所とは違っていることに気がついた。
空は夕焼けに染まりながらも、紫が混ざっていて、どこか夢じみていた。
木々は高く伸びすぎていたし、足元には白い小さな花が咲き乱れていた。
その中心に、ひとりの少女が立っていた。
制服の肩が少しだけ透けて見えるほど、輪郭が淡い。
黒髪が風に揺れていた。
未透によく似ていたけれど、同時にまったく別の誰かのようにも思えた。
俺は一歩、近づいた。
呼びかけようとする。
「……」
でも、声が出なかった。
喉が凍りついたみたいに動かない。
代わりに、胸の奥に何かがせり上がってくる。
懐かしさと、悔いと、恐れ。すべてが混ざりあった、言葉にならない強い衝動。
少女が、こちらに振り向いた。
顔は白く飛んでいて、見えなかった。
目元だけが揺れていて、唇が震えていた。
『……はるくん』
その声は、確かに届いた。
夢なのに、妙に鮮明だった。
誰の声かはわからない。けれど、その呼び方には確かに覚えがあった。
次の瞬間、景色が変わる。
裏庭が教室へと塗り替えられていく。
使い古された色あせた机、何も書かれていない黒板。
曇った窓からは、静かな光が差していた。
ひとりの少女が、教室の隅に座っていた。
白いカーディガン。中学校の頃の夏の制服。
小さな背中を丸めて、机に頬を乗せていた。
身体が小刻みに震えていて、声はないのに泣いているのが分かった。
俺は、ゆっくりと歩み寄った。
今度こそ名前を呼ぼうと、喉に力を込めた。
しかし、それよりも先に少女がコチラを見て口を開く。
「……は」
今にも消え入りそうな声で。
「……る」
吹けば飛んでしまいそうな弱々しい声で。
だけど、その声は聞こえなくて、誰の声は分からなくて、それでもはっきりと俺の耳に届いていた。
「……くん」
そう呼び終えた少女は涙混じりに笑っていた。
そして、ノートを見せてきた。
——はるくん、わたしのために頑張ってくれて、どうもありがとう
同時に俺は理解した。
自分が“はるくん”と呼ばれていたことを、受け入れ始めていた。
次に声なき唇が、何かを言った。
『それでも、わたしを見ててくれた』
胸の奥が、静かに波打つ。
“俺は彼女のことを見ていた”。
たしかにあの時、俺は背を向けなかった。
何度も何度も何度も何度も何度も何度も、この目で彼女のことを見ていた。
しかし、それは、ただ何もできなかっただけだ。
声も、言葉も、名前も出せなかった。
それがずっと悔いとして残っていた。
見ているだけでは意味がない。それに気づきながらも、俺は見ていることしかできなかった。
やがてわ少女の輪郭が、淡く揺れ始める。
教室の光が強くなっていく。
そのなかで、彼女が最後にもう一度、言った。
『——またね』
はっと目を覚ますと、天井がぼやけていた。
心臓がまだドクドクと鳴っていて、指先に汗がにじんでいる。
喉の奥が、燃えるように熱い。ついさっきまでは凍りついたように声が出せなかったのに。
「……はぁはぁ……っ……」
俺は上体を起こして息を荒げた。
そして、胸の中にひとつだけ、確かなものが残っていることに気がついた。
それはとても大切なことで、今までずっと忘れていたこと。だけど、決して忘れてはいけなかったこと。
名前を思い出せなかった彼女のことを思い出すために、必要となる重要なピースだ。
——そうだ、俺は、“はるくん”と呼ばれていた。
俺はあの声を、確かに知っていた。
ノートを開いて、ペンを握る。
白紙のページに、震える手で言葉を綴る。
『思い出すから、待ってて』
それが、夢から覚めた俺が最初に綴った言葉だった。
◇◆◇◆◇
夢から目覚めた翌朝。世界の色はいつもより少しだけ淡く見えた。
窓から差す朝日も、食卓の味噌汁の湯気も、通学路の電柱も。
どこか“本当の世界”じゃないような、ふわふわと浮いた感覚がまとわりついていた。
学校に着いても、足取りは妙に重かった。
夢の中で呼ばれた「はるくん」の声が、耳の奥に残っていた。
誰にも聞かれなかったはずのその呼び名が、なぜか胸をざわつかせる。
教室に入っても、いつもの喧騒が遠く感じた。
声をかけてくるクラスメイトに微笑みを返しながらも、意識はどこか別の場所にあった。
昼休み。窓の外をぼんやりと見ていると、ふと一枚の景色が胸に蘇った。
——図書室。
あの子は、そこによくいた気がする。
朧げだけど覚えている。
細い身体を椅子に沈めて、一人で本を読んでいた。
教室よりも静かで、誰にも邪魔されない場所。
俺が教室で誰かと笑っていた間、彼女は一人、あの静かな空間にいた。
記憶の奥から、ひとつの光景がゆっくりと浮かび上がる。
——ある日、誰もいない図書室の奥で、机に突っ伏していた彼女。小さな背中には寂しさを思わせた。
前までの俺なら声をかけていた。二人で並んで本を読んで、楽しく笑って幸せを共有した。
だから、その時も俺はそっと近づいて、声をかけようとして……結局、できなかった。
代わりに、机の上にあった彼女のノートに、文字がにじんでいたのを見た。
涙で濡れたページだった。
俺は席を立ち、静かに図書室へと向かった。
理由なんてなかった。ただ、行かなくちゃいけない気がした。
図書室の扉を開けると、冷たい空気が肌に触れた。
本の匂いと、紙が静かに呼吸するような空気。
そこにいるだけで、少しだけ心が落ち着いていくのを感じた。
誰もいない。司書の先生すらいない昼休み。
窓際の長机に、何気なく腰を下ろす。
高校生になってから図書室には数えるくらいしか来ていない。
だから、窓際の長机に座ったのはなんとなくだった。
「え?」
そのときだった。
机の奥に、何かが差し込まれているのが見えた。
手を伸ばして引き出すと、それは一冊のノートだった。
表紙は少し色褪せていて、角が折れている。
どこにでもあるような、よく使い込まれたノート。
落とし物か、それとも忘れられたものか。
ふと、胸がざわついた。
ノートの表紙には、名前のシールが貼ってあった。
けれど、シールはほとんど剥がれていて、肝心の名前は読めなかった。
見るに新品ではなくて。それなりに古いノートのようだ。でも、埃は被っていないから、何年も放置されていたわけではなさそうだった。
俺は静かにページをめくった。普段なら落とし物として届けるか、知らないふりをしてそのままにするのに、なぜかそのノートだけは妙に気を引かれてしまった。
ゆっくりと中を確認すると、そこには小さな字で日記のような文章が綴られていた。
数ページ分、誰にも見せるつもりはなかったような、そんなわたし語で溢れていた。
『 また椅子を隠された。
わたしが座っただけで、みんなが離れる。
でも、もう慣れた。
平気なふり、上手になったから 』
胸が痛んだ。
他人事のように読めなかった。
ページをめくるたびに思い出す。
中学時代、あの子が教室の端で一人だったこと。
咳が止まらず、何日も休んでいたこと。
あるとき帰ってきたと思ったら、周囲の目が変わっていたこと。
「感染るんじゃないか?」
「仮病じゃないの?」
「そんなんで休むの?」
そんな声が、飛び交っていた。
最初は誰もが冗談のつもりで言っていた。しかし、ある時を境にそれが本気になった。
彼女は黙っていた。反論もせず、ただ教室の隅に座っていた。
『 本当にしんどいときは、声も出せない。
でもそれが“我慢強い”ってことになるのは
ちょっと違うと思う。
たぶん、わたしが話さないのは、
もう誰にも期待してないからなんだと思う 』
ページの文字が、かすれていた。
涙で濡れたような跡が、いくつもあった。深いシワが刻まれ、やるせない思いが伝わってくる。
『 好きな人ができた。彼は優しい。
わたしとおしゃべりして、笑ってくれる。
バカにしないで寄り添ってくれる。咳をしても怒らないでいてくれる。背中をさすってくれた。
けど、最近はあんまり名前を呼んでくれない。
わたしとも、話してくれなくなった。
でも、それで安心した。名前を呼ばれて、冷たい目で見られるよりはずっといいから 』
それを読んだ瞬間、喉の奥がきゅっと締まった。
俺は彼女の名前を呼ばなかった。
呼べなかった。見ていたくせに、声をかけられなかった。
まるで自分のことを言われているかのようだった。
『 ひとつだけ嬉しかったことがある。
彼と廊下ですれ違ったとき、“目が合った”あの瞬間。
……わたしだけかもしれないけど
こっちを見てくれた気がした。
それだけで今日は生きててよかったって思えた。
勝手な思い込みかもしれないけど
それでもいい 』
最後のページに、そう記されていた。
誰の名前も書かれていない。
でも、その瞬間の記憶は、俺の中に確かにあった。
あの時、帰りの廊下で、彼女と目が合った。
何か言おうとして、何も言えなかった。
——あれは、俺だったんだ。
夢の中で聞いた「はるくん」という声。
その響きが、ここにつながっていた。
ノートを閉じて、胸に抱えた。
このノートの主が誰なのか、確証はない。
けれど、不思議なほどに、その文字たちは未透の言葉に似ていた。
どことなく似ているような気がした。
——いや、それは願望かもしれない。
でも、もしそうだとしたら。
未透は、俺が名前を呼ばなかった“あの子”なのだとしたら——
今、もう一度会えたことには、きっと意味がある。
俺はそっと目を閉じた。
未透が、もし彼女だとしても。
そうでなかったとしても。
どこかで“名を呼ばれなかった誰か”が、まだこの世界に残っているのなら。
今度こそ、俺は——の名前を呼ぶ。
その名前がなんであれ、声が届くかぎり。
そして、俺の名前が“はるくん”であることも、胸を張って認められるように。
教室に残っても、図書室の窓際に立っても、グラウンドの周りを歩いてみても、彼女の姿はどこにもなかった。
いるはずがないことは分かっていた。
だけど、「もしかしたら」と思ってしまって、探す意味のない場所をむやみやたらに探してしまう。
それは希望というより、諦めきれない悪癖のようなものだった。
ふとした拍子に机に向かって教科書を開く。
もちろん内容は頭に入らない。文字がただの模様のように見える。
そんな自分に笑えてくる。
今の俺は未透を探すためだけに学校に通っているみたいだ。
廊下のガラスに映る自分が、どこか他人に見えた。
まっすぐ立って歩いているのに、全く芯がない。
腑抜けた顔が馬鹿らしい。死んではないが生きてるだけ、そんな顔つきだった。
表面だけをなぞるように、日々を繰り返している。
まるで出口のない迷路に迷い込んでしまったかのような感覚だ。
でも、それはきっと、前からそうだった。
未透と出会う前の俺は、ずっとそうやって毎日を消化していた。
迷路の壁に突き当たるたびに、無難にやり過ごしては引き返し、また壁に突き当たり、引き返し……ときには立ち止まって無関心を貫いた。
そんなふうに同じ道をぐるぐる回り続けていた。
それは退屈な日常ではあったけど、やることへの不快感や嫌悪はなかった。なぜなら、俺はそれを当然のものとして消化していたから。
ただ、今はその空虚さが、はっきりとわかる。
彼女が、俺に“色”をくれたのだと思う。
今の俺はもう以前までの無難で普遍的な日常では満足できなくなっていた。
壁に突き当たると、壊したい衝動に駆られる。何か変化が欲しいと思うようになる。それこそがきっと彼女と出会って起こった変化なのかもしれない。
その日の昼休み。
階段の踊り場に座った。
閉ざされた屋上の扉。
そこに背中をもたれさせると、ひやりとした金属の冷たさが、制服越しにじんわりと伝わってくる。
ネクタイは少し緩めていた。シャツの襟元も、一つだけボタンを外してある。
誰も来ないこの場所だけが、自分でいられる場所だった。
それだけは変わらなかった。
俺は鞄の中から、くたびれたノートを取り出す。
ページの角が折れて、表紙も少し色褪せている。
何でもないような授業用のノートだったけど、今はなぜかこの中に、自分の“何か”を書きたくなる。
特に意味があるわけでもなく、ただ何かを書きたくなっていた。
制服の胸ポケットから、黒いペンを取り出した。
ペン先を出すとき、わずかに手が震えているのに気がついた。
靴の先を階段の段差に引っかけるようにして、体育座りになる。
膝にノートを置き、ゆっくりとページをめくる。
静かすぎる空気の中で、紙の擦れる音だけが響いた。
白紙のページが目の前に現れた。
それだけで胸の奥がざわついた。
何かを書こうとしても、すぐに手が止まる。
――書けない。
自分の中にあるはずの“言葉”が、どこにも見当たらない。
口に出せない言葉は文字として残せるのではないか、そんな安直な考えは無に帰した。
未透に”色”をもらった今の俺なら書けると思っていたのに、呼べなかった誰かの名前が、喉の奥で詰まったまま出てこない。無理に出そうとすると吐き気がした。体がそれを受け入れてくれない。
しかし、記憶の中には、ふわりとした影だけが残っている。
その子は確かに笑っていた。す隣にいた。楽しい思い出があった。
でも、名前だけが、うまく浮かばない。
思い出そうとするたびに、心の奥がざらついて、背中が縮こまる。
足元のスニーカーが、ぎゅっと階段を鳴らす。
自然と全身に力が入って、自分のことがやるせなくなる。
「……なんで、思い出せないんだよ」
俺は制服の袖を強く握る。
肩が微かに震えていた。
名前を忘れるはずがない。
なぜなら、あれは今の俺を作り出した重要な分岐点だから。
でも、名前を思い出せば、自分が“何をしなかったのか”が全部明らかになる。現実を突きつけられてしまう。情けなく目を背け、逃げてしまった自分に気づかされてしまう。
だから俺は――たぶん、自分で思い出すことを拒んでいる。
ふと、手が動いた。
ノートの片隅に、ひらがなで、ひとつの言葉だけを書いた。
『ごめん』
その三文字が、紙の上にじんわりと沈んでいった。
無意識に綴られたその言葉は俺の本音だった。それも、とても表面的で、その言葉だけでは取り返せない、弱くて情けなくて、言い訳のような言葉だ。
「なんなんだよ……」
俺は乱暴にノートを閉じ、ペンをカバンの中に放り投げた。
感情的になるのは得意じゃないはずなのに、自分に嫌気がさすとこうも理性を失ってしまうのは驚きだ。
だからこそ理解した。
俺の心の中に残っているのは、“名前”じゃなくて、“後悔”だった。
あまりにも大きすぎる後悔が邪魔をして、肝心の名前を思い出せないのだ。
でも、逆に言えば、後悔がある限り、その名前を忘れることはないし、後悔を払拭しなければ、俺は一生このまま停滞し続ける。
「はぁぁ……」
俺がやるせなく座り込んでいると、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
今日も俺は本当の自分を取り戻せなかった。
糸の切れた人形のような、覚束ない足取りで教室へと戻るのだった。
教室に戻ると、誰かが俺を呼んだ。
振り向くと、そこには杉下がいた。クラスのリーダー格で、よく話しかけてくる。
「陽翔」
「なに?」
「お前さ、最近変わったよな」
「……そう?」
「なんか、目が違うっつーか。ちょっと大人っぽくなった?」
「そんなことないと思うけど」
言いながら、俺は自分の声がどこか他人事に思えた。
でも、確かに自分の中に、何かが変わりつつあるのは感じていた。
以前の俺ならここで自分を偽り取り繕っていただろう。
「まあ、大人っぽくなるならいいんじゃね? 俺たちはもう高2だしなぁ」
彼はそれだけ言っていなくなった。
何を伝えたかったのかはわからない。けど、俺は初めて俺らしく自然な会話ができたと思っていた。
周囲に迎合することなく、偽ることなく、本当の自分には程遠いがわずかな自然さを出すことができた。
無理な笑顔も、愛想の良い褒め言葉も、周りを気遣う献身的な姿勢も、今の会話には何一つとしてなかった。
冷たいと言われればそれまでだけど、本来の俺はそれほど明るい性格じゃない。見た目がそうであるように、中身も似たようなものだった。
こんな自分を出せたのも、未透の言葉が俺の中で生きているおかげだ。
言葉を渡されたことで、少しずつ自分を見つけている気がする。
教室の窓から、少しだけ青空がのぞいた。
その青は、どこかで見たような、懐かしい色だった。
◇◆◇◆
その夜、眠りにつくまでに何度も寝返りを打った。
部屋の明かりはとっくに消えていて、時計の秒針だけが一定のリズムで静けさを刻んでいた。
未透がいない日々にはもう慣れたはずだった。
でも、あの静けさだけは、いまだに慣れることができなかった。
布団の中、閉じたまぶたの裏に、いろんな風景が浮かんでは消えた。
裏庭、階段の踊り場、図書室の窓際。
そして——あの子の背中。
思い出そうとすると、いつも曖昧な霞がかかる。
でも、“いた”という確信だけは、ずっと心の奥に残っている。
名前も、顔も、今は思い出せない。
けれどその子が、俺のことをあだ名で呼んでいた記憶だけは、不意に胸に蘇るときがあった。
今では、誰もそう呼ばない。
その呼び名は、記憶の奥底で、ひっそりと沈んだままだった。
そう思った瞬間、まぶたが重くなった。
意識が深いところへ引き込まれていく——
——夢を、見た。
風が吹いていた。
柔らかくて、あたたかくて、でもどこか不安を煽るような、そんな風だった。
俺は中学校の裏庭に立っていた。
懐かしさが過ぎると同時に、そこが現実の場所とは違っていることに気がついた。
空は夕焼けに染まりながらも、紫が混ざっていて、どこか夢じみていた。
木々は高く伸びすぎていたし、足元には白い小さな花が咲き乱れていた。
その中心に、ひとりの少女が立っていた。
制服の肩が少しだけ透けて見えるほど、輪郭が淡い。
黒髪が風に揺れていた。
未透によく似ていたけれど、同時にまったく別の誰かのようにも思えた。
俺は一歩、近づいた。
呼びかけようとする。
「……」
でも、声が出なかった。
喉が凍りついたみたいに動かない。
代わりに、胸の奥に何かがせり上がってくる。
懐かしさと、悔いと、恐れ。すべてが混ざりあった、言葉にならない強い衝動。
少女が、こちらに振り向いた。
顔は白く飛んでいて、見えなかった。
目元だけが揺れていて、唇が震えていた。
『……はるくん』
その声は、確かに届いた。
夢なのに、妙に鮮明だった。
誰の声かはわからない。けれど、その呼び方には確かに覚えがあった。
次の瞬間、景色が変わる。
裏庭が教室へと塗り替えられていく。
使い古された色あせた机、何も書かれていない黒板。
曇った窓からは、静かな光が差していた。
ひとりの少女が、教室の隅に座っていた。
白いカーディガン。中学校の頃の夏の制服。
小さな背中を丸めて、机に頬を乗せていた。
身体が小刻みに震えていて、声はないのに泣いているのが分かった。
俺は、ゆっくりと歩み寄った。
今度こそ名前を呼ぼうと、喉に力を込めた。
しかし、それよりも先に少女がコチラを見て口を開く。
「……は」
今にも消え入りそうな声で。
「……る」
吹けば飛んでしまいそうな弱々しい声で。
だけど、その声は聞こえなくて、誰の声は分からなくて、それでもはっきりと俺の耳に届いていた。
「……くん」
そう呼び終えた少女は涙混じりに笑っていた。
そして、ノートを見せてきた。
——はるくん、わたしのために頑張ってくれて、どうもありがとう
同時に俺は理解した。
自分が“はるくん”と呼ばれていたことを、受け入れ始めていた。
次に声なき唇が、何かを言った。
『それでも、わたしを見ててくれた』
胸の奥が、静かに波打つ。
“俺は彼女のことを見ていた”。
たしかにあの時、俺は背を向けなかった。
何度も何度も何度も何度も何度も何度も、この目で彼女のことを見ていた。
しかし、それは、ただ何もできなかっただけだ。
声も、言葉も、名前も出せなかった。
それがずっと悔いとして残っていた。
見ているだけでは意味がない。それに気づきながらも、俺は見ていることしかできなかった。
やがてわ少女の輪郭が、淡く揺れ始める。
教室の光が強くなっていく。
そのなかで、彼女が最後にもう一度、言った。
『——またね』
はっと目を覚ますと、天井がぼやけていた。
心臓がまだドクドクと鳴っていて、指先に汗がにじんでいる。
喉の奥が、燃えるように熱い。ついさっきまでは凍りついたように声が出せなかったのに。
「……はぁはぁ……っ……」
俺は上体を起こして息を荒げた。
そして、胸の中にひとつだけ、確かなものが残っていることに気がついた。
それはとても大切なことで、今までずっと忘れていたこと。だけど、決して忘れてはいけなかったこと。
名前を思い出せなかった彼女のことを思い出すために、必要となる重要なピースだ。
——そうだ、俺は、“はるくん”と呼ばれていた。
俺はあの声を、確かに知っていた。
ノートを開いて、ペンを握る。
白紙のページに、震える手で言葉を綴る。
『思い出すから、待ってて』
それが、夢から覚めた俺が最初に綴った言葉だった。
◇◆◇◆◇
夢から目覚めた翌朝。世界の色はいつもより少しだけ淡く見えた。
窓から差す朝日も、食卓の味噌汁の湯気も、通学路の電柱も。
どこか“本当の世界”じゃないような、ふわふわと浮いた感覚がまとわりついていた。
学校に着いても、足取りは妙に重かった。
夢の中で呼ばれた「はるくん」の声が、耳の奥に残っていた。
誰にも聞かれなかったはずのその呼び名が、なぜか胸をざわつかせる。
教室に入っても、いつもの喧騒が遠く感じた。
声をかけてくるクラスメイトに微笑みを返しながらも、意識はどこか別の場所にあった。
昼休み。窓の外をぼんやりと見ていると、ふと一枚の景色が胸に蘇った。
——図書室。
あの子は、そこによくいた気がする。
朧げだけど覚えている。
細い身体を椅子に沈めて、一人で本を読んでいた。
教室よりも静かで、誰にも邪魔されない場所。
俺が教室で誰かと笑っていた間、彼女は一人、あの静かな空間にいた。
記憶の奥から、ひとつの光景がゆっくりと浮かび上がる。
——ある日、誰もいない図書室の奥で、机に突っ伏していた彼女。小さな背中には寂しさを思わせた。
前までの俺なら声をかけていた。二人で並んで本を読んで、楽しく笑って幸せを共有した。
だから、その時も俺はそっと近づいて、声をかけようとして……結局、できなかった。
代わりに、机の上にあった彼女のノートに、文字がにじんでいたのを見た。
涙で濡れたページだった。
俺は席を立ち、静かに図書室へと向かった。
理由なんてなかった。ただ、行かなくちゃいけない気がした。
図書室の扉を開けると、冷たい空気が肌に触れた。
本の匂いと、紙が静かに呼吸するような空気。
そこにいるだけで、少しだけ心が落ち着いていくのを感じた。
誰もいない。司書の先生すらいない昼休み。
窓際の長机に、何気なく腰を下ろす。
高校生になってから図書室には数えるくらいしか来ていない。
だから、窓際の長机に座ったのはなんとなくだった。
「え?」
そのときだった。
机の奥に、何かが差し込まれているのが見えた。
手を伸ばして引き出すと、それは一冊のノートだった。
表紙は少し色褪せていて、角が折れている。
どこにでもあるような、よく使い込まれたノート。
落とし物か、それとも忘れられたものか。
ふと、胸がざわついた。
ノートの表紙には、名前のシールが貼ってあった。
けれど、シールはほとんど剥がれていて、肝心の名前は読めなかった。
見るに新品ではなくて。それなりに古いノートのようだ。でも、埃は被っていないから、何年も放置されていたわけではなさそうだった。
俺は静かにページをめくった。普段なら落とし物として届けるか、知らないふりをしてそのままにするのに、なぜかそのノートだけは妙に気を引かれてしまった。
ゆっくりと中を確認すると、そこには小さな字で日記のような文章が綴られていた。
数ページ分、誰にも見せるつもりはなかったような、そんなわたし語で溢れていた。
『 また椅子を隠された。
わたしが座っただけで、みんなが離れる。
でも、もう慣れた。
平気なふり、上手になったから 』
胸が痛んだ。
他人事のように読めなかった。
ページをめくるたびに思い出す。
中学時代、あの子が教室の端で一人だったこと。
咳が止まらず、何日も休んでいたこと。
あるとき帰ってきたと思ったら、周囲の目が変わっていたこと。
「感染るんじゃないか?」
「仮病じゃないの?」
「そんなんで休むの?」
そんな声が、飛び交っていた。
最初は誰もが冗談のつもりで言っていた。しかし、ある時を境にそれが本気になった。
彼女は黙っていた。反論もせず、ただ教室の隅に座っていた。
『 本当にしんどいときは、声も出せない。
でもそれが“我慢強い”ってことになるのは
ちょっと違うと思う。
たぶん、わたしが話さないのは、
もう誰にも期待してないからなんだと思う 』
ページの文字が、かすれていた。
涙で濡れたような跡が、いくつもあった。深いシワが刻まれ、やるせない思いが伝わってくる。
『 好きな人ができた。彼は優しい。
わたしとおしゃべりして、笑ってくれる。
バカにしないで寄り添ってくれる。咳をしても怒らないでいてくれる。背中をさすってくれた。
けど、最近はあんまり名前を呼んでくれない。
わたしとも、話してくれなくなった。
でも、それで安心した。名前を呼ばれて、冷たい目で見られるよりはずっといいから 』
それを読んだ瞬間、喉の奥がきゅっと締まった。
俺は彼女の名前を呼ばなかった。
呼べなかった。見ていたくせに、声をかけられなかった。
まるで自分のことを言われているかのようだった。
『 ひとつだけ嬉しかったことがある。
彼と廊下ですれ違ったとき、“目が合った”あの瞬間。
……わたしだけかもしれないけど
こっちを見てくれた気がした。
それだけで今日は生きててよかったって思えた。
勝手な思い込みかもしれないけど
それでもいい 』
最後のページに、そう記されていた。
誰の名前も書かれていない。
でも、その瞬間の記憶は、俺の中に確かにあった。
あの時、帰りの廊下で、彼女と目が合った。
何か言おうとして、何も言えなかった。
——あれは、俺だったんだ。
夢の中で聞いた「はるくん」という声。
その響きが、ここにつながっていた。
ノートを閉じて、胸に抱えた。
このノートの主が誰なのか、確証はない。
けれど、不思議なほどに、その文字たちは未透の言葉に似ていた。
どことなく似ているような気がした。
——いや、それは願望かもしれない。
でも、もしそうだとしたら。
未透は、俺が名前を呼ばなかった“あの子”なのだとしたら——
今、もう一度会えたことには、きっと意味がある。
俺はそっと目を閉じた。
未透が、もし彼女だとしても。
そうでなかったとしても。
どこかで“名を呼ばれなかった誰か”が、まだこの世界に残っているのなら。
今度こそ、俺は——の名前を呼ぶ。
その名前がなんであれ、声が届くかぎり。
そして、俺の名前が“はるくん”であることも、胸を張って認められるように。