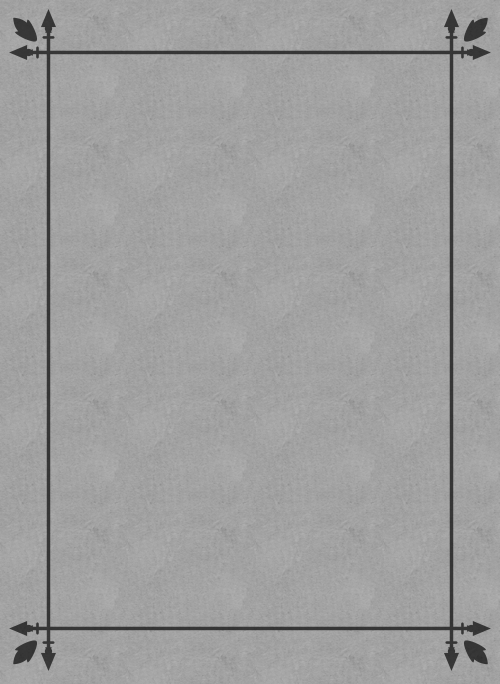名前を聞いた。それだけのことだった。
たったそれだけのはずなのに、心がじわりと濡れていた。
未透。
未完成の“未”に、透明の“透”。
そう名乗ったあの子の声が、今でも耳の奥に残っている。
あのときの会話を、何度も思い返していた。
問いかけの言葉。静かなまなざし。落ち葉を踏む音。
ひとつひとつは些細なのに、どれも消えずに胸の中で色を持って残っていた。
彼女が消えてから、しばらく中庭に立ち尽くしていた。
風が吹いて、葉が揺れて、遠くでチャイムが鳴った。
それだけの世界の中で、俺はしばらく“陽翔”でいることを忘れていた。
その日、家に帰っても何も手につかなかった。
夕飯の味が薄く感じたのは、たぶん気のせいじゃない。
ベッドに寝転びながら、天井を見上げていた。
思い出そうとすればするほど、かえって記憶は曖昧になる。
でも、確かに揺れた。
あの瞬間、自分の中で何かが軋んだ感覚があった。
止まったままの時間が、ほんの少しだけ――動いた気がした。
次の日の朝は、やけに光が強くて、目がすぐに覚めた。
窓の外の空は晴れていて、雲一つない。
でも、昨日までの空とは違って見えた。
制服に袖を通しながら、ふと鏡の中の自分と目が合った。
無意識に“無難な顔”を作っていた自分に気づいて、なんとなくため息が出た。
学校の空気は変わらない。
昇降口で誰かが手を振って、廊下で友達が冗談を言い合って、教室はいつも通り騒がしい。
その中に、俺も混ざっていた。何事もなかったように。
「おはよー、陽翔。昨日のプリント見せてくんね?」
「ああ、うん。これ」
「サンキュー! 助かるわ~」
笑いながらプリントを渡す。
いつものやり取り。何も変わらない。
でも、心のどこかがちょっとだけ冷めていた。
昨日の未透との会話が、こうした“無難な日常”を急に薄く感じさせた。
授業と最中、ふと窓の外を見る。
何を見てるのか、何を見たいのか、それは自分でもわからなかった。
でも、あの黒髪の少女のことを思い出していた。
未透。
まだ、二度しか話していない。
でも、他の誰よりも深く俺の心を揺らしてきた。
“君も、何かを探してるよね?”
あのとき言われた言葉が、頭から離れない。
わかってるはずなのにわからない。
俺は何を探してるんだろう。
見つけたくて、でも見たくなくて。
きっとそれは、“あのとき”の記憶に繋がっている。
昼休み。
弁当を開きながらも、箸が進まない。
「陽翔、今日テンション低くね?」
「え、そう?」
「いや、なんかさ。疲れてる?」
「ああ……ちょっと寝不足で」
適当に笑ってごまかす。
けれど、笑ってる自分に違和感を覚える。
未透が言っていた言葉が、胸に残っていた。
――言えなかったことがある人って、自分でも気づいてないことが多い。
気づいてない? 俺が?
違う。俺は気づいてる。
ただ、言いたくないだけだ。言ってしまえば、もう戻れなくなるから。
あのとき――声をかけられなかった。
背中が遠ざかっていくのを見ながら、喉の奥で言葉を呑み込んだ。
本当は、呼びたかった名前があった。かけたい言葉があった。伝えたい話があった。
でも、出せなかった。
出したくなかった。
その選択をしたのは、他でもない、自分だった。
そんなことは誰にも言っていない。誰にも話せなかった。
だから、俺はこんなふうに無難な毎日を過ごしてきた。
波風を立てずに。
誰の心にも触れずに。
俺自身も、誰にも触れられないように。
誰かを傷つけないためには、誰とも深く関わらないのが最善だと思った。
……でも、未透は違った。
彼女の目は、俺を“見て”いた。
ただそこにいる誰か、じゃなくて、“俺”という人間を。
そう思ってしまった時点で、もう何もかもが変わり始めていたのかもしれない。
昼休みが終わる直前、ふと思い立って教室を出た。
人気のない廊下を抜けて、階段を降りる。
どこへ行くというわけでもない。
でも、気づけば足は自然とあの日の中庭へ向かっていた。
そこに、彼女の姿はなかった。
風が吹いて、木々がさやさやと揺れる音だけが響く。
誰もいない場所。なのに、少しだけ温かい空気が残っていた。
俺はベンチに腰を下ろして、ポケットからスマホを取り出す。
ホーム画面に通知が溜まっていた。返事をする気にはなれなかった。
誰と話したって、表面を撫でるだけの言葉しか出てこない。
本当のことなんて、誰にも言えない。
でも。
――もし、未透になら。
ふと、そんなことを考えていた。
名前を呼びたかった誰か。
言えなかった言葉。
そのすべてを、彼女になら話してもいいのかもしれない――そう思っている自分に、俺は少しだけ驚いた。
秋の風が吹いた。
落ち葉が一枚、膝の上に落ちてくる。
その小さな揺れが、胸の奥に静かに染みていく。
俺はまだ、誰のことも呼べていない。
でも、いつか――
そのとき、背後で誰かの足音がした。
◇◆◇◆
――足音がした。
ゆっくりと、地面を踏みしめるような音だった。
俺は肩をすくめそうになりながら、そっと後ろを振り返った。
そこにいたのは、やっぱり未透だった。
風に揺れる黒髪。白い肌。
まるで季節の空気ごと溶け込んでいるような気配で、彼女はそこに立っていた。
「やっぱり……いたんだね」
そう言ったのは、どちらだったか分からない。
たぶん、俺だったと思う。けれど、未透の口元も同時に動いた気がした。
彼女は何も言わず、俺の隣に腰を下ろした。
ベンチがわずかに沈む。落ち葉が一枚、彼女の膝に舞い落ちる。
少しの間、沈黙があった。
でも、それは苦痛ではなかった。
むしろ心地よい静けさだった。
「今日も、何か見えた?」
俺は問いかけた。自分の声がやけに穏やかだったのが、自分でも不思議だった。
「ううん。今日は見えてない」
「そっか。じゃあ、ここに来たのはなんで?」
「……君が来そうな気がしたから」
その言葉に、少しだけ息を呑んだ。
偶然なんて、なかったのかもしれない。
でも、必然と言えるほどの理由もなかった。
ただ、不思議な一致。それだけで十分だった。
「わたしね、あんまり学校に来てないんだ」
未透は空を見上げながらぽつりとそう言った。唐突だった。
「体、弱いの?」
聞いていいのか迷った。でも、聞かずにはいられなかった。
「……うん。昔からずっと」
あっさりとした答えに、逆に胸がざわついた。
悲観的な様子はなく、ただ当然かのように冷静な面持ちだった。
「入退院を繰り返してる。だから、授業もほとんど出てない。高校に入ってからは、2日連続で学校に来たのも今日が初めて。みんなにはあんまり知られてないんじゃないかな。陽翔くんも知らなかったでしょ?」
なるほど、とだけ俺は言った。
それ以上、何も言葉が出てこなかった。
だから、今まで見たことがなかったのか。
高校生活の記憶を辿ってみても、彼女はどこの学年のどこのクラスにもいなかった。
いないのが当たり前だったから、気づかなかった。
「ここは静かでいいよね。わたしは読書が好きだから、ここなら落ち着いて読めるしね」
未透はそう言って、足元の落ち葉を軽くつまんだ。
「にぎやかなところも嫌いじゃないけど、長くいるとしんどくなっちゃうから」
「わかるかも。俺も、あんまり人混みとか得意じゃないし」
「うん。陽翔くんは……そんな感じ。誰かといるとき、少し肩に力が入ってる。無意識なんだろうけど」
ふと、未透の声がやわらかく響いた。
その目が、まっすぐに俺を見ていた。
「学校で俺を見かけたことあるの?」
「あるよ。色んな人に頼られてる。誰からも好かれて、誰からも嫌われてなくて、すごいと思う」
未透の言葉に嫌味なんてなかった。
でも、そう演じている俺からすれば心が少し痛くなった。
「……未透さんからしたら、俺は胡散臭く見えるでしょ」
「ううん。人間関係の構築が上手だなって思うよ。でも、無理してる」
「やっぱ、そう見える?」
「他の人は気づいてないと思うけど、わたしは分かるよ」
未透が断言したのがおかしくて、俺は少しだけ笑ってうつむいた。
誰にも気づかれないようにしてきたのに。
この子には、簡単に見透かされてしまう。
「言葉って、重たいよね」
未透がぽつりと言った。それも唐突に。
「うまく言えないときもあるし、言ったことで壊れちゃうこともある。でも、言わないままにしてると、それもまた、ちょっとずつ自分を削っていくような気がして」
「……未透さんは、相手に言わなくちゃいけないことを言わなかったことがあるの?」
「あるよ。だから、“見える”んだよ」
未透はそう言って、手のひらを開いた。
その手のひらの上で、ひとひらの落ち葉が揺れていた。
彼女は一つ息を吐くと、静かに口を開く。
「昔ね、大切だった子がいて。その子のことを、ちゃんと好きだって言えなかった」
「……」
「気づいたら、その子は遠くに行っちゃってて。もう戻らなかった。違うか、わたしが遠くに追いやられたのかもしれない。だから、伝えられなかった言葉が、ずっと胸の中に残ってる。消えてくれないの。忘れられないの。その子に言いたかった言葉が、何年経っても残り続けてる」
俺は何も言えなかった。
その話が、どこか自分自身のことのように思えてしまったから。
言えなかった言葉。
呼べなかった名前。
何度も、何度も、思い出しては胸の中に沈めた記憶。時間が経とうと時折り夢に見るほど、あの時のか記憶は胸にこびりついて拭えなかった。
それが今、未透の言葉によって表層に浮かびかけていた。
「君にも、そういう誰かがいる?」
「……」
俺はわずかに首を縦に振った。
「名前は言える?」
「……言えない。まだ」
言えない、というよりも、思い出せない、わからない……という表現のほうが正しいのかもしれない。
心の奥底に封じ込められたあの時の記憶はそう簡単に想起することができなかった。
「うん。それでいい。言えるときが来たらでいい」
未透はそれ以上、何も聞かなかった。
ただ、優しい声色でそう言って、隣にいてくれた。
それだけで、少しだけ心が軽くなった気がした。
「ありがとう……」
「いいんだよ」
「……なんで未透さんは、俺に寄り添ってくれるの?」
「悩んでそうだったから」
迷いのない簡単な答えだった。
「それだけ?」
「うん。わたしね、言葉って……すごいなって思ってるんだ」
未透はその言葉を皮切りに、ぽつぽつと語り始めた。
「陽翔くんも誰かの何気ない一言に救われたり、逆に傷ついたりするでしょ? 目に見えないのに、人の心を動かす力がある。それって、ちょっと魔法みたいだと思わない?」
未透は空を見上げながら微笑む。
その顔はどこか遠くを見ているようだった。
「わたし、そういう言葉を大切にしたくて……“ことばノート”をつけてるんだ」
「ことばノート……?」
思わず聞き返したその瞬間、
俺の胸の奥が、かすかにざわめいた。
“ことばノート”
それはどこかで聞いたことがある気がした。
でも、思い出そうとしても、指の隙間から零れ落ちるように掴めない。
頭のどこかがぼんやりとして、胸の奥がじんわりと熱を帯びるような感覚。
「それ……どういうの?」
俺がそう聞くと、未透は嬉しそうにうなずいた。
「たとえば、人からもらった優しい言葉とか、自分が感じたこと、ふと浮かんだ一文とか……何でも書いてるの。わたしにとっては、小さな宝箱みたいなものなんだ」
「宝箱……か」
俺はその響きに、自然と惹かれていた。
「そう、宝箱。言葉はお宝なんだよ。全員が口にできるけど、全員違うものを自由に使えるの」
「なんか、いいね。自分だけの“宝箱”って」
「ふふ。陽翔くんも持ってみたら?」
「俺に……書けるかな」
「きっと書けるよ。だって、君の中にも、ちゃんと届いてない言葉があるでしょ?」
未透は俺の目を見て言った。
そのまなざしには嘘がなくて、でもどこか不安げで、それでも信じようとしてくれているような、そんな目だった。
胸の奥が、また静かに揺れる。
“ことばノート”。
なぜか妙に耳に残るその響きが、
これからの何かを導いてくれる気がしていた。
それから俺たちはしばらくの間、言葉を交わさず、空を見上げていた。
夕陽がゆっくりと傾いて、空にオレンジ色のグラデーションが広がっていく。
ふと、未透が立ち上がった。
「そろそろ行かないと、また会えるといいね」
彼女はそう言って、笑った。
その笑顔は、どこか透けて見えるような、不思議な透明さがあった。
「うん。また、ここで」
俺がそう返すと、未透は軽く手を振って歩き出した。
その背中を、俺はしばらく見つめていた。
――言えなかった言葉。
もしも、誰かに渡せるなら。伝えられるなら、
未透に話すことで、それが少しずつ形になる気がしていた。
でも、俺はまだ、名前を呼べていない。
だから、まだ立ち止まったままだ。
だけど今は、それでも少しだけ、前に進めるような気がしていた。
◇◆◇◆◇
次の日の朝、教室に入った瞬間、今日も変わらずざわめきが耳に飛び込んできた。
誰かが笑っていて、誰かがスマホを見せ合っていて、誰かが机に突っ伏していた。
いつもと変わらない、見慣れた光景――のはずだった。
でも、そのはずの景色が、今日は妙に“ぼやけて”見えた。
「おはよ、陽翔~」
「昨日のノート、見せてくれたら神」
「今日小テストっしょ? マジ死ぬわ」
いくつかの声が飛び交う。俺は、それにいつも通り笑って応じる。
「あー。うん、いいよ。はい、これ」
「マジ助かる!」
差し出す手。返ってくる笑顔。軽く交わす言葉。
それは“ちゃんとした会話”のように見えた。
ただ、俺の中ではどこか空洞が鳴っていた。
――普段の俺なら、もっと冗談混じりに軽口を叩いて、空気に馴染ませていた。
でも、今日はそれができなかった。
言葉の端が、少しだけ遅れて口を出る。
笑顔も、どこか作り物みたいに感じられた。
自分がやっていることに対して、自分の手応えがない。
まるで、体だけが動いているみたいだった。
それはいつもそうだったはずなのに、最近はそれが如実に感じられた。自分なのに自分じゃない、ふわふわとした感覚が常に残り続けている。
授業中。ノートを取る手が止まりそうになる。
黒板の文字が目に入っているはずなのに、意味が通らない。
前の席の子が消しゴムを落として拾う仕草すら、スローモーションみたいに見える。
“何かが違う”。
その正体が、自分の中にあることだけはわかっていた。
未透と話したことで、俺は確かに何かに触れてしまった。
言葉にできない“ひび”のようなものが、自分の内側に走っている。
これまでなら、ここにいる自分に何の違和感も覚えなかったのに。
今日は、まるで“借り物の姿”で教室に座っているような気分だった。
いつもなら気にしない誰かの声が、遠くに聞こえる。
冗談も、笑い声も、雑音のように耳をすり抜けていった。
俺は今、何をしてるんだろう。
誰の中に、どんな顔で混ざってるんだろう。
そんなことを考えてしまう自分に、また小さな違和感が重なる。
昼休み。
パンを買いに行く流れに乗らず、俺は一人で教室に残った。
窓の外を見ながら、昨日のことを思い出す。
未透の言葉が、風の音に重なって蘇る。
――名前、言える?
――それでいい。言えるときが来たらでいい。
あのときの彼女の声は、驚くほどまっすぐだった。
どこにも無理がなくて、押しつけがましさもなかった。
ただ、受け入れてくれる空気だけがあった。
俺の全てを受容し、理解し、待ってくれる。
まるで当事者のような口ぶりだった。
思考に耽っていると、ふと教室の入り口の方から声が聞こえた。
誰かが、俺の名前を呼んだ気がした。
でも、気のせいかもしれない。
返事をする気にはならなかった。
次に舌打ちが聞こえた。それでも俺は一瞥すらしなかった。
どうしてかはわからない。もしかしたら、いつもの演じた姿を見せるのが嫌になり始めたのかもしれない。
やがて昼休みが終わると、授業が再開される。
板書を写しながらも、頭の中はまったく別のことで埋まっていた。
――未透は、今日来ているんだろうか。
どのクラスかは知らない。聞けていない。なぜか聞くのが憚られた気がしたから。
かと言って、名簿を確認するほどの勇気はない。
けれど、校舎のどこかにいるような気がしていた。
いや、もしかしたら今日は来ていないのかもしれない。2日連続で登校するのが初めてだと言っていたし。
そう考えたとき、不思議な喪失感が胸の奥に広がった。
今までは何とも思っていなかった“特定の人物の不在”が、今日に限って、やけに重たく感じられた。
どうしてだろう。
ふと、心がざわめく。
呼びたかった名前。
それを思い出しかけるたびに、胸が苦しくなる。
俺は、誰を、呼びたかった?
誰に、何を、言えなかった?
その問いの答えは、まだ言葉にはならない。
放課後。
俺は迷うことなく中庭に足を運んでいた。
夕陽が差し込む静かな場所。
昨日と同じ風が吹いていた。
でも、ベンチの上には誰の姿もなかった。
俺はそこに座って、しばらく何もせずに空を見ていた。
未透はいなかった。
だけど、彼女の言葉が、そこに残っている気がした。
「……言えるときが来たら、でいい」
俺は、その言葉を心の中で繰り返す。
まだ、何も言えない。
でも、きっと――そのときは来る。
来ると信じていい気がしていた。
空の色が、少しずつ深くなっていく。
風が、落ち葉をひとひら巻き上げた。
帰り道。
自転車を押しながら、ふと足が止まる。
校舎の窓を見上げた。
まだ明かりがついている教室があった。
そのどれかに、未透がいたかもしれない。
あるいは、どこにもいなかったのかもしれない。
でも、もう一度会える気がした。
それは根拠のない、確かな予感だった。
胸の奥にある名前。
それが、ゆっくりと輪郭を取り戻し始めている。
あの放課後。
声をかけられなかった、あの背中。
あのとき言えなかった言葉が、確かにまだ、ここにある。
そしてそれを、きっと誰かに渡せる日が来る。
未透は、たぶん――そのきっかけになる人だ。
俺はもう一度、空を見上げた。
そこには、昨日と同じ夕焼けが広がっていた。
でも、昨日とまったく同じではなかった。
少しだけ色が濃く見えた。
少しだけ胸があたたかかった。
それだけで、今日は十分だった。
◇◆◇◆
ある日の放課後。
俺は屋上へと続く階段を登っていた。
教室からも昇降口からも遠い、ほとんど使われなくなった北館の奥。
もちろん屋上の扉は施錠されていて、生徒は立ち入り禁止になっている。
でも、俺はよくこの踊り場に来る。
誰も来ないから。音がないから。
階段に座っていると、自分だけ世界から切り離されたような感覚になる。
今日も同じように、ひとりになりたくてここに来た――はずだった。
しかし、先に誰かがいた。
廊下の光が漏れる位置に、制服の影があった。
壁に背を預けて、じっと上を見ている。
その横顔を見た瞬間、胸が少しだけ熱くなった。
「……未透、さん?」
俺が名前を呟くと、彼女はゆっくりと顔をこちらに向けて、ふわりと笑った。
「やっぱり、来たね」
「どうしてここに?」
「静かだから。わたしもたまに来るの。たまにって言ってもあんまり学校に来てないから知れてるけど……陽翔くんもこういうところが好きだよね」
「まあ、そうだけど……よくわかったね」
俺は彼女の隣に腰を下ろした。
この狭い踊り場には、たった二人分の空間しかなかった。
少し身体が近くて、それだけで言葉を選んでしまう。
階段のコンクリートが、少しひんやりとしていた。
「久しぶりだね」
未透が言った。小さく三角にたたまれた足はびっくりするくらい華奢だった。
「1週間ぶりかな」
「うん。実は新しいお薬を使い始めたせいで、眠気が酷くてなかなか学校に来れなかったんだよね」
「そうなんだ。体、今は平気なの?」
「平気。陽翔くんと話せるから」
未透の言葉の真意はわからなかったけど、俺はどことなく嬉しくなって微笑んでいた。
「笑えたね」
「え」
「いつもと違う、本当の笑顔だよね、それ」
俺の顔を覗き込んでくる未透は嬉しそうに口角を上げていた。
「……そうかもね」
「普段からそうすればいいのにってわたしが言うのは勝手かな」
「勝手じゃないけど……本当の自分を出すのが怖いんだ」
俺は未透になら話してもいいかなと思えていた。
本当は誰にも明かさずにいるつもりだったあの時を後悔を。
「……この前、話したよね? 俺の、後悔」
俺はおもむろに言葉を紡いだ。
「うん」
「もう少し、ちゃんと話してもいい? 前は未透さんが話してくれたから、俺のも聞いてほしい」
未透は、何も言わずに小さく頷いた。
それだけで、俺は続きを話そうと思えた。
「――中学のとき。仲のいい友達がいた……いや、友達って言っていいのかもわからないくらい、最後は距離があったかもしれない」
「……」
「俺は、その子の隣にいるのが好きだった。話すのが楽しくて、他の誰よりも自然にいられた。でも、あるときから、ちょっとずつ何かが変わっていったんだ」
言葉を選ぶように、ゆっくりと話す。
「その子は……学校に来る日が少なくなって、俺は怖かったんだ。何もかも変わってしまったことに気づいてるのに、知らないふりをしてた。“どうしたの?”のひと言が、全部を壊してしまいそうで……怖かった」
ただ話をしているだけなのに、異様なほど口の中が乾いていた。
「だから、黙ってた。何も言わなかった。俺は言葉を飲み込んで、笑って、その子が来ない日も平気な顔をしてた。本当は、すごく怖かったのに……何かを失っていく音が、崩れていく音が、毎日、心のどこかで鳴ってたのに」
そのときの自分を思い出すと、息が詰まるような感覚になる。
「そしたら、ある日、その子は突然来なくなった……教室から姿が消えて、連絡も取れなくなって、それっきり」
未透は目を伏せたまま、黙って聞いている。
俺は少しずつ声が震えていくのを止められなかった。
「あとから聞いた話だけど……その子、色んなことがあったらしいんだ。家のこと、心のこと。体のこと。俺が知らないふりをしている“日常”の裏で、ずっと戦っていたんだ。なのに、俺はなにもできなかった。やろうとすらしなかった。本当は……その子に起きた異変に気づいてたのに、目を背けて知らないふりをしていたんだ」
喉の奥が熱くなる。
「名前を呼べなかったんだ。そうなってから最後まで一度も。声をかけたかったのに、名前すら出せなかった。名前を呼んだら、全部が壊れてしまいそうで。俺は手を差し伸べる勇気がなかった。でも今は、名前を呼ばなかったことを、言葉をかけなかったことを、助けてあげられなかったことを、すごく悔やんでる。どうしようもないくらい……悔やんでる」
思い出の中のその子は、いつも背を向けている。
ふと振り返るかもしれない瞬間に、俺はいつも声を飲み込んでいた。
その場面が、何度も夢に出てくる。
夢の中でも、俺は声が出せないままだ。
「未透さん。俺、怖いんだ」
その声は、ようやく自分の本音だった。
「もう一度、誰かの名前を呼ぼうとして、また逃げ出す自分がいる気がして。言いたいことがあるのに、言葉が喉で止まる……そんなの、もう繰り返したくないんだよ」
膝の上に置いた拳には無意識に力が入っていた。
すると、未透はそっと、俺の手の甲に自分の手を重ねた。
その手はあたたかかった。けど、すこしだけ震えていた。
俺の言葉と同じように。
そして、その表情は険しく暗かった。
「陽翔くん……その想いは、ちゃんと届かなかっただけで、まだどこかに残ってるよ。呼べなかった名前は消えてなんかいない。かけられなかった言葉も一緒だよ。きっと、その子は待ってる。君がもう一度、向き合うのを」
言葉が、胸の奥に染みていく。
優しいのに、強い響きだった。
俺は、顔を伏せた。
何も言えなかった。
ただ、伝えなければいけない言葉があった。
「ありがとう」
「ううん。いいんだよ。こっちこそ悩みを打ち明けてくれてありがとう」
笑みを交わして柔らかな空気になると、心地よい沈黙が訪れた。
それは10秒くらいか。そんな沈黙を破って、未透が小さく息を吐いた。
「ねぇ、陽翔くん。少し、付き合ってくれる?」
顔を上げると、未透はゆっくりと立ち上がっていた。
彼女の瞳は揺らぎなく、どこか決意に満ちていた。
「行きたい場所があるの。ほんの少しだけでいいから」
「うん」
俺も静かに立ち上がった。
未透の手は、また軽く俺の袖を引いて、北館の薄暗い階段を下りていく。
連れて行かれたのは、校舎の裏手。
体育館の裏にある小さな植え込みだった。
風も光もほとんど届かないその場所は、草の香りと、ひんやりとした湿度に包まれていた。
こんな場所があったんだ。というのが最初の感想だった。通り過ぎたことはあったけれど、こうして足を運んだのは初めてだった。
未透は植え込みの中の、ほんの少し空いた場所に立ち止まった。
草の合間に、小さな石碑のようなものが置かれているのが見えた。
「……ここ、知ってた?」
「知ってはいたけど、初めて来たかも」
「たぶん、ほとんどの人は通り過ぎちゃうと思う。気づかないし、気づいても気にしない。誰にも手入れされず、ずっと放置されてる場所だと思うんだ」
未透はしゃがみ込み、小さな石の前に指をそっと伸ばした。
風が、ざわりと草を揺らす。
すると、ふいに耳鳴りのような感覚がして、遠くで“何か”の声が聞こえた気がした。
——ありがとう。
それは幻聴だったのかもしれない。
でも、確かに、何かが通り抜けた感覚があった。
どこからともなく、音の出所はわからない。
ただ、確実に聞こえた。
「今……何か、聞こえたような」
「それは誰かの想いだよ」
「“想い”?」
未透は草の先を見つめたまま、小さく頷いた。
「言葉にできなかった気持ち、伝えられなかった感謝、後悔、祈り。そういうのが、ふとした拍子に何かに宿ることがあるの。わたしは、それが“見える”というか、“感じられる”だけ」
「……幽霊が見えるってこと?」
未透は笑った。
でもその笑顔は、いつもの冗談まじりのものではなかった。
「そういうのとはちょっと違うかな。幽霊みたいに形がないから、それが“誰か”かどうかも分からない。ただ……残った気配みたいなものが、ふっとわたしに触れるの」
「さっきの……“ありがとう”も?」
俺が首を傾げると、未透は少しだけ目を細めて静かに頷いた。
「うん。ずっとここにあった“声”なんだと思う」
俺は改めて足元の小さな石碑を見る。
その傍らには、割れかけた素焼きの鉢植えがひとつ、草に埋もれるようにして置かれていた。
中には、半分枯れかけた、でもどこか力強く根を張った小さな植物が生えていた。
白くて細い花が、一輪だけ咲いていた。
「これは誰かが置いたの?」
「たぶん、何年も前のものじゃないかな」
未透は、そっとその鉢に手を触れる。
触れた瞬間、風がひとつ、やさしく草を揺らした。
「わたし、最初にこの場所を見つけたとき、ここに鉢があるのを見てね、何でこんな場所に、って思ったの。でも、そのときすぐ“言葉”が聞こえた。ありがとうって、すごく優しい声で」
「誰の声なのかはわからない?」
「そう、わからない。名前も顔もない、ただの想い」
未透は、膝をついて鉢植えを見つめた。
「ここに何かを植えた誰かがいたんだと思う。誰にも言えないまま、そっとこの場所に……誰かのために、願いを込めて」
「誰かの……ため?」
「うん。きっと大切だった誰かが辛い思いをしていて、どうしても直接は言えなくて、それでも何か残したかった。言葉じゃ届かないなら、形にして残そうって……。そんな想いが、この小さな鉢に込められてたんだと思う」
俺は言葉を失ったまま、白い花を見つめた。
それは、かすかに風に揺れていた。
まるで、誰かがその“想い”を、今も見届けてくれているように。
「それで、どうして“ありがとう”だったの?」
ふと、素朴な疑問が口をついて出た。
未透は一瞬だけ目を伏せ、やがてぽつりと答えた。
「さっきの声はね、きっと……想いを残した“誰か”の声じゃなくて、それを受け取った“誰か”の声なんだと思う」
「……え?」
「言葉は伝わらないといけないってこと。意味がないとは言わないけど……やっぱり、伝えたいことはきちんと相手に伝えないと、それが後悔につながってお互い嫌な思いしちゃうと思わない?」
そう言いながら、未透はそっと花に触れる。
まるで撫でるように優しく。
「じゃあ、ここにこの花を植えた誰かの無念とか後悔は、伝えたい人にきちんと届いたってことだよね」
「そう。言葉って、声に出さなくても、どこかに届くんだよ。時間がかかっても、伝えようとした気持ちはちゃんと残る」
俺はその花を見つめながら、ふと思った。
俺の中にも、まだ届けられていない言葉がある。
誰にも渡せなかった言葉、呼べなかった名前。
それはまだ、どこかに置き去りのままだ。
「……未透さん」
「なに?」
「君のその力って……“見える”というより、“感じる”ってイメージなんだよね」
「音じゃないし、色でもないから、空気の中にある“心の跡”みたいなものかな?」
小さく首を傾げると綺麗な黒髪が揺れた。それは本人にもよく分からない感覚らしい。
「俺にも、わかるかな。そういうの」
「わかるよ。だってこの鉢植えを見たとき、確かに聞こえたんだもんね?」
未透はそっと笑うと、言葉を続けた。
「……陽翔くんの中にも、言えなかった言葉があるでしょ? それがある限り、人の気持ちに気づけるんだと思う」
俺は、小さく息を吐いた。
ありがとう。
あの言葉が、誰かの胸の奥で紡がれた一瞬の光だったとして。
それを拾える彼女のように、俺もなりたいと思った。
そして——
俺の中に眠る、まだ呼べていない名前にも。
いつか、きちんと“ありがとう”を伝えられるように。
「……不思議だね」
「不思議でいいんだよ。そこの理屈はどうでもいいの。ただ、誰かの“想い”がちゃんと残ってるんだって、わたしは信じてるから」
未透は立ち上がると、風に揺れる前髪を押さえながら、俺を見つめた。
「陽翔くんの言葉もね……届くよ。きっと、その子に」
その目は、どこか遠い記憶を見つめるようだった。
俺はうまく返せず、ただ頷いた。
二人でいる時間は心地よかった。会って数回の異性が相手とはとても思えないほどに。
だから、俺たちは何も言わずにしばらく草の上に座っていた。
風が枝を揺らし、鳥の声が遠くに響いた。
未透の持つ変わった力は説明できないけれど、どこか現実味があった。俺自身も声が聞こえたし、たぶん本当なんだと思う。
そして俺は、彼女の“言葉”が、誰よりも深く、誰よりも遠くに届くものなんだと、少しずつ理解し始めていた。
たった一言で、誰かを救える力。
それが、未透の中にあって。
今、俺にも、その意味がほんの少しだけ分かった気がした。
もう一度名前を呼ぶために——
今度こそ、言葉を届けるために。
この出会いは、偶然なんかじゃない。
◇◆◇◆
最初は、たまたま休みかと思った。
体調の波があるとは聞いていたし、あまり通学していないとも言っていた。
けれど、2日目、3日目……1週間、2週間が過ぎても、彼女の姿はどこにもなかった。
あれから毎日のように、屋上へ続く階段に足を運んだ。
中庭にも、中庭にも、校舎の端のベンチにも、そっと目をやってみた。
全てのクラスを見て回ったりもしたけど、未透はいなかった。
まるで、風のように、ふっといなくなってしまったようだった。
“またね?”
体育館裏から離れるとき、未透はそう言って微笑んだ。
その言葉だけが、耳に焼きついて離れなかった。
俺の心には靄がかかっていたが、周囲の様子はいつも通りだった。
テスト前の話題、文化祭の準備、週末の予定。
みんなの言葉が交差するなかで、俺だけが置いていかれていた。
いつもなら、笑って相づちを打っていた会話が、今日はただの雑音にしか聞こえなかった。
そんな折、ふと、誰かに話しかけられる。
「陽翔、今日も屋上のとこ行ってた?」
「……え? ああ、ちょっとだけ」
「なんかあんの? あそこ、閉まってんじゃん」
「別に、なんでもないよ」
「ふーん。お前、最近変だぜ? 昨日も中庭で座り込んでたろ? その前は一人で色んなところ歩き回ってたしよ」
「そう、かな……気のせいだよ」
俺は何でもないような顔をして言う。
でも、胸の奥では何かが暴れていた。
未透のことを、誰にも話せなかった。
どこのクラスかも、連絡先も、何も知らない。
試しに先生に尋ねてみても、
「みとう、さん?」
「俺と同じ2年生の女の子で、体が弱いと聞いていたんですが……」
「あー、あの子ね。あなたの言う通り、ちょっと体が弱いみたいなのよ。ごめんなさい。それ以上のことは……ね? 本人の事情もあるし話せないのよ」
当たり障りのない言葉を返されるだけだった。
まるで眼中にないのか、名前すらまともに把握していない始末だった。
それが、いちばん胸に刺さった。
誰にも知られていない子のことを、俺だけがこんなに探している。
先生たちも心配そうにはしていない。
彼女の話題がクラスメイトから上がることもない。
それが、なんだか滑稽に思えて、でもやめられなくて。
あの細い声と、笑ったときの目元と、落ち葉をつまんだ指先が、ずっと心に居座っていた。
彼女の全てが何度も頭の中を巡る。
でも答えは出ない。誰にも、出せない。
だから俺は、未透の言葉を思い返していた。
「言葉って、重たいよね」
「でも、言わないままにしてると、それもまた、ちょっとずつ自分を削っていく」
気づけば、俺の手は机の上で鉛筆を握っていた。
ノートの片隅に、何かを書こうとして……でも、何一つとして言葉にできず手は止まっていた。
伝えられなかった言葉。
呼べなかった名前。
それを、今度は絶対に逃さずにいたいと思った。
未透がいたから。
彼女が、俺の“止まった時間”に、手を差し伸べてくれたから。
誰かにとっては、一生徒の不在かもしれない。
でも俺にとっては、あの時間が確かにあった。未透がいたから変われる気がした。
彼女が俺に言葉を渡してくれたから、寄り添ってくれたから、心の中が晴れやかになって前向きになれた。
だから今度は、自分の足で歩いてみる。
もう一度、誰かに言葉を届けられる自分になるために。
教室の窓から見える空は、分厚い雲に覆われていた。
でも、その向こうにある青さを、俺は少しだけ信じられる気がしていた。
それだけでいい。
まだ、名前は呼べていないけれど――
きっと、前より少しだけ、俺は“自分”に近づいている。
たったそれだけのはずなのに、心がじわりと濡れていた。
未透。
未完成の“未”に、透明の“透”。
そう名乗ったあの子の声が、今でも耳の奥に残っている。
あのときの会話を、何度も思い返していた。
問いかけの言葉。静かなまなざし。落ち葉を踏む音。
ひとつひとつは些細なのに、どれも消えずに胸の中で色を持って残っていた。
彼女が消えてから、しばらく中庭に立ち尽くしていた。
風が吹いて、葉が揺れて、遠くでチャイムが鳴った。
それだけの世界の中で、俺はしばらく“陽翔”でいることを忘れていた。
その日、家に帰っても何も手につかなかった。
夕飯の味が薄く感じたのは、たぶん気のせいじゃない。
ベッドに寝転びながら、天井を見上げていた。
思い出そうとすればするほど、かえって記憶は曖昧になる。
でも、確かに揺れた。
あの瞬間、自分の中で何かが軋んだ感覚があった。
止まったままの時間が、ほんの少しだけ――動いた気がした。
次の日の朝は、やけに光が強くて、目がすぐに覚めた。
窓の外の空は晴れていて、雲一つない。
でも、昨日までの空とは違って見えた。
制服に袖を通しながら、ふと鏡の中の自分と目が合った。
無意識に“無難な顔”を作っていた自分に気づいて、なんとなくため息が出た。
学校の空気は変わらない。
昇降口で誰かが手を振って、廊下で友達が冗談を言い合って、教室はいつも通り騒がしい。
その中に、俺も混ざっていた。何事もなかったように。
「おはよー、陽翔。昨日のプリント見せてくんね?」
「ああ、うん。これ」
「サンキュー! 助かるわ~」
笑いながらプリントを渡す。
いつものやり取り。何も変わらない。
でも、心のどこかがちょっとだけ冷めていた。
昨日の未透との会話が、こうした“無難な日常”を急に薄く感じさせた。
授業と最中、ふと窓の外を見る。
何を見てるのか、何を見たいのか、それは自分でもわからなかった。
でも、あの黒髪の少女のことを思い出していた。
未透。
まだ、二度しか話していない。
でも、他の誰よりも深く俺の心を揺らしてきた。
“君も、何かを探してるよね?”
あのとき言われた言葉が、頭から離れない。
わかってるはずなのにわからない。
俺は何を探してるんだろう。
見つけたくて、でも見たくなくて。
きっとそれは、“あのとき”の記憶に繋がっている。
昼休み。
弁当を開きながらも、箸が進まない。
「陽翔、今日テンション低くね?」
「え、そう?」
「いや、なんかさ。疲れてる?」
「ああ……ちょっと寝不足で」
適当に笑ってごまかす。
けれど、笑ってる自分に違和感を覚える。
未透が言っていた言葉が、胸に残っていた。
――言えなかったことがある人って、自分でも気づいてないことが多い。
気づいてない? 俺が?
違う。俺は気づいてる。
ただ、言いたくないだけだ。言ってしまえば、もう戻れなくなるから。
あのとき――声をかけられなかった。
背中が遠ざかっていくのを見ながら、喉の奥で言葉を呑み込んだ。
本当は、呼びたかった名前があった。かけたい言葉があった。伝えたい話があった。
でも、出せなかった。
出したくなかった。
その選択をしたのは、他でもない、自分だった。
そんなことは誰にも言っていない。誰にも話せなかった。
だから、俺はこんなふうに無難な毎日を過ごしてきた。
波風を立てずに。
誰の心にも触れずに。
俺自身も、誰にも触れられないように。
誰かを傷つけないためには、誰とも深く関わらないのが最善だと思った。
……でも、未透は違った。
彼女の目は、俺を“見て”いた。
ただそこにいる誰か、じゃなくて、“俺”という人間を。
そう思ってしまった時点で、もう何もかもが変わり始めていたのかもしれない。
昼休みが終わる直前、ふと思い立って教室を出た。
人気のない廊下を抜けて、階段を降りる。
どこへ行くというわけでもない。
でも、気づけば足は自然とあの日の中庭へ向かっていた。
そこに、彼女の姿はなかった。
風が吹いて、木々がさやさやと揺れる音だけが響く。
誰もいない場所。なのに、少しだけ温かい空気が残っていた。
俺はベンチに腰を下ろして、ポケットからスマホを取り出す。
ホーム画面に通知が溜まっていた。返事をする気にはなれなかった。
誰と話したって、表面を撫でるだけの言葉しか出てこない。
本当のことなんて、誰にも言えない。
でも。
――もし、未透になら。
ふと、そんなことを考えていた。
名前を呼びたかった誰か。
言えなかった言葉。
そのすべてを、彼女になら話してもいいのかもしれない――そう思っている自分に、俺は少しだけ驚いた。
秋の風が吹いた。
落ち葉が一枚、膝の上に落ちてくる。
その小さな揺れが、胸の奥に静かに染みていく。
俺はまだ、誰のことも呼べていない。
でも、いつか――
そのとき、背後で誰かの足音がした。
◇◆◇◆
――足音がした。
ゆっくりと、地面を踏みしめるような音だった。
俺は肩をすくめそうになりながら、そっと後ろを振り返った。
そこにいたのは、やっぱり未透だった。
風に揺れる黒髪。白い肌。
まるで季節の空気ごと溶け込んでいるような気配で、彼女はそこに立っていた。
「やっぱり……いたんだね」
そう言ったのは、どちらだったか分からない。
たぶん、俺だったと思う。けれど、未透の口元も同時に動いた気がした。
彼女は何も言わず、俺の隣に腰を下ろした。
ベンチがわずかに沈む。落ち葉が一枚、彼女の膝に舞い落ちる。
少しの間、沈黙があった。
でも、それは苦痛ではなかった。
むしろ心地よい静けさだった。
「今日も、何か見えた?」
俺は問いかけた。自分の声がやけに穏やかだったのが、自分でも不思議だった。
「ううん。今日は見えてない」
「そっか。じゃあ、ここに来たのはなんで?」
「……君が来そうな気がしたから」
その言葉に、少しだけ息を呑んだ。
偶然なんて、なかったのかもしれない。
でも、必然と言えるほどの理由もなかった。
ただ、不思議な一致。それだけで十分だった。
「わたしね、あんまり学校に来てないんだ」
未透は空を見上げながらぽつりとそう言った。唐突だった。
「体、弱いの?」
聞いていいのか迷った。でも、聞かずにはいられなかった。
「……うん。昔からずっと」
あっさりとした答えに、逆に胸がざわついた。
悲観的な様子はなく、ただ当然かのように冷静な面持ちだった。
「入退院を繰り返してる。だから、授業もほとんど出てない。高校に入ってからは、2日連続で学校に来たのも今日が初めて。みんなにはあんまり知られてないんじゃないかな。陽翔くんも知らなかったでしょ?」
なるほど、とだけ俺は言った。
それ以上、何も言葉が出てこなかった。
だから、今まで見たことがなかったのか。
高校生活の記憶を辿ってみても、彼女はどこの学年のどこのクラスにもいなかった。
いないのが当たり前だったから、気づかなかった。
「ここは静かでいいよね。わたしは読書が好きだから、ここなら落ち着いて読めるしね」
未透はそう言って、足元の落ち葉を軽くつまんだ。
「にぎやかなところも嫌いじゃないけど、長くいるとしんどくなっちゃうから」
「わかるかも。俺も、あんまり人混みとか得意じゃないし」
「うん。陽翔くんは……そんな感じ。誰かといるとき、少し肩に力が入ってる。無意識なんだろうけど」
ふと、未透の声がやわらかく響いた。
その目が、まっすぐに俺を見ていた。
「学校で俺を見かけたことあるの?」
「あるよ。色んな人に頼られてる。誰からも好かれて、誰からも嫌われてなくて、すごいと思う」
未透の言葉に嫌味なんてなかった。
でも、そう演じている俺からすれば心が少し痛くなった。
「……未透さんからしたら、俺は胡散臭く見えるでしょ」
「ううん。人間関係の構築が上手だなって思うよ。でも、無理してる」
「やっぱ、そう見える?」
「他の人は気づいてないと思うけど、わたしは分かるよ」
未透が断言したのがおかしくて、俺は少しだけ笑ってうつむいた。
誰にも気づかれないようにしてきたのに。
この子には、簡単に見透かされてしまう。
「言葉って、重たいよね」
未透がぽつりと言った。それも唐突に。
「うまく言えないときもあるし、言ったことで壊れちゃうこともある。でも、言わないままにしてると、それもまた、ちょっとずつ自分を削っていくような気がして」
「……未透さんは、相手に言わなくちゃいけないことを言わなかったことがあるの?」
「あるよ。だから、“見える”んだよ」
未透はそう言って、手のひらを開いた。
その手のひらの上で、ひとひらの落ち葉が揺れていた。
彼女は一つ息を吐くと、静かに口を開く。
「昔ね、大切だった子がいて。その子のことを、ちゃんと好きだって言えなかった」
「……」
「気づいたら、その子は遠くに行っちゃってて。もう戻らなかった。違うか、わたしが遠くに追いやられたのかもしれない。だから、伝えられなかった言葉が、ずっと胸の中に残ってる。消えてくれないの。忘れられないの。その子に言いたかった言葉が、何年経っても残り続けてる」
俺は何も言えなかった。
その話が、どこか自分自身のことのように思えてしまったから。
言えなかった言葉。
呼べなかった名前。
何度も、何度も、思い出しては胸の中に沈めた記憶。時間が経とうと時折り夢に見るほど、あの時のか記憶は胸にこびりついて拭えなかった。
それが今、未透の言葉によって表層に浮かびかけていた。
「君にも、そういう誰かがいる?」
「……」
俺はわずかに首を縦に振った。
「名前は言える?」
「……言えない。まだ」
言えない、というよりも、思い出せない、わからない……という表現のほうが正しいのかもしれない。
心の奥底に封じ込められたあの時の記憶はそう簡単に想起することができなかった。
「うん。それでいい。言えるときが来たらでいい」
未透はそれ以上、何も聞かなかった。
ただ、優しい声色でそう言って、隣にいてくれた。
それだけで、少しだけ心が軽くなった気がした。
「ありがとう……」
「いいんだよ」
「……なんで未透さんは、俺に寄り添ってくれるの?」
「悩んでそうだったから」
迷いのない簡単な答えだった。
「それだけ?」
「うん。わたしね、言葉って……すごいなって思ってるんだ」
未透はその言葉を皮切りに、ぽつぽつと語り始めた。
「陽翔くんも誰かの何気ない一言に救われたり、逆に傷ついたりするでしょ? 目に見えないのに、人の心を動かす力がある。それって、ちょっと魔法みたいだと思わない?」
未透は空を見上げながら微笑む。
その顔はどこか遠くを見ているようだった。
「わたし、そういう言葉を大切にしたくて……“ことばノート”をつけてるんだ」
「ことばノート……?」
思わず聞き返したその瞬間、
俺の胸の奥が、かすかにざわめいた。
“ことばノート”
それはどこかで聞いたことがある気がした。
でも、思い出そうとしても、指の隙間から零れ落ちるように掴めない。
頭のどこかがぼんやりとして、胸の奥がじんわりと熱を帯びるような感覚。
「それ……どういうの?」
俺がそう聞くと、未透は嬉しそうにうなずいた。
「たとえば、人からもらった優しい言葉とか、自分が感じたこと、ふと浮かんだ一文とか……何でも書いてるの。わたしにとっては、小さな宝箱みたいなものなんだ」
「宝箱……か」
俺はその響きに、自然と惹かれていた。
「そう、宝箱。言葉はお宝なんだよ。全員が口にできるけど、全員違うものを自由に使えるの」
「なんか、いいね。自分だけの“宝箱”って」
「ふふ。陽翔くんも持ってみたら?」
「俺に……書けるかな」
「きっと書けるよ。だって、君の中にも、ちゃんと届いてない言葉があるでしょ?」
未透は俺の目を見て言った。
そのまなざしには嘘がなくて、でもどこか不安げで、それでも信じようとしてくれているような、そんな目だった。
胸の奥が、また静かに揺れる。
“ことばノート”。
なぜか妙に耳に残るその響きが、
これからの何かを導いてくれる気がしていた。
それから俺たちはしばらくの間、言葉を交わさず、空を見上げていた。
夕陽がゆっくりと傾いて、空にオレンジ色のグラデーションが広がっていく。
ふと、未透が立ち上がった。
「そろそろ行かないと、また会えるといいね」
彼女はそう言って、笑った。
その笑顔は、どこか透けて見えるような、不思議な透明さがあった。
「うん。また、ここで」
俺がそう返すと、未透は軽く手を振って歩き出した。
その背中を、俺はしばらく見つめていた。
――言えなかった言葉。
もしも、誰かに渡せるなら。伝えられるなら、
未透に話すことで、それが少しずつ形になる気がしていた。
でも、俺はまだ、名前を呼べていない。
だから、まだ立ち止まったままだ。
だけど今は、それでも少しだけ、前に進めるような気がしていた。
◇◆◇◆◇
次の日の朝、教室に入った瞬間、今日も変わらずざわめきが耳に飛び込んできた。
誰かが笑っていて、誰かがスマホを見せ合っていて、誰かが机に突っ伏していた。
いつもと変わらない、見慣れた光景――のはずだった。
でも、そのはずの景色が、今日は妙に“ぼやけて”見えた。
「おはよ、陽翔~」
「昨日のノート、見せてくれたら神」
「今日小テストっしょ? マジ死ぬわ」
いくつかの声が飛び交う。俺は、それにいつも通り笑って応じる。
「あー。うん、いいよ。はい、これ」
「マジ助かる!」
差し出す手。返ってくる笑顔。軽く交わす言葉。
それは“ちゃんとした会話”のように見えた。
ただ、俺の中ではどこか空洞が鳴っていた。
――普段の俺なら、もっと冗談混じりに軽口を叩いて、空気に馴染ませていた。
でも、今日はそれができなかった。
言葉の端が、少しだけ遅れて口を出る。
笑顔も、どこか作り物みたいに感じられた。
自分がやっていることに対して、自分の手応えがない。
まるで、体だけが動いているみたいだった。
それはいつもそうだったはずなのに、最近はそれが如実に感じられた。自分なのに自分じゃない、ふわふわとした感覚が常に残り続けている。
授業中。ノートを取る手が止まりそうになる。
黒板の文字が目に入っているはずなのに、意味が通らない。
前の席の子が消しゴムを落として拾う仕草すら、スローモーションみたいに見える。
“何かが違う”。
その正体が、自分の中にあることだけはわかっていた。
未透と話したことで、俺は確かに何かに触れてしまった。
言葉にできない“ひび”のようなものが、自分の内側に走っている。
これまでなら、ここにいる自分に何の違和感も覚えなかったのに。
今日は、まるで“借り物の姿”で教室に座っているような気分だった。
いつもなら気にしない誰かの声が、遠くに聞こえる。
冗談も、笑い声も、雑音のように耳をすり抜けていった。
俺は今、何をしてるんだろう。
誰の中に、どんな顔で混ざってるんだろう。
そんなことを考えてしまう自分に、また小さな違和感が重なる。
昼休み。
パンを買いに行く流れに乗らず、俺は一人で教室に残った。
窓の外を見ながら、昨日のことを思い出す。
未透の言葉が、風の音に重なって蘇る。
――名前、言える?
――それでいい。言えるときが来たらでいい。
あのときの彼女の声は、驚くほどまっすぐだった。
どこにも無理がなくて、押しつけがましさもなかった。
ただ、受け入れてくれる空気だけがあった。
俺の全てを受容し、理解し、待ってくれる。
まるで当事者のような口ぶりだった。
思考に耽っていると、ふと教室の入り口の方から声が聞こえた。
誰かが、俺の名前を呼んだ気がした。
でも、気のせいかもしれない。
返事をする気にはならなかった。
次に舌打ちが聞こえた。それでも俺は一瞥すらしなかった。
どうしてかはわからない。もしかしたら、いつもの演じた姿を見せるのが嫌になり始めたのかもしれない。
やがて昼休みが終わると、授業が再開される。
板書を写しながらも、頭の中はまったく別のことで埋まっていた。
――未透は、今日来ているんだろうか。
どのクラスかは知らない。聞けていない。なぜか聞くのが憚られた気がしたから。
かと言って、名簿を確認するほどの勇気はない。
けれど、校舎のどこかにいるような気がしていた。
いや、もしかしたら今日は来ていないのかもしれない。2日連続で登校するのが初めてだと言っていたし。
そう考えたとき、不思議な喪失感が胸の奥に広がった。
今までは何とも思っていなかった“特定の人物の不在”が、今日に限って、やけに重たく感じられた。
どうしてだろう。
ふと、心がざわめく。
呼びたかった名前。
それを思い出しかけるたびに、胸が苦しくなる。
俺は、誰を、呼びたかった?
誰に、何を、言えなかった?
その問いの答えは、まだ言葉にはならない。
放課後。
俺は迷うことなく中庭に足を運んでいた。
夕陽が差し込む静かな場所。
昨日と同じ風が吹いていた。
でも、ベンチの上には誰の姿もなかった。
俺はそこに座って、しばらく何もせずに空を見ていた。
未透はいなかった。
だけど、彼女の言葉が、そこに残っている気がした。
「……言えるときが来たら、でいい」
俺は、その言葉を心の中で繰り返す。
まだ、何も言えない。
でも、きっと――そのときは来る。
来ると信じていい気がしていた。
空の色が、少しずつ深くなっていく。
風が、落ち葉をひとひら巻き上げた。
帰り道。
自転車を押しながら、ふと足が止まる。
校舎の窓を見上げた。
まだ明かりがついている教室があった。
そのどれかに、未透がいたかもしれない。
あるいは、どこにもいなかったのかもしれない。
でも、もう一度会える気がした。
それは根拠のない、確かな予感だった。
胸の奥にある名前。
それが、ゆっくりと輪郭を取り戻し始めている。
あの放課後。
声をかけられなかった、あの背中。
あのとき言えなかった言葉が、確かにまだ、ここにある。
そしてそれを、きっと誰かに渡せる日が来る。
未透は、たぶん――そのきっかけになる人だ。
俺はもう一度、空を見上げた。
そこには、昨日と同じ夕焼けが広がっていた。
でも、昨日とまったく同じではなかった。
少しだけ色が濃く見えた。
少しだけ胸があたたかかった。
それだけで、今日は十分だった。
◇◆◇◆
ある日の放課後。
俺は屋上へと続く階段を登っていた。
教室からも昇降口からも遠い、ほとんど使われなくなった北館の奥。
もちろん屋上の扉は施錠されていて、生徒は立ち入り禁止になっている。
でも、俺はよくこの踊り場に来る。
誰も来ないから。音がないから。
階段に座っていると、自分だけ世界から切り離されたような感覚になる。
今日も同じように、ひとりになりたくてここに来た――はずだった。
しかし、先に誰かがいた。
廊下の光が漏れる位置に、制服の影があった。
壁に背を預けて、じっと上を見ている。
その横顔を見た瞬間、胸が少しだけ熱くなった。
「……未透、さん?」
俺が名前を呟くと、彼女はゆっくりと顔をこちらに向けて、ふわりと笑った。
「やっぱり、来たね」
「どうしてここに?」
「静かだから。わたしもたまに来るの。たまにって言ってもあんまり学校に来てないから知れてるけど……陽翔くんもこういうところが好きだよね」
「まあ、そうだけど……よくわかったね」
俺は彼女の隣に腰を下ろした。
この狭い踊り場には、たった二人分の空間しかなかった。
少し身体が近くて、それだけで言葉を選んでしまう。
階段のコンクリートが、少しひんやりとしていた。
「久しぶりだね」
未透が言った。小さく三角にたたまれた足はびっくりするくらい華奢だった。
「1週間ぶりかな」
「うん。実は新しいお薬を使い始めたせいで、眠気が酷くてなかなか学校に来れなかったんだよね」
「そうなんだ。体、今は平気なの?」
「平気。陽翔くんと話せるから」
未透の言葉の真意はわからなかったけど、俺はどことなく嬉しくなって微笑んでいた。
「笑えたね」
「え」
「いつもと違う、本当の笑顔だよね、それ」
俺の顔を覗き込んでくる未透は嬉しそうに口角を上げていた。
「……そうかもね」
「普段からそうすればいいのにってわたしが言うのは勝手かな」
「勝手じゃないけど……本当の自分を出すのが怖いんだ」
俺は未透になら話してもいいかなと思えていた。
本当は誰にも明かさずにいるつもりだったあの時を後悔を。
「……この前、話したよね? 俺の、後悔」
俺はおもむろに言葉を紡いだ。
「うん」
「もう少し、ちゃんと話してもいい? 前は未透さんが話してくれたから、俺のも聞いてほしい」
未透は、何も言わずに小さく頷いた。
それだけで、俺は続きを話そうと思えた。
「――中学のとき。仲のいい友達がいた……いや、友達って言っていいのかもわからないくらい、最後は距離があったかもしれない」
「……」
「俺は、その子の隣にいるのが好きだった。話すのが楽しくて、他の誰よりも自然にいられた。でも、あるときから、ちょっとずつ何かが変わっていったんだ」
言葉を選ぶように、ゆっくりと話す。
「その子は……学校に来る日が少なくなって、俺は怖かったんだ。何もかも変わってしまったことに気づいてるのに、知らないふりをしてた。“どうしたの?”のひと言が、全部を壊してしまいそうで……怖かった」
ただ話をしているだけなのに、異様なほど口の中が乾いていた。
「だから、黙ってた。何も言わなかった。俺は言葉を飲み込んで、笑って、その子が来ない日も平気な顔をしてた。本当は、すごく怖かったのに……何かを失っていく音が、崩れていく音が、毎日、心のどこかで鳴ってたのに」
そのときの自分を思い出すと、息が詰まるような感覚になる。
「そしたら、ある日、その子は突然来なくなった……教室から姿が消えて、連絡も取れなくなって、それっきり」
未透は目を伏せたまま、黙って聞いている。
俺は少しずつ声が震えていくのを止められなかった。
「あとから聞いた話だけど……その子、色んなことがあったらしいんだ。家のこと、心のこと。体のこと。俺が知らないふりをしている“日常”の裏で、ずっと戦っていたんだ。なのに、俺はなにもできなかった。やろうとすらしなかった。本当は……その子に起きた異変に気づいてたのに、目を背けて知らないふりをしていたんだ」
喉の奥が熱くなる。
「名前を呼べなかったんだ。そうなってから最後まで一度も。声をかけたかったのに、名前すら出せなかった。名前を呼んだら、全部が壊れてしまいそうで。俺は手を差し伸べる勇気がなかった。でも今は、名前を呼ばなかったことを、言葉をかけなかったことを、助けてあげられなかったことを、すごく悔やんでる。どうしようもないくらい……悔やんでる」
思い出の中のその子は、いつも背を向けている。
ふと振り返るかもしれない瞬間に、俺はいつも声を飲み込んでいた。
その場面が、何度も夢に出てくる。
夢の中でも、俺は声が出せないままだ。
「未透さん。俺、怖いんだ」
その声は、ようやく自分の本音だった。
「もう一度、誰かの名前を呼ぼうとして、また逃げ出す自分がいる気がして。言いたいことがあるのに、言葉が喉で止まる……そんなの、もう繰り返したくないんだよ」
膝の上に置いた拳には無意識に力が入っていた。
すると、未透はそっと、俺の手の甲に自分の手を重ねた。
その手はあたたかかった。けど、すこしだけ震えていた。
俺の言葉と同じように。
そして、その表情は険しく暗かった。
「陽翔くん……その想いは、ちゃんと届かなかっただけで、まだどこかに残ってるよ。呼べなかった名前は消えてなんかいない。かけられなかった言葉も一緒だよ。きっと、その子は待ってる。君がもう一度、向き合うのを」
言葉が、胸の奥に染みていく。
優しいのに、強い響きだった。
俺は、顔を伏せた。
何も言えなかった。
ただ、伝えなければいけない言葉があった。
「ありがとう」
「ううん。いいんだよ。こっちこそ悩みを打ち明けてくれてありがとう」
笑みを交わして柔らかな空気になると、心地よい沈黙が訪れた。
それは10秒くらいか。そんな沈黙を破って、未透が小さく息を吐いた。
「ねぇ、陽翔くん。少し、付き合ってくれる?」
顔を上げると、未透はゆっくりと立ち上がっていた。
彼女の瞳は揺らぎなく、どこか決意に満ちていた。
「行きたい場所があるの。ほんの少しだけでいいから」
「うん」
俺も静かに立ち上がった。
未透の手は、また軽く俺の袖を引いて、北館の薄暗い階段を下りていく。
連れて行かれたのは、校舎の裏手。
体育館の裏にある小さな植え込みだった。
風も光もほとんど届かないその場所は、草の香りと、ひんやりとした湿度に包まれていた。
こんな場所があったんだ。というのが最初の感想だった。通り過ぎたことはあったけれど、こうして足を運んだのは初めてだった。
未透は植え込みの中の、ほんの少し空いた場所に立ち止まった。
草の合間に、小さな石碑のようなものが置かれているのが見えた。
「……ここ、知ってた?」
「知ってはいたけど、初めて来たかも」
「たぶん、ほとんどの人は通り過ぎちゃうと思う。気づかないし、気づいても気にしない。誰にも手入れされず、ずっと放置されてる場所だと思うんだ」
未透はしゃがみ込み、小さな石の前に指をそっと伸ばした。
風が、ざわりと草を揺らす。
すると、ふいに耳鳴りのような感覚がして、遠くで“何か”の声が聞こえた気がした。
——ありがとう。
それは幻聴だったのかもしれない。
でも、確かに、何かが通り抜けた感覚があった。
どこからともなく、音の出所はわからない。
ただ、確実に聞こえた。
「今……何か、聞こえたような」
「それは誰かの想いだよ」
「“想い”?」
未透は草の先を見つめたまま、小さく頷いた。
「言葉にできなかった気持ち、伝えられなかった感謝、後悔、祈り。そういうのが、ふとした拍子に何かに宿ることがあるの。わたしは、それが“見える”というか、“感じられる”だけ」
「……幽霊が見えるってこと?」
未透は笑った。
でもその笑顔は、いつもの冗談まじりのものではなかった。
「そういうのとはちょっと違うかな。幽霊みたいに形がないから、それが“誰か”かどうかも分からない。ただ……残った気配みたいなものが、ふっとわたしに触れるの」
「さっきの……“ありがとう”も?」
俺が首を傾げると、未透は少しだけ目を細めて静かに頷いた。
「うん。ずっとここにあった“声”なんだと思う」
俺は改めて足元の小さな石碑を見る。
その傍らには、割れかけた素焼きの鉢植えがひとつ、草に埋もれるようにして置かれていた。
中には、半分枯れかけた、でもどこか力強く根を張った小さな植物が生えていた。
白くて細い花が、一輪だけ咲いていた。
「これは誰かが置いたの?」
「たぶん、何年も前のものじゃないかな」
未透は、そっとその鉢に手を触れる。
触れた瞬間、風がひとつ、やさしく草を揺らした。
「わたし、最初にこの場所を見つけたとき、ここに鉢があるのを見てね、何でこんな場所に、って思ったの。でも、そのときすぐ“言葉”が聞こえた。ありがとうって、すごく優しい声で」
「誰の声なのかはわからない?」
「そう、わからない。名前も顔もない、ただの想い」
未透は、膝をついて鉢植えを見つめた。
「ここに何かを植えた誰かがいたんだと思う。誰にも言えないまま、そっとこの場所に……誰かのために、願いを込めて」
「誰かの……ため?」
「うん。きっと大切だった誰かが辛い思いをしていて、どうしても直接は言えなくて、それでも何か残したかった。言葉じゃ届かないなら、形にして残そうって……。そんな想いが、この小さな鉢に込められてたんだと思う」
俺は言葉を失ったまま、白い花を見つめた。
それは、かすかに風に揺れていた。
まるで、誰かがその“想い”を、今も見届けてくれているように。
「それで、どうして“ありがとう”だったの?」
ふと、素朴な疑問が口をついて出た。
未透は一瞬だけ目を伏せ、やがてぽつりと答えた。
「さっきの声はね、きっと……想いを残した“誰か”の声じゃなくて、それを受け取った“誰か”の声なんだと思う」
「……え?」
「言葉は伝わらないといけないってこと。意味がないとは言わないけど……やっぱり、伝えたいことはきちんと相手に伝えないと、それが後悔につながってお互い嫌な思いしちゃうと思わない?」
そう言いながら、未透はそっと花に触れる。
まるで撫でるように優しく。
「じゃあ、ここにこの花を植えた誰かの無念とか後悔は、伝えたい人にきちんと届いたってことだよね」
「そう。言葉って、声に出さなくても、どこかに届くんだよ。時間がかかっても、伝えようとした気持ちはちゃんと残る」
俺はその花を見つめながら、ふと思った。
俺の中にも、まだ届けられていない言葉がある。
誰にも渡せなかった言葉、呼べなかった名前。
それはまだ、どこかに置き去りのままだ。
「……未透さん」
「なに?」
「君のその力って……“見える”というより、“感じる”ってイメージなんだよね」
「音じゃないし、色でもないから、空気の中にある“心の跡”みたいなものかな?」
小さく首を傾げると綺麗な黒髪が揺れた。それは本人にもよく分からない感覚らしい。
「俺にも、わかるかな。そういうの」
「わかるよ。だってこの鉢植えを見たとき、確かに聞こえたんだもんね?」
未透はそっと笑うと、言葉を続けた。
「……陽翔くんの中にも、言えなかった言葉があるでしょ? それがある限り、人の気持ちに気づけるんだと思う」
俺は、小さく息を吐いた。
ありがとう。
あの言葉が、誰かの胸の奥で紡がれた一瞬の光だったとして。
それを拾える彼女のように、俺もなりたいと思った。
そして——
俺の中に眠る、まだ呼べていない名前にも。
いつか、きちんと“ありがとう”を伝えられるように。
「……不思議だね」
「不思議でいいんだよ。そこの理屈はどうでもいいの。ただ、誰かの“想い”がちゃんと残ってるんだって、わたしは信じてるから」
未透は立ち上がると、風に揺れる前髪を押さえながら、俺を見つめた。
「陽翔くんの言葉もね……届くよ。きっと、その子に」
その目は、どこか遠い記憶を見つめるようだった。
俺はうまく返せず、ただ頷いた。
二人でいる時間は心地よかった。会って数回の異性が相手とはとても思えないほどに。
だから、俺たちは何も言わずにしばらく草の上に座っていた。
風が枝を揺らし、鳥の声が遠くに響いた。
未透の持つ変わった力は説明できないけれど、どこか現実味があった。俺自身も声が聞こえたし、たぶん本当なんだと思う。
そして俺は、彼女の“言葉”が、誰よりも深く、誰よりも遠くに届くものなんだと、少しずつ理解し始めていた。
たった一言で、誰かを救える力。
それが、未透の中にあって。
今、俺にも、その意味がほんの少しだけ分かった気がした。
もう一度名前を呼ぶために——
今度こそ、言葉を届けるために。
この出会いは、偶然なんかじゃない。
◇◆◇◆
最初は、たまたま休みかと思った。
体調の波があるとは聞いていたし、あまり通学していないとも言っていた。
けれど、2日目、3日目……1週間、2週間が過ぎても、彼女の姿はどこにもなかった。
あれから毎日のように、屋上へ続く階段に足を運んだ。
中庭にも、中庭にも、校舎の端のベンチにも、そっと目をやってみた。
全てのクラスを見て回ったりもしたけど、未透はいなかった。
まるで、風のように、ふっといなくなってしまったようだった。
“またね?”
体育館裏から離れるとき、未透はそう言って微笑んだ。
その言葉だけが、耳に焼きついて離れなかった。
俺の心には靄がかかっていたが、周囲の様子はいつも通りだった。
テスト前の話題、文化祭の準備、週末の予定。
みんなの言葉が交差するなかで、俺だけが置いていかれていた。
いつもなら、笑って相づちを打っていた会話が、今日はただの雑音にしか聞こえなかった。
そんな折、ふと、誰かに話しかけられる。
「陽翔、今日も屋上のとこ行ってた?」
「……え? ああ、ちょっとだけ」
「なんかあんの? あそこ、閉まってんじゃん」
「別に、なんでもないよ」
「ふーん。お前、最近変だぜ? 昨日も中庭で座り込んでたろ? その前は一人で色んなところ歩き回ってたしよ」
「そう、かな……気のせいだよ」
俺は何でもないような顔をして言う。
でも、胸の奥では何かが暴れていた。
未透のことを、誰にも話せなかった。
どこのクラスかも、連絡先も、何も知らない。
試しに先生に尋ねてみても、
「みとう、さん?」
「俺と同じ2年生の女の子で、体が弱いと聞いていたんですが……」
「あー、あの子ね。あなたの言う通り、ちょっと体が弱いみたいなのよ。ごめんなさい。それ以上のことは……ね? 本人の事情もあるし話せないのよ」
当たり障りのない言葉を返されるだけだった。
まるで眼中にないのか、名前すらまともに把握していない始末だった。
それが、いちばん胸に刺さった。
誰にも知られていない子のことを、俺だけがこんなに探している。
先生たちも心配そうにはしていない。
彼女の話題がクラスメイトから上がることもない。
それが、なんだか滑稽に思えて、でもやめられなくて。
あの細い声と、笑ったときの目元と、落ち葉をつまんだ指先が、ずっと心に居座っていた。
彼女の全てが何度も頭の中を巡る。
でも答えは出ない。誰にも、出せない。
だから俺は、未透の言葉を思い返していた。
「言葉って、重たいよね」
「でも、言わないままにしてると、それもまた、ちょっとずつ自分を削っていく」
気づけば、俺の手は机の上で鉛筆を握っていた。
ノートの片隅に、何かを書こうとして……でも、何一つとして言葉にできず手は止まっていた。
伝えられなかった言葉。
呼べなかった名前。
それを、今度は絶対に逃さずにいたいと思った。
未透がいたから。
彼女が、俺の“止まった時間”に、手を差し伸べてくれたから。
誰かにとっては、一生徒の不在かもしれない。
でも俺にとっては、あの時間が確かにあった。未透がいたから変われる気がした。
彼女が俺に言葉を渡してくれたから、寄り添ってくれたから、心の中が晴れやかになって前向きになれた。
だから今度は、自分の足で歩いてみる。
もう一度、誰かに言葉を届けられる自分になるために。
教室の窓から見える空は、分厚い雲に覆われていた。
でも、その向こうにある青さを、俺は少しだけ信じられる気がしていた。
それだけでいい。
まだ、名前は呼べていないけれど――
きっと、前より少しだけ、俺は“自分”に近づいている。