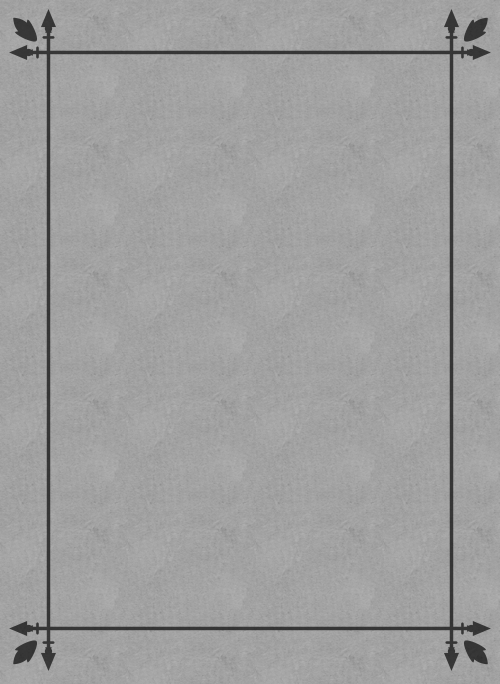朝の空は、やけに青かった。
雲ひとつない晴天で、風も穏やか。
天気予報では「初夏の陽気」なんて言ってたけど、俺にとってはただの“今日”だ。
特別でも、退屈でもない。
いつも通りの一日が始まる、ただそれだけの朝。
「おはよー、陽翔! 今日もさわやかイケメンじゃん」
校門の前で手を振ってきたのは、同じクラスの委員長だった。男子だ。
こいつはいいやつだけど声がでかい。
あと、俺は別にイケメンじゃない。黒髪の前髪が目元に少しだけかかっていて、どこか頼りない印象を与えているし、昔から「静かそうだね」と言われることが多い。それはきっと、このちょっと暗い表情のせいだと思う。
まして身長も平均的だ。人付き合いだって無難を選んで生きているから、日頃から笑って受け流すのがもう習慣になってる。
「おはよ、いや、今日なんか寝癖ひどいし……」
「謙遜しすぎ~。てかさ、昨日の課題やった? 俺、ガチで忘れててさ」
「んー……出したよ。ま、写してもバレない程度になら貸すけど」
「マジ神!」
俺は鞄からノートを取り出して渡す。大志は何度も頭を下げて感謝してくる。こうして、いつも通りの“いい奴”を演じる。別に悪い気はしない。けど、心が動くわけでもない。
――いつも、こんな感じだ。
無難に話を合わせて、角を立てずに過ごす。誰とも深く関わらず、けど孤立もせず、クラスの中に自然と溶け込んでいる。誰も俺を“演じてる”なんて思ってない。俺がそう思わせないようにしてるから。
“空気を読む”っていうのは、ある意味才能だ。気まずくならないように、相手の表情と言葉を見て、最適解を口にする。そうすれば、争いは起きない。嫌われることもない。誰も傷つかない。
――ただ、俺のことも誰も知らない。
知ってほしいとも、思わない。
でも時々、全部ぶち壊したくなる衝動が、ふと湧いてくることがある。
教室に入った瞬間、湿度のない賑やかさが肌にまとわりついた。
ガヤガヤと笑い声が飛び交い、誰かの机に集まってスマホを見せ合うグループ。
教科書を開いているのに全然進んでなさそうな自習組。
ぼーっと窓の外を眺めているやつもいれば、寝癖のまま突っ伏してるやつもいる。
俺は、そのどれでもない。
だけど、そのどれにでも“なれる”。
「おはよ、陽翔くん」
前の席の佐伯がふと振り返り、小さく手を振ってきた。
茶髪を一つにまとめたポニーテールがふわりと揺れる。声も仕草も、相変わらず柔らかい。
「おはよ」
俺は微笑んで返す。たったそれだけ。
彼女とは特別仲がいいわけじゃない。
けれど、誰よりも遠いわけでもない。
佐伯はにこっと笑って、また女子グループの輪に戻っていった。
すぐに、他の話題に紛れて俺の存在は霞んでいく。
……そう、それでいい。
それが、いつもの日常だ。
昼休みになると、
「ねえ、陽翔。今度の体育祭の実行委員、やらない?」
パンを頬張りながら、杉下が話しかけてきた。
彼は学級委員で、先生からの信頼も厚い“リーダー格”だ。
その口ぶりは一見フランクだけど、断られることを前提にしてない空気がにじんでいた。
俺の“断らない性格”を、知っていた上で言っている。
「うん、いいよ。特に予定ないし」
「マジ助かる! やっぱ陽翔、そういうとこ神~!」
その一言で、また教室の空気が流れる。
別の話題へ。別の関心へ。
俺はその流れを、ただ見送る。
そうして俺は、また“いい奴”のまま一日を消化していく。
悪くない。
誰からも嫌われず、トラブルもなく、表面上は順調な毎日。
だけど……時々、どうしようもなく、息が詰まる瞬間がある。
他愛もない会話をしている最中に、ふと。
教室の中の誰かが笑ってる、その声が急に遠くに聞こえる。
自分の声だけが、よそよそしく反響してくるような気がする。
まるで、ここにいながら、どこにもいないみたいな――そんな、変な感覚。
俺の“本当”は、どこにあるんだろう。
それを誰かに話したことなんて、一度もない。
……いや、違う。一度だけ、ある。
たった一人だけ。俺の“本音”に近づいてきた人がいた。
俺はそれを受け止めた。しかし……あの悲劇に繋がった。
頭の奥が痛む。思い出しかけた映像を、意識的に押し戻す。
見ないようにしてきた。忘れようとしてきた。
今さら掘り返したところで、何も変わらない。
「ねえ、陽翔くん。あんた、断らなさすぎじゃない?」
昼休みの終わり、佐伯がふと口にした。
からかうような口調だったけど、少しだけ本気っぽかった。
「“何でも受け入れてくれる便利な人”って、定着しちゃうと損だよ」
「そうかな?」と笑いながら答えたけど、心の中には何か引っかかるものが残った。
たぶん、彼女は悪気があったわけじゃない。
ただ、ちょっとした気づきとして言っただけ。
けれどそれは、俺がずっと見ないふりをしてきた部分を、思いがけず突かれたような気がした。
自分を守るために選んだ“無難”な振る舞い。
けれど、それを続けるたびに、何かがすり減っていく感覚がある。
それに名前はつけられない。ただ、確実に削られている。
ホームルームが終わり、教室から生徒が一人、また一人と出ていく。
気がつけばもう下校時刻だ。今日も何もなく学校が終わった。
俺も鞄を持ち、立ち上がると、足早に昇降口へ向かった。
靴箱で並ぶ足音。
うしろに人がいる気配がしたから、少しだけ身体をずらした。
ぶつからないように、さりげなく。
声をかけられる前に、軽く会釈をしておく。
たぶん名前も顔も知ってるはずだけど、記憶には残っていない。
相手もきっと、俺をそう思ってる。
靴を履いて立ち上がると、前から誰かが走ってきた。
俺は避けるように、一段ずれて右側を歩いた。
昇降口のドアを開けるとき、向こう側に誰かの気配がしたから、ドアノブを半秒だけゆっくり回した。
ふと、すれ違う誰かが俺に向かって軽く手を振った。
名前を思い出せなかったけど、とりあえず笑って返した。
それは、いつも通りの動きだった。
誰かの邪魔にならないように。誰にも不快感を与えないように。
波風を立てずに、ただ通り過ぎていくための所作。
それを意識してるつもりはなかったけど、気づけば毎日、無意識にそうしている。
それが俺の日常だった。
翌日の昼休み。
教室の隅で誰かが相談事をしていた。
「それなら、あっちに頼んだほうがいいんじゃない?」
「ああ、でもあいつも忙しいって言ってたし」
「じゃあ……」
声が小さくなる。
すると、視線が、ちらっと俺のほうへ向いたのがわかった。
俺はその瞬間、わずかに笑ってうなずいた。
「俺でよかったら」
その言葉を口に出す前に、相手は少しほっとした顔をしていた。
もう“そうなる”ってわかってたんだろう。
俺が断らないこと。笑って受け入れること。
別に嫌なわけじゃない。面倒なことが好きなわけでもないけど、断る理由を探すほうが疲れる。
「助かる」って言われるたびに、自分の価値がそこにあるような気がして、安心する。
気づかれないように、輪の中に入りすぎないように。
でも、輪の外にも出ないように。
ぴったりとした中間地点に、俺はいつも立っている。
「ねえ、どっちが似合うと思う?」
次はクラスメイトの女子がカラフルなハンカチを見せてきた。
二枚あるそれは、どちらも似たような柄に見える。
正直、どっちでもいい、なんて言ったら空気が壊れる。
だから数秒考えるふりをして、「こっち、かな」と答える。
「やっぱり? 私もそう思ってた!」
彼女は「ありがとねっ!」と言って立ち去った。
そこに俺への好意はない。単にその場にいたから聞かれたに過ぎない。
ごくごく自然な当たり障りのない会話。俺の返答や思考は明瞭な適当さがあったから、無難な会話が容易に成立する。
いつからだろうか、俺がこうして本音を隠して無難に逃げるようになったのは。言いたいことを言えずに、周りを気にしながら過ごすようになったのは。
高校2年生になったっていうのに、俺は俺でいることを諦めてしまっていた。
だが、それでいい。
誰も、俺の“本当”なんて気にしない。
俺も、自分の“本当”を気にしない。
それが無難に過ごした結果、辿り着いた答えだった。
別に、誰かに好かれたいわけじゃない。
嫌われるのが怖いだけでもない。
ただ、何も起きないように。
誰かの感情に、波を立てないように。
それが、習慣になっていた。
俺は“色のない誰か”を演じている。
それが、楽だった。
何も知られないというのは、安心だった。
ただ、夜になると、ときどき思い出す。
あの時、言いたかった言葉。
あの時、言えなかった言葉。
飲み込んで、忘れたふりをして、どこにも置き場のない感情たち。
それでも、俺は“いい奴”のまま、今日を終える。
◇◆◇◆
放課後の校舎は、朝や昼とは違う匂いがする。
どこか冷たく、静かで、音の輪郭がくっきりと浮かぶような――そんな空気。
俺は帰り支度を終えたはずなのに、気がつけば俺は昇降口を通り過ぎていた。
明確な理由なんてなかった。ただ、少しだけ一人になりたかった。
ざわざわした教室から抜け出した身体が、勝手に別の場所を求めていた。
渡り廊下を抜け、人気のない中庭に足を向ける。
誰もいないはずの、その場所で。
――誰かの声が、聞こえた。
「……ごめんねなんて思う必要はないよ。十分助けられたから、だからもう自分を悔やまないで?」
最初、独り言かと思った。
でも、その声には確かに“誰かに話しかけている”響きがあった。いや、話しかけているというよりは、語りかけるような……自分の心に問いて処理しているような感じだった。
ふと立ち止まり、声のするほうに視線を向ける。
茂った植え込みの向こう。
木陰に立つ彼女の背中が見えた。
肩より少し下まで伸びた黒髪が、風に揺れている。
制服のリボンがほどけかけていて、鞄も持っていない。
まるで、ここが自分の居場所であるかのように、自然に佇んでいた。
「うん。大丈夫、ちゃんと覚えてる……だから、もう、いいんだよ」
小さな声は、やさしい響きを帯びていた。
まるで幼い子供に接するような声色だ。
しかし、それは人間に向けられているものには思えなかった。
目に見えない“誰か”を相手にしているようだった。
俺は一歩だけ踏み出した。
その足音に、彼女がふいにこちらを振り返る。
目が合った。
その瞬間、胸の奥がきゅっと締めつけられた。
驚いたような、でも怯えているわけでもない。
どこか静かで、湖面のような眼差し。
「あ……ごめん。誰かと、話してるのかと思って」
気まずさを隠すように声をかけると、彼女は一瞬黙ってから、小さく首を振った。
「ううん、大丈夫。もう済んだから」
「済んだ?」
「うん。さっきまで、ここにいたの。でも……もう、いなくなったみたい」
俺は返す言葉を探したが、何も思いつかなかった。
その受け答えは、あまりに不思議で、現実味がなかった。
でも、彼女の声には嘘がなかった。
ただまっすぐに、そこにある事実だけを伝えるような、そんな声音だった。
「……誰か、見えてたの?」
気づけば、口が勝手に動いていた。
彼女は少しだけ目を細めて、空を見上げた。
そして、ぽつりと、こう言った。
「わたしはそこに“誰かの想い”が残ってるときだけ、時々見えることがあるの。だから、見えるときもあれば、見えないときもある」
その言葉の意味を、すぐに理解することはできなかった。
けれど、彼女の目に映る何かが俺には見えないものだということだけは、妙にリアルに感じられた。
あの世でもこの世でもない、別世界の”何か”が見えているようだった。
「……そっか」
そう言って、俺はその場を離れようとした。
関わるのが億劫だったのかもしれない。
でも、背中越しに小さな声が届く。
「ねぇ」
立ち止まる。
「いつもここには誰も来ないのに……君は見てたんだね、わたしのこと」
振り返ると、彼女はまだ同じ場所に立っていた。
でも、その表情には不思議なほど動揺がなかった。
むしろ妙な笑みを浮かべていた。まさか見られていたことを喜んでいる? どうして?
そもそもこんな場所で誰と何を話していたんだろう?
俺は色々な疑問を胸中で思案したけど、いくら考えても答えは見つからなかった。
ただ一つ思ったことがある。この人は変わった雰囲気を持っている。
他の誰とも違う、触れると簡単に壊れてしまいそうな……だけれど、心の奥には確かな強さがあって、無難を選択して過ごす俺とはまるで違う存在だった。
「どうしたの?」
「っ……ごめん、もう行くね」
じろじろ見てしまっていたようだ。
気恥ずかしくなった俺はその場から逃げるように立ち去ろうとした。しかし、またも彼女が呼び止めてくる。
「……待って。名前、聞いてもいい?」
その問いに、俺は少しだけ考えてから答えた。
「陽翔。太陽の陽に、飛翔の翔……で、普通に、“はると”って読む」
「ひしょうのしょう?」
「羊に羽だよ」
「翔ぶって漢字?」
「そう」
「周りからは、はるくんとか呼ばれてる?」
「いや、全然。普通に呼び捨てか、くん付けかな」
「そっか」
彼女はふわりと、薄く笑った。
それは、どこか“久しぶりに人と話した”ような、寂しげでやさしい笑みだった。
こんなやりとりは何回もしてきた。本来なら飽き飽きしてるはずなのに、なぜかこの時ばかりは俺の心は新鮮さで満たされていた。
「陽翔くんは、2年生だよね」
「うん、そうだよ。ところで、君の名前は?」
「わたしは――」
名前を聞いた気がした。
けれどその瞬間、強い風が吹いて、音がかき消えた。
気づけば彼女は、いつのまにかもう背を向けて歩き出していた。
そして、まるで最初から“そこにはいなかった”かのように、中庭の茂みに溶けていった。
不思議と、怖さはなかった。
ただ――心のどこかが、かすかに揺れた。
誰も接しても、話しても、顔を合わせても、これまでは何も感じなかったのに、今は違う。
まるで何かを忘れていたような。何かを思い出しそうな。
そんな風が、胸の奥を通り抜けていった。
帰り道。
俺はずっと、あの中庭の景色を頭の中で繰り返していた。
言葉にするにはあまりに曖昧で、だけど簡単に忘れてしまうには濃すぎる時間だった。
風の音、彼女の声、視線が合ったときの静けさ――それら全部が、妙に印象に残っている。
考え事をしているうちに、自転車置き場を通り過ぎていた。
徒歩で帰るには少し遠い距離だけど、なんだか今日は引き返すのも億劫で、そのまま歩くことにした。
夕暮れが、少しずつ街を染めていく。
遠くでセミの鳴き声が残っていたが、もうそろそろ夏の終わりを告げているような響きだった。
こんなとき、いつもなら音楽を聴きながら帰る。
けど今日はイヤホンを耳に入れる気になれなかった。
静かなまま歩いていると、風の音や自分の足音がやけに大きく聞こえる。
心の中まで透けてしまいそうで、落ち着かない。
さっきの彼女――名前は聞こえなかった。風にかき消されたから。
それは偶然だったのか。はたまた必然だったのか。
彼女が“誰か”と話していたことも、その“誰か”がこの世にいない存在だったということも、俺には信じられるような、信じられないような。
でも、たった一つだけ確かなことがあった。
――あのとき、俺は確かに惹かれていた。
その理由はわからない。
ただの興味かもしれない。少し変わった子だという好奇心かもしれない。
けどそれ以上に、自分が見えていないものを見ている彼女が、どこか羨ましかった。
俺はずっと、何も見ないようにしてきた。
言いたいことも、思ったことも、心の底に沈めて。
誰にも見せずに、気づかれないようにして。
……それが、彼女には見えている。
誰にも届かないはずの“想い”を、彼女は受け取っていた。
そんな力があるのなら、俺の中に眠っている“言えなかった言葉”も、見えてしまうんじゃないか。
そんな考えが、一瞬よぎった。
でも、すぐに自分でその思考を打ち消す。
「なに考えてんだ、俺は」
そもそも、彼女が言っていたことだって現実味がない。
“想いが見える”なんて、普通なら信じられない話だ。
けれど、あの目を見たとき、どうしても嘘には思えなかった。
――彼女は確かに、そこに”何か”が見えていた。
家に着くころには空が朱に染まり始めていた。
玄関のドアを開けると、リビングからテレビの音が漏れてきた。
「おかえり」と母の声がした。しかし、視線はスマホの画面に向いたまま。
俺は「ただいま」とだけ返して、靴を脱ぎ、自室へ向かった。
自室へ入るなり、鞄を投げてベッドに倒れ込む。
「はぁぁぁ……」
天井を見上げながら深く息を吐いた。
カーテンの隙間から、橙色の光が差し込んでいる。
心なしか、部屋の中が少しだけ静かすぎるように感じた。
――あの子、なんだったんだろう。
ぼんやりと考える。いや、考えてしまう。
無理にでも忘れようとすればするほど、余計に気になってしまう。
名前も、学年も、クラスもわからない。
本当に同じ学校の生徒だったのかさえ、今となっては確信が持てなかった。
でも、あの制服は確かにうちの学校のものだった。
スカートのライン、リボンの色。見間違えるはずがない。
じゃあ、なぜ今まで会ったことがないんだ?
それなりに顔は広い方だと思っていた。
特別目立つタイプではないけれど、人の名前や顔くらいは記憶しているつもりだ。
けれど、あの子だけはどこにも思い出せなかった。
まるで、ぽっかりと空いた空白の中から、急に現れたみたいに。
スマホを手に取って、何の気なしにSNSを開く。
けれど、タイムラインにはどうでもいい投稿ばかりが流れていく。
「今日の自分、天才だった」
「カフェ行ってきた!スイーツ最高」
「課題やってなくて詰んだ」
言葉が軽い。笑って見ていられる。
でも、どこか遠く感じる。
スクロールを止めて、スマホを伏せた。
無音の部屋に戻ると、急にひとりでいることが怖くなった。
誰かに電話をかける気にもなれない。
友達の誰かに「さっきさ、変な子に会ってさ」なんて言っても、きっと笑って終わる。
その笑いに、俺はうまく乗れない気がしていた。
こんな異質な想いを、単なる変わった子との奇怪な出会いという話だけで終わらせたくなかった。
だから、結局、誰にも話せない。
そもそも話したところで誰も本気では聞いてくれない。
――いつも、そうだった。
言葉にしてしまえば、軽くなる。
本当の重さなんて、誰にも伝わらない。
だから俺は、ずっと飲み込んできた。
でも、あの子は違った。
何も言わなくても、何かを知っているような目をしていた。
また会えるだろうか。
そんなことを考えてしまった自分に、少し驚く。
たった一度、数分話しただけ。名前すら聞こえなかった。
それでも、もう一度会いたいと思ってしまった。
理由なんて、きっとどうでもよかった。
あの静かな声が、もう一度聞きたい。ただ、それだけだった。
◇◆◇◆◇
翌日の放課後。
校舎の中は静けさを増していた。
いつものように、教室を出た後の足取りは自然に昇降口へ向かう。
しかし、何も考えずに歩くはずだったその足は、なぜか中庭へと向かっていた。
理由は、今でもわからない。
ただ、何となく――またあの場所に足を運ばずにはいられなかった。
あの日のことが、どこか心の隅に残っていたからだろうか。
自分でも不思議な感覚だった。出会ったのはほんの数分のこと。それなのに、あの彼女の姿や言葉が、まるで心の中で動き続けているように感じていた。
中庭に着いても、やはり彼女の姿はなかった。
静けさだけが広がっている。風が木々を揺らす音が、少しだけ耳に届く。
木陰にあるベンチに腰を下ろし、何気なく空を見上げる。雲ひとつない青空が、なんとも無機質に広がっていた。
そこには、何もない。ただの空白だ。
そんな空間に、なぜか少しだけ居心地の悪さを感じていた。
ふと、ポケットに手を入れてスマホを取り出す。
いつものように、何の考えもなく画面をスワイプしていく。
しかし、目に入るのは、他人のささいなつぶやきや、ただの食事報告。
どれも、無意味ではないけれど、心には届かない。
俺はどこに向かっているのだろう。
なんとなく、そんな思いが頭を過る。
振り返ると、やはりあの場所は静まり返っている。誰もいない。
あの彼女が話していた“誰か”は、本当にどこかにいたのだろうか。
――“見えることがある”と彼女は言った。
見えないものを見ている彼女を、俺は不思議に思った。
そして、もう一度あの言葉を反芻する。
――“想い”が残っているときだけ、見える。
その言葉の意味は、未だに腑に落ちない。
でも、俺は心のどこかで、あの時の彼女の目が本物だと感じていた。
何かを見ている、その目に、嘘がないように思えた。
再び、俺はスマホを手に取る。
画面を見つめると、SNSで流れてくる一つ一つの通知が、なんだか空疎に感じる。
そうだ、昨日もこんなことがあった。
昼休みに、ふと声をかけた誰かがいた。
でも、俺の返事に誰も反応しなかった。
あの時、俺はその会話の中で完全に“存在感”を消していた気がした。
ちょっとした一言を発したつもりが、そのままスルーされて、他の誰かが割って入ってきてしまう。
まるで、俺がいなくても構わないように、周囲はそのまま自分たちの会話を続けていた。
そこで俺は痛感した。
ああ、俺って、こういう“透明人間”みたいな存在だったんだな……と。
小さな嘆きのようなものが胸の中に浮かぶ。
結局、俺は数十分間じっと彼女のことを待ってみたが、彼女が現れることはなかった。
「……彼女は何が見えていたんだろう」
俺は彼女が立っていた位置に立った。
何も見えない、何も聞こえない、何も感じない。
行っちゃった、と言っていたから、もしかしたらもうここには何もないのかもしれない。
じゃあ、また別の場所に行けばそれがあるのか?
俺は疑問を呈してみたけど、答えなんて出るわけがなかった。
かくして、俺は彼女の捜索を諦めて家に帰ったのだった。
諦めて家に帰ると、母が夕食の支度をしていた。
台所から聞こえる音が、リズムよく響いている。
「おかえり」と軽く言われ、俺はただ「ただいま」と返した。いつもの光景だ。変哲とない、ごく普通のやり取りだ。
その後、また何気ない会話が続いた。
「今日は何かあった?」
「うん、特に。普通だった」
「そう。じゃあ、早く食べてお風呂入ってね」
母はそれだけいうとリビングからいなくなった。
いつものこと、これはいつものこと、しかし、なぜか今日だけはそのいつものことが奇妙に思えた。
「ね、ねぇ」
「ん? どしたの?」
「……あ、いや、やっぱりなんでもない」
「あらそう? 疲れてるなら早く寝るのよ」
母は俺に話しかけられて驚いていたが、すぐに元通りになった。
これもまた、いつものことのはずだった。
家では寡黙な俺が話しかけると、母は少し驚きながら接してくれる。だから、違和感なんて芽生えるはずがない。
しかし、今は心の中に引っかかる違和感が、どんどん大きくなっていった。
俺は、どうしてこんなにも、どこかで“誰かに見られたかった”って思ってるんだろう?
こんなにも、誰かに言葉を返してほしいと思っていたのか?
母との会話が終わってしまった瞬間に、心は穴が空いたように空虚になった。
誰にでもこの感覚はあるのだろうか?
他人の中に、自分の居場所があると感じたことがあるだろうか?
あの彼女は、中庭で何を見ていたんだろう。
そして、俺は一体、何を見ているんだろう。
何を望んでいるんだろう。
思考しながらも夕食を食べ終わり、部屋に戻ると、いつも通りベッドに倒れ込む。
でも今日は違った。
なんとなく、寝られなかった。
目を閉じても、彼女のことが頭を離れない。
――また、会えるだろうか。
そんなことを思っていた。
ただ、何となく、無意識のうちに彼女を探し続けているような気がしてならなかった。
◇◆◇◆◇
再び、彼女と出会ったのは、偶然――というには、あまりにも静かすぎる午後だった。
秋の匂いが、校舎の石畳を伝ってゆっくりと流れてくる。
その日は朝から空気が澄んでいて、授業中の窓から見えた空は妙に遠く感じた。
放課後、鞄を肩にかけたまま、俺はなんの気無しに校舎の裏手、古い講堂の脇にある、使われなくなった中庭に足を運んでいた。
普段は人気もなく、落ち葉ばかりが目立つ、忘れられたような空間だった。
中庭とはまた違う空気がある。
ふとその場所を通りかかったとき、風の中に声が混じった。
「っ!」
俺はハッと息を呑んで耳を澄ませた。
「……ここじゃ、なかったんだね」
小さな声が聞こえてきた。集中しないと絶対に聞こえないほどの、細くて透き通るような声だ。
俺は間違いなくこの声に聞き覚えがあった。
中庭を進んで、ふと視線を向けると、いた。
前と変わらぬ制服姿、ほどけかけたリボン。
黒髪が風にそよいで、陽の光に淡く透けていた。
普段はそんな真似しないのに、その時の俺は距離を詰めて声をかけていた。
「また、何かを見ていたの?」
そう問いかけた俺に、彼女はくるりと振り向いた。
あの日と同じ、静かな目だった。
だけど、あの日よりも、ほんのわずかにだけ“人間味”を帯びているように見えた。
「うん。たぶん、ちょっとだけ迷ってた」
「迷ってた?」
「……ここにいた人の“想い”が、どこかに行きかけてたから。まだ残ってるのか、もう消えたのか、わからなくなったの」
何を言っているのか、最初はやっぱり理解できなかった。
しかし、彼女の言葉を頭の中でなぞるうちに、ふと気づく。
「“想い”って……そうやって、探したり見るものなの?」
彼女は小さく笑った。
風が、その笑みに乗って流れていく。
「そういうのが残ってると、私は声が聞こえることがあるの。でも、ちゃんと届いた想いは、もう何も言わない」
「声って……誰の?」
「わからない。誰かが言えなかったことだったり、伝えきれなかったことだったり。ここに残る“なにか”の一部みたいなもの。それは形には残らないけど、想いとして残る」
彼女はまるで、目の前に見えない誰かを追いかけるように、ふわりと歩いた。
枯れ葉が舞い、足元に散る。
その光景が、妙に現実離れして見えた。
彼女は落ち葉を枯葉を踏み締めて少し歩き回ると、唐突にこちらに振り返ってきた。
「……君も、何かを探してるよね?」
彼女からのその問いに、俺は言葉を返せなかった。
何を探してるかなんて、自分でもわからなかった。
ただ、ここ最近、心の奥が少しずつ軋んでいるような感覚だけがあって。
それが何なのか、ずっと考えているのに答えが出ない。
「言えなかったことがある人ってね。自分でも気づいてないことが多いんだよ」
彼女がぽつりと呟く。
俺の胸が、ほんの少しだけざわついた。
「自分の中にあるのに、無かったことにしてたり、閉じ込めてたり。そうしてるうちに心のどこかにひっそり沈んで……でも、忘れたふりをしても、なくなったりはしない。必ずどこかに残ってるんだよ」
「……」
俺はざわつく胸に手を当て無言で俯いた。
「君も、あるんだね、忘れられないことや言えなかったことが、胸の中に……」
「わからない。でも……最近はモヤモヤしてるかも。心が落ち着かないっていうか、納得できないことが多いかな」
「納得できない? 誰に?」
「――自分自身にだよ」
「そっか。ずっと隠してきたんだね」
彼女の声色は優しいのに、鋭く胸に刺さるようだった。
まるで俺の奥底にしまい込んでいたものを、見透かしているようだった。
全てを知られているような、そんな感覚だった。
「陽翔くんは……まだ、止まったままなんだよ」
「……止まったまま?」
思わず聞き返す。まるで俺の過去を見通しているかのような口ぶりだった。
でも彼女は、それ以上は何も言わなかった。
ただ静かに、俺の方を見ていた。
その綺麗な目には、動揺する俺が反射していた。
思わず俺は視線を逸らした。そして止まったままの自分を考えた。
心の奥に、沈んだ記憶がある。
誰にも言ってこなかったこと。
俺が、言えなかった言葉。
あの日、言えばよかった言葉。
でも、言えなかった。言わなかった。
それがすべての始まりで、終わりだった。
今の俺を形成したすべてだった。
俺はそれを忘れようとして、心の奥底に封じ込めてきた。
ずっと思い出さないようにしてきた。
しかし、たった今、彼女に言われてそれが徐々に表出し始めていることに気がついた。
「……ぁ」
彼女は俺の沈黙を責めなかった。
ただ、落ち葉の上で立ち止まり、風を受けていた。
「言えなかったことがあるなら、それはまだ、ここにあるんだよ。残り続けてるんだよ。それはいつか後悔になって、心を蝕んじゃうの。もしかしたらもう後悔してるかもしれない、人はすぐにダメになる。強いと思っていても、実は弱い生き物なんだよね」
「……君は何者なの?」
思わず漏れたその問いに、彼女はふっと微笑んだ。
「わたしは……たまたま、“そういうの”が見えたり感じちゃうだけの普通の人間だよ」
「おかしな力だね」
「うん。でもね、この力はきっと有限なの。わたしが変わった時点で失われちゃうんだよ」
その言葉が俺の胸を静かに打った。
理由はわからない。
でも、今の言葉だけは、なぜか嘘じゃないと、そう思えた。
「ねえ、陽翔くん。君は自分の言葉を誰かに渡したいと思ったことある?」
渡したい? 言葉を? 誰かに?
答えはすぐに出なかった。
でも、あのときの光景が、ふいに脳裏に浮かんだ。
これまでは封じ込めてきたつもりだったのに、唐突に記憶が蘇る。
中学の頃、あの日、あの放課後。
俺は、誰かの背中を見ていた。
でも、声をかけなかった。
呼べなかった名前が、ひとつだけあった。
その名前を、口に出したことはあの日を境に一度もない。
「……どうだろう」
俺はぼそりとそれだけ返した。本当はわかっているはずなのに。
彼女はそれ以上何も言わなかった。
ただ、笑っていた。
そして風が吹いた。
落ち葉が舞い上がり、彼女の姿がその中に溶けていく。
きっと声をかけなければ、このまま彼女またいなくなってしまうような気がした。
「あ、えっと……名前、もう一度聞いてもいい?」
俺は咄嗟に話しかけた。
失礼なのは承知だったけど、彼女は目をぱちりと見開き、それから小さく頷いてくれた。
「……そっか、わたしの名前を知りたいんだね」
「うん、昨日は風が強かったからか聞き逃しちゃったんだ」
「風、強かったもんね。じゃあもう一度言うよ。わたしの名前は、未透。未完成の“未”に、透明の“透”って書いて、“みとう”と読む」
今日は彼女の名前がはっきり聞こえた。
「未透、か」
そんな珍しい名前の響きが、彼女の雰囲気に妙に合っていた。
どこか空気のようで、でも確かに“そこにいる”という存在感。
見えているのに、どこか遠い。手を伸ばせば触れられそうで、でも触れたら消えてしまいそうな。
名前だけではなく、その容姿もまた特徴的だった。
黒髪は肩の下までまっすぐに伸びていた。
その肌は透けるように白く、日差しを受けても影を落とさないほどだった。
線の細い腕と、少し大きめに見える制服のせいで、彼女がどこかこの世界の“手触り”から離れているように思えた。
でも、不自然さというより、静かな輪郭のようなものだった。
……どこか、少しだけ儚い印象を受けた。
「わたしの顔に何かある? 昨日も見てた気がする」
「いや、特に……ただ見てただけだよ」
他意はない。本当にただ見てただけだ。俺は彼女のように”何か”が見えたり感じられるわけではないから。
「ねぇ、陽翔くん」
「なに、未透さん」
唐突に名前を呼ばれたから、俺は名前を呼び返した。
すると、彼女はくるりと回って俺の目を見つめてきた。
「……見つかるといいね、探しもの」
俺は心臓を両手で包まれるような感覚に陥った。
何も言えず固まり、ふと我に返った時には、既に彼女の姿はなかった。
俺は一人、中庭に取り残された。
だけど、なぜか寂しくはなかった。
胸の奥で、なにかが静かに、揺れていた。
止まったままの自分の時間が、ほんのわずかに――微かに、動いたような気がした。
雲ひとつない晴天で、風も穏やか。
天気予報では「初夏の陽気」なんて言ってたけど、俺にとってはただの“今日”だ。
特別でも、退屈でもない。
いつも通りの一日が始まる、ただそれだけの朝。
「おはよー、陽翔! 今日もさわやかイケメンじゃん」
校門の前で手を振ってきたのは、同じクラスの委員長だった。男子だ。
こいつはいいやつだけど声がでかい。
あと、俺は別にイケメンじゃない。黒髪の前髪が目元に少しだけかかっていて、どこか頼りない印象を与えているし、昔から「静かそうだね」と言われることが多い。それはきっと、このちょっと暗い表情のせいだと思う。
まして身長も平均的だ。人付き合いだって無難を選んで生きているから、日頃から笑って受け流すのがもう習慣になってる。
「おはよ、いや、今日なんか寝癖ひどいし……」
「謙遜しすぎ~。てかさ、昨日の課題やった? 俺、ガチで忘れててさ」
「んー……出したよ。ま、写してもバレない程度になら貸すけど」
「マジ神!」
俺は鞄からノートを取り出して渡す。大志は何度も頭を下げて感謝してくる。こうして、いつも通りの“いい奴”を演じる。別に悪い気はしない。けど、心が動くわけでもない。
――いつも、こんな感じだ。
無難に話を合わせて、角を立てずに過ごす。誰とも深く関わらず、けど孤立もせず、クラスの中に自然と溶け込んでいる。誰も俺を“演じてる”なんて思ってない。俺がそう思わせないようにしてるから。
“空気を読む”っていうのは、ある意味才能だ。気まずくならないように、相手の表情と言葉を見て、最適解を口にする。そうすれば、争いは起きない。嫌われることもない。誰も傷つかない。
――ただ、俺のことも誰も知らない。
知ってほしいとも、思わない。
でも時々、全部ぶち壊したくなる衝動が、ふと湧いてくることがある。
教室に入った瞬間、湿度のない賑やかさが肌にまとわりついた。
ガヤガヤと笑い声が飛び交い、誰かの机に集まってスマホを見せ合うグループ。
教科書を開いているのに全然進んでなさそうな自習組。
ぼーっと窓の外を眺めているやつもいれば、寝癖のまま突っ伏してるやつもいる。
俺は、そのどれでもない。
だけど、そのどれにでも“なれる”。
「おはよ、陽翔くん」
前の席の佐伯がふと振り返り、小さく手を振ってきた。
茶髪を一つにまとめたポニーテールがふわりと揺れる。声も仕草も、相変わらず柔らかい。
「おはよ」
俺は微笑んで返す。たったそれだけ。
彼女とは特別仲がいいわけじゃない。
けれど、誰よりも遠いわけでもない。
佐伯はにこっと笑って、また女子グループの輪に戻っていった。
すぐに、他の話題に紛れて俺の存在は霞んでいく。
……そう、それでいい。
それが、いつもの日常だ。
昼休みになると、
「ねえ、陽翔。今度の体育祭の実行委員、やらない?」
パンを頬張りながら、杉下が話しかけてきた。
彼は学級委員で、先生からの信頼も厚い“リーダー格”だ。
その口ぶりは一見フランクだけど、断られることを前提にしてない空気がにじんでいた。
俺の“断らない性格”を、知っていた上で言っている。
「うん、いいよ。特に予定ないし」
「マジ助かる! やっぱ陽翔、そういうとこ神~!」
その一言で、また教室の空気が流れる。
別の話題へ。別の関心へ。
俺はその流れを、ただ見送る。
そうして俺は、また“いい奴”のまま一日を消化していく。
悪くない。
誰からも嫌われず、トラブルもなく、表面上は順調な毎日。
だけど……時々、どうしようもなく、息が詰まる瞬間がある。
他愛もない会話をしている最中に、ふと。
教室の中の誰かが笑ってる、その声が急に遠くに聞こえる。
自分の声だけが、よそよそしく反響してくるような気がする。
まるで、ここにいながら、どこにもいないみたいな――そんな、変な感覚。
俺の“本当”は、どこにあるんだろう。
それを誰かに話したことなんて、一度もない。
……いや、違う。一度だけ、ある。
たった一人だけ。俺の“本音”に近づいてきた人がいた。
俺はそれを受け止めた。しかし……あの悲劇に繋がった。
頭の奥が痛む。思い出しかけた映像を、意識的に押し戻す。
見ないようにしてきた。忘れようとしてきた。
今さら掘り返したところで、何も変わらない。
「ねえ、陽翔くん。あんた、断らなさすぎじゃない?」
昼休みの終わり、佐伯がふと口にした。
からかうような口調だったけど、少しだけ本気っぽかった。
「“何でも受け入れてくれる便利な人”って、定着しちゃうと損だよ」
「そうかな?」と笑いながら答えたけど、心の中には何か引っかかるものが残った。
たぶん、彼女は悪気があったわけじゃない。
ただ、ちょっとした気づきとして言っただけ。
けれどそれは、俺がずっと見ないふりをしてきた部分を、思いがけず突かれたような気がした。
自分を守るために選んだ“無難”な振る舞い。
けれど、それを続けるたびに、何かがすり減っていく感覚がある。
それに名前はつけられない。ただ、確実に削られている。
ホームルームが終わり、教室から生徒が一人、また一人と出ていく。
気がつけばもう下校時刻だ。今日も何もなく学校が終わった。
俺も鞄を持ち、立ち上がると、足早に昇降口へ向かった。
靴箱で並ぶ足音。
うしろに人がいる気配がしたから、少しだけ身体をずらした。
ぶつからないように、さりげなく。
声をかけられる前に、軽く会釈をしておく。
たぶん名前も顔も知ってるはずだけど、記憶には残っていない。
相手もきっと、俺をそう思ってる。
靴を履いて立ち上がると、前から誰かが走ってきた。
俺は避けるように、一段ずれて右側を歩いた。
昇降口のドアを開けるとき、向こう側に誰かの気配がしたから、ドアノブを半秒だけゆっくり回した。
ふと、すれ違う誰かが俺に向かって軽く手を振った。
名前を思い出せなかったけど、とりあえず笑って返した。
それは、いつも通りの動きだった。
誰かの邪魔にならないように。誰にも不快感を与えないように。
波風を立てずに、ただ通り過ぎていくための所作。
それを意識してるつもりはなかったけど、気づけば毎日、無意識にそうしている。
それが俺の日常だった。
翌日の昼休み。
教室の隅で誰かが相談事をしていた。
「それなら、あっちに頼んだほうがいいんじゃない?」
「ああ、でもあいつも忙しいって言ってたし」
「じゃあ……」
声が小さくなる。
すると、視線が、ちらっと俺のほうへ向いたのがわかった。
俺はその瞬間、わずかに笑ってうなずいた。
「俺でよかったら」
その言葉を口に出す前に、相手は少しほっとした顔をしていた。
もう“そうなる”ってわかってたんだろう。
俺が断らないこと。笑って受け入れること。
別に嫌なわけじゃない。面倒なことが好きなわけでもないけど、断る理由を探すほうが疲れる。
「助かる」って言われるたびに、自分の価値がそこにあるような気がして、安心する。
気づかれないように、輪の中に入りすぎないように。
でも、輪の外にも出ないように。
ぴったりとした中間地点に、俺はいつも立っている。
「ねえ、どっちが似合うと思う?」
次はクラスメイトの女子がカラフルなハンカチを見せてきた。
二枚あるそれは、どちらも似たような柄に見える。
正直、どっちでもいい、なんて言ったら空気が壊れる。
だから数秒考えるふりをして、「こっち、かな」と答える。
「やっぱり? 私もそう思ってた!」
彼女は「ありがとねっ!」と言って立ち去った。
そこに俺への好意はない。単にその場にいたから聞かれたに過ぎない。
ごくごく自然な当たり障りのない会話。俺の返答や思考は明瞭な適当さがあったから、無難な会話が容易に成立する。
いつからだろうか、俺がこうして本音を隠して無難に逃げるようになったのは。言いたいことを言えずに、周りを気にしながら過ごすようになったのは。
高校2年生になったっていうのに、俺は俺でいることを諦めてしまっていた。
だが、それでいい。
誰も、俺の“本当”なんて気にしない。
俺も、自分の“本当”を気にしない。
それが無難に過ごした結果、辿り着いた答えだった。
別に、誰かに好かれたいわけじゃない。
嫌われるのが怖いだけでもない。
ただ、何も起きないように。
誰かの感情に、波を立てないように。
それが、習慣になっていた。
俺は“色のない誰か”を演じている。
それが、楽だった。
何も知られないというのは、安心だった。
ただ、夜になると、ときどき思い出す。
あの時、言いたかった言葉。
あの時、言えなかった言葉。
飲み込んで、忘れたふりをして、どこにも置き場のない感情たち。
それでも、俺は“いい奴”のまま、今日を終える。
◇◆◇◆
放課後の校舎は、朝や昼とは違う匂いがする。
どこか冷たく、静かで、音の輪郭がくっきりと浮かぶような――そんな空気。
俺は帰り支度を終えたはずなのに、気がつけば俺は昇降口を通り過ぎていた。
明確な理由なんてなかった。ただ、少しだけ一人になりたかった。
ざわざわした教室から抜け出した身体が、勝手に別の場所を求めていた。
渡り廊下を抜け、人気のない中庭に足を向ける。
誰もいないはずの、その場所で。
――誰かの声が、聞こえた。
「……ごめんねなんて思う必要はないよ。十分助けられたから、だからもう自分を悔やまないで?」
最初、独り言かと思った。
でも、その声には確かに“誰かに話しかけている”響きがあった。いや、話しかけているというよりは、語りかけるような……自分の心に問いて処理しているような感じだった。
ふと立ち止まり、声のするほうに視線を向ける。
茂った植え込みの向こう。
木陰に立つ彼女の背中が見えた。
肩より少し下まで伸びた黒髪が、風に揺れている。
制服のリボンがほどけかけていて、鞄も持っていない。
まるで、ここが自分の居場所であるかのように、自然に佇んでいた。
「うん。大丈夫、ちゃんと覚えてる……だから、もう、いいんだよ」
小さな声は、やさしい響きを帯びていた。
まるで幼い子供に接するような声色だ。
しかし、それは人間に向けられているものには思えなかった。
目に見えない“誰か”を相手にしているようだった。
俺は一歩だけ踏み出した。
その足音に、彼女がふいにこちらを振り返る。
目が合った。
その瞬間、胸の奥がきゅっと締めつけられた。
驚いたような、でも怯えているわけでもない。
どこか静かで、湖面のような眼差し。
「あ……ごめん。誰かと、話してるのかと思って」
気まずさを隠すように声をかけると、彼女は一瞬黙ってから、小さく首を振った。
「ううん、大丈夫。もう済んだから」
「済んだ?」
「うん。さっきまで、ここにいたの。でも……もう、いなくなったみたい」
俺は返す言葉を探したが、何も思いつかなかった。
その受け答えは、あまりに不思議で、現実味がなかった。
でも、彼女の声には嘘がなかった。
ただまっすぐに、そこにある事実だけを伝えるような、そんな声音だった。
「……誰か、見えてたの?」
気づけば、口が勝手に動いていた。
彼女は少しだけ目を細めて、空を見上げた。
そして、ぽつりと、こう言った。
「わたしはそこに“誰かの想い”が残ってるときだけ、時々見えることがあるの。だから、見えるときもあれば、見えないときもある」
その言葉の意味を、すぐに理解することはできなかった。
けれど、彼女の目に映る何かが俺には見えないものだということだけは、妙にリアルに感じられた。
あの世でもこの世でもない、別世界の”何か”が見えているようだった。
「……そっか」
そう言って、俺はその場を離れようとした。
関わるのが億劫だったのかもしれない。
でも、背中越しに小さな声が届く。
「ねぇ」
立ち止まる。
「いつもここには誰も来ないのに……君は見てたんだね、わたしのこと」
振り返ると、彼女はまだ同じ場所に立っていた。
でも、その表情には不思議なほど動揺がなかった。
むしろ妙な笑みを浮かべていた。まさか見られていたことを喜んでいる? どうして?
そもそもこんな場所で誰と何を話していたんだろう?
俺は色々な疑問を胸中で思案したけど、いくら考えても答えは見つからなかった。
ただ一つ思ったことがある。この人は変わった雰囲気を持っている。
他の誰とも違う、触れると簡単に壊れてしまいそうな……だけれど、心の奥には確かな強さがあって、無難を選択して過ごす俺とはまるで違う存在だった。
「どうしたの?」
「っ……ごめん、もう行くね」
じろじろ見てしまっていたようだ。
気恥ずかしくなった俺はその場から逃げるように立ち去ろうとした。しかし、またも彼女が呼び止めてくる。
「……待って。名前、聞いてもいい?」
その問いに、俺は少しだけ考えてから答えた。
「陽翔。太陽の陽に、飛翔の翔……で、普通に、“はると”って読む」
「ひしょうのしょう?」
「羊に羽だよ」
「翔ぶって漢字?」
「そう」
「周りからは、はるくんとか呼ばれてる?」
「いや、全然。普通に呼び捨てか、くん付けかな」
「そっか」
彼女はふわりと、薄く笑った。
それは、どこか“久しぶりに人と話した”ような、寂しげでやさしい笑みだった。
こんなやりとりは何回もしてきた。本来なら飽き飽きしてるはずなのに、なぜかこの時ばかりは俺の心は新鮮さで満たされていた。
「陽翔くんは、2年生だよね」
「うん、そうだよ。ところで、君の名前は?」
「わたしは――」
名前を聞いた気がした。
けれどその瞬間、強い風が吹いて、音がかき消えた。
気づけば彼女は、いつのまにかもう背を向けて歩き出していた。
そして、まるで最初から“そこにはいなかった”かのように、中庭の茂みに溶けていった。
不思議と、怖さはなかった。
ただ――心のどこかが、かすかに揺れた。
誰も接しても、話しても、顔を合わせても、これまでは何も感じなかったのに、今は違う。
まるで何かを忘れていたような。何かを思い出しそうな。
そんな風が、胸の奥を通り抜けていった。
帰り道。
俺はずっと、あの中庭の景色を頭の中で繰り返していた。
言葉にするにはあまりに曖昧で、だけど簡単に忘れてしまうには濃すぎる時間だった。
風の音、彼女の声、視線が合ったときの静けさ――それら全部が、妙に印象に残っている。
考え事をしているうちに、自転車置き場を通り過ぎていた。
徒歩で帰るには少し遠い距離だけど、なんだか今日は引き返すのも億劫で、そのまま歩くことにした。
夕暮れが、少しずつ街を染めていく。
遠くでセミの鳴き声が残っていたが、もうそろそろ夏の終わりを告げているような響きだった。
こんなとき、いつもなら音楽を聴きながら帰る。
けど今日はイヤホンを耳に入れる気になれなかった。
静かなまま歩いていると、風の音や自分の足音がやけに大きく聞こえる。
心の中まで透けてしまいそうで、落ち着かない。
さっきの彼女――名前は聞こえなかった。風にかき消されたから。
それは偶然だったのか。はたまた必然だったのか。
彼女が“誰か”と話していたことも、その“誰か”がこの世にいない存在だったということも、俺には信じられるような、信じられないような。
でも、たった一つだけ確かなことがあった。
――あのとき、俺は確かに惹かれていた。
その理由はわからない。
ただの興味かもしれない。少し変わった子だという好奇心かもしれない。
けどそれ以上に、自分が見えていないものを見ている彼女が、どこか羨ましかった。
俺はずっと、何も見ないようにしてきた。
言いたいことも、思ったことも、心の底に沈めて。
誰にも見せずに、気づかれないようにして。
……それが、彼女には見えている。
誰にも届かないはずの“想い”を、彼女は受け取っていた。
そんな力があるのなら、俺の中に眠っている“言えなかった言葉”も、見えてしまうんじゃないか。
そんな考えが、一瞬よぎった。
でも、すぐに自分でその思考を打ち消す。
「なに考えてんだ、俺は」
そもそも、彼女が言っていたことだって現実味がない。
“想いが見える”なんて、普通なら信じられない話だ。
けれど、あの目を見たとき、どうしても嘘には思えなかった。
――彼女は確かに、そこに”何か”が見えていた。
家に着くころには空が朱に染まり始めていた。
玄関のドアを開けると、リビングからテレビの音が漏れてきた。
「おかえり」と母の声がした。しかし、視線はスマホの画面に向いたまま。
俺は「ただいま」とだけ返して、靴を脱ぎ、自室へ向かった。
自室へ入るなり、鞄を投げてベッドに倒れ込む。
「はぁぁぁ……」
天井を見上げながら深く息を吐いた。
カーテンの隙間から、橙色の光が差し込んでいる。
心なしか、部屋の中が少しだけ静かすぎるように感じた。
――あの子、なんだったんだろう。
ぼんやりと考える。いや、考えてしまう。
無理にでも忘れようとすればするほど、余計に気になってしまう。
名前も、学年も、クラスもわからない。
本当に同じ学校の生徒だったのかさえ、今となっては確信が持てなかった。
でも、あの制服は確かにうちの学校のものだった。
スカートのライン、リボンの色。見間違えるはずがない。
じゃあ、なぜ今まで会ったことがないんだ?
それなりに顔は広い方だと思っていた。
特別目立つタイプではないけれど、人の名前や顔くらいは記憶しているつもりだ。
けれど、あの子だけはどこにも思い出せなかった。
まるで、ぽっかりと空いた空白の中から、急に現れたみたいに。
スマホを手に取って、何の気なしにSNSを開く。
けれど、タイムラインにはどうでもいい投稿ばかりが流れていく。
「今日の自分、天才だった」
「カフェ行ってきた!スイーツ最高」
「課題やってなくて詰んだ」
言葉が軽い。笑って見ていられる。
でも、どこか遠く感じる。
スクロールを止めて、スマホを伏せた。
無音の部屋に戻ると、急にひとりでいることが怖くなった。
誰かに電話をかける気にもなれない。
友達の誰かに「さっきさ、変な子に会ってさ」なんて言っても、きっと笑って終わる。
その笑いに、俺はうまく乗れない気がしていた。
こんな異質な想いを、単なる変わった子との奇怪な出会いという話だけで終わらせたくなかった。
だから、結局、誰にも話せない。
そもそも話したところで誰も本気では聞いてくれない。
――いつも、そうだった。
言葉にしてしまえば、軽くなる。
本当の重さなんて、誰にも伝わらない。
だから俺は、ずっと飲み込んできた。
でも、あの子は違った。
何も言わなくても、何かを知っているような目をしていた。
また会えるだろうか。
そんなことを考えてしまった自分に、少し驚く。
たった一度、数分話しただけ。名前すら聞こえなかった。
それでも、もう一度会いたいと思ってしまった。
理由なんて、きっとどうでもよかった。
あの静かな声が、もう一度聞きたい。ただ、それだけだった。
◇◆◇◆◇
翌日の放課後。
校舎の中は静けさを増していた。
いつものように、教室を出た後の足取りは自然に昇降口へ向かう。
しかし、何も考えずに歩くはずだったその足は、なぜか中庭へと向かっていた。
理由は、今でもわからない。
ただ、何となく――またあの場所に足を運ばずにはいられなかった。
あの日のことが、どこか心の隅に残っていたからだろうか。
自分でも不思議な感覚だった。出会ったのはほんの数分のこと。それなのに、あの彼女の姿や言葉が、まるで心の中で動き続けているように感じていた。
中庭に着いても、やはり彼女の姿はなかった。
静けさだけが広がっている。風が木々を揺らす音が、少しだけ耳に届く。
木陰にあるベンチに腰を下ろし、何気なく空を見上げる。雲ひとつない青空が、なんとも無機質に広がっていた。
そこには、何もない。ただの空白だ。
そんな空間に、なぜか少しだけ居心地の悪さを感じていた。
ふと、ポケットに手を入れてスマホを取り出す。
いつものように、何の考えもなく画面をスワイプしていく。
しかし、目に入るのは、他人のささいなつぶやきや、ただの食事報告。
どれも、無意味ではないけれど、心には届かない。
俺はどこに向かっているのだろう。
なんとなく、そんな思いが頭を過る。
振り返ると、やはりあの場所は静まり返っている。誰もいない。
あの彼女が話していた“誰か”は、本当にどこかにいたのだろうか。
――“見えることがある”と彼女は言った。
見えないものを見ている彼女を、俺は不思議に思った。
そして、もう一度あの言葉を反芻する。
――“想い”が残っているときだけ、見える。
その言葉の意味は、未だに腑に落ちない。
でも、俺は心のどこかで、あの時の彼女の目が本物だと感じていた。
何かを見ている、その目に、嘘がないように思えた。
再び、俺はスマホを手に取る。
画面を見つめると、SNSで流れてくる一つ一つの通知が、なんだか空疎に感じる。
そうだ、昨日もこんなことがあった。
昼休みに、ふと声をかけた誰かがいた。
でも、俺の返事に誰も反応しなかった。
あの時、俺はその会話の中で完全に“存在感”を消していた気がした。
ちょっとした一言を発したつもりが、そのままスルーされて、他の誰かが割って入ってきてしまう。
まるで、俺がいなくても構わないように、周囲はそのまま自分たちの会話を続けていた。
そこで俺は痛感した。
ああ、俺って、こういう“透明人間”みたいな存在だったんだな……と。
小さな嘆きのようなものが胸の中に浮かぶ。
結局、俺は数十分間じっと彼女のことを待ってみたが、彼女が現れることはなかった。
「……彼女は何が見えていたんだろう」
俺は彼女が立っていた位置に立った。
何も見えない、何も聞こえない、何も感じない。
行っちゃった、と言っていたから、もしかしたらもうここには何もないのかもしれない。
じゃあ、また別の場所に行けばそれがあるのか?
俺は疑問を呈してみたけど、答えなんて出るわけがなかった。
かくして、俺は彼女の捜索を諦めて家に帰ったのだった。
諦めて家に帰ると、母が夕食の支度をしていた。
台所から聞こえる音が、リズムよく響いている。
「おかえり」と軽く言われ、俺はただ「ただいま」と返した。いつもの光景だ。変哲とない、ごく普通のやり取りだ。
その後、また何気ない会話が続いた。
「今日は何かあった?」
「うん、特に。普通だった」
「そう。じゃあ、早く食べてお風呂入ってね」
母はそれだけいうとリビングからいなくなった。
いつものこと、これはいつものこと、しかし、なぜか今日だけはそのいつものことが奇妙に思えた。
「ね、ねぇ」
「ん? どしたの?」
「……あ、いや、やっぱりなんでもない」
「あらそう? 疲れてるなら早く寝るのよ」
母は俺に話しかけられて驚いていたが、すぐに元通りになった。
これもまた、いつものことのはずだった。
家では寡黙な俺が話しかけると、母は少し驚きながら接してくれる。だから、違和感なんて芽生えるはずがない。
しかし、今は心の中に引っかかる違和感が、どんどん大きくなっていった。
俺は、どうしてこんなにも、どこかで“誰かに見られたかった”って思ってるんだろう?
こんなにも、誰かに言葉を返してほしいと思っていたのか?
母との会話が終わってしまった瞬間に、心は穴が空いたように空虚になった。
誰にでもこの感覚はあるのだろうか?
他人の中に、自分の居場所があると感じたことがあるだろうか?
あの彼女は、中庭で何を見ていたんだろう。
そして、俺は一体、何を見ているんだろう。
何を望んでいるんだろう。
思考しながらも夕食を食べ終わり、部屋に戻ると、いつも通りベッドに倒れ込む。
でも今日は違った。
なんとなく、寝られなかった。
目を閉じても、彼女のことが頭を離れない。
――また、会えるだろうか。
そんなことを思っていた。
ただ、何となく、無意識のうちに彼女を探し続けているような気がしてならなかった。
◇◆◇◆◇
再び、彼女と出会ったのは、偶然――というには、あまりにも静かすぎる午後だった。
秋の匂いが、校舎の石畳を伝ってゆっくりと流れてくる。
その日は朝から空気が澄んでいて、授業中の窓から見えた空は妙に遠く感じた。
放課後、鞄を肩にかけたまま、俺はなんの気無しに校舎の裏手、古い講堂の脇にある、使われなくなった中庭に足を運んでいた。
普段は人気もなく、落ち葉ばかりが目立つ、忘れられたような空間だった。
中庭とはまた違う空気がある。
ふとその場所を通りかかったとき、風の中に声が混じった。
「っ!」
俺はハッと息を呑んで耳を澄ませた。
「……ここじゃ、なかったんだね」
小さな声が聞こえてきた。集中しないと絶対に聞こえないほどの、細くて透き通るような声だ。
俺は間違いなくこの声に聞き覚えがあった。
中庭を進んで、ふと視線を向けると、いた。
前と変わらぬ制服姿、ほどけかけたリボン。
黒髪が風にそよいで、陽の光に淡く透けていた。
普段はそんな真似しないのに、その時の俺は距離を詰めて声をかけていた。
「また、何かを見ていたの?」
そう問いかけた俺に、彼女はくるりと振り向いた。
あの日と同じ、静かな目だった。
だけど、あの日よりも、ほんのわずかにだけ“人間味”を帯びているように見えた。
「うん。たぶん、ちょっとだけ迷ってた」
「迷ってた?」
「……ここにいた人の“想い”が、どこかに行きかけてたから。まだ残ってるのか、もう消えたのか、わからなくなったの」
何を言っているのか、最初はやっぱり理解できなかった。
しかし、彼女の言葉を頭の中でなぞるうちに、ふと気づく。
「“想い”って……そうやって、探したり見るものなの?」
彼女は小さく笑った。
風が、その笑みに乗って流れていく。
「そういうのが残ってると、私は声が聞こえることがあるの。でも、ちゃんと届いた想いは、もう何も言わない」
「声って……誰の?」
「わからない。誰かが言えなかったことだったり、伝えきれなかったことだったり。ここに残る“なにか”の一部みたいなもの。それは形には残らないけど、想いとして残る」
彼女はまるで、目の前に見えない誰かを追いかけるように、ふわりと歩いた。
枯れ葉が舞い、足元に散る。
その光景が、妙に現実離れして見えた。
彼女は落ち葉を枯葉を踏み締めて少し歩き回ると、唐突にこちらに振り返ってきた。
「……君も、何かを探してるよね?」
彼女からのその問いに、俺は言葉を返せなかった。
何を探してるかなんて、自分でもわからなかった。
ただ、ここ最近、心の奥が少しずつ軋んでいるような感覚だけがあって。
それが何なのか、ずっと考えているのに答えが出ない。
「言えなかったことがある人ってね。自分でも気づいてないことが多いんだよ」
彼女がぽつりと呟く。
俺の胸が、ほんの少しだけざわついた。
「自分の中にあるのに、無かったことにしてたり、閉じ込めてたり。そうしてるうちに心のどこかにひっそり沈んで……でも、忘れたふりをしても、なくなったりはしない。必ずどこかに残ってるんだよ」
「……」
俺はざわつく胸に手を当て無言で俯いた。
「君も、あるんだね、忘れられないことや言えなかったことが、胸の中に……」
「わからない。でも……最近はモヤモヤしてるかも。心が落ち着かないっていうか、納得できないことが多いかな」
「納得できない? 誰に?」
「――自分自身にだよ」
「そっか。ずっと隠してきたんだね」
彼女の声色は優しいのに、鋭く胸に刺さるようだった。
まるで俺の奥底にしまい込んでいたものを、見透かしているようだった。
全てを知られているような、そんな感覚だった。
「陽翔くんは……まだ、止まったままなんだよ」
「……止まったまま?」
思わず聞き返す。まるで俺の過去を見通しているかのような口ぶりだった。
でも彼女は、それ以上は何も言わなかった。
ただ静かに、俺の方を見ていた。
その綺麗な目には、動揺する俺が反射していた。
思わず俺は視線を逸らした。そして止まったままの自分を考えた。
心の奥に、沈んだ記憶がある。
誰にも言ってこなかったこと。
俺が、言えなかった言葉。
あの日、言えばよかった言葉。
でも、言えなかった。言わなかった。
それがすべての始まりで、終わりだった。
今の俺を形成したすべてだった。
俺はそれを忘れようとして、心の奥底に封じ込めてきた。
ずっと思い出さないようにしてきた。
しかし、たった今、彼女に言われてそれが徐々に表出し始めていることに気がついた。
「……ぁ」
彼女は俺の沈黙を責めなかった。
ただ、落ち葉の上で立ち止まり、風を受けていた。
「言えなかったことがあるなら、それはまだ、ここにあるんだよ。残り続けてるんだよ。それはいつか後悔になって、心を蝕んじゃうの。もしかしたらもう後悔してるかもしれない、人はすぐにダメになる。強いと思っていても、実は弱い生き物なんだよね」
「……君は何者なの?」
思わず漏れたその問いに、彼女はふっと微笑んだ。
「わたしは……たまたま、“そういうの”が見えたり感じちゃうだけの普通の人間だよ」
「おかしな力だね」
「うん。でもね、この力はきっと有限なの。わたしが変わった時点で失われちゃうんだよ」
その言葉が俺の胸を静かに打った。
理由はわからない。
でも、今の言葉だけは、なぜか嘘じゃないと、そう思えた。
「ねえ、陽翔くん。君は自分の言葉を誰かに渡したいと思ったことある?」
渡したい? 言葉を? 誰かに?
答えはすぐに出なかった。
でも、あのときの光景が、ふいに脳裏に浮かんだ。
これまでは封じ込めてきたつもりだったのに、唐突に記憶が蘇る。
中学の頃、あの日、あの放課後。
俺は、誰かの背中を見ていた。
でも、声をかけなかった。
呼べなかった名前が、ひとつだけあった。
その名前を、口に出したことはあの日を境に一度もない。
「……どうだろう」
俺はぼそりとそれだけ返した。本当はわかっているはずなのに。
彼女はそれ以上何も言わなかった。
ただ、笑っていた。
そして風が吹いた。
落ち葉が舞い上がり、彼女の姿がその中に溶けていく。
きっと声をかけなければ、このまま彼女またいなくなってしまうような気がした。
「あ、えっと……名前、もう一度聞いてもいい?」
俺は咄嗟に話しかけた。
失礼なのは承知だったけど、彼女は目をぱちりと見開き、それから小さく頷いてくれた。
「……そっか、わたしの名前を知りたいんだね」
「うん、昨日は風が強かったからか聞き逃しちゃったんだ」
「風、強かったもんね。じゃあもう一度言うよ。わたしの名前は、未透。未完成の“未”に、透明の“透”って書いて、“みとう”と読む」
今日は彼女の名前がはっきり聞こえた。
「未透、か」
そんな珍しい名前の響きが、彼女の雰囲気に妙に合っていた。
どこか空気のようで、でも確かに“そこにいる”という存在感。
見えているのに、どこか遠い。手を伸ばせば触れられそうで、でも触れたら消えてしまいそうな。
名前だけではなく、その容姿もまた特徴的だった。
黒髪は肩の下までまっすぐに伸びていた。
その肌は透けるように白く、日差しを受けても影を落とさないほどだった。
線の細い腕と、少し大きめに見える制服のせいで、彼女がどこかこの世界の“手触り”から離れているように思えた。
でも、不自然さというより、静かな輪郭のようなものだった。
……どこか、少しだけ儚い印象を受けた。
「わたしの顔に何かある? 昨日も見てた気がする」
「いや、特に……ただ見てただけだよ」
他意はない。本当にただ見てただけだ。俺は彼女のように”何か”が見えたり感じられるわけではないから。
「ねぇ、陽翔くん」
「なに、未透さん」
唐突に名前を呼ばれたから、俺は名前を呼び返した。
すると、彼女はくるりと回って俺の目を見つめてきた。
「……見つかるといいね、探しもの」
俺は心臓を両手で包まれるような感覚に陥った。
何も言えず固まり、ふと我に返った時には、既に彼女の姿はなかった。
俺は一人、中庭に取り残された。
だけど、なぜか寂しくはなかった。
胸の奥で、なにかが静かに、揺れていた。
止まったままの自分の時間が、ほんのわずかに――微かに、動いたような気がした。