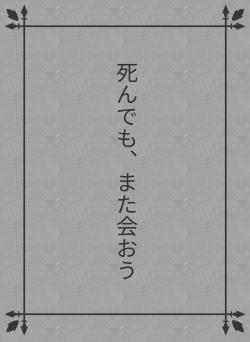「根津さん。会津さんと、どういう関係なんですか?」
昼休みの事だった。
「小・中の同級生。元親友。」
「え〜。じゃあ今は仲良く無いんですか〜?」
「そうだね。」
「深宙。僕は今も仲良くしたいなぁ。」
「ひっ。稀一、いきなり現れるなよ。」
「会津さぁ〜ん。一緒にお昼食べましょお。」
態度が違い過ぎる。女って怖い。
「ごめん深宙と食べるから。」
「はぁ?」
「まぁ良いから良いから。ねっ一緒に食べよ?」
昔からその顔に弱い。
「しょうがないなぁ。」
稀一のお昼ご飯は、コンビニの蕎麦だった。
「稀一。」
「なぁに?深宙。」
「あの時は、ごめん。完全に俺の嫉妬だった。俺には稀一が必要だし、稀一がいたほうが100%幸せだ。」
「うん。良かった。」
「えっ。泣くなよ。おい俺が泣かせたみたいだろ。」
「だってぇ。だってやっぱり僕は恵まれていて、けれど必要無いんだとか。親にも産まなければ良かったと言われたし。」
「なんでそんなこと。」
「誰にも必要とされなかった。けど、稀一が必要としてくれた。と思ってた。」
「必要だよ。今も昔も。」
「僕は間違いなんだ。存在自体が。俺は男が好きなんだ。ゲイなんだ。恥なんだ。深宙が好きなんだ。でも封印しなきゃ。きっと迷惑だ。初めて会った時、こんなに可愛い男がいるのかと驚きだった。初恋だ。これ以上好きになれる人は居ない。深宙が幸せならそれで良い。そこに僕は居なくとも。」
「ちょっと待て。えっ。稀一はゲイで、俺が好きで?俺が可愛いって?」
「ゔん。」
「泣くなって、その顔でどうやって、会社戻るんだよ。」
「ゔん。」
「わかったよ。ありがとな。アセクシャルなんだよ、俺は。誰にも言った事無いけどな。」
「アセクシャル?」
「他者に対して性的欲求・恋愛感情を抱かないセクシュアリティ」
「えっ。」
「まぁ個性だ。性欲も恋愛感情もないという個性。だから稀一のことは好きにならない。というかなれない。」
「そっか。ありがとう。」
「えっ?何が?」
「正直に言ってくれて。マイノリティを言ってくれて。僕を振ってくれて。ありがとう。」
「どういたしまして?」
「好きで居てもいいですか?」
「いいけど報われることはないぞ?」
「良いよ。深宙の隣にいれればそれで。」
「それならいいけど。」
会社に戻ったらそれは、それは騒がれた。バカ正直に稀一が言うもんだから。《深宙に振られました!》って。俺はものすごく怒られたよ。主に女性社員に。こんなに好条件のほうって置くのとか、もう散々。女性は条件でしか男性を見てないのか?やっぱり女性って怖い。
昼休みの事だった。
「小・中の同級生。元親友。」
「え〜。じゃあ今は仲良く無いんですか〜?」
「そうだね。」
「深宙。僕は今も仲良くしたいなぁ。」
「ひっ。稀一、いきなり現れるなよ。」
「会津さぁ〜ん。一緒にお昼食べましょお。」
態度が違い過ぎる。女って怖い。
「ごめん深宙と食べるから。」
「はぁ?」
「まぁ良いから良いから。ねっ一緒に食べよ?」
昔からその顔に弱い。
「しょうがないなぁ。」
稀一のお昼ご飯は、コンビニの蕎麦だった。
「稀一。」
「なぁに?深宙。」
「あの時は、ごめん。完全に俺の嫉妬だった。俺には稀一が必要だし、稀一がいたほうが100%幸せだ。」
「うん。良かった。」
「えっ。泣くなよ。おい俺が泣かせたみたいだろ。」
「だってぇ。だってやっぱり僕は恵まれていて、けれど必要無いんだとか。親にも産まなければ良かったと言われたし。」
「なんでそんなこと。」
「誰にも必要とされなかった。けど、稀一が必要としてくれた。と思ってた。」
「必要だよ。今も昔も。」
「僕は間違いなんだ。存在自体が。俺は男が好きなんだ。ゲイなんだ。恥なんだ。深宙が好きなんだ。でも封印しなきゃ。きっと迷惑だ。初めて会った時、こんなに可愛い男がいるのかと驚きだった。初恋だ。これ以上好きになれる人は居ない。深宙が幸せならそれで良い。そこに僕は居なくとも。」
「ちょっと待て。えっ。稀一はゲイで、俺が好きで?俺が可愛いって?」
「ゔん。」
「泣くなって、その顔でどうやって、会社戻るんだよ。」
「ゔん。」
「わかったよ。ありがとな。アセクシャルなんだよ、俺は。誰にも言った事無いけどな。」
「アセクシャル?」
「他者に対して性的欲求・恋愛感情を抱かないセクシュアリティ」
「えっ。」
「まぁ個性だ。性欲も恋愛感情もないという個性。だから稀一のことは好きにならない。というかなれない。」
「そっか。ありがとう。」
「えっ?何が?」
「正直に言ってくれて。マイノリティを言ってくれて。僕を振ってくれて。ありがとう。」
「どういたしまして?」
「好きで居てもいいですか?」
「いいけど報われることはないぞ?」
「良いよ。深宙の隣にいれればそれで。」
「それならいいけど。」
会社に戻ったらそれは、それは騒がれた。バカ正直に稀一が言うもんだから。《深宙に振られました!》って。俺はものすごく怒られたよ。主に女性社員に。こんなに好条件のほうって置くのとか、もう散々。女性は条件でしか男性を見てないのか?やっぱり女性って怖い。