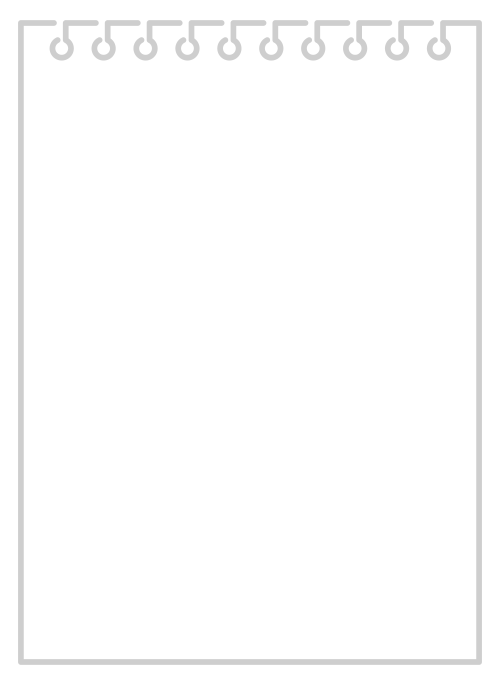教室に入り、まだ名前も把握しきれていないクラスメイトとぎこちない挨拶を交わし合う。男はともかく女子は多すぎて覚えられる気がしない。男子十人に対して女子は三十人もいる。この比率の男女クラスが一学年に四つあり、さらに女子だけのクラスも四つあるので、全体の男女比はより傾くことになる。この偏りは商業高校だからで、先に聞いて知っていたとはいえ実際に目の当たりにするとやっぱり驚く。
入学式の翌日の朝。数少ない男同士で窓際に集まって、出身中学や部活の話をしていたときだった。
「ミツル」
馴染みのある声に振り向くと、先輩がいた。俺たちみたいな新品のまだ硬い制服に着られているような一年と違い、肩付きのいいジャケットと長い脚を包むスラックスが様になっている。制服姿は何度も見ているが改めて教室でその立ち姿を拝むと、うちの制服はスタイルのいい男に着せるとやたらかっこよく見えるものだなと感じ入る。突如教室に現れた目立つ男に、一緒に話していた男連中だけでなく女子たちもこちらを窺うような空気になった。そのことに俺は小さな優越感を覚えた。
「昼、あっちの屋上な。購買で俺のぶんも買ってきて」
俺が何か言う前に一方的に言いつけられる。えっ、とか、は、とかろくな言葉が出ないまま俺がその指先の示す校舎を確かめているうちに先輩は、
「マジックねえの」
と周りのやつに油性ペンを借りていた。右手首を掴まれ、手のひらに何か書き込まれる。反射的に手を引っ込めようとすると「動くと刺す」と脅された。それでもやはり少し動かしてしまい、書かれた文字はちょっと歪んだ。先輩が書いたのは平仮名の「うめ」だった。
「梅おにぎり? てか、わざわざ書かなくても」
「こうして書いとかないと忘れるんだろ」
「それいつの話だよ」
「忘れんなよ」
先輩はペンを持ち主ではなく俺に渡して、来たときと同じように平然と歩いて出ていった。
教室全体に俺の説明を待っているような間ができて、それで俺は、中学のときのバスケ部の先輩だと話した。
先輩が地元の商業高校を受験すると知ったとき、俺は驚いたし、嬉しくもあった。先輩は何でもできるからもっと上のレベルに行くと思っていた。訊けば、俺と同じにしたかったという。
俺の場合は大学進学は端から選択肢になくて、行くとしたら卒業後に就職しやすい商業か工業の二択だった。電気だの回路だの、組立てだの製造だのは性に合わないと思い、早い時期から商業に決めていた。数字が絡むもの全般が苦手だから、電気にしても簿記にしてもどのみちしんどいことには変わりないのだが。
一学年上の先輩は、一足先に中学を卒業してもたびたび部活に顔を出した。ふらりと体育館に現れては俺たちに混じってプレーした。高校にもバスケ部はあるだろうと訊くと先輩は辞めたとあっさり答えた。ミツルがいねえからなと全員に聞かせるように言って笑いを取っていた。
俺と先輩は小学校のときからバスケ部で先輩後輩の仲なので、俺が一番先輩に懐いていたし何かとセットにされてきた。たまに付き合っているのかと冗談めかしや真剣トーンで人に訊かれることがある。そんなときは俺も先輩も顔を見合わせて、まるで何かの企みが成功したかのように小さく笑い合った。付き合うとか付き合わないとかいう話をしたことはないが、俺も先輩も積極的に周囲にそう思わせるような言動をしてみせている節がある。かっこいいし、モテるし、誰もが憧れる人だから、先輩に可愛がられたり周りにそういうふうに見られることは俺としては純粋に嬉しい。
中学最後の夏休みに入ると、俺の高校受験のために先輩がうちに来るようになった。晴れて合格し、こうして入学できているわけだが、俺の学力では正直危なかった。
「何のために同じ高校にしたと思っているんだ、絶対受かれ」
口癖のように何度も言われながら勉強を見てもらった。俺のことめっちゃ好きじゃんとくすぐったいような気分を覚えながら、だけどその言葉はまったくその通りだと思い、俺は必死に勉強した。先輩はどこにだって行けたのに商業高校を選んだ。その理由は俺なのに、俺が受験に失敗するわけにはいかない。先輩からの圧、あるいは愛と、もちろんきめ細かくわかりやすい手ほどきのおかげで俺は今ここにいる。
先輩が高校入学早々バスケ部を辞めた後、まさかの園芸部に入部していたということも、この受験勉強のときに聞いた。先輩と園芸という言葉が結びつかず、えんげいぶという音がまるで意味がわからなかったことを覚えている。花とか土いじりの園芸だとわかり、思いっきり「似合わねー」と腹を抱えて笑ったものだった。
昼休み。購買の袋を提げながら先輩に指定された校舎へと向かう。昨日、つまり入学式の後に新入生全員で敷地内を歩きながら説明を受けたので、そこが情報処理棟と呼ばれる建物だということは知っている。大層な名前をしているが情報処理やプログラミングの授業に使うパソコン教室が三つと、商業科の先生が詰める部屋が一つあるだけの小さな校舎だ。
誰にも出くわしませんようにと祈りながら校舎に入る。先生に見咎められたときのためにもっともらしい説明を用意しなければと思いながら、何も浮かばない。足音を立てないように歩くのでいっぱいだった。
教室や購買のあるメインの校舎にも、そしてこの情報処理棟にも屋上へ続く階段があるが、どちらも立入禁止になっている。先輩が園芸部に入ったのはこれが理由らしい。園芸部はメインの校舎の屋上にプランターを設置して栽培しているという。園芸部は部の活動に限って屋上への立ち入りが許可されているのだ。先輩はそこに目をつけ、今まで使われていなかった情報処理棟の屋上を活用すると言って園芸部に取り入り、その空間を我が物にしたのだった。
そういうことの好きな人だ。所有とか独占とか、自分だけのものにしたがるのが先輩だ。
俺は右手の「うめ」という字を改めて見る。梅おにぎりがいいのかととぼけてみせたが、そんなものを指しているのではないことはよくわかっている。先輩の名前は梅田という。つまり大勢が見ている前で、自分のものに名前を書くみたいに俺の手のひらに「うめ」と書いてみせたわけだ。
こういうことをするのが大好きな人なのだ、先輩は。入学したばかりで周りは俺たちを知らないやつのほうが多い。環境が変わったこともある。だから今までのように先輩に可愛がられたり、周りに俺のこと大好きアピールされたりすることがなくなることも考えていた。当然それでは寂しいと思っていたから、今朝さっそく先輩が来てくれたことに俺は内心ものすごく舞い上がっていた。
屋上への扉には立入禁止とペンで殴り書きされた紙が貼ってあり、施錠できる仕様でもあったが鍵は開いていた。先輩が園芸部特権で開けているのだ。
「遅えよ」
先輩は南向きに置かれたプランターの前にいた。屋上の面積に対して花が占める割合はごくわずかで、三つだけ横に並んだプランターはどこかから迷い込んできてここにいるみたいになっている。白やピンクの花びらの多い花が、四月の晴天のなかで輝くように光を照り返している。花に詳しくないので名前を訊くと、先輩もよくわかっていないのか「なんとかデイジー」と返ってきた。
「先輩、蜂。蜂がいる」
先輩の真横を蜂が浮遊していた。虫にも詳しくないのだが小さいので多分ミツバチだ。なんとかデイジーに近づいたり離れたりを繰り返しているが、一向に花に止まる気配がない。横に先輩がいるせいだろうか。
「そこ危ないって。蜂に警戒されてるんじゃ」
「うるさくするとお前が刺されるぞ」
先輩は蜂など歯牙にもかけずにプランターから離れ、俺から袋を取り上げた。なぜか一つだけ置いてあるベンチに腰かけて物色する。俺も隣に座り先輩がおにぎりを選ぶのを待った。
ベンチは、どこかで使っていたものを移動させてきてそのまま雨風に曝したような、くたびれた感じだった。先輩がどこかから古いのを持ってきたんじゃないかという考えが頭をよぎる。この人ならやりかねない。先輩は梅おにぎりではなく鶏五目めしを取って食べ始めた。その間俺はプランターにいた蜂の動向を見守っていたのだが、結局蜂はどこにも止まることなく飛び去っていった。
「梅食わんの?」
「それはお前の。身体にいいぞ」
「なんだよー」
わざわざ買ってきたのにという態度をしてみせる。ついでに油性ペンの「うめ」も見せれば、先輩は切れ長の目をうんと細めて満足そうな笑みを浮かべた。これ見よがしにじゃれ合ったり俺への愛情をアピールしたりするようなときとは違う、無防備に内から溢れ出たような表情だった。ふとしたときに先輩が見せるこの顔が、俺は好きだ。
「先輩は、バスケ部には戻んねえの」
食べ終えたからあげやポテトサラダの容器を片づけながら、俺は気になっていたことを訊いた。今日からさっそく部活動見学の期間が始まる。来週には入部届を出さないといけないらしい。先輩は俺といたくて高校のバスケ部を抜けて中学に来ていた。本人の弁をそのまま受け取るなら、俺がバスケ部に入ったら先輩もついてくるんじゃないか。あるいは一度辞めたことで再入部はしづらいかもしれない。先輩はどうするのか、俺はどうすればいいのか。そんなことを俺は考えていたのだった。
「そんなにバスケしてえの?」
「いや、別に」
バスケがしたいわけじゃない。小学校からの流れでバスケしかしてこなかったから、ほかにできることやしたいことが思いつかないだけだ。
「でも俺バスケしかわからないし、見学して、いい感じなら入部するかも」
「やめとけ。ここの男バスしょーもねえから」
それはつまり先輩と同じ園芸部にしろということだろうか。こっちのパターンもなんとなく予想はしていた。今のところまったく興味のない分野だ。園芸部に入って、花やら葉やらを育てる自分はまるで想像できない。だが先輩と一緒なら何だっていいし、何だって楽しめると思っている。
何か気の利いた、先輩が喜びそうな言い方で園芸部に入ってもいいということを表明したいと言葉を探していたときだった。突然、大きな音を立てて扉が開け放たれた。驚いてそちらを見ると女子生徒が立っていた。「梅田!」と彼女は先輩を非難するような口調で呼んだ。
「部外者は立入禁止」と先輩が面倒そうに彼女に言う。
「私、園芸部だし」
つかつかと俺たちのいるベンチに近づいてくるその顔には見覚えがあった。中学で見たことがある。先輩と同じ学年で、当時は生徒会長をしていた人だ。
「プランターの写真撮ってきてって言ったのに、これ置いていかないでよ」
彼女は手にデジカメを持っていた。学校から借りているのだろう、職員室と書かれたテープがでかでかと貼ってある。
「断っただろ」
「もういいよ、私が撮るから」
デジカメを構える彼女に、先輩はとっさに立ち上がってその肩を掴んだ。
「やめろって言ってんの」
声を荒げたわけではない。だけどいつになく真剣で低いトーンの声に、彼女はもちろんそばで聞いていた俺もびくりと肩を震わせた。彼女が花の写真を撮るぶんには何も困らないのではないか。俺と同じ疑問を彼女も抱いたことだろう。彼女は怪訝な顔で先輩に向き合った。
「男子部員も募集するからこっちの写真を載せたいって、朝話したじゃん」
「部員なんかいらねえ」
「でも彼は園芸部に呼ぶでしょ」
彼女が俺のほうを目で示す。同じ中学にいたわけだから、俺と先輩がいつもつるんでいるのを知っていてもおかしくなかった。
「呼ばねえよ。男は一人も入れるな。余計なことすんなよ」
「ああ、そう」
今度は俺だけが驚く番だった。どういうわけか彼女のほうはあっさりと引き下がってしまった。俺はてっきり、先輩は俺に園芸部に入ってほしいのだと思っていた。しかしどうやら違うみたいだ。このことを俺はどう捉えればいいのか。
先輩はこの場所を自分のものにした。それをほかの人間に――たとえそれが俺であっても――譲りたくないということか。今のやりとりで先輩は、俺よりも屋上を優先したと、そういうことになるのだろうか。そもそも俺は先輩のなかでどのあたりに位置しているのだろう。俺は勝手に、先輩のなかのほとんど一番上あたりにいると信じていた。信じて疑わなかった。足下を支えていた台がすっと引き抜かれたような気分だった。
聞き分けよく去っていく彼女の後ろ姿を引き留めたい気持ちで見ていた。彼女の口から、先輩と俺のことをもっと突っ込んでほしかった。二人はどういう仲なのか。二人で園芸部をやるんじゃないのか。それでバスケ部を辞めたんじゃないのか。バスケ部に入るなと言ったのは、俺と一緒にいたいからじゃないのか。
俺が自分でそう訊けなかったのは、怖くなったからだ。俺が思っていたほどには先輩は俺のことを思っていなかったのかもしれない。もしそうなら、ここで俺が縋るように問い質してはただのヒステリーだ。
ほどなくして予鈴が鳴り、俺たちは慌ただしく各々の教室に戻ることになった。先輩には当然何も訊けないままだった。
結局、バスケ部の見学には行くことになった。俺がそう決めたのではなく成り行きでそうなった。
クラスに卓球部を志望するやつがいて、部の説明がどちらも体育館で行われるので一緒に行こうと言われたのだった。中学でバスケをしていたことは朝話してしまったし、行かないと言ったところで、じゃあ何部にするのか、どうしてバスケじゃないのかと訊かれても面倒だった。俺自身どうしたいかわかっていなかった。
昼休みの後にも授業はあったが、ぼんやりと過ごしていたら終わっていた。頭のなかで先輩との過去のあれこれを思い返しては、あれは俺のことが好きでああ言ったはずだとか、これは俺のことが好きかどうかに関わりなく起きたことだろうとか、いちいち先輩の気持ちと言動とを結びつけていた。例えば先輩が同じ高校を選んだのは俺のこととは関係なしに商業に行きたかったのだろうとか、高校の部活を辞めてまで中学に顔を出していたのはやっぱり俺に会うためだったのではとか、そんな具合だ。屋上に咲いていた花が花占いに向いたかたちだったせいかもしれない。祈りや願望を乗せて、好き、嫌い、好き、嫌いと花びらを毟っていく感じに似ていた。より正確にいうなら好きか嫌いかではなく、好きか、それほどでもないかの二択だった。こっちのほうが好きか嫌いかよりダメージがでかい気がする。先輩にとってはただのパフォーマンスだったのに、俺一人だけ本気になって浮かれて自惚れていたことになるわけだから。
急に女々しくなった自分にびっくりした。昼のことがだいぶ堪えている。先輩から拒まれる思いをしたのは今回が初めてだと気がついた。
「本当はバレー部がよかったんだけどさ」
横で齊藤が不満そうに零す。放課後、俺たちは体育館に向かって歩いていた。建物や木の陰が伸びて敷地内はどこもうっすら暗くなっている。クラスで体育館に説明を聞きにいく男子は、俺と齊藤だけだった。ちなみに今朝先輩に油性ペンを貸したのがこの齊藤である。
「男子バレー部はもう存在してないんだもんなあ」
それで彼は卓球部にするという。学内の男女比が大幅に偏っているせいか女子のみの部が多かった。かつては男子バレー部もあったが入部者がいない年が続いてなくなったらしい、というのが齊藤情報である。ホームルームで部活について配られた用紙に、各部の簡単な紹介に添えて、男子が入部できるかということが記されていた。茶道部みたいな女子のイメージの強い部活だけでなく、バレー、バドミントンなんかも女子のみだ。文化系の部活にいたっては吹奏楽部か情報処理部しか男子には選択肢がない。茶道、調理、美術、文芸部などと並んで園芸部も、募集は女子のみとなっていた。
「バスケ部も男子は消滅の危機らしいよ。去年は新入生が全員即辞めたとかで、今いるのは三年だけだって」
去年の新入生というのはつまり先輩の代だ。全員が辞めたというのは初耳だった。あの日体育館で「ミツルがいねえからな」と言った先輩の言葉が思い起こされる。また花びらを千切るような思考になりかけ、それ以上はいけないと考えるのを止めた。
「あれ、でも春木の先輩って二年だよな」
齊藤がいらないところにまで気づく。園芸部に移ったと言えば俺がそっちへ行かない理由も説明しないといけなくなる。何を話したものかと思案しかけたところに、小さなものが目の前を横切った。
「すんませーん」
卓球のラケットを持った男が駆けてくる。飛んできたのはピンポン球で、齊藤が拾って返した。体育館の横に卓球台が並んでいた。
「卓球部は外なんだな」
「ええー、室内が良いんだけどな。バスケ部に変えようかな」
「卓球とバスケじゃ全然違うだろ」
「紫外線が嫌なんだよ」
話が逸れて先輩のことは話さずに済んだ。俺たちは体育館に入り、合同説明を聞く集まりに合流した。
体育館の隅に急ごしらえの新入生向け説明会の場が設けられていた。とはいえ椅子や何かがあるわけではなく、一年は制服のまま体育座り。説明役で何人か立っている上級生も各部のユニフォームは着ているが全員手ぶらだ。見学初日のためか人が多く、バドミントンのコートにまで人が溢れてそこだけ一時的に使えなくなってしまっている。
館内ではバドミントン部と体操部、それから舞台の上で卓球部が練習をしていた。全員女子だった。バレー部やバスケ部の姿は見えない。説明によると日によってローテーションで体育館を使える部が変わるのだそうだ。
卓球部のみは毎日使える。しかし体育館の舞台の上が女子、外が男子と分かれており、男子は都度卓球台を体育館横まで運び出しているという。卓球部の代表らしき男が半笑いで「商業高校じゃ何でも女子優先なんで」とおどけて、おそらく笑いを取ろうとしたのだが失敗していた。
説明が終わり、各部の上級生が希望者を引き連れて移動することになった。結局バスケ部を見にいくという齊藤も含めて、一年男子五人で主将の三年についていく。トレーニングの時間らしいが、前を歩く主将は制服から着替えていなかった。成り行きで俺が一年のなかで一番前の位置になっていた。俺たちが連れていかれたのは体育館裏で、ガラの悪そうな男子生徒が二人、着崩した制服姿のまま座り込んでいた。木の陰になっていてただでさえ陰気なところに、さらに嫌な感じの空気が満ちている。主将も主将で、先にいた彼らとニヤニヤし出した。
「これやるよ」
座っていた一人が、ポケットから煙草の箱を差し出してきた。当然、列の一番前にいた俺に言っていた。ぎっしり詰まったうちの一本が飛び出て、これを取れと言わんばかりにしてある。
「そういうのはちょっと」
「そういうのはちょっと、だって」
主将が俺の真似をして、三人は手を叩いて笑う。去年の一年が全員退部したというのも頷ける。去年卒業した三年がどういう人たちだったか知らないが、今年の三年はもう、そもそも誰も入部させる気がないのだろう。
飲酒に喫煙、彼女はいるのか、ヤったことはあるのかとくだらないことで俺たちを質問攻めにした。反応が見たいだけなのだろう、こちらが何を言っても言わなくても、何が楽しいのか三人で下卑た笑い声を立てていた。
「おい、探したぞ」
後ろから俺のよく知っている声がした。その声に驚くよりも安心して、俺は気の抜けた顔をしていたかもしれない。振り向くと先輩が長い脚でスタスタと歩いてきて、俺の腕を取った。
「こいつに用があるんで」
先輩がその場の全員に断りを入れる感じで言い、俺はあっさりと連れ去られた。三年生や取り残された齊藤たちがどんな顔をしていたかはわからない。歩幅のある先輩に置いていかれまいと振り返ることなく駆け足気味で追いかけた。
「先輩、どうして」
俺の声はちょうど一斉に鳴らされた吹奏楽部の音にかき消された。
先輩の足は例の屋上がある情報処理棟に向かっていた。途中、先輩は歩調を緩めて、
「あいつら火持ってねえよ」
と耳打ちした。一瞬何のことかわからなかった。火というのがライターだとわかり、さっきのことを言っているのだと思い至った。
「持ち歩いてちらつかせるだけ。ここで吸ってたら流石にニオイでバレるしな」
言われてみれば、あの箱の中身はまるで減っていなかったような気がする。去年、先輩たちも同じことをされたのかもしれない。
「な、しょーもねえだろ。まあ、俺もあいつらとやってることは変わんねえけど」
最後の呟きはほとんど独り言のようだった。いったいどういうことなのか。言葉を続ける感じではなく、聞き返していいものか迷った。どのみち後ろから呼び止められて話は途切れることになった。
「春木!」
齊藤が追いかけてきていた。齊藤は先輩に「さっきはありがとうございました」と礼を言った。
「おかげで助かりました。あそこを離れるきっかけができたっていうか。ほかのやつらも別の部を見にいくってうまく逃げられて」
「そうか」
まるで関心がない様子で先輩が返す。
「何部なんですか。俺も春木とついてっていいですか」
「悪いけど」
食い気味の齊藤を先輩が制止する。先輩が俺の肩に手を回して抱き寄せて言う。
「俺らこれからデートなんだわ。邪魔しないでくれる」
中学までの俺なら、というか昼までの俺なら、先輩の言葉に素直に笑えたのになと思う。このまま齊藤が勘違いして、明日の朝にでもお前ら付き合っているのかと確かめられたら愉快だと以前なら思ったはずだ。でも今はそれがなんだか虚しく感じられる。
「また明日な」
ぽかんとする齊藤になんとか俺はそう言って、右手を上げた。歩き出してから気づいたが、右手には先輩の書いた「うめ」がしっかり残っていた。あの流れでそれをわざわざ見せつけたようになったわけで、そう考えるとかっと体が熱くなった。
下にいるときは校舎の陰で薄暗く感じたが、屋上に出ると空はまだ青く、暮れる気配がわずかに白く滲み始めたくらいだった。ほかの部活の音がここまで昇ってきている。どこかの部の掛け声とか、楽器の音出しなんかが遠く聞こえた。
「やっぱりお前、バスケがよかった?」
先に屋上に出た先輩が言う。こちらに背を向けているのでその顔は見えない。俺にバスケ部はやめとけと言っておいて、それなのに園芸部にも入れないと言った先輩が、俺はわからない。
「だって、先輩のとこには入れてくれないんだろ」
思いのほか拗ねているような響きが乗ってしまい、俺は口にしたことを後悔する。先輩は振り返って、なぜかくしゃりと笑った。
「何、それで元気ない感じなの?」
「別に」
「いいから座れ」
促されて先輩の左隣に座った。やけに楽しげな先輩の様子に、まるで面白がられているように感じられて癪だった。先輩は誰に聞かれるわけでもないのに内緒話を打ち明けるように小声で話し出した。
「俺も、園芸部には入ってねえよ」
「は」
「正式な入部届は出してないってこと。ずっとお試し期間」
「どういうこと」
「入部しなきゃ活動しちゃいけないなんて決まりはないだろ」
先輩はバスケ部を抜けてから、昼間のあの人つながりで園芸部を手伝い始めたという。女子部員しかいない園芸部に男手は重宝したのだろう、見返りに先輩の屋上利用計画に彼女は手を貸した。園芸部で情報処理棟の屋上も使えるようにし、先輩はその管理を一任された。去年の彼らは一年だったわけだが、こういうことに手が早い先輩と元生徒会長の彼女が組めば実現は難しくなかっただろう。
「普通に入部すればいいのに、なんでお試し期間のままなんだ」
「男の入部実績ができたら、次から男子部員も募集するようになるだろ」
そういえば昼休みの先輩はそのことを強く拒むようだった。写真の一枚も撮らせないほどだった。
「男子部員が増えたら自然と、あっちは女子、こっちは男子の活動の場ってことにされちまうよな。そうなったら――」
先輩はそこで言葉を切って、俺の顔をじっと見つめた。
「ミツルと二人になれねえじゃん」
真正面から端正な顔に笑みを向けられ、かあっと顔が火照るのを感じた。
「俺と? え、俺のため?」
「ほかに誰がいるんだよ」
先輩が笑いながら俺を小突いた。自然とにやけてしまう顔を誤魔化したくて先輩の笑いにつられたふうを装って笑い顔を作った。きっと今、俺はすごく変な顔をしている。なんだか暑いし、顔は真っ赤のはずだ。午後から俺が落ち込んでいたのはいったい何だったのか。先輩はやっぱり先輩のままだった。
「お前も入部の話になったらうまくかわせよ。うちの学校、そこんとこ雑だから」
ここに来る前に先輩が呟いた「俺もあいつらとやってることは変わんねえ」というのはこのことかと思い至った。部員を入れさせないという意味では同じだ。こちらの場合、元々女子のみの募集だったわけで、バスケ部とはだいぶ違うのだが。
後になって知ったが、茶道部や調理部にもしれっと活動に参加したり遊びに行ったりしている男子生徒はいるらしい。こんなことになっているのは部活動紹介の用紙によるところが大きい。その内容のほとんどが何年も使いまわしで、部員から要望がない限り変わらないという。昼に来た彼女は園芸部の欄を自分で書き換える気でいたが、それを先輩が止めたわけだ。ここを俺たち二人で占有するために、男子部員は募集していない、ということにしておきたかったのだ。
「小学校で、六年生を送る会ってあっただろ」
突然何を言い出すのかと思いながら、俺は「あったあった」と相槌を打った。卒業式とは別に、在校生が歌ったり踊ったりと出し物をする行事だ。自分たちが卒業するときにどんな催しがあったかなんて、もうまったく記憶にないが。
「お前、俺ら六年に手紙を書かなきゃいけないからって、手に手紙って書いてて、一応サプライズだったのに前の日にバレてたよな」
「そうだっけ」
確かに小学生のときは宿題や持ち物をよく手に書いていた。でも先輩のときの送る会やその手紙のことを言われてもぴんとこない。小学五年生というのがひどく遠くに感じられる。
「手紙って、何書いたっけ」
「忘れたのかよ。俺はちゃんと覚えてるぞ」
「あ、待って待って、絶対恥ずかしいやつじゃん」
「『うめ田先ぱいと、ずっといっしょにいたいです』って」
「わーっ」
治まってきていた火照りがまたぶり返す。顔から首まで再び真っ赤になったに違いない。
「各部の五年キャプテンから六年キャプテンに渡すやつでさ、本当なら卒業するメンバー全員に宛てて書くもんなのに、お前俺のことしか書いてねえんだもん」
先輩はその手紙を思い出すように遠くを見つめながら嬉しそうに言った。ものすごく恥ずかしい一方で、先輩が幸せそうな顔をしているので満たされた心地になる。
だんだん思い出してきた。送る会の後に六年は部ごとに集まって、キャプテンがその手紙を読み上げる流れだった。俺も自分が卒業するときに次のキャプテンの五年生から手紙をもらった。内容はもう覚えていないが、その手紙を確かに俺はメンバーの前で読んだのだ。先輩は俺が書いたものをどんな気持ちで読み上げたのだろう。小五の俺はどんな気持ちでそれを書いていたのだろう。
どんな気持ちも何も、ただ純粋に「ずっといっしょにいたい」という思いで綴ったはずだ。そこに嫌われたくないとか引かれたらどうしようとか、ためらう気持ちは微塵もない。そんなことは思いつきもしなかっただろう。小学生の俺が羨ましかった。
「あの手紙があったから中学でもバスケやって、小学校にも顔出してやってたんだぜ」
そうだ、先輩は中学だけでなく小学校卒業後も母校の体育館にわざわざやってきていた。当時はバスケがとても好きな人なんだろうと思っていたけどもちろん中学でもバスケ部に入っていたわけで、あの頃から俺に会いに来ていたことになる。中一の先輩も高一の先輩もまったく同じことをしていた。
「中学でバスケやりながら待ってたみたいに、高校でもバスケ部でお前が来るのを迎えてやりたかったんだけどな。……できなくてごめんな」
珍しく殊勝な言葉に俺ははっとした。「バスケ部がいいのか」「バスケがしたいのか」と先輩はたびたび俺に訊いてきた。先輩なりにバスケ部を辞めたことを気にしていたのかもしれない。
午後からずっと、先輩が俺のことを好きかそうでもないかで陰鬱としていたのが嘘のように、今の俺は全部の花びらが好きの一色で、だからこんな想像もできる。先輩ならあの連中を軽くいなしながらバスケ部を続けられたはずだ。だけどそうしなかったのは、俺のためだ。俺が三年にさっきのような絡まれ方をされたり嫌な気分になったりしながら部活を続けるのは、先輩には耐えられないはずだ。それで先輩はバスケ部でいることを諦めたのではないか。先輩は俺が思っている以上に、俺のことを思っているから。そんなことを考えていると体の内側から温かいものが広がるようだった。だってそうだとしたら先輩、俺のことめちゃくちゃ好きじゃん。
「今度ボール一個パクってくるか。そのうちゴールを立ててもいいな」
冗談めかしに言っているが先輩なら本当にやりかねない。先生やほかの園芸部員に目をつけられて追い出されたらかなわない。
「いいって、いらねえって」
俺は慌てて言う。それから、今なら言えると思って、照れる気持ちを抑えて先輩のほうを向き、思い切って言った。
「先輩といられるだけで、いい」
先輩は一瞬目を見開いて、それからその目を細めて満足そうに微笑んだ。愛おしむような眼差しを向けられて、やっぱり先輩は俺のこと大好きだよなと改めて思った。
しばらく見つめ合うかたちでいた俺たちの耳元で、ブンと耳障りな音が短く響いた。俺はその嫌な音にびくりと震え、正体を探すと予想通りそれは蜂だった。幸い俺たちからはすぐに離れ、プランターのほうに飛んでいった。
「お前、びびりすぎ」
ほっとため息をついた俺を先輩が笑う。蜂の羽音は誰だって嫌だろう。
蜂は相変わらず花に止まらない。近くを漂うようにふらふらするだけでどこかへ行ってしまった。昼にもこんなことがあった。先輩が花に対して虫がつかないように何か施しているのではないか。
「あの花、何かしてんの」
「何かって?」
「蜂が止まんねえなと思って。先輩が育てたから止まりにくいとか」
自分のものにするのが大好きな人だ。冗談のつもりで口にしたが、途端にそんな気がしてきてしまう。が、先輩はあっさり「何もしてねえよ」と返した。
「蜂だって、いちいち花に止まって花粉とか蜜があるかなんて確認してられないだろ。蜂は花の電場ってのを感じて、止まるか止まらないか決めてるんだと」
「電場……」
電気とか磁石とかの類は俺の特に苦手な分野だ。先輩はもちろんそんなことも承知していて、俺が微妙な表情をしたのを見て噴き出した。
「蜂も花も電気を帯びてるんだ。蜂が花粉を集めに花に止まると、その花の電場が変わる。後から来た蜂はその電場を感じ取って、もう花粉は取られた後なんだなってわかるわけ」
先輩は俺の右手をとり、手のひらの文字をなぞった。くすぐったくなるような、触れるか触れないかの感触にどきりとする。
「しるしを付けてるみたいだよな。これはもう俺が手を付けたぞ、触んじゃねえぞってさ」
わざと耳元で囁くように言われて背中のほうまで甘い痺れのようなものが走った。先輩の話はまるで俺が花に喩えられているみたいで、俺は花なんてガラでもないから可笑しかった。だけど先輩の振る舞いはしるしを付ける蜂そのものといえた。中学のかつての仲間たちの前でも、今朝の教室でも、さっきの齊藤に対しても先輩は俺のことを自分のものだと臆面なく主張した。もしかしたら元生徒会長やほかの園芸部員にまでもうすでに知れ渡っているのかもしれない。
「でも蜂は、ほかの花にも飛んでいくだろ」
ドキドキさせられたままなのも癪なので言い返してみる。すると先輩は俺の肩に腕を回して、
「じゃあ、しっかり捕まえといてもらわねえとな」
と言って、俺の体を抱き寄せた。これでは捕まえるのが逆だ。
俺は先輩に体を預けるようにしてもたれかかった。もう少しやってもいいかなと思い、ぐりぐりと身じろぎするように先輩とくっついている体の右半分を擦りつけた。
「何」
迷惑どころか嬉しそうに先輩が訊く。
「電気してる」とどう言えばいいかわからないまま思いつきで答える。
蜂がどんなふうにして花の電場を変えているのか知らないが、そんなイメージだ。ひとにはわからないだろうが先輩には伝わるだろう。俺ばっかりが先輩のものになっているんじゃない。先輩だって俺にとってはそうなのだと示したかった。言うまでもなく先輩がよそへ飛んでいくことはないだろうけど、俺からももっと、この気持ちを伝えていきたいと思った。
俺の体を抱く腕に優しく力が加わった。こんなふうにストレートに甘えたのは初めてだ。照れくさくて先輩の顔を見られない。視界の端でプランターのデイジーが風に揺れていた。先輩もきっと、俺の好きなあの無防備で満足そうな表情でそれを見ていることだろう。
入学式の翌日の朝。数少ない男同士で窓際に集まって、出身中学や部活の話をしていたときだった。
「ミツル」
馴染みのある声に振り向くと、先輩がいた。俺たちみたいな新品のまだ硬い制服に着られているような一年と違い、肩付きのいいジャケットと長い脚を包むスラックスが様になっている。制服姿は何度も見ているが改めて教室でその立ち姿を拝むと、うちの制服はスタイルのいい男に着せるとやたらかっこよく見えるものだなと感じ入る。突如教室に現れた目立つ男に、一緒に話していた男連中だけでなく女子たちもこちらを窺うような空気になった。そのことに俺は小さな優越感を覚えた。
「昼、あっちの屋上な。購買で俺のぶんも買ってきて」
俺が何か言う前に一方的に言いつけられる。えっ、とか、は、とかろくな言葉が出ないまま俺がその指先の示す校舎を確かめているうちに先輩は、
「マジックねえの」
と周りのやつに油性ペンを借りていた。右手首を掴まれ、手のひらに何か書き込まれる。反射的に手を引っ込めようとすると「動くと刺す」と脅された。それでもやはり少し動かしてしまい、書かれた文字はちょっと歪んだ。先輩が書いたのは平仮名の「うめ」だった。
「梅おにぎり? てか、わざわざ書かなくても」
「こうして書いとかないと忘れるんだろ」
「それいつの話だよ」
「忘れんなよ」
先輩はペンを持ち主ではなく俺に渡して、来たときと同じように平然と歩いて出ていった。
教室全体に俺の説明を待っているような間ができて、それで俺は、中学のときのバスケ部の先輩だと話した。
先輩が地元の商業高校を受験すると知ったとき、俺は驚いたし、嬉しくもあった。先輩は何でもできるからもっと上のレベルに行くと思っていた。訊けば、俺と同じにしたかったという。
俺の場合は大学進学は端から選択肢になくて、行くとしたら卒業後に就職しやすい商業か工業の二択だった。電気だの回路だの、組立てだの製造だのは性に合わないと思い、早い時期から商業に決めていた。数字が絡むもの全般が苦手だから、電気にしても簿記にしてもどのみちしんどいことには変わりないのだが。
一学年上の先輩は、一足先に中学を卒業してもたびたび部活に顔を出した。ふらりと体育館に現れては俺たちに混じってプレーした。高校にもバスケ部はあるだろうと訊くと先輩は辞めたとあっさり答えた。ミツルがいねえからなと全員に聞かせるように言って笑いを取っていた。
俺と先輩は小学校のときからバスケ部で先輩後輩の仲なので、俺が一番先輩に懐いていたし何かとセットにされてきた。たまに付き合っているのかと冗談めかしや真剣トーンで人に訊かれることがある。そんなときは俺も先輩も顔を見合わせて、まるで何かの企みが成功したかのように小さく笑い合った。付き合うとか付き合わないとかいう話をしたことはないが、俺も先輩も積極的に周囲にそう思わせるような言動をしてみせている節がある。かっこいいし、モテるし、誰もが憧れる人だから、先輩に可愛がられたり周りにそういうふうに見られることは俺としては純粋に嬉しい。
中学最後の夏休みに入ると、俺の高校受験のために先輩がうちに来るようになった。晴れて合格し、こうして入学できているわけだが、俺の学力では正直危なかった。
「何のために同じ高校にしたと思っているんだ、絶対受かれ」
口癖のように何度も言われながら勉強を見てもらった。俺のことめっちゃ好きじゃんとくすぐったいような気分を覚えながら、だけどその言葉はまったくその通りだと思い、俺は必死に勉強した。先輩はどこにだって行けたのに商業高校を選んだ。その理由は俺なのに、俺が受験に失敗するわけにはいかない。先輩からの圧、あるいは愛と、もちろんきめ細かくわかりやすい手ほどきのおかげで俺は今ここにいる。
先輩が高校入学早々バスケ部を辞めた後、まさかの園芸部に入部していたということも、この受験勉強のときに聞いた。先輩と園芸という言葉が結びつかず、えんげいぶという音がまるで意味がわからなかったことを覚えている。花とか土いじりの園芸だとわかり、思いっきり「似合わねー」と腹を抱えて笑ったものだった。
昼休み。購買の袋を提げながら先輩に指定された校舎へと向かう。昨日、つまり入学式の後に新入生全員で敷地内を歩きながら説明を受けたので、そこが情報処理棟と呼ばれる建物だということは知っている。大層な名前をしているが情報処理やプログラミングの授業に使うパソコン教室が三つと、商業科の先生が詰める部屋が一つあるだけの小さな校舎だ。
誰にも出くわしませんようにと祈りながら校舎に入る。先生に見咎められたときのためにもっともらしい説明を用意しなければと思いながら、何も浮かばない。足音を立てないように歩くのでいっぱいだった。
教室や購買のあるメインの校舎にも、そしてこの情報処理棟にも屋上へ続く階段があるが、どちらも立入禁止になっている。先輩が園芸部に入ったのはこれが理由らしい。園芸部はメインの校舎の屋上にプランターを設置して栽培しているという。園芸部は部の活動に限って屋上への立ち入りが許可されているのだ。先輩はそこに目をつけ、今まで使われていなかった情報処理棟の屋上を活用すると言って園芸部に取り入り、その空間を我が物にしたのだった。
そういうことの好きな人だ。所有とか独占とか、自分だけのものにしたがるのが先輩だ。
俺は右手の「うめ」という字を改めて見る。梅おにぎりがいいのかととぼけてみせたが、そんなものを指しているのではないことはよくわかっている。先輩の名前は梅田という。つまり大勢が見ている前で、自分のものに名前を書くみたいに俺の手のひらに「うめ」と書いてみせたわけだ。
こういうことをするのが大好きな人なのだ、先輩は。入学したばかりで周りは俺たちを知らないやつのほうが多い。環境が変わったこともある。だから今までのように先輩に可愛がられたり、周りに俺のこと大好きアピールされたりすることがなくなることも考えていた。当然それでは寂しいと思っていたから、今朝さっそく先輩が来てくれたことに俺は内心ものすごく舞い上がっていた。
屋上への扉には立入禁止とペンで殴り書きされた紙が貼ってあり、施錠できる仕様でもあったが鍵は開いていた。先輩が園芸部特権で開けているのだ。
「遅えよ」
先輩は南向きに置かれたプランターの前にいた。屋上の面積に対して花が占める割合はごくわずかで、三つだけ横に並んだプランターはどこかから迷い込んできてここにいるみたいになっている。白やピンクの花びらの多い花が、四月の晴天のなかで輝くように光を照り返している。花に詳しくないので名前を訊くと、先輩もよくわかっていないのか「なんとかデイジー」と返ってきた。
「先輩、蜂。蜂がいる」
先輩の真横を蜂が浮遊していた。虫にも詳しくないのだが小さいので多分ミツバチだ。なんとかデイジーに近づいたり離れたりを繰り返しているが、一向に花に止まる気配がない。横に先輩がいるせいだろうか。
「そこ危ないって。蜂に警戒されてるんじゃ」
「うるさくするとお前が刺されるぞ」
先輩は蜂など歯牙にもかけずにプランターから離れ、俺から袋を取り上げた。なぜか一つだけ置いてあるベンチに腰かけて物色する。俺も隣に座り先輩がおにぎりを選ぶのを待った。
ベンチは、どこかで使っていたものを移動させてきてそのまま雨風に曝したような、くたびれた感じだった。先輩がどこかから古いのを持ってきたんじゃないかという考えが頭をよぎる。この人ならやりかねない。先輩は梅おにぎりではなく鶏五目めしを取って食べ始めた。その間俺はプランターにいた蜂の動向を見守っていたのだが、結局蜂はどこにも止まることなく飛び去っていった。
「梅食わんの?」
「それはお前の。身体にいいぞ」
「なんだよー」
わざわざ買ってきたのにという態度をしてみせる。ついでに油性ペンの「うめ」も見せれば、先輩は切れ長の目をうんと細めて満足そうな笑みを浮かべた。これ見よがしにじゃれ合ったり俺への愛情をアピールしたりするようなときとは違う、無防備に内から溢れ出たような表情だった。ふとしたときに先輩が見せるこの顔が、俺は好きだ。
「先輩は、バスケ部には戻んねえの」
食べ終えたからあげやポテトサラダの容器を片づけながら、俺は気になっていたことを訊いた。今日からさっそく部活動見学の期間が始まる。来週には入部届を出さないといけないらしい。先輩は俺といたくて高校のバスケ部を抜けて中学に来ていた。本人の弁をそのまま受け取るなら、俺がバスケ部に入ったら先輩もついてくるんじゃないか。あるいは一度辞めたことで再入部はしづらいかもしれない。先輩はどうするのか、俺はどうすればいいのか。そんなことを俺は考えていたのだった。
「そんなにバスケしてえの?」
「いや、別に」
バスケがしたいわけじゃない。小学校からの流れでバスケしかしてこなかったから、ほかにできることやしたいことが思いつかないだけだ。
「でも俺バスケしかわからないし、見学して、いい感じなら入部するかも」
「やめとけ。ここの男バスしょーもねえから」
それはつまり先輩と同じ園芸部にしろということだろうか。こっちのパターンもなんとなく予想はしていた。今のところまったく興味のない分野だ。園芸部に入って、花やら葉やらを育てる自分はまるで想像できない。だが先輩と一緒なら何だっていいし、何だって楽しめると思っている。
何か気の利いた、先輩が喜びそうな言い方で園芸部に入ってもいいということを表明したいと言葉を探していたときだった。突然、大きな音を立てて扉が開け放たれた。驚いてそちらを見ると女子生徒が立っていた。「梅田!」と彼女は先輩を非難するような口調で呼んだ。
「部外者は立入禁止」と先輩が面倒そうに彼女に言う。
「私、園芸部だし」
つかつかと俺たちのいるベンチに近づいてくるその顔には見覚えがあった。中学で見たことがある。先輩と同じ学年で、当時は生徒会長をしていた人だ。
「プランターの写真撮ってきてって言ったのに、これ置いていかないでよ」
彼女は手にデジカメを持っていた。学校から借りているのだろう、職員室と書かれたテープがでかでかと貼ってある。
「断っただろ」
「もういいよ、私が撮るから」
デジカメを構える彼女に、先輩はとっさに立ち上がってその肩を掴んだ。
「やめろって言ってんの」
声を荒げたわけではない。だけどいつになく真剣で低いトーンの声に、彼女はもちろんそばで聞いていた俺もびくりと肩を震わせた。彼女が花の写真を撮るぶんには何も困らないのではないか。俺と同じ疑問を彼女も抱いたことだろう。彼女は怪訝な顔で先輩に向き合った。
「男子部員も募集するからこっちの写真を載せたいって、朝話したじゃん」
「部員なんかいらねえ」
「でも彼は園芸部に呼ぶでしょ」
彼女が俺のほうを目で示す。同じ中学にいたわけだから、俺と先輩がいつもつるんでいるのを知っていてもおかしくなかった。
「呼ばねえよ。男は一人も入れるな。余計なことすんなよ」
「ああ、そう」
今度は俺だけが驚く番だった。どういうわけか彼女のほうはあっさりと引き下がってしまった。俺はてっきり、先輩は俺に園芸部に入ってほしいのだと思っていた。しかしどうやら違うみたいだ。このことを俺はどう捉えればいいのか。
先輩はこの場所を自分のものにした。それをほかの人間に――たとえそれが俺であっても――譲りたくないということか。今のやりとりで先輩は、俺よりも屋上を優先したと、そういうことになるのだろうか。そもそも俺は先輩のなかでどのあたりに位置しているのだろう。俺は勝手に、先輩のなかのほとんど一番上あたりにいると信じていた。信じて疑わなかった。足下を支えていた台がすっと引き抜かれたような気分だった。
聞き分けよく去っていく彼女の後ろ姿を引き留めたい気持ちで見ていた。彼女の口から、先輩と俺のことをもっと突っ込んでほしかった。二人はどういう仲なのか。二人で園芸部をやるんじゃないのか。それでバスケ部を辞めたんじゃないのか。バスケ部に入るなと言ったのは、俺と一緒にいたいからじゃないのか。
俺が自分でそう訊けなかったのは、怖くなったからだ。俺が思っていたほどには先輩は俺のことを思っていなかったのかもしれない。もしそうなら、ここで俺が縋るように問い質してはただのヒステリーだ。
ほどなくして予鈴が鳴り、俺たちは慌ただしく各々の教室に戻ることになった。先輩には当然何も訊けないままだった。
結局、バスケ部の見学には行くことになった。俺がそう決めたのではなく成り行きでそうなった。
クラスに卓球部を志望するやつがいて、部の説明がどちらも体育館で行われるので一緒に行こうと言われたのだった。中学でバスケをしていたことは朝話してしまったし、行かないと言ったところで、じゃあ何部にするのか、どうしてバスケじゃないのかと訊かれても面倒だった。俺自身どうしたいかわかっていなかった。
昼休みの後にも授業はあったが、ぼんやりと過ごしていたら終わっていた。頭のなかで先輩との過去のあれこれを思い返しては、あれは俺のことが好きでああ言ったはずだとか、これは俺のことが好きかどうかに関わりなく起きたことだろうとか、いちいち先輩の気持ちと言動とを結びつけていた。例えば先輩が同じ高校を選んだのは俺のこととは関係なしに商業に行きたかったのだろうとか、高校の部活を辞めてまで中学に顔を出していたのはやっぱり俺に会うためだったのではとか、そんな具合だ。屋上に咲いていた花が花占いに向いたかたちだったせいかもしれない。祈りや願望を乗せて、好き、嫌い、好き、嫌いと花びらを毟っていく感じに似ていた。より正確にいうなら好きか嫌いかではなく、好きか、それほどでもないかの二択だった。こっちのほうが好きか嫌いかよりダメージがでかい気がする。先輩にとってはただのパフォーマンスだったのに、俺一人だけ本気になって浮かれて自惚れていたことになるわけだから。
急に女々しくなった自分にびっくりした。昼のことがだいぶ堪えている。先輩から拒まれる思いをしたのは今回が初めてだと気がついた。
「本当はバレー部がよかったんだけどさ」
横で齊藤が不満そうに零す。放課後、俺たちは体育館に向かって歩いていた。建物や木の陰が伸びて敷地内はどこもうっすら暗くなっている。クラスで体育館に説明を聞きにいく男子は、俺と齊藤だけだった。ちなみに今朝先輩に油性ペンを貸したのがこの齊藤である。
「男子バレー部はもう存在してないんだもんなあ」
それで彼は卓球部にするという。学内の男女比が大幅に偏っているせいか女子のみの部が多かった。かつては男子バレー部もあったが入部者がいない年が続いてなくなったらしい、というのが齊藤情報である。ホームルームで部活について配られた用紙に、各部の簡単な紹介に添えて、男子が入部できるかということが記されていた。茶道部みたいな女子のイメージの強い部活だけでなく、バレー、バドミントンなんかも女子のみだ。文化系の部活にいたっては吹奏楽部か情報処理部しか男子には選択肢がない。茶道、調理、美術、文芸部などと並んで園芸部も、募集は女子のみとなっていた。
「バスケ部も男子は消滅の危機らしいよ。去年は新入生が全員即辞めたとかで、今いるのは三年だけだって」
去年の新入生というのはつまり先輩の代だ。全員が辞めたというのは初耳だった。あの日体育館で「ミツルがいねえからな」と言った先輩の言葉が思い起こされる。また花びらを千切るような思考になりかけ、それ以上はいけないと考えるのを止めた。
「あれ、でも春木の先輩って二年だよな」
齊藤がいらないところにまで気づく。園芸部に移ったと言えば俺がそっちへ行かない理由も説明しないといけなくなる。何を話したものかと思案しかけたところに、小さなものが目の前を横切った。
「すんませーん」
卓球のラケットを持った男が駆けてくる。飛んできたのはピンポン球で、齊藤が拾って返した。体育館の横に卓球台が並んでいた。
「卓球部は外なんだな」
「ええー、室内が良いんだけどな。バスケ部に変えようかな」
「卓球とバスケじゃ全然違うだろ」
「紫外線が嫌なんだよ」
話が逸れて先輩のことは話さずに済んだ。俺たちは体育館に入り、合同説明を聞く集まりに合流した。
体育館の隅に急ごしらえの新入生向け説明会の場が設けられていた。とはいえ椅子や何かがあるわけではなく、一年は制服のまま体育座り。説明役で何人か立っている上級生も各部のユニフォームは着ているが全員手ぶらだ。見学初日のためか人が多く、バドミントンのコートにまで人が溢れてそこだけ一時的に使えなくなってしまっている。
館内ではバドミントン部と体操部、それから舞台の上で卓球部が練習をしていた。全員女子だった。バレー部やバスケ部の姿は見えない。説明によると日によってローテーションで体育館を使える部が変わるのだそうだ。
卓球部のみは毎日使える。しかし体育館の舞台の上が女子、外が男子と分かれており、男子は都度卓球台を体育館横まで運び出しているという。卓球部の代表らしき男が半笑いで「商業高校じゃ何でも女子優先なんで」とおどけて、おそらく笑いを取ろうとしたのだが失敗していた。
説明が終わり、各部の上級生が希望者を引き連れて移動することになった。結局バスケ部を見にいくという齊藤も含めて、一年男子五人で主将の三年についていく。トレーニングの時間らしいが、前を歩く主将は制服から着替えていなかった。成り行きで俺が一年のなかで一番前の位置になっていた。俺たちが連れていかれたのは体育館裏で、ガラの悪そうな男子生徒が二人、着崩した制服姿のまま座り込んでいた。木の陰になっていてただでさえ陰気なところに、さらに嫌な感じの空気が満ちている。主将も主将で、先にいた彼らとニヤニヤし出した。
「これやるよ」
座っていた一人が、ポケットから煙草の箱を差し出してきた。当然、列の一番前にいた俺に言っていた。ぎっしり詰まったうちの一本が飛び出て、これを取れと言わんばかりにしてある。
「そういうのはちょっと」
「そういうのはちょっと、だって」
主将が俺の真似をして、三人は手を叩いて笑う。去年の一年が全員退部したというのも頷ける。去年卒業した三年がどういう人たちだったか知らないが、今年の三年はもう、そもそも誰も入部させる気がないのだろう。
飲酒に喫煙、彼女はいるのか、ヤったことはあるのかとくだらないことで俺たちを質問攻めにした。反応が見たいだけなのだろう、こちらが何を言っても言わなくても、何が楽しいのか三人で下卑た笑い声を立てていた。
「おい、探したぞ」
後ろから俺のよく知っている声がした。その声に驚くよりも安心して、俺は気の抜けた顔をしていたかもしれない。振り向くと先輩が長い脚でスタスタと歩いてきて、俺の腕を取った。
「こいつに用があるんで」
先輩がその場の全員に断りを入れる感じで言い、俺はあっさりと連れ去られた。三年生や取り残された齊藤たちがどんな顔をしていたかはわからない。歩幅のある先輩に置いていかれまいと振り返ることなく駆け足気味で追いかけた。
「先輩、どうして」
俺の声はちょうど一斉に鳴らされた吹奏楽部の音にかき消された。
先輩の足は例の屋上がある情報処理棟に向かっていた。途中、先輩は歩調を緩めて、
「あいつら火持ってねえよ」
と耳打ちした。一瞬何のことかわからなかった。火というのがライターだとわかり、さっきのことを言っているのだと思い至った。
「持ち歩いてちらつかせるだけ。ここで吸ってたら流石にニオイでバレるしな」
言われてみれば、あの箱の中身はまるで減っていなかったような気がする。去年、先輩たちも同じことをされたのかもしれない。
「な、しょーもねえだろ。まあ、俺もあいつらとやってることは変わんねえけど」
最後の呟きはほとんど独り言のようだった。いったいどういうことなのか。言葉を続ける感じではなく、聞き返していいものか迷った。どのみち後ろから呼び止められて話は途切れることになった。
「春木!」
齊藤が追いかけてきていた。齊藤は先輩に「さっきはありがとうございました」と礼を言った。
「おかげで助かりました。あそこを離れるきっかけができたっていうか。ほかのやつらも別の部を見にいくってうまく逃げられて」
「そうか」
まるで関心がない様子で先輩が返す。
「何部なんですか。俺も春木とついてっていいですか」
「悪いけど」
食い気味の齊藤を先輩が制止する。先輩が俺の肩に手を回して抱き寄せて言う。
「俺らこれからデートなんだわ。邪魔しないでくれる」
中学までの俺なら、というか昼までの俺なら、先輩の言葉に素直に笑えたのになと思う。このまま齊藤が勘違いして、明日の朝にでもお前ら付き合っているのかと確かめられたら愉快だと以前なら思ったはずだ。でも今はそれがなんだか虚しく感じられる。
「また明日な」
ぽかんとする齊藤になんとか俺はそう言って、右手を上げた。歩き出してから気づいたが、右手には先輩の書いた「うめ」がしっかり残っていた。あの流れでそれをわざわざ見せつけたようになったわけで、そう考えるとかっと体が熱くなった。
下にいるときは校舎の陰で薄暗く感じたが、屋上に出ると空はまだ青く、暮れる気配がわずかに白く滲み始めたくらいだった。ほかの部活の音がここまで昇ってきている。どこかの部の掛け声とか、楽器の音出しなんかが遠く聞こえた。
「やっぱりお前、バスケがよかった?」
先に屋上に出た先輩が言う。こちらに背を向けているのでその顔は見えない。俺にバスケ部はやめとけと言っておいて、それなのに園芸部にも入れないと言った先輩が、俺はわからない。
「だって、先輩のとこには入れてくれないんだろ」
思いのほか拗ねているような響きが乗ってしまい、俺は口にしたことを後悔する。先輩は振り返って、なぜかくしゃりと笑った。
「何、それで元気ない感じなの?」
「別に」
「いいから座れ」
促されて先輩の左隣に座った。やけに楽しげな先輩の様子に、まるで面白がられているように感じられて癪だった。先輩は誰に聞かれるわけでもないのに内緒話を打ち明けるように小声で話し出した。
「俺も、園芸部には入ってねえよ」
「は」
「正式な入部届は出してないってこと。ずっとお試し期間」
「どういうこと」
「入部しなきゃ活動しちゃいけないなんて決まりはないだろ」
先輩はバスケ部を抜けてから、昼間のあの人つながりで園芸部を手伝い始めたという。女子部員しかいない園芸部に男手は重宝したのだろう、見返りに先輩の屋上利用計画に彼女は手を貸した。園芸部で情報処理棟の屋上も使えるようにし、先輩はその管理を一任された。去年の彼らは一年だったわけだが、こういうことに手が早い先輩と元生徒会長の彼女が組めば実現は難しくなかっただろう。
「普通に入部すればいいのに、なんでお試し期間のままなんだ」
「男の入部実績ができたら、次から男子部員も募集するようになるだろ」
そういえば昼休みの先輩はそのことを強く拒むようだった。写真の一枚も撮らせないほどだった。
「男子部員が増えたら自然と、あっちは女子、こっちは男子の活動の場ってことにされちまうよな。そうなったら――」
先輩はそこで言葉を切って、俺の顔をじっと見つめた。
「ミツルと二人になれねえじゃん」
真正面から端正な顔に笑みを向けられ、かあっと顔が火照るのを感じた。
「俺と? え、俺のため?」
「ほかに誰がいるんだよ」
先輩が笑いながら俺を小突いた。自然とにやけてしまう顔を誤魔化したくて先輩の笑いにつられたふうを装って笑い顔を作った。きっと今、俺はすごく変な顔をしている。なんだか暑いし、顔は真っ赤のはずだ。午後から俺が落ち込んでいたのはいったい何だったのか。先輩はやっぱり先輩のままだった。
「お前も入部の話になったらうまくかわせよ。うちの学校、そこんとこ雑だから」
ここに来る前に先輩が呟いた「俺もあいつらとやってることは変わんねえ」というのはこのことかと思い至った。部員を入れさせないという意味では同じだ。こちらの場合、元々女子のみの募集だったわけで、バスケ部とはだいぶ違うのだが。
後になって知ったが、茶道部や調理部にもしれっと活動に参加したり遊びに行ったりしている男子生徒はいるらしい。こんなことになっているのは部活動紹介の用紙によるところが大きい。その内容のほとんどが何年も使いまわしで、部員から要望がない限り変わらないという。昼に来た彼女は園芸部の欄を自分で書き換える気でいたが、それを先輩が止めたわけだ。ここを俺たち二人で占有するために、男子部員は募集していない、ということにしておきたかったのだ。
「小学校で、六年生を送る会ってあっただろ」
突然何を言い出すのかと思いながら、俺は「あったあった」と相槌を打った。卒業式とは別に、在校生が歌ったり踊ったりと出し物をする行事だ。自分たちが卒業するときにどんな催しがあったかなんて、もうまったく記憶にないが。
「お前、俺ら六年に手紙を書かなきゃいけないからって、手に手紙って書いてて、一応サプライズだったのに前の日にバレてたよな」
「そうだっけ」
確かに小学生のときは宿題や持ち物をよく手に書いていた。でも先輩のときの送る会やその手紙のことを言われてもぴんとこない。小学五年生というのがひどく遠くに感じられる。
「手紙って、何書いたっけ」
「忘れたのかよ。俺はちゃんと覚えてるぞ」
「あ、待って待って、絶対恥ずかしいやつじゃん」
「『うめ田先ぱいと、ずっといっしょにいたいです』って」
「わーっ」
治まってきていた火照りがまたぶり返す。顔から首まで再び真っ赤になったに違いない。
「各部の五年キャプテンから六年キャプテンに渡すやつでさ、本当なら卒業するメンバー全員に宛てて書くもんなのに、お前俺のことしか書いてねえんだもん」
先輩はその手紙を思い出すように遠くを見つめながら嬉しそうに言った。ものすごく恥ずかしい一方で、先輩が幸せそうな顔をしているので満たされた心地になる。
だんだん思い出してきた。送る会の後に六年は部ごとに集まって、キャプテンがその手紙を読み上げる流れだった。俺も自分が卒業するときに次のキャプテンの五年生から手紙をもらった。内容はもう覚えていないが、その手紙を確かに俺はメンバーの前で読んだのだ。先輩は俺が書いたものをどんな気持ちで読み上げたのだろう。小五の俺はどんな気持ちでそれを書いていたのだろう。
どんな気持ちも何も、ただ純粋に「ずっといっしょにいたい」という思いで綴ったはずだ。そこに嫌われたくないとか引かれたらどうしようとか、ためらう気持ちは微塵もない。そんなことは思いつきもしなかっただろう。小学生の俺が羨ましかった。
「あの手紙があったから中学でもバスケやって、小学校にも顔出してやってたんだぜ」
そうだ、先輩は中学だけでなく小学校卒業後も母校の体育館にわざわざやってきていた。当時はバスケがとても好きな人なんだろうと思っていたけどもちろん中学でもバスケ部に入っていたわけで、あの頃から俺に会いに来ていたことになる。中一の先輩も高一の先輩もまったく同じことをしていた。
「中学でバスケやりながら待ってたみたいに、高校でもバスケ部でお前が来るのを迎えてやりたかったんだけどな。……できなくてごめんな」
珍しく殊勝な言葉に俺ははっとした。「バスケ部がいいのか」「バスケがしたいのか」と先輩はたびたび俺に訊いてきた。先輩なりにバスケ部を辞めたことを気にしていたのかもしれない。
午後からずっと、先輩が俺のことを好きかそうでもないかで陰鬱としていたのが嘘のように、今の俺は全部の花びらが好きの一色で、だからこんな想像もできる。先輩ならあの連中を軽くいなしながらバスケ部を続けられたはずだ。だけどそうしなかったのは、俺のためだ。俺が三年にさっきのような絡まれ方をされたり嫌な気分になったりしながら部活を続けるのは、先輩には耐えられないはずだ。それで先輩はバスケ部でいることを諦めたのではないか。先輩は俺が思っている以上に、俺のことを思っているから。そんなことを考えていると体の内側から温かいものが広がるようだった。だってそうだとしたら先輩、俺のことめちゃくちゃ好きじゃん。
「今度ボール一個パクってくるか。そのうちゴールを立ててもいいな」
冗談めかしに言っているが先輩なら本当にやりかねない。先生やほかの園芸部員に目をつけられて追い出されたらかなわない。
「いいって、いらねえって」
俺は慌てて言う。それから、今なら言えると思って、照れる気持ちを抑えて先輩のほうを向き、思い切って言った。
「先輩といられるだけで、いい」
先輩は一瞬目を見開いて、それからその目を細めて満足そうに微笑んだ。愛おしむような眼差しを向けられて、やっぱり先輩は俺のこと大好きだよなと改めて思った。
しばらく見つめ合うかたちでいた俺たちの耳元で、ブンと耳障りな音が短く響いた。俺はその嫌な音にびくりと震え、正体を探すと予想通りそれは蜂だった。幸い俺たちからはすぐに離れ、プランターのほうに飛んでいった。
「お前、びびりすぎ」
ほっとため息をついた俺を先輩が笑う。蜂の羽音は誰だって嫌だろう。
蜂は相変わらず花に止まらない。近くを漂うようにふらふらするだけでどこかへ行ってしまった。昼にもこんなことがあった。先輩が花に対して虫がつかないように何か施しているのではないか。
「あの花、何かしてんの」
「何かって?」
「蜂が止まんねえなと思って。先輩が育てたから止まりにくいとか」
自分のものにするのが大好きな人だ。冗談のつもりで口にしたが、途端にそんな気がしてきてしまう。が、先輩はあっさり「何もしてねえよ」と返した。
「蜂だって、いちいち花に止まって花粉とか蜜があるかなんて確認してられないだろ。蜂は花の電場ってのを感じて、止まるか止まらないか決めてるんだと」
「電場……」
電気とか磁石とかの類は俺の特に苦手な分野だ。先輩はもちろんそんなことも承知していて、俺が微妙な表情をしたのを見て噴き出した。
「蜂も花も電気を帯びてるんだ。蜂が花粉を集めに花に止まると、その花の電場が変わる。後から来た蜂はその電場を感じ取って、もう花粉は取られた後なんだなってわかるわけ」
先輩は俺の右手をとり、手のひらの文字をなぞった。くすぐったくなるような、触れるか触れないかの感触にどきりとする。
「しるしを付けてるみたいだよな。これはもう俺が手を付けたぞ、触んじゃねえぞってさ」
わざと耳元で囁くように言われて背中のほうまで甘い痺れのようなものが走った。先輩の話はまるで俺が花に喩えられているみたいで、俺は花なんてガラでもないから可笑しかった。だけど先輩の振る舞いはしるしを付ける蜂そのものといえた。中学のかつての仲間たちの前でも、今朝の教室でも、さっきの齊藤に対しても先輩は俺のことを自分のものだと臆面なく主張した。もしかしたら元生徒会長やほかの園芸部員にまでもうすでに知れ渡っているのかもしれない。
「でも蜂は、ほかの花にも飛んでいくだろ」
ドキドキさせられたままなのも癪なので言い返してみる。すると先輩は俺の肩に腕を回して、
「じゃあ、しっかり捕まえといてもらわねえとな」
と言って、俺の体を抱き寄せた。これでは捕まえるのが逆だ。
俺は先輩に体を預けるようにしてもたれかかった。もう少しやってもいいかなと思い、ぐりぐりと身じろぎするように先輩とくっついている体の右半分を擦りつけた。
「何」
迷惑どころか嬉しそうに先輩が訊く。
「電気してる」とどう言えばいいかわからないまま思いつきで答える。
蜂がどんなふうにして花の電場を変えているのか知らないが、そんなイメージだ。ひとにはわからないだろうが先輩には伝わるだろう。俺ばっかりが先輩のものになっているんじゃない。先輩だって俺にとってはそうなのだと示したかった。言うまでもなく先輩がよそへ飛んでいくことはないだろうけど、俺からももっと、この気持ちを伝えていきたいと思った。
俺の体を抱く腕に優しく力が加わった。こんなふうにストレートに甘えたのは初めてだ。照れくさくて先輩の顔を見られない。視界の端でプランターのデイジーが風に揺れていた。先輩もきっと、俺の好きなあの無防備で満足そうな表情でそれを見ていることだろう。