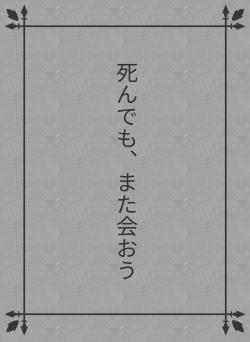「そうだ、あき。」
「なぁに勝兄?」
「雅さんの秘密知ってるか?」
「へっ知らないけど。教えて教えて。」
「雅さんはへそピがあいている。」
「へそピ!!てか、なんで知ってるの?」
「それは雅さんに聞いてみな。」
「雅!!」
「どうされました?そんなに慌てて。」
「勝兄がなんで雅のへそピ知ってるのー。」
「勝宏坊っちゃんはまた余計なことを。」
「なんで、ねぇなんで。」
「では、少し昔話をしましょうか。」
―――むかしむかし、まだ私が29程の頃。私は少々遊び人でした。私の仕事で急を要することがあり雇い主の息子が私を迎えに行きました。指定された場所はホテルで私は事後でした。少々……いやかなり手荒な人で私はパンイチで彼を迎えました。その時にみられたのでしょうね。
「雅って遊び人だったの……?手荒な人って…………?てか、勝兄ずるい。僕も雅のパンイチみたい。」
「欲目ですねぇ。」
純粋な目で欲望にまっすぐで、汚れない明宏坊っちゃんがどうしても羨ましくて、時々虚しくなる。そんな人に自分は好かれているんだと思うと本当に申し訳ない気持ちになる。純粋とは程遠くて汚れを知りすぎた私なんかに彼は相応しくない。
「―――雅。ねぇ雅ってば。」
「あっはい。どうされました?」
「いや、雅って僕のこと好きだよねって話。」
「それは、またなんで?」
「6割方、勘なんだけど。一番の理由は僕を見る目かな。」
「それはどんな?」
「自覚ないの?大好きで大事でたまらないって目。」
「そうですか…………。」
自覚はない。第一彼は私のタイプではないし、恋愛対象外のはずだ。そのはずだったのに。いつの間にこんなに好きになっていたのだろう。私の中心にはいつも明宏坊っちゃんがいて、それが当たり前で、でもそれ以上に彼が私の深層部に入ってきて。けれど嫌悪感も何もなくて、ただただ安心感に満ちていて。これが恋なのだろうか?それならば私の初恋は明宏坊っちゃんかも知れない。こんなに美しい気持ちになったことなかった。もしかしたら忘れていただけかも知れない。
「雅。真っ赤。」
「これは、違うんです。」
「何が違うの?」
「つ…………。」
「ゆっくりでいいから聞かせて。」
「貴方には負い目を感じています。それは無くなることはありません。私は貴方に相応しくない。」
「相応しいとか相応しくないとか誰が決めるの。恋するのにそれは必要?少なくとも、僕は相応しいと思うよ。」
「好きですよ、そういうところも。好きなんです。でも…………。私は恋が怖い。貴方みたいに純粋に楽しめない。辛いことも沢山ある、これからきっと。」
「そうだね。でも乗り越えられると思わない?辛くても良い。雅の隣にいれるならきっと辛くなんてない。雅の気持ちを知っても尚、このままでは居られないよ。せっかく両思いなのに。」
「明宏坊っちゃんがそこまで言うなら、きっと大丈夫かもしれませんね。」
「えってことは!?」
「お付き合いしますか?」
「勿論!!」
「なぁに勝兄?」
「雅さんの秘密知ってるか?」
「へっ知らないけど。教えて教えて。」
「雅さんはへそピがあいている。」
「へそピ!!てか、なんで知ってるの?」
「それは雅さんに聞いてみな。」
「雅!!」
「どうされました?そんなに慌てて。」
「勝兄がなんで雅のへそピ知ってるのー。」
「勝宏坊っちゃんはまた余計なことを。」
「なんで、ねぇなんで。」
「では、少し昔話をしましょうか。」
―――むかしむかし、まだ私が29程の頃。私は少々遊び人でした。私の仕事で急を要することがあり雇い主の息子が私を迎えに行きました。指定された場所はホテルで私は事後でした。少々……いやかなり手荒な人で私はパンイチで彼を迎えました。その時にみられたのでしょうね。
「雅って遊び人だったの……?手荒な人って…………?てか、勝兄ずるい。僕も雅のパンイチみたい。」
「欲目ですねぇ。」
純粋な目で欲望にまっすぐで、汚れない明宏坊っちゃんがどうしても羨ましくて、時々虚しくなる。そんな人に自分は好かれているんだと思うと本当に申し訳ない気持ちになる。純粋とは程遠くて汚れを知りすぎた私なんかに彼は相応しくない。
「―――雅。ねぇ雅ってば。」
「あっはい。どうされました?」
「いや、雅って僕のこと好きだよねって話。」
「それは、またなんで?」
「6割方、勘なんだけど。一番の理由は僕を見る目かな。」
「それはどんな?」
「自覚ないの?大好きで大事でたまらないって目。」
「そうですか…………。」
自覚はない。第一彼は私のタイプではないし、恋愛対象外のはずだ。そのはずだったのに。いつの間にこんなに好きになっていたのだろう。私の中心にはいつも明宏坊っちゃんがいて、それが当たり前で、でもそれ以上に彼が私の深層部に入ってきて。けれど嫌悪感も何もなくて、ただただ安心感に満ちていて。これが恋なのだろうか?それならば私の初恋は明宏坊っちゃんかも知れない。こんなに美しい気持ちになったことなかった。もしかしたら忘れていただけかも知れない。
「雅。真っ赤。」
「これは、違うんです。」
「何が違うの?」
「つ…………。」
「ゆっくりでいいから聞かせて。」
「貴方には負い目を感じています。それは無くなることはありません。私は貴方に相応しくない。」
「相応しいとか相応しくないとか誰が決めるの。恋するのにそれは必要?少なくとも、僕は相応しいと思うよ。」
「好きですよ、そういうところも。好きなんです。でも…………。私は恋が怖い。貴方みたいに純粋に楽しめない。辛いことも沢山ある、これからきっと。」
「そうだね。でも乗り越えられると思わない?辛くても良い。雅の隣にいれるならきっと辛くなんてない。雅の気持ちを知っても尚、このままでは居られないよ。せっかく両思いなのに。」
「明宏坊っちゃんがそこまで言うなら、きっと大丈夫かもしれませんね。」
「えってことは!?」
「お付き合いしますか?」
「勿論!!」