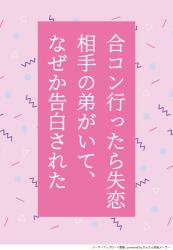※付き合う前のお話
はじめて存在を意識したのは、図書室で泣いている姿を見てからだった。
その日の放課後。俺は図書委員で、カウンターにつっぷしながら、同じ委員会の女子と楽しく会話をしていた。
「芹沢、これ棚に戻しておいて」
その子から返却本を受け取り、「りょうかーい」とだけ答えて立ち上がる。放課後の図書室は静かで、カウンターでの会話も小声でしかできない。だからこそ、奥から聞こえてくる誰かのすすり泣くような小さな息づかいが、妙に耳に残った。
本を棚に戻し終えてから、鼻をすする音を頼りに図書室の奥に向かった。
黒髪の男子生徒が、奥の席にひとりだけぽつんと座っている。よく見ると肩が小刻みに震え、本を持つ指先が白くなるほど力が入っていた。
俺は本棚の影に身を隠すようにして、誰かさんの姿を見つめていた。
ぐすっと鼻をすする音がして、次の瞬間、彼の目からぽろぽろと涙がこぼれていくのを見た。大粒の涙が、頬を伝って落ちる前に、彼の指先が少しだけ乱暴な仕草で涙を払っていく。
それが鈴木だった。その時は、名前も知らなかったのだけれど。
他の誰にも気づかれないように、でも自分の感情にはとても正直に、鈴木は泣いていた。鈴木が持つ繊細さと強さが同時に伝わってきて、俺はなぜか胸が締め付けられるような感覚に陥った。
小柄な鈴木は図書室のいちばん端っこの席で、俺たちがいたカウンターにも、ほかの利用者にも背を向けるようにして座っていた。誰にも気づかれないように、誰にも邪魔されないように、そっと物語の中に沈んでいる。
俺はもう目が離せなくなっていた。
鈴木は本の世界に没頭していて、俺の存在などいっさい気づいていなかった。無防備な泣き顔に、胸の奥がざわめく。
声をかけたかった。普段の俺なら当然そうしていたと思う。他の人間にするように、軽いノリで「えー、めっちゃ泣いてんじゃん。この本おもしれぇの? 俺にも読ませてよ」そんな風に。
でも、そんなことをしたら名前もわからない彼は慌てて涙を隠し、きっと俺の前からすぐに逃げていってしまうような気がした。
物語に心を奪われて、感情があふれ出すほど没頭する姿。それは俺が持ち合わせていない純粋さで、何だか猛烈にうらやましいと思った。同時にどんな物語を読んでいるのか、なぜそこまで心を動かされるのか、知りたくなった。
俺ができることは、鈴木の邪魔をしないようにひっそり見つめることと、鈴木がここを出て行く前に読んでいる小説の情報を頭にたたき込むことだけだった。あの本を俺も読んでみたい。それが鈴木の世界に一歩近づく唯一の俺の手段だった。
視力はかなりいいほうだが、光の反射と鈴木の白い指先で隠されてしまい、あいにくタイトルが読めなかった。見えるのは『石橋』というおそらく作者の名字と、でかでかと帯に書かれている『はせふか』の文字だけ。
どれだけ鈴木を見つめていたのか、鈴木は手早く涙を拭うと、ふいに我に返ったように周囲をきょろきょろ見回した。俺は咄嗟に本棚に隠れてしまった。そして、もう一度鈴木の姿を探したときには、もう彼はいなくなっていた。
「あのさ、さっき奥の席で本読んでた男子生徒いたじゃん。黒髪でこんくらいの背の……知ってる?」
図書委員の女子にさりげなく尋ねると、
「多分、鈴木創くんだよ。同じ一年の」
と答えが返ってきた。
「……鈴木、か」
名前を知って、妙に胸が熱くなったのを今でも覚えている。
学校帰りに立ち寄った書店で、検索機の前に立ちすくむ。『石橋』という作者名で検索したら、画面に表示された『1372件見つかりました』の文字にめまいがした。これでは針に糸を通すようなものだ。
もうひとつのヒントである『はせふか』で検索し直したが、今度は『該当する商品はありません』という冷たい文字が画面に浮かぶ。店内を見回し、小説売り場を隅から隅まで探したものの、見つける手がかりは得られない。
諦めかけたが、ふとスマホを取り出した。『石橋 はせふか』このワードで検索すると、答えがあっさりと見つかった。
――石橋叩割先生のBL小説デビュー作 "はせふか"の純愛に必ず涙する。
「……あ、BLなんだ」
どうやら『はせふか』というのはカップリング名だったらしい。少しだけ意外に思いつつ、BLコーナーでようやくお目当ての本を見つけ、さっそく買って帰った。
リビングで読んでいたら、姉貴に「BL小説? しかも石橋先生のじゃん! なんで? アンタ急にどした……?」と不思議がられた。
俺だってどうしてこんなことになったのかわからない。だけど、読み進めるうちに徐々に引き込まれていった。
夕飯を食べてからもずっと読んでいた。友人たちからひっきりになしにラインのメッセージがきていたけれど、今日は返せそうにない。
「たぶん、ここだ……」
物語も佳境に入ったところで、受けが攻めを思うあまり、離れていく場面があった。細かく描写される受けの心の痛み。胸が締め付けられる感覚が生々しくて、俺も思わず目頭が熱くなった。
鈴木もこの場面で泣いていたのだろうか。それとも、もっと先の展開で? 本を読み進めるうちに、鈴木の反応が気になって仕方なくなった。彼はどのシーンに共感して、どこで涙したんだろう。どのセリフが彼の琴線に触れたのだろう。俺には知る由もない。
気がつけば深夜二時。最後まで読み終えて、号泣している自分を笑った。まさかこんなに風に感情移入するとは思わなかった。
頬を伝う涙を拭いながら、本を閉じる。
なぁ、鈴木。このBL小説、おもしろかったよ。すげぇよかった。鈴木はどこが好きだった? どこでキュンとした? どこで泣いた?
ベッドにあお向けになりながら、もう一度あの図書室の光景を思い出す。
勝手に鈴木の世界に一歩近づいたような、そんな満足感と高揚感が入り混じり、俺はそんな自分に苦笑いをこぼすしかなかった。
これじゃあまるで鈴木に恋をしているみてぇじゃん。
自分でもばかみたいだと思うほど、鈴木創という同級生が気になって仕方なくなっていた。図書室で泣いている姿を見たあの日から、鈴木のことを意識してしまう。知れば知るほど、彼の行動や仕草ひとつひとつが目に入ってくる。
鈴木が持っているBLをおそろいで買い集め続けた結果、本棚はいっぱいになってしまった。俺は鈴木のおかげで、BLという素晴らしい世界を知ったのだ。
そうして声がかけられないまま迎えた一年の冬。なぜか鈴木が普段一緒にいた友人たちと距離を置いているのに気づいた。ケンカでもしたのだろうかと不思議に思う。
その謎が解けたのは、一週間後のことだった。
放課後、佐伯たちを教室に待たせて一年の男子トイレに立ち寄ろうとした時、中から声が聞こえてきた。
「マジでさー、最近、鈴木と気まずくね?」
鈴木の名前が聞こえて、一瞬ドキリとしながらも、そのままトイレに入った。一年が三人。どこかで見たことがあると思い、ようやく思い出す。前まで鈴木と一緒につるんでいたクラスメイトたちだ。
「わかる。あいつ、ひとりでずっとBL読んでるよな」
「俺らに気づかれたくないんだろうけど、めっちゃバレバレなのウケる」
「おいおい、あんま言うなって!」
「は? お前も言ってたじゃん、引いたって!」
げらげらと笑う声が脳内に響く。腹が立った。勢いよく「なぁ」と声をかけ、洗面台で手を洗っていた彼らを見据えた。
「BLの話? 俺もすげぇ好きなんだけど、おすすめあったら教えてよ」
その口で、その声で、鈴木のことを勝手に語るな。苛立ちが収まらない。彼らは俺の姿を見て、一瞬で怯えたような表情に変わった。
「せ、芹沢……くん……」
俺はこいつらの名前も知らないけれど、どうやらこいつらは俺を知っているらしい。
「言えよ、俺にも引いたって。そいつと同じでBL好きなんだから」
にこりと笑みを浮かべながら言うと、彼らは何も言わず逃げるように出て行った。
もしかすると鈴木はあいつらに何かを言われてしまったのかもしれない。それとも、自分の趣味を隠すために自ら距離を置いたのか。やっぱり俺には知る由もなかった。
「おせーよ、芹沢ぁ」
教室で待ちぼうけを食らったのが気に入らなかったのか、佐伯たちが不機嫌そうな声で俺を呼んだ。その声に、ようやく我に返る。
「……え、何? どうしたんだよ、芹沢。怪物でも見たような顔してるけど?」
泣いている鈴木の姿が脳裏に浮かんでいた。小説に感動したからじゃない。傷ついて泣いている鈴木の姿だ。
「お前らさ、もし俺がBL大好きだって言ったらどうする?」
「なに、急に」
「BL大好きでも、別にどうもしねぇけど……なぁ?」
「うん。つうか、早くファミレス行こうって。BLの話聞いてやるから」
佐伯も竹内も岩崎も、予想どおりけろっとした顔をしていた。
ほら、こういうやつらだっているよ、鈴木。
心の中のつぶやきは、どうやったって鈴木には届かない。
冬休み明け、鈴木は相変わらずひとりでBLを読んでいた。それから、スマホを操作していたり、キャンパスノートに何かを書き込んでいることも多くなった。どこかふっきれたような鈴木の表情を見て、心臓がぎゅっとなる。
きっと鈴木は、自分の好きなものを隠して生きることを選んだんだと思った。
誰かに正体を見せることの怖さも、好きなものを好きだと言えないつらさも、なんとなくだけれどわかる。そんな重荷を抱えていても、ひとりで凜として立っている鈴木がとても愛おしく思えた。
俺は決めた。鈴木が怖がらないように、傷つけないように、驚かさないように近づきたいと。彼が本当の自分を隠さなくていいように。
日々沸き上がるこの激しい感情に名前をつけるのをずいぶんとためらっていたけれど、もう逃げられないと悟った。
これは、恋だ。
好きだよ、鈴木。話したこともないし、鈴木は俺のことを知らないだろうけれど、それでも俺はお前が好きだ。
そして季節は巡り、二年になった俺は奇跡的に鈴木と同じクラスになれた。けれど、実際に鈴木と仲良くなるきっかけはなかなか掴めなかった。鈴木は二年になっても、ひとりでBLを読んでいた。俺は相も変わらず、鈴木の横顔をじっと見つめるだけだ。
そんな俺たちの関係を変えるきっかけになったのは、選択授業の日だった。誰かが机に忘れていったノートを見つけて、開いてみると——そこにはオリジナルの受けや攻めの物語が紡がれていた。
鈴木だとすぐにわかった。名前は書かれていなかったけれど、その独特で丁寧な字体と、読んだことのあるBL作品の影響が随所に見られたからだ。
――これ、鈴木の?
声をかけた時の彼の驚いた表情も、赤くなった頬も、どうしようもないくらいかわいかった。
今では『芹沢システム』なるものまで築き上げ、鈴木が小説を書く間、俺が鈴木にご飯を食べさせている。
鈴木の小説を読むたび、心が震えた。鈴木がどんな思いで物語を紡いでいるのか、どんな想像の世界を持っているのか、少しずつ知ることができる。鈴木の物語の「読者一号」という特別な立場は、俺にとって何物にも代えがたい宝物だった。
でも、足りない。もっと、もっと、鈴木に近づきたい。
「なぁ、なんであんなに鈴木って、かわいいわけ?」
その日の昼休み。昼飯を食べ終えた俺は鈴木が美化委員として中庭の花壇で作業している姿を、ベンチに座ってぼんやりと眺めていた。本当は空き教室でいつものように鈴木を抱っこしていたかったのだけれど、委員会があると言われたらどうすることもできない。だから、今日はわざわざ佐伯たちを中庭に集合させたのだ。
「え? 何? 鈴木?」
隣で紙パックの野菜ジュースを飲んでいた佐伯が、不思議そうに鈴木のほうを見やる。彼の視線の先で、鈴木は丁寧に苗を植えていた。
「……ああ、たしかにかわいいよな」
佐伯が言うと、竹内も「わかる」と同意して鈴木を見つめた。鈴木は俺たちに見られていることも知らず、植えたばかりの花に今度は一生懸命水をやっている。
「素直だし、真面目だし、好感度高ぇ」
竹内が続ける。たしかにそのとおりだ。鈴木は自分を偽ったり、飾ったりせず、いつでも誠実に生きている。そんなとこもめちゃくちゃかわいいと思う。
「あと笑い上戸っつうの? くだんねぇことに笑ってる顔もかわいい」
岩崎もそう言いながら、鈴木のほうを見ていた。仲良くなってから気づいたことだ。鈴木はちょっとした冗談でけらけらと笑ってくれる。……だけど、どうやらそれは俺だけってわけじゃないらしい。
「は? なんなのお前ら! 俺の鈴木なんだけど!」
急に胸の内側から湧き上がる感情を抑えきれない。鈴木のことになると、こっちはガチモードだ。
「自分で聞いといて……さすがに理不尽すぎる」
佐伯が呆れたように言う。
「つーか、お前のじゃねぇだろ」
「そーだそーだ」
岩崎と竹内が同時に言って、せせら笑うように口角を上げた。
「マジでさ……俺の鈴木が、かわいすぎるせいだわ……」
最初は単なる興味だけだったのに、いつの間にかこんなにも鈴木のことを考えるようになっている。
「全然話聞いてねぇ」
「メンタル強すぎ」
「ワガママボーイ極めんな」
三人の言葉は耳に届いても、すぐに右から左に抜けていく。今、俺の頭の中は鈴木でいっぱいだった。
「俺がこれから稼ぐ全財産鈴木に使いたい……」
「芹沢、キモいて……」
「芹沢、無理あるて……」
「鈴木、逃げろて……」
どうしようもなく、胸の奥が熱くなる。こんな感情、初めてだった。
スコップを持って土を固めている愛らしい鈴木に釘付けになりながらも、ぼそりとつぶやく。
「お前ら的にどう思う? 脈ありだと思う?」
急に不安になって、友人たちの意見を聞きたくなった。こっちはこんなに鈴木のことを見つめているのに、あっちが俺をどう思っているのか、さっぱりわからない。鈴木と距離を縮める前、鈴木はまぶしいものでも見るかのような視線をいつも俺に投げかけてきた。嫌われてはいないと思うし、今は信頼関係を築けているとも思う。だけど、恋愛的な要素で言えば、鈴木は『キングオブ鈍感』な男子高校生なのだ。(まあ、そこがかわいいんだけど)
「せーので言おう」
と、佐伯がにやっとして言う。
「せーの」
「なし」
「あり」
「なし」
三人中ふたりも「なし」と言ったことに、急に苛立ちがこみ上げてきた。
「今、なしって言ったやつ、名乗り出ろよこら。つーか、連帯責任で全員ボコボコにすっから!」
冗談半分、本気半分で三人に詰め寄ると、竹内が大声で鈴木を呼んだ。
「鈴木ー! 芹沢の機嫌悪いー!」
突然の呼びかけに、鈴木がぱっと顔を上げる。そして、彼は園芸用の手袋をしたまま俺たちのところへ来た。
「どした? ……芹沢?」
鈴木が少し首を傾げて、俺を見つめる。その仕草がたまらなくかわいくて、さっきまでの苛立ちがどこかへ消えていった。のだけれども……、
「聞いてよ、鈴木。芹沢がまたワガママばっか言っててさぁ」
「はぁ? お前らだろ」
佐伯たちがにやにやと薄気味悪い笑顔でそんなことを言うから、また苛立ちが再燃する。
「鈴木、こいつらムカつく」
むすっとして鈴木に言うと、鈴木は意外な行動に出た。園芸用の手袋を外し、近くの水道で手を洗って丁寧にハンカチで拭いてから、俺の前に立つ。
「よしよし……芹沢、いい子いい子」
鈴木が俺の頭を撫でる。その優しい手の温もりに、単純な俺の心臓はドクドクと高鳴った。
「……ん」
自然と声が出てしまう。他のやつだったら手を振り払っているが、鈴木に撫でられるのは嫌いじゃない。むしろ大好きだ。一生こうされていたいし、鈴木にもしてやりたい。
「芹沢、手、貸して」
言われるがまま手を差し出す。鈴木の手は俺よりも小さく、指先は細くて、少し冷たかった。
「……あったかいね」
鈴木が俺の手を握りながら言った。
「芹沢さ、たぶん眠いんだろ? 芹沢って眠いとお手々熱くなるから」
鈴木の言葉に、くらっと目が回る。『お手々』って……俺の手をそう呼ばれたのは、幼稚園以来かもしれない。でも鈴木から子供扱いされるのは、なぜか全然嫌じゃなかった。
「ちょっと、寝てたら? 俺、花を植え終わったら起こしにくるよ」
「……ん」
それしか答えられない。もっとうまくやれるはずなのに、鈴木の前だといつもの調子が出せなくなる。
「俺の上着貸すから、ちゃんといい子にしてて、芹沢」
鈴木が制服の上着を脱ぎ、俺に差し出してきた。彼の体温とかすかな香りがまだ残っている上着を受け取ると、体の芯がじわりと熱を持つ。
「……ん」
「よし、じゃああとでね、芹沢」
鈴木はにこりと笑うと、また園芸用の手袋をはめて、花壇の前に行ってしまった。
「何が『……ん』だよ。キッショ……」
後ろで竹内がつぶやいたが、まったく気にならなかった。
「今の聞いた? お手々だって……鈴木、かわいすぎ……ブレザーも貸してくれた……かわいすぎ……やっぱ俺のこと好きじゃね……?」
佐伯たちに向かって言うと、岩崎が眉をひそめる。
「こいつ自分の悪口聞こえない設定になってる?」
「あー……ほんと全財産鈴木に使いたい……。つーか付き合いたい……鈴木ともっかいキスしてぇ……今度は舌入れてぇ……」
もうブレーキが効かない。心の声がダダ漏れになっていく。
「最後にどぎつい本音言うのやめろて」
佐伯が冗談っぽくそう言うと、竹内も岩崎もおもしろがるように「鈴木、逃げろて~~」と声を出して笑った。
自慢じゃないけれど、実は鈴木とは、一度キスをした仲なのだ。
鈴木の隣にいられるだけで満足していた。少なくともキスをするまでは。けれど、一度鈴木の唇の感触を知ってしまったあの日から、日に日にその言葉は嘘になっていく。もっと近づきたい、もっと触れたい、もっと知りたい、奥の奥まで——その思いを抑えるのは、想像以上に難しかった。
鈴木を怖がらせないよう、一歩一歩ゆっくりと距離を縮めていく。それが正しいと頭では理解していても、心は時に悲鳴を上げる。この我慢が、いつか報われる日が来るのだろうか。
鈴木の警戒心は思った以上に強固……というか、俺の渾身のアピールが効いている気がしない。鈴木の心の壁を越えるのは簡単じゃないのだ。あと一歩のところで踏み出せないもどかしさに、胸が締め付けられる。
だけど、こういう時こそ冷静にならなければいけない。急いては事を仕損じると言うではないか。焦るほど遠ざかるものだ、鈴木という愛らしい人間は。
ゆっくり、じっくり、確実に。鈴木の心が俺に向かうまで、待ち続ける。
「……俺寝るわ。鈴木が起こしに来るからさ、お前ら、マジで静かにしてて」
そう言って、鈴木の上着を肩にかけ、中庭のベンチに横になった。鈴木の甘い匂いが鼻をくすぐる。
「鈴木の匂いに包まれて寝んの……最高……」
半分夢ごごちでつぶやくと、佐伯たちの声が遠くから聞こえてくる。
「だる……」
「うざ……」
「きも……」
どんな悪口も気にならない。鈴木の匂いを嗅ぎながら、いつか鈴木の心に触れられる時をずっと願っている。
もちろん、逃がすつもりなんてない。
はじめて存在を意識したのは、図書室で泣いている姿を見てからだった。
その日の放課後。俺は図書委員で、カウンターにつっぷしながら、同じ委員会の女子と楽しく会話をしていた。
「芹沢、これ棚に戻しておいて」
その子から返却本を受け取り、「りょうかーい」とだけ答えて立ち上がる。放課後の図書室は静かで、カウンターでの会話も小声でしかできない。だからこそ、奥から聞こえてくる誰かのすすり泣くような小さな息づかいが、妙に耳に残った。
本を棚に戻し終えてから、鼻をすする音を頼りに図書室の奥に向かった。
黒髪の男子生徒が、奥の席にひとりだけぽつんと座っている。よく見ると肩が小刻みに震え、本を持つ指先が白くなるほど力が入っていた。
俺は本棚の影に身を隠すようにして、誰かさんの姿を見つめていた。
ぐすっと鼻をすする音がして、次の瞬間、彼の目からぽろぽろと涙がこぼれていくのを見た。大粒の涙が、頬を伝って落ちる前に、彼の指先が少しだけ乱暴な仕草で涙を払っていく。
それが鈴木だった。その時は、名前も知らなかったのだけれど。
他の誰にも気づかれないように、でも自分の感情にはとても正直に、鈴木は泣いていた。鈴木が持つ繊細さと強さが同時に伝わってきて、俺はなぜか胸が締め付けられるような感覚に陥った。
小柄な鈴木は図書室のいちばん端っこの席で、俺たちがいたカウンターにも、ほかの利用者にも背を向けるようにして座っていた。誰にも気づかれないように、誰にも邪魔されないように、そっと物語の中に沈んでいる。
俺はもう目が離せなくなっていた。
鈴木は本の世界に没頭していて、俺の存在などいっさい気づいていなかった。無防備な泣き顔に、胸の奥がざわめく。
声をかけたかった。普段の俺なら当然そうしていたと思う。他の人間にするように、軽いノリで「えー、めっちゃ泣いてんじゃん。この本おもしれぇの? 俺にも読ませてよ」そんな風に。
でも、そんなことをしたら名前もわからない彼は慌てて涙を隠し、きっと俺の前からすぐに逃げていってしまうような気がした。
物語に心を奪われて、感情があふれ出すほど没頭する姿。それは俺が持ち合わせていない純粋さで、何だか猛烈にうらやましいと思った。同時にどんな物語を読んでいるのか、なぜそこまで心を動かされるのか、知りたくなった。
俺ができることは、鈴木の邪魔をしないようにひっそり見つめることと、鈴木がここを出て行く前に読んでいる小説の情報を頭にたたき込むことだけだった。あの本を俺も読んでみたい。それが鈴木の世界に一歩近づく唯一の俺の手段だった。
視力はかなりいいほうだが、光の反射と鈴木の白い指先で隠されてしまい、あいにくタイトルが読めなかった。見えるのは『石橋』というおそらく作者の名字と、でかでかと帯に書かれている『はせふか』の文字だけ。
どれだけ鈴木を見つめていたのか、鈴木は手早く涙を拭うと、ふいに我に返ったように周囲をきょろきょろ見回した。俺は咄嗟に本棚に隠れてしまった。そして、もう一度鈴木の姿を探したときには、もう彼はいなくなっていた。
「あのさ、さっき奥の席で本読んでた男子生徒いたじゃん。黒髪でこんくらいの背の……知ってる?」
図書委員の女子にさりげなく尋ねると、
「多分、鈴木創くんだよ。同じ一年の」
と答えが返ってきた。
「……鈴木、か」
名前を知って、妙に胸が熱くなったのを今でも覚えている。
学校帰りに立ち寄った書店で、検索機の前に立ちすくむ。『石橋』という作者名で検索したら、画面に表示された『1372件見つかりました』の文字にめまいがした。これでは針に糸を通すようなものだ。
もうひとつのヒントである『はせふか』で検索し直したが、今度は『該当する商品はありません』という冷たい文字が画面に浮かぶ。店内を見回し、小説売り場を隅から隅まで探したものの、見つける手がかりは得られない。
諦めかけたが、ふとスマホを取り出した。『石橋 はせふか』このワードで検索すると、答えがあっさりと見つかった。
――石橋叩割先生のBL小説デビュー作 "はせふか"の純愛に必ず涙する。
「……あ、BLなんだ」
どうやら『はせふか』というのはカップリング名だったらしい。少しだけ意外に思いつつ、BLコーナーでようやくお目当ての本を見つけ、さっそく買って帰った。
リビングで読んでいたら、姉貴に「BL小説? しかも石橋先生のじゃん! なんで? アンタ急にどした……?」と不思議がられた。
俺だってどうしてこんなことになったのかわからない。だけど、読み進めるうちに徐々に引き込まれていった。
夕飯を食べてからもずっと読んでいた。友人たちからひっきりになしにラインのメッセージがきていたけれど、今日は返せそうにない。
「たぶん、ここだ……」
物語も佳境に入ったところで、受けが攻めを思うあまり、離れていく場面があった。細かく描写される受けの心の痛み。胸が締め付けられる感覚が生々しくて、俺も思わず目頭が熱くなった。
鈴木もこの場面で泣いていたのだろうか。それとも、もっと先の展開で? 本を読み進めるうちに、鈴木の反応が気になって仕方なくなった。彼はどのシーンに共感して、どこで涙したんだろう。どのセリフが彼の琴線に触れたのだろう。俺には知る由もない。
気がつけば深夜二時。最後まで読み終えて、号泣している自分を笑った。まさかこんなに風に感情移入するとは思わなかった。
頬を伝う涙を拭いながら、本を閉じる。
なぁ、鈴木。このBL小説、おもしろかったよ。すげぇよかった。鈴木はどこが好きだった? どこでキュンとした? どこで泣いた?
ベッドにあお向けになりながら、もう一度あの図書室の光景を思い出す。
勝手に鈴木の世界に一歩近づいたような、そんな満足感と高揚感が入り混じり、俺はそんな自分に苦笑いをこぼすしかなかった。
これじゃあまるで鈴木に恋をしているみてぇじゃん。
自分でもばかみたいだと思うほど、鈴木創という同級生が気になって仕方なくなっていた。図書室で泣いている姿を見たあの日から、鈴木のことを意識してしまう。知れば知るほど、彼の行動や仕草ひとつひとつが目に入ってくる。
鈴木が持っているBLをおそろいで買い集め続けた結果、本棚はいっぱいになってしまった。俺は鈴木のおかげで、BLという素晴らしい世界を知ったのだ。
そうして声がかけられないまま迎えた一年の冬。なぜか鈴木が普段一緒にいた友人たちと距離を置いているのに気づいた。ケンカでもしたのだろうかと不思議に思う。
その謎が解けたのは、一週間後のことだった。
放課後、佐伯たちを教室に待たせて一年の男子トイレに立ち寄ろうとした時、中から声が聞こえてきた。
「マジでさー、最近、鈴木と気まずくね?」
鈴木の名前が聞こえて、一瞬ドキリとしながらも、そのままトイレに入った。一年が三人。どこかで見たことがあると思い、ようやく思い出す。前まで鈴木と一緒につるんでいたクラスメイトたちだ。
「わかる。あいつ、ひとりでずっとBL読んでるよな」
「俺らに気づかれたくないんだろうけど、めっちゃバレバレなのウケる」
「おいおい、あんま言うなって!」
「は? お前も言ってたじゃん、引いたって!」
げらげらと笑う声が脳内に響く。腹が立った。勢いよく「なぁ」と声をかけ、洗面台で手を洗っていた彼らを見据えた。
「BLの話? 俺もすげぇ好きなんだけど、おすすめあったら教えてよ」
その口で、その声で、鈴木のことを勝手に語るな。苛立ちが収まらない。彼らは俺の姿を見て、一瞬で怯えたような表情に変わった。
「せ、芹沢……くん……」
俺はこいつらの名前も知らないけれど、どうやらこいつらは俺を知っているらしい。
「言えよ、俺にも引いたって。そいつと同じでBL好きなんだから」
にこりと笑みを浮かべながら言うと、彼らは何も言わず逃げるように出て行った。
もしかすると鈴木はあいつらに何かを言われてしまったのかもしれない。それとも、自分の趣味を隠すために自ら距離を置いたのか。やっぱり俺には知る由もなかった。
「おせーよ、芹沢ぁ」
教室で待ちぼうけを食らったのが気に入らなかったのか、佐伯たちが不機嫌そうな声で俺を呼んだ。その声に、ようやく我に返る。
「……え、何? どうしたんだよ、芹沢。怪物でも見たような顔してるけど?」
泣いている鈴木の姿が脳裏に浮かんでいた。小説に感動したからじゃない。傷ついて泣いている鈴木の姿だ。
「お前らさ、もし俺がBL大好きだって言ったらどうする?」
「なに、急に」
「BL大好きでも、別にどうもしねぇけど……なぁ?」
「うん。つうか、早くファミレス行こうって。BLの話聞いてやるから」
佐伯も竹内も岩崎も、予想どおりけろっとした顔をしていた。
ほら、こういうやつらだっているよ、鈴木。
心の中のつぶやきは、どうやったって鈴木には届かない。
冬休み明け、鈴木は相変わらずひとりでBLを読んでいた。それから、スマホを操作していたり、キャンパスノートに何かを書き込んでいることも多くなった。どこかふっきれたような鈴木の表情を見て、心臓がぎゅっとなる。
きっと鈴木は、自分の好きなものを隠して生きることを選んだんだと思った。
誰かに正体を見せることの怖さも、好きなものを好きだと言えないつらさも、なんとなくだけれどわかる。そんな重荷を抱えていても、ひとりで凜として立っている鈴木がとても愛おしく思えた。
俺は決めた。鈴木が怖がらないように、傷つけないように、驚かさないように近づきたいと。彼が本当の自分を隠さなくていいように。
日々沸き上がるこの激しい感情に名前をつけるのをずいぶんとためらっていたけれど、もう逃げられないと悟った。
これは、恋だ。
好きだよ、鈴木。話したこともないし、鈴木は俺のことを知らないだろうけれど、それでも俺はお前が好きだ。
そして季節は巡り、二年になった俺は奇跡的に鈴木と同じクラスになれた。けれど、実際に鈴木と仲良くなるきっかけはなかなか掴めなかった。鈴木は二年になっても、ひとりでBLを読んでいた。俺は相も変わらず、鈴木の横顔をじっと見つめるだけだ。
そんな俺たちの関係を変えるきっかけになったのは、選択授業の日だった。誰かが机に忘れていったノートを見つけて、開いてみると——そこにはオリジナルの受けや攻めの物語が紡がれていた。
鈴木だとすぐにわかった。名前は書かれていなかったけれど、その独特で丁寧な字体と、読んだことのあるBL作品の影響が随所に見られたからだ。
――これ、鈴木の?
声をかけた時の彼の驚いた表情も、赤くなった頬も、どうしようもないくらいかわいかった。
今では『芹沢システム』なるものまで築き上げ、鈴木が小説を書く間、俺が鈴木にご飯を食べさせている。
鈴木の小説を読むたび、心が震えた。鈴木がどんな思いで物語を紡いでいるのか、どんな想像の世界を持っているのか、少しずつ知ることができる。鈴木の物語の「読者一号」という特別な立場は、俺にとって何物にも代えがたい宝物だった。
でも、足りない。もっと、もっと、鈴木に近づきたい。
「なぁ、なんであんなに鈴木って、かわいいわけ?」
その日の昼休み。昼飯を食べ終えた俺は鈴木が美化委員として中庭の花壇で作業している姿を、ベンチに座ってぼんやりと眺めていた。本当は空き教室でいつものように鈴木を抱っこしていたかったのだけれど、委員会があると言われたらどうすることもできない。だから、今日はわざわざ佐伯たちを中庭に集合させたのだ。
「え? 何? 鈴木?」
隣で紙パックの野菜ジュースを飲んでいた佐伯が、不思議そうに鈴木のほうを見やる。彼の視線の先で、鈴木は丁寧に苗を植えていた。
「……ああ、たしかにかわいいよな」
佐伯が言うと、竹内も「わかる」と同意して鈴木を見つめた。鈴木は俺たちに見られていることも知らず、植えたばかりの花に今度は一生懸命水をやっている。
「素直だし、真面目だし、好感度高ぇ」
竹内が続ける。たしかにそのとおりだ。鈴木は自分を偽ったり、飾ったりせず、いつでも誠実に生きている。そんなとこもめちゃくちゃかわいいと思う。
「あと笑い上戸っつうの? くだんねぇことに笑ってる顔もかわいい」
岩崎もそう言いながら、鈴木のほうを見ていた。仲良くなってから気づいたことだ。鈴木はちょっとした冗談でけらけらと笑ってくれる。……だけど、どうやらそれは俺だけってわけじゃないらしい。
「は? なんなのお前ら! 俺の鈴木なんだけど!」
急に胸の内側から湧き上がる感情を抑えきれない。鈴木のことになると、こっちはガチモードだ。
「自分で聞いといて……さすがに理不尽すぎる」
佐伯が呆れたように言う。
「つーか、お前のじゃねぇだろ」
「そーだそーだ」
岩崎と竹内が同時に言って、せせら笑うように口角を上げた。
「マジでさ……俺の鈴木が、かわいすぎるせいだわ……」
最初は単なる興味だけだったのに、いつの間にかこんなにも鈴木のことを考えるようになっている。
「全然話聞いてねぇ」
「メンタル強すぎ」
「ワガママボーイ極めんな」
三人の言葉は耳に届いても、すぐに右から左に抜けていく。今、俺の頭の中は鈴木でいっぱいだった。
「俺がこれから稼ぐ全財産鈴木に使いたい……」
「芹沢、キモいて……」
「芹沢、無理あるて……」
「鈴木、逃げろて……」
どうしようもなく、胸の奥が熱くなる。こんな感情、初めてだった。
スコップを持って土を固めている愛らしい鈴木に釘付けになりながらも、ぼそりとつぶやく。
「お前ら的にどう思う? 脈ありだと思う?」
急に不安になって、友人たちの意見を聞きたくなった。こっちはこんなに鈴木のことを見つめているのに、あっちが俺をどう思っているのか、さっぱりわからない。鈴木と距離を縮める前、鈴木はまぶしいものでも見るかのような視線をいつも俺に投げかけてきた。嫌われてはいないと思うし、今は信頼関係を築けているとも思う。だけど、恋愛的な要素で言えば、鈴木は『キングオブ鈍感』な男子高校生なのだ。(まあ、そこがかわいいんだけど)
「せーので言おう」
と、佐伯がにやっとして言う。
「せーの」
「なし」
「あり」
「なし」
三人中ふたりも「なし」と言ったことに、急に苛立ちがこみ上げてきた。
「今、なしって言ったやつ、名乗り出ろよこら。つーか、連帯責任で全員ボコボコにすっから!」
冗談半分、本気半分で三人に詰め寄ると、竹内が大声で鈴木を呼んだ。
「鈴木ー! 芹沢の機嫌悪いー!」
突然の呼びかけに、鈴木がぱっと顔を上げる。そして、彼は園芸用の手袋をしたまま俺たちのところへ来た。
「どした? ……芹沢?」
鈴木が少し首を傾げて、俺を見つめる。その仕草がたまらなくかわいくて、さっきまでの苛立ちがどこかへ消えていった。のだけれども……、
「聞いてよ、鈴木。芹沢がまたワガママばっか言っててさぁ」
「はぁ? お前らだろ」
佐伯たちがにやにやと薄気味悪い笑顔でそんなことを言うから、また苛立ちが再燃する。
「鈴木、こいつらムカつく」
むすっとして鈴木に言うと、鈴木は意外な行動に出た。園芸用の手袋を外し、近くの水道で手を洗って丁寧にハンカチで拭いてから、俺の前に立つ。
「よしよし……芹沢、いい子いい子」
鈴木が俺の頭を撫でる。その優しい手の温もりに、単純な俺の心臓はドクドクと高鳴った。
「……ん」
自然と声が出てしまう。他のやつだったら手を振り払っているが、鈴木に撫でられるのは嫌いじゃない。むしろ大好きだ。一生こうされていたいし、鈴木にもしてやりたい。
「芹沢、手、貸して」
言われるがまま手を差し出す。鈴木の手は俺よりも小さく、指先は細くて、少し冷たかった。
「……あったかいね」
鈴木が俺の手を握りながら言った。
「芹沢さ、たぶん眠いんだろ? 芹沢って眠いとお手々熱くなるから」
鈴木の言葉に、くらっと目が回る。『お手々』って……俺の手をそう呼ばれたのは、幼稚園以来かもしれない。でも鈴木から子供扱いされるのは、なぜか全然嫌じゃなかった。
「ちょっと、寝てたら? 俺、花を植え終わったら起こしにくるよ」
「……ん」
それしか答えられない。もっとうまくやれるはずなのに、鈴木の前だといつもの調子が出せなくなる。
「俺の上着貸すから、ちゃんといい子にしてて、芹沢」
鈴木が制服の上着を脱ぎ、俺に差し出してきた。彼の体温とかすかな香りがまだ残っている上着を受け取ると、体の芯がじわりと熱を持つ。
「……ん」
「よし、じゃああとでね、芹沢」
鈴木はにこりと笑うと、また園芸用の手袋をはめて、花壇の前に行ってしまった。
「何が『……ん』だよ。キッショ……」
後ろで竹内がつぶやいたが、まったく気にならなかった。
「今の聞いた? お手々だって……鈴木、かわいすぎ……ブレザーも貸してくれた……かわいすぎ……やっぱ俺のこと好きじゃね……?」
佐伯たちに向かって言うと、岩崎が眉をひそめる。
「こいつ自分の悪口聞こえない設定になってる?」
「あー……ほんと全財産鈴木に使いたい……。つーか付き合いたい……鈴木ともっかいキスしてぇ……今度は舌入れてぇ……」
もうブレーキが効かない。心の声がダダ漏れになっていく。
「最後にどぎつい本音言うのやめろて」
佐伯が冗談っぽくそう言うと、竹内も岩崎もおもしろがるように「鈴木、逃げろて~~」と声を出して笑った。
自慢じゃないけれど、実は鈴木とは、一度キスをした仲なのだ。
鈴木の隣にいられるだけで満足していた。少なくともキスをするまでは。けれど、一度鈴木の唇の感触を知ってしまったあの日から、日に日にその言葉は嘘になっていく。もっと近づきたい、もっと触れたい、もっと知りたい、奥の奥まで——その思いを抑えるのは、想像以上に難しかった。
鈴木を怖がらせないよう、一歩一歩ゆっくりと距離を縮めていく。それが正しいと頭では理解していても、心は時に悲鳴を上げる。この我慢が、いつか報われる日が来るのだろうか。
鈴木の警戒心は思った以上に強固……というか、俺の渾身のアピールが効いている気がしない。鈴木の心の壁を越えるのは簡単じゃないのだ。あと一歩のところで踏み出せないもどかしさに、胸が締め付けられる。
だけど、こういう時こそ冷静にならなければいけない。急いては事を仕損じると言うではないか。焦るほど遠ざかるものだ、鈴木という愛らしい人間は。
ゆっくり、じっくり、確実に。鈴木の心が俺に向かうまで、待ち続ける。
「……俺寝るわ。鈴木が起こしに来るからさ、お前ら、マジで静かにしてて」
そう言って、鈴木の上着を肩にかけ、中庭のベンチに横になった。鈴木の甘い匂いが鼻をくすぐる。
「鈴木の匂いに包まれて寝んの……最高……」
半分夢ごごちでつぶやくと、佐伯たちの声が遠くから聞こえてくる。
「だる……」
「うざ……」
「きも……」
どんな悪口も気にならない。鈴木の匂いを嗅ぎながら、いつか鈴木の心に触れられる時をずっと願っている。
もちろん、逃がすつもりなんてない。