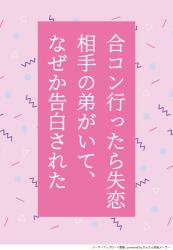その日の朝。グループラインに芹沢からメッセージが届いた。
『ふつうに寝坊した。二時限目ぐらいには間に合うから待ってて、特に鈴木』
俺は芹沢の冗談に胸が締めつけられながらも、「芹沢、うざいて~」と笑い合っている佐伯と竹内と岩崎を見つめる。
芹沢の「好きな人」の存在を知ってから今日まで、毎日が地獄のようだった。
「あのさ、……よかったら相談にのってほしいんだけど」
意を決してそう言った俺を見据え、三人のイケメンたちは軽いノリで笑った。
「おー、何?」
「芹沢じゃなくていいの?」
佐伯と竹内の言葉に、難しい顔をしてうなずく。
「芹沢には言えない。……せ、芹沢のことだから」
言いながら、俺は持っていたスマホをぎゅっと握りしめた。佐伯も竹内も岩崎もふっと笑顔をやめたかと思うと、俺の緊張が伝染したみたいに「え、何?」「どした?」「言ってみ?」と心配そうにつぶやく。
「ものすごく端的に言うと、俺、……芹沢のこと、好きになっちゃったんだ……よね……」
教室の騒がしさが遠ざかっていく。
「……」
「……」
「……」
反応が怖くて、みんなの顔を見られなかった。だけど、彼らが息を呑んだような雰囲気をしっかりと感じる。
「ほ、ほんと、ごめん。こんなこといきなり言われてもキモいよな……。でも、なんか……ひとりじゃ抱えきれなくて」
芹沢に好きな人がいると知ってから、この三日間悩みに悩みまくった。それも、ひどい嫉妬に苛まれながら。
別の世界の人間だと思っていたのに、いつの間にか俺は芹沢のことを好きになってしまっていたのだ。そして気づいたときには、もう手遅れだった。
「いや、キモいとかねぇって。俺らは全然言ってほしい」
恐る恐る顔を上げると、三人は困ったような笑顔を浮かべて俺を見つめていた。彼らの目には、俺が思っていたような軽蔑の色はなく、むしろ励ましの光が宿っているように思える。
「そりゃそうだろ」
「言われないほうがさみしいって」
優しい佐伯たちの言葉に、鼻の奥がツンと痛みを感じる。今日まで抱えていた思いが、どんどん胸の奥から洪水みたいにあふれてくる。
「ありがとな、みんな……。俺、もうほんとキモいんだ。芹沢の夢小説とか書き始めちゃうし、芹沢の好きな人のこともずっと考えてる。このままじゃ芹沢のストーカーになりそうで……」
頭を抱えながら、机に項垂れると、佐伯が普段よりもさらに落ち着いた様子で問いかけてきた。
「えーと、鈴木さ、プランA・B・Cがあるんだけど」
「う、うん……?」
プランとは何だろう? あらかじめ想定されていたような佐伯の口ぶりを、少しだけ不思議に感じた。
「……鈴木って映画とかのネタバレは平気なほう?」
なぜいきなり映画の話なのかと思ったが、正直に答える。
「むり、ネタバレは。ぜったいネタバレは見たくないし、聞きたくない」
佐伯は竹内と岩崎に目配せし、小さくうなずいた。
「じゃあ、プランAはなしで……残りはBかCだな。……鈴木的には、ひとりで自分の気持ち、芹沢に言えそう?」
俺は泣きそうな顔で佐伯と竹内と岩崎を順番に見つめた。
「……情けないんだけど、……みんな、俺が逃げないように、そばにいてくれる?」
「「「かわいい~~~」」」
三人が口を揃えて言うのを、微妙な感情で睨みつけた。あとでいくらでもからかってもらっていいから、とにかく今は早く楽になりたい。
芹沢を求めてさまよう怪物にはなりたくない。きちんと区切りをつけなければ、芹沢にだって、佐伯たちにだって迷惑をかけてしまいそうだった。だから――。
深く息を吸い、覚悟を決めた。
「俺、今日芹沢に言う」
佐伯も、竹内も、岩崎も、なぜか菩薩のような笑顔を浮かべながら、俺の肩を掴んだ。
「よし……じゃあ、プランCで」
その日の放課後。俺たちはいつものファミレスにいた。
「学級会をはじめまーす」
佐伯の声が、ファミレスの騒がしい空気の中で、やけにのんきに響いていた。
不思議そうにしている芹沢と、生きた心地がしない俺、そして妙にそわそわしている竹内、岩崎のふたり。五人分のドリンクが運ばれてきたが、俺は手をつける余裕すらなかった。
――鈴木の気持ち、芹沢ならちゃんと受け止められるから、あいつのこと信じてやってよ。
――なんたって、メンタル鬼つよだから、芹沢は。
佐伯たちはそう言っていた。もちろん、芹沢は精神的にとってもタフで、誰からも好かれるみんなの太陽だってことはわかっている。だけど、それが俺の告白となると、話は違ってくるだろう。
どう考えても振られる未来しか見えなくて、今すぐにでも逃げ出したくなってしまう。心臓はドクドクと早鐘を打ち、呼吸が浅くなっていくのを感じた。
「えー、今回の議題はふたたび『芹沢と鈴木が微妙な件』についてでーす」
佐伯の言葉に、芹沢はおかしそうに肩を揺らした。彼は何も知らず、いつもの陽気な様子でジュースのストローをくわえている。その何も知らない態度が、俺の罪悪感を増幅させていた。
「え、なんで? 俺は別に鈴木と微妙じゃねぇけど……?」
芹沢は少しだけ考えるような仕草をしたあと、隣にいる俺の顔を覗き込んでくる。今、芹沢の瞳に映る自分は、いったいどんな顔をしているのだろう。想像しても全然わからない。
「……鈴木、もしかして、俺の好きな人のこと気にしてる?」
いきなり図星をさされた俺は、「ごめん……」と赤い顔でうつむいた。言うしかない。怪物にはなりたくない。
「……お、俺はもう無理なんだよ。芹沢にこれ以上迷惑かけたくないし、ストーカーにもなりたくないから……いっそ、ちゃんと振ってもらおうって思って……」
芹沢は時が止まったみたいに、真顔で俺を見つめていた。
「せ、芹沢のこと、好きなんだよ、俺」
言葉を発した瞬間、胸の内にあった重しが少しだけ軽くなった気がした。
「……あ、……………………え? マジで………………?」
かなり動揺させてしまったらしい。芹沢の整った顔が、一瞬にして困惑の表情になった。それでも、言葉を続けるしかない。
「俺ならよかったって、ずっと思ってた。……芹沢にBLを教えたのが俺ならよかったのにって……」
言葉につまる度に、佐伯たちが見守るような目で俺を励ましてくれているのが感じられた。ありがとう、これで俺は怪物にはならずに、潔く散っていける。
そう思った矢先、芹沢が俺の両肩を掴み、真剣な顔をする。彼の指先は強く、若干肩に食い込む。
「そうだって、鈴木」
「……へ?」
「俺は、君からBLを教わってます」
ぽかんと口を開けて、固まること数秒。店内の騒がしさも、佐伯たちの視線も、すべて遠のいた。やっと我に返った俺は、眉間に思い切り皺を寄せて言った。
「芹沢にBLを教えたことなんてねぇよ……!」
二年になって同じクラスになるまで、芹沢とはしゃべったこともなかったのだ。もちろん、人気者な芹沢の存在は知っていたけれど、それだけだ。俺たちが話すようになったのは、芹沢にBL小説を書いているのがバレた時だったし、その時にはすでに芹沢は腐男子だった。
「そっか、そこが引っかかってたのか……。最初から話すわ。めちゃくちゃ長くなりそうだけど」
芹沢はアイスクリームみたいに甘くてとろけるような笑顔を浮かべ、俺の耳元に唇を寄せる。
「こっからはふたりっきりで話せるとこ行こ」
驚いた俺が助けを求めるように佐伯たちを見据えると、彼らはこうなることがわかっていたみたいに、やけに満足げに笑っていた。どうやらまた、わかっていないのは俺だけだったらしい。
それから、俺たちは場所を変え、芹沢に誘われるがまま彼の部屋に出向いた。夕暮れの光が、芹沢の部屋を染めている。壁には以前見た大きな本棚がずらりと並び、俺の好きな作家の作品が所狭しと並んでいる。
「つ、つまりこういうこと?」
ひとしきり芹沢の説明を聞いたあと、動揺を抑えきれずに言った。
「一年の時、俺が図書館でBL小説読んで泣いてるのを見て、気になってタイトルを検索したのが、芹沢が腐男子になるはじまり?」
「俺の長い説明を、めっちゃまとめるじゃん、鈴木」
芹沢は笑いながらも、その目はいつになく真剣だった。
「で、でも、おかしいだろ! だって、もしそうなら……芹沢が俺のこと好きってことになる……!」
自分でも信じられない仮説を口にした瞬間、くらくらとめまいがする。
「だから、そうだって言ってんじゃん」
ベッドに座った俺に近づき、芹沢がにこりと妖艶な笑みを浮かべた。
「俺はずっとそう言ってたよ。鈴木はまったく気づいてなかったけど。つうか、俺から言うつもりだったのに、先越されたわ」
「……な」
言葉にならない声が喉から漏れる。心臓が早鐘を打つ。
「最初は興味だけだったよ。『へぇーそんなに泣くほどおもしろい小説なんだ』って思って、読んだらBLで、しかも俺まで泣いて……マジでびびった」
ゆっくりと俺の後ろにまわり、芹沢が俺の体を抱きしめてくる。芹沢の体温と鼓動が伝わってきて、身動きが取れない。
「その小説読み返しているうちに、もしかして、このシーンが好きなのかなとか、ほかにどんなのが好きなのかなとか、鈴木のことすげぇ気になって、ずっと目で追ってた」
芹沢の指先が熱くなった俺の頬をなぞる。上を向かされて、芹沢のきれいな瞳とかち合う。
「仲良くなりたいって思った。感想言い合いたいなって。自慢じゃないけど、俺視力めっちゃいいんだよね。だから、鈴木がどんなの読んでんのか、調べて、そのあと買って〜って、繰り返してたわけ……って、待って、俺のがストーカーっぽいなこれ」
キスをするような距離の近さに、俺はこくりと唾を飲み込んだ。芹沢の吐息が頬にかかる。
「とにかく、二年になって奇跡的に鈴木と同じクラスになったし、すげぇ鈴木が俺のこと見てくるから、もしかして脈ありかもって自惚れてたよ。でも、ずっと話しかけるきっかけがなかった。鈴木の警戒心強めだったから、下手に近づいたらだめになりそうで。だから、鈴木のノートが俺の机に入ってたとき、これだって思った」
――これ、鈴木の?
あの時、ノートを差し出してきた芹沢の言葉を思い出す。まるで昨日のことのように鮮明に脳裏に浮かんできた。あの瞬間から、俺の世界は少しずつ色づき始めた。
「好きだよ、鈴木」
芹沢の言葉が、全身を熱く染めていく。まるで灼かれているかのような感覚に、呼吸が苦しくなる。
「わ、わかんない。……わ、わかんねぇよ……!」
「わかるよ、鈴木。もうわかってる」
なぁ、と芹沢が言う。彼の声は低く、甘く、心臓の奥のほうまで響いてくるようだった。
「俺のこと、好きだろ?」
芹沢の攻撃力は抜群だ。一言一言が矢のように心臓に突き刺さる。
「……す、好き」
「うん、うれしい。俺も好きだよ」
「……だ、誰にでも言ってない? それ、ちゃんと俺だけの言葉?」
「……信じろって。鈴木だけが、大好きだから」
「だって、芹沢は、……みんなの太陽なのに」
芹沢は俺の言葉がおかしかったのか、少しだけ笑ったあと、真面目な顔をして言った。
「……鈴木だけの俺にしてよ。そうじゃなきゃ許さない」
芹沢のきれいな瞳がすぐ目の前にあった。何も聞こえない。何も考えられない。吸い寄せられるように、芹沢と唇を重ねた。それから何度も芹沢が角度を変えてキスをしてきて、俺は泣きそうになりながら、それを受け止めた。唇に伝わる芹沢の温もりと、彼の指が髪に絡まる感触に、全身の感覚が研ぎ澄まされていく。
芹沢がベッドに押し倒そうとしてきたところで、はっとして芹沢から距離をとった。現実感が一気に押し寄せてきて、顔から火が出そうなほど熱くなる。
「だ、だめだって! ……ま、またキスしちゃったじゃん、俺ら!」
「ははっ、落ち着けって、鈴木。大丈夫、今は両想いだから」
両想いという言葉に、心臓がぎゅんぎゅんしてしまった。
いまだにこの状況が理解できていない。
芹沢は俺がきっかけでBLを知って、そして俺のことが好きだなんて、こんなことありえるわけがない。なのに、芹沢が本当に俺のことを好きみたいな目で見てくるから……。
「ほんとに芹沢は……お、俺のこと好きなの?」
「うん。鈴木は? 俺のこと好き?」
「……す、好き」
恥ずかしさで顔を背けたくなるのを、芹沢の指先がしっかりと固定してくる。
「俺も鈴木が好きだよ。ちゃんと受け取って、俺の気持ち」
ずいぶんと時間をかけ、泣きそうな思いで、小さくうなずく。
「よし、いい子。……ああ、マジで鈴木かわいすぎ」
「……う、うれしい……芹沢が俺のこと、好きだなんて……なにこれ、すげぇうれしい……だけど……なんか、わけわかんない……芹沢、俺、頭がパンクしそうなんだけど……」
「おっけ。じゃあ鈴木がちゃんとわかるまで、何回でもしよ」
「……へ?」
芹沢が意地悪く、にやりと笑う。
「そのためにふたりっきりになったんだから」
芹沢、無理あるて。芹沢、うざいて。芹沢、だるいて。
心の中の文句は言葉にならなかった。あっという間に、唇を塞がれる。俺は芹沢のキスを真っ赤な顔で受け止めるしかなかった。
芹沢に何度も、何度も、わからせられる。
溺れるかと思うほどのキスを浴びせられたあと、
「鈴木、わかった?」
芹沢はいたずらっぽく笑みを浮かべた。芹沢の想いが全身を満たしている。
幸せで、怖くて、恥ずかしくて、だけどずっとこうしていたくて、体の奥がむずむずと疼く。
ようやくわかったけれど――。
俺が赤い顔で首を横に振ると、芹沢は一瞬逡巡し、けれどすぐに俺の想いを悟ったのか、「おっけ」と陽キャ一軍男子らしく手慣れた仕草で俺の顎をつかんだ。
「じゃあ、もう一回ね」
おわり
『ふつうに寝坊した。二時限目ぐらいには間に合うから待ってて、特に鈴木』
俺は芹沢の冗談に胸が締めつけられながらも、「芹沢、うざいて~」と笑い合っている佐伯と竹内と岩崎を見つめる。
芹沢の「好きな人」の存在を知ってから今日まで、毎日が地獄のようだった。
「あのさ、……よかったら相談にのってほしいんだけど」
意を決してそう言った俺を見据え、三人のイケメンたちは軽いノリで笑った。
「おー、何?」
「芹沢じゃなくていいの?」
佐伯と竹内の言葉に、難しい顔をしてうなずく。
「芹沢には言えない。……せ、芹沢のことだから」
言いながら、俺は持っていたスマホをぎゅっと握りしめた。佐伯も竹内も岩崎もふっと笑顔をやめたかと思うと、俺の緊張が伝染したみたいに「え、何?」「どした?」「言ってみ?」と心配そうにつぶやく。
「ものすごく端的に言うと、俺、……芹沢のこと、好きになっちゃったんだ……よね……」
教室の騒がしさが遠ざかっていく。
「……」
「……」
「……」
反応が怖くて、みんなの顔を見られなかった。だけど、彼らが息を呑んだような雰囲気をしっかりと感じる。
「ほ、ほんと、ごめん。こんなこといきなり言われてもキモいよな……。でも、なんか……ひとりじゃ抱えきれなくて」
芹沢に好きな人がいると知ってから、この三日間悩みに悩みまくった。それも、ひどい嫉妬に苛まれながら。
別の世界の人間だと思っていたのに、いつの間にか俺は芹沢のことを好きになってしまっていたのだ。そして気づいたときには、もう手遅れだった。
「いや、キモいとかねぇって。俺らは全然言ってほしい」
恐る恐る顔を上げると、三人は困ったような笑顔を浮かべて俺を見つめていた。彼らの目には、俺が思っていたような軽蔑の色はなく、むしろ励ましの光が宿っているように思える。
「そりゃそうだろ」
「言われないほうがさみしいって」
優しい佐伯たちの言葉に、鼻の奥がツンと痛みを感じる。今日まで抱えていた思いが、どんどん胸の奥から洪水みたいにあふれてくる。
「ありがとな、みんな……。俺、もうほんとキモいんだ。芹沢の夢小説とか書き始めちゃうし、芹沢の好きな人のこともずっと考えてる。このままじゃ芹沢のストーカーになりそうで……」
頭を抱えながら、机に項垂れると、佐伯が普段よりもさらに落ち着いた様子で問いかけてきた。
「えーと、鈴木さ、プランA・B・Cがあるんだけど」
「う、うん……?」
プランとは何だろう? あらかじめ想定されていたような佐伯の口ぶりを、少しだけ不思議に感じた。
「……鈴木って映画とかのネタバレは平気なほう?」
なぜいきなり映画の話なのかと思ったが、正直に答える。
「むり、ネタバレは。ぜったいネタバレは見たくないし、聞きたくない」
佐伯は竹内と岩崎に目配せし、小さくうなずいた。
「じゃあ、プランAはなしで……残りはBかCだな。……鈴木的には、ひとりで自分の気持ち、芹沢に言えそう?」
俺は泣きそうな顔で佐伯と竹内と岩崎を順番に見つめた。
「……情けないんだけど、……みんな、俺が逃げないように、そばにいてくれる?」
「「「かわいい~~~」」」
三人が口を揃えて言うのを、微妙な感情で睨みつけた。あとでいくらでもからかってもらっていいから、とにかく今は早く楽になりたい。
芹沢を求めてさまよう怪物にはなりたくない。きちんと区切りをつけなければ、芹沢にだって、佐伯たちにだって迷惑をかけてしまいそうだった。だから――。
深く息を吸い、覚悟を決めた。
「俺、今日芹沢に言う」
佐伯も、竹内も、岩崎も、なぜか菩薩のような笑顔を浮かべながら、俺の肩を掴んだ。
「よし……じゃあ、プランCで」
その日の放課後。俺たちはいつものファミレスにいた。
「学級会をはじめまーす」
佐伯の声が、ファミレスの騒がしい空気の中で、やけにのんきに響いていた。
不思議そうにしている芹沢と、生きた心地がしない俺、そして妙にそわそわしている竹内、岩崎のふたり。五人分のドリンクが運ばれてきたが、俺は手をつける余裕すらなかった。
――鈴木の気持ち、芹沢ならちゃんと受け止められるから、あいつのこと信じてやってよ。
――なんたって、メンタル鬼つよだから、芹沢は。
佐伯たちはそう言っていた。もちろん、芹沢は精神的にとってもタフで、誰からも好かれるみんなの太陽だってことはわかっている。だけど、それが俺の告白となると、話は違ってくるだろう。
どう考えても振られる未来しか見えなくて、今すぐにでも逃げ出したくなってしまう。心臓はドクドクと早鐘を打ち、呼吸が浅くなっていくのを感じた。
「えー、今回の議題はふたたび『芹沢と鈴木が微妙な件』についてでーす」
佐伯の言葉に、芹沢はおかしそうに肩を揺らした。彼は何も知らず、いつもの陽気な様子でジュースのストローをくわえている。その何も知らない態度が、俺の罪悪感を増幅させていた。
「え、なんで? 俺は別に鈴木と微妙じゃねぇけど……?」
芹沢は少しだけ考えるような仕草をしたあと、隣にいる俺の顔を覗き込んでくる。今、芹沢の瞳に映る自分は、いったいどんな顔をしているのだろう。想像しても全然わからない。
「……鈴木、もしかして、俺の好きな人のこと気にしてる?」
いきなり図星をさされた俺は、「ごめん……」と赤い顔でうつむいた。言うしかない。怪物にはなりたくない。
「……お、俺はもう無理なんだよ。芹沢にこれ以上迷惑かけたくないし、ストーカーにもなりたくないから……いっそ、ちゃんと振ってもらおうって思って……」
芹沢は時が止まったみたいに、真顔で俺を見つめていた。
「せ、芹沢のこと、好きなんだよ、俺」
言葉を発した瞬間、胸の内にあった重しが少しだけ軽くなった気がした。
「……あ、……………………え? マジで………………?」
かなり動揺させてしまったらしい。芹沢の整った顔が、一瞬にして困惑の表情になった。それでも、言葉を続けるしかない。
「俺ならよかったって、ずっと思ってた。……芹沢にBLを教えたのが俺ならよかったのにって……」
言葉につまる度に、佐伯たちが見守るような目で俺を励ましてくれているのが感じられた。ありがとう、これで俺は怪物にはならずに、潔く散っていける。
そう思った矢先、芹沢が俺の両肩を掴み、真剣な顔をする。彼の指先は強く、若干肩に食い込む。
「そうだって、鈴木」
「……へ?」
「俺は、君からBLを教わってます」
ぽかんと口を開けて、固まること数秒。店内の騒がしさも、佐伯たちの視線も、すべて遠のいた。やっと我に返った俺は、眉間に思い切り皺を寄せて言った。
「芹沢にBLを教えたことなんてねぇよ……!」
二年になって同じクラスになるまで、芹沢とはしゃべったこともなかったのだ。もちろん、人気者な芹沢の存在は知っていたけれど、それだけだ。俺たちが話すようになったのは、芹沢にBL小説を書いているのがバレた時だったし、その時にはすでに芹沢は腐男子だった。
「そっか、そこが引っかかってたのか……。最初から話すわ。めちゃくちゃ長くなりそうだけど」
芹沢はアイスクリームみたいに甘くてとろけるような笑顔を浮かべ、俺の耳元に唇を寄せる。
「こっからはふたりっきりで話せるとこ行こ」
驚いた俺が助けを求めるように佐伯たちを見据えると、彼らはこうなることがわかっていたみたいに、やけに満足げに笑っていた。どうやらまた、わかっていないのは俺だけだったらしい。
それから、俺たちは場所を変え、芹沢に誘われるがまま彼の部屋に出向いた。夕暮れの光が、芹沢の部屋を染めている。壁には以前見た大きな本棚がずらりと並び、俺の好きな作家の作品が所狭しと並んでいる。
「つ、つまりこういうこと?」
ひとしきり芹沢の説明を聞いたあと、動揺を抑えきれずに言った。
「一年の時、俺が図書館でBL小説読んで泣いてるのを見て、気になってタイトルを検索したのが、芹沢が腐男子になるはじまり?」
「俺の長い説明を、めっちゃまとめるじゃん、鈴木」
芹沢は笑いながらも、その目はいつになく真剣だった。
「で、でも、おかしいだろ! だって、もしそうなら……芹沢が俺のこと好きってことになる……!」
自分でも信じられない仮説を口にした瞬間、くらくらとめまいがする。
「だから、そうだって言ってんじゃん」
ベッドに座った俺に近づき、芹沢がにこりと妖艶な笑みを浮かべた。
「俺はずっとそう言ってたよ。鈴木はまったく気づいてなかったけど。つうか、俺から言うつもりだったのに、先越されたわ」
「……な」
言葉にならない声が喉から漏れる。心臓が早鐘を打つ。
「最初は興味だけだったよ。『へぇーそんなに泣くほどおもしろい小説なんだ』って思って、読んだらBLで、しかも俺まで泣いて……マジでびびった」
ゆっくりと俺の後ろにまわり、芹沢が俺の体を抱きしめてくる。芹沢の体温と鼓動が伝わってきて、身動きが取れない。
「その小説読み返しているうちに、もしかして、このシーンが好きなのかなとか、ほかにどんなのが好きなのかなとか、鈴木のことすげぇ気になって、ずっと目で追ってた」
芹沢の指先が熱くなった俺の頬をなぞる。上を向かされて、芹沢のきれいな瞳とかち合う。
「仲良くなりたいって思った。感想言い合いたいなって。自慢じゃないけど、俺視力めっちゃいいんだよね。だから、鈴木がどんなの読んでんのか、調べて、そのあと買って〜って、繰り返してたわけ……って、待って、俺のがストーカーっぽいなこれ」
キスをするような距離の近さに、俺はこくりと唾を飲み込んだ。芹沢の吐息が頬にかかる。
「とにかく、二年になって奇跡的に鈴木と同じクラスになったし、すげぇ鈴木が俺のこと見てくるから、もしかして脈ありかもって自惚れてたよ。でも、ずっと話しかけるきっかけがなかった。鈴木の警戒心強めだったから、下手に近づいたらだめになりそうで。だから、鈴木のノートが俺の机に入ってたとき、これだって思った」
――これ、鈴木の?
あの時、ノートを差し出してきた芹沢の言葉を思い出す。まるで昨日のことのように鮮明に脳裏に浮かんできた。あの瞬間から、俺の世界は少しずつ色づき始めた。
「好きだよ、鈴木」
芹沢の言葉が、全身を熱く染めていく。まるで灼かれているかのような感覚に、呼吸が苦しくなる。
「わ、わかんない。……わ、わかんねぇよ……!」
「わかるよ、鈴木。もうわかってる」
なぁ、と芹沢が言う。彼の声は低く、甘く、心臓の奥のほうまで響いてくるようだった。
「俺のこと、好きだろ?」
芹沢の攻撃力は抜群だ。一言一言が矢のように心臓に突き刺さる。
「……す、好き」
「うん、うれしい。俺も好きだよ」
「……だ、誰にでも言ってない? それ、ちゃんと俺だけの言葉?」
「……信じろって。鈴木だけが、大好きだから」
「だって、芹沢は、……みんなの太陽なのに」
芹沢は俺の言葉がおかしかったのか、少しだけ笑ったあと、真面目な顔をして言った。
「……鈴木だけの俺にしてよ。そうじゃなきゃ許さない」
芹沢のきれいな瞳がすぐ目の前にあった。何も聞こえない。何も考えられない。吸い寄せられるように、芹沢と唇を重ねた。それから何度も芹沢が角度を変えてキスをしてきて、俺は泣きそうになりながら、それを受け止めた。唇に伝わる芹沢の温もりと、彼の指が髪に絡まる感触に、全身の感覚が研ぎ澄まされていく。
芹沢がベッドに押し倒そうとしてきたところで、はっとして芹沢から距離をとった。現実感が一気に押し寄せてきて、顔から火が出そうなほど熱くなる。
「だ、だめだって! ……ま、またキスしちゃったじゃん、俺ら!」
「ははっ、落ち着けって、鈴木。大丈夫、今は両想いだから」
両想いという言葉に、心臓がぎゅんぎゅんしてしまった。
いまだにこの状況が理解できていない。
芹沢は俺がきっかけでBLを知って、そして俺のことが好きだなんて、こんなことありえるわけがない。なのに、芹沢が本当に俺のことを好きみたいな目で見てくるから……。
「ほんとに芹沢は……お、俺のこと好きなの?」
「うん。鈴木は? 俺のこと好き?」
「……す、好き」
恥ずかしさで顔を背けたくなるのを、芹沢の指先がしっかりと固定してくる。
「俺も鈴木が好きだよ。ちゃんと受け取って、俺の気持ち」
ずいぶんと時間をかけ、泣きそうな思いで、小さくうなずく。
「よし、いい子。……ああ、マジで鈴木かわいすぎ」
「……う、うれしい……芹沢が俺のこと、好きだなんて……なにこれ、すげぇうれしい……だけど……なんか、わけわかんない……芹沢、俺、頭がパンクしそうなんだけど……」
「おっけ。じゃあ鈴木がちゃんとわかるまで、何回でもしよ」
「……へ?」
芹沢が意地悪く、にやりと笑う。
「そのためにふたりっきりになったんだから」
芹沢、無理あるて。芹沢、うざいて。芹沢、だるいて。
心の中の文句は言葉にならなかった。あっという間に、唇を塞がれる。俺は芹沢のキスを真っ赤な顔で受け止めるしかなかった。
芹沢に何度も、何度も、わからせられる。
溺れるかと思うほどのキスを浴びせられたあと、
「鈴木、わかった?」
芹沢はいたずらっぽく笑みを浮かべた。芹沢の想いが全身を満たしている。
幸せで、怖くて、恥ずかしくて、だけどずっとこうしていたくて、体の奥がむずむずと疼く。
ようやくわかったけれど――。
俺が赤い顔で首を横に振ると、芹沢は一瞬逡巡し、けれどすぐに俺の想いを悟ったのか、「おっけ」と陽キャ一軍男子らしく手慣れた仕草で俺の顎をつかんだ。
「じゃあ、もう一回ね」
おわり