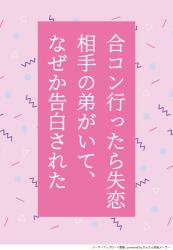「……こ、ここって」
俺は大きな建物の入り口で立ち止まり、声を詰まらせた。目の前には、水色のガラス張りの外壁が、日の光を浴びてキラキラと美しく輝いている。
芹沢は整った唇の端をあげて、
「どうしてここを選んだか、わかる?」
と尋ねてくる。
「わ、わかるって…『はせふか』が初デートした『みらい水族館』だろ!」
胸の高鳴りを抑えきれず、思わず声を荒らげてしまう。ここは、俺と芹沢が好きな作家――石橋叩割先生の大ヒット作に登場する聖地だ。主人公であり受けの深瀬さんと攻めの長谷川くんが仲を深めた重要なシーンの舞台でもある。
「おー、さすが、鈴木」
芹沢は「デートと聖地巡礼で、一石二鳥じゃね?」と完璧な笑顔でピースサインをしてくる。
俺はまた何も言えなくなり、右手で口元を押さえて固まっていた。これほど俺のツボを心得た場所に連れてきてくれるなんて、芹沢の心遣いにただただ感動するしかなかった。
やっぱ、俺、芹沢になら抱かれてもいいかも……。
「あれ? 鈴木、もしかしてだめだった?」
芹沢が少し心配そうに俺の表情を覗き込む。完璧な眉が少しだけ寄っていた。
「……だめ。……ほんと、だめ……めっちゃ感動してる。ありがとう、芹沢」
素直な気持ちをぶつけると、芹沢は俺の感動が伝染したのか、同じように口元を隠しながら「……わいすぎだろ」とぶつぶつなにか言っていた。
「え? なに?」
不思議に思って、芹沢の顔をのぞき込む。
「いや、鈴木はあいつらとは大違いな反応するなって。聞こえてこねぇ? 『芹沢、だるいて~~』『芹沢、うざいて~~』『芹沢ぁ、お前が水族館建てたみてぇにドヤ顔すんなて~~』って」
芹沢の言葉に思わず噴き出す。陽キャ一軍男子たちの反応を想像すると、確かにそんなことを言いそうだった。
でも、俺にとっては完璧なデートプランだ。
「俺は……すごく、すごくすごくうれしいよ、芹沢」
ちゃんと気持ちが届くように、芹沢の目を見て真剣な顔で伝えた。芹沢はとろけるような笑顔で、
「……うん。思いっきり今日は楽しもうな」
とつぶやいた。
割り勘でチケットを買って、水族館の中に入った。『はせふか』が通った道を歩いているのだと思うと、感動で胸がいっぱいになる。
入り口を抜けて最初に目に入ったのは、神秘的な青い光に包まれた大きな魚の水槽だった。
「うぅ……きれー……アクスタ持ってくればよかった……」
思わず漏らした言葉に、芹沢は鞄から何かを取り出す。
「はい、そういうと思いまして」
芹沢の手のひらには、石橋叩割先生の作品に登場するキャラクターのアクリルスタンドが二つあった。
「は、はせふかじゃん! ……せ、せりざわぁ! 完璧すぎるて! 天才だって!」
俺は思わず声を上げて芹沢の肩を掴むと、芹沢は嬉しそうに笑いながら、「写真撮ろ」とスマホの画面を明るくした。芹沢のスマホには、いつかの日に俺と撮った、芹沢と俺とこんにゃくのスリーショットが映し出されている。
「……せ、芹沢、まだこんにゃくをロック画面にしてんの」
「うん、気に入ってたから。でも、今日変える」
「……え?」
一瞬、ショックを受けてしまった。
芹沢が俺との写真をロック画面にしてくれているのが、実は少しだけ……いや、本音を言うとかなりうれしかったのだ。でも、そんなこと言えるわけもなく、「そっか」とお茶を濁すように笑っていたら、芹沢はすぐさまスマホのインカメを起動する。
「笑って、鈴木。はい、チーズ」
俺は言われるがまま、アクスタを持って急いで口角を上げた。
「いいね。めっちゃいい」
芹沢はスマホの画面を慣れた手つきで操作すると、少年みたいな笑顔を浮かべてその画面を見せてくる。
「見て、俺の新ロック画面」
スマホのロック画面には、かっこいい芹沢の笑顔と、はせふかのアクスタを持ってヘタクソに笑う俺の姿、そしてきれいな魚たちがバックに収められていた。
「……俺もそれロック画面にしたいから……写真、ちょうだい」
込み上げるうれしさを抑え、努めて冷静に俺が言うと、芹沢はますます楽しそうに「おそろいだ」と声を上げて笑った。
芹沢とイルカショーを見て、そのあとはカートに乗ったかわいいペンギンを触った。芹沢はずっとけらけらと笑っていて、すぐに周りの子供だったり、その親だったり、飼育員さんたちと仲良くなってしまった。芹沢は本当に太陽みたいなやつだ。
そんな芹沢を見て、俺はなんだかずっとドキドキしていた。私服の芹沢のかっこよさにまだ慣れていないのかもしれない。
「見て、鈴木。ご自由にかぶってくださいだって」
水族館の案内板付近には、「海の生き物帽子」という奇妙なグッズが並んでいた。魚やヒトデ、カニなど海の生き物をモチーフにしたなんともコミカルな帽子だ。
芹沢はためらいなくサメの帽子をかぶり、俺にはクジラの帽子をかぶせてくれた。
「クジラの鈴木、かわいい~。どう? 俺もサメ似合ってる?」
芹沢のポテンシャルはすごい。サメのかぶり物を被っても、芹沢のかっこよさが失われるどころか、さらにかわいさもプラスされて、もはや一般人だというのが憚れるレベルになっている。俺はスマホを構えて、写真を撮りながら興奮気味に伝えた。
「似合ってる! たぶん、クラスで……いや、世界でいちばん似合ってる!」
佐伯たちにも見せなければ……。あとでグループラインにあげるために、何枚も写真を撮っていると、芹沢は堪えきれなかったみたいに「ぶはっ」と声を出して笑った。
「そうやって、鈴木って、いつも俺がキラキラした人間みたいな目で見てくれるよな。鈴木がそう言うとホントにそうかもって思えてくるわ」
「……は?」
突然の言葉に、俺は少し戸惑った。
「な、何言ってんの? 実際そうだし……」
芹沢が何を言おうとしているのかよくわからなかった。眉間に皺を寄せて考えを巡らす。
もしかして芹沢って……自分が太陽だって気づいていない……のか……?
「キラキラしてねーよ。強いて言えば、ギラギラ? あ、ムラムラ?」
「……な、なんだよ、それ! そっちこそ、自己評価低く見積もりすぎじゃね!? ほんとに芹沢ちゃんと鏡見てる!? 俺、マジで心配になるんだけど!」
「……だよなぁ。鈴木には通じねぇよなぁ……わかってたよ」
芹沢が真顔でぽつりと言う。通じるわけがない。
お前は太陽なんだぞ、芹沢。自分のポテンシャル、なめんなて、芹沢。
そのあと、俺たちは大きな水槽の前でしばらく魚たちを見ていた。メインの水槽では、マグロやサメが悠々と泳いでいる。あまりに美しい光景に見とれていると、芹沢が俺の手を握ってきた。突然の接触に、心臓が跳ね上がる。
「せ、芹沢……」
「だめ?」
「……だ、だめじゃないけど……恥ずかしくねぇの、芹沢は。俺と……手つないで」
芹沢の長く綺麗な指が、俺の手と絡み合う。
「なんで? 全然。つなぎたいよ、鈴木と」
芹沢は言葉のとおり堂々としていて、少しも恥じらいを見せない。
「手を離すんかい、離さないんかい、筋肉ルーレットスタ――」
「スタートしなくていいから!」
「じゃあ、このままね」
すでに握られていた手を、芹沢がさらにぎゅっと握る。温かく、大きな芹沢の手。指先が触れ合ったら、芹沢のキラキラエフェクトがもっと増えたみたいで、俺は顔が熱くなるのを止められなかった。
人がいるせいか、芹沢は俺の耳もとに口を寄せ、小さな声で尋ねてくる。
「どう? 繋いだ感想」
「どうもこうも……ドキドキして心臓痛い。……もう無理、芹沢かっこよすぎて死ぬ……」
心の声がそのまま漏れた気がしたけれど、実際それどころではなくて、あまりの恥ずかしさにぎゅっと目を閉じた。
「こんなにドキドキすんの、芹沢だけだよ、俺……」
絞り出した声は、なんて情けなく響くのか。このままでは胸キュンBL小説だけでなく、芹沢の夢小説も量産してしまいそうだ。頭の中には次々と芹沢の甘い妄想が浮かんでくる。
「ふふっ、……ふっ、……ふふふっ」
完全に笑っている芹沢の声が聞こえて、ぱっと目を開けた。芹沢は慌てて真顔になっていたが、間に合っていない。
「にやにやすんなし、芹沢!」
「はぁ? してませーん。鈴木、目ぇつぶってたんだから見えてねぇだろ!」
「……実際ににやけてんの見ましたぁ!」
「見間違いですぅ!」
ばかみたいな会話を続けている芹沢は、明らかに俺が恥ずかしがっているのを楽しんでいるように見えた。いたずらっぽい笑みを浮かべ、俺の手をさらにぎゅっと握り締める。
「うそ、ごめん。にやけた。鈴木がすげぇかわいくて、つい」
「……だ、だから、そういう胸キュン言葉吐いたらストーカー生まれるって! ストーカー量産機だって!」
「ははっ、量産はしたくねぇわ。ひとりだけでいい」
「ひとりもいちゃだめなんだよ!」
ごちゃごちゃと言い合いをしながら、俺たちは手を繋いで水族館の中を進んでいく。水族館の青い光に照らされると、芹沢の表情がより一層大人びて魅力的に見える。
「デートの描写、うまく書けそう?」
芹沢の横顔を見上げながら、俺は静かにうなずいた。
「……書ける、気がする」
悔しいことに、今日の出来事をBL小説の中に織り込むことを想像すると、文章がすらすらと頭に浮かんでくる。芹沢は嬉しそうに微笑んだ。
「ははっ、やった」
それからも俺たちはたくさんの展示を見て回った。海の中をモチーフにしたカフェでアイスクリームを食べたり、ドクターフィッシュのいる水槽に手を入れる体験で声を上げて笑ったり。時間はあっという間に過ぎていった。
「また一緒にデートしような、鈴木。俺がいっぱいドキドキさせるから」
出口に向かう頃、芹沢が笑って、ぎゅっと俺の手を握ってくる。心臓が破裂しそうだった俺は、小さく「うん」とだけつぶやいた。
ドキドキするから、こっち見んなて、芹沢。
◇
「はぁ……」
翌日の学校。俺は昨日のデートの余韻にすっかり浸っていた。芹沢の沼は深すぎる。あんな風に誰かとデートするのは初めてだった。
正直、……初デートが芹沢で本当によかった、と思っている。
おそろいにしたスマホのロック画面をぼんやり眺めていると、「あのさ、鈴木」と女子ふたりが話しかけてきた。同じクラスの宮本さんと高橋さんだ。
「な、何?」
「鈴木って、最近、芹沢たちとよく絡んでるよね?」
「え……」
もしかして、「お前みたいな平凡野郎が芹沢の隣にいんのは似合わない」系のお言葉がくるのだろうか。若干身構えると、彼女たちは慌てたように手を横に振った。
「違う違う! 悪い意味じゃなくて! なんか鈴木の雰囲気が丸くなったから、つい話しかけちゃったんだけど……」
宮本さんたちの表情は、意外にも柔らかく、友好的だった。
「ほらさ、あのー……いつもノートに書いてたり、スマホ操作してるから、うちらに話しかけられんの嫌なのかと思って、今まで遠慮してたんだよ。でも最近は芹沢たちと騒いでるみたいだったから……。ごめん、嫌だった?」
「嫌じゃない! そういうわけではなくて……!」
慌てて否定する俺に、宮本さんたちはほっとしたように笑った。もしかすると、俺が自ら壁を作っていたせいで、気づかないうちに、クラスの雰囲気を悪くしてたのかもしれない。
「……い、色々、気ぃ使わせてたらごめんな」
「なんで、謝んの!」
「もし、話すの嫌じゃなかったら、うちらも仲良くなりたいっていうだけだから!」
彼女たちの明るい声に、強張っていた肩の力が抜けた。
「うちのクラスって、二年のクラスが、そのまんま三年に持ち上がりじゃん? 来年もあるし、みんな仲良くしたいねー的なノリで」
「ありがとう。俺も仲良くできると……うれしい」
素直な気持ちを伝えると、宮本さんと高橋さんの表情もパッと明るくなる。
「よかったー。てか、鈴木と芹沢って何がきっかけで仲良くなったの?」
唐突な質問に、少しだけ戸惑った。だけど、芹沢や佐伯たちのことを思い浮かべ、ぎゅっとこぶしを握りしめる。
「……び……BL……俺、そういうの好きで」
少しだけ声を落として言うと、彼女たちはまったく驚いた様子もなく、むしろ嬉しそうに反応してくれた。
「ああそっか! 芹沢、腐男子だ! ゆかぽんも好きだったよね? 前も芹沢と話してたじゃん」
「そう、結構話すー。でも、芹沢に新刊貸してあげるって言っても断られるよ。汚したら申し訳ないとかなんとか言って、あいつ無駄に遠慮してくる」
意外な情報に少し驚いた。芹沢がそんなに遠慮するタイプだとは思えなかった。
「え、マジで? 俺、この前貸したんだけど……」
同性だから、気軽に貸し借りできたのだろうか。万が一の可能性として、もしも芹沢が俺に気を許してくれているからなのだとしたら、それはそれで嬉しいのだけれど……。
ふたりは、目と目で何かを伝え合うような仕草をした後、意味ありげに笑った。
「はっはーん、なるほどなるほど」
「……何がなるほど?」
俺だけわかっていないようだったが、宮本さんたちは話を続ける。
「そういえば芹沢って、好きな人がBL好きだからハマったって公言してたよね?」
「……え?」
一瞬、頭が真っ白になった。芹沢に好きな人……?
「うん。なんかBLはその人に教えてもらったって」
「もしかして、それってさ、鈴――」
彼女たちが顔を寄せ合って話しているうちに、背後から聞き慣れた声が聞こえてくる。
「待って、俺の鈴木が女子に囲まれてる。何話してんのー」
芹沢が現れ、俺たちの会話に入ってきた。
「「俺の鈴木」」
宮本さんたちは口々にそう繰り返し、くすくすと笑った。俺は芹沢の軽い冗談にも笑えなかった。頭の中はさっきの話でいっぱいだったのだ。
芹沢は俺の横に椅子を持ってくると、横から俺の体に長い腕を絡ませて、ぐいっと引き寄せた。いつもの戯れだ。その親密な仕草に、彼女たちはさらに意味ありげな顔をしてにやにやしている。
「芹沢が好きな人にBL教えてもらったって話してた。言っても大丈夫だったよね?」
彼女の問いかけに、芹沢は平然とした顔で答えた。
「ああ、うん。全然平気」
ちらりと見つめた芹沢の表情に、動揺は見られなかった。俺は若干の動揺を抱えたまま、小さな声で芹沢に尋ねる。
「ほんとに……? す、好きな人に教えてもらったの……BLを?」
芹沢は妖艶に目を細め、なんだか含みのある言い方をした。
「うん、そう。だから、俺の趣味はその好きな人の趣味にすげぇ似てんの。鈴木も俺の本棚見ただろ?」
芹沢の言葉に、胸がぎゅっと締め付けられた。そうか、芹沢の本棚の中身が俺とよく似ていたのは、好きな人の趣味に合わせたからなのか。
「芹沢さぁ、もしかして好きな人って、今身近にいる?」と宮本さんが興味津々で尋ねた。
芹沢は意味深な笑みを浮かべ、「ああ、めちゃくちゃ近くにいる」と答える。
同じ学校の子なのかもしれない。心臓が急に暴れ出して、息ができない。
「てかさ、芹沢、なんで鈴木に抱きついてんの?」
高橋さんの率直な質問に、芹沢はニヤリと笑った。
「抱きついてんじゃねぇって、これ鈴木の安全バーだから」
「鈴木が飛び出さないように?」
「そうそう」
「芹沢、だるいてー!」
芹沢と女子たちの笑い声が耳に届く。だけど、なんだか頭ががんがんしていて、よく聞き取れなかった。
そうなんだ、芹沢。そっか、好きな人がいたのか。そりゃあいるよな。いるんだ。そっか。その人にBLを教えてもらったんだ。そっか。そっか……。
なぁ、芹沢。なんかさ、俺、……なんか胸が苦しいよ。
俺は大きな建物の入り口で立ち止まり、声を詰まらせた。目の前には、水色のガラス張りの外壁が、日の光を浴びてキラキラと美しく輝いている。
芹沢は整った唇の端をあげて、
「どうしてここを選んだか、わかる?」
と尋ねてくる。
「わ、わかるって…『はせふか』が初デートした『みらい水族館』だろ!」
胸の高鳴りを抑えきれず、思わず声を荒らげてしまう。ここは、俺と芹沢が好きな作家――石橋叩割先生の大ヒット作に登場する聖地だ。主人公であり受けの深瀬さんと攻めの長谷川くんが仲を深めた重要なシーンの舞台でもある。
「おー、さすが、鈴木」
芹沢は「デートと聖地巡礼で、一石二鳥じゃね?」と完璧な笑顔でピースサインをしてくる。
俺はまた何も言えなくなり、右手で口元を押さえて固まっていた。これほど俺のツボを心得た場所に連れてきてくれるなんて、芹沢の心遣いにただただ感動するしかなかった。
やっぱ、俺、芹沢になら抱かれてもいいかも……。
「あれ? 鈴木、もしかしてだめだった?」
芹沢が少し心配そうに俺の表情を覗き込む。完璧な眉が少しだけ寄っていた。
「……だめ。……ほんと、だめ……めっちゃ感動してる。ありがとう、芹沢」
素直な気持ちをぶつけると、芹沢は俺の感動が伝染したのか、同じように口元を隠しながら「……わいすぎだろ」とぶつぶつなにか言っていた。
「え? なに?」
不思議に思って、芹沢の顔をのぞき込む。
「いや、鈴木はあいつらとは大違いな反応するなって。聞こえてこねぇ? 『芹沢、だるいて~~』『芹沢、うざいて~~』『芹沢ぁ、お前が水族館建てたみてぇにドヤ顔すんなて~~』って」
芹沢の言葉に思わず噴き出す。陽キャ一軍男子たちの反応を想像すると、確かにそんなことを言いそうだった。
でも、俺にとっては完璧なデートプランだ。
「俺は……すごく、すごくすごくうれしいよ、芹沢」
ちゃんと気持ちが届くように、芹沢の目を見て真剣な顔で伝えた。芹沢はとろけるような笑顔で、
「……うん。思いっきり今日は楽しもうな」
とつぶやいた。
割り勘でチケットを買って、水族館の中に入った。『はせふか』が通った道を歩いているのだと思うと、感動で胸がいっぱいになる。
入り口を抜けて最初に目に入ったのは、神秘的な青い光に包まれた大きな魚の水槽だった。
「うぅ……きれー……アクスタ持ってくればよかった……」
思わず漏らした言葉に、芹沢は鞄から何かを取り出す。
「はい、そういうと思いまして」
芹沢の手のひらには、石橋叩割先生の作品に登場するキャラクターのアクリルスタンドが二つあった。
「は、はせふかじゃん! ……せ、せりざわぁ! 完璧すぎるて! 天才だって!」
俺は思わず声を上げて芹沢の肩を掴むと、芹沢は嬉しそうに笑いながら、「写真撮ろ」とスマホの画面を明るくした。芹沢のスマホには、いつかの日に俺と撮った、芹沢と俺とこんにゃくのスリーショットが映し出されている。
「……せ、芹沢、まだこんにゃくをロック画面にしてんの」
「うん、気に入ってたから。でも、今日変える」
「……え?」
一瞬、ショックを受けてしまった。
芹沢が俺との写真をロック画面にしてくれているのが、実は少しだけ……いや、本音を言うとかなりうれしかったのだ。でも、そんなこと言えるわけもなく、「そっか」とお茶を濁すように笑っていたら、芹沢はすぐさまスマホのインカメを起動する。
「笑って、鈴木。はい、チーズ」
俺は言われるがまま、アクスタを持って急いで口角を上げた。
「いいね。めっちゃいい」
芹沢はスマホの画面を慣れた手つきで操作すると、少年みたいな笑顔を浮かべてその画面を見せてくる。
「見て、俺の新ロック画面」
スマホのロック画面には、かっこいい芹沢の笑顔と、はせふかのアクスタを持ってヘタクソに笑う俺の姿、そしてきれいな魚たちがバックに収められていた。
「……俺もそれロック画面にしたいから……写真、ちょうだい」
込み上げるうれしさを抑え、努めて冷静に俺が言うと、芹沢はますます楽しそうに「おそろいだ」と声を上げて笑った。
芹沢とイルカショーを見て、そのあとはカートに乗ったかわいいペンギンを触った。芹沢はずっとけらけらと笑っていて、すぐに周りの子供だったり、その親だったり、飼育員さんたちと仲良くなってしまった。芹沢は本当に太陽みたいなやつだ。
そんな芹沢を見て、俺はなんだかずっとドキドキしていた。私服の芹沢のかっこよさにまだ慣れていないのかもしれない。
「見て、鈴木。ご自由にかぶってくださいだって」
水族館の案内板付近には、「海の生き物帽子」という奇妙なグッズが並んでいた。魚やヒトデ、カニなど海の生き物をモチーフにしたなんともコミカルな帽子だ。
芹沢はためらいなくサメの帽子をかぶり、俺にはクジラの帽子をかぶせてくれた。
「クジラの鈴木、かわいい~。どう? 俺もサメ似合ってる?」
芹沢のポテンシャルはすごい。サメのかぶり物を被っても、芹沢のかっこよさが失われるどころか、さらにかわいさもプラスされて、もはや一般人だというのが憚れるレベルになっている。俺はスマホを構えて、写真を撮りながら興奮気味に伝えた。
「似合ってる! たぶん、クラスで……いや、世界でいちばん似合ってる!」
佐伯たちにも見せなければ……。あとでグループラインにあげるために、何枚も写真を撮っていると、芹沢は堪えきれなかったみたいに「ぶはっ」と声を出して笑った。
「そうやって、鈴木って、いつも俺がキラキラした人間みたいな目で見てくれるよな。鈴木がそう言うとホントにそうかもって思えてくるわ」
「……は?」
突然の言葉に、俺は少し戸惑った。
「な、何言ってんの? 実際そうだし……」
芹沢が何を言おうとしているのかよくわからなかった。眉間に皺を寄せて考えを巡らす。
もしかして芹沢って……自分が太陽だって気づいていない……のか……?
「キラキラしてねーよ。強いて言えば、ギラギラ? あ、ムラムラ?」
「……な、なんだよ、それ! そっちこそ、自己評価低く見積もりすぎじゃね!? ほんとに芹沢ちゃんと鏡見てる!? 俺、マジで心配になるんだけど!」
「……だよなぁ。鈴木には通じねぇよなぁ……わかってたよ」
芹沢が真顔でぽつりと言う。通じるわけがない。
お前は太陽なんだぞ、芹沢。自分のポテンシャル、なめんなて、芹沢。
そのあと、俺たちは大きな水槽の前でしばらく魚たちを見ていた。メインの水槽では、マグロやサメが悠々と泳いでいる。あまりに美しい光景に見とれていると、芹沢が俺の手を握ってきた。突然の接触に、心臓が跳ね上がる。
「せ、芹沢……」
「だめ?」
「……だ、だめじゃないけど……恥ずかしくねぇの、芹沢は。俺と……手つないで」
芹沢の長く綺麗な指が、俺の手と絡み合う。
「なんで? 全然。つなぎたいよ、鈴木と」
芹沢は言葉のとおり堂々としていて、少しも恥じらいを見せない。
「手を離すんかい、離さないんかい、筋肉ルーレットスタ――」
「スタートしなくていいから!」
「じゃあ、このままね」
すでに握られていた手を、芹沢がさらにぎゅっと握る。温かく、大きな芹沢の手。指先が触れ合ったら、芹沢のキラキラエフェクトがもっと増えたみたいで、俺は顔が熱くなるのを止められなかった。
人がいるせいか、芹沢は俺の耳もとに口を寄せ、小さな声で尋ねてくる。
「どう? 繋いだ感想」
「どうもこうも……ドキドキして心臓痛い。……もう無理、芹沢かっこよすぎて死ぬ……」
心の声がそのまま漏れた気がしたけれど、実際それどころではなくて、あまりの恥ずかしさにぎゅっと目を閉じた。
「こんなにドキドキすんの、芹沢だけだよ、俺……」
絞り出した声は、なんて情けなく響くのか。このままでは胸キュンBL小説だけでなく、芹沢の夢小説も量産してしまいそうだ。頭の中には次々と芹沢の甘い妄想が浮かんでくる。
「ふふっ、……ふっ、……ふふふっ」
完全に笑っている芹沢の声が聞こえて、ぱっと目を開けた。芹沢は慌てて真顔になっていたが、間に合っていない。
「にやにやすんなし、芹沢!」
「はぁ? してませーん。鈴木、目ぇつぶってたんだから見えてねぇだろ!」
「……実際ににやけてんの見ましたぁ!」
「見間違いですぅ!」
ばかみたいな会話を続けている芹沢は、明らかに俺が恥ずかしがっているのを楽しんでいるように見えた。いたずらっぽい笑みを浮かべ、俺の手をさらにぎゅっと握り締める。
「うそ、ごめん。にやけた。鈴木がすげぇかわいくて、つい」
「……だ、だから、そういう胸キュン言葉吐いたらストーカー生まれるって! ストーカー量産機だって!」
「ははっ、量産はしたくねぇわ。ひとりだけでいい」
「ひとりもいちゃだめなんだよ!」
ごちゃごちゃと言い合いをしながら、俺たちは手を繋いで水族館の中を進んでいく。水族館の青い光に照らされると、芹沢の表情がより一層大人びて魅力的に見える。
「デートの描写、うまく書けそう?」
芹沢の横顔を見上げながら、俺は静かにうなずいた。
「……書ける、気がする」
悔しいことに、今日の出来事をBL小説の中に織り込むことを想像すると、文章がすらすらと頭に浮かんでくる。芹沢は嬉しそうに微笑んだ。
「ははっ、やった」
それからも俺たちはたくさんの展示を見て回った。海の中をモチーフにしたカフェでアイスクリームを食べたり、ドクターフィッシュのいる水槽に手を入れる体験で声を上げて笑ったり。時間はあっという間に過ぎていった。
「また一緒にデートしような、鈴木。俺がいっぱいドキドキさせるから」
出口に向かう頃、芹沢が笑って、ぎゅっと俺の手を握ってくる。心臓が破裂しそうだった俺は、小さく「うん」とだけつぶやいた。
ドキドキするから、こっち見んなて、芹沢。
◇
「はぁ……」
翌日の学校。俺は昨日のデートの余韻にすっかり浸っていた。芹沢の沼は深すぎる。あんな風に誰かとデートするのは初めてだった。
正直、……初デートが芹沢で本当によかった、と思っている。
おそろいにしたスマホのロック画面をぼんやり眺めていると、「あのさ、鈴木」と女子ふたりが話しかけてきた。同じクラスの宮本さんと高橋さんだ。
「な、何?」
「鈴木って、最近、芹沢たちとよく絡んでるよね?」
「え……」
もしかして、「お前みたいな平凡野郎が芹沢の隣にいんのは似合わない」系のお言葉がくるのだろうか。若干身構えると、彼女たちは慌てたように手を横に振った。
「違う違う! 悪い意味じゃなくて! なんか鈴木の雰囲気が丸くなったから、つい話しかけちゃったんだけど……」
宮本さんたちの表情は、意外にも柔らかく、友好的だった。
「ほらさ、あのー……いつもノートに書いてたり、スマホ操作してるから、うちらに話しかけられんの嫌なのかと思って、今まで遠慮してたんだよ。でも最近は芹沢たちと騒いでるみたいだったから……。ごめん、嫌だった?」
「嫌じゃない! そういうわけではなくて……!」
慌てて否定する俺に、宮本さんたちはほっとしたように笑った。もしかすると、俺が自ら壁を作っていたせいで、気づかないうちに、クラスの雰囲気を悪くしてたのかもしれない。
「……い、色々、気ぃ使わせてたらごめんな」
「なんで、謝んの!」
「もし、話すの嫌じゃなかったら、うちらも仲良くなりたいっていうだけだから!」
彼女たちの明るい声に、強張っていた肩の力が抜けた。
「うちのクラスって、二年のクラスが、そのまんま三年に持ち上がりじゃん? 来年もあるし、みんな仲良くしたいねー的なノリで」
「ありがとう。俺も仲良くできると……うれしい」
素直な気持ちを伝えると、宮本さんと高橋さんの表情もパッと明るくなる。
「よかったー。てか、鈴木と芹沢って何がきっかけで仲良くなったの?」
唐突な質問に、少しだけ戸惑った。だけど、芹沢や佐伯たちのことを思い浮かべ、ぎゅっとこぶしを握りしめる。
「……び……BL……俺、そういうの好きで」
少しだけ声を落として言うと、彼女たちはまったく驚いた様子もなく、むしろ嬉しそうに反応してくれた。
「ああそっか! 芹沢、腐男子だ! ゆかぽんも好きだったよね? 前も芹沢と話してたじゃん」
「そう、結構話すー。でも、芹沢に新刊貸してあげるって言っても断られるよ。汚したら申し訳ないとかなんとか言って、あいつ無駄に遠慮してくる」
意外な情報に少し驚いた。芹沢がそんなに遠慮するタイプだとは思えなかった。
「え、マジで? 俺、この前貸したんだけど……」
同性だから、気軽に貸し借りできたのだろうか。万が一の可能性として、もしも芹沢が俺に気を許してくれているからなのだとしたら、それはそれで嬉しいのだけれど……。
ふたりは、目と目で何かを伝え合うような仕草をした後、意味ありげに笑った。
「はっはーん、なるほどなるほど」
「……何がなるほど?」
俺だけわかっていないようだったが、宮本さんたちは話を続ける。
「そういえば芹沢って、好きな人がBL好きだからハマったって公言してたよね?」
「……え?」
一瞬、頭が真っ白になった。芹沢に好きな人……?
「うん。なんかBLはその人に教えてもらったって」
「もしかして、それってさ、鈴――」
彼女たちが顔を寄せ合って話しているうちに、背後から聞き慣れた声が聞こえてくる。
「待って、俺の鈴木が女子に囲まれてる。何話してんのー」
芹沢が現れ、俺たちの会話に入ってきた。
「「俺の鈴木」」
宮本さんたちは口々にそう繰り返し、くすくすと笑った。俺は芹沢の軽い冗談にも笑えなかった。頭の中はさっきの話でいっぱいだったのだ。
芹沢は俺の横に椅子を持ってくると、横から俺の体に長い腕を絡ませて、ぐいっと引き寄せた。いつもの戯れだ。その親密な仕草に、彼女たちはさらに意味ありげな顔をしてにやにやしている。
「芹沢が好きな人にBL教えてもらったって話してた。言っても大丈夫だったよね?」
彼女の問いかけに、芹沢は平然とした顔で答えた。
「ああ、うん。全然平気」
ちらりと見つめた芹沢の表情に、動揺は見られなかった。俺は若干の動揺を抱えたまま、小さな声で芹沢に尋ねる。
「ほんとに……? す、好きな人に教えてもらったの……BLを?」
芹沢は妖艶に目を細め、なんだか含みのある言い方をした。
「うん、そう。だから、俺の趣味はその好きな人の趣味にすげぇ似てんの。鈴木も俺の本棚見ただろ?」
芹沢の言葉に、胸がぎゅっと締め付けられた。そうか、芹沢の本棚の中身が俺とよく似ていたのは、好きな人の趣味に合わせたからなのか。
「芹沢さぁ、もしかして好きな人って、今身近にいる?」と宮本さんが興味津々で尋ねた。
芹沢は意味深な笑みを浮かべ、「ああ、めちゃくちゃ近くにいる」と答える。
同じ学校の子なのかもしれない。心臓が急に暴れ出して、息ができない。
「てかさ、芹沢、なんで鈴木に抱きついてんの?」
高橋さんの率直な質問に、芹沢はニヤリと笑った。
「抱きついてんじゃねぇって、これ鈴木の安全バーだから」
「鈴木が飛び出さないように?」
「そうそう」
「芹沢、だるいてー!」
芹沢と女子たちの笑い声が耳に届く。だけど、なんだか頭ががんがんしていて、よく聞き取れなかった。
そうなんだ、芹沢。そっか、好きな人がいたのか。そりゃあいるよな。いるんだ。そっか。その人にBLを教えてもらったんだ。そっか。そっか……。
なぁ、芹沢。なんかさ、俺、……なんか胸が苦しいよ。