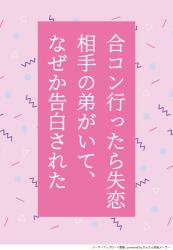「ママ、いつも言ってるでしょう? タダより怖いものはないって」
「ごめんな、ママ……」
朝。教室についた途端、芹沢と佐伯が何やら話し込んでいるのが聞こえた。佐伯に両肩を掴まれている芹沢は、なぜか落ち込んでいる様子で、俺は慌てて彼らの元に急ぐ。
「え……ど、どうした、芹沢……?」
「おー、来た来た。芹沢マスター」
芹沢は俺の顔を見たあと、ぱっと笑顔を浮かべた。
「おはよ、鈴木」
「はよ。……あ、あれ? 芹沢、落ち込んでたんじゃ……ねぇのか……。ごめん、勘違い……」
「合ってるよ、鈴木。今日はちょっと落ち込んでる」
そう言った芹沢の笑顔は、やっぱりほんのわずかに悲しそうだった。芹沢が落ち込んでいると、俺まで悲しくなってくる。
「ど、どうしたんだよ、芹沢」
「それがさぁ……」
「この前もらった貢物、フラグだったみてぇよ?」
意気消沈している芹沢に代わり、苦笑いを浮かべた佐伯が詳しく説明してくれた。
以前、芹沢にお菓子をたくさんくれたあの先輩たちのことだ。どうやら昨日、芹沢は先輩グループの女の子のひとりと、一対一のデートをねだられたらしい。芹沢がやんわり逃げようとしても、「あのお菓子食べたでしょ? もう断れないよー」と愛らしい笑顔で迫ってきたという。
「全力で断ったよ、申し訳ねーけど」
骨張った指先を絡めながら、気まずそうに芹沢が目を伏せる。
「先輩たちはマジでいい人だし、デート行きたいって言ってくれた子も、すげぇいい子なのよ。でも100%気持ちを返せないってわかってて、デート行って、気ぃ持たせんのほんと無理」
きっと芹沢は、こういう悪意のない好意をたくさん向けられているのだろう。俺だって……まるでアイドルを見るような視線で、いつも芹沢を見つめていた。芹沢の内面をある程度知った今でも、時折そういう目で見てしまうときもある。……すまない、芹沢よ。
「……あのさ、芹沢。これ、よかったら」
今日は芹沢にとことん優しくしてやりたい。
放課後にこっそり渡そうとしていたBL漫画の新刊を、今、渡すことにした。芹沢が喜んでくれるなら、クラスの誰に見られてもかまわない。
「え、いいの? あー、石橋叩割先生のじゃん! 読みたかったやつ!」
いいよ、芹沢。たとえすげぇ声が大きくても、クラスの女子たちが驚いたようにこっちを見ていても、いいんだよ、芹沢。いいんだ。
「俺はもう読んだから」
「偶然だわ。実は、俺も持ってきた」
芹沢がいつもの優しい笑みを浮かべたから、俺はちょっとだけほっとしてしまった。そして、彼が鞄から出した漫画を見て、BLオタクの血が抑えきれずに感嘆の声を上げる。
「し、知らない先生だ……!」
「あ、マジ? 前は少女漫画専門だったんだけど、今回BLに初挑戦したんだって」
「絵、きれー……。ありがとう、芹沢。ほんとに、ほんとに、うれしい」
俺を思って持ってきてくれたことが、何よりもありがたくて、くすぐったい。
「……俺もうれしいよ、鈴木」
芹沢がどうしようもなく格好良く見える。いや、前から格好いいけど……。
「大事に読むから」
「うん、俺も大事に読む」
屈託なく笑う芹沢のことも、芹沢が貸してくれたBL漫画も、どっちも大切にしたくて、ぎゅっと本を抱きしめた。吸い込まれそうにきれいな芹沢の黒い瞳。
立ち上がった芹沢の手が、俺の首筋に触れる。巨大な引力が発生する。吸い寄せられる、芹沢に。
「おっはよー!」
竹内の声が耳に届き、はっとして我に返った。芹沢は笑っていた、めちゃくちゃ意地悪な顔をして。
竹内と同時に岩崎も来て、俺たちを交互に見て不思議そうにつぶやく。
「おはよ。お前ら、何見つめ合ってんの?」
「あ、やべ、俺らなんか見逃した? 佐伯、ダイジェストよろしく」
竹内が焦ったように問うと、佐伯は「鈴木と芹沢が、BL漫画交換してお互いにうれしいねーって、なってるとこ」と笑いをこらえながら言った。
「そんだけ?」
「そんだけー」
「あっぶねぇ」
何があぶないのか……説明してくれそうもない三人をちょっとだけ不満の目で見つめる。「まあまあ、鈴木」とわけもわからず宥めてくる彼らをさらに睨みつけながら、俺は芹沢が貸してくれたBL漫画を丁寧に鞄へとしまった。
「……デートといえばさぁ!」
急に芹沢が声を上げ、びっくりした俺は目を丸くして芹沢を見つめた。
「急に話題をぶり返したな」と佐伯。
「……お、これはなんの導入だ?」と竹内。
「ざわざわ……ざわざわ……」と岩崎。
「昨日芹沢にもらった小説、改めて読み返したんだけど」
「あ、どうだった……?」
わずかに緊張が走り、恐る恐る芹沢に聞いた。初めて最後まで完成させたBL小説を何度も読み返して改稿し、昨日芹沢に送っていたのだ。
「最初のデート感、薄くね?」
「……え」
いつもこっちが恥ずかしくなるくらい褒めてくれる芹沢だから、どこかできっと今日も褒めてくれると期待していたのかもしれない。けれど、予想とは裏腹に、今日の芹沢は容赦なく俺を切り捨てていく。
「話の流れ自体はいい感じなのに、デートになった途端、流れ作業でもったいねぇっていうかー」
「……」
「温度感が伝わんないっつうかー」
「……」
「どこ行ってー、どこ行ってー、何しました~楽しかったです~、みたいなー」
「……」
「ちょっと小学生の日記っぽいから、ドキドキ感が欲しいんだよなー」
「……」
「……そこでなんだけど、鈴木、俺と――」
今日は芹沢にとことん優しくしてやりたい……なんて気持ちは脆くも崩れ去った。
「おりゃあああ!」
あからさまに劣等感を刺激された俺は、芹沢が言葉を続ける前に肩パンを繰り出す。しかし、普段から鍛えていて、体幹が強い芹沢は俺のふいうちの動作にもまったく驚かなかったし、ぴくりとも動かなかった。むしろ、なぜか嬉しそうまである。
「怒んなって、鈴木」
「……芹沢は俺を傷つけた! 芹沢は~! 俺を~! 傷つけた~!」
ぽすぽすと芹沢にパンチを繰り出すと、乱闘止め係のはずだった岩崎が、
「鈴木が荒ぶってる。めっちゃめずらしいわ」
とおかしそうに口角を上げた。芹沢は俺のパンチを受けながら、肩を揺らして笑っている。
「ごめんごめん。てか鈴木さ、荒ぶっても優しさ出ちゃってる。パンチが弱ぇ弱ぇ。そんなんじゃ世界とれないって」
「うるせぇ、芹沢!」
なんで顔も声もよくて、勉強も運動も(最近は煮物も)できんだよ、ふざけんな!
渾身のパンチは芹沢の大きな手に軽々と止められてしまい、言葉をなくした。
「こら。鈴木が怪我すんだろ。俺は怪我してもいいけど、鈴木は許さないから」
大変悔しいことに、怒りを含んだ芹沢の真剣な顔がまぶしくて、俺は早々に敗北を認めざるを得なかった。片や百戦錬磨の陽キャ一軍男子芹沢、片やキング・オブ・ザ・凡人の俺。
「わァ……ァァァ……」
打ちひしがれる俺。完全な敗北。
「『わァ……』って泣くんだ、鈴木。ウケる」
「ちいかわ、泣いちゃった」
「芹沢ー、鈴木泣かすなよー」
岩崎がぽんぽんと頭を撫でてくれたから、俺は芹沢の手を振り払って岩崎の胸に飛び込んだ。
「……ありがとな、岩崎」
柔道部エースである岩崎の鍛えられた胸筋に埋まっていると、とても安心することに気がついた。俺、岩崎になら抱かれてもい――。
「くっつきすぎだから!」
手首をひかれ、芹沢のほうを強制的に向かされた。普段から芹沢のほうが距離感が近いのは、棚に上げているらしい。
唇を尖らせていると、ほんのちょっとだけ言いにくそうに芹沢が言う。
「ごめんね、鈴木。でも、俺は言わないより、ちゃんと言ったほうがいいと思ってる。鈴木が真剣に小説書いてること、知ってるから」
「……それはそう」
「鈴木の小説、すげぇ好きだよ、俺」
掴まれた手首に力を入れられて、心臓が痛いくらい鳴った。自分の書いたものを好きだといってもらえるのは、本当に奇跡みたいなことだ。
「ありがとう、芹沢……。小説はちゃんと直す……。これからも意見もらえると助かる」
「もちろん。……てかさ、鈴木が今までのデートで一番よかったのって、どこに、誰と行ったやつ?」
またもや劣等感を刺激され、俺の怒りは再燃した。
「……な……いに、……ってんだろ……」
「え?」
「デートなんてしたことないけど、それがなんなんだよ! 陽キャ一軍たちと一緒にすんなよ!」
「ははっ、なんでキレてんだよ、鈴木」
「そういう芹沢は、なんでうれしそうなんだよ!」
「いや、別に……? 全然うれしそうじゃなくね?」
芹沢は真顔になろうとしていたけれど、口の端はずっと上がっていて、やっぱり俺は苛立ちを抑えられなかった。
佐伯たちは計ったようなタイミングで順番に吐き捨てる。
「無理あるて、芹沢」
「だるいて、芹沢」
「うざいて、芹沢」
まったくそのとおりだよ、陽キャ一軍男子高校生たちよ。
ふんっと芹沢から顔を逸らすと、芹沢が涼しい顔をして覗き込んでくる。
「じゃあ、俺とする?」
「……は? ど、どういうこと?」
「俺とデートしようよ、鈴木」
「あー、導入ここに繋がるんだわ!」と竹内が盛り上がっている。「なげぇ導入だったな」と佐伯。「こいつ回りくどいし、昨日の夜、この流れぜったいシミュレーションしてただろ」と竹内。
俺は佐伯たちの声もあまり聞こえておらず、半信半疑で芹沢に問いかける。
「……ガチ?」
「ガチ中のガチ。楽しいよ、俺とデート」
デートと呼ぶかどうかは後で考えるとして、たしかに芹沢とのお出かけはとても楽しそうだ。
「きっと鈴木の小説にも役立つ」
にやっと笑った芹沢。攻撃の効果はバツグンだ。
たしかにそうなんだけど……。
俺は逡巡したあと、意を決して芹沢を見上げた。
「……い、一週間くれるなら行く」
「一週間? 全然いいけど、なんで?」
「芹沢と出かけるための服がないばかりか、芹沢と出かける服を買いに行くための服がない」
かなり切実な悩みなのに、芹沢は爆笑していた。おい、芹沢。
「服はなんでもいいって、鈴木がいてくれれば」
芹沢はなんにもわかっちゃいない。陰キャのクローゼット、なめんなて、芹沢。
デート当日。待ち合わせ場所で芹沢の姿を見た俺は絶句した。
「こうなると思ったよ……。解散!」
「なになになに! どこ行くんだって、鈴木!」
泣きたい思いで、俺の肩を掴んでいる芹沢を上から下まで見つめる。
「芹沢、かっこよすぎ!」
「えー、ありがと、うれしい」
いつも以上にキマっている髪型も、シンプルで身の丈に合った服も、新品みたいに手入れされたシューズも、たくさん耳に付けているピアスも、相変わらず強すぎる顔面も、イケメンな声もぜんぶ完璧だ。
「俺、隣にいて申し訳ないじゃんか……!」
どうせブランドの服なんだろ!と騒ぐと、芹沢は「靴とピアス以外ぜんぶウニクロ」と俺の心臓を軽く抉っていった。イケメンがイケメンであるゆえんを真っ向から突きつけられる。今日も俺はルッキズムに敗北しそうになっていた。
「自己評価低いんだよなぁ、鈴木は。ほかの奴とかクソほど知らねぇけどさ、俺はすげぇ好み。今日の格好も、髪型も」
服は普段ならぜったいに足を踏み入れないオシャレな洋服屋さんで、マネキンが着ていたのをぜんぶ買った。髪はよくわからなかったから、ちょっとワックスをつけた程度だ。芹沢に褒められるようなことは何もしていない。
「あと鈴木の性格も、一生懸命書いてる小説も、煮物をがんばって作んのも好みだよ」
いまいち納得できていない俺が「……煮物、頑張って作ってんのは芹沢じゃん」とつぶやくと、芹沢が笑う。
「煮物は動悸が不純だから。それよりも、鈴木だよ。ひとつひとつがんばって成果を出すだろ?」
「がんばってない……。小説はこの前初めて書き終えたし、勉強も運動も要領悪いから人の何倍もかかる」
「そういうのががんばるってことでしょ。なぁ、鈴木」
芹沢が俺に一歩近づき、きゅるきゅるの顔で覗き込んでくる。
「……『どっかの誰かの想像した評価』じゃなくて、俺が鈴木のこと『いいな』って思ってる気持ちをちゃんと受け取ってよ」
「……」
「かっこいいよ、鈴木。俺の隣にいて欲しいランキング第1位」
芹沢が両手で俺の頬を包む。背が高い芹沢を、俺は赤い顔でじっと見上げた。
「なぁ、ちゃんと受け取って、俺の気持ち」
「……わかった、受け取る」
「いい子だね、鈴木」
大人びた笑みを浮かべて、芹沢は俺の頬をむにむにと撫でた。こういうところが『沼』なわけで、俺が不安になってしまう原因なのだ。
「あのはへりはわいっほふけぼは」
「何言ってっか全然わかんねー」
むにむにと頬を撫でられながら言ったから、伝わらなかったらしい。俺の両頬にいまだに手をやっている芹沢は、「むにむにしないから、もう一回言って」と笑いを堪えている。
「あのさ芹沢、言っとくけどさ。こういうことして、もしも俺が執着受け……ああ、執着攻めでもなんでもいいんだけど、……とにかく、そうだったら今頃芹沢のストーカーになってるからな? 胸キュンセリフ言うときは相手に気をつけろよ、ほんとに……。心配だよ、俺」
そうでなくても芹沢は好意を向けられやすいのだから。芹沢は長い長い沈黙のあと、俺の頬からゆっくりと手を離した。
「………………。鈴木はなんないんだ俺のストーカーに」
「なっ、なんねぇよっ! 芹沢には迷惑かけないって!」
「迷惑、かけ……うーん………………まぁいっか………………うん、鈴木だしな」
「……なに?」
「なんでもない。行こう鈴木」
笑って、芹沢が歩き出す。俺はうなずいて、芹沢の隣に行った。
「てか、芹沢さ、さっきのセリフ小説に使っていい?」
「だめ。俺が鈴木にしか言わない言葉だし、鈴木だけが持ってて」
「今のも使っていい?」
「……すぐネタに使おうとすんのやめてもろて」
ねっとりと俺を睨んでくる芹沢がかわいくて、ぶはっと笑ってフォローした。
「冗談だよ、芹沢。……俺だけの言葉だから、俺だけが持ってる」
「ん」
見つめ合い、ちょっと照れたりして。
緊張しながらかっこよすぎる私服姿の芹沢の隣を歩き、「ちなみに、どこに行くつもり?」と尋ねると、芹沢は「鈴木が喜ぶところ」ととびっきりの笑顔を浮かべた。
水族館デート編につづく……
「ごめんな、ママ……」
朝。教室についた途端、芹沢と佐伯が何やら話し込んでいるのが聞こえた。佐伯に両肩を掴まれている芹沢は、なぜか落ち込んでいる様子で、俺は慌てて彼らの元に急ぐ。
「え……ど、どうした、芹沢……?」
「おー、来た来た。芹沢マスター」
芹沢は俺の顔を見たあと、ぱっと笑顔を浮かべた。
「おはよ、鈴木」
「はよ。……あ、あれ? 芹沢、落ち込んでたんじゃ……ねぇのか……。ごめん、勘違い……」
「合ってるよ、鈴木。今日はちょっと落ち込んでる」
そう言った芹沢の笑顔は、やっぱりほんのわずかに悲しそうだった。芹沢が落ち込んでいると、俺まで悲しくなってくる。
「ど、どうしたんだよ、芹沢」
「それがさぁ……」
「この前もらった貢物、フラグだったみてぇよ?」
意気消沈している芹沢に代わり、苦笑いを浮かべた佐伯が詳しく説明してくれた。
以前、芹沢にお菓子をたくさんくれたあの先輩たちのことだ。どうやら昨日、芹沢は先輩グループの女の子のひとりと、一対一のデートをねだられたらしい。芹沢がやんわり逃げようとしても、「あのお菓子食べたでしょ? もう断れないよー」と愛らしい笑顔で迫ってきたという。
「全力で断ったよ、申し訳ねーけど」
骨張った指先を絡めながら、気まずそうに芹沢が目を伏せる。
「先輩たちはマジでいい人だし、デート行きたいって言ってくれた子も、すげぇいい子なのよ。でも100%気持ちを返せないってわかってて、デート行って、気ぃ持たせんのほんと無理」
きっと芹沢は、こういう悪意のない好意をたくさん向けられているのだろう。俺だって……まるでアイドルを見るような視線で、いつも芹沢を見つめていた。芹沢の内面をある程度知った今でも、時折そういう目で見てしまうときもある。……すまない、芹沢よ。
「……あのさ、芹沢。これ、よかったら」
今日は芹沢にとことん優しくしてやりたい。
放課後にこっそり渡そうとしていたBL漫画の新刊を、今、渡すことにした。芹沢が喜んでくれるなら、クラスの誰に見られてもかまわない。
「え、いいの? あー、石橋叩割先生のじゃん! 読みたかったやつ!」
いいよ、芹沢。たとえすげぇ声が大きくても、クラスの女子たちが驚いたようにこっちを見ていても、いいんだよ、芹沢。いいんだ。
「俺はもう読んだから」
「偶然だわ。実は、俺も持ってきた」
芹沢がいつもの優しい笑みを浮かべたから、俺はちょっとだけほっとしてしまった。そして、彼が鞄から出した漫画を見て、BLオタクの血が抑えきれずに感嘆の声を上げる。
「し、知らない先生だ……!」
「あ、マジ? 前は少女漫画専門だったんだけど、今回BLに初挑戦したんだって」
「絵、きれー……。ありがとう、芹沢。ほんとに、ほんとに、うれしい」
俺を思って持ってきてくれたことが、何よりもありがたくて、くすぐったい。
「……俺もうれしいよ、鈴木」
芹沢がどうしようもなく格好良く見える。いや、前から格好いいけど……。
「大事に読むから」
「うん、俺も大事に読む」
屈託なく笑う芹沢のことも、芹沢が貸してくれたBL漫画も、どっちも大切にしたくて、ぎゅっと本を抱きしめた。吸い込まれそうにきれいな芹沢の黒い瞳。
立ち上がった芹沢の手が、俺の首筋に触れる。巨大な引力が発生する。吸い寄せられる、芹沢に。
「おっはよー!」
竹内の声が耳に届き、はっとして我に返った。芹沢は笑っていた、めちゃくちゃ意地悪な顔をして。
竹内と同時に岩崎も来て、俺たちを交互に見て不思議そうにつぶやく。
「おはよ。お前ら、何見つめ合ってんの?」
「あ、やべ、俺らなんか見逃した? 佐伯、ダイジェストよろしく」
竹内が焦ったように問うと、佐伯は「鈴木と芹沢が、BL漫画交換してお互いにうれしいねーって、なってるとこ」と笑いをこらえながら言った。
「そんだけ?」
「そんだけー」
「あっぶねぇ」
何があぶないのか……説明してくれそうもない三人をちょっとだけ不満の目で見つめる。「まあまあ、鈴木」とわけもわからず宥めてくる彼らをさらに睨みつけながら、俺は芹沢が貸してくれたBL漫画を丁寧に鞄へとしまった。
「……デートといえばさぁ!」
急に芹沢が声を上げ、びっくりした俺は目を丸くして芹沢を見つめた。
「急に話題をぶり返したな」と佐伯。
「……お、これはなんの導入だ?」と竹内。
「ざわざわ……ざわざわ……」と岩崎。
「昨日芹沢にもらった小説、改めて読み返したんだけど」
「あ、どうだった……?」
わずかに緊張が走り、恐る恐る芹沢に聞いた。初めて最後まで完成させたBL小説を何度も読み返して改稿し、昨日芹沢に送っていたのだ。
「最初のデート感、薄くね?」
「……え」
いつもこっちが恥ずかしくなるくらい褒めてくれる芹沢だから、どこかできっと今日も褒めてくれると期待していたのかもしれない。けれど、予想とは裏腹に、今日の芹沢は容赦なく俺を切り捨てていく。
「話の流れ自体はいい感じなのに、デートになった途端、流れ作業でもったいねぇっていうかー」
「……」
「温度感が伝わんないっつうかー」
「……」
「どこ行ってー、どこ行ってー、何しました~楽しかったです~、みたいなー」
「……」
「ちょっと小学生の日記っぽいから、ドキドキ感が欲しいんだよなー」
「……」
「……そこでなんだけど、鈴木、俺と――」
今日は芹沢にとことん優しくしてやりたい……なんて気持ちは脆くも崩れ去った。
「おりゃあああ!」
あからさまに劣等感を刺激された俺は、芹沢が言葉を続ける前に肩パンを繰り出す。しかし、普段から鍛えていて、体幹が強い芹沢は俺のふいうちの動作にもまったく驚かなかったし、ぴくりとも動かなかった。むしろ、なぜか嬉しそうまである。
「怒んなって、鈴木」
「……芹沢は俺を傷つけた! 芹沢は~! 俺を~! 傷つけた~!」
ぽすぽすと芹沢にパンチを繰り出すと、乱闘止め係のはずだった岩崎が、
「鈴木が荒ぶってる。めっちゃめずらしいわ」
とおかしそうに口角を上げた。芹沢は俺のパンチを受けながら、肩を揺らして笑っている。
「ごめんごめん。てか鈴木さ、荒ぶっても優しさ出ちゃってる。パンチが弱ぇ弱ぇ。そんなんじゃ世界とれないって」
「うるせぇ、芹沢!」
なんで顔も声もよくて、勉強も運動も(最近は煮物も)できんだよ、ふざけんな!
渾身のパンチは芹沢の大きな手に軽々と止められてしまい、言葉をなくした。
「こら。鈴木が怪我すんだろ。俺は怪我してもいいけど、鈴木は許さないから」
大変悔しいことに、怒りを含んだ芹沢の真剣な顔がまぶしくて、俺は早々に敗北を認めざるを得なかった。片や百戦錬磨の陽キャ一軍男子芹沢、片やキング・オブ・ザ・凡人の俺。
「わァ……ァァァ……」
打ちひしがれる俺。完全な敗北。
「『わァ……』って泣くんだ、鈴木。ウケる」
「ちいかわ、泣いちゃった」
「芹沢ー、鈴木泣かすなよー」
岩崎がぽんぽんと頭を撫でてくれたから、俺は芹沢の手を振り払って岩崎の胸に飛び込んだ。
「……ありがとな、岩崎」
柔道部エースである岩崎の鍛えられた胸筋に埋まっていると、とても安心することに気がついた。俺、岩崎になら抱かれてもい――。
「くっつきすぎだから!」
手首をひかれ、芹沢のほうを強制的に向かされた。普段から芹沢のほうが距離感が近いのは、棚に上げているらしい。
唇を尖らせていると、ほんのちょっとだけ言いにくそうに芹沢が言う。
「ごめんね、鈴木。でも、俺は言わないより、ちゃんと言ったほうがいいと思ってる。鈴木が真剣に小説書いてること、知ってるから」
「……それはそう」
「鈴木の小説、すげぇ好きだよ、俺」
掴まれた手首に力を入れられて、心臓が痛いくらい鳴った。自分の書いたものを好きだといってもらえるのは、本当に奇跡みたいなことだ。
「ありがとう、芹沢……。小説はちゃんと直す……。これからも意見もらえると助かる」
「もちろん。……てかさ、鈴木が今までのデートで一番よかったのって、どこに、誰と行ったやつ?」
またもや劣等感を刺激され、俺の怒りは再燃した。
「……な……いに、……ってんだろ……」
「え?」
「デートなんてしたことないけど、それがなんなんだよ! 陽キャ一軍たちと一緒にすんなよ!」
「ははっ、なんでキレてんだよ、鈴木」
「そういう芹沢は、なんでうれしそうなんだよ!」
「いや、別に……? 全然うれしそうじゃなくね?」
芹沢は真顔になろうとしていたけれど、口の端はずっと上がっていて、やっぱり俺は苛立ちを抑えられなかった。
佐伯たちは計ったようなタイミングで順番に吐き捨てる。
「無理あるて、芹沢」
「だるいて、芹沢」
「うざいて、芹沢」
まったくそのとおりだよ、陽キャ一軍男子高校生たちよ。
ふんっと芹沢から顔を逸らすと、芹沢が涼しい顔をして覗き込んでくる。
「じゃあ、俺とする?」
「……は? ど、どういうこと?」
「俺とデートしようよ、鈴木」
「あー、導入ここに繋がるんだわ!」と竹内が盛り上がっている。「なげぇ導入だったな」と佐伯。「こいつ回りくどいし、昨日の夜、この流れぜったいシミュレーションしてただろ」と竹内。
俺は佐伯たちの声もあまり聞こえておらず、半信半疑で芹沢に問いかける。
「……ガチ?」
「ガチ中のガチ。楽しいよ、俺とデート」
デートと呼ぶかどうかは後で考えるとして、たしかに芹沢とのお出かけはとても楽しそうだ。
「きっと鈴木の小説にも役立つ」
にやっと笑った芹沢。攻撃の効果はバツグンだ。
たしかにそうなんだけど……。
俺は逡巡したあと、意を決して芹沢を見上げた。
「……い、一週間くれるなら行く」
「一週間? 全然いいけど、なんで?」
「芹沢と出かけるための服がないばかりか、芹沢と出かける服を買いに行くための服がない」
かなり切実な悩みなのに、芹沢は爆笑していた。おい、芹沢。
「服はなんでもいいって、鈴木がいてくれれば」
芹沢はなんにもわかっちゃいない。陰キャのクローゼット、なめんなて、芹沢。
デート当日。待ち合わせ場所で芹沢の姿を見た俺は絶句した。
「こうなると思ったよ……。解散!」
「なになになに! どこ行くんだって、鈴木!」
泣きたい思いで、俺の肩を掴んでいる芹沢を上から下まで見つめる。
「芹沢、かっこよすぎ!」
「えー、ありがと、うれしい」
いつも以上にキマっている髪型も、シンプルで身の丈に合った服も、新品みたいに手入れされたシューズも、たくさん耳に付けているピアスも、相変わらず強すぎる顔面も、イケメンな声もぜんぶ完璧だ。
「俺、隣にいて申し訳ないじゃんか……!」
どうせブランドの服なんだろ!と騒ぐと、芹沢は「靴とピアス以外ぜんぶウニクロ」と俺の心臓を軽く抉っていった。イケメンがイケメンであるゆえんを真っ向から突きつけられる。今日も俺はルッキズムに敗北しそうになっていた。
「自己評価低いんだよなぁ、鈴木は。ほかの奴とかクソほど知らねぇけどさ、俺はすげぇ好み。今日の格好も、髪型も」
服は普段ならぜったいに足を踏み入れないオシャレな洋服屋さんで、マネキンが着ていたのをぜんぶ買った。髪はよくわからなかったから、ちょっとワックスをつけた程度だ。芹沢に褒められるようなことは何もしていない。
「あと鈴木の性格も、一生懸命書いてる小説も、煮物をがんばって作んのも好みだよ」
いまいち納得できていない俺が「……煮物、頑張って作ってんのは芹沢じゃん」とつぶやくと、芹沢が笑う。
「煮物は動悸が不純だから。それよりも、鈴木だよ。ひとつひとつがんばって成果を出すだろ?」
「がんばってない……。小説はこの前初めて書き終えたし、勉強も運動も要領悪いから人の何倍もかかる」
「そういうのががんばるってことでしょ。なぁ、鈴木」
芹沢が俺に一歩近づき、きゅるきゅるの顔で覗き込んでくる。
「……『どっかの誰かの想像した評価』じゃなくて、俺が鈴木のこと『いいな』って思ってる気持ちをちゃんと受け取ってよ」
「……」
「かっこいいよ、鈴木。俺の隣にいて欲しいランキング第1位」
芹沢が両手で俺の頬を包む。背が高い芹沢を、俺は赤い顔でじっと見上げた。
「なぁ、ちゃんと受け取って、俺の気持ち」
「……わかった、受け取る」
「いい子だね、鈴木」
大人びた笑みを浮かべて、芹沢は俺の頬をむにむにと撫でた。こういうところが『沼』なわけで、俺が不安になってしまう原因なのだ。
「あのはへりはわいっほふけぼは」
「何言ってっか全然わかんねー」
むにむにと頬を撫でられながら言ったから、伝わらなかったらしい。俺の両頬にいまだに手をやっている芹沢は、「むにむにしないから、もう一回言って」と笑いを堪えている。
「あのさ芹沢、言っとくけどさ。こういうことして、もしも俺が執着受け……ああ、執着攻めでもなんでもいいんだけど、……とにかく、そうだったら今頃芹沢のストーカーになってるからな? 胸キュンセリフ言うときは相手に気をつけろよ、ほんとに……。心配だよ、俺」
そうでなくても芹沢は好意を向けられやすいのだから。芹沢は長い長い沈黙のあと、俺の頬からゆっくりと手を離した。
「………………。鈴木はなんないんだ俺のストーカーに」
「なっ、なんねぇよっ! 芹沢には迷惑かけないって!」
「迷惑、かけ……うーん………………まぁいっか………………うん、鈴木だしな」
「……なに?」
「なんでもない。行こう鈴木」
笑って、芹沢が歩き出す。俺はうなずいて、芹沢の隣に行った。
「てか、芹沢さ、さっきのセリフ小説に使っていい?」
「だめ。俺が鈴木にしか言わない言葉だし、鈴木だけが持ってて」
「今のも使っていい?」
「……すぐネタに使おうとすんのやめてもろて」
ねっとりと俺を睨んでくる芹沢がかわいくて、ぶはっと笑ってフォローした。
「冗談だよ、芹沢。……俺だけの言葉だから、俺だけが持ってる」
「ん」
見つめ合い、ちょっと照れたりして。
緊張しながらかっこよすぎる私服姿の芹沢の隣を歩き、「ちなみに、どこに行くつもり?」と尋ねると、芹沢は「鈴木が喜ぶところ」ととびっきりの笑顔を浮かべた。
水族館デート編につづく……