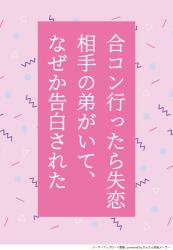芹沢が近い。
「ほら、鈴木。あーん」
いつにも増して芹沢との距離が近すぎる。一瞬もブレない芹沢の強いまなざしが、ずっと降り注いでいるのを感じていた。抱きしめられているような格好で、後ろに芹沢がぴったりと寄り添っていて、冗談ではなく本気で息ができない。
BL小説だって書き終えたし、今のところ俺には芹沢システムは必要ない。けれど、芹沢は俺のことを離すつもりはなさそうだった。
怖じ気づきながらも、芹沢に差し出された煮物(ニンジン)をぱくりと食べる。
牧場でニンジンを食べているウサギってこんな気持ちなのかも……。
綺麗すぎる芹沢の顔面からも、現実の問題からも目を逸らし、無心でニンジンを咀嚼した。
「どう、うまい?」
「めちゃくちゃうまい……で、ごじゃ、います」
「よかったー。鈴木のために作ったから、いっぱい食べてー」
嘘偽りなく、芹沢がリベンジした煮物はおいしかった。だが、近い。どう考えても近すぎる。いつもの二割増しで近い。
俺の推測によると、これはなんらかの意思表明であり、芹沢は①機嫌が悪い、②怒っている、のどちらかだと考えられる。
そういえば、授業中もなんだかおかしかった。いつもなら、芹沢を中心に賑やかな笑いが起こるのに、芹沢は何かを考え込むようにして頬杖をついていた。その芹沢の横顔を見て、クラスの女子たちは「マジ顔面良すぎ」「綺麗すぎてウケる」と言っていたけれど、俺も完全に同意だった。
怒ってるんだよな、きっと……。数時間前、俺がしてしまった過ちが、まだ胸を騒がせていた。
あの時のことを思い出すと、全身に火がついたみたいに熱くなる。
俺と芹沢はどういうわけか、(お互いの合意の元に)キスをしてしまったのだ。あのキスがなんだったのか、おそらく俺も芹沢も説明できないだろう。
誰か、あのキスを俺たちに説明してくれ。
助けを求めるように顔を上げた瞬間、空き教室の扉の向こうから愛らしい声が聞こえた。
「せーりーざーわー、お菓子あげるから、おいでー!」
三年の先輩たちのはしゃぐ声が、鼓膜を鮮明に揺らす。短いスカート、手入れされたぴかぴかの爪、唇は潤い、瞳はまん丸と大きい。常に自分を磨き、綺麗になる努力を続けている、尊敬すべきストイックな方々だ。
彼女たちの強い生命力が、離れていても伝わってくる。俺は思わず、小さく身を縮込ませた。
「え、マジ? 先輩ら、なんかくれるんスか?」
「あげるー。おいで、おいで」
へらっとした愛嬌のある笑みを浮かべ、芹沢はゆっくりと立ち上がった。背中に感じていた芹沢の圧がなくなって少しだけほっとしていると、完璧すぎて畏怖を感じるほどの笑顔で、芹沢が俺の肩を掴む。耳元にかすかに感じる、芹沢の熱い息。
キスをしたときの距離感を思い出して、一瞬ぞくりとしてしまった。
「すぐ戻る。残りも俺が食べさせるから、待ってて、鈴木」
笑顔が一瞬、真顔になったような気がして、ぽかんと口を開けたまま目を瞬かせた。次の瞬間にはいつもの優しい笑みを浮かべていたから、俺の見間違いだったのかもしれない。
俺への表面的な態度はいつもと変わらないのに、今の芹沢はどこかひやりとした冷たい何かを感じさせた。
あの瞬間、たしかに心が通じ合えたと思った。だけど、キスをしてしまったせいで、俺と芹沢の関係は変な方向にねじ曲がってしまったのだ。
なんでだよ、俺のばか。
なんで……みんなの太陽である芹沢とキスをしてしまったのか。あの時の俺はどうかしていた。そして、芹沢も同様に。
ツンと鼻の奥が痛み、心がどんどん重くなっていく。まるで足元が床にめり込んでいくみたいだ。
「どーした? 鈴木?」
佐伯が心配そうに問いかけてくる。その優しさに背中を押され、小さくつぶやく。
「せ、芹沢ってさ、……俺に怒ってるよね?」
自分の中でぐるぐる考え続けるのは苦しすぎる。どうしても客観的な意見が欲しくて、佐伯、竹内、岩崎の順番に視線を合わせると、最初に岩崎が口火を切った。
「別に怒ってねぇだろ。なぁ竹内?」
「……えー、わかんね。でもたしかに、なんかいつもとちょっと違うような」
竹内が首を傾げている横で、佐伯が身を乗り出す。
「鈴木、あれはたぶん怒ってるっていうか、拗ね――」
佐伯がその先を言おうとしたところで、いつの間にか芹沢の影が佐伯を覆った。ポッキーやら、グミやら、チョコやら、たくさんの貢ぎものを先輩女子からもらったらしい芹沢は、瞳を弧にし、美しく口角を上げる。
「何? なんの話? 俺がいない間に鈴木と何話してた? ぜんぶ教えて?」
芹沢以外の人間が全員こくりと唾を飲み込む。
笑顔が怖いて、芹沢。
どこでボタンを掛け違えたのか、何をどうすれば芹沢と前みたいに自然に話せるのか。何も答えが出ないまま迎えた放課後。小さくため息を吐いていると、目の前に難しい顔をして腕を組んでいる竹内がいた。
「鈴木、今日ひま?」
「ひ、ひま、だけど?」
「じゃあ、行こ」
竹内が振り向き、「鈴木行けるって」と佐伯に報告する。佐伯は笑顔でうなずき、その隣にいた芹沢は無言でかばんを背負った。
「え、どこに?」
「いいから行くぞ、鈴木」
岩崎が俺の肩を軽く叩く。今日は柔道部の練習がないらしい。
そうして、半ば連行されるようにして、学校の近くのファミレスに来た。
先に座った竹内の隣に座ろうとすると、「鈴木はこっち、俺の隣」と芹沢に腕を引っ張られる。
俺、芹沢。その前には竹内、佐伯、岩崎。男子高校生が三人座っている竹内たちの席はとても狭そうで、一番端っこの岩崎の体はちょっとだけ椅子からはみ出していた。
「俺、体小さいから、岩崎と交換す――」
「いいから、鈴木はここ」
身を乗り出して提案したけれど、すぐに芹沢に却下されてしまい、渋々元の席に座り直す。やっぱり、芹沢はどこか機嫌が悪そうだ。
「そんじゃあ、今から学級会を始めようと思いまーす。賛成の人ー」
竹内の言葉に、ぱっと顔を上げる。
「お、久しぶりじゃね。やろうぜ」
と、岩崎。
「俺も賛成。こういうのは長引けば長引くほど後を引くからね~。さっさと解決しましょうね~」
と、佐伯。
俺はまだ何がなんだかわからない状況だったけれど、次に聞こえた竹内の言葉に、すべて納得いったのだった。
「議題は『芹沢と鈴木が微妙な件』について」
びくっと肩が揺れる。隣の芹沢は涼しい顔で、水を飲んでいた。
「雑だな~~、議題が」
「書記、佐伯」
「あーい」
「乱闘止め係、岩崎」
「あーい」
乱闘する気はまったくないので、岩崎の出番がないことを心から願う。
「で、君らの問題の発端は? 数時間前まで普通だったのに、急に気まずくなった原因があんだろ?」
「吐いて楽になっちまえよ」
竹内と佐伯が言い、その後に岩崎が続いてにやりと笑った。
「低気圧だろ? この世のすべては気圧のせい」
「岩崎黙ってて」
「……ッス」
岩崎がすんとした顔になるを見守った俺は、芹沢に「言ってもいい?」と小声で聞いた。「いいよ」とつぶやく芹沢の顔は綺麗過ぎて何を考えているのかよくわからない。
「あの……、実は……お、俺と芹沢が……あ、あれをヤッちゃって……」
「え、ガチ?」
「……おい、シャレになんねぇぞ、芹沢」
「てめぇ、鈴木に何したんだよ……」
「キスした」
悪びれもせず、堂々と言い放った芹沢の様子に、少しだけ尊敬の念を抱いてしまった。
怖い顔をしていた三人は、芹沢の言葉を受け、なぜかほっとしたように背もたれに寄りかかる。
「なんだ、キスかよ……解散」
「乱闘を止めるどころか、俺が乱闘しちまうとこだったわ……」
「まったく、この佐伯さんを焦らせんなよ……」
三人からふんと顔を背けた芹沢は明らかに機嫌が悪く、俺は怖気づきながら芹沢の横顔を見つめる。
「ご、ごめんな、芹沢。もし俺のせいで、嫌な思いさせてたら……ほんとに謝る。……俺は、芹沢と仲直りしたい、です」
明後日の方向を見ていた芹沢が、驚いたように俺のほうを向いた。かと思うと髪をくしゃりと撫でつけ、「あーーーー」と声を出しながら顔を歪める。
「くっそ……俺って、めちゃくちゃ格好悪いじゃん……もうやだ……」
「いやいや、芹沢はめちゃくちゃ格好いいから! あのさ、鏡ちゃんと見てる!?」
「鈴木黙ってて」
「……はい」
佐伯に窘められた俺がすんとした顔をしていると、芹沢が申し訳なさそうに俺を見つめてくる。
「そもそも鈴木とケンカしたつもりねぇし、嫌な思いなんてしてないから」
「ほ、ほんとに……?」
「ほんと。鈴木は全然悪くない。俺が少し焦りすぎたってだけ」
「……え?」
佐伯は俺のほうに体を向け、しっかりと頭を下げて言った。
「鈴木、今日は変な態度取って、心配かけてごめんなさい。……俺としては、ふたりに起こった出来事を、色々と整理する時間が必要だった」
俺が思っている以上に、芹沢も動揺していたようだ。芹沢の心情を慮ることができなかった自分の幼さを反省し、泣きそうになりながら、俺も芹沢に頭を下げる。
「俺のほうこそほんとごめん、芹沢……!」
「謝んなくていい。つうか、鈴木があれを忘れたいっていうなら、それでいいし、俺は鈴木のペースに合わせる」
「うん、ありがとう。……ありが、とう……?」
話がうまくまとまったと思いつつも、俺の中で若干の疑問が残った。俺のペースに合わせる……とは?
「……芹沢、やっぱそうなんだなお前」
竹内の言葉に、ますます俺は首を傾げた。芹沢は飄々とした顔で「そうだよ」と答える。
「だとしたら性急すぎ。キモいて、うざいて、無理あるて、芹沢」
「うるせぇわ、わかってんだよ、こっちだって」
苛立ったように佐伯に反発する芹沢の腕を、俺は両手で掴んで問いかけた。
「……あのさ、芹沢、なんの話してる?」
「いいんだよ、鈴木。大丈夫、大丈夫」
いや、だから、何が?
「「「大丈夫だよ、鈴木」」」
俺以外全員わかっているようで、みんなにこにこと優しい笑みを浮かべていた。
いや、だから、何が!?!?
「なんかまぁ、こういう時もあるっしょ!」
陽キャのノリ全開で、佐伯が爽やかな笑顔を浮かべる。
「てか、キスくらいなら俺ら全員してるしなー。今さらなー」
「はいっ!?」
「あー、そういえばあったわ! なんか流れでね!」
どんな流れだよ、と突っ込む暇もなく、佐伯たちの会話は続いていく。
「記憶の片隅にあるわ。なんだったっけ、あれ」
「ポッキーゲームっしょ。去年の11月11日」
「そうそう、思い出した、やっば!」
「待って、あったわ! ほら、証拠写真!」
佐伯のスマホには、たしかにキスをしている佐伯と岩崎の姿が映し出されていた。ほかにも、芹沢と竹内、竹内と芹沢。全員ノリノリでポッキーゲームをしている。
「ま、待ってよ、マジでキスしてんじゃんっ……。つうか、無理。も、もうしまって……俺には刺激が強すぎる」
イケメン同士のキスの破壊力は、想像以上だった。みんなに聞こえてしまうかと思うくらい心臓が鳴っていた。BL妄想はいつもしているけれど、実在する人たちで妄想するのは俺のコンプライアンス的にタブーなのだ。赤い顔で目を背けた俺を見て、みんなはゲラゲラと笑うと「ポムじいさんかよ」とふざけたツッコミを入れていた。
「せ、芹沢、……俺以外にもキスしてたんだな……」
なんだかそれはそれで、もやもやしてしまうのはどうしてなのだろう。
「うーん、……ニュアンスが全然ちげーんだけど……」
困ったように髪をかきあげ、逡巡したかと思うと、芹沢は何か吹っ切れたように真顔で言った。
「まあ、たしかにしたっちゃした。……こんな感じだから、ほんとに気に病まないで、鈴木。忘れていいから」
俺にとっては大問題だったけれど、芹沢にとっては、俺とのキスも軽いノリだったのかもしれない。
ほっとしたような、やっぱりどこか胸の奥がちくりとするような。
どっちにしても、今、言わなきゃ一生後悔すると思った。
「……忘れんのは、なしにする」
「は?」
「あの時、芹沢がすごくこう……キ、キスしたくなるくらいすげぇ大切に思えた気持ちは嘘じゃないし、これからも俺にとってはそうだから、……忘れない」
目を丸くした芹沢は、少ししてからゆっくりと口角を上げた。意地悪な笑顔に、胸がキュンと痺れる。
「1、2のポカンしなくていいの?」
それはごめんて、芹沢。
「俺も忘れねぇし、最初からそのつもり」
「……せ、せりざわぁ」
「もう一回しとく? キス」
「ばっ、ばかかよ! ……いや、芹沢はばかじゃないわ、ごめん」
「ははっ! ほんと鈴木は素直だな」
芹沢が屈託なく笑うのを見て、ますます心臓がぎゅっとなった。赤くなっている頬を隠すようにうつむき、コップの水をずずっと啜る。
「はい! みんな仲直り! つうことで、学級会おわり! 次の話題は鈴木のBL小説です!」
「えっ、俺!?」
「芹沢、読んだんだろ?」
「読んだよ。すげぇよかった。鈴木っぽくて、優しくてあったかい話」
うれしい。めちゃくちゃうれしい。
「じゃあ、俺らも――」
「だめ」
「あ?」
「だめ。俺が読んでから、一般の読者に解禁になるまで一週間は必要だから」
悪びれもせずそう言う芹沢に、みんな真顔をしている。
「それでいいよな? 鈴木。なぁ、いいだろ、いいって言えよ」
「……芹沢って、ほんとにワガママボーイだな」
子供のような芹沢がおかしくて、笑ったままそう言うと、芹沢は少しだけ反省したみたいにぽつりとつぶやく。
「……ごめん」
「いいよ。芹沢がそうしたいなら」
「ん……ありがと、鈴木」
ちょっとはわがままへの罪悪感を感じているらしい。
弱ってる攻め……っていうか、ふいに見せる弱ってる芹沢って、やっぱたまんないかも……。
衝動を抑えきれず、芹沢の頭をくしゃくしゃと撫でる。芹沢は文句を言わなかったから、さらにくしゃくしゃと撫でつけた。微妙に笑いかけた顔で、芹沢が言う。
「手にワックスつくよ、鈴木くんてば」
「いい。あとで芹沢の制服で拭くから」
「それはやめてもろて」
「俺に撫でられんのいや?」
「……そっちはどうぞ、好きなだけ」
頬杖をついて、芹沢が苦笑する。あー、やっぱ芹沢はかっこいいわー。
芹沢はみんなの芹沢で、俺はどこにでもいる平凡な高校生だ。だけど、もし芹沢が許してくれるのなら、ずっと芹沢と仲良しでいたい。
もっと、もっと、芹沢の隣にいられる今を大事にしようと思った。
俺にとって芹沢はまぶしくて、遠い存在で、だけどなぜかいつも近くにいてくれて、大切で、特別な人。
「よかったねー、仲直りできて」
「だから、ケンカしてねぇっつの。俺と鈴木は仲良しなんだよ」
「つーか俺ら、芹沢使いが誕生した瞬間を見たんじゃね、今」
佐伯の冗談にみんながからかうような笑みを浮かべる。
「なんだよ、芹沢使いって」
「ワガママボーイを唯一扱える芹沢マスター鈴木」
「やめてもらえる? 鈴木には『天然冷えピタ鈴木』っていう立派な異名がすでにあんだよ」
「……言いにくいんだけどさ、芹沢。俺自身、もう忘れてたんだわ」
「行けっ! 芹沢! 10万ボルド! 鈴木、命令してやって」
「なんなの岩崎、お前やんのかこら、表出ろよ」
「おっ、やろうぜ、鈴木」
「先生! 乱闘止め係が乱闘とめませーーん!」
「鈴木! 芹沢の頭を撫でて差し上げて」
「どうどう、芹沢。よーしよし、いい子いい子」
「…………ん」
俺が頭を撫でた途端、芹沢は目をつぶって俺に身を委ねてきた。
「マジで大人しくなんのかい!」
その日から、ちょっとでも芹沢の機嫌が悪いと、『ワガママボーイを唯一扱える芹沢マスター』である俺が呼ばれることになるとは思いもしなかったのだ。
なぁ、芹沢。頼むて、芹沢。
「ほら、鈴木。あーん」
いつにも増して芹沢との距離が近すぎる。一瞬もブレない芹沢の強いまなざしが、ずっと降り注いでいるのを感じていた。抱きしめられているような格好で、後ろに芹沢がぴったりと寄り添っていて、冗談ではなく本気で息ができない。
BL小説だって書き終えたし、今のところ俺には芹沢システムは必要ない。けれど、芹沢は俺のことを離すつもりはなさそうだった。
怖じ気づきながらも、芹沢に差し出された煮物(ニンジン)をぱくりと食べる。
牧場でニンジンを食べているウサギってこんな気持ちなのかも……。
綺麗すぎる芹沢の顔面からも、現実の問題からも目を逸らし、無心でニンジンを咀嚼した。
「どう、うまい?」
「めちゃくちゃうまい……で、ごじゃ、います」
「よかったー。鈴木のために作ったから、いっぱい食べてー」
嘘偽りなく、芹沢がリベンジした煮物はおいしかった。だが、近い。どう考えても近すぎる。いつもの二割増しで近い。
俺の推測によると、これはなんらかの意思表明であり、芹沢は①機嫌が悪い、②怒っている、のどちらかだと考えられる。
そういえば、授業中もなんだかおかしかった。いつもなら、芹沢を中心に賑やかな笑いが起こるのに、芹沢は何かを考え込むようにして頬杖をついていた。その芹沢の横顔を見て、クラスの女子たちは「マジ顔面良すぎ」「綺麗すぎてウケる」と言っていたけれど、俺も完全に同意だった。
怒ってるんだよな、きっと……。数時間前、俺がしてしまった過ちが、まだ胸を騒がせていた。
あの時のことを思い出すと、全身に火がついたみたいに熱くなる。
俺と芹沢はどういうわけか、(お互いの合意の元に)キスをしてしまったのだ。あのキスがなんだったのか、おそらく俺も芹沢も説明できないだろう。
誰か、あのキスを俺たちに説明してくれ。
助けを求めるように顔を上げた瞬間、空き教室の扉の向こうから愛らしい声が聞こえた。
「せーりーざーわー、お菓子あげるから、おいでー!」
三年の先輩たちのはしゃぐ声が、鼓膜を鮮明に揺らす。短いスカート、手入れされたぴかぴかの爪、唇は潤い、瞳はまん丸と大きい。常に自分を磨き、綺麗になる努力を続けている、尊敬すべきストイックな方々だ。
彼女たちの強い生命力が、離れていても伝わってくる。俺は思わず、小さく身を縮込ませた。
「え、マジ? 先輩ら、なんかくれるんスか?」
「あげるー。おいで、おいで」
へらっとした愛嬌のある笑みを浮かべ、芹沢はゆっくりと立ち上がった。背中に感じていた芹沢の圧がなくなって少しだけほっとしていると、完璧すぎて畏怖を感じるほどの笑顔で、芹沢が俺の肩を掴む。耳元にかすかに感じる、芹沢の熱い息。
キスをしたときの距離感を思い出して、一瞬ぞくりとしてしまった。
「すぐ戻る。残りも俺が食べさせるから、待ってて、鈴木」
笑顔が一瞬、真顔になったような気がして、ぽかんと口を開けたまま目を瞬かせた。次の瞬間にはいつもの優しい笑みを浮かべていたから、俺の見間違いだったのかもしれない。
俺への表面的な態度はいつもと変わらないのに、今の芹沢はどこかひやりとした冷たい何かを感じさせた。
あの瞬間、たしかに心が通じ合えたと思った。だけど、キスをしてしまったせいで、俺と芹沢の関係は変な方向にねじ曲がってしまったのだ。
なんでだよ、俺のばか。
なんで……みんなの太陽である芹沢とキスをしてしまったのか。あの時の俺はどうかしていた。そして、芹沢も同様に。
ツンと鼻の奥が痛み、心がどんどん重くなっていく。まるで足元が床にめり込んでいくみたいだ。
「どーした? 鈴木?」
佐伯が心配そうに問いかけてくる。その優しさに背中を押され、小さくつぶやく。
「せ、芹沢ってさ、……俺に怒ってるよね?」
自分の中でぐるぐる考え続けるのは苦しすぎる。どうしても客観的な意見が欲しくて、佐伯、竹内、岩崎の順番に視線を合わせると、最初に岩崎が口火を切った。
「別に怒ってねぇだろ。なぁ竹内?」
「……えー、わかんね。でもたしかに、なんかいつもとちょっと違うような」
竹内が首を傾げている横で、佐伯が身を乗り出す。
「鈴木、あれはたぶん怒ってるっていうか、拗ね――」
佐伯がその先を言おうとしたところで、いつの間にか芹沢の影が佐伯を覆った。ポッキーやら、グミやら、チョコやら、たくさんの貢ぎものを先輩女子からもらったらしい芹沢は、瞳を弧にし、美しく口角を上げる。
「何? なんの話? 俺がいない間に鈴木と何話してた? ぜんぶ教えて?」
芹沢以外の人間が全員こくりと唾を飲み込む。
笑顔が怖いて、芹沢。
どこでボタンを掛け違えたのか、何をどうすれば芹沢と前みたいに自然に話せるのか。何も答えが出ないまま迎えた放課後。小さくため息を吐いていると、目の前に難しい顔をして腕を組んでいる竹内がいた。
「鈴木、今日ひま?」
「ひ、ひま、だけど?」
「じゃあ、行こ」
竹内が振り向き、「鈴木行けるって」と佐伯に報告する。佐伯は笑顔でうなずき、その隣にいた芹沢は無言でかばんを背負った。
「え、どこに?」
「いいから行くぞ、鈴木」
岩崎が俺の肩を軽く叩く。今日は柔道部の練習がないらしい。
そうして、半ば連行されるようにして、学校の近くのファミレスに来た。
先に座った竹内の隣に座ろうとすると、「鈴木はこっち、俺の隣」と芹沢に腕を引っ張られる。
俺、芹沢。その前には竹内、佐伯、岩崎。男子高校生が三人座っている竹内たちの席はとても狭そうで、一番端っこの岩崎の体はちょっとだけ椅子からはみ出していた。
「俺、体小さいから、岩崎と交換す――」
「いいから、鈴木はここ」
身を乗り出して提案したけれど、すぐに芹沢に却下されてしまい、渋々元の席に座り直す。やっぱり、芹沢はどこか機嫌が悪そうだ。
「そんじゃあ、今から学級会を始めようと思いまーす。賛成の人ー」
竹内の言葉に、ぱっと顔を上げる。
「お、久しぶりじゃね。やろうぜ」
と、岩崎。
「俺も賛成。こういうのは長引けば長引くほど後を引くからね~。さっさと解決しましょうね~」
と、佐伯。
俺はまだ何がなんだかわからない状況だったけれど、次に聞こえた竹内の言葉に、すべて納得いったのだった。
「議題は『芹沢と鈴木が微妙な件』について」
びくっと肩が揺れる。隣の芹沢は涼しい顔で、水を飲んでいた。
「雑だな~~、議題が」
「書記、佐伯」
「あーい」
「乱闘止め係、岩崎」
「あーい」
乱闘する気はまったくないので、岩崎の出番がないことを心から願う。
「で、君らの問題の発端は? 数時間前まで普通だったのに、急に気まずくなった原因があんだろ?」
「吐いて楽になっちまえよ」
竹内と佐伯が言い、その後に岩崎が続いてにやりと笑った。
「低気圧だろ? この世のすべては気圧のせい」
「岩崎黙ってて」
「……ッス」
岩崎がすんとした顔になるを見守った俺は、芹沢に「言ってもいい?」と小声で聞いた。「いいよ」とつぶやく芹沢の顔は綺麗過ぎて何を考えているのかよくわからない。
「あの……、実は……お、俺と芹沢が……あ、あれをヤッちゃって……」
「え、ガチ?」
「……おい、シャレになんねぇぞ、芹沢」
「てめぇ、鈴木に何したんだよ……」
「キスした」
悪びれもせず、堂々と言い放った芹沢の様子に、少しだけ尊敬の念を抱いてしまった。
怖い顔をしていた三人は、芹沢の言葉を受け、なぜかほっとしたように背もたれに寄りかかる。
「なんだ、キスかよ……解散」
「乱闘を止めるどころか、俺が乱闘しちまうとこだったわ……」
「まったく、この佐伯さんを焦らせんなよ……」
三人からふんと顔を背けた芹沢は明らかに機嫌が悪く、俺は怖気づきながら芹沢の横顔を見つめる。
「ご、ごめんな、芹沢。もし俺のせいで、嫌な思いさせてたら……ほんとに謝る。……俺は、芹沢と仲直りしたい、です」
明後日の方向を見ていた芹沢が、驚いたように俺のほうを向いた。かと思うと髪をくしゃりと撫でつけ、「あーーーー」と声を出しながら顔を歪める。
「くっそ……俺って、めちゃくちゃ格好悪いじゃん……もうやだ……」
「いやいや、芹沢はめちゃくちゃ格好いいから! あのさ、鏡ちゃんと見てる!?」
「鈴木黙ってて」
「……はい」
佐伯に窘められた俺がすんとした顔をしていると、芹沢が申し訳なさそうに俺を見つめてくる。
「そもそも鈴木とケンカしたつもりねぇし、嫌な思いなんてしてないから」
「ほ、ほんとに……?」
「ほんと。鈴木は全然悪くない。俺が少し焦りすぎたってだけ」
「……え?」
佐伯は俺のほうに体を向け、しっかりと頭を下げて言った。
「鈴木、今日は変な態度取って、心配かけてごめんなさい。……俺としては、ふたりに起こった出来事を、色々と整理する時間が必要だった」
俺が思っている以上に、芹沢も動揺していたようだ。芹沢の心情を慮ることができなかった自分の幼さを反省し、泣きそうになりながら、俺も芹沢に頭を下げる。
「俺のほうこそほんとごめん、芹沢……!」
「謝んなくていい。つうか、鈴木があれを忘れたいっていうなら、それでいいし、俺は鈴木のペースに合わせる」
「うん、ありがとう。……ありが、とう……?」
話がうまくまとまったと思いつつも、俺の中で若干の疑問が残った。俺のペースに合わせる……とは?
「……芹沢、やっぱそうなんだなお前」
竹内の言葉に、ますます俺は首を傾げた。芹沢は飄々とした顔で「そうだよ」と答える。
「だとしたら性急すぎ。キモいて、うざいて、無理あるて、芹沢」
「うるせぇわ、わかってんだよ、こっちだって」
苛立ったように佐伯に反発する芹沢の腕を、俺は両手で掴んで問いかけた。
「……あのさ、芹沢、なんの話してる?」
「いいんだよ、鈴木。大丈夫、大丈夫」
いや、だから、何が?
「「「大丈夫だよ、鈴木」」」
俺以外全員わかっているようで、みんなにこにこと優しい笑みを浮かべていた。
いや、だから、何が!?!?
「なんかまぁ、こういう時もあるっしょ!」
陽キャのノリ全開で、佐伯が爽やかな笑顔を浮かべる。
「てか、キスくらいなら俺ら全員してるしなー。今さらなー」
「はいっ!?」
「あー、そういえばあったわ! なんか流れでね!」
どんな流れだよ、と突っ込む暇もなく、佐伯たちの会話は続いていく。
「記憶の片隅にあるわ。なんだったっけ、あれ」
「ポッキーゲームっしょ。去年の11月11日」
「そうそう、思い出した、やっば!」
「待って、あったわ! ほら、証拠写真!」
佐伯のスマホには、たしかにキスをしている佐伯と岩崎の姿が映し出されていた。ほかにも、芹沢と竹内、竹内と芹沢。全員ノリノリでポッキーゲームをしている。
「ま、待ってよ、マジでキスしてんじゃんっ……。つうか、無理。も、もうしまって……俺には刺激が強すぎる」
イケメン同士のキスの破壊力は、想像以上だった。みんなに聞こえてしまうかと思うくらい心臓が鳴っていた。BL妄想はいつもしているけれど、実在する人たちで妄想するのは俺のコンプライアンス的にタブーなのだ。赤い顔で目を背けた俺を見て、みんなはゲラゲラと笑うと「ポムじいさんかよ」とふざけたツッコミを入れていた。
「せ、芹沢、……俺以外にもキスしてたんだな……」
なんだかそれはそれで、もやもやしてしまうのはどうしてなのだろう。
「うーん、……ニュアンスが全然ちげーんだけど……」
困ったように髪をかきあげ、逡巡したかと思うと、芹沢は何か吹っ切れたように真顔で言った。
「まあ、たしかにしたっちゃした。……こんな感じだから、ほんとに気に病まないで、鈴木。忘れていいから」
俺にとっては大問題だったけれど、芹沢にとっては、俺とのキスも軽いノリだったのかもしれない。
ほっとしたような、やっぱりどこか胸の奥がちくりとするような。
どっちにしても、今、言わなきゃ一生後悔すると思った。
「……忘れんのは、なしにする」
「は?」
「あの時、芹沢がすごくこう……キ、キスしたくなるくらいすげぇ大切に思えた気持ちは嘘じゃないし、これからも俺にとってはそうだから、……忘れない」
目を丸くした芹沢は、少ししてからゆっくりと口角を上げた。意地悪な笑顔に、胸がキュンと痺れる。
「1、2のポカンしなくていいの?」
それはごめんて、芹沢。
「俺も忘れねぇし、最初からそのつもり」
「……せ、せりざわぁ」
「もう一回しとく? キス」
「ばっ、ばかかよ! ……いや、芹沢はばかじゃないわ、ごめん」
「ははっ! ほんと鈴木は素直だな」
芹沢が屈託なく笑うのを見て、ますます心臓がぎゅっとなった。赤くなっている頬を隠すようにうつむき、コップの水をずずっと啜る。
「はい! みんな仲直り! つうことで、学級会おわり! 次の話題は鈴木のBL小説です!」
「えっ、俺!?」
「芹沢、読んだんだろ?」
「読んだよ。すげぇよかった。鈴木っぽくて、優しくてあったかい話」
うれしい。めちゃくちゃうれしい。
「じゃあ、俺らも――」
「だめ」
「あ?」
「だめ。俺が読んでから、一般の読者に解禁になるまで一週間は必要だから」
悪びれもせずそう言う芹沢に、みんな真顔をしている。
「それでいいよな? 鈴木。なぁ、いいだろ、いいって言えよ」
「……芹沢って、ほんとにワガママボーイだな」
子供のような芹沢がおかしくて、笑ったままそう言うと、芹沢は少しだけ反省したみたいにぽつりとつぶやく。
「……ごめん」
「いいよ。芹沢がそうしたいなら」
「ん……ありがと、鈴木」
ちょっとはわがままへの罪悪感を感じているらしい。
弱ってる攻め……っていうか、ふいに見せる弱ってる芹沢って、やっぱたまんないかも……。
衝動を抑えきれず、芹沢の頭をくしゃくしゃと撫でる。芹沢は文句を言わなかったから、さらにくしゃくしゃと撫でつけた。微妙に笑いかけた顔で、芹沢が言う。
「手にワックスつくよ、鈴木くんてば」
「いい。あとで芹沢の制服で拭くから」
「それはやめてもろて」
「俺に撫でられんのいや?」
「……そっちはどうぞ、好きなだけ」
頬杖をついて、芹沢が苦笑する。あー、やっぱ芹沢はかっこいいわー。
芹沢はみんなの芹沢で、俺はどこにでもいる平凡な高校生だ。だけど、もし芹沢が許してくれるのなら、ずっと芹沢と仲良しでいたい。
もっと、もっと、芹沢の隣にいられる今を大事にしようと思った。
俺にとって芹沢はまぶしくて、遠い存在で、だけどなぜかいつも近くにいてくれて、大切で、特別な人。
「よかったねー、仲直りできて」
「だから、ケンカしてねぇっつの。俺と鈴木は仲良しなんだよ」
「つーか俺ら、芹沢使いが誕生した瞬間を見たんじゃね、今」
佐伯の冗談にみんながからかうような笑みを浮かべる。
「なんだよ、芹沢使いって」
「ワガママボーイを唯一扱える芹沢マスター鈴木」
「やめてもらえる? 鈴木には『天然冷えピタ鈴木』っていう立派な異名がすでにあんだよ」
「……言いにくいんだけどさ、芹沢。俺自身、もう忘れてたんだわ」
「行けっ! 芹沢! 10万ボルド! 鈴木、命令してやって」
「なんなの岩崎、お前やんのかこら、表出ろよ」
「おっ、やろうぜ、鈴木」
「先生! 乱闘止め係が乱闘とめませーーん!」
「鈴木! 芹沢の頭を撫でて差し上げて」
「どうどう、芹沢。よーしよし、いい子いい子」
「…………ん」
俺が頭を撫でた途端、芹沢は目をつぶって俺に身を委ねてきた。
「マジで大人しくなんのかい!」
その日から、ちょっとでも芹沢の機嫌が悪いと、『ワガママボーイを唯一扱える芹沢マスター』である俺が呼ばれることになるとは思いもしなかったのだ。
なぁ、芹沢。頼むて、芹沢。