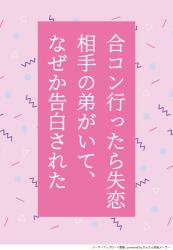息をするのも忘れるくらい夢中になって、スマホをフリックする。最後の一文を書き上げた瞬間、ようやく深い息を吐いた。
「……か、書けた」
合計5万字。初めて最後まで書いたBL小説。うまく書けたかどうかはわからない、だけど――。
「書けた! 書けた! 書けたーー!」
誰もいない自室のベッドの上でばたばたと喜びを噛みしめると、すぐに芹沢の顔が浮かんできた。
「せ、芹沢に連絡……!」
ラインのメッセージを書いている途中、はたと動きを止める。ラインじゃなくて、直接、芹沢の顔を見て言いたかった。
「早く明日になんねーかなぁ……」
少しでも早く芹沢に会いたい。
にやけた顔でベッドに寝転び、いつの間にか芹沢の存在が特別なものになっているのを感じていた。芹沢となら大好きなBLを分かち合える。
そう思う一方で、あっちも同じように感じてくれるとは限らないともう一人の自分が言う。わかってるよ。ちゃんとわきまえなければ――。
俺はどこにでもあるような石で、芹沢はみんなの太陽だ。
顔を引き締め、無言で天井を見つめた。けれど、すぐに頬が緩んでしまう。明日、芹沢はどんな顔をするのだろう。
***
次の日、張り切りすぎていつもより早く教室に着いてしまった。
芹沢はまだ登校していないようだ。そわそわと昨日書いた小説を読み返していると、佐伯と竹内と岩崎が「はよー、鈴木」と近くにやってくる。
「みんな、おはよう。てか岩崎、今日は早いね。柔道部の朝練ナシ?」
「そう。鈴木も来んの早くね?」
「ああ……うん、ちょっとね……」
芹沢に会いたくて待ちきれなかった、とは言えるはずがなかった。苦笑を返すと、人懐っこい笑みを浮かべた佐伯が俺の前の席に座る。
「ずっと気になってたんだけど、もしかして鈴木って小説書いてんの?」
「それ、俺も気になってた」
「俺も」
佐伯と竹内と岩崎の視線が俺に集中し、ドキドキと心臓が鳴った。以前までの自分だったら、ぜったいに言わなかっただろう。でも、今は……。住む世界が違くて、イケメンで、何もかも持っているような陽キャの彼らが、どんな人間なのか少しは知っている。
俺は意を決して顔を上げ、こくりとうなずいた。
「やっぱそうなんだ!」
「すげぇじゃん」
「芹沢には読ましてんだろ? なぁ、俺らも読みたい」
「え、でも、……び」
「び……?」
その先を言うのはさすがに抵抗があった。一年前についた心臓の古傷がずきりと痛んだが、おずおずと彼らを見上げて言う。
「BLだよ?」
三人はきょとんと目を瞬かせたあと、それぞれが爽やかな笑顔を浮かべた。
「モーマンタイ」と竹内。「芹沢に何度も読まされてるし」と岩崎。「意外と好きだよ、俺らも」と佐伯。みんなの言葉に思わず身を乗り出した。
「……えっ、ほんとに!?」
「うん。君たちほどの熱量はないからあんま言わないけど。ほら、あれじゃん? めちゃくちゃBL好きな人の前でにわかすんの申し訳ねぇじゃん?」
「そ、そんなの関係ないって!」
彼らもBLを読んでいたことを初めて知った。ここにも同士がいるんだとうれしくなって、ちょっとだけ泣きそうになりながら彼らの前にスマホを差し出す。
「よかったら、よ、読んで……」
「おー!」
「あ、やっぱごめん、待って!」
興味津々になってスマホ画面を見ている三人のイケメンに、慌てて声をかけた。
「ん? どした?」
「あのさ、一番最初に芹沢に読んでほしいから。……その後でもいい?」
引きつった顔で俺がお願いすると、三人はまったく同じ言葉を示し合わせたように言った。
「「「かわいい〜〜」」」
おい、お前ら。
「ば、ばかにしてねぇ……?」
「してねぇって。俺らがそういうんじゃないってわかるっしょ?」
三人の笑顔がまぶしくて、目眩がしそうになりながらも肯定してうなずいた。それぞれタイプの違うイケメンたちが、俺を見てにやにやしている。
「芹沢はばかにするけど、鈴木はしないよ」
竹内の言葉に、うんうんと佐伯と岩崎が意地悪に微笑んでいた。
「……芹沢のこともばかにすんなよ」
なんたって芹沢は、一番輝く特別な太陽なんだから。むっとした顔をしていると、三人は一瞬真顔になり、
「「「かわいい〜〜」」」
と俺の頭を順番に撫でてくる。いや、だからなんでそうなんの。
結局、芹沢がギリギリにやってきて、残念ながら小説を見せられなかった。二時限目前の休み時間、ようやく話しかけようと椅子から腰を浮かしたところで、クラスの女子たちが芹沢の隣を占領してしまう。
完全にタイミングをのがした。彼女たちをかき分けて、芹沢を奪う気力もない。
楽しそうに女子と話す芹沢。俺は教室の隅っこで、そんな芹沢の姿にこっそりと見とれていた。
やっぱ今日もかっこいいわ~、芹沢。
「今日の芹沢、なんか醤油の匂いしない?」
「あ、わかった? 俺、香水、醤油に変えたから」
「ねぇ、ほんとうざい〜!」
「てかごめん。用事あるから行くわ」
「えー……!」
ブーイングする女子を振り切ってどこに行くのかと思えば、芹沢はずんずんとこちらに向かってきた。
「鈴木! ワッツアップメーン!」
声を落とせ、芹沢。頼むから俺を巻き込んで目立つな、芹沢。
今日も芹沢は120%陽キャだ。一瞬、逃げ出そうと思ってしまったけれど、風邪で弱った芹沢を思い出したら、ギリ許せるような気がした。あの時のプリン食べる芹沢、かわいかったな……。
「小説、進んだ?」
「あっ、そのことなんだけどさ! 芹沢、俺――!」
喜々として芹沢に報告しようとした時、ふいに黒い感情が心に広がった。
「ん?」
芹沢はまるで非の打ち所がない笑顔を俺に向けてくる。
俺がBL小説を書き上げようが何をしようが、芹沢にとってはそんなに嬉しいことじゃないかもしれない。急に不安な気持ちがよぎり、冷静になって言葉を吐き出した。
「き、昨日完成したんだ、アレが……」
「小説!? マジで!? すげぇ!」
芹沢のテンションの高さに驚いていると、芹沢は俺の肩を抱き、耳元でこっそりとささやく。
「今すぐ読みたい。ふたりっきりになれるとこ、行こ」
あー、だめだ。俺、芹沢になら抱かれてもいいかも……。
いつも昼飯を食べている三回の空き教室で、完成したBL小説を芹沢に読んでもらった。待っている間、妙に緊張して何度も唾を飲み込んでしまう。
「……ハッピーエンドだ」
ぜんぶ読み終えた芹沢が、ぽつりとつぶやいた。
「なんか……感動だわ。こいつらが両想いになったのうれしすぎる。てか、ほんとすげぇよ、鈴木」
じわじわとうれしさが込み上げてきたけれど、顔には出さないように眉間に力を入れる。
「まだ初稿……えっと、最初の段階だから、推敲しないといけないんだけどさ」
いつになく真面目な顔をして、芹沢が俺を見据える。
「鈴木がたくさん悩んで苦しんで、がんばって書いたものがこうして形になってなってんのってマジですごいことだかんね? わかってる?」
指先が震えた。息を呑んだ俺に優しく微笑んで、芹沢が言葉を続ける。
「鈴木の小説が読めてよかった。俺が鈴木の『ハジメテ』の読者になれて本当によかった。ありがとう、鈴木」
真摯な言葉に胸を打たれ、思わずうつむいた。ぎゅっと握った手の甲に、ぽたぽたと水滴が落ちる。気づいたときには目から涙があふれ出ていた。芹沢の視線が俺に向かっているのを、見なくても感じていた。
「……わ、悪い。急に泣くの、キモいよな……」
芹沢は「キモくないから」と怒ったように言い、俺の隣にぴったりと寄り添って、背中をさすってくれた。その手の優しさが、ますます涙を誘う。
「な、なんかうれしくて。芹沢にそんな風に言ってもらえて」
「うん」
「い、一年のとき……、腐男子だって言ったら、友達に引かれたんだ。だから、安易に好きなことを好きって言っちゃだめなんだって思った。二年になってからはずっと隠してたし、わかってもらえないくらいならひとりでいいって思ってた。だって、好きなもんは好きだから」
「うん」
「でも、芹沢にあのノートのことがバレて、芹沢とBLのこと話せるようになって……」
「うん」
「芹沢は堂々と腐男子だって言える強い人だから、そんな芹沢にそんなこと言われたら、なんか……すげぇうれしいよー、俺ー……」
込み上げる気持ちを抑えきれない。芹沢が小さく笑って、俺の背中をごりごりとさする。
「小説書き上げられたのもうれしいし、芹沢に読んでもらえたこともうれしいし、芹沢とBLの話できんのもすげぇうれしい。さっきも佐伯たちが、俺がBL小説書いてるって知っても、そのまんまでいてくれて……なんかそういうのほんとにだめだ……」
涙が止まらない顔で、芹沢を見上げた。
「うれしい。今、ここに、俺の隣に、芹沢がいてくれて、すげぇすげぇうれしい」
芹沢は喉仏を上下させ、困ったように言葉をなくす。少しだけ怖くなったけれど、でもすぐに大丈夫だと思えた。芹沢だから、きっと受け止めてくれる。
「俺も、うれしいよ、鈴木」
ほら、やっぱり。
いたずらっこな笑みで、芹沢が片眉を上げる。
「あのさ、こんなこと言うのは絶対に不謹慎なんだけどさ」
「え……?」
「朝から鈴木のために煮物作ってきた。この前のリベンジってことで」
思いも寄らない芹沢の言葉に、涙は止まった。煮物のリベンジをしたから、今日の芹沢はかすかに醤油の匂いがするのだ。
「煮物王に?」
「俺はなる!」
ひとしきり笑いあった後、どちらからともなく見つめ合う。
何もかもどうでもよくなって、ただひとり、芹沢だけが目の前にいてくれた。芹沢の黒くて綺麗な瞳と視線が絡み合う。だんだんふたりの心がひとつになっていくみたいな不思議な感覚がした。
「鈴木、鈴木、すずき、すずき、すずき、すずき」
「……ははっ、呼びすぎだって」
笑っている間に、芹沢の顔が近づいた。涙で濡れた頬を撫でられ、吸い寄せられるように顔を寄せて、自らの唇を芹沢の唇に押し当てる。そうしない理由が見つからなかった。
初めて感じる他人の唇の柔らかさ。芹沢の手が俺の腰に回り、もっと体ごと引き寄せられた。角度を変えて芹沢が口づけてくるのを、ただ自然なこととして受け入れる。
俺、芹沢とずっとこうしていたいかも……。
その時、チャイムが鳴った。
……え?
はっとして芹沢の胸を押す。途中でキスを止められた芹沢は怪訝そうな顔で、「鈴木?」と俺の名を呼ぶ。
「ま、待って。何してんの、俺ら……」
よくあるBL漫画のシーンで、言葉もなく、まるで磁石みたいにキスをするふたりに憧れながらも、現実にはそんなこと起こるはずがないって思ってた。でも、実際に起こってしまった。俺と芹沢の間で。
「何してんのって、キスだろ」
「やっ……やばすぎるだろ! えっ、待って、無理、何してんのほんとに」
全身から血の気が引いて、慌てて芹沢から距離を取った。
「も、もしかして今、俺って無意識に芹沢に合意のないキスしてた!? 最低じゃね!?」
「いや、合意しまくってたから平気だし、なんなら俺が先にキスした」
「それはそれでだめだろ!」
動揺している俺を尻目に、芹沢はひどく冷静だった。
「落ち着けって、鈴木」
「だってチャイムなってるし、授業遅れるし、キッ、キスしちゃったじゃん!」
「サボればいいだろ。なぁ、いいから、続きし――」
伸びてくる芹沢の手を、ばっと振り払う。
「逆になんでそんな落ち着いてんの!? 俺、ファーストキスなんだけど!?」
一瞬、目を丸くした芹沢は、ゆっくりと口角を上げた。
「そっか」
「にやにやすんなよ、せりざわぁ!」
そりゃあ、言うまでもなく、芹沢のほうが経験豊富だろう。芹沢の彼女と噂されていた女の子の名前も何人か知っている。だけど、そんな芹沢と違って、俺はまったく免疫がないのだ。
「あのさ、鈴木――」
「なかったことにしよ! なっ? そうしよ!」
「………………は?」
芹沢にぎろりと睨まれても、引き下がるわけにはいかなかった。
「忘れて! 1、2のポカン! よし、忘れたね!? 忘れた! 忘れたよな!?」
「忘れるわけな――」
「お昼、煮物楽しみにしてるから! ほら、授業、行こう! 芹沢!」
無理やり芹沢を教室まで引っ張って行く。チャイムが鳴ってから結構たっていたが、幸運なことにまだ教師は来ていなかった。
額に浮かんだ汗を袖で拭い、自分の席に座って深呼吸をする。
忘れた。俺は忘れた。
その間も、芹沢がめちゃくちゃこちらを睨んできていることは、わかっていた。俺だってあんなことになるなんて思いもしなかったのだ。
だって、あんなの。あれは、あんなのは。
まずいて、芹沢。
「……か、書けた」
合計5万字。初めて最後まで書いたBL小説。うまく書けたかどうかはわからない、だけど――。
「書けた! 書けた! 書けたーー!」
誰もいない自室のベッドの上でばたばたと喜びを噛みしめると、すぐに芹沢の顔が浮かんできた。
「せ、芹沢に連絡……!」
ラインのメッセージを書いている途中、はたと動きを止める。ラインじゃなくて、直接、芹沢の顔を見て言いたかった。
「早く明日になんねーかなぁ……」
少しでも早く芹沢に会いたい。
にやけた顔でベッドに寝転び、いつの間にか芹沢の存在が特別なものになっているのを感じていた。芹沢となら大好きなBLを分かち合える。
そう思う一方で、あっちも同じように感じてくれるとは限らないともう一人の自分が言う。わかってるよ。ちゃんとわきまえなければ――。
俺はどこにでもあるような石で、芹沢はみんなの太陽だ。
顔を引き締め、無言で天井を見つめた。けれど、すぐに頬が緩んでしまう。明日、芹沢はどんな顔をするのだろう。
***
次の日、張り切りすぎていつもより早く教室に着いてしまった。
芹沢はまだ登校していないようだ。そわそわと昨日書いた小説を読み返していると、佐伯と竹内と岩崎が「はよー、鈴木」と近くにやってくる。
「みんな、おはよう。てか岩崎、今日は早いね。柔道部の朝練ナシ?」
「そう。鈴木も来んの早くね?」
「ああ……うん、ちょっとね……」
芹沢に会いたくて待ちきれなかった、とは言えるはずがなかった。苦笑を返すと、人懐っこい笑みを浮かべた佐伯が俺の前の席に座る。
「ずっと気になってたんだけど、もしかして鈴木って小説書いてんの?」
「それ、俺も気になってた」
「俺も」
佐伯と竹内と岩崎の視線が俺に集中し、ドキドキと心臓が鳴った。以前までの自分だったら、ぜったいに言わなかっただろう。でも、今は……。住む世界が違くて、イケメンで、何もかも持っているような陽キャの彼らが、どんな人間なのか少しは知っている。
俺は意を決して顔を上げ、こくりとうなずいた。
「やっぱそうなんだ!」
「すげぇじゃん」
「芹沢には読ましてんだろ? なぁ、俺らも読みたい」
「え、でも、……び」
「び……?」
その先を言うのはさすがに抵抗があった。一年前についた心臓の古傷がずきりと痛んだが、おずおずと彼らを見上げて言う。
「BLだよ?」
三人はきょとんと目を瞬かせたあと、それぞれが爽やかな笑顔を浮かべた。
「モーマンタイ」と竹内。「芹沢に何度も読まされてるし」と岩崎。「意外と好きだよ、俺らも」と佐伯。みんなの言葉に思わず身を乗り出した。
「……えっ、ほんとに!?」
「うん。君たちほどの熱量はないからあんま言わないけど。ほら、あれじゃん? めちゃくちゃBL好きな人の前でにわかすんの申し訳ねぇじゃん?」
「そ、そんなの関係ないって!」
彼らもBLを読んでいたことを初めて知った。ここにも同士がいるんだとうれしくなって、ちょっとだけ泣きそうになりながら彼らの前にスマホを差し出す。
「よかったら、よ、読んで……」
「おー!」
「あ、やっぱごめん、待って!」
興味津々になってスマホ画面を見ている三人のイケメンに、慌てて声をかけた。
「ん? どした?」
「あのさ、一番最初に芹沢に読んでほしいから。……その後でもいい?」
引きつった顔で俺がお願いすると、三人はまったく同じ言葉を示し合わせたように言った。
「「「かわいい〜〜」」」
おい、お前ら。
「ば、ばかにしてねぇ……?」
「してねぇって。俺らがそういうんじゃないってわかるっしょ?」
三人の笑顔がまぶしくて、目眩がしそうになりながらも肯定してうなずいた。それぞれタイプの違うイケメンたちが、俺を見てにやにやしている。
「芹沢はばかにするけど、鈴木はしないよ」
竹内の言葉に、うんうんと佐伯と岩崎が意地悪に微笑んでいた。
「……芹沢のこともばかにすんなよ」
なんたって芹沢は、一番輝く特別な太陽なんだから。むっとした顔をしていると、三人は一瞬真顔になり、
「「「かわいい〜〜」」」
と俺の頭を順番に撫でてくる。いや、だからなんでそうなんの。
結局、芹沢がギリギリにやってきて、残念ながら小説を見せられなかった。二時限目前の休み時間、ようやく話しかけようと椅子から腰を浮かしたところで、クラスの女子たちが芹沢の隣を占領してしまう。
完全にタイミングをのがした。彼女たちをかき分けて、芹沢を奪う気力もない。
楽しそうに女子と話す芹沢。俺は教室の隅っこで、そんな芹沢の姿にこっそりと見とれていた。
やっぱ今日もかっこいいわ~、芹沢。
「今日の芹沢、なんか醤油の匂いしない?」
「あ、わかった? 俺、香水、醤油に変えたから」
「ねぇ、ほんとうざい〜!」
「てかごめん。用事あるから行くわ」
「えー……!」
ブーイングする女子を振り切ってどこに行くのかと思えば、芹沢はずんずんとこちらに向かってきた。
「鈴木! ワッツアップメーン!」
声を落とせ、芹沢。頼むから俺を巻き込んで目立つな、芹沢。
今日も芹沢は120%陽キャだ。一瞬、逃げ出そうと思ってしまったけれど、風邪で弱った芹沢を思い出したら、ギリ許せるような気がした。あの時のプリン食べる芹沢、かわいかったな……。
「小説、進んだ?」
「あっ、そのことなんだけどさ! 芹沢、俺――!」
喜々として芹沢に報告しようとした時、ふいに黒い感情が心に広がった。
「ん?」
芹沢はまるで非の打ち所がない笑顔を俺に向けてくる。
俺がBL小説を書き上げようが何をしようが、芹沢にとってはそんなに嬉しいことじゃないかもしれない。急に不安な気持ちがよぎり、冷静になって言葉を吐き出した。
「き、昨日完成したんだ、アレが……」
「小説!? マジで!? すげぇ!」
芹沢のテンションの高さに驚いていると、芹沢は俺の肩を抱き、耳元でこっそりとささやく。
「今すぐ読みたい。ふたりっきりになれるとこ、行こ」
あー、だめだ。俺、芹沢になら抱かれてもいいかも……。
いつも昼飯を食べている三回の空き教室で、完成したBL小説を芹沢に読んでもらった。待っている間、妙に緊張して何度も唾を飲み込んでしまう。
「……ハッピーエンドだ」
ぜんぶ読み終えた芹沢が、ぽつりとつぶやいた。
「なんか……感動だわ。こいつらが両想いになったのうれしすぎる。てか、ほんとすげぇよ、鈴木」
じわじわとうれしさが込み上げてきたけれど、顔には出さないように眉間に力を入れる。
「まだ初稿……えっと、最初の段階だから、推敲しないといけないんだけどさ」
いつになく真面目な顔をして、芹沢が俺を見据える。
「鈴木がたくさん悩んで苦しんで、がんばって書いたものがこうして形になってなってんのってマジですごいことだかんね? わかってる?」
指先が震えた。息を呑んだ俺に優しく微笑んで、芹沢が言葉を続ける。
「鈴木の小説が読めてよかった。俺が鈴木の『ハジメテ』の読者になれて本当によかった。ありがとう、鈴木」
真摯な言葉に胸を打たれ、思わずうつむいた。ぎゅっと握った手の甲に、ぽたぽたと水滴が落ちる。気づいたときには目から涙があふれ出ていた。芹沢の視線が俺に向かっているのを、見なくても感じていた。
「……わ、悪い。急に泣くの、キモいよな……」
芹沢は「キモくないから」と怒ったように言い、俺の隣にぴったりと寄り添って、背中をさすってくれた。その手の優しさが、ますます涙を誘う。
「な、なんかうれしくて。芹沢にそんな風に言ってもらえて」
「うん」
「い、一年のとき……、腐男子だって言ったら、友達に引かれたんだ。だから、安易に好きなことを好きって言っちゃだめなんだって思った。二年になってからはずっと隠してたし、わかってもらえないくらいならひとりでいいって思ってた。だって、好きなもんは好きだから」
「うん」
「でも、芹沢にあのノートのことがバレて、芹沢とBLのこと話せるようになって……」
「うん」
「芹沢は堂々と腐男子だって言える強い人だから、そんな芹沢にそんなこと言われたら、なんか……すげぇうれしいよー、俺ー……」
込み上げる気持ちを抑えきれない。芹沢が小さく笑って、俺の背中をごりごりとさする。
「小説書き上げられたのもうれしいし、芹沢に読んでもらえたこともうれしいし、芹沢とBLの話できんのもすげぇうれしい。さっきも佐伯たちが、俺がBL小説書いてるって知っても、そのまんまでいてくれて……なんかそういうのほんとにだめだ……」
涙が止まらない顔で、芹沢を見上げた。
「うれしい。今、ここに、俺の隣に、芹沢がいてくれて、すげぇすげぇうれしい」
芹沢は喉仏を上下させ、困ったように言葉をなくす。少しだけ怖くなったけれど、でもすぐに大丈夫だと思えた。芹沢だから、きっと受け止めてくれる。
「俺も、うれしいよ、鈴木」
ほら、やっぱり。
いたずらっこな笑みで、芹沢が片眉を上げる。
「あのさ、こんなこと言うのは絶対に不謹慎なんだけどさ」
「え……?」
「朝から鈴木のために煮物作ってきた。この前のリベンジってことで」
思いも寄らない芹沢の言葉に、涙は止まった。煮物のリベンジをしたから、今日の芹沢はかすかに醤油の匂いがするのだ。
「煮物王に?」
「俺はなる!」
ひとしきり笑いあった後、どちらからともなく見つめ合う。
何もかもどうでもよくなって、ただひとり、芹沢だけが目の前にいてくれた。芹沢の黒くて綺麗な瞳と視線が絡み合う。だんだんふたりの心がひとつになっていくみたいな不思議な感覚がした。
「鈴木、鈴木、すずき、すずき、すずき、すずき」
「……ははっ、呼びすぎだって」
笑っている間に、芹沢の顔が近づいた。涙で濡れた頬を撫でられ、吸い寄せられるように顔を寄せて、自らの唇を芹沢の唇に押し当てる。そうしない理由が見つからなかった。
初めて感じる他人の唇の柔らかさ。芹沢の手が俺の腰に回り、もっと体ごと引き寄せられた。角度を変えて芹沢が口づけてくるのを、ただ自然なこととして受け入れる。
俺、芹沢とずっとこうしていたいかも……。
その時、チャイムが鳴った。
……え?
はっとして芹沢の胸を押す。途中でキスを止められた芹沢は怪訝そうな顔で、「鈴木?」と俺の名を呼ぶ。
「ま、待って。何してんの、俺ら……」
よくあるBL漫画のシーンで、言葉もなく、まるで磁石みたいにキスをするふたりに憧れながらも、現実にはそんなこと起こるはずがないって思ってた。でも、実際に起こってしまった。俺と芹沢の間で。
「何してんのって、キスだろ」
「やっ……やばすぎるだろ! えっ、待って、無理、何してんのほんとに」
全身から血の気が引いて、慌てて芹沢から距離を取った。
「も、もしかして今、俺って無意識に芹沢に合意のないキスしてた!? 最低じゃね!?」
「いや、合意しまくってたから平気だし、なんなら俺が先にキスした」
「それはそれでだめだろ!」
動揺している俺を尻目に、芹沢はひどく冷静だった。
「落ち着けって、鈴木」
「だってチャイムなってるし、授業遅れるし、キッ、キスしちゃったじゃん!」
「サボればいいだろ。なぁ、いいから、続きし――」
伸びてくる芹沢の手を、ばっと振り払う。
「逆になんでそんな落ち着いてんの!? 俺、ファーストキスなんだけど!?」
一瞬、目を丸くした芹沢は、ゆっくりと口角を上げた。
「そっか」
「にやにやすんなよ、せりざわぁ!」
そりゃあ、言うまでもなく、芹沢のほうが経験豊富だろう。芹沢の彼女と噂されていた女の子の名前も何人か知っている。だけど、そんな芹沢と違って、俺はまったく免疫がないのだ。
「あのさ、鈴木――」
「なかったことにしよ! なっ? そうしよ!」
「………………は?」
芹沢にぎろりと睨まれても、引き下がるわけにはいかなかった。
「忘れて! 1、2のポカン! よし、忘れたね!? 忘れた! 忘れたよな!?」
「忘れるわけな――」
「お昼、煮物楽しみにしてるから! ほら、授業、行こう! 芹沢!」
無理やり芹沢を教室まで引っ張って行く。チャイムが鳴ってから結構たっていたが、幸運なことにまだ教師は来ていなかった。
額に浮かんだ汗を袖で拭い、自分の席に座って深呼吸をする。
忘れた。俺は忘れた。
その間も、芹沢がめちゃくちゃこちらを睨んできていることは、わかっていた。俺だってあんなことになるなんて思いもしなかったのだ。
だって、あんなの。あれは、あんなのは。
まずいて、芹沢。