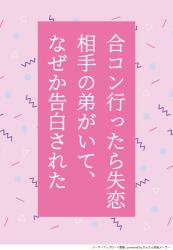芹沢が風邪をひいて、二日がたった。
芹沢のいない教室は、妙に静まっていて、明らかにみんなさみしそうだ。佐伯たちは「お葬式会場かよ」と笑っていたが、俺は笑えなかった。
芹沢が読んでくれなきゃ、せっかく続きを書いたBL小説も読者ゼロになってしまう。
その日の放課後。俺はマンションの玄関ホールで立ちすくんでいた。佐伯たちに教えてもらったマンションの部屋番号を押すか押さないか数分迷い、結局ラインを送ることにした。
『今、マンションの下にいるんだけど、会えそう?』
数秒ですぐに既読がついた。でも、返信がこない。
え、まさか社交辞令だった?
今日、見舞いに来たのは、芹沢のラインがきっかけだった。
一日目は『プリンが食べたい』だの『暇』だの、うるさいくらいたくさんのラインが来ていた。でも、二日目には何もメッセージが来なくなって、そして今日のラインだ。
『鈴木に会いたい』
昼休み、俺のスマホに送られてきた、たった7文字。そのメッセージに、俺はいつもの芹沢とは違う何かを感じ取っていた。
――あの、……よかったら放課後、芹沢のお見舞い行かない?
恐る恐る俺が誘うと、佐伯も、岩崎も、竹内も、みんなまるで示し合わせたかのように笑顔で言った。
「「「鈴木だけで行ったほうが、絶対喜ぶ」」」
陽キャ一軍たちよ……そう言っていたではないか……。
なのに、ラインの返信がこないのはいったいどういうことだ。だいたい、俺だけがお見舞いに来て喜ぶはずがない。どうしてあの時の俺は、何も疑問に思わなかったのか。
あれもそれもこれも、佐伯たちの無駄に説得力のある顔面偏差値の高さが問題なのだ。
くっそ、一軍連中め……。
だんだん不安になってきた俺は、次のラインを送った。
『ポストにプリントだけ入れておくから。あとで受け取って。お大事にな、芹沢』
このラインも既読にすらならなかった。やっぱり家まで来たのは、やりすぎだったかもしれない。少しだけ落ち込みつつ、プリントを芹沢のポストに入れようとしたところで、エントランスの自動ドアが開く音がした。反射的に振り返った先に、マスクをしたイケメンが立っている。
「せ、芹沢!?」
「……鈴木、マジで来てくれたんだ」
風邪のせいか、少しかすれた芹沢の声。芹沢は上下グレーのシンプルなスウェットパジャマを着ていた。急いで来てくれたらしく、足元は裸足にサンダルだし、肩で苦しそうに息をしている。
俺に会うために走ってきてくれたのかも……、なんて一瞬でも思ってしまった自分に言い聞かせる。身の程をわきまえろ、凡人が。
どこにでもいるようなモブの俺とは違う。やっぱ今日もかっこいいな~、芹沢は。
具合が悪くたってなんだって、芹沢の格好良さはどんな時も失われない。
「鈴木?」
うっとりと見とれている自分に気づき、慌てて手に持っていたプリントを目の前に掲げた。
「み、見舞いのついでに、プリント持ってきた。……芹沢が困るかなと思って」
「わざわざごめんな。ラインで画像送るだけでもよかったのに」
「あ、そっか……その手があったか」
完全に思考から抜け落ちていた。軽い衝撃を受けていると、芹沢は「来て、鈴木」と呼ぶ。
エレベーターに乗っている間、芹沢は俺に慎重な手つきで白いマスクを付けた。
「ごめん。俺もつけるけど、芹沢もつけて。風邪、うつしたくねぇから」
俺はいつもより熱い芹沢の指先を感じながら、こくりとうなずいた。
「ぐ、具合は……どう?」
「まだすげぇしんどい」
掠れた声から薄々感じ取っていたけれど、まだ本調子じゃないようだ。俺の相手をしている気力なんて、本当はないのかもしれない。
押しかけてしまった自分にますます自己嫌悪していると、そんな俺に許しを与えるかのように芹沢が目を細める。
「つーか来てくれて嬉しい」
本当に幸せそうに芹沢が言うから、顔が熱くなってしまった。だから身の程をわきまえろ、凡人モブが。
「上がって」
芹沢が家の玄関を開けた途端、めちゃくちゃいい匂いがした。さすが芹沢の家だとひとり心の中で感心する。
「マンションの場所すぐわかった?」
「あ、うん。佐伯たちが教えてくれたから」
「……そっか。昼飯、あいつらと食べてたって聞いたけど」
「……あー、うん」
佐伯か誰かが芹沢と連絡を取っていたのだろう。そもそも芹沢という強力な接着剤があったから、俺はあの一軍連中と一緒にいられた。芹沢がいない間、もちろん別々に食べるのだろうと思っていたら、佐伯たちは「鈴木、飯食い行くぞー」とまるでいつものメンバーのように扱ってくれたのだ。
なんだかすごく申し訳なくて、そしてすごく嬉しかった。
「あいつらと仲良くなんのはいいんだけど、俺より仲良くなんないで、鈴木」
芹沢の切れ長の目が、俺をまっすぐに射貫く。風邪をひいているからか、芹沢の目はどこか熱を孕んでいた。
「な、何を言って……」
「返事」
「……わかりました」
芹沢の圧に押されて、とっさに返事をしてしまう。きっと芹沢は風邪で正気を失っているんだ、そうに違いない。
「本気だからね、鈴木」
念を押すような言葉に、思わず息を呑んだ。絵に描いたような嫉妬深い攻めみたいだと思ってしまったけれど、心の声を聞かなかったことにして、芹沢のあとに続く。
「ここが俺の部屋で、これが俺のコレクション」
芹沢の部屋は予想どおり、とてもおしゃれだった。そして、芹沢の目線の先には白い木枠の大きな本棚が三つ並んでいる。
「……すごい。ほとんど俺が持ってるのと一緒だ」
「鈴木ならもっと持ってんだろ?」
「そ、そうだけど……」
俺が大好きな漫画や小説が、所狭しと棚に並んでいた。人それぞれに性癖があるというけれど、よっぽど俺と芹沢は趣味が近いらしい。
芹沢の本棚に夢中になっている間、芹沢が辛そうに咳き込み、はっとして俺は言った。
「横になってていいから! ほんとに寝て!」
「……ん」
芹沢の背中を押し、無理やりベッドに寝かせる。
「そうだ。プリン、食べられる……? コンビニのだけど」
来る途中にお土産として買ったプリンを鞄から差し出すと、芹沢がマスクの下で笑ったような気配がした。
「……鈴木が食べさせてくれんなら食べる」
芹沢システムならぬ、鈴木システムだ。いつもは食べさせてもらっていたけど、今日は俺が芹沢にプリンを食べさせている。それも、自室で寝ている芹沢に。
人生というのは本当にわからない。
マスクを少しだけずらした芹沢の口に、スプーンを差し入れる。芹沢はプリンを口に含むと、すぐにマスクを元に戻した。
「おいしい?」
「……めちゃくちゃうまい。沁みる」
マスク越しでも伝わる芹沢の嬉しそうな表情に、なんだか照れくさくなって視線を逸らす。
こんなことを考えるのはクズだ。そうわかっているのに、止められなかった。
「……どした、鈴木」
「あの……こんなこと言うのは絶対に不謹慎なんだけどさ……」
「いいって、言えよ」
「ほら、芹沢ってよく、自分のこと『健気攻め』って言ってんじゃん」
「うん」
「だからというか、なんというか……自称攻めが弱ってるとこってたまんねぇなと思いまして……」
芹沢が驚いたように目を見開く。
「もしかして、俺にキュンときてんの?」
「……はい、大変申し訳ごじゃ、い、ません」
俺が深く頭を下げると、
「鈴木って、追い詰められるとみやびに噛むよな」
そう言って芹沢が苦笑する。
「怒ってない……?」
「なんで怒んだって、むしろ――」
「……むしろ?」
その言葉の先は聞けなかった。芹沢は俺の手首を掴み、「プリン、止まってる」と催促する。なんだか、話を逸らされたような気がするけれど、言われるがままプリンをまた芹沢の口にせっせと運んだ。
芹沢が俺の手首を掴んでいる状態で、もう一度スプーンを頬張る。この様子だと自分で食べたほうが断然早い。でも、病人相手なので言わなかった。
「プリン、うまかった。残りは後で食べる」
うん、とうなずいて、半分残ったプリンはふたをしてテーブルの上に置いた。芹沢の息づかいが荒い。少し動いて疲れたのかもしれない。
「ね、熱は……?」
触った芹沢のおでこは、まるで燃えるように熱くて、心配な気持ちが加速した。
「きもちー……鈴木の個性、天然冷えピタじゃん」
「……全然嬉しくないんだけど」
「ヒーロー名、天然冷えピタ鈴木でいい?」
「そのまんまだろ、もっとひねれよ……」
少しだけ考えた芹沢がぽつりとつぶやく。
「クールりんりんツリー」
「やっぱ、天然冷えピタ鈴木でいいわ」
少しだけ笑った芹沢が、「ここも冷やして」と首に俺の手を持っていく。汗ばんだ肌、上下する喉仏、少しだけ見えた鎖骨。芹沢のすべてが色っぽくて、なんだか急に居心地が悪くなってしまった。
「……えーと、あれだ、あのー、ね、熱、測った?」
「38.5」
「病院は?」
「昨日、行った。薬飲んでたら治るってさ」
天然冷えピタ鈴木としての仕事を全うするために、芹沢の頬にもう片方の手を添えた。芹沢はとても気持ちよさそうに目を閉じている。
どれだけそうしていたのだろう。外はすっかり日が落ちてしまった。うとうととし始めた芹沢に遠慮しながら、耳元でつぶやく。
「じゃあ、俺はそろそろ帰――」
腰を浮かそうとした体勢のまま、急に伸びてきた芹沢の手に引っ張られた。「あ」と声が漏れた瞬間には、芹沢に抱きしめられていてぎょっとする。
「せ、芹沢……!?」
「……帰んないで、鈴木。朝までここにいて」
「は!?」
耳元に芹沢の低い声が響く。
「ひとりにしないで」
「ひとりにって……お、親御さんは?」
「母親は夜勤でいない。姉貴は大学の集まり。泊まりだから昨日からいない。あと、親父はもともと単身赴任」
「え、……まさか今日、芹沢ひとり?」
「うん」
「そ、そんな……」
俺の背骨に芹沢の熱っぽい手が回った。
「だから、ひとりにしないで」
いつもの軽口にも、冗談にも思えなかった。俺には本当のSOSに聞こえたのだ。
「…………わかった。いいよ」
自分でお願いしたくせに、ワガママボーイ芹沢は怒ったように眉根を寄せた。
「……は?」
俺は芹沢に抱きしめられながら、語気を強める。
「ひとりにできるわけないだろ。そんなに辛そうなのに」
***
そのあと、母さんにすぐ電話し、すべてを話して協力を求めた。物わかりのいい母さんは『友達は大事にしなさい』と二つ返事で了承してくれた。でも、なんとなく『この子にお友達いたのね、あー本当によかった!』という雰囲気を感じ取ったのは俺の気のせいだと思いたい。
「母さん直伝、何の変哲もない鈴木家のおかゆです」
ビデオ通話で繋いだ母さんの指示により、なんとか夕飯は作れた。ただの卵がゆだったけれど、芹沢は食べ終わったあと、ひどく感激したように言う。
「今まで食べた中で、一番うまい」
普通に褒めすぎだから、芹沢。
「ほら、芹沢。もう無理しないで、寝ろって!」
「でも鈴木の風呂とか、洗い物とか、お持てなしのダンスとか、ふたりでSwitchとか……」
「おもてなしはぜんぶいらないって!」
ワガママボーイはどうした、芹沢。
その後、芹沢をようやくベッドに寝かし、せっせと布団を整える。
「命令だから、マジで寝て!」
「……じゃあ、鈴木もここで一緒に寝ろよ」
ワガママボーイ復活早すぎだろ、芹沢。
「お願い、鈴木」
マスクをした芹沢が、捨てられた子猫のような瞳で見つめてくる。さすがに図体がデカすぎるけれど、血筋は争えない。俺のばあちゃん家には、保護した野良猫が四匹もいるのだ。
「…………………わかった」
いそいそとベッドの中に入り、天然冷えピタ鈴木としての任務を遂行するべく、そっと頬に手を触れる。まだまだ熱い、芹沢の体。
「鈴木、うつすのやだから、あっち向いて」
「……はいはい」
ワガママボーイの命令どおり、反対方向を向いた瞬間、後ろから抱きしめられて、うなじに熱い吐息がかかった。さすがにこれはまずいだろう。慌てて文句を言おうとした瞬間、耳に芹沢の言葉が届いた。
「……鈴木の小説、はやく読みたい」
ちょっとだけ泣きそうになって、慌てて瞬きをした。そんなこと誰も言ってくれやしない。芹沢だけだ。
頭がくらくらして、やっぱ芹沢になら抱かれてもいい、そう思った。
待て待て、ナシナシ。今この状況でそれはやばすぎる。BLの神様、今のはナシでお願いします。
***
次の日の早朝。ピピピッと鳴った体温計を芹沢の脇の下から取り出し、俺は感嘆の声を上げた。
「熱、下がってる! やったな、芹沢!」
「鈴木先生の献身的な看病のおかげで」
「……ほんとにな」
昨夜のワガママボーイ加減は本当にひどかった。急いで帰り支度をしながら、芹沢に念を押す。
「今日も休めよ、芹沢」
「えー、鈴木と一緒に行きたい」
「だめだって。俺は一度家に戻ってから、学校に行くから。もう一回言っとくけど、芹沢はあと一日だけ休むこと!」
「えー……」
「返事」
「……はーい」
殊勝な顔でうなずいた芹沢をみて、「よし」とうなずいた。
「えっと、鍵閉めたら、その鍵はポストに入れるから」
「ん、オッケー」
「じゃあ、俺は行くから」
「なぁ、鈴木」
かばんを背負って、ドアノブに手をかけた俺に、芹沢が声をかけてくる。「なに?」と問いかけると、芹沢はイケメンがイケメンであるゆえんを見せつけるように、余裕のある仕草で軽く首を傾けた。
「朝帰りだな、俺のせいで」
マスクをしていたけれど、意地悪な芹沢の笑みがありありと想像できた。赤くなっていく頬をぜったいに認めたくなくて、平常心で返す。
「……だるいて、芹沢」
「あと、こんなこと言うのは絶対に不謹慎なんだけどさ」
ぜったい意地悪なこと言うつもりだろ、芹沢。
「鈴木の抱き心地、すげぇエロくてよかった」
芹沢の笑う声は聞こえなかったことにして、部屋の扉をきっちりと閉めた。
心臓の鼓動がうるさい。
明日になったら、きっともっと元気になった芹沢に会えるだろう。そうしたら、芹沢がいない間に書き溜めたBL小説を読んでもらって、それから芹沢システムで小説の続きを書いて、それから……耳元でこう言ってやる。
うざいて、芹沢。