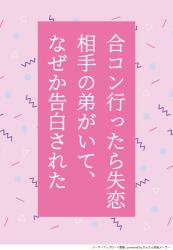あくびをかみ殺し、靴箱にシューズを入れている時、後ろに何やら気配を感じた。
「鈴木先生、おはようございます」
耳元にわざとらしいイケメンボイスが届く。呆れて振り返った俺の顔は、たぶん相当まぬけな顔をしていたと思う。
「……おはよ、芹沢」
芹沢がたまに鈴木先生と呼んでくるのは、めちゃくちゃ気まずい。けれど、最近はもう諦めていた。芹沢は俺がBL妄想をしていたノートのことを、いまだに誰にも言っていないみたいだし。
「ワッツアップ、メーン!」
いたずらっぽい笑みで、芹沢が俺の肩を抱く。絵に描いたような陽キャすぎてほんと無理。
「鈴木、なんか眠そうじゃね?」
「……ちょっとだけって思ってたんだけど、夜中までBL漫画読んじゃったから」
「なんだよ、起きてたの? 声聞きたかったのに」
昨日の夜、11時過ぎに芹沢からラインがきていたのを思い出す。
『もう寝た? ちょっと話せる?』
急に来たメッセージに、十分くらいどうしようかと部屋をぐるぐると歩き回っていると、芹沢からまたメッセージが来た。
『おやすみ、鈴木』
ほっとすると同時に、なんだか急に心臓が苦しくなって眠れなくなってしまった。で、救いを求め、BL漫画に手を伸ばしたのだ。
「ごめん……漫画に夢中になってた」
「それはわかる」
「ていうか芹沢は、朝から元気がよろしいようで……」
「うん。だって、調理実習あんじゃん。鈴木と料理できんの楽しみ」
芹沢が白い歯を見せて、爽やかに笑う。今日の調理実習のメンバーは俺と芹沢、佐伯、竹内、岩崎の五人だ。もしも間違い探しだったら、見た瞬間、すぐに答えがわかってしまうくらい、彼らの中で唯一俺だけが浮いている。もちろん非常に悪い意味で。
――鈴木は俺と一緒のグループね。
昨日、調理実習のグループ決めの時、まるで前から決まっていたことのように芹沢から告げられた。俺はたくさんのハテナマークを頭に浮かべつつも、「……あ、うん」としか反応できなかった。
ペアで柔道をする際も、美術の授業でお互いの顔を描くという際も、なぜか芹沢は俺を指名してくれた。おそらく、俺の書くBL小説をよっぽど気に入ってくれたのだと思うが、彼の本音は未だに聞けていない。
芹沢に肩を抱かれながら、廊下を歩く。すれ違う生徒たちみんなが芹沢に羨望のまなざしを向けているような気がして、なんだか居心地が悪かった。
「鈴木、どした?」
「いや、なんでもない。……あ、あのさ、芹沢は……」
――なんで俺にかまうの?
なんて、聞けるか。自意識過剰すぎるだろ。言葉の先を促すように、「なになに?」と芹沢が微笑む。
「えっと……こ、こんにゃく持ってきた?」
「持ってきた。鈴木はにんじん持ってきた?」
「うん」
あーだめだ。やっぱ今日もかっこいいわ~、芹沢。
鏡に映った自分の平凡な顔を見るたび、『この世のルッキズムがすべて死に絶えますように』と心の底から祈っている。だけど、芹沢の姿を見ると、ついついその格好良さにうっとりとしてしまう。
人間というのは矛盾した生き物だ。
「で、鈴木先生、あっちのほうの進捗は?」
芹沢にBL小説を書いていることがバレてからもう一週間がたつ。まだ最後まで書き上げていないが、前回挫折した文字数より先に進んでいた。芹沢のおかげと言っても過言ではない……気がする。
「……ちょっとだけ進んだ」
「えらすぎ。あとで読まして」
褒められたこと、そして続きを楽しみにしてもらえること。素直に芹沢の言葉に喜んでしまっている自分に気づき、赤い顔でこくりとうなずいた
俺が小説を書いている間に、芹沢が俺にご飯を食べさせるシステム。通称芹沢システムは昨日も一昨日(おととい)も――ていうかこの前からずっと作動していた。
ついこの間までボッチで昼飯を食べていたのに、気づけば先週からずっと一軍連中と昼飯を共にしている……。
どうしてこんなことになったのか、自分でもよくわかっていないけれど、初めて読者一号になってくれた芹沢の存在はなんだかとてもくすぐったい。
気を抜くと甘い優越感で満たされそうになる自分を叱りつけた。芹沢にとって、別に俺は特別でもなんでもないのだから。
「あ、鈴木がまた捕獲されてる」
後ろから、今日も顔面偏差値がばっちり高い佐伯が来た。佐伯の隣には、これまた可愛らしい後輩の彼女がいて、ふたりの手はしっかりと握られている。
そして次の瞬間、佐伯が「あとでね」と彼女の唇に短いキスをした。嬉しそうにはにかんだ彼女は、ぱたぱたと一年の教室へと走っていく。
え……どゆこと? 何、今の……。キ、キスしたよな……?
あまりの出来事に、心臓がバクバクと鳴っている。真っ赤な顔で固まった俺の肩をぐいっと引き寄せ、芹沢が苛立ったようにつぶやいた。
「佐伯ぃ……お前、鈴木になんてもん見せてんだよ。よそでやれよ」
「え? ただのチュウじゃん。舌入れたわけじゃあるまいし」
「鈴木にとってはちげーんだよ。なぁ、鈴木」
ここで「はい」というのも「いいえ」というのも正解じゃない気がした。俺はひどく曖昧な笑顔で「……はははは」とごまかす。
「俺の彼女かわいいっしょ~?」
「かわいいよ? かわいいけど、鈴木のほうがかわいいから」
やめろ、芹沢。
「手持ちの鈴木で戦おうとすんなし」
「は? 一番強ぇカードだろ」
いや、カードではない。さらに言うのならば、おそらく強くもない、最弱だ。陽キャの陽キャによる陽キャのための会話に心の中でツッコミを入れていると、佐伯はふと思い出したように芹沢に問う。
「てか、芹沢、こんにゃくは?」
「持ってきた」
芹沢、俺、佐伯。なぞの並びで廊下を歩いていると、また後ろから新たな陽キャがやってきた。竹内だ。
「おい芹沢ー、お前、ちゃんとこんにゃく持ってきた?」
「……持ってきたって」
芹沢の隣に来た竹内がからかうようにケラケラと笑っている間に、今度は柔道部の朝練が終わったらしい岩崎が、いつのまにか佐伯の隣に並んで芹沢の顔を見やる。
「こんにゃく持ってきたんだろうな、芹沢」
「だから、持ってきたって言ってんだろうが!」
「なんだよ。急にキレんなよ、カルシウム不足かよ。こんにゃく食えよ」
「こんにゃくにカルシウム入ってねーだろ。なぁ、鈴木」
「……たしか入ってる。板こんにゃく1枚に、コップ一杯の牛乳の半分くらい」
「微妙だわ~~、めちゃくちゃ微妙だわ~~」
そんなことより、180センチのイケメン一軍男子たちに囲まれる、平凡な俺の心情を慮れよ。
そわそわと落ち着かない俺にとどめを刺すがごとく、後ろから陽キャな後輩の女の子たちが、芹沢のところに集まってくる。
「遥人(はると)先輩、おはようございます!」
「はよー」
「あ、先輩。昨日言ってた、こんにゃく持ってきました?」
一瞬、真顔になった芹沢が、
「……みんな俺のこんにゃくだけ心配しすぎじゃね?」
と、俺の耳元でぼそっとつぶやく。
もうだめだ。堪えきれずに俺が笑い出すと、「鈴木がおもしれぇんなら別にいいか」と真面目な顔で、かばんからこんにゃくを取り出した。
「竹内、鈴木と一緒に撮って」
「いや、なんでだよ」
「芹沢ー、鈴木がツボにハマりすぎて、息できてねーじゃん」
「だからだって! 早く撮って!」
「こんにゃくに美白エフェクトかかってんのウケる」
げらげらと笑っている陽キャ一軍連中に見守られて、芹沢と俺とこんにゃくのスリーショットを撮られながら、俺は笑いすぎて呼吸困難になっていた。
写真を撮ってもらって満足したのか、芹沢がこんにゃくを片手に「行こ、鈴木」と綺麗な瞳を細めて笑う。……俺、こいつになら抱かれてもいいかも。
廊下を歩いている最中、ふと正気に戻った。
やっぱりおかしい。どうして俺は芹沢にぴったりと肩を抱かれて、陽キャたちに囲まれているんだろう。
三時限目と四時限目の調理実習が始まる際、芹沢は言った。
「俺、健気攻めだよ? たいてい攻めは料理うまいって決まってんだよ。な、鈴木」
芹沢の言葉に、俺は海よりも深くうなずいた。
「それはそう」
竹内と岩崎が呆れたような表情を浮かべたと同時に、佐伯が「これは期待大」と茶化すように笑った。
「まかせろって。煮物王に俺はなる」
それから十分後。
ばっちり準備したイケメン陽キャ軍団は、みんなエプロンが似合っていた。中でも一番芹沢のエプロン姿が格好よくて、しばらく見とれてしまったのは内緒だ。(芹沢は俺のエプロン姿を「似合う似合う」としきりに言っていたが、無視をした)
芹沢は本当に煮物王になってしまうのかもしれない、そう思った矢先。
「ふっ、おもしれーコンニャク」
「ちゃんと掴めよ、芹沢ー」
「なにが煮物王だよ、芹沢ー」
芹沢は完全に見かけ倒しで、彼の手からこんにゃくは逃げていくばかりだ。そして……。
「ふっ、おもしれー大根」
「ぜんぶ繋がってんぞ、芹沢ー」
「ちゃんと切れー、芹沢ー」
不格好な大根を見つめながら、俺は運動も勉強も容姿だって完璧な男にも、苦手なものはあるのだと知った。
散々佐伯たちにからかわれた芹沢は、包丁をまな板の上に置いて、真顔で彼らを見やる。
「あのさ、あんまごちゃごちゃ言ってっと、方向性の違いでグループ辞めるよ?」
本気だか冗談だかわからない芹沢の言葉に、彼らは次々と「今すぐやめろ」「そもそもグループ入ってない」「だるいて、芹沢」とにやにやと笑って返す。
「鈴木ー、こいつらがちくちく言葉、言ってくる」
甘えた言い方でそう言い、芹沢は俺の肩に頭をのせてきた。
「健気攻めなのに、俺、料理ヘタクソなんだけど」
芹沢の言葉に、俺はざるの中の米を研ぎながらつぶやく。
「これからだって。攻めだってみんな練習してうまくなってんだから。それに、うまい煮物、みんなで食いたいじゃん。がんばろう、芹沢。煮物王になるんだろ?」
落ち込んでいる芹沢の頭を左手でぽんぽんと撫でてやると、芹沢は少しだけ困ったみたいに口角を上げた。それを見て、さぁっと血の気が引いていく。
やば、咄嗟に撫でてしまったが、キモかったかも……いや、キモすぎるだろ。
「ありがと、鈴木。元気出たわ」
「……そ、それはよかったでごじゃ、ります」
「またみやびに噛んでるし」
芹沢はずっとにやけたまま、また大根を切り始めた。
「めちゃくちゃ機嫌良くなってんじゃん、芹沢」
竹内の言葉に、ほっと安堵する。
よくわからないが、キモいとは思われなかった……らしい。
それから俺たちは慣れない料理に悪戦苦闘しながら、ようやくメニューを完成させた。
『炊き加減を間違えたちょっとべちゃべちゃのご飯』と、『鶏肉とこんにゃくが異様にでかくて、野菜が不格好な煮物』と『佐伯が整えた完璧なサラダ』だ。
「うまい。ほら、鈴木」
「ん……ほんとだ、うまい!」
サラダ以外、見た目はぜんぶやばかったけれど、味は最高だった。「もう一口」と芹沢に言われ、大きな口を開けていると、佐伯たちが「お前ら、ほんとにウケんだけど」と口元を押さえて笑いを堪えている。
俺ははっとして、口を閉じた。この一週間、芹沢システムに慣れきってしまっていたせいで、昼飯を自分で食べるという大事な人間の本能を忘れていたのだ。どんだけばかなんだよ、しっかりしろ。
「え、別によくね?」
芹沢がけろっと言ったところで、隣の班の女子たちが声をかけてきた。
「ねぇねぇ芹沢、こっち来て。うちらが作ったのも食べてよ」
芹沢はあっという間に彼女たちに両手を掴まれ、連行されていった。
「鈴木! 俺がいない間、ひとこともこいつらと話さないで!」
大声で言った芹沢に、ぽかんと口を開ける。同じように驚いていた佐伯は、しばらくして、
「何今のキモいセリフ」
とドン引いていた。
「そろそろ鈴木は、芹沢のこと殴っていいと思うぞ」
と、岩崎。
「で、鈴木は最近どう?」
と、竹内。
どうやら芹沢の言葉は完全に無視することに決めたらしい。
次の日。芹沢のスマホのロック画面が、爆笑している俺と、爽やかにイケメンらしく笑っている芹沢と、こんにゃくのスリーショットになっていたのは見ないフリをした。
だるいて、芹沢。