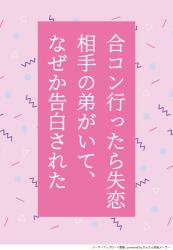やっぱ今日もかっこいいわ~、芹沢。
「はよ」
淡々と挨拶をして教室に入ってきた芹沢遙人に、クラスメイトたちが一斉に返事する。十人中十人いや……十人中二十人がイケメンだと答えるであろう彼は、今日も見目麗しい。
180センチを超える高身長に、まるでアイドルのような整った顔立ち。彼の近くに寄るとかすかに高そうな香水の香りがするが、おしゃれに無頓着な俺にはどこのブランドかさっぱりわからない。
ありきたりな言葉で要約すると、芹沢は『住む世界が違う人間』だ。
まぶしさから逃れるように視線を外し、いつものごとくメモアプリを立ち上げた。この一週間、執筆は止まったままだ。受けの心情がいまいち掴めない。またボツになるかもしれない……。
うんうんと頭を悩ませながら、妄想の世界にダイブしかけた、その時。
「鈴木」
いつものメンバーのところに行くのかと思いきや、芹沢はなぜか俺の机の前に来て、そしてなぜか俺を見下ろしていた。
「……鈴木。おい、鈴木。お前は鈴木のはずだ、しっかりしろ」
反応のない俺を見て、芹沢がつぶやく。俺、鈴木だっけ? そうだった……俺は鈴木。鈴木創。
ばかみたいな言葉を心の中で繰り返しながら、顔がいいクラスメイトを恐る恐る見上げた。
「あ、ごめん……ぼうっとしてた。芹沢、なんか用?」
クラス一の人気者である芹沢と話すのはこれが3回目だ。一回目はたまたま靴箱の前で鉢合わせした時の「おはよう」で、二回目は芹沢が落とした消しゴム拾った時の「鈴木、ありがとう」。
貴族に話しかけられた平民のような、妙な緊張感の中で、心臓が少しだけ早めに鳴っている。
「これ、鈴木の?」
ふいに目の前に差し出されたキャンパスノートを見て、俺の心臓は先ほどの比ではなく、狂ったように鳴り始めた。汗がどっと噴き出す。これはまずい。非常にまずい。
「昨日、選択授業あったじゃん? そん時、間違って俺の机に入れてなかった?」
「……入れてたかも」
「そっか、よかったわ。名前なかったけど、たぶん鈴木のだろうって――」
「なっ、中身読んだ?」
芹沢の言葉を遮って食い気味に問うと、芹沢はクラスの女子なら倒れそうなくらいの美しく冷たい微笑で、
「昼休み、三階の空き教室で待ってる」
と俺のノートを持って、いつものメンバーのところへ行ってしまった。
昼休み。訂正、地獄の昼休み。空き教室で、クラスで一番人気者の芹沢とふたりきり。
「これって小説?」
向かい合って座っている芹沢の尋問に、俺は生きた心地がしないまま答えた。
「……小説じゃなくて、プロット」
「プロット?」
「小説の前の段階っていうか、それを元に小説を書く的な……設計図みたいな感じ」
芹沢は「へぇ」と言いながら、俺がノートに書いた手書きの文字を興味深そうに追っている。
「金でもなんでも差し出すんで、みんなには言わないでもらえると助かる……」
どこに出しても恥ずかしい俺のBL妄想が詰まったノートの中身を頭に思い浮かべながら、俺は赤い顔で芹沢に懇願した。
「何それ、ちょっと傷ついたんだけど」
芹沢は少しだけ眉間に皺を寄せると、「誰にも言わねーし」とむっとしたように付け加える。
「ご、ごめん」
「なんか鈴木に誤解されてる気がする。俺、好きだよ」
「……え?」
「BL。腐男子だもん」
聞き慣れた単語が耳に届き、思わず身を乗り出した。
「ほんとに!?」
「うん」
「せ、芹沢、BL漫画読むの?」
「読む読む。小説も読む。自分でも持ってるし、時々姉貴の本棚から借りる時もあるよ」
「え……どの先生が好き?」
急に親近感が湧き、じっと芹沢を見上げた。芹沢は飄々とした様子で言葉を続ける。
「最近だとピーヒャラ松子先生がよかった。あと、小説だと石橋叩割先生」
「俺も好きー! めっちゃ好きなんだけど! 石橋叩割先生のは作家買いで、全巻持ってる!」
「やっぱ趣味一緒じゃん。鈴木が書いたコレも性癖ど真ん中だったから」
キャンパスノートを揺らしながら、芹沢が言った。爽やかな笑顔で最高に嬉しい言葉をぶつけられ、全身がどろどろに溶けそうになる。……俺、芹沢にだったら、抱かれてもいい。
「あ……ありがとう、ごっ、ごじゃ、ります」
「みやびに噛みすぎだろ」
けらけらと笑った後、芹沢はふと真面目な顔をして言った。
「年下攻め、いいよな」
「わ、わかる! 年下の攻めが生意気であればあるほどいいし、あがけばあがくほどいい!」
「解釈一致」
パンと右手でハイタッチを交わし、どちらからともなく笑った。まるで殴り合った後、わかり合えた不良たちのような……いや、その比喩があっているかどうかはわからないが、少なくとも俺と芹沢には、言葉にできないなんらかの絆が生まれた気がしていた。
「このノートに書いてあるプロット……?の小説は完成した?」
「まだ。六割、七割……くらいかな」
「マジ? 読まして」
ノリノリで笑う芹沢に見つめられ、そっと目を逸らす。
「でも……誰にも読ませたことないから」
「じゃあ俺が鈴木の『読者一号』だ」
さすがにそれはどうなんだろう。悩み始めた俺の背中を押すように、芹沢がまぶしい笑みを浮かべる。
「俺にちょうだいよ。鈴木の『読者一号』」
ぐっと覗き込んできた芹沢の綺麗な瞳に、戸惑う俺が映っていた。
「決め台詞、やば……」
「キュンときた?」
「ちょっと微妙……。『読者一号』が微妙。『俺にちょうだいよ、鈴木の “ハジメテ” 』とかのほうがいいかも。あ、『ハジメテ』はカタカナで」
「待って、エロい。さすが鈴木先生」
「……先生って呼ぶのやめて」
笑っている芹沢に、俺は大変申し訳ない気持ちで懺悔した。
「実は最後まで書き上げたことないんだよね、小説」
「え、そうなの?」
「うん……たいてい『これほんとにおもしろいんか病』を患って、途中で離脱しちゃうから……」
目下の悩みを素直につぶやくと、芹沢は切れ長の瞳をおかしそうに細めた。
「なおさら読みたくなった。鈴木のBL小説」
「……うぅ、でも」
「鈴木の“ハジメテ” くれんの? くれないの? どっちなんだい! 筋肉ルーレットスタート!」
イケメンな芹沢らしからぬ冗談に、ぶはっ、と噴き出し、そのままツボにハマってしまって俺はしばらく笑っていた。
「思いのほかウケたわ。ってことで、ちょうだい、鈴木のハジメテ」
そう笑う芹沢は、なんだかいつもより表情が柔らかい。
「……俺のでよければ。あげますけども」
もうヤケクソだった。それに、いつか誰かに読んでもらいたい、そんな欲望を持っていたこともたしかだった。
芹沢は俺が差し出したスマホのメモアプリを、静かに読み始めた。芹沢に読んでもらうなんて無謀としか思えない。心臓が痛いくらい鳴っていた。
もう無理。口から心臓出る。
芹沢は驚くような集中力であっという間に読み切ると、放心したようにぽつりとつぶやく。
「……めっちゃ続き気になるところで終わった」
「マジ!? ほんとに読める? ていうか、ちゃんと小説になってる? 受けに好感持てる? サブキャラありきたりじゃねぇ!?」
芹沢は作者のうざい質問にも、嫌な顔ひとつせず答えてくれた。ちゃんと小説になってる、受けめっちゃ好きだしかわいい、サブキャラも良い味だしてんね。そんな風に。
俺の中で芹沢の好感度が爆上がりしていた。なんていい読者……。
「続き書いて、今」
「い、今……?」
「そう今。Now」
初めて読んでもらえた高揚と、その読者一号が芹沢であることに、とてもドキドキしていた。
「たしかに今なら続き、……書けるかも」
手元に戻ってきたスマホに、急いで脳内の妄想を書き留めた。一週間も止まっていた受けの感情が、生き生きと動き出す。
急いで頭の中に浮かんだ言葉をアウトプットする。俺が指先で入力した文字を隣で追っていた芹沢が、やきもきするみたいに言った。
「見づらい。鈴木、ここ来て。ここなら俺も画面見えるから」
ここ、と指差された場所は、芹沢の足の間だった。
「早く」
「……え、でも、なんか変じゃない?」
「なんで? 変じゃないよ?」
芹沢の圧に押されるまま、彼の足の間に座った。やっぱり芹沢は足が長いとか、いい香りがするとか、芹沢の顔が近くてハズいとか、そんな煩悩に呑み込まれそうな俺を知ってか知らずか、芹沢が耳元で囁いてくる。
「鈴木、居心地悪くない?」
「……ない、けど」
俺が椅子から落ちないように、ぐいっと体を引き寄せて芹沢が言った。
「それでは鈴木先生、読者一号のために続きをお願いします」
「……はい」
そうだ、ハジメテの読者の要望には応えねばならない。
俺の腹に回る芹沢の手とか、俺の肩に乗る芹沢の整った顔とか、ミントの匂いのする息とか、初めて親以外の誰かに強く抱きしめられている感覚とか、そういうのは無視をして……。無視をして……。
「芹沢ー頼まれてた昼飯ー。って、え、何してんの?」
騒がしい足音が近づいてきたと思ったら、同じクラスの一軍連中、佐伯と岩崎と竹内が少しだけ面食らったみたいに俺たちを見つめていた。彼らは順番につぶやく。
「鈴木だー」
「芹沢に捕獲されてるし」
「お前ら、そんな仲良かったっけ?」
とても愛らしい呑気な笑顔をしているのが佐伯、その肩を抱いてからかうように笑っているのが岩崎で、怪訝そうにしているのが竹内だ。彼らはそれぞれ背が高く、もちろん俺より顔面偏差値がはるかに高い。
「今、交流を深めてるとこ」
耳元で芹沢が言い、背筋がぞくっとした。
「……芹沢の一方通行じゃなくて?」
竹内の疑問は、俺の疑問でもある。
「ちげーし。だよね? 鈴木。なぁ、そうだろ。そうだって言えよ」
「その言い方がすでに一方通行なんだけど」
佐伯がけらけらと笑い、近い席に腰を下ろす。それを合図に、岩崎、竹内も続いた。
「まあいいや。メシ食っていい?」
「どーぞどーぞ」
柔道部の太い腕を駆使し、岩崎が総菜パンの袋を開ける。「彼女が作ってくれたんだよねー」とノロケている佐伯は手作りの弁当、竹内は購買で売っているからあげ弁当を食べ始めた。和やかな昼休みだ。俺以外は。
「あのさ、芹沢」
完全に正気に戻った俺と、「ん?」と相変わらず距離の近い芹沢。
「俺もごはん、た、食べようかな? か、買ってこないと」
芹沢の腕から逃れようとしたのに、うんともすんとも言わない。なんて馬鹿力だ。
「大丈夫。鈴木の分も買ってきたって」
「俺らが、な?」
竹内のツッコミにへらへらと芹沢が笑った。
「金出したのはね、俺だからね。それはわきまえないと」
「ねぇ~~、当たり前のことをさも偉そうに言う~~。芹沢構文~~」
キャラ設定が謎な佐伯のセリフを聞き流し、芹沢は俺を抱きしめていない方の手で、竹内からビニール袋を受け取った。
今なら逃げられるかもしれないと腰を浮かせたけれど、逆にぐいっと引き寄せられ、さらに芹沢との距離がゼロに近づく。むしろ、ふたりでひとりだろ、これ。
「鈴木、どれがいい?」
「じゃあ、明太子おにぎり……」
「俺はサンドイッチにしよー。鈴木、ツナマヨあげる。俺、たまねぎ辛くて食べらんないから」
どうやら芹沢はイケイケな見た目に似合わず、口がおこちゃまのようだ。
「鈴木は俺が食べさせるから、続き書いて」
「どういう状況なん?」
「シュール過ぎ」
芹沢は丁寧におにぎりの海苔を巻き、口元に差し出してくる。もう何を言っても無駄なような気がして、俺はぱくりとそれを頬張った。
「おいしい?」
「おいしい……けどさ、やっぱ変じゃない?」
「変じゃないって」
おにぎりを咀嚼しながら、スマホをぎゅっと掴む。わからない、俺には何が正解なのか、わからない。
「鈴木、なんの労働させられてんの?」
「弱み握られてる系?」
「だめでーす。俺と鈴木だけの秘密でーす」
「嫌だったら、ガチで言って? こいつ、ワガママボーイだから」
「鈴木先生は集中してんだよ。話しかけんな」
続き続き、とせがんでくる読者一号の芹沢を無視できるわけもなく、小説を書きながら、彼が口元に運んでくるおにぎりをむしゃむしゃと食べた。案外、いいシステムかもしれない。
「鈴木にこうして食べさせてると、アレ思い出すなーアレ」
「なんだよ」
「牧場でウサギに餌あげるやつ」
高一の時に行った研修旅行のことだろう。去年は芹沢たちとは別のクラスだった。
俺もウサギに餌をあげたかったのに、なぜか俺の番になったら、ウサギはこっちを見もしなかった。
「芹沢、あのウサギにかわいいかわいいって、餌やりすぎてたもんな」
お前が原因か、芹沢。
「満腹になってるウサギもかわいかった」
「……なんか微妙にヤンデレを感じんだよなぁ」
「は? 俺は健気攻めだし」
芹沢の言葉に咳き込んでいると、不思議そうな顔で佐伯が「なんだよ、攻めって」と聞いてくる。
「いや、こっちの話」
「……どうせ、BLだろ。芹沢、腐男子だから」
芹沢が腐男子なのは今に始まったことではないらしい。顔面偏差値の高い彼らの顔を順番に見て、「ほへー」っと見とれていると、「こら、よそ見すんな」と芹沢に活を入れられた。
「手が止まってる。書いて」
「……ああ、はいはい」
「あとちゃんと食べて。鈴木、細すぎ」
芹沢の手が俺のあばらをするりと撫でる。びくっと少しだけ体が反応してから、今さらながら真実に気がついた。
こんな状況で書けるわけがない。