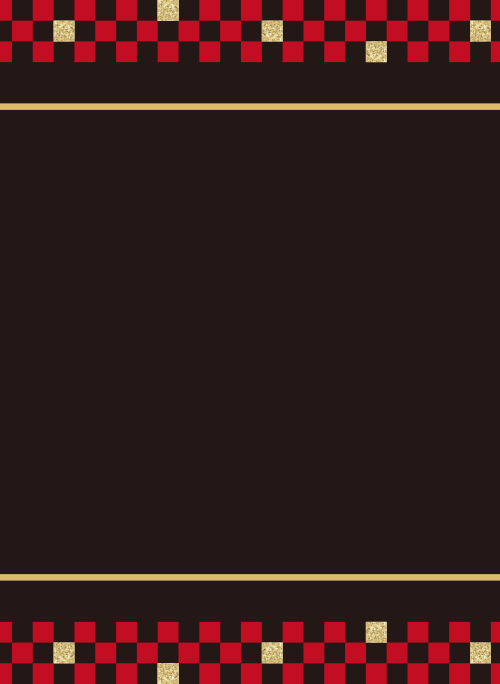「龍胆さま、助かりそうですか? その子」
雪は水を張ったたらいを持ち上げていった。水は、小梅の血で真っ赤に染まっている。
龍胆は傷口を針と糸で縫合しながら、「大丈夫さ」と言った。
「薔薇様にしては傷口が浅い。――殺す気はなかったのかもしれないね」
たらいの重さに耐えかね、雪はつまずく。それを支えたのは菫だった。
「雪お姉ちゃん。この水すごく美味しそう。飲んでもいい?」
「悪趣味にもほどがある!」
龍胆は菫をげんこつで殴る。菫は雪に「いじめられたー!」と泣きついた。
「菫ちゃん。これは飲み物ではないわ。それに、おくすりも混ざっているから、美味しくないはずよ」
「雪。もっとまともなあやし方はないのか?」
どいつもこいつも。龍胆は最後の縫い口を鋏で切る。
「その子ども、助けるのはいいが、どうするつもりだ」
すっかり忘れ去られた男の声がした。白木蓮が、刀を抱いたまま治療の順番待ちをしていた。
龍胆は傷の手当に慣れている。医者を呼べない今、唯一の頼りだ。
「朝廷に返すのか?」
「・・・返したら、間違いなく殺されるだろうな」
龍胆は静かに言った。雪は目を丸くする。
「なぜ・・・?」
「信用できないからだよ。――この子は賢い。賢すぎる駒は逆に使いづらい。薔薇を裏切り、長男についたつもりだろうが、この子はあのとき、朝廷からの命をなんの違和感もなく読んでいた。この子は長男にも見切りをつけ、朝廷の犬になるつもりだったのさ」
「あのまま、ご長男様のもとにいても、なんの旨味もないからですよ」
不意にかわいい声がした。小梅は目が覚めたようだった。
「龍胆さま。あなたと同じです。あなたは穢土で人斬りを命じられたが、次第に連絡が途切れてゆき、違う方に命じられて人を斬っていたでしょう。駄賃も安くなっていったはずです。・・・僕も同じこと。どれだけ尽くしても、薔薇さまは最後はトカゲの尻尾のように切り捨ててゆく。あの竜笛を奏でられるのは僕だけじゃない。奏者は大勢います」
「ではなぜ、朝廷についても殺されるのですか?」
雪が尋ねる。よしよしと小梅の頭を撫でる。生意気な子どもはうっとおしそうにその手を振り払った。代わりに龍胆が口を開く。
「朝廷は十六夜家自体を信用していない。都から離れて長い俺にはもうわからないが。十六夜家の勢力に朝廷は混乱している。小梅、おまえもなにか口約束で朝廷と手を組んだんだろうが、平気で反故にするのが政だ。ふふ、まだ子どもだな。詰めが甘い」
龍胆に笑われ、小梅はムッとする。菫が「いいこいいこ」と頭を撫でる。ついに小梅はブチギレた。
「僕はあなたがたのお世話になるつもりは、ありませんからっ!」
「おや。この猛吹雪の中、その傷で出ていったら死ぬぞ」
「このどら猫と共存などできませんっ!」
すると、菫が反応した。
動けないでいる小梅の上にまたがった。顔をずいっと近づけ、にやりと笑う。
「何を勘違いしているの? 子猫ちゃん。君はこれから僕の舎弟になるのですよ」
「しゃ、舎弟だと・・・!?」
大人たちは白木蓮の治療に夢中だ。小梅は冷や汗で布団を濡らす。
誰も聞いていないのをいいことに、菫は満面の笑みでニタァ・・・と笑う。瞳は青い。
「ずっと子分が欲しかったの。僕にも春が来ましたね、朝廷のことなんか忘れるくらい、たあっぷりかわいがってあげるから。楽しみにしててね」
「さ、させるか! どら猫め」
小梅は顔をそらして必死に平静を装う。
「僕にはあの笛があるんだ。おまえなんか、座敷牢に閉じ込めて二度と出られなくしてやるっ!」
「あ、言っておくが、笛は没収だよ」
龍胆は白木蓮の腕に包帯を巻きながら、なんでもないことのように言った。
「え?」
「あんな呪具、子どもが持っていいものではない。――ここでは、ただの『お子様』として生活していただく。よろしいかな? 小梅殿」
「返せっ! あれは僕のものだ!」
「・・・かえせ?」
龍胆はむっとして顔をこちらに向ける。白木蓮は「おい、途中だぞ」と言ったが、無視された。
菫と同じく布団に手を付けると、顔をずいっと近づける。
「どうやら、薔薇さまは大人へ対する敬意を教えていなかったようだ・・・。菫」
「はい」
――調教してやれ。
冷酷なお言葉。菫は元気よく「はいっ!」と返事をした。
「そんなっ!」
「言っておくがな、小僧」
白木蓮は静かに言う。
「この龍胆さんは元軍人で『鬼』と呼ばれていた男だ。礼儀に厳しい。猫に調教されてるほうがよほどマシだと思うがな」
「・・・・・・・っ!!」
小梅の目尻が、じわっと熱くなる。小梅は布団から飛び起きると、人畜無害そうな雪のもとへ走った。腹に抱きつき、わあっ! と大声で泣く。
「あらあら。どうしたの? じっとしていなきゃだめよ」
雪の穏やかな笑顔は、菩薩様に見えた。小梅はいい避難場所を見つけたと、龍胆と菫に舌を出す。
「いい度胸ですね、子猫ちゃん」
菫は黒い笑みを浮かべると、小梅の手を引いた。
「あら、どこへゆくの?」
「二階だよっ。二人でおままごとするんだぁ」
「怪我してるから、無理させちゃだめよ」
「はぁい!」
小梅はこれでもかと暴れたが、力で菫に勝てるはずもない。引きずられるようにして、二階へ連れて行かれる。
――小梅の悲鳴が響き渡るまで、あと五分。
雪は水を張ったたらいを持ち上げていった。水は、小梅の血で真っ赤に染まっている。
龍胆は傷口を針と糸で縫合しながら、「大丈夫さ」と言った。
「薔薇様にしては傷口が浅い。――殺す気はなかったのかもしれないね」
たらいの重さに耐えかね、雪はつまずく。それを支えたのは菫だった。
「雪お姉ちゃん。この水すごく美味しそう。飲んでもいい?」
「悪趣味にもほどがある!」
龍胆は菫をげんこつで殴る。菫は雪に「いじめられたー!」と泣きついた。
「菫ちゃん。これは飲み物ではないわ。それに、おくすりも混ざっているから、美味しくないはずよ」
「雪。もっとまともなあやし方はないのか?」
どいつもこいつも。龍胆は最後の縫い口を鋏で切る。
「その子ども、助けるのはいいが、どうするつもりだ」
すっかり忘れ去られた男の声がした。白木蓮が、刀を抱いたまま治療の順番待ちをしていた。
龍胆は傷の手当に慣れている。医者を呼べない今、唯一の頼りだ。
「朝廷に返すのか?」
「・・・返したら、間違いなく殺されるだろうな」
龍胆は静かに言った。雪は目を丸くする。
「なぜ・・・?」
「信用できないからだよ。――この子は賢い。賢すぎる駒は逆に使いづらい。薔薇を裏切り、長男についたつもりだろうが、この子はあのとき、朝廷からの命をなんの違和感もなく読んでいた。この子は長男にも見切りをつけ、朝廷の犬になるつもりだったのさ」
「あのまま、ご長男様のもとにいても、なんの旨味もないからですよ」
不意にかわいい声がした。小梅は目が覚めたようだった。
「龍胆さま。あなたと同じです。あなたは穢土で人斬りを命じられたが、次第に連絡が途切れてゆき、違う方に命じられて人を斬っていたでしょう。駄賃も安くなっていったはずです。・・・僕も同じこと。どれだけ尽くしても、薔薇さまは最後はトカゲの尻尾のように切り捨ててゆく。あの竜笛を奏でられるのは僕だけじゃない。奏者は大勢います」
「ではなぜ、朝廷についても殺されるのですか?」
雪が尋ねる。よしよしと小梅の頭を撫でる。生意気な子どもはうっとおしそうにその手を振り払った。代わりに龍胆が口を開く。
「朝廷は十六夜家自体を信用していない。都から離れて長い俺にはもうわからないが。十六夜家の勢力に朝廷は混乱している。小梅、おまえもなにか口約束で朝廷と手を組んだんだろうが、平気で反故にするのが政だ。ふふ、まだ子どもだな。詰めが甘い」
龍胆に笑われ、小梅はムッとする。菫が「いいこいいこ」と頭を撫でる。ついに小梅はブチギレた。
「僕はあなたがたのお世話になるつもりは、ありませんからっ!」
「おや。この猛吹雪の中、その傷で出ていったら死ぬぞ」
「このどら猫と共存などできませんっ!」
すると、菫が反応した。
動けないでいる小梅の上にまたがった。顔をずいっと近づけ、にやりと笑う。
「何を勘違いしているの? 子猫ちゃん。君はこれから僕の舎弟になるのですよ」
「しゃ、舎弟だと・・・!?」
大人たちは白木蓮の治療に夢中だ。小梅は冷や汗で布団を濡らす。
誰も聞いていないのをいいことに、菫は満面の笑みでニタァ・・・と笑う。瞳は青い。
「ずっと子分が欲しかったの。僕にも春が来ましたね、朝廷のことなんか忘れるくらい、たあっぷりかわいがってあげるから。楽しみにしててね」
「さ、させるか! どら猫め」
小梅は顔をそらして必死に平静を装う。
「僕にはあの笛があるんだ。おまえなんか、座敷牢に閉じ込めて二度と出られなくしてやるっ!」
「あ、言っておくが、笛は没収だよ」
龍胆は白木蓮の腕に包帯を巻きながら、なんでもないことのように言った。
「え?」
「あんな呪具、子どもが持っていいものではない。――ここでは、ただの『お子様』として生活していただく。よろしいかな? 小梅殿」
「返せっ! あれは僕のものだ!」
「・・・かえせ?」
龍胆はむっとして顔をこちらに向ける。白木蓮は「おい、途中だぞ」と言ったが、無視された。
菫と同じく布団に手を付けると、顔をずいっと近づける。
「どうやら、薔薇さまは大人へ対する敬意を教えていなかったようだ・・・。菫」
「はい」
――調教してやれ。
冷酷なお言葉。菫は元気よく「はいっ!」と返事をした。
「そんなっ!」
「言っておくがな、小僧」
白木蓮は静かに言う。
「この龍胆さんは元軍人で『鬼』と呼ばれていた男だ。礼儀に厳しい。猫に調教されてるほうがよほどマシだと思うがな」
「・・・・・・・っ!!」
小梅の目尻が、じわっと熱くなる。小梅は布団から飛び起きると、人畜無害そうな雪のもとへ走った。腹に抱きつき、わあっ! と大声で泣く。
「あらあら。どうしたの? じっとしていなきゃだめよ」
雪の穏やかな笑顔は、菩薩様に見えた。小梅はいい避難場所を見つけたと、龍胆と菫に舌を出す。
「いい度胸ですね、子猫ちゃん」
菫は黒い笑みを浮かべると、小梅の手を引いた。
「あら、どこへゆくの?」
「二階だよっ。二人でおままごとするんだぁ」
「怪我してるから、無理させちゃだめよ」
「はぁい!」
小梅はこれでもかと暴れたが、力で菫に勝てるはずもない。引きずられるようにして、二階へ連れて行かれる。
――小梅の悲鳴が響き渡るまで、あと五分。