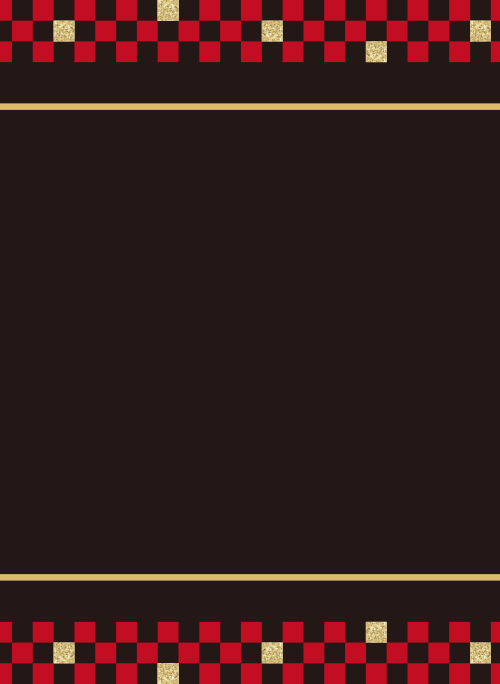龍胆も、薔薇でさえも。驚愕に目を見開き、僧侶をじっと見つめる。
雪だけが、呆然と、だが妙な懐かしさを覚えて立っていた。
父というより叔父や祖父、のような。親戚に会ったようなものだ。
僧侶――第六天魔王は龍胆へ視線を向ける。
「俺の忠告を受けても人を斬り、鬼となったか。やはり、俺の目に狂いはなかった」
「どういう、意味だ」
声に怒りが満ちていた。龍胆は刀に手をかけたまま僧侶を睨む。
「雪は我が娘。夫は俺が選んでやった。残忍で、哀れで、絶えず哀しい血の匂いがする男。極上の鬼にお前さんを育て上げたのは俺だ」
「・・・すべて貴様の差し金だったのか?」
「ほざくな小僧。義父は敬えよ」
魔王はひょうひょうと語る。
「俺は神でも仏でもない。厄災の権化。死体を食う鬼なんぞとは比べ物にならない魔物だ。そんな俺にしては優しくて手ぬるかったはずだが? 俺はな、哀しくて、酷で、残虐なものが大好きだ。我が娘から両親を奪ったのも、おまえと十年別れさせたのも、馬小屋で寝かせたのも、俺の愛。かわいい我が子の人生を哀しく彩るのは親心だ」
「あやめに両親を殺させたのは、貴様だったのか?」
「何度も言う。俺は哀しい厄災の権化。神仏(かみほとけ)ではなくとも俺と縁を結べば自ずと不幸が訪れる。人間の号哭は実に美しい。うっとり聞き惚れてしまうほどに」
「雪をそんな目に合わせて、貴様はそれでも父親か!?」
「人間の物差しで測るんじゃない。龍胆」
薔薇が、静かに言った。「尋ねるだけ無駄なこと。同じ答えが返ってくるだけだ」
魔王は龍胆と薔薇を無視すると、おもむろに雪のもとへ歩いてゆく。
雪は一瞬戸惑った。先程の話をされて、冷静でいられるはずがない。
雪は龍胆が戦っているときから冷静ではなかった。
自分は魔王の娘と言われ、実の母親は自害し、両親が死んだことも、今まで辛かったことすべてが魔王のせいだと判明し。
もはや怒る気にもなれない。皆が自分の人生を狂わせていくような、やるせない感情でいっぱいになった。
「哀しいか? 恫喝して喉をかきむしりたいだろう、我が娘」
魔王は満面の笑みで雪の顔を覗き込む。
すると。龍胆が後ろからふわりと抱きしめてきた。
背後から青い炎が上がる。菫は雪を守るようにシャーッと威嚇した。
「ほう。あやかしに随分愛されているようだ」
魔王は物珍しそうに雪を見た。
「そなたは、あやかしとなら、俺の大嫌いな幸福というものを手にできるやもしれぬな」
雪を凝視した魔王はにやりと笑う。
「夫の愛が勝ったか。躰の中に、仏の加護が視える」
雪ははっとした。龍胆が食べさせてくれたおかゆ。それに入れられたのは御仏が植えたとされるゆりの根だった。
「人に戻したり、あやかしに戻ったり。愉快な夫婦になりそうだ」
魔王はすこし悔しげだったが、雪から離れる。膝をつく薔薇の下へ向かった。
「そうび。おまえの魂は俺のものだ」
「――」
「どこで終演を迎えるかも決めるのも俺だ。朝廷に召し捕られ生き恥をさらすのはおまえらしくないだろう。――なんとまあ、俺も雪のように優しくなったものだ。この男の哀しみの声も聞きたかったのだが。俺も娘には甘い」
刹那、薔薇は円形の結界に囲まれた。それは次第に中の薔薇ごと小さくなり、飴玉ほど小さくなった。コロコロと転がってきたそれを魔王は拾い、懐にしまう。
「俺の用事は終わりだ」
終始あっけらかんとした男だ。雪の感情もそのままに、さっさと帰るつもりらしい。
ゴオッと突風が吹く。
消える間際、雪の耳には届いた。
「いい夫婦になれよ、雪」
風はふっと消える。乱れた雪の上、立っているのは龍胆と菫、雪のみだった。
「何だったのでしょう」
雪は言う。
「わたしのお父様たちは、わたしを何だと思って・・・!!」
涙が止まらない。泣き崩れそうな雪を菫が支え、龍胆が抱きしめた。
「俺がいる。雪。俺も、菫も、だれもおまえを悲しませない」
雪の頬を両手で包む。すっかり冷え切った頰に口付けを落とし、龍胆は言った。
「ここは冷える。帰ろう。――我が家へ」
雪だけが、呆然と、だが妙な懐かしさを覚えて立っていた。
父というより叔父や祖父、のような。親戚に会ったようなものだ。
僧侶――第六天魔王は龍胆へ視線を向ける。
「俺の忠告を受けても人を斬り、鬼となったか。やはり、俺の目に狂いはなかった」
「どういう、意味だ」
声に怒りが満ちていた。龍胆は刀に手をかけたまま僧侶を睨む。
「雪は我が娘。夫は俺が選んでやった。残忍で、哀れで、絶えず哀しい血の匂いがする男。極上の鬼にお前さんを育て上げたのは俺だ」
「・・・すべて貴様の差し金だったのか?」
「ほざくな小僧。義父は敬えよ」
魔王はひょうひょうと語る。
「俺は神でも仏でもない。厄災の権化。死体を食う鬼なんぞとは比べ物にならない魔物だ。そんな俺にしては優しくて手ぬるかったはずだが? 俺はな、哀しくて、酷で、残虐なものが大好きだ。我が娘から両親を奪ったのも、おまえと十年別れさせたのも、馬小屋で寝かせたのも、俺の愛。かわいい我が子の人生を哀しく彩るのは親心だ」
「あやめに両親を殺させたのは、貴様だったのか?」
「何度も言う。俺は哀しい厄災の権化。神仏(かみほとけ)ではなくとも俺と縁を結べば自ずと不幸が訪れる。人間の号哭は実に美しい。うっとり聞き惚れてしまうほどに」
「雪をそんな目に合わせて、貴様はそれでも父親か!?」
「人間の物差しで測るんじゃない。龍胆」
薔薇が、静かに言った。「尋ねるだけ無駄なこと。同じ答えが返ってくるだけだ」
魔王は龍胆と薔薇を無視すると、おもむろに雪のもとへ歩いてゆく。
雪は一瞬戸惑った。先程の話をされて、冷静でいられるはずがない。
雪は龍胆が戦っているときから冷静ではなかった。
自分は魔王の娘と言われ、実の母親は自害し、両親が死んだことも、今まで辛かったことすべてが魔王のせいだと判明し。
もはや怒る気にもなれない。皆が自分の人生を狂わせていくような、やるせない感情でいっぱいになった。
「哀しいか? 恫喝して喉をかきむしりたいだろう、我が娘」
魔王は満面の笑みで雪の顔を覗き込む。
すると。龍胆が後ろからふわりと抱きしめてきた。
背後から青い炎が上がる。菫は雪を守るようにシャーッと威嚇した。
「ほう。あやかしに随分愛されているようだ」
魔王は物珍しそうに雪を見た。
「そなたは、あやかしとなら、俺の大嫌いな幸福というものを手にできるやもしれぬな」
雪を凝視した魔王はにやりと笑う。
「夫の愛が勝ったか。躰の中に、仏の加護が視える」
雪ははっとした。龍胆が食べさせてくれたおかゆ。それに入れられたのは御仏が植えたとされるゆりの根だった。
「人に戻したり、あやかしに戻ったり。愉快な夫婦になりそうだ」
魔王はすこし悔しげだったが、雪から離れる。膝をつく薔薇の下へ向かった。
「そうび。おまえの魂は俺のものだ」
「――」
「どこで終演を迎えるかも決めるのも俺だ。朝廷に召し捕られ生き恥をさらすのはおまえらしくないだろう。――なんとまあ、俺も雪のように優しくなったものだ。この男の哀しみの声も聞きたかったのだが。俺も娘には甘い」
刹那、薔薇は円形の結界に囲まれた。それは次第に中の薔薇ごと小さくなり、飴玉ほど小さくなった。コロコロと転がってきたそれを魔王は拾い、懐にしまう。
「俺の用事は終わりだ」
終始あっけらかんとした男だ。雪の感情もそのままに、さっさと帰るつもりらしい。
ゴオッと突風が吹く。
消える間際、雪の耳には届いた。
「いい夫婦になれよ、雪」
風はふっと消える。乱れた雪の上、立っているのは龍胆と菫、雪のみだった。
「何だったのでしょう」
雪は言う。
「わたしのお父様たちは、わたしを何だと思って・・・!!」
涙が止まらない。泣き崩れそうな雪を菫が支え、龍胆が抱きしめた。
「俺がいる。雪。俺も、菫も、だれもおまえを悲しませない」
雪の頬を両手で包む。すっかり冷え切った頰に口付けを落とし、龍胆は言った。
「ここは冷える。帰ろう。――我が家へ」