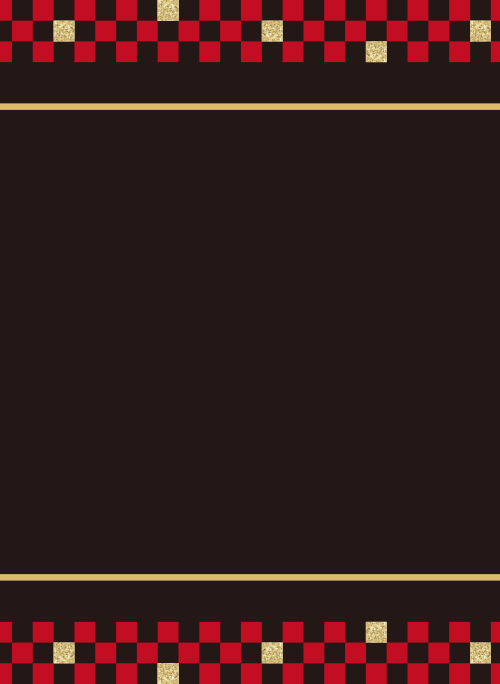「雪の父は俺だ」
「何を、言っているの・・・?」
雪は目を丸くして、薔薇を見つめた。薔薇は自身に満ちた声色で言う。
「生まれてすぐのおまえを、身の危険を感じた母親が乳母に託したのだ。おまえが母親だと思っていたのは乳母。本当の母親はその場で自決した。俺の拷問を受けて白状しなかったものはいないからな」
――お母さんは、二人いた・・??
「なぜ、自害なされたのですか」
言葉が出てこない雪の代わりに、龍胆が問う。
「俺が、第六天魔王と契約を結んだからだ。俺は魔王に自分と、生まれてくる子どもに力を授けていただいた。紅葉――いや、雪は魔王の子ども。あやかしを魅了する美しさがあるのはそれ故。ククッ! その面差し、髪の色、俺そっくりだ」
「自分の娘でしょう!? なぜ妖怪などに!?」
「全ては『家』のためよ、龍胆。おまえを拾ったのも、穢土にあやかしを放ったのも、すべて十六夜家の繁栄のため。おまえにはわからぬだろう、朝廷で家を背負って立つのが、いかに難しいのか」
――家・・・。
雪は泣き崩れた。『家』があって自分がある。だがその繁栄のために、一体どれほどの血が流れ、多くの犠牲を出してきたのだろう。
「あ、あああっ・・・!」
かつて両親が抱きしめたり、頭を撫でてくれたことを思い出すと、涙が溢れて止まらない。
本当の母親からの愛情も、同時に感じていた。
ふわりと温かな空気が雪を包む。
(おかあさま・・・?)
自害し、もうこの世にはいないはずのぬくもり。それは亡き母の魂だろうか。ふわりと光の玉が雪には見えた。
光は雪の頬をなで、それから竜胆のもとへと飛んでゆく。
竜胆の耳元へふわりと寄り添うと、
『娘を、頼みましたよ』
涼やかな声がした。――気がした。
龍胆はハッとして光を見つめる。だがその光は雪のそばに戻ると、ふっと消えた。
「ご安心を。母上様」
龍胆は刀を構える。
「雪は、この俺が護ります」
「どうだ、龍胆。そろそろ戻ってくる気にならぬか?」
薔薇のまったりとした声が響いた。
「こっちへおいで、龍胆。この父の元へ」
竜胆は目を閉じる。
俺はもう人を斬らない。
「俺はもう、十六夜 龍胆ではない。ただの龍胆だ」
「ほう?」
「過去の罪を償いながら生きてゆく。雪とともにならできる」
「雪は俺の娘だ。力ずくで勝ち取るか?」
「あなたは、もはや人間ではない。雪の父親の資格はない」
部屋の空気が変わった。
風の音、花の揺れるささやかな音まで聞こえる。鼓膜が痛いほどの沈黙を破ったのは、薔薇だった。
「俺も息子も娘も、血の宴が好きでこまる」
刹那、薔薇は踏み込んだ。
金属のぶつかり合う音。火花が散る。鍔迫り合い。とても重たい束帯装束を来ているとは思えない速さだ。
(まったく見えなかった。反射的に防げたから良かったが)
間近で見る、かつての師匠の笑みは、敵に向かってほほ笑む狂気へと変貌していた。
龍胆はひとまず背後へ引き下がる。だが薔薇は待ったなしの攻撃を仕掛けてきた。
弟子の動きのくせ、思考など手に取るようにわかるのだ。
薔薇は言う。
「人を斬るのをやめたと申したな。ならば俺を斬らずして倒せるか?」
「っ!」
眼球ギリギリを刃先がかすってゆく。剣さばき、込められた力は、とても人間わざとは思えない。一発でもくらえば、致命傷になることは確実だった。
(こんなときに、人間をやめたことを後悔することになるとは!)
屍食鬼だったら、傷の治りも早い。だが今は人間。分が悪い、悪すぎる。
雪は、二人の戦いを目で追うのがやっとだった。
座り込んだ床の違和感に気づくのに遅れた。
「なにっ?」
ぐらりと家具が陽炎のように揺らぐ。また、あの笛の音がした。
不意に、声をかけられた。
「雪お姉さん。この部屋では戦いの邪魔になるので、退散しましょうか」
男の子の声。桃色のベールを被った男の子が一本下駄で立っていた。小梅だ。
すると、襖の向こうから、芍薬の呑気な会話が割って入る。
「にいさま。もうはじめたのですか。まさか、龍胆相手に、手こずっている、なんてことありませんよねぇ? クククッ!」
「黙れ芍薬。弟とはいえ、首をはねるぞ」
怖や怖や。芍薬は腕の中の猫を抱く。
雪はその猫を見て、(なんでここにいるの、菫ちゃん!)と声が出そうになるのを、必死に押さえつけた。
「あの、その猫は・・・?」
「やりませんよ。私の猫です。さっき廊下で拾ったのです」
「それはいいですね。たっぷり『しつけ』してやらないと!」
小梅が喜ぶ。菫だとわかっているようだった。菫はじっとり猫目で睨む。小梅は再び、竜笛を奏で始めた。
部屋が揺らぐ。姫君の私室のようだったそこは調度品が消え、部屋の壁が広がってゆく。雪と芍薬と腕の中の菫は、見物席のような場所へと追いやられる。
小梅だけを残し、決戦の場所は大きな歌舞の舞台のような場所へ移っていた。
薄暗かった室内は蝋燭の灯が灯り、昼間のように明るい。
薔薇は大きな袖を翻し攻撃する。その剣さばきは剣舞の如き華麗で優美。だが恐ろしいのは一太刀の重さにある。それは薔薇が人ではないからだろう。鬼と同じ筋力と体力を一切無駄のない動きで叩き込んでくる。龍胆は防戦一方。重い剣を受け続けた両手は、次第にしびれてきた。刀を持っているのがやっとの状態だ。
背後に飛び退っても、長身故か一瞬で距離を縮められる。龍胆は体中をかすめていった剣先で血の花びらが舞う。
小梅の笛が煽るように響き渡る。一段下に移動させられた雪は、口の中がからからになりながら、状況を見守る。今声をかけるのは気が散るだろうし、今自分にできるのは戦いの邪魔をいしないこと。・・・ただそれだけだ。
(だれか、助けて!)
雪は手を合わせて祈る。すると、猫が間延びした声でみゃおんと鳴いた。
「すみれちゃん!?」
菫はそのまま芍薬の腕から飛び降り、薄暗い廊下へたたたっと走ってゆく。
「おやおや。さすが猫ですねぇ。自由気ままです」
芍薬は立ち上がると、ちらりと戦っている兄――薔薇を見た。
「もう時期、決着がつきそうですし、私は猫と戯れるといたしましょう」
芍薬は雪を置き去りに、ふわり髪をなびかせて菫の跡を追っていった。
(菫ちゃん・・・。なにか考えがあるの?)
雪はそちらも気になったが、やはり龍胆のもとへ残った。今、自分がうろつけば、気が散るだろう。極限の緊張感の中、一瞬でも気を抜けば龍胆は斬られる。血の海に沈む。
ふと。
劣勢だった竜胆が、急に薔薇の間合いへ踏み込んだ。
――ザクッ!!
薔薇の胸元から朱の花びらが散る。
!?
龍胆の目は、らんらんと狼の如き青い目に変貌していた。
薔薇は驚きに目を見張る。その隙を龍胆は見逃さない。
返す刀でさらなる斬撃を叩き込む。薔薇はそれを受け止めた。――薔薇の手が、攻撃の重さに耐えかね、震えていた。
「ふっ」
薔薇は初めて背後へ引き下がる。斬られた腹、しびれた手をもう片方で包み、珍しいものを見たように龍胆へ笑いかけた。
「刃こぼれができてしまった。初めてのことだ・・・」
雪は龍胆を見る。あっと息を呑んだ。
じわり墨汁を洗い落とすように、髪の毛の白い部分が増えてゆく。毛先だけ灰色を残し、龍胆の髪は白雪の如き真っ白に染まった。白いまつげ、血色のない頬、骨が浮き出た躰――。
「屍食鬼に戻ったか」
薔薇は微笑する。愛弟子の変貌ぶりさえ愛でているようだった。
「時間がきたようだな。雪の口づけで戻れるのは一日だけか」
「俺の雪を盗み見るな、下衆が」
龍胆は、もはや敬う心を捨てたようだった。らんらんと光る鬼の瞳は、薔薇の一挙一動を観察している。
龍胆はようやく、笑みを浮かべた。
――残忍に。それから、ひどく楽しげに。
「何を、言っているの・・・?」
雪は目を丸くして、薔薇を見つめた。薔薇は自身に満ちた声色で言う。
「生まれてすぐのおまえを、身の危険を感じた母親が乳母に託したのだ。おまえが母親だと思っていたのは乳母。本当の母親はその場で自決した。俺の拷問を受けて白状しなかったものはいないからな」
――お母さんは、二人いた・・??
「なぜ、自害なされたのですか」
言葉が出てこない雪の代わりに、龍胆が問う。
「俺が、第六天魔王と契約を結んだからだ。俺は魔王に自分と、生まれてくる子どもに力を授けていただいた。紅葉――いや、雪は魔王の子ども。あやかしを魅了する美しさがあるのはそれ故。ククッ! その面差し、髪の色、俺そっくりだ」
「自分の娘でしょう!? なぜ妖怪などに!?」
「全ては『家』のためよ、龍胆。おまえを拾ったのも、穢土にあやかしを放ったのも、すべて十六夜家の繁栄のため。おまえにはわからぬだろう、朝廷で家を背負って立つのが、いかに難しいのか」
――家・・・。
雪は泣き崩れた。『家』があって自分がある。だがその繁栄のために、一体どれほどの血が流れ、多くの犠牲を出してきたのだろう。
「あ、あああっ・・・!」
かつて両親が抱きしめたり、頭を撫でてくれたことを思い出すと、涙が溢れて止まらない。
本当の母親からの愛情も、同時に感じていた。
ふわりと温かな空気が雪を包む。
(おかあさま・・・?)
自害し、もうこの世にはいないはずのぬくもり。それは亡き母の魂だろうか。ふわりと光の玉が雪には見えた。
光は雪の頬をなで、それから竜胆のもとへと飛んでゆく。
竜胆の耳元へふわりと寄り添うと、
『娘を、頼みましたよ』
涼やかな声がした。――気がした。
龍胆はハッとして光を見つめる。だがその光は雪のそばに戻ると、ふっと消えた。
「ご安心を。母上様」
龍胆は刀を構える。
「雪は、この俺が護ります」
「どうだ、龍胆。そろそろ戻ってくる気にならぬか?」
薔薇のまったりとした声が響いた。
「こっちへおいで、龍胆。この父の元へ」
竜胆は目を閉じる。
俺はもう人を斬らない。
「俺はもう、十六夜 龍胆ではない。ただの龍胆だ」
「ほう?」
「過去の罪を償いながら生きてゆく。雪とともにならできる」
「雪は俺の娘だ。力ずくで勝ち取るか?」
「あなたは、もはや人間ではない。雪の父親の資格はない」
部屋の空気が変わった。
風の音、花の揺れるささやかな音まで聞こえる。鼓膜が痛いほどの沈黙を破ったのは、薔薇だった。
「俺も息子も娘も、血の宴が好きでこまる」
刹那、薔薇は踏み込んだ。
金属のぶつかり合う音。火花が散る。鍔迫り合い。とても重たい束帯装束を来ているとは思えない速さだ。
(まったく見えなかった。反射的に防げたから良かったが)
間近で見る、かつての師匠の笑みは、敵に向かってほほ笑む狂気へと変貌していた。
龍胆はひとまず背後へ引き下がる。だが薔薇は待ったなしの攻撃を仕掛けてきた。
弟子の動きのくせ、思考など手に取るようにわかるのだ。
薔薇は言う。
「人を斬るのをやめたと申したな。ならば俺を斬らずして倒せるか?」
「っ!」
眼球ギリギリを刃先がかすってゆく。剣さばき、込められた力は、とても人間わざとは思えない。一発でもくらえば、致命傷になることは確実だった。
(こんなときに、人間をやめたことを後悔することになるとは!)
屍食鬼だったら、傷の治りも早い。だが今は人間。分が悪い、悪すぎる。
雪は、二人の戦いを目で追うのがやっとだった。
座り込んだ床の違和感に気づくのに遅れた。
「なにっ?」
ぐらりと家具が陽炎のように揺らぐ。また、あの笛の音がした。
不意に、声をかけられた。
「雪お姉さん。この部屋では戦いの邪魔になるので、退散しましょうか」
男の子の声。桃色のベールを被った男の子が一本下駄で立っていた。小梅だ。
すると、襖の向こうから、芍薬の呑気な会話が割って入る。
「にいさま。もうはじめたのですか。まさか、龍胆相手に、手こずっている、なんてことありませんよねぇ? クククッ!」
「黙れ芍薬。弟とはいえ、首をはねるぞ」
怖や怖や。芍薬は腕の中の猫を抱く。
雪はその猫を見て、(なんでここにいるの、菫ちゃん!)と声が出そうになるのを、必死に押さえつけた。
「あの、その猫は・・・?」
「やりませんよ。私の猫です。さっき廊下で拾ったのです」
「それはいいですね。たっぷり『しつけ』してやらないと!」
小梅が喜ぶ。菫だとわかっているようだった。菫はじっとり猫目で睨む。小梅は再び、竜笛を奏で始めた。
部屋が揺らぐ。姫君の私室のようだったそこは調度品が消え、部屋の壁が広がってゆく。雪と芍薬と腕の中の菫は、見物席のような場所へと追いやられる。
小梅だけを残し、決戦の場所は大きな歌舞の舞台のような場所へ移っていた。
薄暗かった室内は蝋燭の灯が灯り、昼間のように明るい。
薔薇は大きな袖を翻し攻撃する。その剣さばきは剣舞の如き華麗で優美。だが恐ろしいのは一太刀の重さにある。それは薔薇が人ではないからだろう。鬼と同じ筋力と体力を一切無駄のない動きで叩き込んでくる。龍胆は防戦一方。重い剣を受け続けた両手は、次第にしびれてきた。刀を持っているのがやっとの状態だ。
背後に飛び退っても、長身故か一瞬で距離を縮められる。龍胆は体中をかすめていった剣先で血の花びらが舞う。
小梅の笛が煽るように響き渡る。一段下に移動させられた雪は、口の中がからからになりながら、状況を見守る。今声をかけるのは気が散るだろうし、今自分にできるのは戦いの邪魔をいしないこと。・・・ただそれだけだ。
(だれか、助けて!)
雪は手を合わせて祈る。すると、猫が間延びした声でみゃおんと鳴いた。
「すみれちゃん!?」
菫はそのまま芍薬の腕から飛び降り、薄暗い廊下へたたたっと走ってゆく。
「おやおや。さすが猫ですねぇ。自由気ままです」
芍薬は立ち上がると、ちらりと戦っている兄――薔薇を見た。
「もう時期、決着がつきそうですし、私は猫と戯れるといたしましょう」
芍薬は雪を置き去りに、ふわり髪をなびかせて菫の跡を追っていった。
(菫ちゃん・・・。なにか考えがあるの?)
雪はそちらも気になったが、やはり龍胆のもとへ残った。今、自分がうろつけば、気が散るだろう。極限の緊張感の中、一瞬でも気を抜けば龍胆は斬られる。血の海に沈む。
ふと。
劣勢だった竜胆が、急に薔薇の間合いへ踏み込んだ。
――ザクッ!!
薔薇の胸元から朱の花びらが散る。
!?
龍胆の目は、らんらんと狼の如き青い目に変貌していた。
薔薇は驚きに目を見張る。その隙を龍胆は見逃さない。
返す刀でさらなる斬撃を叩き込む。薔薇はそれを受け止めた。――薔薇の手が、攻撃の重さに耐えかね、震えていた。
「ふっ」
薔薇は初めて背後へ引き下がる。斬られた腹、しびれた手をもう片方で包み、珍しいものを見たように龍胆へ笑いかけた。
「刃こぼれができてしまった。初めてのことだ・・・」
雪は龍胆を見る。あっと息を呑んだ。
じわり墨汁を洗い落とすように、髪の毛の白い部分が増えてゆく。毛先だけ灰色を残し、龍胆の髪は白雪の如き真っ白に染まった。白いまつげ、血色のない頬、骨が浮き出た躰――。
「屍食鬼に戻ったか」
薔薇は微笑する。愛弟子の変貌ぶりさえ愛でているようだった。
「時間がきたようだな。雪の口づけで戻れるのは一日だけか」
「俺の雪を盗み見るな、下衆が」
龍胆は、もはや敬う心を捨てたようだった。らんらんと光る鬼の瞳は、薔薇の一挙一動を観察している。
龍胆はようやく、笑みを浮かべた。
――残忍に。それから、ひどく楽しげに。