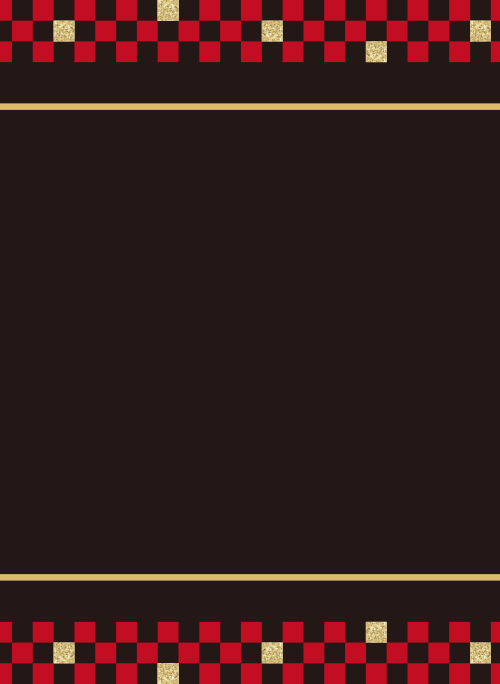こみ上げる怒りは、到底心のなかに収められるものではなかった。
雪は立ち上がり、震える身体を叱咤して怒鳴った。
「龍胆さまを、人の命を何だと思っておられるのですか!」
「息子だよ。人もあやかしも、みな血が好きなのさ」
小娘の怒りなどではびくともしない。男は風に前髪を遊ばせ愉悦の笑みを浮かべる。
「姫よ。いい娘に育ったが、少々世間知らずのようだ。日向ばかりを歩いてきた人間のいうことそのものだな。そなたと龍胆は全く違う。――だが、そなたが知らないばかりで、龍胆とそなたは違うようで、同じなのだ。そなたの業(ごう)は、龍胆よりも深いのだぞ」
「業・・・?」
雪は理由(わけ)がわからず男を見つめる。初対面のこの男は、自分の何を知っているというのか。
しかし迷いを蹴り飛ばすように、背後の襖がものすごい音を立てて吹き飛んできた。雪は目を見開き、部屋の中を闊歩する男を見つけた。
「龍胆さま――!!」
雪は薔薇の横をすり抜け、龍胆へ抱きつく。龍胆は片手で雪の頭を撫でた。
「無事か?」
「それはあなたの方でしょう」
「すまない。少し量が多くて。刻むのに時間がかかったのだよ」
刻む・・・? 雪は龍胆の背後を見やり、息を呑んだ。
大量の妖怪の屍が転がっていた。『刻む』という表現通り、肉塊と化している。
龍胆は雪を抱いたまま、優雅に座して酒を傾ける男へ、
「お久しゅうございます。『薔薇』さま」
と声をかけた。
「なんだ。もう父と呼ぶ気も失せたか」
「あなたなど、親ではない」
龍胆ははっきりと言い放った。
「俺は世間知らずだった。あなたを神のように敬い、尊敬し、唯一神であるがごとく何でも言うことを聞いてきた。あなたが喜ぶならと手を血に染めて。あなたは国すら傾けようとする化け物であることに、気づかなかった」
「ばけもの、とな?」
・・・薔薇はことりと盃を置いた。
「龍胆。誰に口を利いている――?」
ビリビリと大気が揺れた。
この男の背後にあるものは、『死』。避けようのない『死』だ。
明確な殺意の塊が二人に襲いかかる。
雪は立っているのがやっとだ。龍胆が支えてくれなければ、腰を抜かしていただろう。龍胆も唇を噛む。だが、薔薇の『死』を纏う殺気に負けない気迫が全身からみなぎっていた。
これから起こる全てを理解した上で、この男の前に立っているのだ。
雪を支える手は、微塵も震えていなかった。
薔薇は続ける。
「誰のお陰で奉行所へ連れてゆかずにすんだ? 男娼として身体を売るところを拾ったのは誰だ? 剣を教えたのは誰だ? すべて俺だ。――俺が、おまえを立派に育て上げた『父親』だ」
「違う」
龍胆は雪を後ろへ下がらせる。刀を抜いた。
「あなたは殺し屋を育てたかっただけだ。幼子なら、疑問すら抱かず親の言うがまま人だって殺せる。俺の人生を血に染めたのは、あなただ!」
「ふっ。くふふっ!」
高らかな笑い声がした。薔薇は、袖を口に当て思い切り笑っている。
「俺に合う前から人を殺めたくせに、俺のせいにするとは。――姫よ。そなたに出会ってから、息子がおかしくなってしまったではないか。どうしてくれる」
「り、龍胆さまのおっしゃるとおりです」
雪は両手を胸の前で握りしめながら、震える声で言う。
「龍胆さまだけじゃない。まだまだあなたに操られている子どもたちがいるはず。あなたは私に世間知らずとおっしゃいましたが、日向を歩くことこそ、人のあるべき生き方と存じます。日陰を歩まれていらっしゃるのは貴方様ではありませんか?」
薔薇の笑い声が消えた。
「姫。・・・知ったような口を叩くな――!!」
雪は今度こそ腰を抜かした。薔薇の両の目は虹色の光を放ち始める。龍胆は平気なのかと雪は見つめる。
――手が、震えていた。
龍胆の身体が、震えている。幼い頃からこの男の恐ろしいところを何度も見てきたからだろう。
残虐で、無情で。優美で、底しれぬ漢(おとこ)。
雪は精一杯の力で柱につかまり、立っていた。龍胆の邪魔にならぬよう気を使ってのことだ。
薔薇は、激怒しても、美しさを損なわない。今度は優しい猫なで声で雪に語りかける。
「決めた。親不孝者の龍胆はここで散る。それを見ればそなたも、己の歩むべき道が見えてくるであろう」
――すっかり忘れ去った、鬼女としての本分を思い出すはずだ。
「鬼女――?」
雪はごくりとつばを飲む。龍胆も今度ばかりはわからぬ顔をしていた。
「まだ、わからぬか。そなたの本名は雪ではない。紅葉(もみじ)。十六夜 紅葉(いざよい もみじ)だ」
「は」
――拾い子の龍胆とは違う。
「十六夜家の長女。俺の娘だ」
雪は立ち上がり、震える身体を叱咤して怒鳴った。
「龍胆さまを、人の命を何だと思っておられるのですか!」
「息子だよ。人もあやかしも、みな血が好きなのさ」
小娘の怒りなどではびくともしない。男は風に前髪を遊ばせ愉悦の笑みを浮かべる。
「姫よ。いい娘に育ったが、少々世間知らずのようだ。日向ばかりを歩いてきた人間のいうことそのものだな。そなたと龍胆は全く違う。――だが、そなたが知らないばかりで、龍胆とそなたは違うようで、同じなのだ。そなたの業(ごう)は、龍胆よりも深いのだぞ」
「業・・・?」
雪は理由(わけ)がわからず男を見つめる。初対面のこの男は、自分の何を知っているというのか。
しかし迷いを蹴り飛ばすように、背後の襖がものすごい音を立てて吹き飛んできた。雪は目を見開き、部屋の中を闊歩する男を見つけた。
「龍胆さま――!!」
雪は薔薇の横をすり抜け、龍胆へ抱きつく。龍胆は片手で雪の頭を撫でた。
「無事か?」
「それはあなたの方でしょう」
「すまない。少し量が多くて。刻むのに時間がかかったのだよ」
刻む・・・? 雪は龍胆の背後を見やり、息を呑んだ。
大量の妖怪の屍が転がっていた。『刻む』という表現通り、肉塊と化している。
龍胆は雪を抱いたまま、優雅に座して酒を傾ける男へ、
「お久しゅうございます。『薔薇』さま」
と声をかけた。
「なんだ。もう父と呼ぶ気も失せたか」
「あなたなど、親ではない」
龍胆ははっきりと言い放った。
「俺は世間知らずだった。あなたを神のように敬い、尊敬し、唯一神であるがごとく何でも言うことを聞いてきた。あなたが喜ぶならと手を血に染めて。あなたは国すら傾けようとする化け物であることに、気づかなかった」
「ばけもの、とな?」
・・・薔薇はことりと盃を置いた。
「龍胆。誰に口を利いている――?」
ビリビリと大気が揺れた。
この男の背後にあるものは、『死』。避けようのない『死』だ。
明確な殺意の塊が二人に襲いかかる。
雪は立っているのがやっとだ。龍胆が支えてくれなければ、腰を抜かしていただろう。龍胆も唇を噛む。だが、薔薇の『死』を纏う殺気に負けない気迫が全身からみなぎっていた。
これから起こる全てを理解した上で、この男の前に立っているのだ。
雪を支える手は、微塵も震えていなかった。
薔薇は続ける。
「誰のお陰で奉行所へ連れてゆかずにすんだ? 男娼として身体を売るところを拾ったのは誰だ? 剣を教えたのは誰だ? すべて俺だ。――俺が、おまえを立派に育て上げた『父親』だ」
「違う」
龍胆は雪を後ろへ下がらせる。刀を抜いた。
「あなたは殺し屋を育てたかっただけだ。幼子なら、疑問すら抱かず親の言うがまま人だって殺せる。俺の人生を血に染めたのは、あなただ!」
「ふっ。くふふっ!」
高らかな笑い声がした。薔薇は、袖を口に当て思い切り笑っている。
「俺に合う前から人を殺めたくせに、俺のせいにするとは。――姫よ。そなたに出会ってから、息子がおかしくなってしまったではないか。どうしてくれる」
「り、龍胆さまのおっしゃるとおりです」
雪は両手を胸の前で握りしめながら、震える声で言う。
「龍胆さまだけじゃない。まだまだあなたに操られている子どもたちがいるはず。あなたは私に世間知らずとおっしゃいましたが、日向を歩くことこそ、人のあるべき生き方と存じます。日陰を歩まれていらっしゃるのは貴方様ではありませんか?」
薔薇の笑い声が消えた。
「姫。・・・知ったような口を叩くな――!!」
雪は今度こそ腰を抜かした。薔薇の両の目は虹色の光を放ち始める。龍胆は平気なのかと雪は見つめる。
――手が、震えていた。
龍胆の身体が、震えている。幼い頃からこの男の恐ろしいところを何度も見てきたからだろう。
残虐で、無情で。優美で、底しれぬ漢(おとこ)。
雪は精一杯の力で柱につかまり、立っていた。龍胆の邪魔にならぬよう気を使ってのことだ。
薔薇は、激怒しても、美しさを損なわない。今度は優しい猫なで声で雪に語りかける。
「決めた。親不孝者の龍胆はここで散る。それを見ればそなたも、己の歩むべき道が見えてくるであろう」
――すっかり忘れ去った、鬼女としての本分を思い出すはずだ。
「鬼女――?」
雪はごくりとつばを飲む。龍胆も今度ばかりはわからぬ顔をしていた。
「まだ、わからぬか。そなたの本名は雪ではない。紅葉(もみじ)。十六夜 紅葉(いざよい もみじ)だ」
「は」
――拾い子の龍胆とは違う。
「十六夜家の長女。俺の娘だ」