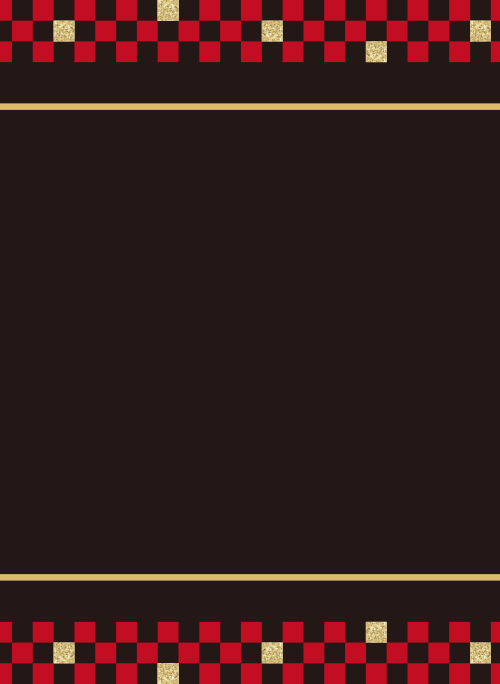雪は朱色の絨毯が敷かれた部屋に、ぽつんと立っていた。
部屋の中は見事な金粉で装飾された長持や鏡、化粧道具などの調度品であふれ、まるで姫君の私室のようだった。
開け放たれた障子からは、屋敷すべてを飲み込みそうなくらい大きな青い満月がこうこうと月光を注いでいる。
白い桜は満開で、見事な枝ぶりだ。おそらく自分は建物の二階にいるのだろうと雪は思った。
「気に入ったか? 我が姫よ。ここはそなたの部屋だ。好きに使え」
「は・・・」
後ろから声をかけられ、雪は体を震わせた。
振り向き、雪は目を見開いた。予想外すぎる男が立っていたからだ。
その男の出で立ちは、着流しでもない。カラスのような軍服でもない。
満開の桜の如き、麗しい束帯装束(そくたいしょうぞく)だった。
冠(かんむり)に艷やかな黒髪をすべて収めている。ほろりとこぼれ落ちた前髪が一房だけ、ひたいで揺れている。
細筆で描いたような眉、白く通った鼻筋、微笑を含んだ唇の色も、すべてがハッと息を呑むほど麗しい。だが、その黒眼は月光の当たらない場所でもうっすら虹色を帯びていて、魔物であるかのような怖れを抱かせる。
――まるで夜桜。美しいが、人を狂わせる恐ろしさを兼ね備えた華。
「あなたは人間ですか?」
雪は尋ねながら、背中を冷たい氷が滑り落ちていくような、嫌な感覚に襲われた。
男は雪の動揺にくすっと笑うと、「・・・鬼だと言ったらどうする?」と逆に尋ね返してきた。雪はしばし、思案する。
束帯は朝廷で着るものだ。透けるような白い衣は、男の身分の高さを物語っている。
鬼であったら、格上の鬼であろうし、人だったら。なぜここにいるのかわからない。
「お手上げか?」
「はい・・・。あなたは何者ですか?」
男はふふんと微笑する。おもむろに口を開いた。
「俺は薔薇(そうび)。十六夜 薔薇(いざよい そうび)だ」
――人だよ。・・・たぶん、な。
静かな室内に、衣擦れの音が響く。薔薇は雪のそばで立ち止まる。こうしてみると背が高い。薔薇は身体がカチコチになった雪を見下ろし、ふわりと笑った。
とても満足げに。とても嬉しそうに。
「そなたにはないだろうが、俺には積もる話があってな。茶でも飲みながら付き合ってくれるか? イケるクチなら酒もあるぞ」
「いえ、私は結構です・・・」
雪は遠慮した。男は障子から廊下へ出ると、優雅に座った。片膝を立て、胡座をかく。桜を愛でながら雪を待っていた。
(龍胆さまは無事かしら)
雪はかなり迷ったが、この男が敵であろうと味方であろうと、機嫌を損ねるのはまずいと判断した。
男とちょうど良い距離感を保ち、そっと座布団に座る。
薔薇はゆっくり酒を楽しんでいた。空の盃を雪に無理やりもたせると、トクトク酒をつぐ。
「あの、わたし、お酒はちょっと・・・」
「俺の姫だ。下戸ではないと思うが」
とろりと酒が揺れる。雪は困ったが、勇気を出して一口、唇に含んだ。
(まぎれもない。ちゃんとしたお酒だわ・・・)
妖怪の怪しい酒ではなさそうだ。雪はホッと息を吐いた。
「うむ。それで良い」
薔薇は嬉しそうに微笑む。
「あなたは、私と竜胆さまをご存知なのですか?」
雪にしては、踏み込んだ質問をした。男は盃を弄びながら、「知っているとも」と頷いた。
「数少ない『十六夜』の名字を持つもの。なにかピンとこないか?」
雪は首を振った。
「竜胆さまも私も。名字など持てる身分ではありません」
「なんだ。内緒にしていたのか。龍胆のやつは」
「はい?」
「十六夜 龍胆。奴は我が息子よ」
雪は盃を取り落とした。からからと転がってゆく。
「あなたは、龍胆さまの、おとうさま・・・!?」
雪は舐めるように男を見つめた。見た目はどう見積もっても二十代後半だ。それに、龍 胆とは全く似ていない。
「俺は大所帯でな。妻は三十人いる。子どもは・・・数えるのをやめたから、性格には覚えていない」
――龍胆は拾った子どもだ。龍胆は子らの中でも、一番お気に入りだったなぁ
薔薇はおもむろに雪へ手を伸ばす。床に垂らした長い髪をすくい取った。
「きれいな髪だな、姫よ。俺は美しいものに目がない。妻も子も、つい収集品に加えたくなるのだ」
――龍胆も、収集品の一人だった。
雪は身震いする。
(この人は、あやめさんと同じ匂いがする。・・・でも、少しだけ違う)
それは、ほのかなぬくもりか。愛情と呼べるものなのか。
父親なら、龍胆が何をさせられてきたかも知っているはずだ。
暖かさの中に、明確な『狂気』を隠している。
薔薇はゆっくり口を開いた。
「そなたも、知っておくべきだろう。竜胆の過去を」
部屋の中は見事な金粉で装飾された長持や鏡、化粧道具などの調度品であふれ、まるで姫君の私室のようだった。
開け放たれた障子からは、屋敷すべてを飲み込みそうなくらい大きな青い満月がこうこうと月光を注いでいる。
白い桜は満開で、見事な枝ぶりだ。おそらく自分は建物の二階にいるのだろうと雪は思った。
「気に入ったか? 我が姫よ。ここはそなたの部屋だ。好きに使え」
「は・・・」
後ろから声をかけられ、雪は体を震わせた。
振り向き、雪は目を見開いた。予想外すぎる男が立っていたからだ。
その男の出で立ちは、着流しでもない。カラスのような軍服でもない。
満開の桜の如き、麗しい束帯装束(そくたいしょうぞく)だった。
冠(かんむり)に艷やかな黒髪をすべて収めている。ほろりとこぼれ落ちた前髪が一房だけ、ひたいで揺れている。
細筆で描いたような眉、白く通った鼻筋、微笑を含んだ唇の色も、すべてがハッと息を呑むほど麗しい。だが、その黒眼は月光の当たらない場所でもうっすら虹色を帯びていて、魔物であるかのような怖れを抱かせる。
――まるで夜桜。美しいが、人を狂わせる恐ろしさを兼ね備えた華。
「あなたは人間ですか?」
雪は尋ねながら、背中を冷たい氷が滑り落ちていくような、嫌な感覚に襲われた。
男は雪の動揺にくすっと笑うと、「・・・鬼だと言ったらどうする?」と逆に尋ね返してきた。雪はしばし、思案する。
束帯は朝廷で着るものだ。透けるような白い衣は、男の身分の高さを物語っている。
鬼であったら、格上の鬼であろうし、人だったら。なぜここにいるのかわからない。
「お手上げか?」
「はい・・・。あなたは何者ですか?」
男はふふんと微笑する。おもむろに口を開いた。
「俺は薔薇(そうび)。十六夜 薔薇(いざよい そうび)だ」
――人だよ。・・・たぶん、な。
静かな室内に、衣擦れの音が響く。薔薇は雪のそばで立ち止まる。こうしてみると背が高い。薔薇は身体がカチコチになった雪を見下ろし、ふわりと笑った。
とても満足げに。とても嬉しそうに。
「そなたにはないだろうが、俺には積もる話があってな。茶でも飲みながら付き合ってくれるか? イケるクチなら酒もあるぞ」
「いえ、私は結構です・・・」
雪は遠慮した。男は障子から廊下へ出ると、優雅に座った。片膝を立て、胡座をかく。桜を愛でながら雪を待っていた。
(龍胆さまは無事かしら)
雪はかなり迷ったが、この男が敵であろうと味方であろうと、機嫌を損ねるのはまずいと判断した。
男とちょうど良い距離感を保ち、そっと座布団に座る。
薔薇はゆっくり酒を楽しんでいた。空の盃を雪に無理やりもたせると、トクトク酒をつぐ。
「あの、わたし、お酒はちょっと・・・」
「俺の姫だ。下戸ではないと思うが」
とろりと酒が揺れる。雪は困ったが、勇気を出して一口、唇に含んだ。
(まぎれもない。ちゃんとしたお酒だわ・・・)
妖怪の怪しい酒ではなさそうだ。雪はホッと息を吐いた。
「うむ。それで良い」
薔薇は嬉しそうに微笑む。
「あなたは、私と竜胆さまをご存知なのですか?」
雪にしては、踏み込んだ質問をした。男は盃を弄びながら、「知っているとも」と頷いた。
「数少ない『十六夜』の名字を持つもの。なにかピンとこないか?」
雪は首を振った。
「竜胆さまも私も。名字など持てる身分ではありません」
「なんだ。内緒にしていたのか。龍胆のやつは」
「はい?」
「十六夜 龍胆。奴は我が息子よ」
雪は盃を取り落とした。からからと転がってゆく。
「あなたは、龍胆さまの、おとうさま・・・!?」
雪は舐めるように男を見つめた。見た目はどう見積もっても二十代後半だ。それに、龍 胆とは全く似ていない。
「俺は大所帯でな。妻は三十人いる。子どもは・・・数えるのをやめたから、性格には覚えていない」
――龍胆は拾った子どもだ。龍胆は子らの中でも、一番お気に入りだったなぁ
薔薇はおもむろに雪へ手を伸ばす。床に垂らした長い髪をすくい取った。
「きれいな髪だな、姫よ。俺は美しいものに目がない。妻も子も、つい収集品に加えたくなるのだ」
――龍胆も、収集品の一人だった。
雪は身震いする。
(この人は、あやめさんと同じ匂いがする。・・・でも、少しだけ違う)
それは、ほのかなぬくもりか。愛情と呼べるものなのか。
父親なら、龍胆が何をさせられてきたかも知っているはずだ。
暖かさの中に、明確な『狂気』を隠している。
薔薇はゆっくり口を開いた。
「そなたも、知っておくべきだろう。竜胆の過去を」