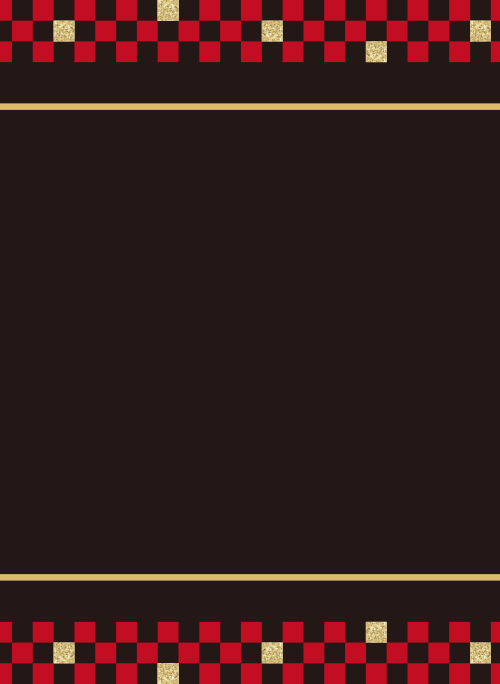青い満月が不気味な月光を降り注ぐ。大きな月だ。屋敷全部を飲み込みそうなほど。それは中庭の白い桜に、良く映えていた。
「さあ、誰が先にたどり着くかな?」
男は透ける純白の束帯(そくたい)をふわりと着ていた。冠(かんむり)はそよ風に揺れる。
酒がたっぷり揺れる漆塗りの大きな盃を置くと、朱塗りの柱が雅やかな縁側へ繰り出す。
「寄木細工の如きこの屋敷。この俺に辿り着く前に死なねばよいが」
男は部屋を振り返り、語りかける。そこには大きな鏡が置かれていた。
鏡に写る、人間に戻った龍胆。
男は、喉の奥でククッと笑った。
地震に耐え、雪煙に包まれた菫は、視界を妨げる雪をゴシゴシとぬぐう。男の子の笛の音はやまない。ようやく視界がひらけてきた。――が、その光景を見た菫は、口をあんぐりと開けた。
「これは・・・!!」
まるで大きな寺社がそのまま地面からそそり立つようだった。
幾重にもつながる朱色の鳥居は、屋敷の中へつながる唯一の道か。
子どもは一旦、笛をやめると、おもむろに自己紹介した。
「・・・ぼくは小梅(こうめ)。この屋敷はぼくの幻術。空にも地面にも結界が張ってある。空へ飛んでも地面を掘っても無駄、無駄」
――ようこそ。夢幻の館へ。
菫は呆然としていたが、やがて小さな唇から牙をのぞかせた。
「ならば、おまえを食べちゃえば、この幻も終わりでしょう」
「賢い猫さんだね。――やれるものならやってごらん?」
「ぬかすな。こぞう」
男の子はにやりと笑う。両者、微笑みを絶やさない。どちらも子どもの顔ではなかった。
先に動いたのは菫だった。
げんこつを握りしめ、小梅の小さな顔を思い切り殴る。菫が殴りつけた場所の雪は吹き飛び、大きな穴が湯気を立てて空いていた。
だが小梅も反応が早かった。ひらりと上に飛び上がり、瞬速の拳を交わす。逆さまの体制のまま竜笛に口笛を添えた。
美しい曲が辺りに響き渡る。すると地面から次々、青竹がメキメキと生えてきた。竹林は一部の隙間もない。
屍食鬼の館までの道を完璧に塞がれてしまった。
菫は、次の攻撃に備える。
(これじゃ、火車に戻ることはできない。雪お姉ちゃんとも引き剥がされちゃった)
雪は無事だろうか。菫は小さく舌打ちした。
(お姉ちゃんのことは、龍胆さんに任せましょう)
大変、不本意だが、こうなってからではどうしようもない。
小梅は懐からなにかを取り出すと、逃げ場を失った菫へなにかを、ふうと吹きかけた。桃色で美しい。かぐわしい甘い香りが菫を包む。
(梅の花びら・・・!)
菫は渋面した。
梅には厄除けの効果がある。あやかしにとってその香りは麻酔であり、花びらは剃刀同然だ。無数の花びらは、菫の皮膚を裂いた。
「――っ!」
菫は全身傷だらけだ。
一方、小梅は無邪気に笑う。獲物を弄んで楽しんでいるのだ。
「うふふっ! 僕の勝ちだねっ」
「せいかくのネジ曲がったクソガキめ・・・! 許しませんよっ」
菫のぷくぷくの頬は花びらに斬られた。
血がぽたりと落ちた。
その血は、長らく忘れていた野生の勘を思い起こさせた。
菫は地面に落ちた花びらの山を、思い切り足で蹴った。小梅の視界を奪う。
その隙に片手を、化猫の手に変化させる。遠距離でも届く化猫の鋭い鉤爪は、間一髪かわした小梅のベールを切り裂いた。菫は奥歯をギリッと噛みしめる。
(おのれ、ちょこまかと・・・!)
小梅は軽々と跳躍し、鳥居の上へ避難する。
(意外だったな。猫なのにここまで知能が高いとは)
この戦いは、深追いしないほうがいいかもしれない。
すると、脳裏に男の声が響いてきた。
『小梅。そこはいい。――戻ってこい』
それは屋敷の奥深くに潜む男のものだった。
「はい」
『おとうさま』
小梅は、再び梅の花びらを吹いて乱舞させた。菫の足が止まる。
菫が目を開けたときには、小梅の姿はなかった。
「逃げるな、ひきょうもの!」
菫の絶叫がほとばしった。
「さあ、誰が先にたどり着くかな?」
男は透ける純白の束帯(そくたい)をふわりと着ていた。冠(かんむり)はそよ風に揺れる。
酒がたっぷり揺れる漆塗りの大きな盃を置くと、朱塗りの柱が雅やかな縁側へ繰り出す。
「寄木細工の如きこの屋敷。この俺に辿り着く前に死なねばよいが」
男は部屋を振り返り、語りかける。そこには大きな鏡が置かれていた。
鏡に写る、人間に戻った龍胆。
男は、喉の奥でククッと笑った。
地震に耐え、雪煙に包まれた菫は、視界を妨げる雪をゴシゴシとぬぐう。男の子の笛の音はやまない。ようやく視界がひらけてきた。――が、その光景を見た菫は、口をあんぐりと開けた。
「これは・・・!!」
まるで大きな寺社がそのまま地面からそそり立つようだった。
幾重にもつながる朱色の鳥居は、屋敷の中へつながる唯一の道か。
子どもは一旦、笛をやめると、おもむろに自己紹介した。
「・・・ぼくは小梅(こうめ)。この屋敷はぼくの幻術。空にも地面にも結界が張ってある。空へ飛んでも地面を掘っても無駄、無駄」
――ようこそ。夢幻の館へ。
菫は呆然としていたが、やがて小さな唇から牙をのぞかせた。
「ならば、おまえを食べちゃえば、この幻も終わりでしょう」
「賢い猫さんだね。――やれるものならやってごらん?」
「ぬかすな。こぞう」
男の子はにやりと笑う。両者、微笑みを絶やさない。どちらも子どもの顔ではなかった。
先に動いたのは菫だった。
げんこつを握りしめ、小梅の小さな顔を思い切り殴る。菫が殴りつけた場所の雪は吹き飛び、大きな穴が湯気を立てて空いていた。
だが小梅も反応が早かった。ひらりと上に飛び上がり、瞬速の拳を交わす。逆さまの体制のまま竜笛に口笛を添えた。
美しい曲が辺りに響き渡る。すると地面から次々、青竹がメキメキと生えてきた。竹林は一部の隙間もない。
屍食鬼の館までの道を完璧に塞がれてしまった。
菫は、次の攻撃に備える。
(これじゃ、火車に戻ることはできない。雪お姉ちゃんとも引き剥がされちゃった)
雪は無事だろうか。菫は小さく舌打ちした。
(お姉ちゃんのことは、龍胆さんに任せましょう)
大変、不本意だが、こうなってからではどうしようもない。
小梅は懐からなにかを取り出すと、逃げ場を失った菫へなにかを、ふうと吹きかけた。桃色で美しい。かぐわしい甘い香りが菫を包む。
(梅の花びら・・・!)
菫は渋面した。
梅には厄除けの効果がある。あやかしにとってその香りは麻酔であり、花びらは剃刀同然だ。無数の花びらは、菫の皮膚を裂いた。
「――っ!」
菫は全身傷だらけだ。
一方、小梅は無邪気に笑う。獲物を弄んで楽しんでいるのだ。
「うふふっ! 僕の勝ちだねっ」
「せいかくのネジ曲がったクソガキめ・・・! 許しませんよっ」
菫のぷくぷくの頬は花びらに斬られた。
血がぽたりと落ちた。
その血は、長らく忘れていた野生の勘を思い起こさせた。
菫は地面に落ちた花びらの山を、思い切り足で蹴った。小梅の視界を奪う。
その隙に片手を、化猫の手に変化させる。遠距離でも届く化猫の鋭い鉤爪は、間一髪かわした小梅のベールを切り裂いた。菫は奥歯をギリッと噛みしめる。
(おのれ、ちょこまかと・・・!)
小梅は軽々と跳躍し、鳥居の上へ避難する。
(意外だったな。猫なのにここまで知能が高いとは)
この戦いは、深追いしないほうがいいかもしれない。
すると、脳裏に男の声が響いてきた。
『小梅。そこはいい。――戻ってこい』
それは屋敷の奥深くに潜む男のものだった。
「はい」
『おとうさま』
小梅は、再び梅の花びらを吹いて乱舞させた。菫の足が止まる。
菫が目を開けたときには、小梅の姿はなかった。
「逃げるな、ひきょうもの!」
菫の絶叫がほとばしった。