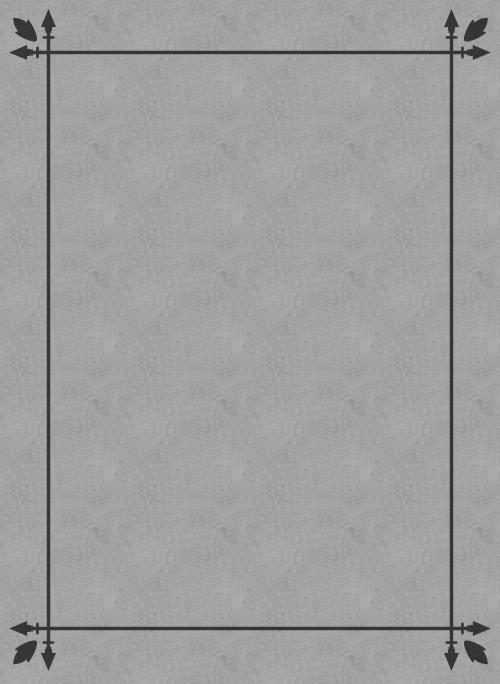名は佐山、年は十七、趣味は筋トレと睡眠、得意教科はない。
俺は誰よりもつまらないプロフィールを持つ男という自負があった。
高校生活に華はなく、数少ない友人とごくたまに会話をして過ごす日々。
部活はせず、委員会も半分くらいは休み、テキトーにダラーっと生きている。
俺らしいと言えば俺らしい。
別に退屈はしてないし、癒しや華を求めることもない。ただただ平穏に過ごしたかった。
今の日常には十分満足していた。
「……にしても、暑いな」
くだらん俺の情報はさておくとして、今日はとにかくひどい猛暑日だった。
じめじめとした真夏の午後。
こんな日は、早く家に帰ってシャワーを浴びて、エアコンで涼みながら夜まで眠りたい。
あと五分も歩けば家に着く。
この公園を通り抜けるルートが最も早い。
「あちぃ……」
俺はいつものように公園を横切っていた。
日差しに耐えながら、のんびりと歩いて帰路に着く。
何の気なしに歩いていると、ベンチに座り泣いている女の子を見つけた。
「ん?」
ベンチに座っていると言っても普通に座っているわけではない。
ベンチの上で両足を三角に立てて座っており、真正面からは下着が見えてしまいそうな感じだ。
「大丈夫か?」
心配で声をかけた。別に他意はない。
制服を見るにうちの高校の生徒みたいだし、チラッと見えるリボンの色からして後輩の一年だろう。変なことをする気は一切ない。
「あ、あなたは……?」
後輩女子はマジ泣きしていたのか、こちらを見る顔はぐしゃぐしゃになっていた。
目が赤く腫れ上がり、口元は歪んでいる。
よっぽど悲しいことがあったのだろう。
「俺は佐山。龍ヶ崎高校の二年だよ」
「……先輩でしたか。てっきり不審者か変態かと思いました。私の体目的ではないんですね?」
「違ぇよ。普通に心配して声かけただけだ。なんか思ったよりも元気そうだし、俺はもう行くわ。暑いから早く帰れよ」
俺は早々に見切りをつけて立ち去ることにした。
よくわからないが、そんなに傷心しているわけではなさそうだったし、多分問題ないと思う。
しかし、此奴はそれを許してくれなかった。
「待ってください、佐山先輩」
後輩女子は俺の手首を掴んで離さない。
三角に畳んでいた足は地面についており、ホールドされた手首には力が込められている。
「なんだよ」
「せっかくですし、私の悩みを聞いてくださいよ」
「やだよ。今日は忙しいんだ」
俺は忙しい。帰ったら筋トレをして体を疲れさせた後に、たっぷり寝ないといけないんだ。
トレーニング後はベッドにダイブしてスリーピーに没頭するんだ。
「何か大切な用事があるんですか?」
「んー、まあな……詳しくは言えないけど」
「暇なんですね。じゃあ、隣に座ってください」
「……勝手に決めつけるなよ」
なにを言っても無駄なような気がしたので、やむなく後輩女子の隣に座った。
もちろん、それなりに間隔を空けて。
「で、悩みってなんだ? 手短に頼む」
「佐山先輩は私が泣いていた理由について気になりますよね。だから声をかけてきたんだと思いますし」
「別に気にならないけど」
「気になりますよね?」
「いや、本当にどうでもいい」
「気になりますよね? そうですよね?」
「……そうだな」
抗うのはやめた。
こいつ、頑固なタイプだ。
「ですよねー、やっぱり気になっちゃいますよね」
もったいぶりやがって。
「そうだなぁ……気になるなぁ、ほんとに」
「はいはい。そこまで気になるなら教えてあげます。実は失恋しちゃいまして……」
「へー、相手は?」
「お? 興味が出てきましたか?」
「違う。聞いてほしそうな顔だったから、気を利かせて聞いてみただけだ」
「ありがとうございます。お相手は三年生の先輩です。委員会で会った時に一目惚れしちゃったんですよね」
「カッコいいのか?」
「そりゃあもう、イケメンです。佐山先輩はヌボーッとしたゾンビみたいな顔ですけど、その先輩は爽やかでクールで背が高くてスタイルの良いイケメンなんです」
そう口にする後輩女子の目はキラキラしていた。俺の見た目の評価はさておき、その先輩は絵本の王子様みたいなルックスだな。
後輩女子は言葉を続ける。
「それでここからが本題なんですけど、その先輩とお話ししていい感じになれたのに、なんと先輩には彼女さんがいたんですっ! 先輩は私のことが好きって言ってくれたのに、まさかまさかの浮気だったんです! 他にも何人もの女子を口説いているらしくて、それを知っちゃったらもう悲しいですし、悔しいです! どう思いますか!?」
後輩女子はしくしくわんわん言いながら、大袈裟に泣く仕草を見せてきた。
多分、本当にショックを受けているんだろうけど、いかんせんあざとい。真っ先にそのことについて触れたかった。
しかし、根本的に考え方が違う気がしてそれが気になった。
「……それ、失恋なのか? だってお前はイケメン先輩のことをまだ恋愛的に好きだったわけじゃないんだろ?」
「確かにまだ好きという段階ではありませんでしたけど、恋が実らなかったので立派な失恋です。佐山先輩には無縁の感覚でしょうけど」
「まあ、俺の話は置いておいて、一般的に失恋ってのは告白して振られたりするもんを指すんじゃないか? 今回の相手は彼女持ちのだらしないやつなんだろ? むしろ付き合わなくて正解だと思うが……」
ショックを受ける気持ちはわからなくもないが、泣くほどのことかと思ってしまう。
今の話だけ聞くと悪いのは先輩一人だけだから、何も思い悩む必要はない。
「私の場合は意中の男の人が靡かなかったことがありませんし、これこそが失恋なんですよ! 私が浮気相手の一人にされかけたという事実が許せないので、必ず夢の中でぶっ殺です!」
「モテるんだな」
物騒な言葉が聞こえたがナチュラルに受け流し、後輩女子が喜ぶワードをチョイスした。
「そりゃーもう、私は中学時代からモテモテですよ。ラブレターなんてもらいまくってきましたし、先輩や後輩、同級生からも何度も何度も呼び出されて告白されたことがありますもん」
胸を張って偉そうにしてる。
まあ、納得だな。
確かに容姿は整ってるし。
見た目は小動物系とでも言おうか。
身長が低く、きゃるるんとした雰囲気がある。愛嬌抜群モンスターってところだ。
髪は明るめの茶髪だが不潔感はないし、顔は目鼻立ちがはっきりしていて声もあざと可愛い。
ただ、内面は読めない。ちょっと毒気がありそうだ。
「佐山先輩は本当に優しさだけで私に声をかけてくれたんですか? 下心はありませんか?」
「ない。早く帰りたい」
「……変な人ですねぇ……私と話して私のことを好きになったりしないですか?」
「しない。早く帰りたい」
マジでありえない。
名も知らぬ目の前の後輩女子が可愛いのは真実だが、今の俺は暑さと気怠さのせいでそんな気分じゃない。
早く帰りたいんだよ。解放してくれ。
「それはそれでムカつきますね」
「なんでだよ」
「でもまあ、他の男の人よりはマシですね。私って男の人からは人気なんですけど、結局は下僕みたいになっちゃって進展しませんし、モテすぎるから同性からは嫌われてるので……佐山先輩みたく普通に話せる人は珍しいです」
溜め息混じりに打ち明けてくれたけど、マジで興味ない。
「そうか。よかったな。で、話は終わりか? 俺は帰るぞ?」
「冷たいですねー、もっと優しくしてくださいよー」
「はいはい。次からはいい男を見つけられるように頑張れよ。少なくとも浮気なんてしないやつをな。ちなみに俺のおすすめは”とことんモテない男”だ。そういう奴は絶対に浮気をしないからな。じゃあな」
ぶーぶーごねているようだったが、俺は気にせず退散した。
優しいやつも浮気しないやつもたくさんいる。
選り好みしなければ、ぴったりの相手を探せるはずだ。
まあ、後輩女子の恋愛事情なんて心底どうでもいいんだけどね。
◇◆◇◆
数日後の放課後、
俺はいつものように家に直帰するつもりだった。
だけど、相変わらず外は暑いし、そのせいで喉がカラカラだった。
冷たいものでも飲みたいと思い、近所のコンビニに立ち寄ることにした。
店内に入ると冷房の風が体を包む。気持ちいい。
とりあえず飲み物コーナーに向かい、スポーツドリンクを手に取る。
ついでに次はアイスでも見て帰ろうか。
そんなことを考えながらアイスコーナーへ向かうと、そこに見覚えのある後ろ姿があった。
「ん?」
サラッとしたボブカットで茶髪の小柄な女子——こいつ、数日前に公園で泣いていた後輩か?
あまり人のことを覚えられない俺だが、こいつは性格や見た目に一癖あったので覚えていた。
名前は聞いてないから知らん。
真剣な顔でアイスのパッケージを見比べているみたいだが、早く退いてほしい。
「……」
俺は無言で背後に佇んだ。
どうせすぐに選び終えるだろうし、じっくりと待つ。
しかし、後輩女子は優柔不断なのか、「んー、んー!」と口ずさみながら悩みに悩んでいた。
遅い。パッと選んでほしい。
「スイカバーでいいだろ、夏だし」
俺はつい声をかけてしまった。
「えっ?」
後輩女子が振り返り、目が合う。
驚いたような表情だったが、すぐに満面の笑みを浮かべた。
「佐山先輩! こんなところで会うなんて運命ですね!」
「ただの偶然だろ」
「いえ、運命です! ちょうどお財布を家に忘れてアイスを買えなかったので、これは佐山先輩にご馳走してもらえる運命です!」
よくない運命だった。
アイスに悩んでいたわけではなく、食べたいのに食べられなくて困っていただけだったらしい。
「俺はご馳走しないぞ」
「いえ、運命です!」
なんだこいつ、押しが強すぎる。ぐいっと距離を詰めてくるぞ。やわな男なら勘違いして惚れてしまいそうだ。危ない。
「……どのアイスがいいんだ?」
何を言っても無駄だと思ったので、仕方なく今回だけは折れることにした。百円ポッチで満足してくれるならもうそれでいい。
「えーっと……バニラが無難ですけど、チョコの誘惑も捨てがたいですよね。佐山先輩ならどっちを選びます?」
「俺ならチョコクランキーのやつだな」
「えー、意外ですね」
「悪いか?」
食感が美味いんだよな、これ。
「いえ、もっと地味なの選ぶかと思いました。なんか私の方が地味なアイス選ぶのは癪なので、私も佐山先輩と同じやつにします」
「俺の影響受けすぎだろ」
「佐山先輩のこと、ちょっとだけ知りたいですから」
後輩女子はくすっと笑った。少しだけ子供っぽい無邪気な笑顔だ。
そう言いながら、彼女は俺にアイスを手渡すと、我先にと店の外へ出て行った。
なんだかんだで、自然に会話が続いているのが不思議だ。
俺は買い物を済ませてコンビニの外に出たが、相変わらず日差しが強い。
「ほらよ。今回だけだからな」
「はーい。ありがとーございまーす!」
めちゃくちゃ嬉しそうだった。お礼を言いながらも袋を開けてチョコクランキーアイスにかぶりついている。
「冷たくておいしいです!」
「そりゃあな。アイスなんだから」
続いて俺もアイスを口にした。やはり美味い。
「佐山先輩って優しいですねー」
「普通だろ」
おだてても何も出ないぞ。むしろ俺は無愛想でぶっきらぼうで優しくないとも思うし。
「そうですかね? っていうか、私の名前って知ってますか?」
「知らん」
「知りたくなりませんか」
「知りたくならないな」
どうせこれっきりの関係だし知る必要もない。一ヶ月も経てば綺麗さっぱり忘れる自信がある。
「小倉由花です!」
なぜか後輩女子は透き通る声色で名乗り始めた。
小倉って言うんだね、きみ。あんこみたいで美味しそうな名前だこと。
「……聞いてないんだけど」
「聞かせたんです!」
「あ、そう。小倉ね」
「特別に由花って呼んでもいいですよ?」
「遠慮しとく。それより、口にチョコついてるぞ」
「え! 恥ずかしいです! 拭くもの、拭くもの……」
「ほら、これで拭け」
俺はアイスと一緒にもらっていた個包装のウェットティッシュを差し出した。
「わぁ、気が利きますね! ありがたくいただきますっ!」
後輩女子こと小倉は、丁寧に口元を拭うと、それからすぐにアイスを食べ終えた。
かなり満足したのか、幸せに満ちた表情を浮かべている。
「佐山先輩、ごちそうさまでした! 美味しかったです!」
「そりゃよかった」
奢らされたのは不服だったが、すげぇ嬉しそうな顔だから許すことにした。
今回だけだからな。
「では、私はこれにて失礼します」
「もう行くのか?」
「なんですか、私に行ってほしくないんですか? 佐山先輩がキュートな私に求愛する気持ちはわかりますが、残念なことに今日は他校のイケメンとデートするんです。すみません」
「……そっか、楽しんでくれ」
「はいっ、めっちゃ楽しみます! 私の人生初彼氏ができたら報告しますね! では!」
小倉は、それはもう楽しそうなスキップで立ち去った。
他校のイケメンとかマジでどうでもいい。小倉の予定なんて微塵も興味はないし、ただなんとなく聞いてみただけだ。
「……帰ろ」
俺は少しぬるくなったスポドリ片手に帰路についた。
◇◆◇◆
翌朝。学校に行くと、俺の耳に妙なニュースが飛び込んできた。
「なあなあ、佐山」
「なんだ、五十嵐」
わざわざ机の前にまで来て話しかけてきたのは、俺にとって唯一の友人とも呼べる五十嵐だった。
イケメンでフレンドリーなクラスの中心人物ながら、なぜか地味な俺と馬が合うのでよく話す仲だ。
「一年の小倉さんって知ってる?」
「あー、うん。まさか、お前も惚れたのか? お前は彼女いるからマズイだろ」
ここ最近は二度も絡まれているので、忘れたくても忘れられなかった。
「確かにあの子は人気だけどそんなんじゃないよ」
「じゃあなんだよ。小倉がどうかしたのか」
「実はね、小倉さんが佐山と二人で仲良く話してるのを見かけたって噂を聞いたんだよ。コンビニで二人でアイスを買って、イチャイチャしながら盛り上がってたってね。この噂マジ? 付き合ってんの? いつから?」
「はぁ? バカいうな。昨日のアレは俺がたかられただけだ」
「だよねー。だと思った」
「……悪いやつだな、お前。俺みたいな地味なやつと小倉がそんな関係になるわけないってお前がよくわかってるだろ?」
からかい上手な五十嵐に対し、俺は少しムッとしてしまった。
「あははーっ、ごめんごめん! 怒らないで。本当はそんな噂なんかないから安心してよ。僕がたまたまコンビニで二人のことを見かけただけだからさ」
五十嵐はケラケラと笑い飛ばして釈明した。そんな噂がないならよかった。安心だ。
「……どこから見てたんだよ、全然気づかなかったぞ」
「反対側の道路を歩いていたら本当に偶然見かけただけだよ。佐山が異性と話すなんて思わなくて驚いたけど、まさかその相手も一年女子一番人気の小倉さんだとはねぇ……本当になにもないの?」
「ない。そんなこと小倉の前で言うなよ? あいつは多分面食いだからイケメンにしか興味ないし、俺に話しかけてくるのは揶揄うためだけだからな」
小倉が物語の主人公格なのだとしたら、俺はモブキャラで名無しの男だ。対等に渡り合える日は二度と来ないし、そんな展開は誰も望んでいない。
「ふーん……佐山自身がそう思ってるならいいけどさ。それより話戻すけど、小倉さんについて別の噂があるんだよ」
「……あれか、他校のイケメンどうこうの話だろう」
「おー、察しがいいね。実は、昨日の放課後に佐山と別れた後に、小椋さんが他校の男子とつるんでたらしいんだ。隣町の高校あるでしょ? あそこの三年生と夜遅くまで遊んでたみたいだよ。はちゃめちゃなイケメンくんらしくてね、みんな朝からその噂で持ちきりさ」
「それを俺に言ってどうするんだよ。誰とどう遊ぼうが小倉の自由だろ」
「んー、いや、ただ昨日は二人で仲良く話してたみたいだし、一応伝えておこうかなって思っただけだよ。あんまり気にならない?」
五十嵐なりの優しさだったようだが、あいにく俺は小倉への情は全くないし、能動的に何かをするつもりもない。
「……頭には入れておく」
「冷めてるねぇ……でもまあ、僕は嬉しいよ。孤独な佐山にも彼女ができるかもしれないんだからね。じゃあ、今日も孤独に学校生活を謳歌してねー」
「余計なお世話だ」
軽口を言い合って会話は終わった。
五十嵐はフランクな性格で人が良いから、俺に気遣って小倉の噂を教えてくれたんだろう。
最後のセリフは煽りとして受け止めておく。
俺としては何も考えるつもりはない。
いつも通り平穏に過ごすだけだ。
昼休みになると、俺は一人で教室を抜けて一年生の教室へ足を運んでいた。
なぜこんな場所に来たのかというと、理科室に落ちていた小テストの用紙を届けに来たからだ。
一年二組の男子生徒の名前が書いてある。
拾った時に理科の先生に渡してみたが、忙しいから自分で届けろと断られてしまった。
なんで俺が行かなきゃならないんだよ。
知り合いがいないアウェイの地にたった一人で乗り込むのはさすがに気まずいぞ。
「……ここか」
俺は一年二組の前に到着すると、ドアの隙間から教室の中を覗いた。
各々が昼食を摂っている。
声をかけるのは憚られたので、俺はドアの前で立ち尽くしていた。
数十秒ほど、どうしようかの悩みあぐねいていると、背後から唐突に肩を突かれた。
誰だ?
「——佐山先輩? 私のクラスに何か用事ですか?」
振り向くと、そこには噂の小倉由花が立っていた。
ナイスタイミングだ。よくぞ現れてくれた。
「小倉。ちょうどよかった。これをあげよう」
「はい? なんですか、これ」
小倉は小テストのペラ紙を受け取ると、キョトンとした顔で首を傾げた。
相変わらず愛嬌たっぷりなあざとい仕草だが、今日はどことなく疲れた顔つきだ。
「理科室で拾った小テストだ。このクラスのやつのもんだろ?」
「そうですね。本人に渡しておきますか?」
「頼めるか」
「お任せください!」
親指を立てて快諾してくれた。さすがは人気者だ。相手が男子なら誰彼構わず話しかけるスキルを持っているから頼りになる。
「助かる。それより……」
「なんですか? 私の顔をじっくり見て……とうとう惚れちゃいましたか?」
小倉はわざとらしく口元に両手をやった。
きゃはっ☆って感じのギャルポーズ的なアレだ。
「……」
「あの、さすがに見つけすぎでは……? 照れちゃいますよ……佐山先輩?」
俺は間抜けなギャルポーズには目もくれず、小倉の顔を凝視した。
照れられても困る。俺にそんな意図はないし、単にお前の具合が気になるだけだ。
「……小倉。お前、ちょっと疲れてないか?」
「え?」
とぼける小倉だが、よく見たらわかる。
化粧でうまく隠しているように見えるが、小倉の目の下には薄いクマができていて顔色も少しだけ悪かった。
「あまり寝てないのか?」
「よく分かりましたね。ちょっとキモイかもです」
「すまん。何かあったのか」
「んー、まあ……実は色々あって、私ともあろうパーフェクトキューティーガールもほんの少し疲れてます」
色々の中身を聞く気はない。
ただ小倉が自分の体の異変に気がついているのならそれで問題ない。無意識にげっそりしているなら保健室ルートだったが。
「ふーん。体には気をつけろよ、じゃあな」
「えー、もう行くんですか?」
俺は軽く労いの言葉をかけて踵を返したのだが、小倉に手を引かれて立ち止まった。
ナチュラルにお手手を繋いでくるんじゃない。やわらかくてびっくりしちゃうだろ。
「昼休みは一時間しかないし、俺も早く教室に戻って飯を食わないといけないからな」
こんな場所で時間をロストするのはもったいなく感じる。
空腹は限界に近いし、早く朝コンビニで買った菓子パンで腹を満たしたい。
「……どうせなら一緒に食べませんか?」
「小倉と? なんで?」
俺は嫌な表情を隠さなかった。臨機応変なポーカーフェイスのオンオフが求められる。
多分、今はゴキブリを発見したときみたいな顔だと思う。
俺だったら、話し相手にそんな顔をされたら嫌だ。小倉も嫌がると思う。早く諦めろ。
しかし、小倉はめげない。しょげない。むしろ、どこか悩ましげな様子で言葉を続けた。
「なんでって……実はちょっとだけ込み入った訳があるんです。佐山先輩はまだ何も知らないでしょうけど、昨日ややこしいことになっちゃって困ってるんですよ」
「……俺なんかに頼っても役に立たないと思うぞ」
「別に佐山先輩を利用するつもりはないので、少し話を聞いてくれるだけでいいですよ。他に話せる人もいないのでお願いします」
「わかった。じゃあ、体育倉庫に来てくれ。あそこはひと気がないし、話をするにはちょうどいいからな」
そこまで言われたら断るわけにもいかない。
俺のとっておきスポットに招待しよう。体育館の真隣にある体育倉庫は何よりも涼しい。少し埃っぽいのが難点だが。
「りょーかいです! 準備できたらすぐ向かいますね!」
小倉はそれだけ言い残して教室に戻っていった。
知らん一年連中にちらちら見られはしたが、変なやり取りではなかったから問題はないと思う。目立つことはなかった。
俺もとっとと菓子パンを持って体育倉庫に向かうか。
どうせ小倉が話したいことっていうのはわかってる。今朝、五十嵐に聞いた例の噂とやらだろう。
何があったか知らないが話だけでも聞いてみるか。
◇◆◇◆
体育倉庫は予想通り快適だった。
つい最近新品になったばかりのマットがあり、その上は清潔でふかふかで最高だ。
しかも、涼しい。窓が大きく開け放たれ、尚且つエアコンのある図書室と隣接しているからか、古い体育館の倉庫には冷たい隙間風がビュービュー入ってくる。最高だ。
一人で過ごすにはうってつけの穴場だろう。
まあ、今日は残念ながら珍客がいるのだが。
「で、話ってなんだ?」
菓子パンを貪りながら小倉に尋ねた。バターとチーズとハムが乗っかってる油まみれの菓子パンだ。安くてジャンキーで最高だ。
「んーーーーー……ここにきて迷いが出てきました」
小倉は六段くらいの跳び箱の上に座り、足をぶらつかせながら言った。
「おいおい」
「聞きたいですか?」
「……」
焦らされてしまうと聞きたくなってしまうのが人間の性だ。
聞きたくない! と、はっきり言えない自分が悔しい。
「そんなに聞きたそうな顔をされたらもう私も話すしかないじゃないですか~。仕方ありませんねぇ~」
小倉は渋みのある俺の顔を見て心を改めたらしい。
さっきは悩ましそうにしていたのに、今度はノリノリになった。
感情の起伏がわかりやすいから話しやすい。
「結構大事な話なのか?」
「まあ、そうですね……昨日、佐山先輩と別れた後に他校のイケメンと遊んだのは知ってますよね?」
やっぱりこの話か。テキトーに相槌を打っておこう。
「ニッコニコでスキップしてたから覚えてるぞ」
「恥ずかしいのでそれは忘れてください! それで、その他校のイケメンがちょっと厄介なんですよ」
「ふーん、どんな感じに厄介なんだ」
「ストーカー気質っていうか、じっとりねっちょりしてるっていうか、なんかこう……しつこい性格なんです」
「危ないやつなのか?」
「私の対人センサーは危険信号を出してます! 見た目は良い感じなのに!」
小倉はほっぺたをぷっくりと膨らませていた。不満そうにしている。性格はアレだったのかもしれないが、噂通りのイケメンではあったのだろう。
「お前の好みは知らんが、なんで相手がストーカー気質だってわかったんだ? 嫌なことでもされたのか?」
「もちろんです。まず、勘違いが多すぎます! ちょっとボディタッチしただけで腕を組もうとしてきたり、カラオケで二人きりになったら肩を寄せてこようとしたり、そんな感じでグイグイこられるのは嫌なので冷めちゃいました」
「……他には?」
最初はテキトーに流すつもりでいたが、話を聞くにつれて俺も言いたいことが続々と湧いて出てきた。
まあ、まだ何かありそうだし、まずは聞いてみることにしよう。
「えとえと、試しに上目遣いで甘えてみたら顔真っ赤になっちゃったり、パフェをあーんして食べさせてあげたらデレデレニヤけたり……とにかく態度が露骨なんです。完全に惚れられた感じですね」
「へー」
「なんですかその冷めた反応は!」
ドライな相槌を打ったのがバレバレだったらしく、小倉はぷんすか怒りながら前のめりになった。ぶらつかせる足の速度は次第に速くなっている。
「いや、なんでもない。とにかくお前はそんなイケメンの反応を見てガッカリしたんだな?」
「はい。私に対して簡単になびきすぎです!」
「ストーカー気質ってのはこれに関係してるのか?」
「そうなんです! 本当は夜の七時までには帰りたかったのに、なかなか解散してくれなくて、結局は十時くらいにやっと離れられました。その間に好きな男の子のタイプとか歴代彼氏はどんな人なの~とか色々質問攻めされて……もうクタクタですよ。
これって立派なストーカー気質ですよね? 佐山先輩もそう思いませんか?」
小倉は呆れた面持ちで同意を求めてきたが、はっきり言って俺には彼女の気持ちが全くわからなかった。
だって、しょうがなくない?
というか、小倉が悪いとすら思える。
他校のイケメン先輩は男として正常だろう。
こいつは何か勘違いしているようだから、はっきり教えてやるか。
嫌われてもいいし、なんかもう我慢できない。
「はぁぁぁ……小倉」
「なんですか。深いため息なんてついて」
「お前は何もわかってないな」
「はい?」
「そもそも発端はお前だろ。なんのためにイケメンに自己アピールをしたんだ? ボディタッチをしたり、上目遣いで甘えてみたり、二人きりでカラオケに行ってみたり……それってお前がイケメンのことを好きだからやったんじゃないのか?」
小倉のようなタイプなら、嫌いな相手にそんなことをするわけがない。分別があるはずだ。
「別にあの人のことを好きにはなってませんよ。だって、私って一目惚れはしないタイプじゃないですか?」
「うん、まあ、知らんけど。じゃあ、なんでそんなことしたんだ?」
「相手のことを確かめるためですよ。そんなことに簡単に惑わされる男の人は信用できませんから! 現に私はもうあの人のことを信用できなくなりましたもん!」
極端だ。極端すぎる。それに、間違っている。
そんなことで相手を知ることはできない。
「イケメンがほいほい惚れてきたから興味を失った、そういうことか?」
「まとめるとそういうことになります。私は誰よりも一番可愛い自覚がありますけど、そんな私に一目惚れするってことは顔しか見てないと思うんです。みんなそうでした。私の好きな食べ物とか好きな色とか趣味とか、何にも知らないし知ろうともしないんですよ。
だからお付き合いする相手は、私の内面を見てくれる人じゃないと嫌なんですよ。わかりますか?」
「はぁぁぁぁぁ……」
「さっきよりも深いため息ですね。しかも、私に対して何か言いたそうですし」
俺のため息が露骨すぎたのか、小倉は不貞腐れたように睨みつけてくる。
「はっきり言うが、お前はバカだ。自分のことも、相手のことも何もわかっていない」
後先なんて考えていられない。
無自覚に男を沼らせるこいつを見過ごすわけにはいかない。他校のイケメンが堕ちてしまったように、被害者が増えるのも時間の問題だ。
「っ! 急になんですか! ムカつく言い方ですね!」
「小倉、思春期の男子高校生がどんな気持ちで日々過ごしているのか知ってるか」
「知るわけないじゃないですか、私は女ですし」
小倉はムスッとして答えた。
「だよなぁ。思春期の男ってのはアホなんだ。視線は女子の胸に勝手に誘導されるし、大きなお尻があればついつい目で追ってしまう。
異性に話しかけられたら心の底から嬉しくなるし、ボディタッチなんてされたら勘違いしちまうんだ。あれ? こいつ俺のこと好きなんじゃね? って具合にな」
淡々と説明したが、俺だって思春期の男子高校生だ。
当然、悶々とすることはあるし、異性への興味も強い。
だが、それはこの年齢なら仕方のないことだ。日常生活の一部として制御するしかない。
だって保健の授業でそう教わったもん。
無論、小倉のような破壊者がいたら別の話だが。
「……佐山先輩は私が悪いって言いたいんですか? イケメンのあの人があんな風になったのも私のせいですか?」
小倉はおもむろに跳び箱から飛び降りると、こちらに近寄ってきた。
可愛らしい怒りではなく、きちんと眉を潜めて不満を露わにしている。
予想に反して、俺が全く味方になってくれなかったからだろう。
だが、最後まで聞いてほしい。
解決方法は簡単なんだ。
「一つ勘違いしてほしくないが、お前はお前が思うよりもずっと可愛いんだ。背が低くて顔が整っていて髪もサラサラで綺麗だ。おまけに愛嬌があって声も心地良い。たとえ嘘でも、そんな天使みたいな女子に言い寄られたら、どんな男も、さすがのイケメンでさえも、全員がイチコロだ。勘違いしちまうのはしょうがないんだよ。内面を知る前にその可愛さに目がいくのは必然なんだ。わかるか?」
「……」
俺の言葉を受けた小倉は途端に顔を朱色に染めると、ぷるぷると震えながら俯いてしまった。
「おい、聞いてるか?」
「それは、佐山先輩もそうなんですか?」
「ん? どういう意味だ?」
「だから! 佐山先輩も……私がそういうことをしたら、好きになっちゃうんですかって聞いてるんです!」
小倉は顔を勢いよくあげた。
潤んだ瞳、赤らんだ顔、力の入った口元。嘘が本当かわからないが、いつもより凄みがあった。
「……うーん、俺は……わからない。でも、小倉に手を引かれたり、今みたく上目遣いで見つめられると、少しだけ気持ちが変になる。多分、俺もお前が嫌っているような人間の一人なんだろうな」
嘘偽りなく答えた。
小倉の些細な仕草一つで心が動きかける自分が情けないが、それはきっと他の男子も同じなのだろう。
確かに小倉の言いたいこともわかる。すごくわかる。
人を見た目だけで判断するなってのは、小倉くらいの可愛いやつになると身に沁みて思うことなのだろう。モテモテだからこそ痛感する部分なのかもしれない。
でも、自分の可愛さや魅力を理解しきれていないうちは、そんな誤った方法でこれからもバカな男を堕としてしまう。
「あともう一つ付け加えるなら、他校のイケメン先輩は正常だってことだ」
俺は言葉を続けた。少し空気が張り詰めているのを肌身で感じる。
「佐山先輩は……いえ、なんでもありません」
小倉は何かを言いかけたが口をつぐむと、膝を曲げてしゃがみ込んだ。肩で息をして下に視線を落としている。
怒っている様子はないが、普段の余裕そうな雰囲気ではなかった。その心情は俺にはわからない。
しばし沈黙の時間が流れた。
おそらく三十秒くらい経っただろうか。
「……佐山先輩は、私のこと可愛いって思いますか?」
小倉はゆっくり立ち上がると、今度は俺から体を背けて尋ねてきた。
何を聞かれているのか、一瞬理解できなかった。
改めて伝えるのは少し恥ずかしい。
だが、俺は隠すことはしなかった。
「ああ。小倉は可愛いと思う」
「ほんとーに?」
「本当に」
決して嘘ではない。世間一般的にも、俺の目から見ても、小倉は可愛い。
校内でも上位の可愛さだと思う。
まだ彼女の内面なんて全く知らないが、顔だけで言えば間違いなく可愛い部類だ。
「……そうですか。佐山先輩から見ても私は可愛いんですね。じゃあ、私のことは好きですか? みんなと同じように一目惚れはしてませんよね? イケメンのあの人と同じようにデレデレして来ないんですか? だって気持ちが変になるんですよね?」
小倉は矢継ぎ早に言葉を吐き出した。
正直答えにくい。でも、ここも素直に答えるべきだと思った。
小倉の真意が気になるし。
「俺はお前に一目惚れはしてないが、別に嫌いなわけじゃない。むしろ、年が違うのにこうして思ったことを口できる相手は中々いないだろうし、どちらかと言えば好きなんだと思う……悪い、気持ち悪いこと言ってるよな」
はっきり答えたかったとはいえ、俺の発言はいささか達観しすぎて気持ち悪かった。
恋人でもそういう空気でもない相手にこんなことを伝えるのは、どう考えてもお門違いだ。言葉にして後悔した。すまん、小倉。いつものようにからかって罵ってくれで構わない。
しかし、そんな俺の申し訳なさとは裏腹に、小倉は力強く首を横に振った。
「……いえ、気持ち悪いだなんて一ミリも思ったことありません! というか、佐山先輩、よく人たらしって言われませんか?」
「友達が一人しかいない俺に人をたらす才能なんてない」
「そうですか」
小倉はここにきて初めて笑ってくれた。くすくすと小さな笑みではあったが、友達が一人しかいない俺にウケたらしい。
空気が少し温和になった。
よかった、友達一人しかいなくて。ありがとな、五十嵐。
「……佐山先輩」
五十嵐への感謝を胸に秘めていると、唐突に名前を呼ばれた。
小倉の背中が小さく見える。
「なんだ。大丈夫か? 声が変だぞ?」
俺の名前を呼ぶ小倉の声は少しばかり揺らいでいた。ふにゃっとして力の抜けた感じだ。
「さやませんぱい」
ゆっくりと静かに振り向いた小倉唯は、どこか虚な目をしていて、ぼーっと熱のある視線を向けてきた。
明らかに変だった。さっきまでの平常な感情ではない。
「おい、なんか熱っぽくないか?」
向かい合う小倉の顔は真っ赤だった。
彼女はふらふらとした足取りで近づいてくる。
言い方は悪いが末期のゾンビのような、おぼつかない感じだ。
「わたし、わたし……」
小倉は荒れた呼吸で何かを言おうとしていた。
「一回落ち着け」
虚な瞳を見つめて言葉をかけた。
「……わたしは、さやませんぱいのこと……」
制止も虚しく、小倉はバランスを崩して俺の胸に飛び込んできた。
咄嗟に肩を掴んで支えたが、体は高い熱を持っていた。
昨日の夜は帰りが遅かったみたいだし、疲れが溜まっていたのだろう。
大丈夫なんて言っていたが、強がりだったみたいだな。
「全く……」
俺は小倉をおんぶして保健室へと向かった。
人目に着いたら最悪だと思っていたが、幸いにも誰にも出くわすことなく到着した。
保健室が体育館から近い位置にあって助かった。
「先生、熱があるみたいなのでベッドで寝かせてあげてください」
保健室の女の先生は「あらあら」と口にしてニヤけていた。
なんだその茶化すような”へ”みたいな形のスケベな目は。
「……うふふふふ、奥のベッドに寝かせてあげてちょうだい」
「わかりました」
俺は小倉をベットの上に寝かした。
「こいつは一年二組の小倉です。あとはお願いします」
「はいはい。もうお昼休みは終わっちゃうから、彼氏さんは授業に行きなさいね。心配だからって覗き込んだらダメですからねー?」
「小倉が起きてる時にそんな冗談言ったら怒られそうなんで勘弁してくださいね。では」
俺はテキトーに返して保健室を後にした。
煽ってくる保健室の先生はちょっと苦手だ。
俺と小倉がカップルに見えるなんてありえない。
バカにされてるのは明らかだった。
「……ったく、結局、あいつは俺にあの話をしてどうしてほしかったんだ」
他校のイケメンがストーカー気質なんかではないのは確かだが、話を聞いて何が進展したのかはわからなかった。
俺が単純に小倉由花という女子の魅力に取りつかれただけだ。
今も少し胸がドキドキしている。おんぶしたときに耳に掛かる艶かしい吐息と、甘い匂いが忘れられない。
俺だって、今のようなフランクな関係ではなくて、もしも出会い方が違っていたら彼女のことを好きになっていたかもしれない。
それくらい、小倉由花という女子には魔性の魅力があった。
◇◆◇◆
ある日の午後一時ごろ。
夏休みを目前に控える中で、一年生と二年生の合同プール授業が開かれることになった。
俺が一年生の時はプール授業自体なかったはずなのに、まさかまさかの初プール授業は予想外の合同ときた。
厄介だ。
だって、俺、泳げないんだもん。
しかも、プールの授業と銘打っているが、担任の話によればリフレッシュ目的らしい。
堅苦しい授業は全くなく、基本的にはルールの範囲内でフリータイムなんだとか。
なんだよそれ、屋内プール施設を貸し切ってまでやることか?
最悪だな。フリータイムならぼっちで過ごすのが確定してしまう。それは別にいいんだが、逃げ場がない。ここでは本を読めないしスマホも見れない。
どうする?
いや、考えるまでもないか——うん、サボろう。
捻挫したとかテキトーに言えばいいや。
「……欠席するのは俺だけか」
というわけで、俺は広大なプールを一望できる場所に来ていた。
展望台というのか、高台というのかわからないが、前方向がガラス張りになっている控え室的な部屋だ。例えるなら、アメリカの刑務所にあるような監視塔みたいなやつ。
中はエアコンが効いて温度はバッチリだし、ウォーターサーバーとソファがあって気楽に休める。
おまけに体育の授業と扱いが一緒だからか、制服ではなくジャージで過ごせるのも最高だ。
「誰もいないって最高じゃん」
まさかの欠席者は俺一人だけだった。
一、二年生合わせて百をゆうに超える数の生徒がいるのにもかかわらずだ。
まあ、こんなに広い屋内プールだし、名目上は授業だが中身は遊びみたいなもんだし……そりゃみんな乗り気になるよな。
「ふぅ、最高だなぁ」
ソファにもたれかかって息をつく。冷たい水で喉を潤し、壁掛け時計の心地よい秒針の音に酔いしれる。
眠くなってきた。一人だからぐっすり眠ってしまうのも手だな。
「……」
目を閉じた。
徐々に睡魔が襲ってくる。
多分、一瞬で眠れる。
「……ん?」
その瞬間だった。出入り口の扉が静かに開かれる音がした。
俺はすぐに目を開け姿勢を正すと、おもむろに扉の方に目を向けた。
すると、そこにはなぜか小倉の姿があった。制服でも水着でもなく紺色のジャージを着ている。下はハーフパンツ、上はジップを上まで上げた長袖だ。
彼女は恐る恐る部屋に入ってくると、気まずそうな顔でこちらを見た。
「あ……佐山先輩もいたんですね」
俺も少しだけ気まずかった。実を言うと、体育倉庫で話したあの日以来、彼女とは顔を合わせていなかったからだ。
まあ、普段から話す機会が多いわけではないし、今回でまだ四回目くらいだが、変に意識してしまい会わない期間が気まずさを募らせていた。
「えと……佐山先輩はどうしたんですか?」
しんとした空気になる前に、小倉が早口で尋ねてきた。
「あー、俺は……まあ、色々だな」
「サボりですか?」
「包み隠さず言うなら、そんな感じだ」
「私と一緒ですね」
「そうなのか?」
「はい。全然やる気になれなくて、先生に言って抜けてきちゃいました」
小倉はイタズラな笑みを浮かべると、俺の向かいのソファに座った。
全然元気そうだ。あれから見かけてなかったが、体調不良は治ったみたいだな。
「体は平気か? っていうか、自分が倒れたこと覚えてるのか?」
「気がついたら保健室にいたんですけど、先生に聞きました。佐山先輩が運んでくれたんですよね……ありがとうございます。お礼伝えるの、遅くなっちゃいました」
「気にすんな。それより、やっぱり体壊してたんだな」
「実はあの日は起きた時から怠かったんですよね。そのせいで倒れちゃいましたし、その前のやりとりの記憶が曖昧です。私、変なこと言ってませんでしたか? 佐山先輩に大事なことを伝えたような気がするんです」
俺の覚えている限りだと、大事なことは特に伝えられてなかったと思う。
倒れる直前の小倉は俺の名前を連呼するだけだったし。別におかしなことではない。体がきつくて介抱を求めていただけだと思う。
「……変なことは特に言ってなかったぞ。どの辺りの記憶がないんだ?」
「佐山先輩と少し言い合いになりそうだったのは覚えています。わからないのは最後の倒れる直前だけです。その前の記憶ははっきり残ってます」
「これまたピンポイントだな。じゃあ、嫌な気持ちの方が大きいかもな。俺のことを嫌いになっただろ」
体育倉庫での一幕は、俺的には小倉を思った言葉だった。
彼女からすれば違うかもしれない。
「……正直、あんなこと言われると思ってませんでした。私が相談したらみんな慰めてくれるのが当たり前だったので変な感じです」
「そっか」
「でも、嬉しかったです。あれは私のことを考えてくれてたってことですもんね?」
「変な意味はないが、その解釈であながち間違ってないと思う」
お前をことを考えていた……なんてキザな言葉は出てこなかった。遠回しで情けない言い回しになってしまう。
だが、それでも小倉は嬉しそうにはにかんでいた。
「やっぱり嬉しいです! なんか、ほっとしました! ずっと気になってたんです。私も少しムッてしちゃいましたし、そのせいで佐山先輩に嫌われてないかなって不安でした!」
「嫌われる? そんなこと気にしてたのか」
「そりゃそうですよ! 佐山先輩には嫌われたくないですもん!」
「っ……そうか」
つい嬉しさが込み上げてきそうになったが、ここで喜んでしまえば小倉に堕ちた他の男子と同じだった。
間に受けたら俺がバカを見る。
俺が小倉を好きになってはいけない。
「ところで……どうしてサボってるんですか?」
「んー、泳げないからなぁ、俺」
「なんか意外ですね。佐山先輩ってなんでもバランスよくできそうなイメージありましたけど。意外と不器用だったりするんですか?」
「俺は不器用だな」
不器用でありながらも、何もかもが下手だ。
勉強は並だが努力が苦手だし、方法を模索するのも下手くそだ。
もちろん人付き合いも苦手だ。こうして普通に話をできているのが奇跡だと思えるくらいには。
「私も不器用なので一緒ですね!」
「お前は器用だろ」
「いえ、そんなことないですよ。私は不器用だから間違ったことばかりやっちゃうんです。佐山先輩にあんなふうに言われなかったら、今頃もプールでおかしなことをしてたかもしれません」
小倉はジャージの上着のジップに片手を添えながら、照れ臭そうに笑った。
「なんだよ、おかしなことって」
「……知りたいんですか?」
「ん……まあ、可能なら」
よくわからなかったが、話ついでに気になった。
すると、小倉は恥ずかしそうに立ち上がると、ジップに手をやりゆっくりと下に下ろし始めた。
袖が長くて萌え袖になっており、それはわざとではない部分だからこそ、自然な仕草でいつもより可愛く見えた。
「なんで脱いでんだ? 暑いのか?」
「……まだわからないんですか」
疑問を投げる俺に対して、小倉は恥ずかしそうにジップを下ろしていく。
ここでようやく俺は気がついた。
「おい、こんなところで水着になるなよ!」
小倉はジャージの下に水着を着ていた。
それも授業用の地味なやつではなく、海に遊びにいくようなカラフルなビキニだった。
「どうですか? これでみんなの前に行ったら、多分めちゃくちゃ見られると思いますし、もっと私の可愛さが伝わると思うんです。そうすれば、一年生と二年生の男子の視線を釘付けにできますよね」
小倉はジップを半分まで下ろすと、ガラス張りの下に広がる景色を眺めた。
まるで過去の自分を天から俯瞰しているかのような口ぶりだった。
「でも、それはお前の外見の話でしかないな」
「その通りです。それは佐山先輩が教えてくれました。だからやめたんです。ああいうやり方で人の心を決めつけるのは……もう、やめにしたんです」
「そうか。俺の言葉とやり方が正しいのかはわからないけど、それで本当に好きな人が見つかるといいな。小倉の内面を見てくれるような人がきっといると思うから」
「……もう、います」
「え?」
「な、なんでもないですっ! それよりも! 連絡先交換しましょう!」
俺が言葉の意味を理解するよりも先に、小倉は慌てふためいて話をかき消し、トンチンカンなことを言い始めた。
「スマホは学校だぞ」
「そ、そうでした……」
「どうした? また顔が赤いぞ。先生に言って俺が付き添ってやるから学校に戻るか?」
俺は立ち上がり小倉と視線の高さを合わせた。
間近に顔がある。パチクリと高速で瞬きをしており、長いまつ毛がよく見える。
そんなことより、勘違いをして恥ずかしがっているにしては顔が赤すぎる。
やっぱりまだ体調不良は治っていないのかもしれない。
もう一度、保健室送りにした方が良さそうだ。
「大丈夫ですから! ほんとーに! 私は平気です! ただ、話してたらちょっと暑くなっただけなので、お水もらいますねっ!」
小倉は途端に大きな声を張り上げると、なぜか俺の紙コップを手に取りぐいっと水をあおった。
もう様子がおかしいのは目に見えている。
「ぷはぁっ! これでもう大丈夫です!」
ぬるくなりかけた水を飲んでスッキリするわけないが、満足そうにしているからもういいや。
「元気になってよかったな」
「はい」
小倉は満面の笑みを浮かべていた。
とことこと歩いてきて、なぜか俺の隣に腰を下ろす。
二人掛けのソファだから少し狭い。
「……向かいのソファはガラ空きだぞ」
「ここがいいんです。今思えば、二人きりで話す機会はたくさんありましたけど、お互いのことを知る機会はなかったですよね。プールの時間が終わるまでまだありますし、よかったらたくさん話しませんか?」
「わかった。でも、隣に座る必要はあるか?」
やはり気になる。甘い匂いがするし、肩が少し触れ合っている。心なしか小倉が俺側に傾いている気がするし……色々と落ち着かない。
「嫌ですか?」
「嫌ってことじゃなくて……なんか距離が近いから少し、な」
俺は何とかはぐらかしたが、心臓は高鳴り続けていた。
そして、こう言ってしまえば小倉がバカにしてくるのもわかっていた。
どうせ「あれあれー? 恥ずかしんですかー? 佐山先輩ってば、私のこと好きになっちゃいましたかー?」って言われると思う。
小倉は男を判断する例のやり口をやめたとは言っていたが、俺をバカにするのは別の話だろうしな。
「……」
俺の予想に反して、小倉は俯いて黙りこくった。
「小倉?」
「あの……恥ずかしいのは私も一緒です。だから、気にしないでください」
「え?」
「……佐山先輩だけじゃありませんから」
「そ、そうか」
意外な反応だった。というより、予想外だ。
変な空気になっちゃった。ぽわぽわしているというか、なんというか……温かくもあり、柔らかくもあり、それでいて刺激的な肌がチクチクするようなイメージだ。
どうしよ。この空気。俺から何か話すべきだよな。
俺は意を決して口を開いた。
「な、なぁ——」
「——おーい、二人とも! どうせこんな場所にいても暇だろうし、今日はもう先に帰ってもいいぞー。みんなには内緒で特別だからな」
俺の言葉を遮るように、タイミングよく先生が入ってきた。
まだここにきて十分くらいしか経ってないが、まさかの帰宅の許可が出た。
「え? いいんですか? 佐山先輩、やりましたね!」
「お、おう。そうだな」
「学校に荷物やら何やら取りに戻ったら、すぐに帰るんだぞ。ちなみにジャージのままだから寄り道は禁止だ。わかったなー」
困惑する俺と小倉をよそに、先生はそれだけ言い残して早々にいなくなった、
本当に帰れるらしい。まだ時間は一時過ぎだ。
寄り道禁止とはいえ、家に帰ればめちゃくちゃゆっくりできそうだ。
「……帰ろうか」
「そうですね」
俺は小倉と共に簡単な荷物をまとめると、屋内プールを後にして学校へと戻った。
何気ない雑談をしながら校門をくぐり、それぞれの教室へ向けて歩き出す。
そこで教科書やら何やらとスマホを回収する。
あとはとっとと家に帰るだけだった。
しかし、校門に戻ると、俺たちは何の約束もしていないのに鉢合わせた。
違う。お互いがお互いのことを考えていたのかもしれない。
俺は小倉を、小倉は俺を、それぞれが無意識のうちに一緒に帰ろうと心で思っていたのだろう。
「……行こうか」
「はい」
ごく自然に、俺は手を伸ばしていた。
そして、ごく自然に、小倉は俺の手を取った。
いくら歩こうとも、繋がれた手の手は離れなかった。
暑い夏の日のじめっとした気温が気にならないくらい、気分は高揚していた。
それは俺だけではないと思う。だって、横目で見た小倉の顔は緊張しているみたいだったし。
だが、会話はない。
気がつけば、俺が小倉と最初に出会った公園の前にいた。
「この公園、俺が初めてお前に声をかけた場所だな」
「失恋した私がベンチで泣いてたんですよね。今思い返したら、なんであんなに凹んでたのかわからないですけど」
「ちょっと座って休もうか」
「そうですね」
俺は小倉と共にベンチに腰掛けた。
最初の頃とは違い、二人の間に距離はない。
「小倉」
「なんですか、佐山先輩」
「……自分語りで申し訳ないんだけど、俺、今まで好きな人とかできたことなかったし、そういうのを避けて生きてきたんだ」
「そうなんですか」
「うん。あんまり他人に興味がないからだと思う。友達だって一人しかいないし、俺はずっとそういうもんだって思ってたから」
一人でいるのはむしろ好きだ。
誰とも話さなくたって不満はない。
ただ小倉と出会ってからは、ふとした拍子に他の考えがよぎることがある。
その答えはもうわかっていた。けど、俺にとっては考えるだけでも難しく思えるし、無縁の世界すぎて頭を抱えたくなるほどだった。
「佐山先輩は、変わりましたか?」
「……変わったな。少し前とはだいぶ違う気がする」
不器用でぶっきらぼうで、バカな俺でも自分に起きた変化がわかる。
「何が違うんですか?」
「——いいなって思える人を見つけたんだ——」
「…………」
「その相手を見た時、一目惚れはしなかったし運命を感じることもなかった。でも、時間を共に過ごすにつれて、一つ気がついたことがあった。
俺はその子といる時は自分らしさを出せるような気がしたんだ。普段は冷静を装ってるけど、その子の前なら感情を出せたし、言いたいことを口にできた。行動に移して手を握れた。伝えたい思いを伝えられた。
そして……今は、一緒に過ごせて幸せだって思ってる」
もう迷いなんてなかった。全く躊躇する気持ちもなかった。
むしろ、この思いを早く伝えたかった。
「俺は——小倉由花という後輩のことが好きになっちゃったみたいだ」
あざとくて計算高く見えるけど、実は不器用な一面があって間違った選択をする。
照れや恥ずかしさを感じるとすぐに顔が赤くなり、突拍子もない行動を取る。
でも、その中にも愛嬌や愛らしさは滲み出ていて、取り繕ったあざとさなんかなくても、誰よりも可愛かった。
それは見た目だけでじゃなくて、彼女があまり表に出してこなかったであろう内面の部分もそうだ。これからもっと知っていきたいと強く思う。
「やっぱり、俺はお前のことが好きだ」
「……せん、ぱいっ……」
小倉は驚いたように俺を見つめていた。
以前まで頻繁に見せていたあざとい笑顔も、からかうような軽口も、今は一切ない。
その澄んだ瞳が俺の言葉を真っ直ぐに受け止めているのが分かる。
「……小倉?」
声をかけると、俺の手を握る力が強くなった。少しだけ俯いている。
快活で活発で、俺なんかと話してくれる、そんな彼女からは想像もつかないような、どこか頼りない仕草だった。
「……私なんかでいいんですか?」
「どういう意味だよ」
「佐山先輩は見た目こそイケメンには及びませんけど、話してみるとすごい良い人で、面白くて、優しくて、頼りになって……でも、私はそんな立派じゃないし、もっと良い人がいる気がしちゃうんです……」
小倉の声は震えていた。でもその目には、涙の代わりに意地が見える。
自分の弱さを認めながらも、それを克服しようとする力があった。
「……そう思うのはお前だけだ」
俺は体を小倉の方に向けると、そっと小倉の両手を包み込んだ。
彼女の手は夏なのに少し冷たくなっていた。
「俺には、泣いてるお前も、笑ってるお前も、全部がちゃんと見えてる。強がってるとこも、優しいとこも。だからこそ、俺はお前がいい」
小倉は目を見開いた。そして、少しずつその瞳が潤み始めた。
「……ほんと、ですか……?」
「ああ、本当に」
それ以上言葉を重ねる必要はなかった。
俺の手を握る小倉の力が、少しだけ強くなったことが答えだったから。
しばらくの沈黙の後、小倉が小さな声で口を開いた。
「……私、気づいたら先輩のことばっかり考えるようになってて……いつからかわからないんですけど、お話しするたびに少しずつ気持ちが変わっていたんだと思います」
小倉の頬が赤くなり、さらに言葉を紡ぐ。
「私も、先輩のこと、好きになっちゃいました」
彼女の言葉が終わると、静かな夏の午後の風が吹いた。
蝉の声が遠く響く中、俺たちはただじっと、その時を待った。
そして、俺は小倉の手をもう一度強く握り返した。
彼女がその手に応えるように握り返してくる。視線もこちらに向けられて、涙交じりの瞳で見つめてきた。
「じゃあ、これからも一緒にいてくれるか」
「はい……! 佐山先輩と、ずっと一緒にいたいです」
小倉の笑顔が太陽に照らされ、今までで一番輝いて見えた。
その瞬間、俺は彼女の唇を奪った。
俺は誰よりもつまらないプロフィールを持つ男という自負があった。
高校生活に華はなく、数少ない友人とごくたまに会話をして過ごす日々。
部活はせず、委員会も半分くらいは休み、テキトーにダラーっと生きている。
俺らしいと言えば俺らしい。
別に退屈はしてないし、癒しや華を求めることもない。ただただ平穏に過ごしたかった。
今の日常には十分満足していた。
「……にしても、暑いな」
くだらん俺の情報はさておくとして、今日はとにかくひどい猛暑日だった。
じめじめとした真夏の午後。
こんな日は、早く家に帰ってシャワーを浴びて、エアコンで涼みながら夜まで眠りたい。
あと五分も歩けば家に着く。
この公園を通り抜けるルートが最も早い。
「あちぃ……」
俺はいつものように公園を横切っていた。
日差しに耐えながら、のんびりと歩いて帰路に着く。
何の気なしに歩いていると、ベンチに座り泣いている女の子を見つけた。
「ん?」
ベンチに座っていると言っても普通に座っているわけではない。
ベンチの上で両足を三角に立てて座っており、真正面からは下着が見えてしまいそうな感じだ。
「大丈夫か?」
心配で声をかけた。別に他意はない。
制服を見るにうちの高校の生徒みたいだし、チラッと見えるリボンの色からして後輩の一年だろう。変なことをする気は一切ない。
「あ、あなたは……?」
後輩女子はマジ泣きしていたのか、こちらを見る顔はぐしゃぐしゃになっていた。
目が赤く腫れ上がり、口元は歪んでいる。
よっぽど悲しいことがあったのだろう。
「俺は佐山。龍ヶ崎高校の二年だよ」
「……先輩でしたか。てっきり不審者か変態かと思いました。私の体目的ではないんですね?」
「違ぇよ。普通に心配して声かけただけだ。なんか思ったよりも元気そうだし、俺はもう行くわ。暑いから早く帰れよ」
俺は早々に見切りをつけて立ち去ることにした。
よくわからないが、そんなに傷心しているわけではなさそうだったし、多分問題ないと思う。
しかし、此奴はそれを許してくれなかった。
「待ってください、佐山先輩」
後輩女子は俺の手首を掴んで離さない。
三角に畳んでいた足は地面についており、ホールドされた手首には力が込められている。
「なんだよ」
「せっかくですし、私の悩みを聞いてくださいよ」
「やだよ。今日は忙しいんだ」
俺は忙しい。帰ったら筋トレをして体を疲れさせた後に、たっぷり寝ないといけないんだ。
トレーニング後はベッドにダイブしてスリーピーに没頭するんだ。
「何か大切な用事があるんですか?」
「んー、まあな……詳しくは言えないけど」
「暇なんですね。じゃあ、隣に座ってください」
「……勝手に決めつけるなよ」
なにを言っても無駄なような気がしたので、やむなく後輩女子の隣に座った。
もちろん、それなりに間隔を空けて。
「で、悩みってなんだ? 手短に頼む」
「佐山先輩は私が泣いていた理由について気になりますよね。だから声をかけてきたんだと思いますし」
「別に気にならないけど」
「気になりますよね?」
「いや、本当にどうでもいい」
「気になりますよね? そうですよね?」
「……そうだな」
抗うのはやめた。
こいつ、頑固なタイプだ。
「ですよねー、やっぱり気になっちゃいますよね」
もったいぶりやがって。
「そうだなぁ……気になるなぁ、ほんとに」
「はいはい。そこまで気になるなら教えてあげます。実は失恋しちゃいまして……」
「へー、相手は?」
「お? 興味が出てきましたか?」
「違う。聞いてほしそうな顔だったから、気を利かせて聞いてみただけだ」
「ありがとうございます。お相手は三年生の先輩です。委員会で会った時に一目惚れしちゃったんですよね」
「カッコいいのか?」
「そりゃあもう、イケメンです。佐山先輩はヌボーッとしたゾンビみたいな顔ですけど、その先輩は爽やかでクールで背が高くてスタイルの良いイケメンなんです」
そう口にする後輩女子の目はキラキラしていた。俺の見た目の評価はさておき、その先輩は絵本の王子様みたいなルックスだな。
後輩女子は言葉を続ける。
「それでここからが本題なんですけど、その先輩とお話ししていい感じになれたのに、なんと先輩には彼女さんがいたんですっ! 先輩は私のことが好きって言ってくれたのに、まさかまさかの浮気だったんです! 他にも何人もの女子を口説いているらしくて、それを知っちゃったらもう悲しいですし、悔しいです! どう思いますか!?」
後輩女子はしくしくわんわん言いながら、大袈裟に泣く仕草を見せてきた。
多分、本当にショックを受けているんだろうけど、いかんせんあざとい。真っ先にそのことについて触れたかった。
しかし、根本的に考え方が違う気がしてそれが気になった。
「……それ、失恋なのか? だってお前はイケメン先輩のことをまだ恋愛的に好きだったわけじゃないんだろ?」
「確かにまだ好きという段階ではありませんでしたけど、恋が実らなかったので立派な失恋です。佐山先輩には無縁の感覚でしょうけど」
「まあ、俺の話は置いておいて、一般的に失恋ってのは告白して振られたりするもんを指すんじゃないか? 今回の相手は彼女持ちのだらしないやつなんだろ? むしろ付き合わなくて正解だと思うが……」
ショックを受ける気持ちはわからなくもないが、泣くほどのことかと思ってしまう。
今の話だけ聞くと悪いのは先輩一人だけだから、何も思い悩む必要はない。
「私の場合は意中の男の人が靡かなかったことがありませんし、これこそが失恋なんですよ! 私が浮気相手の一人にされかけたという事実が許せないので、必ず夢の中でぶっ殺です!」
「モテるんだな」
物騒な言葉が聞こえたがナチュラルに受け流し、後輩女子が喜ぶワードをチョイスした。
「そりゃーもう、私は中学時代からモテモテですよ。ラブレターなんてもらいまくってきましたし、先輩や後輩、同級生からも何度も何度も呼び出されて告白されたことがありますもん」
胸を張って偉そうにしてる。
まあ、納得だな。
確かに容姿は整ってるし。
見た目は小動物系とでも言おうか。
身長が低く、きゃるるんとした雰囲気がある。愛嬌抜群モンスターってところだ。
髪は明るめの茶髪だが不潔感はないし、顔は目鼻立ちがはっきりしていて声もあざと可愛い。
ただ、内面は読めない。ちょっと毒気がありそうだ。
「佐山先輩は本当に優しさだけで私に声をかけてくれたんですか? 下心はありませんか?」
「ない。早く帰りたい」
「……変な人ですねぇ……私と話して私のことを好きになったりしないですか?」
「しない。早く帰りたい」
マジでありえない。
名も知らぬ目の前の後輩女子が可愛いのは真実だが、今の俺は暑さと気怠さのせいでそんな気分じゃない。
早く帰りたいんだよ。解放してくれ。
「それはそれでムカつきますね」
「なんでだよ」
「でもまあ、他の男の人よりはマシですね。私って男の人からは人気なんですけど、結局は下僕みたいになっちゃって進展しませんし、モテすぎるから同性からは嫌われてるので……佐山先輩みたく普通に話せる人は珍しいです」
溜め息混じりに打ち明けてくれたけど、マジで興味ない。
「そうか。よかったな。で、話は終わりか? 俺は帰るぞ?」
「冷たいですねー、もっと優しくしてくださいよー」
「はいはい。次からはいい男を見つけられるように頑張れよ。少なくとも浮気なんてしないやつをな。ちなみに俺のおすすめは”とことんモテない男”だ。そういう奴は絶対に浮気をしないからな。じゃあな」
ぶーぶーごねているようだったが、俺は気にせず退散した。
優しいやつも浮気しないやつもたくさんいる。
選り好みしなければ、ぴったりの相手を探せるはずだ。
まあ、後輩女子の恋愛事情なんて心底どうでもいいんだけどね。
◇◆◇◆
数日後の放課後、
俺はいつものように家に直帰するつもりだった。
だけど、相変わらず外は暑いし、そのせいで喉がカラカラだった。
冷たいものでも飲みたいと思い、近所のコンビニに立ち寄ることにした。
店内に入ると冷房の風が体を包む。気持ちいい。
とりあえず飲み物コーナーに向かい、スポーツドリンクを手に取る。
ついでに次はアイスでも見て帰ろうか。
そんなことを考えながらアイスコーナーへ向かうと、そこに見覚えのある後ろ姿があった。
「ん?」
サラッとしたボブカットで茶髪の小柄な女子——こいつ、数日前に公園で泣いていた後輩か?
あまり人のことを覚えられない俺だが、こいつは性格や見た目に一癖あったので覚えていた。
名前は聞いてないから知らん。
真剣な顔でアイスのパッケージを見比べているみたいだが、早く退いてほしい。
「……」
俺は無言で背後に佇んだ。
どうせすぐに選び終えるだろうし、じっくりと待つ。
しかし、後輩女子は優柔不断なのか、「んー、んー!」と口ずさみながら悩みに悩んでいた。
遅い。パッと選んでほしい。
「スイカバーでいいだろ、夏だし」
俺はつい声をかけてしまった。
「えっ?」
後輩女子が振り返り、目が合う。
驚いたような表情だったが、すぐに満面の笑みを浮かべた。
「佐山先輩! こんなところで会うなんて運命ですね!」
「ただの偶然だろ」
「いえ、運命です! ちょうどお財布を家に忘れてアイスを買えなかったので、これは佐山先輩にご馳走してもらえる運命です!」
よくない運命だった。
アイスに悩んでいたわけではなく、食べたいのに食べられなくて困っていただけだったらしい。
「俺はご馳走しないぞ」
「いえ、運命です!」
なんだこいつ、押しが強すぎる。ぐいっと距離を詰めてくるぞ。やわな男なら勘違いして惚れてしまいそうだ。危ない。
「……どのアイスがいいんだ?」
何を言っても無駄だと思ったので、仕方なく今回だけは折れることにした。百円ポッチで満足してくれるならもうそれでいい。
「えーっと……バニラが無難ですけど、チョコの誘惑も捨てがたいですよね。佐山先輩ならどっちを選びます?」
「俺ならチョコクランキーのやつだな」
「えー、意外ですね」
「悪いか?」
食感が美味いんだよな、これ。
「いえ、もっと地味なの選ぶかと思いました。なんか私の方が地味なアイス選ぶのは癪なので、私も佐山先輩と同じやつにします」
「俺の影響受けすぎだろ」
「佐山先輩のこと、ちょっとだけ知りたいですから」
後輩女子はくすっと笑った。少しだけ子供っぽい無邪気な笑顔だ。
そう言いながら、彼女は俺にアイスを手渡すと、我先にと店の外へ出て行った。
なんだかんだで、自然に会話が続いているのが不思議だ。
俺は買い物を済ませてコンビニの外に出たが、相変わらず日差しが強い。
「ほらよ。今回だけだからな」
「はーい。ありがとーございまーす!」
めちゃくちゃ嬉しそうだった。お礼を言いながらも袋を開けてチョコクランキーアイスにかぶりついている。
「冷たくておいしいです!」
「そりゃあな。アイスなんだから」
続いて俺もアイスを口にした。やはり美味い。
「佐山先輩って優しいですねー」
「普通だろ」
おだてても何も出ないぞ。むしろ俺は無愛想でぶっきらぼうで優しくないとも思うし。
「そうですかね? っていうか、私の名前って知ってますか?」
「知らん」
「知りたくなりませんか」
「知りたくならないな」
どうせこれっきりの関係だし知る必要もない。一ヶ月も経てば綺麗さっぱり忘れる自信がある。
「小倉由花です!」
なぜか後輩女子は透き通る声色で名乗り始めた。
小倉って言うんだね、きみ。あんこみたいで美味しそうな名前だこと。
「……聞いてないんだけど」
「聞かせたんです!」
「あ、そう。小倉ね」
「特別に由花って呼んでもいいですよ?」
「遠慮しとく。それより、口にチョコついてるぞ」
「え! 恥ずかしいです! 拭くもの、拭くもの……」
「ほら、これで拭け」
俺はアイスと一緒にもらっていた個包装のウェットティッシュを差し出した。
「わぁ、気が利きますね! ありがたくいただきますっ!」
後輩女子こと小倉は、丁寧に口元を拭うと、それからすぐにアイスを食べ終えた。
かなり満足したのか、幸せに満ちた表情を浮かべている。
「佐山先輩、ごちそうさまでした! 美味しかったです!」
「そりゃよかった」
奢らされたのは不服だったが、すげぇ嬉しそうな顔だから許すことにした。
今回だけだからな。
「では、私はこれにて失礼します」
「もう行くのか?」
「なんですか、私に行ってほしくないんですか? 佐山先輩がキュートな私に求愛する気持ちはわかりますが、残念なことに今日は他校のイケメンとデートするんです。すみません」
「……そっか、楽しんでくれ」
「はいっ、めっちゃ楽しみます! 私の人生初彼氏ができたら報告しますね! では!」
小倉は、それはもう楽しそうなスキップで立ち去った。
他校のイケメンとかマジでどうでもいい。小倉の予定なんて微塵も興味はないし、ただなんとなく聞いてみただけだ。
「……帰ろ」
俺は少しぬるくなったスポドリ片手に帰路についた。
◇◆◇◆
翌朝。学校に行くと、俺の耳に妙なニュースが飛び込んできた。
「なあなあ、佐山」
「なんだ、五十嵐」
わざわざ机の前にまで来て話しかけてきたのは、俺にとって唯一の友人とも呼べる五十嵐だった。
イケメンでフレンドリーなクラスの中心人物ながら、なぜか地味な俺と馬が合うのでよく話す仲だ。
「一年の小倉さんって知ってる?」
「あー、うん。まさか、お前も惚れたのか? お前は彼女いるからマズイだろ」
ここ最近は二度も絡まれているので、忘れたくても忘れられなかった。
「確かにあの子は人気だけどそんなんじゃないよ」
「じゃあなんだよ。小倉がどうかしたのか」
「実はね、小倉さんが佐山と二人で仲良く話してるのを見かけたって噂を聞いたんだよ。コンビニで二人でアイスを買って、イチャイチャしながら盛り上がってたってね。この噂マジ? 付き合ってんの? いつから?」
「はぁ? バカいうな。昨日のアレは俺がたかられただけだ」
「だよねー。だと思った」
「……悪いやつだな、お前。俺みたいな地味なやつと小倉がそんな関係になるわけないってお前がよくわかってるだろ?」
からかい上手な五十嵐に対し、俺は少しムッとしてしまった。
「あははーっ、ごめんごめん! 怒らないで。本当はそんな噂なんかないから安心してよ。僕がたまたまコンビニで二人のことを見かけただけだからさ」
五十嵐はケラケラと笑い飛ばして釈明した。そんな噂がないならよかった。安心だ。
「……どこから見てたんだよ、全然気づかなかったぞ」
「反対側の道路を歩いていたら本当に偶然見かけただけだよ。佐山が異性と話すなんて思わなくて驚いたけど、まさかその相手も一年女子一番人気の小倉さんだとはねぇ……本当になにもないの?」
「ない。そんなこと小倉の前で言うなよ? あいつは多分面食いだからイケメンにしか興味ないし、俺に話しかけてくるのは揶揄うためだけだからな」
小倉が物語の主人公格なのだとしたら、俺はモブキャラで名無しの男だ。対等に渡り合える日は二度と来ないし、そんな展開は誰も望んでいない。
「ふーん……佐山自身がそう思ってるならいいけどさ。それより話戻すけど、小倉さんについて別の噂があるんだよ」
「……あれか、他校のイケメンどうこうの話だろう」
「おー、察しがいいね。実は、昨日の放課後に佐山と別れた後に、小椋さんが他校の男子とつるんでたらしいんだ。隣町の高校あるでしょ? あそこの三年生と夜遅くまで遊んでたみたいだよ。はちゃめちゃなイケメンくんらしくてね、みんな朝からその噂で持ちきりさ」
「それを俺に言ってどうするんだよ。誰とどう遊ぼうが小倉の自由だろ」
「んー、いや、ただ昨日は二人で仲良く話してたみたいだし、一応伝えておこうかなって思っただけだよ。あんまり気にならない?」
五十嵐なりの優しさだったようだが、あいにく俺は小倉への情は全くないし、能動的に何かをするつもりもない。
「……頭には入れておく」
「冷めてるねぇ……でもまあ、僕は嬉しいよ。孤独な佐山にも彼女ができるかもしれないんだからね。じゃあ、今日も孤独に学校生活を謳歌してねー」
「余計なお世話だ」
軽口を言い合って会話は終わった。
五十嵐はフランクな性格で人が良いから、俺に気遣って小倉の噂を教えてくれたんだろう。
最後のセリフは煽りとして受け止めておく。
俺としては何も考えるつもりはない。
いつも通り平穏に過ごすだけだ。
昼休みになると、俺は一人で教室を抜けて一年生の教室へ足を運んでいた。
なぜこんな場所に来たのかというと、理科室に落ちていた小テストの用紙を届けに来たからだ。
一年二組の男子生徒の名前が書いてある。
拾った時に理科の先生に渡してみたが、忙しいから自分で届けろと断られてしまった。
なんで俺が行かなきゃならないんだよ。
知り合いがいないアウェイの地にたった一人で乗り込むのはさすがに気まずいぞ。
「……ここか」
俺は一年二組の前に到着すると、ドアの隙間から教室の中を覗いた。
各々が昼食を摂っている。
声をかけるのは憚られたので、俺はドアの前で立ち尽くしていた。
数十秒ほど、どうしようかの悩みあぐねいていると、背後から唐突に肩を突かれた。
誰だ?
「——佐山先輩? 私のクラスに何か用事ですか?」
振り向くと、そこには噂の小倉由花が立っていた。
ナイスタイミングだ。よくぞ現れてくれた。
「小倉。ちょうどよかった。これをあげよう」
「はい? なんですか、これ」
小倉は小テストのペラ紙を受け取ると、キョトンとした顔で首を傾げた。
相変わらず愛嬌たっぷりなあざとい仕草だが、今日はどことなく疲れた顔つきだ。
「理科室で拾った小テストだ。このクラスのやつのもんだろ?」
「そうですね。本人に渡しておきますか?」
「頼めるか」
「お任せください!」
親指を立てて快諾してくれた。さすがは人気者だ。相手が男子なら誰彼構わず話しかけるスキルを持っているから頼りになる。
「助かる。それより……」
「なんですか? 私の顔をじっくり見て……とうとう惚れちゃいましたか?」
小倉はわざとらしく口元に両手をやった。
きゃはっ☆って感じのギャルポーズ的なアレだ。
「……」
「あの、さすがに見つけすぎでは……? 照れちゃいますよ……佐山先輩?」
俺は間抜けなギャルポーズには目もくれず、小倉の顔を凝視した。
照れられても困る。俺にそんな意図はないし、単にお前の具合が気になるだけだ。
「……小倉。お前、ちょっと疲れてないか?」
「え?」
とぼける小倉だが、よく見たらわかる。
化粧でうまく隠しているように見えるが、小倉の目の下には薄いクマができていて顔色も少しだけ悪かった。
「あまり寝てないのか?」
「よく分かりましたね。ちょっとキモイかもです」
「すまん。何かあったのか」
「んー、まあ……実は色々あって、私ともあろうパーフェクトキューティーガールもほんの少し疲れてます」
色々の中身を聞く気はない。
ただ小倉が自分の体の異変に気がついているのならそれで問題ない。無意識にげっそりしているなら保健室ルートだったが。
「ふーん。体には気をつけろよ、じゃあな」
「えー、もう行くんですか?」
俺は軽く労いの言葉をかけて踵を返したのだが、小倉に手を引かれて立ち止まった。
ナチュラルにお手手を繋いでくるんじゃない。やわらかくてびっくりしちゃうだろ。
「昼休みは一時間しかないし、俺も早く教室に戻って飯を食わないといけないからな」
こんな場所で時間をロストするのはもったいなく感じる。
空腹は限界に近いし、早く朝コンビニで買った菓子パンで腹を満たしたい。
「……どうせなら一緒に食べませんか?」
「小倉と? なんで?」
俺は嫌な表情を隠さなかった。臨機応変なポーカーフェイスのオンオフが求められる。
多分、今はゴキブリを発見したときみたいな顔だと思う。
俺だったら、話し相手にそんな顔をされたら嫌だ。小倉も嫌がると思う。早く諦めろ。
しかし、小倉はめげない。しょげない。むしろ、どこか悩ましげな様子で言葉を続けた。
「なんでって……実はちょっとだけ込み入った訳があるんです。佐山先輩はまだ何も知らないでしょうけど、昨日ややこしいことになっちゃって困ってるんですよ」
「……俺なんかに頼っても役に立たないと思うぞ」
「別に佐山先輩を利用するつもりはないので、少し話を聞いてくれるだけでいいですよ。他に話せる人もいないのでお願いします」
「わかった。じゃあ、体育倉庫に来てくれ。あそこはひと気がないし、話をするにはちょうどいいからな」
そこまで言われたら断るわけにもいかない。
俺のとっておきスポットに招待しよう。体育館の真隣にある体育倉庫は何よりも涼しい。少し埃っぽいのが難点だが。
「りょーかいです! 準備できたらすぐ向かいますね!」
小倉はそれだけ言い残して教室に戻っていった。
知らん一年連中にちらちら見られはしたが、変なやり取りではなかったから問題はないと思う。目立つことはなかった。
俺もとっとと菓子パンを持って体育倉庫に向かうか。
どうせ小倉が話したいことっていうのはわかってる。今朝、五十嵐に聞いた例の噂とやらだろう。
何があったか知らないが話だけでも聞いてみるか。
◇◆◇◆
体育倉庫は予想通り快適だった。
つい最近新品になったばかりのマットがあり、その上は清潔でふかふかで最高だ。
しかも、涼しい。窓が大きく開け放たれ、尚且つエアコンのある図書室と隣接しているからか、古い体育館の倉庫には冷たい隙間風がビュービュー入ってくる。最高だ。
一人で過ごすにはうってつけの穴場だろう。
まあ、今日は残念ながら珍客がいるのだが。
「で、話ってなんだ?」
菓子パンを貪りながら小倉に尋ねた。バターとチーズとハムが乗っかってる油まみれの菓子パンだ。安くてジャンキーで最高だ。
「んーーーーー……ここにきて迷いが出てきました」
小倉は六段くらいの跳び箱の上に座り、足をぶらつかせながら言った。
「おいおい」
「聞きたいですか?」
「……」
焦らされてしまうと聞きたくなってしまうのが人間の性だ。
聞きたくない! と、はっきり言えない自分が悔しい。
「そんなに聞きたそうな顔をされたらもう私も話すしかないじゃないですか~。仕方ありませんねぇ~」
小倉は渋みのある俺の顔を見て心を改めたらしい。
さっきは悩ましそうにしていたのに、今度はノリノリになった。
感情の起伏がわかりやすいから話しやすい。
「結構大事な話なのか?」
「まあ、そうですね……昨日、佐山先輩と別れた後に他校のイケメンと遊んだのは知ってますよね?」
やっぱりこの話か。テキトーに相槌を打っておこう。
「ニッコニコでスキップしてたから覚えてるぞ」
「恥ずかしいのでそれは忘れてください! それで、その他校のイケメンがちょっと厄介なんですよ」
「ふーん、どんな感じに厄介なんだ」
「ストーカー気質っていうか、じっとりねっちょりしてるっていうか、なんかこう……しつこい性格なんです」
「危ないやつなのか?」
「私の対人センサーは危険信号を出してます! 見た目は良い感じなのに!」
小倉はほっぺたをぷっくりと膨らませていた。不満そうにしている。性格はアレだったのかもしれないが、噂通りのイケメンではあったのだろう。
「お前の好みは知らんが、なんで相手がストーカー気質だってわかったんだ? 嫌なことでもされたのか?」
「もちろんです。まず、勘違いが多すぎます! ちょっとボディタッチしただけで腕を組もうとしてきたり、カラオケで二人きりになったら肩を寄せてこようとしたり、そんな感じでグイグイこられるのは嫌なので冷めちゃいました」
「……他には?」
最初はテキトーに流すつもりでいたが、話を聞くにつれて俺も言いたいことが続々と湧いて出てきた。
まあ、まだ何かありそうだし、まずは聞いてみることにしよう。
「えとえと、試しに上目遣いで甘えてみたら顔真っ赤になっちゃったり、パフェをあーんして食べさせてあげたらデレデレニヤけたり……とにかく態度が露骨なんです。完全に惚れられた感じですね」
「へー」
「なんですかその冷めた反応は!」
ドライな相槌を打ったのがバレバレだったらしく、小倉はぷんすか怒りながら前のめりになった。ぶらつかせる足の速度は次第に速くなっている。
「いや、なんでもない。とにかくお前はそんなイケメンの反応を見てガッカリしたんだな?」
「はい。私に対して簡単になびきすぎです!」
「ストーカー気質ってのはこれに関係してるのか?」
「そうなんです! 本当は夜の七時までには帰りたかったのに、なかなか解散してくれなくて、結局は十時くらいにやっと離れられました。その間に好きな男の子のタイプとか歴代彼氏はどんな人なの~とか色々質問攻めされて……もうクタクタですよ。
これって立派なストーカー気質ですよね? 佐山先輩もそう思いませんか?」
小倉は呆れた面持ちで同意を求めてきたが、はっきり言って俺には彼女の気持ちが全くわからなかった。
だって、しょうがなくない?
というか、小倉が悪いとすら思える。
他校のイケメン先輩は男として正常だろう。
こいつは何か勘違いしているようだから、はっきり教えてやるか。
嫌われてもいいし、なんかもう我慢できない。
「はぁぁぁ……小倉」
「なんですか。深いため息なんてついて」
「お前は何もわかってないな」
「はい?」
「そもそも発端はお前だろ。なんのためにイケメンに自己アピールをしたんだ? ボディタッチをしたり、上目遣いで甘えてみたり、二人きりでカラオケに行ってみたり……それってお前がイケメンのことを好きだからやったんじゃないのか?」
小倉のようなタイプなら、嫌いな相手にそんなことをするわけがない。分別があるはずだ。
「別にあの人のことを好きにはなってませんよ。だって、私って一目惚れはしないタイプじゃないですか?」
「うん、まあ、知らんけど。じゃあ、なんでそんなことしたんだ?」
「相手のことを確かめるためですよ。そんなことに簡単に惑わされる男の人は信用できませんから! 現に私はもうあの人のことを信用できなくなりましたもん!」
極端だ。極端すぎる。それに、間違っている。
そんなことで相手を知ることはできない。
「イケメンがほいほい惚れてきたから興味を失った、そういうことか?」
「まとめるとそういうことになります。私は誰よりも一番可愛い自覚がありますけど、そんな私に一目惚れするってことは顔しか見てないと思うんです。みんなそうでした。私の好きな食べ物とか好きな色とか趣味とか、何にも知らないし知ろうともしないんですよ。
だからお付き合いする相手は、私の内面を見てくれる人じゃないと嫌なんですよ。わかりますか?」
「はぁぁぁぁぁ……」
「さっきよりも深いため息ですね。しかも、私に対して何か言いたそうですし」
俺のため息が露骨すぎたのか、小倉は不貞腐れたように睨みつけてくる。
「はっきり言うが、お前はバカだ。自分のことも、相手のことも何もわかっていない」
後先なんて考えていられない。
無自覚に男を沼らせるこいつを見過ごすわけにはいかない。他校のイケメンが堕ちてしまったように、被害者が増えるのも時間の問題だ。
「っ! 急になんですか! ムカつく言い方ですね!」
「小倉、思春期の男子高校生がどんな気持ちで日々過ごしているのか知ってるか」
「知るわけないじゃないですか、私は女ですし」
小倉はムスッとして答えた。
「だよなぁ。思春期の男ってのはアホなんだ。視線は女子の胸に勝手に誘導されるし、大きなお尻があればついつい目で追ってしまう。
異性に話しかけられたら心の底から嬉しくなるし、ボディタッチなんてされたら勘違いしちまうんだ。あれ? こいつ俺のこと好きなんじゃね? って具合にな」
淡々と説明したが、俺だって思春期の男子高校生だ。
当然、悶々とすることはあるし、異性への興味も強い。
だが、それはこの年齢なら仕方のないことだ。日常生活の一部として制御するしかない。
だって保健の授業でそう教わったもん。
無論、小倉のような破壊者がいたら別の話だが。
「……佐山先輩は私が悪いって言いたいんですか? イケメンのあの人があんな風になったのも私のせいですか?」
小倉はおもむろに跳び箱から飛び降りると、こちらに近寄ってきた。
可愛らしい怒りではなく、きちんと眉を潜めて不満を露わにしている。
予想に反して、俺が全く味方になってくれなかったからだろう。
だが、最後まで聞いてほしい。
解決方法は簡単なんだ。
「一つ勘違いしてほしくないが、お前はお前が思うよりもずっと可愛いんだ。背が低くて顔が整っていて髪もサラサラで綺麗だ。おまけに愛嬌があって声も心地良い。たとえ嘘でも、そんな天使みたいな女子に言い寄られたら、どんな男も、さすがのイケメンでさえも、全員がイチコロだ。勘違いしちまうのはしょうがないんだよ。内面を知る前にその可愛さに目がいくのは必然なんだ。わかるか?」
「……」
俺の言葉を受けた小倉は途端に顔を朱色に染めると、ぷるぷると震えながら俯いてしまった。
「おい、聞いてるか?」
「それは、佐山先輩もそうなんですか?」
「ん? どういう意味だ?」
「だから! 佐山先輩も……私がそういうことをしたら、好きになっちゃうんですかって聞いてるんです!」
小倉は顔を勢いよくあげた。
潤んだ瞳、赤らんだ顔、力の入った口元。嘘が本当かわからないが、いつもより凄みがあった。
「……うーん、俺は……わからない。でも、小倉に手を引かれたり、今みたく上目遣いで見つめられると、少しだけ気持ちが変になる。多分、俺もお前が嫌っているような人間の一人なんだろうな」
嘘偽りなく答えた。
小倉の些細な仕草一つで心が動きかける自分が情けないが、それはきっと他の男子も同じなのだろう。
確かに小倉の言いたいこともわかる。すごくわかる。
人を見た目だけで判断するなってのは、小倉くらいの可愛いやつになると身に沁みて思うことなのだろう。モテモテだからこそ痛感する部分なのかもしれない。
でも、自分の可愛さや魅力を理解しきれていないうちは、そんな誤った方法でこれからもバカな男を堕としてしまう。
「あともう一つ付け加えるなら、他校のイケメン先輩は正常だってことだ」
俺は言葉を続けた。少し空気が張り詰めているのを肌身で感じる。
「佐山先輩は……いえ、なんでもありません」
小倉は何かを言いかけたが口をつぐむと、膝を曲げてしゃがみ込んだ。肩で息をして下に視線を落としている。
怒っている様子はないが、普段の余裕そうな雰囲気ではなかった。その心情は俺にはわからない。
しばし沈黙の時間が流れた。
おそらく三十秒くらい経っただろうか。
「……佐山先輩は、私のこと可愛いって思いますか?」
小倉はゆっくり立ち上がると、今度は俺から体を背けて尋ねてきた。
何を聞かれているのか、一瞬理解できなかった。
改めて伝えるのは少し恥ずかしい。
だが、俺は隠すことはしなかった。
「ああ。小倉は可愛いと思う」
「ほんとーに?」
「本当に」
決して嘘ではない。世間一般的にも、俺の目から見ても、小倉は可愛い。
校内でも上位の可愛さだと思う。
まだ彼女の内面なんて全く知らないが、顔だけで言えば間違いなく可愛い部類だ。
「……そうですか。佐山先輩から見ても私は可愛いんですね。じゃあ、私のことは好きですか? みんなと同じように一目惚れはしてませんよね? イケメンのあの人と同じようにデレデレして来ないんですか? だって気持ちが変になるんですよね?」
小倉は矢継ぎ早に言葉を吐き出した。
正直答えにくい。でも、ここも素直に答えるべきだと思った。
小倉の真意が気になるし。
「俺はお前に一目惚れはしてないが、別に嫌いなわけじゃない。むしろ、年が違うのにこうして思ったことを口できる相手は中々いないだろうし、どちらかと言えば好きなんだと思う……悪い、気持ち悪いこと言ってるよな」
はっきり答えたかったとはいえ、俺の発言はいささか達観しすぎて気持ち悪かった。
恋人でもそういう空気でもない相手にこんなことを伝えるのは、どう考えてもお門違いだ。言葉にして後悔した。すまん、小倉。いつものようにからかって罵ってくれで構わない。
しかし、そんな俺の申し訳なさとは裏腹に、小倉は力強く首を横に振った。
「……いえ、気持ち悪いだなんて一ミリも思ったことありません! というか、佐山先輩、よく人たらしって言われませんか?」
「友達が一人しかいない俺に人をたらす才能なんてない」
「そうですか」
小倉はここにきて初めて笑ってくれた。くすくすと小さな笑みではあったが、友達が一人しかいない俺にウケたらしい。
空気が少し温和になった。
よかった、友達一人しかいなくて。ありがとな、五十嵐。
「……佐山先輩」
五十嵐への感謝を胸に秘めていると、唐突に名前を呼ばれた。
小倉の背中が小さく見える。
「なんだ。大丈夫か? 声が変だぞ?」
俺の名前を呼ぶ小倉の声は少しばかり揺らいでいた。ふにゃっとして力の抜けた感じだ。
「さやませんぱい」
ゆっくりと静かに振り向いた小倉唯は、どこか虚な目をしていて、ぼーっと熱のある視線を向けてきた。
明らかに変だった。さっきまでの平常な感情ではない。
「おい、なんか熱っぽくないか?」
向かい合う小倉の顔は真っ赤だった。
彼女はふらふらとした足取りで近づいてくる。
言い方は悪いが末期のゾンビのような、おぼつかない感じだ。
「わたし、わたし……」
小倉は荒れた呼吸で何かを言おうとしていた。
「一回落ち着け」
虚な瞳を見つめて言葉をかけた。
「……わたしは、さやませんぱいのこと……」
制止も虚しく、小倉はバランスを崩して俺の胸に飛び込んできた。
咄嗟に肩を掴んで支えたが、体は高い熱を持っていた。
昨日の夜は帰りが遅かったみたいだし、疲れが溜まっていたのだろう。
大丈夫なんて言っていたが、強がりだったみたいだな。
「全く……」
俺は小倉をおんぶして保健室へと向かった。
人目に着いたら最悪だと思っていたが、幸いにも誰にも出くわすことなく到着した。
保健室が体育館から近い位置にあって助かった。
「先生、熱があるみたいなのでベッドで寝かせてあげてください」
保健室の女の先生は「あらあら」と口にしてニヤけていた。
なんだその茶化すような”へ”みたいな形のスケベな目は。
「……うふふふふ、奥のベッドに寝かせてあげてちょうだい」
「わかりました」
俺は小倉をベットの上に寝かした。
「こいつは一年二組の小倉です。あとはお願いします」
「はいはい。もうお昼休みは終わっちゃうから、彼氏さんは授業に行きなさいね。心配だからって覗き込んだらダメですからねー?」
「小倉が起きてる時にそんな冗談言ったら怒られそうなんで勘弁してくださいね。では」
俺はテキトーに返して保健室を後にした。
煽ってくる保健室の先生はちょっと苦手だ。
俺と小倉がカップルに見えるなんてありえない。
バカにされてるのは明らかだった。
「……ったく、結局、あいつは俺にあの話をしてどうしてほしかったんだ」
他校のイケメンがストーカー気質なんかではないのは確かだが、話を聞いて何が進展したのかはわからなかった。
俺が単純に小倉由花という女子の魅力に取りつかれただけだ。
今も少し胸がドキドキしている。おんぶしたときに耳に掛かる艶かしい吐息と、甘い匂いが忘れられない。
俺だって、今のようなフランクな関係ではなくて、もしも出会い方が違っていたら彼女のことを好きになっていたかもしれない。
それくらい、小倉由花という女子には魔性の魅力があった。
◇◆◇◆
ある日の午後一時ごろ。
夏休みを目前に控える中で、一年生と二年生の合同プール授業が開かれることになった。
俺が一年生の時はプール授業自体なかったはずなのに、まさかまさかの初プール授業は予想外の合同ときた。
厄介だ。
だって、俺、泳げないんだもん。
しかも、プールの授業と銘打っているが、担任の話によればリフレッシュ目的らしい。
堅苦しい授業は全くなく、基本的にはルールの範囲内でフリータイムなんだとか。
なんだよそれ、屋内プール施設を貸し切ってまでやることか?
最悪だな。フリータイムならぼっちで過ごすのが確定してしまう。それは別にいいんだが、逃げ場がない。ここでは本を読めないしスマホも見れない。
どうする?
いや、考えるまでもないか——うん、サボろう。
捻挫したとかテキトーに言えばいいや。
「……欠席するのは俺だけか」
というわけで、俺は広大なプールを一望できる場所に来ていた。
展望台というのか、高台というのかわからないが、前方向がガラス張りになっている控え室的な部屋だ。例えるなら、アメリカの刑務所にあるような監視塔みたいなやつ。
中はエアコンが効いて温度はバッチリだし、ウォーターサーバーとソファがあって気楽に休める。
おまけに体育の授業と扱いが一緒だからか、制服ではなくジャージで過ごせるのも最高だ。
「誰もいないって最高じゃん」
まさかの欠席者は俺一人だけだった。
一、二年生合わせて百をゆうに超える数の生徒がいるのにもかかわらずだ。
まあ、こんなに広い屋内プールだし、名目上は授業だが中身は遊びみたいなもんだし……そりゃみんな乗り気になるよな。
「ふぅ、最高だなぁ」
ソファにもたれかかって息をつく。冷たい水で喉を潤し、壁掛け時計の心地よい秒針の音に酔いしれる。
眠くなってきた。一人だからぐっすり眠ってしまうのも手だな。
「……」
目を閉じた。
徐々に睡魔が襲ってくる。
多分、一瞬で眠れる。
「……ん?」
その瞬間だった。出入り口の扉が静かに開かれる音がした。
俺はすぐに目を開け姿勢を正すと、おもむろに扉の方に目を向けた。
すると、そこにはなぜか小倉の姿があった。制服でも水着でもなく紺色のジャージを着ている。下はハーフパンツ、上はジップを上まで上げた長袖だ。
彼女は恐る恐る部屋に入ってくると、気まずそうな顔でこちらを見た。
「あ……佐山先輩もいたんですね」
俺も少しだけ気まずかった。実を言うと、体育倉庫で話したあの日以来、彼女とは顔を合わせていなかったからだ。
まあ、普段から話す機会が多いわけではないし、今回でまだ四回目くらいだが、変に意識してしまい会わない期間が気まずさを募らせていた。
「えと……佐山先輩はどうしたんですか?」
しんとした空気になる前に、小倉が早口で尋ねてきた。
「あー、俺は……まあ、色々だな」
「サボりですか?」
「包み隠さず言うなら、そんな感じだ」
「私と一緒ですね」
「そうなのか?」
「はい。全然やる気になれなくて、先生に言って抜けてきちゃいました」
小倉はイタズラな笑みを浮かべると、俺の向かいのソファに座った。
全然元気そうだ。あれから見かけてなかったが、体調不良は治ったみたいだな。
「体は平気か? っていうか、自分が倒れたこと覚えてるのか?」
「気がついたら保健室にいたんですけど、先生に聞きました。佐山先輩が運んでくれたんですよね……ありがとうございます。お礼伝えるの、遅くなっちゃいました」
「気にすんな。それより、やっぱり体壊してたんだな」
「実はあの日は起きた時から怠かったんですよね。そのせいで倒れちゃいましたし、その前のやりとりの記憶が曖昧です。私、変なこと言ってませんでしたか? 佐山先輩に大事なことを伝えたような気がするんです」
俺の覚えている限りだと、大事なことは特に伝えられてなかったと思う。
倒れる直前の小倉は俺の名前を連呼するだけだったし。別におかしなことではない。体がきつくて介抱を求めていただけだと思う。
「……変なことは特に言ってなかったぞ。どの辺りの記憶がないんだ?」
「佐山先輩と少し言い合いになりそうだったのは覚えています。わからないのは最後の倒れる直前だけです。その前の記憶ははっきり残ってます」
「これまたピンポイントだな。じゃあ、嫌な気持ちの方が大きいかもな。俺のことを嫌いになっただろ」
体育倉庫での一幕は、俺的には小倉を思った言葉だった。
彼女からすれば違うかもしれない。
「……正直、あんなこと言われると思ってませんでした。私が相談したらみんな慰めてくれるのが当たり前だったので変な感じです」
「そっか」
「でも、嬉しかったです。あれは私のことを考えてくれてたってことですもんね?」
「変な意味はないが、その解釈であながち間違ってないと思う」
お前をことを考えていた……なんてキザな言葉は出てこなかった。遠回しで情けない言い回しになってしまう。
だが、それでも小倉は嬉しそうにはにかんでいた。
「やっぱり嬉しいです! なんか、ほっとしました! ずっと気になってたんです。私も少しムッてしちゃいましたし、そのせいで佐山先輩に嫌われてないかなって不安でした!」
「嫌われる? そんなこと気にしてたのか」
「そりゃそうですよ! 佐山先輩には嫌われたくないですもん!」
「っ……そうか」
つい嬉しさが込み上げてきそうになったが、ここで喜んでしまえば小倉に堕ちた他の男子と同じだった。
間に受けたら俺がバカを見る。
俺が小倉を好きになってはいけない。
「ところで……どうしてサボってるんですか?」
「んー、泳げないからなぁ、俺」
「なんか意外ですね。佐山先輩ってなんでもバランスよくできそうなイメージありましたけど。意外と不器用だったりするんですか?」
「俺は不器用だな」
不器用でありながらも、何もかもが下手だ。
勉強は並だが努力が苦手だし、方法を模索するのも下手くそだ。
もちろん人付き合いも苦手だ。こうして普通に話をできているのが奇跡だと思えるくらいには。
「私も不器用なので一緒ですね!」
「お前は器用だろ」
「いえ、そんなことないですよ。私は不器用だから間違ったことばかりやっちゃうんです。佐山先輩にあんなふうに言われなかったら、今頃もプールでおかしなことをしてたかもしれません」
小倉はジャージの上着のジップに片手を添えながら、照れ臭そうに笑った。
「なんだよ、おかしなことって」
「……知りたいんですか?」
「ん……まあ、可能なら」
よくわからなかったが、話ついでに気になった。
すると、小倉は恥ずかしそうに立ち上がると、ジップに手をやりゆっくりと下に下ろし始めた。
袖が長くて萌え袖になっており、それはわざとではない部分だからこそ、自然な仕草でいつもより可愛く見えた。
「なんで脱いでんだ? 暑いのか?」
「……まだわからないんですか」
疑問を投げる俺に対して、小倉は恥ずかしそうにジップを下ろしていく。
ここでようやく俺は気がついた。
「おい、こんなところで水着になるなよ!」
小倉はジャージの下に水着を着ていた。
それも授業用の地味なやつではなく、海に遊びにいくようなカラフルなビキニだった。
「どうですか? これでみんなの前に行ったら、多分めちゃくちゃ見られると思いますし、もっと私の可愛さが伝わると思うんです。そうすれば、一年生と二年生の男子の視線を釘付けにできますよね」
小倉はジップを半分まで下ろすと、ガラス張りの下に広がる景色を眺めた。
まるで過去の自分を天から俯瞰しているかのような口ぶりだった。
「でも、それはお前の外見の話でしかないな」
「その通りです。それは佐山先輩が教えてくれました。だからやめたんです。ああいうやり方で人の心を決めつけるのは……もう、やめにしたんです」
「そうか。俺の言葉とやり方が正しいのかはわからないけど、それで本当に好きな人が見つかるといいな。小倉の内面を見てくれるような人がきっといると思うから」
「……もう、います」
「え?」
「な、なんでもないですっ! それよりも! 連絡先交換しましょう!」
俺が言葉の意味を理解するよりも先に、小倉は慌てふためいて話をかき消し、トンチンカンなことを言い始めた。
「スマホは学校だぞ」
「そ、そうでした……」
「どうした? また顔が赤いぞ。先生に言って俺が付き添ってやるから学校に戻るか?」
俺は立ち上がり小倉と視線の高さを合わせた。
間近に顔がある。パチクリと高速で瞬きをしており、長いまつ毛がよく見える。
そんなことより、勘違いをして恥ずかしがっているにしては顔が赤すぎる。
やっぱりまだ体調不良は治っていないのかもしれない。
もう一度、保健室送りにした方が良さそうだ。
「大丈夫ですから! ほんとーに! 私は平気です! ただ、話してたらちょっと暑くなっただけなので、お水もらいますねっ!」
小倉は途端に大きな声を張り上げると、なぜか俺の紙コップを手に取りぐいっと水をあおった。
もう様子がおかしいのは目に見えている。
「ぷはぁっ! これでもう大丈夫です!」
ぬるくなりかけた水を飲んでスッキリするわけないが、満足そうにしているからもういいや。
「元気になってよかったな」
「はい」
小倉は満面の笑みを浮かべていた。
とことこと歩いてきて、なぜか俺の隣に腰を下ろす。
二人掛けのソファだから少し狭い。
「……向かいのソファはガラ空きだぞ」
「ここがいいんです。今思えば、二人きりで話す機会はたくさんありましたけど、お互いのことを知る機会はなかったですよね。プールの時間が終わるまでまだありますし、よかったらたくさん話しませんか?」
「わかった。でも、隣に座る必要はあるか?」
やはり気になる。甘い匂いがするし、肩が少し触れ合っている。心なしか小倉が俺側に傾いている気がするし……色々と落ち着かない。
「嫌ですか?」
「嫌ってことじゃなくて……なんか距離が近いから少し、な」
俺は何とかはぐらかしたが、心臓は高鳴り続けていた。
そして、こう言ってしまえば小倉がバカにしてくるのもわかっていた。
どうせ「あれあれー? 恥ずかしんですかー? 佐山先輩ってば、私のこと好きになっちゃいましたかー?」って言われると思う。
小倉は男を判断する例のやり口をやめたとは言っていたが、俺をバカにするのは別の話だろうしな。
「……」
俺の予想に反して、小倉は俯いて黙りこくった。
「小倉?」
「あの……恥ずかしいのは私も一緒です。だから、気にしないでください」
「え?」
「……佐山先輩だけじゃありませんから」
「そ、そうか」
意外な反応だった。というより、予想外だ。
変な空気になっちゃった。ぽわぽわしているというか、なんというか……温かくもあり、柔らかくもあり、それでいて刺激的な肌がチクチクするようなイメージだ。
どうしよ。この空気。俺から何か話すべきだよな。
俺は意を決して口を開いた。
「な、なぁ——」
「——おーい、二人とも! どうせこんな場所にいても暇だろうし、今日はもう先に帰ってもいいぞー。みんなには内緒で特別だからな」
俺の言葉を遮るように、タイミングよく先生が入ってきた。
まだここにきて十分くらいしか経ってないが、まさかの帰宅の許可が出た。
「え? いいんですか? 佐山先輩、やりましたね!」
「お、おう。そうだな」
「学校に荷物やら何やら取りに戻ったら、すぐに帰るんだぞ。ちなみにジャージのままだから寄り道は禁止だ。わかったなー」
困惑する俺と小倉をよそに、先生はそれだけ言い残して早々にいなくなった、
本当に帰れるらしい。まだ時間は一時過ぎだ。
寄り道禁止とはいえ、家に帰ればめちゃくちゃゆっくりできそうだ。
「……帰ろうか」
「そうですね」
俺は小倉と共に簡単な荷物をまとめると、屋内プールを後にして学校へと戻った。
何気ない雑談をしながら校門をくぐり、それぞれの教室へ向けて歩き出す。
そこで教科書やら何やらとスマホを回収する。
あとはとっとと家に帰るだけだった。
しかし、校門に戻ると、俺たちは何の約束もしていないのに鉢合わせた。
違う。お互いがお互いのことを考えていたのかもしれない。
俺は小倉を、小倉は俺を、それぞれが無意識のうちに一緒に帰ろうと心で思っていたのだろう。
「……行こうか」
「はい」
ごく自然に、俺は手を伸ばしていた。
そして、ごく自然に、小倉は俺の手を取った。
いくら歩こうとも、繋がれた手の手は離れなかった。
暑い夏の日のじめっとした気温が気にならないくらい、気分は高揚していた。
それは俺だけではないと思う。だって、横目で見た小倉の顔は緊張しているみたいだったし。
だが、会話はない。
気がつけば、俺が小倉と最初に出会った公園の前にいた。
「この公園、俺が初めてお前に声をかけた場所だな」
「失恋した私がベンチで泣いてたんですよね。今思い返したら、なんであんなに凹んでたのかわからないですけど」
「ちょっと座って休もうか」
「そうですね」
俺は小倉と共にベンチに腰掛けた。
最初の頃とは違い、二人の間に距離はない。
「小倉」
「なんですか、佐山先輩」
「……自分語りで申し訳ないんだけど、俺、今まで好きな人とかできたことなかったし、そういうのを避けて生きてきたんだ」
「そうなんですか」
「うん。あんまり他人に興味がないからだと思う。友達だって一人しかいないし、俺はずっとそういうもんだって思ってたから」
一人でいるのはむしろ好きだ。
誰とも話さなくたって不満はない。
ただ小倉と出会ってからは、ふとした拍子に他の考えがよぎることがある。
その答えはもうわかっていた。けど、俺にとっては考えるだけでも難しく思えるし、無縁の世界すぎて頭を抱えたくなるほどだった。
「佐山先輩は、変わりましたか?」
「……変わったな。少し前とはだいぶ違う気がする」
不器用でぶっきらぼうで、バカな俺でも自分に起きた変化がわかる。
「何が違うんですか?」
「——いいなって思える人を見つけたんだ——」
「…………」
「その相手を見た時、一目惚れはしなかったし運命を感じることもなかった。でも、時間を共に過ごすにつれて、一つ気がついたことがあった。
俺はその子といる時は自分らしさを出せるような気がしたんだ。普段は冷静を装ってるけど、その子の前なら感情を出せたし、言いたいことを口にできた。行動に移して手を握れた。伝えたい思いを伝えられた。
そして……今は、一緒に過ごせて幸せだって思ってる」
もう迷いなんてなかった。全く躊躇する気持ちもなかった。
むしろ、この思いを早く伝えたかった。
「俺は——小倉由花という後輩のことが好きになっちゃったみたいだ」
あざとくて計算高く見えるけど、実は不器用な一面があって間違った選択をする。
照れや恥ずかしさを感じるとすぐに顔が赤くなり、突拍子もない行動を取る。
でも、その中にも愛嬌や愛らしさは滲み出ていて、取り繕ったあざとさなんかなくても、誰よりも可愛かった。
それは見た目だけでじゃなくて、彼女があまり表に出してこなかったであろう内面の部分もそうだ。これからもっと知っていきたいと強く思う。
「やっぱり、俺はお前のことが好きだ」
「……せん、ぱいっ……」
小倉は驚いたように俺を見つめていた。
以前まで頻繁に見せていたあざとい笑顔も、からかうような軽口も、今は一切ない。
その澄んだ瞳が俺の言葉を真っ直ぐに受け止めているのが分かる。
「……小倉?」
声をかけると、俺の手を握る力が強くなった。少しだけ俯いている。
快活で活発で、俺なんかと話してくれる、そんな彼女からは想像もつかないような、どこか頼りない仕草だった。
「……私なんかでいいんですか?」
「どういう意味だよ」
「佐山先輩は見た目こそイケメンには及びませんけど、話してみるとすごい良い人で、面白くて、優しくて、頼りになって……でも、私はそんな立派じゃないし、もっと良い人がいる気がしちゃうんです……」
小倉の声は震えていた。でもその目には、涙の代わりに意地が見える。
自分の弱さを認めながらも、それを克服しようとする力があった。
「……そう思うのはお前だけだ」
俺は体を小倉の方に向けると、そっと小倉の両手を包み込んだ。
彼女の手は夏なのに少し冷たくなっていた。
「俺には、泣いてるお前も、笑ってるお前も、全部がちゃんと見えてる。強がってるとこも、優しいとこも。だからこそ、俺はお前がいい」
小倉は目を見開いた。そして、少しずつその瞳が潤み始めた。
「……ほんと、ですか……?」
「ああ、本当に」
それ以上言葉を重ねる必要はなかった。
俺の手を握る小倉の力が、少しだけ強くなったことが答えだったから。
しばらくの沈黙の後、小倉が小さな声で口を開いた。
「……私、気づいたら先輩のことばっかり考えるようになってて……いつからかわからないんですけど、お話しするたびに少しずつ気持ちが変わっていたんだと思います」
小倉の頬が赤くなり、さらに言葉を紡ぐ。
「私も、先輩のこと、好きになっちゃいました」
彼女の言葉が終わると、静かな夏の午後の風が吹いた。
蝉の声が遠く響く中、俺たちはただじっと、その時を待った。
そして、俺は小倉の手をもう一度強く握り返した。
彼女がその手に応えるように握り返してくる。視線もこちらに向けられて、涙交じりの瞳で見つめてきた。
「じゃあ、これからも一緒にいてくれるか」
「はい……! 佐山先輩と、ずっと一緒にいたいです」
小倉の笑顔が太陽に照らされ、今までで一番輝いて見えた。
その瞬間、俺は彼女の唇を奪った。