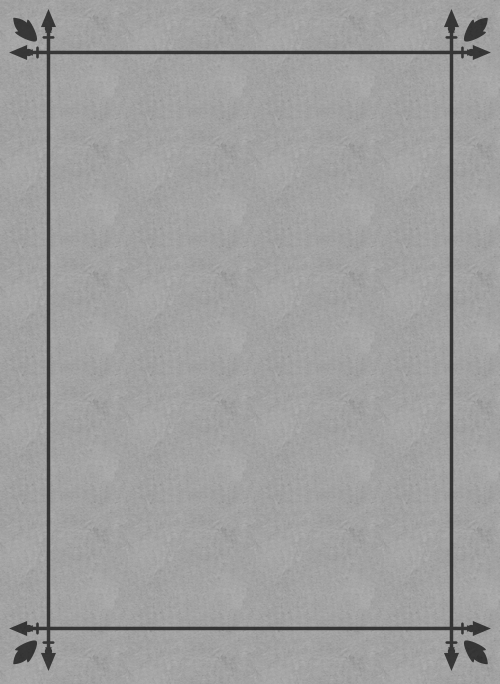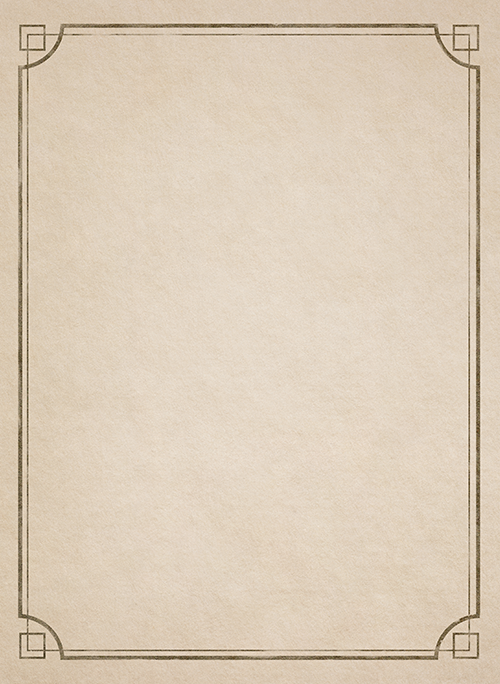高校三年の秋。
今は大学受験やら就職やらの影響で、学校中が忙しなくなっている。
授業中であろうと静かとは呼べず、誰もがピリピリしながら過ごしている。
そんな喧騒が嘘みたいに、ここは落ち着いている。
まるで別世界に来たかのようなこの場所は、そう、図書室。
俺、赤木斗真が最も気を許せる場所だ。
理由は簡単。誰もいないから。
コミュ障で人付き合いが苦手で、友達がほぼいない俺にとって、高校生活は苦行以外の何者でもなかった。
だから、たまにこうして授業をサボり、図書室に逃げ込むことがあった。
大学進学は推薦で確定させているし、もう授業に出ずとも卒業はできる。あとは残された二、三ヶ月間の高校生活をすり潰して過ごすだけだ。
「ふぅ……」
図書室の隅の隠れたスペースで、家から持ち込んできたゲーム機をいじる。
プレイしているのは、この前セールで買ったギャルゲーだ。
ゲーム内のヒロインが俺に笑顔を向けてくれる。
それだけで、現実の煩わしさを忘れられる。
「選択肢は……『手を繋ぐ』か、『見つめ合う』……か。花火大会のイベント終わりだから、ここは攻めてみてもいいな」
小声で独り言を漏らしながらボタンを押す。
手を繋ごう。二人きりで花火大会に来れた時点で、脈なしというわけではないはずだ。
「……さあ、どうなる」
俺はドキドキしながらヒロインの反応を待った。
ヒロインの彼女は金髪を風に靡かせながら、頬を赤く染めていた。
そして、数秒後。
手を繋いだ効果はテキメン。ゲーム内のヒロインが照れた表情になり、グッと距離を詰めてきた。
よし、選択に間違いはなかったらしい。さすがだ、俺。
こうして授業中をサボって、一人で図書室に逃げ込み、ゲームに興じるのもまた悪い選択ではないのかもしれない。
一種の青春だ。
陽キャの青春はよくわからないが、俺にとっての青春は孤独にゲームと向き合うことだった。
なんて思いながら、次の会話イベントに集中していると、不意に背後から声がした。
「ねぇ、あんたなにしてんのー?」
唐突な声に、俺は反射的にゲーム機を懐に隠した。
恐る恐る振り向くと、そこには金髪の女子——制服のスカートを短くし、ネイルを輝かせた派手な存在が立っていた。
ま、眩しい! 直視できん!
なんだこのギャルは! ゲームの世界から飛び出してきたのか!?
「……どなたでしょうか」
口をついて出た一言に、金髪ギャルはニヤリと笑った。
「星野紗奈だよ? うちの生徒のくせに、あーしのこと知らないとかマジで言ってんの? っつーか、あんたこそ誰? 上靴の色一緒だし、あーしとタメ? 三年だよね?」
グイグイくる金髪ギャルの名前は、星野紗奈。
しらばっくれてとぼけたが、本当は彼女のことを知っている。
だって、一応同じクラスだし、このギャルはめちゃくちゃ目立つし、見た目の派手さと性格の明るさは有名だった。
ってか、こいつ可愛すぎるだろ。
目は大きくてキラッキラ輝いてるし、右の下の泣きぼくろは色気がある。短いスカートの下に見える太ももはしなやかで長い。もうゲームの世界から飛び出してきたキャラクターのようだった。
こんなに近くで顔を見たのは初めてだ。
ゲーム内なら即攻略対象になるが、あいにく俺とは縁遠い存在だ。
「……」
自己紹介をすべきか?
それすらもわからず困惑してしまい、俺は無言で立ち去ろうとした。
しかし、金髪ギャルはそれを許してくれない。
「待ちなー、なんで逃げようとすんのさ。何隠したのか見せなよ!」
「……嫌だ」
「はぁ? お互い授業サボってるくせに生意気なんですけど、先生にチクるよ?」
「っ! それは卑怯だろ!」
先生に言うのは反則だ。横暴だ。同じサボり組ではあるが、俺と金髪ギャルの発言力には天と地ほどの差がある。先生にバレるのはまずい。
「やっとちゃんと喋った。で、あんたの名前は? あーしとタメっしょ?」
「……赤木斗真。一応、三年二組で同じクラスだ」
「まじぃ!? うちのクラスにいたっけ?」
金髪ギャルは飛び跳ねて驚いた。いちいちリアクションがうるさい。誰もいない図書室の静けさを返してくれ。
「で、赤木はこんなとこで何してんの?」
そう言いながら、彼女は遠慮もなく俺の隣の席に座る。
香水だろうか。甘い匂いがふわりと漂ってきて、無意識に少し身を引いてしまった。
良い匂いだが、俺には刺激が強い。
なんかこう……樹液に群がる虫の気分になる。情けないことにクラクラしてくる。
「なんで離れるし!」
星野は尚も距離を詰めてきた。もう諦めよう。こういう性格の人からは逃げられない気がする。
「……それで、なんだっけ? 俺が図書室で何してたって話だっけ?」
「そそそ。何してたん? めっちゃ焦ってたけど、もしかして……やばいこととか?」
「別に、ただの暇つぶしだよ」
適当に答えると、星野の目が俺の手元に注がれる。
「あっ、それゲーム機じゃん! 見せてよ、見せて!」
星野は興奮気味に身を乗り出してくるが、俺は慌ててゲーム機を抱え込む。
「ダメだ! 大事なゲーム機だから見られるのも嫌だ!」
苦し紛れの言い訳を探す俺を見て、星野はさらに面白そうに笑った。
ゲーム機の画面はすでに一度見られているのか、揶揄われるのはわかりきっていた。
「へぇ~、じゃあ教えてよ。どんなゲーム? どうせヒロインとイチャイチャするやつっしょ?」
確信めいた予想だった。
その言葉に、俺は顔が一気に熱くなるのを感じた。
やばい、完全にバレてる。恥ずかしい。
「これは、その……そう、脳トレだ。選択肢を考えて脳を鍛えるやつ!」
「なにそれウケる! あーしみたいな金髪の女の人が画面に映ってたの見たし、しかも、赤木がそれにデレデレしてたのも見てたから、いまさら何言っても無駄だし」
「……はぁぁ」
「ねえねえ、赤木ってもしかしかくても彼女とかいない感じ?」
顔を覗き込むようにしてくる星野。
彼女の髪が俺の肩に触れる距離に、思わず息を飲む。なんかもう抵抗すんのもバカらしくなってきた。完全にお互いの立場がはっきりしてるし。
どうせならとことん冷たくあしらっていなくなってもらおう。グイグイ来られて俺のテリトリーを荒らされるくらいなら、いっそのこととことん嫌われたほうがマシなまである。
「……関係ないだろ。俺に構うなよ。どっかいけよ」
俺はそっけなく返した。
これで星野は、ぷんすか怒って立ち去るだろう……そう思っていたのだが、なぜか彼女は引くどころかさらに距離を詰めてきた。
「ねぇ、さっきのゲームで、金髪の女の子と手ぇ繋いでたじゃん? こういうのって現実の恋愛の参考になるの? たとえば、こんな感じで——」
そう言って、星野は唐突に俺の手を握ってきた。
温かくて柔らかい感触に、思考が飛んだ。
「赤木、ドキドキしてる? どんな気分?」
その挑発的な笑みに俺は完全に翻弄されてしまい、もう何を言うことができなくなっていた。
「……女の子とこんなことしたの、初めて?」
完全に揶揄われている。手を繋いだまま、肩を寄せられ、下から顔を覗き込まれ、挑発的な言葉を浴びせられる。
こんな経験、初めてに決まってるだろうが。
「お前、なんなんだよ……」
俺はようやく絞り出すように言葉を吐くと、星野の手を振り払って彼女から視線を逸らした。
すると、星野はまたクスクス笑った。
「なにって、ただの暇つぶしだけどぉ? でも、赤木もこーゆーのが好きだから、ゲームで女の子とイチャイチャしてたんでしょ? しかも……こういうの、全然慣れてないんでしょ?」
明るい声色と、どこか楽しげな目。
俺の脳内では警報が鳴り響いていた。ゲームないだけならまだしも、現実世界の金髪ギャルなんて、危ないのは確定している。どんなヤンキー男とつるんでるかわからないし、何を考えているのかもわからない。
絶対に関わったら面倒だ——でも、どうしてだろう。この距離の近さが、嫌いじゃない気がする。
俺はもうすでに星野紗奈に魅了されかけているのかもしれない……悲しきかな、純情な俺。
「やば! もう昼休みになるじゃん! あーしもう行くね!」
俺がぼーっと考えに耽っていると、星野は忙しなく立ち上がった。
時刻は昼過ぎ。もうあと五分もすれば昼休みになる。
「赤木、またねー」
「おう」
「なにその返事」
俺は精一杯搾り出した挙げ句こんな返事しかできなかったが、対する星野は楽しそうに笑って立ち去った。
るんるんスキップなのは、彼女の性根の明るさを示している。
まさしく、俺という影とは真逆の存在だった。
◇◆◇◆
星野紗奈という金髪ギャルとの邂逅から数日が経ち、俺は彼女のことなどすっかり忘れたかけていた。
いつもの平穏を取り戻し、今日は校舎裏で昼休みを謳歌していた。
やはりここは静かでいい。
ここは俺にとって図書室の次に落ち着ける場所だ。
今くらいの秋口の季節は気温も天気も何もかもがちょうどいい。大好きだ。
適当にコンビニで買ったおにぎりを、一人で黙々と食べる。
クラスメイトの輪に入る勇気もなければ、必要性も感じない俺には、これくらいの距離感がちょうどいい。
——はずだった。
「うわ、赤木また一人じゃん! どーもー!」
金髪ギャルの声が背後から降ってきた。
聞き間違えであってくれと祈りながら振り向くと、そこには案の定、星野紗奈が立っていた。
今日は長い金髪をポニーテールしている。少し大人っぽく見える。
「なんでここにいるんだよ……」
「んー? たまたま通りがかったら、赤木が寂しそうに飯食ってたからさー! あ、これ何? コンビニのおにぎり? うける!」
星野は勝手に俺の隣に腰を下ろすと、図々しくおにぎりを覗き込んできた。
俺の一人時間が、瞬く間に侵略されていく。
あと、おにぎりを見てうけてるのはお前だけだ。
笑いの沸点が低すぎて、俺が一発ギャグかましても爆笑しそうなレベルだ。
「……なにしにきたんだよ、こんな校舎裏に」
「んー、なんとなく? でか、赤木ってほんとに友達いないんだねー。こんな日陰のベンチで寂しくない?」
悪びれもせず笑いながら、星野は俺の隣に腰を下ろした。
俺を揶揄っているのかと思いきや、星野の表情はどこか自然で、嫌な感じはしない。
本当にたまたまここに来たらしい。
「だからって、いちいち絡んでくるなよ」
「えー? ひどー」
星野は前回と同じく、わざと俺との距離を詰めてきた。
さっきまではひと一人分くらいのスペースはあったのに、今では肩が振れるくらいにまで近い。
やっぱり良い匂いがする。なんだこれ、むさ苦しい男とはまるで違う。
「……」
くらくらして頭がおかしくなりそうだったので、俺はおもむろに数センチ横にずれた。
すると、星野はニヤッと笑う。
「またドキドキしてんのー?」
「別に……」
俺は咄嗟に首を横に振ったが、本当はドキドキしていた。甘い匂いと肩と肩が触れ合う感覚だけで、俺の思考はいっぱいだった。
「嘘が下手すぎるし!」
「嘘じゃない」
「じゃあ、なんで目合わせてくれないの?」
星野の挑発的な声が耳に響く。
明らかに舐められている。
このまま黙っていたら、また図書室での時みたいにからかわれるのがオチだ。
無様に負けて取り残されるのは勘弁したい。ギャルゲーのように強気な選択はできないが、多少なりとも俺だってやる時はやる。
……ちょっと頑張ってみるか。
「別に……ほら、目くらい合わせてやるよ」
そう言って、俺は覚悟を決めて星野の目を見据えた。
彼女の瞳は、思っていた以上に鮮やかで、どこか吸い込まれそうな色をしている。
星野は一瞬だけ「えっ」と目を丸くしたが、すぐにいつもの軽い笑みを浮かべた。
「ふーん、やるじゃん。赤木のくせに生意気だし」
口ではそう言っているが、どこか声の調子が不自然に聞こえる。
気のせいか? 動揺しているのか? いや、まさかな。校内でトップクラスに目立つあの金髪ギャルの星野紗奈が、こんなことで動揺するはずがない。
「……」
俺は目を逸らさないまま、じっと星野を見つめ続ける。
その間、妙に長い沈黙が流れた。
秋風に揺れる木々や草木の音だけが聞こえてくる。
「……な、なに?」
星野が少し首をかしげながら言う。
その動きで、ポニーテールの髪がふわりと揺れた。
「いや、お前が合わせろって言ったから合わせてるだけだ」
「そ、そっか……」
微妙にぎこちない声。
普段の彼女ならもっとテンポよくからかってくるはずなのに、今はなぜか違う。
さらに見つめ続けると、星野が少し落ち着かない様子で視線を泳がせ始めた。
指先でポニーテールの先をいじったり、やけに大きなため息をついてみたり。
「な、なんかじーっと見られると気持ち悪いし!」
「気持ち悪いなら、お前から目を逸らせばいいだろ」
「はぁ? あーしから逸らすわけないし!」
そう言いながらも、星野の頬にほんのりと赤みがさしている気がする。
日差しのせいだろうか。いや、さっきまでそんなことはなかったはずだ。
「……な、なにニヤニヤしてんの!」
「してないけど?」
「してるし!」
星野の声が、少し裏返っている。
ポニーテールを握りしめている手が、どこかそわそわと動いているのが見えた。
——これは、照れているのか?
いやいや、あの天下の星野紗奈がそんな簡単に照れるわけがない。
けれど、その態度はどう見ても落ち着きがない。
ノンデリカシーな俺の推察からするに、星野は尿意を催しているに違いない。動揺ではなく我慢だったのか。目を逸らせば金髪ギャルが根暗男子に敗北してしまうし、かといって我慢を続ければダムが決壊してしまう。
今の星野は、そんなジレンマに立たされているんだ。
可哀想に。だが、この勝負は俺がもらう。
「赤木、もういいし! じーっと見んな!」
「お前が合わせろって言ったんだろ。俺は絶対に目を合わせ続けるからな」
「うっさい!」
結局、最後は半ば投げやりに叫ぶと、星野は急に立ち上がり、俺に背を向けた。
我慢の限界だったらしい。俺が止めるよりも先に、駆け足気味で走り出している。
「じゃ、じゃあね!」
「あ、おい!」
最後、ほんの一瞬振り返った横顔は……赤く見えた。
「……なんだよ、あいつ」
残された俺は、秋風に揺れるポニーテールの残像をぼんやりと目で追っていた。
同時に昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
俺は中途半端に残されたおにぎりを口に詰め込み、教室へと戻ったのだった。
ただ、教室には星野の姿はなかった。先生の話によると、体調を崩して保健室にいるらしい。
悪いことをした。お見舞いに行くようなことはしないが、心の中では”早く良くなるように”と願った。
◇◆◇◆
土曜日の昼下がり。
俺は特に目的もなく、街をぶらぶら歩いていた。
最近気になっているゲームのセール品でも探そうかと、古びた商店街を覗いていた時のことだ。
「——え、赤木じゃん?」
突然、聞き慣れた声が背後から飛び込んできた。
振り返ると、やはりそこにいたのは星野紗奈だった。
ここ数日のうちに三回目の邂逅となる。まるで運命の巡り合わせかのように。まあ、本当に偶然なんだろうけど。
ただし、今日は一人ではなく、派手な二人組のギャルと一緒だ。
星野は金髪で普遍的なギャル。
もう一人は黒髪だがピアスまみれであり、ボーイッシュなタイプ。この人も多分ギャル。
さらにもう一人は、明るすぎるくらいの茶髪に、カラフルなネイルに目立つアクセサリー、お姉さん感増し増しの雰囲気に抜群のスタイル。
正直、俺とは住む世界がまるで違う。
「赤木ってば意外と外出るんだね。ひきこもりかと思ったー!」
星野は駆け寄ってきて肩をバンバン叩いてくる。馴れ馴れしい。プライベートで見かけて声をかけるような間柄でもないのに、とてつもなくフランクに接してくる。
過剰なボディータッチとラフな態度に動揺しそうになったが、俺はバレないように声を取り繕った。
「星野こそ何してんだよ……」
「何って、普通に買い物だけど?」
星野は軽い調子で俺の前に立ち止まる。
その声に釣られるように、お連れのギャル二人も俺を見て興味津々な顔をしていた。
「紗奈、この人誰?」
「友達? にしては地味だけど、まさかこういう系が好みなん? 大学に行ったらもっと良い男いると思うよ?」
そう聞いてきたのは二人のギャルだった。
「んー? ただのクラスメイト」
星野は至って普通のトーンで俺を紹介した。
特に気まずそうな様子もなく、いつもの調子だ。
「クラスメイトなんだ。意外かも」
「そうそう、紗奈ってもっと派手なやつとつるんでるイメージだったけど……意外にも高校では大人しかったりするん?」
ピアスまみれの黒髪ギャルは静かな反応を見せ、明るい茶髪のお姉さんギャルは面白がるように笑いながら、俺をジロジロと観察している。
「別にクラスのやつってだけだってば。ね、赤木?」
「……まあ、そうだな。ただの同級生だ。正直、全然話したことないし。俺は星野のことなんてあんまり知らない」
俺はあっさりと肯定する。事実、それ以上でも以下でもない。
話した回数はたった三回だけ。しかも、直近の一週間のうちに三回だ。三年間全く関わりはなかったし、お互いに気にすることもなかったか間柄だ。
だが、この瞬間、星野がチラリと俺を横目で睨むような視線を向けた。
「……ふーん」
星野の声は平静を装っていたが、どこか刺々しい。
すると、茶髪ギャルがさらに話題を広げるように俺に話しかけてきた。
「ねえ赤木くん、紗奈とは仲は良くないの? あたしってば紗奈の二個上で大学二年生なんだけど、普段の紗奈は高校どんな感じなのか教えてくれる?」
「あー……すみません、よくわかりません。そんなに親しくないですし、あんまり話したこともないです。絡まれたことしかないので」
「絡むって、紗奈が赤木くんに? あはは、なにそれ面白い!」
茶髪ギャルがケラケラ笑い、黒髪ギャルも小さく微笑む。
何が面白いのかよくわからない。
その間、星野は何も言わず黙り込んでいた。
何気なく横を見ると、星野が微妙に不満そうに口をへの字にしているのが目に入る。
「何だよ、その顔」
「……べっつにー? 赤木は絡まれたとしか思ってなかったわけ? 他に何も思わなかったの?」
星野はそっぽを向きながら、気取ったような口調で返した。
何に対して不満なのか分からないが、確実に機嫌が悪そうだ。
「まあまあ、紗奈、そうツンケンしないの。どうせあれでしょ? 紗奈がアプローチしても、思ったより赤木くんが面白い反応をしないから楽しくないんでしょ?」
茶髪ギャルが軽く星野の肩を叩き、俺にウインクしてきた。
「アプローチって、そ、そんなんじゃないし! ただおもしろそーだから、ちょっとだけからかってみて……でも確かに前は見つめられて……」
「見つめられたの? 紗奈が? どうだった?」
黒髪ギャルが食いついた。
しかし、星野は慌てふためいて即座に否定する。
「ちがうし! 急に見つめられたから気持ち悪いって思っただけ! だよね、赤木!」
「お、おう」
よくわからないが、圧に負けて首を縦に振った。
なんか、すごい動揺してて新鮮だ。前は尿意を催してただけだったのだろうが、今回に限ってはあからさまに取り乱している。
「そ、それより、買い物の続きしよっ! あーし、ほしい服あるからさ!」
「……忘れてたー、あたしたち二人で夜とこあったんだったー! ごめんだけど、紗奈は赤木くんと買い物してくれる? 終わったら連絡して? それじゃ!」
茶髪ギャルは黒髪ギャルの手を引くと、脱兎の如く走り去っていった。すごいスピードだ。もう見えなくなった。
というか、星野と二人きりにさせられたんだけど……どうすんの、この状況。
「……星野?」
俺はおずおずと声をかけた。当の星野は肩を落として俯いている。何を考えているのかはよくわからないが、深いため息を吐いているのは見えた。
「赤木」
「ん?」
「……ごめん」
「何が?」
「いや、その……赤木も用事あるんだもんね。なのに変なことに巻き込んじゃってごめん」
「あー、別に気にしなくていい。俺はちょうど暇だったし、茶髪のお姉さんギャルとピアスまみれの黒髪ギャルはノリノリで楽しそうだったし」
本当に暇だったから時間的なことは全く問題ない。
まあ、茶髪のお姉さんギャルのテンションの高さに胃もたれしかけたのは内緒だが。
「二人とも大学二年生で、あーしの先輩だし。しかも、あれは楽しんでるんじゃなくて、あーしのことをバカにしてるだけだし」
「バカにしてたのか? あれ」
「……その話はもうやめた。仕方ないから赤木と買い物するしかなさそうかな」
「トイレにこもってやり過ごせないかな」
「どうせ二人揃って影から覗き見してると思うから無理っしょ。ってか、なんでそんなに行きたくなさそーにしてるわけ? うちの高校でナンバーワンギャルのあーしとデートできるんだよ? もっと喜ぶもんっしょ?」
「はいはい」
俺は軽く返事をした。
「はぁぁぁぁ……ついてきて。せっかくだし、赤木の男としての目線を聞かせな。色んな服着るから感想ちょーだいね」
星野はため息を吐いてから先に歩いていった。
俺の答えに不満があったのか?
正直、星野と話したり、こうして一緒に過ごしたりすることを喜んでいないと言えば嘘になる。
図書室で手を繋がれた時はドキドキしたし、校舎裏のベンチで肩を寄せ合った時も目を合わせて見つめあった時もドキドキした。
ただ、からかわれているのが明白なので、それ以上の感情を持つことはなかった。
更に言えば、今日で三回目の邂逅となるので、俺はそこそこ心の準備ができ始めていたのもある。
結局のところ、俺はギャルゲーしかしたことない恋愛未経験プレイヤーなわけで、現実世界の金髪ギャルとは相容れない存在だ。
当然のように向こうが俺に惚れることもなければ、立場を弁えた俺が靡くこともない。
どうせ高校卒業までの二、三ヶ月間の一過性のイベントだろうし、テキトーに過ごして終わらせるのが吉だろうな。
◇◆◇◆
星野に引っ張られる形で向かったのは、駅前の商業ビル。
三階建ての施設には、若者向けのファッションショップがぎっしり詰まっている。
「……本当に俺、ここに入って大丈夫か?」
「何が? 普通じゃん。むしろあーしと一緒だから安心でしょ?」
星野はあっけらかんとしているが、俺にはこの手の空間は未知の領域だ。
眩しい店内、オシャレなBGM、そして服を選ぶ客たちのキラキラ感。
どれも俺とは無縁すぎて、すでに逃げ出したくなっていた。
「ほら、こっち行こ」
星野に急かされ、意を決して店内に足を踏み入れる。
最初の店は大人びた服が多かった。
星野は慣れた様子で棚から服を選び、次々と手に取る。
「ね、これどう思う?」
星野が持ってきたのはチェック柄のワンピース。
どこか秋っぽい色合いで、落ち着いた雰囲気だ。
「……似合うんじゃないか?」
「んー、じゃあ試着してみるから、ちょっと待ってて」
そう言い残して、星野は試着室に入っていった。俺は促されるまま近くの椅子に座り、視線を彷徨わせる。周りはオシャレな女子ばかりで、完全に場違い感が半端ない。
しかし、試着室のカーテンが開くと、そんな考えは一瞬で吹き飛んだ。
「どう? これ」
星野が出てきた瞬間、言葉を失った。
シンプルなチェック柄のワンピースが彼女に驚くほどよく似合っている。
普段のギャルっぽい派手さとは違い、大人っぽくて、どこか清楚な雰囲気が漂っていた。
「……すごく似合ってると思う」
正直な感想が口をついて出た。
すると、星野は少しだけ照れたように髪を触る。
「そ、そっか。ま、赤木がそう言うなら買っちゃおうかな」
珍しく控えめな反応に、俺は少し驚いた。
その後も、星野は何着か試着を繰り返した。
毎回「どう?」と俺に感想を求めてくるので、なるべく的確に答えるようにした。
「このスカート、どうかな?」
「うん、脚が長く見えていいと思う」
「このトップスは?」
「派手すぎずにオシャレだし、星野らしさが出てる」
俺の言葉に星野は素直に喜んでいた。
いつもの茶化すような態度はどこか影を潜め、純粋にファッションを楽しんでいる様子だった。
「へへ、赤木って意外とセンスあるじゃん。将来、スタイリストにでもなる?」
「いや、ならないけど」
軽口を叩く星野に返しながら、俺は内心で不思議な感覚を抱いていた。
これまで突っかかってくるか、からかってくるかのどちらかの星野が、今日はやけに楽しそうで、しかも素直だ。
もちろん、俺が星野に惚れるなんてことはない……はずだ。そう考えていたし、確信していた。
けど、こうして目の前で色々な服を着て嬉しそうにしている姿を見ると、自然と「素敵だな」と思ってしまう自分がいる。
向こうはこんな態度を見せてくれてはいるが、内心はどうせ俺のことなんて眼中ないと思う。だって、星野は別世界の住人だから。
校内の人気者で見た目も良くて性格も明るい。俺とは到底釣り合わない。
だから俺は惚れてはいけない。決して心を靡かせてはいけない。
「……」
心に思いを決めていると、目の前のカーテンがゆっくりと開かれた。
星野が最後に試着したのは、シンプルなダークブラウンのニットワンピースだった。少しだけ肩が見えるデザインで、普段の星野にはない柔らかさを感じさせる。
色合いも秋冬っぽく温かみがあり、素材感も相まってより一層大人びていた。
「これ、どう?」
「……なんか、すごくいいと思う。大人っぽいし……可愛い」
自分でも驚くほど真っ直ぐな感想を口にしていた。
まずい。あんまりこういうストレートな表現は口にすべきじゃなかった。キモがられるし、もしかしたら周りに吹聴されてしまうかもしれない。
俺は息を呑んで、自分の吐いた言葉を後悔した。
しかし、目の前の星野は、俺の予想とは裏腹に全く違う種類を反応を見せていた。
彼女は、ふいっと視線を逸らして「そ、そっか」と小さく呟くだけだった。
その耳が、ほんのり赤くなっているのを、俺は見逃さなかった。
「……あーし、これ買うわ」
星野は恥ずかしそうにそっぽを向きながら、ニットワンピースの裾を軽く引っ張った。
その動きがどこかぎこちなく、普段の彼女の自信満々な態度とは違う。
なんか、妙にドキッとする。
これ以上見つめたら、変な空気になりそうで、俺は慌てて視線を逸らした。
意識が持っていかれそうだった。誓ったはずの心持ちが変わってしまいそうだった。
「……いいと思うよ。似合ってる」
俺は静かに答えた。
「そ、そっか。じゃあ、これで買い物は終わりだし!」
星野は軽く手を叩いて、自分を無理にでも元の調子に戻そうとしているようだった。
その時、まるでタイミングを見計らったかのように、二人組のギャルが現れた。
「おー、いいじゃん紗奈、そのニット。デートっぽいじゃん!」
茶髪ギャルがにやにやしながら星野に声をかける。
「赤木くんとペアルックにしちゃえば?」
ピアスまみれの黒髪ギャルも、茶化すような視線を俺に向けてくる。
「……ペアルック? あーしがこれを着るからには、相手はもっとちゃんとしたイケメンじゃないとだし!」
星野はぷいっと顔を逸らして、ふてくされたように反論する。
しかし、尚も茶髪ギャルはニヤニヤをやめない。
「紗奈は赤木くんのことイケメンじゃないとダメって言ってるけど、普通にかっこいいクールな顔してない? 地味めな雰囲気はあるけど、話したらけっこー楽しいし、もしかしたら狙ってる女の子もいるかもよ?」
「……優しい系だから意外にモテると思う」
茶髪ギャルが肘で小突いてきた。ついでと言わんばかりに、黒髪ギャルが横から覗き込んでくる。
お世辞なのは分かってるが、顔と性格を良く言われるのは少し嬉しかった。
「……まあ、その辺にいるいけすかないナンパ男よりはずっとマシだし」
二人に乗っかるようにして、星野の反応もそんなに悪くなかった。
「だってさ!」
「……ずっと俺抜きになんの話してるんですか」
魔に受けたら負けるような気がしたので、俺はしらを切って話を流した。
「で、で、で? ペアルックはどうなの? 赤木くん、否定はしてなかったけど、まさかやる気満々だったりする!?」
「そういうのは星野に悪いんでやらないですよ。本人の言うとおり、もっともっとふさわしい人がいると思いますしね」
茶髪ギャルの問いかけに対し、俺は即座に否定した。
断る以外の選択肢はなかった。ギャルゲーの世界なら、ここはグイグイいくべきだが、あいにくここは現実世界だ。
こんなところで攻めてしまったら、ドン引きされて冷ややかな目で見られるのは確実だった。
現に、星野は少しだけ眉をしかめていたが、俺がその返答をしたことですぐに何でもないような顔に戻っていた。
当たり前だが、俺如きが彼女の恋愛面を茶化す真似はよろしくないな。
「ふーん、今はまだそんな感じなんだー。じゃあ赤木くんの出番はここまでかな。ありがとね、色々つきあってくれて」
「あ、はい」
「他に用事あるだろうし、紗奈の服は改めてあたしたちがチェックするから、赤木くんは帰っていーよ!」
「……わかりました。それではまた。星野もまたな」
俺は茶髪ギャルに気圧されるがままに店を出た。
店の外から振り返ると、星野は二人のギャルと何か楽しそうに話しているように見える。
ほっぺたを膨らまし、身振り手振りで何かを伝えているようだった。
「……まあ、これでいいんだろうな」
そう呟きながら、俺は来た道を引き返した。
どこか胸の奥にモヤモヤした感情が残っている気がしたが、それが何なのか、俺にはまだわからなかった。
星野のこと? それとも自分のこと?
なんなんだろうな。この感覚は。
◇◆◇◆
十二月を目前に控え、季節は秋から冬へ移り変わる最中。暖房が入り始めた図書室はぽかぽかと暖かく、休息にはうってつけだった。
午後の授業が自習になったおかげで、俺はここでのんびりできている。静かな空間に身を沈めていたが、ふと入口から軽い足音が聞こえてきた。
顔を上げると、見知らぬ後輩の女子が棚を見回している。困った様子で目を泳がせていた。
そのぎこちなさに、俺はつい声をかけた。
「何か探してるのか?」
驚いた顔で振り返った彼女は、少し赤面しながら答えた。
「あ、はい。一年生の生物の授業で使う参考書を探してるんですけど、どこにあるのか分からなくて……」
「ああ、それならあっちだよ」
俺が指差すと、後輩は顔をぱっと明るくして走り去り、しばらくして本を抱えて戻ってきた。ほんのり頬が赤くなっている。
「ありがとうございます! 先輩、三年生ですよね? お勉強、頑張ってください!」
謎のエールを残し、後輩は小走りで去っていった。
俺はぽつりとつぶやいた。
「……変わった子だな」
後輩女子とのやりとりを終えて机に戻ろうとしたその時、視線を感じて振り向くと、図書室の出入り口に星野が立っていた。
いつもならテンション高く絡んでくるのに、今日は様子が違う。眉を少しひそめ、口元を引き締めている。
「星野? どうしたんだ?」
声をかけると、星野は顔をそむけながら小さく答えた。
「……別に。ただ見てただけ」
どことなく不機嫌そうなその表情に、俺は少し戸惑う。
「さっきの後輩の子、知り合い?」
星野はこちらに近づきながら、軽く尋ねてきた。
「あの子? 全然知らない子だよ。参考書の場所を教えただけだな」
俺がそう答えると、星野はわずかに笑った。
「ふーん。でも、あんまり親切にしすぎない方がいいよ。先輩にいい顔してるだけかもだし」
冗談っぽく言われ、俺は肩をすくめる。
「わかってるよ」
「ほんとにー?」
「……なにを気にしてんだよ」
俺がそう返すと、星野は急に黙り込んだ。
そして、俺の隣に腰を下ろしながら鞄から文庫本を取り出した。
「というか、なんで俺の隣に座るんだよ? 席ならたくさん空いてるだろ」
俺が問いかけると、星野は少しふざけた調子で答える。
「最近、赤木と静かに過ごすのも悪くないって思ってさ。これって大人になった証拠かな?」
「知らんけど。てか、本とか読むなんて意外だな」
俺が思わず口にすると、星野はムッとした表情で睨んできた。
「バカにしてんの?」
「そういうわけじゃない。勉強はしなくていいのか?」
「勉強は嫌いだからしない主義!」
「へー」
俺は淡白に返して話を終わらせた。
星野の学力や進路は知らないが、勉強嫌いなら強制することはないか。人付き合いがうまそうだし見た目もいいから、勉強なんかしなくても大丈夫なタイプだと思う。俺とは違ってな。
それから図書室には静かな時間が流れた。
俺は机に伏せて目を閉じて心を整え、星野は俺の隣でのんびり読書にのめり込んでいた。
「……あ、そういえば」
ふとした拍子に、星野が俺の肩を指で突いてきた。
「どうした?」
顔を上げて星野を見上げた。彼女の視線は図書室の掲示板へと注がれていた。
「ねぇ、赤木。駅前のイルミネーションって見たことある?」
星野が見ていたのは、掲示板に貼られたポスターだった。
どうやら、クリスマスを目掛けて、駅前に大々的なイルミネーションが展開されるらしい。
ポスターにはカラフルな光が散りばめられている。
「イルミネーションなんて、あんまり見たことないな」
俺には無縁だった。
ゲーム内ではヒロインと共に数々のイベントを消化してきたが、現実世界では一度として堪能したことがない。
「ふーん」
「星野は誰かと行く予定でもあるのか? 友達のギャルとか」
「あの二人は彼氏いるし。今んとこ、あーしにそんな予定はないよ。なに、あーしの予定が気になったん?」
「試しに聞いてみただけだ。仮に俺と星野が二人でイルミネーションなんて見てたら、クラスの連中に影でバカにされるだろ。だから俺から誘ったりはしないよ」
自分で言っていて悲しくなるが、俺と星野じゃ全く釣り合いが取れない。
今だって一緒に時間を過ごしているが、誰かに見られるのはよろしくないことなのだ。
変な噂がたったら星野に迷惑がかかる。
「はぁ? そんなこと気にしてんの?」
「……星野だって嫌だろ。普段は陽キャとつるんでるのに、俺と話していても面白くないだろうし……」
「なに言ってんの。赤木だって面白いし! たまーにあーしの胸を見てたり、髪の毛の匂い嗅いでる時はちょっとだけキモって思うけど、それでも悪いやつじゃないのはわかるから! もっと自信持っていいっしょ!」
褒められているのか、暴露して辱めようとしているのか、それははっきりわからない。ただ、星野の言葉に嘘はなさそうだった。本当に俺のことを嫌いではないらしい。変わり者だ。
ギャルのくせに根暗の俺なんかに構う時でおかしいが、こうして対等に話をしてくれるのはもっとおかしい。
「……星野が嫌じゃないならいいんだけど」
「あーしはそんなん気にしないし! むしろ、変なこと言うやついたらぶっとばすからさ!」
星野は手をグーにして素振りを披露した。
決して強そうには見えないが頼りにはなる。俺にはない性根からの明るさを持っているからか、話してるだけで自然と俺の気持ちも明るくなる気がする。
「ありがとう」
「で、話は戻るけど……あーしと行かない? イルミネーション!」
「え? 星野と?」
咄嗟に聞き返す。まさかの誘いだった。
「うん。ダメ?」
「….星野さえ良ければ」
唐突な誘いに俺は一瞬面食らったが、特に断る理由なんてなかった。
イルミネーションが気になるのもそうだし、何よりも今は星野と時間を過ごしたいと思うようになっていた。
恥ずかしいことに、俺はゲーム内だけでは満足できなくなっているのかもしれない。
星野を見ていると……少し気分が高揚してしまう。
「やったー! 今週の日曜、駅前に集合だし!」
星野は静かな図書室に声を響き渡らせると、俺の左腕をがっちり掴んできた。
以前よりも一層強くホールドされているせいで、星野の柔らかい二つのボールがぶち当たる。
キモがられないようにリアクションはしないように心掛ける。
「お供します」
鼻では良い匂いを感じ、左腕には未知の柔らかさを感じ、耳では嬉々とする星野の声を感じていた。五巻の全てを星野に支配されている状態だ。
「お供しますってなに? 桃太郎? 犬とかサルのセリフにある”お供させてください”的なアレ? もしかして、赤木ってドMってやつ?」
「違う。俺は猿じゃなくて人間だし、ドMじゃない。多分、ノーマルだ」
「へー。じゃあ、今度の日曜ね! マジで楽しみだし! 赤木もワクワクして待ってなね!」
星野は俺よ華麗なツッコミを受け流すと、文庫本を片手に図書室から走り去っていった。
二度目の拝見となるルンルンステップだ。
スカートが短いから、後少しふわっとすれば中身が見えてしまう。俺には刺激的すぎる。
「……はぁ……夢か? これ、ゲームの世界に迷い込んだのか?」
取り残された俺はボーッと虚な気分に陥っていた。
まさか、つい数週間前までは話したことすらなかった金髪ギャルと、二人でイルミネーションを見に行く日が来るなんて……全くの予想外だ。
嬉しい反面、これが現実の世界とは思えなくなる。
「来週の日曜、楽しみだなぁ」
昼下がりの図書室で、俺は一人でにやけたのだった。
ちなみに、窓ガラスに反射する俺のニヤケヅラは心底気持ち悪かった。
◇◆◇◆
星野と二人でイルミネーションの話をした翌日。
クラス中で妙な噂が囁かれ始めた。
「赤木が紗奈に手を出したって本当?」
「ああ見えて二人ともノリノリらしいよ」
「マジで?あんな地味男、絶対ないでしょ。俺の方が幸せにできるって!」
噂はどんどん広がり、クスクス笑う声が耳に入ってくる。
俺の名前と星野の名前が同じ会話に出るたび、嫌な汗が背中を伝った。
言い出したのは陽キャの連中だ。
彼らは普段から星野と軽口を叩き合うようなタイプで、俺なんかには話しかけてもこない人種。
そんな彼らの一言一言が教室の空気を変えていった。
だが、対する当人の星野は噂なんて気にしていないように見えた。
むしろ、いつも通り堂々としている。
昼休みになると、彼女は変わらず陽キャ連中と盛り上がっている。
教室では俺に話しかけてくることはほとんどないが、時折視線を向けてくることはある。
今もそうだ。星野は陽キャ連中と話しながらも、ちらちらとこちらを見てきた。まるで捨てられた子犬を見るかのように。
ジレンマがあるのだろう。
友達との付き合いと、俺との交友を天秤にかけて迷っているように見えた。
ただ、そこは俺を優先してほしくはなかった。
確かに、星野は気にしていないのかもしれないけど、俺にはわかる。いつもより視線が泳いでいたり、声が微妙に小さいことに気づいてしまう。
変に俺のことを気にするあまり、いつもの自分を出せていないようだった。
「……くそ」
教室の隅の席で、俺は一人悩み込んだ。
教室の雰囲気も変わり始めていた。
俺が何かをするたびに、笑いをこらえたような声が漏れ聞こえる。
誰も星野本人に噂の真意を聞くことはなく、ただそれに呼応するように遠くから薄ら笑いが返ってきた。
「赤木、なんか調子乗ってない?」
「紗奈って、誰にでも優しいんだな~。あいつには不釣り合いだよ」
そんな陰口が聞こえるたび、俺の心はざわついた。
翌週。
相変わらず、星野は本当に噂なんてどうでもいいと思っているように見える。
実際、彼女は教室のど真ん中を堂々と歩き、陽キャ連中の軽口にも笑顔で返している。
けど、俺にはわかる。廊下でふと視線を伏せる瞬間や、ため息をつく姿が痛々しかった。
昼休みになり、いつものように俺が校舎裏のベンチに腰掛けていると、そこに星野がやってきた。
「赤木、変な噂気にしすぎだよ。あーし、全然気にしてないから! 前も言ったっしょ?」
その無邪気な笑顔に、俺は何も言えなかった。
だけど、それでも俺は悩んだ。
口では気にしていないと言うが、それは彼女が強いからだ。
俺がそばにいることで、星野が居心地悪くなっているのではないか。
それがどうしても引っかかった。
「……少し、距離を置いたほうがお互いのためだな」
俺は自分で自分にそう言い聞かせるように、机に向かった。
次の日から、俺は星野のことを目で追うのをやめた。ごくたまに教室で声をかけてくることもあったが、それすらも適当にあしらった。
そして、何かしら理由をつけて教室を離れるようにした。それが正しいことだと思ったから。
だが、そんな俺の態度に気づかない星野ではなかった。
俺が距離を取るようになっても、星野は変わらず教室で笑っていた。
噂なんて気にしないと強がる姿は、相変わらず堂々としている。それでもその笑顔がどこか空回りしているのも、俺にはわかっていた。
そしてついに展開が変わった。
ある日の放課後になったばかりの時間だった。
星野は人目も憚らず俺の机の前にやってくると、机をバンっと叩いて強く言い放った。
「もうダメ! 我慢できない! あーしが全部終わらせる! 赤木は黙ってていいから!」
星野は自信満々だったが、俺は心配しかなかった。
「そんなことしたら、余計に変な噂が広がるだけだろ」
「いいの! あーしのやり方で、みんなにわからせてやるから!」
星野はそう言ってクラス中を見渡した後、大きく息を吸い込んだ。
「最近、あーしと赤木のことで変な噂が出回ってるけど、何か言いたいこと、聞きたいことがある人いる?」
彼女は余裕を装うように腕を組んでいた。
しかし、その手が微かに震えていることに俺は気づいた。
結局、無理してるんじゃないか。
星野の意気込みに応えられるような器量が、俺にあるとは思えなかった。
俺が黙って見ているわけにはいかない。
星野が噂の矢面に立つくらいなら、俺がその役を引き受ければいい。
それが星野を守る最善策だと考えた。
「はぁぁ……なんでこんなことになったんだ」
俺は机に伏せてやるせない出来事の連続に辟易した。
クラスは静まり返っている。思わぬ宣言をした星野を見て誰もが驚愕していた。
同時に、俺に対する視線は鋭くなっていった。
今しかない。
絶好の機会だった。
これを機に、こんな意味不明な噂は終わらせよう。
「——ありもしない噂をしてる奴らに言っとくけど、悪いのは全部俺だ。星野には関係ない。俺が無理やり星野を遊びに誘ったんだ。星野は優しから断れずに受け入れてくれた。本当は嫌だって思ってるのにな」
瞬間、教室がざわついた。
全ての視線が俺へと集約され、陽キャのリーダー格がニヤッと笑った。
「はぁ? 赤木、お前が何したって? はっきり言えよ。紗奈を口説いてたんだろ? 正直、釣り合ってないって思わないか? まさか惚れたとかいうのか?」
その言葉に笑いが起きるかと思ったが、直後に教室の扉が勢いよく開いた。
「紗奈ー! いるー? 久々に来たわー!」
入ってきたのは、二人のギャルだった。
一人は明るすぎるくらいの茶髪に派手な服装に高めのヒール、キラキラのネイル。
もう一人は落ち着いた黒髪だが、顔やら耳やらピアスまみれ。クールな雰囲気を身に纏っている。
俺は二人のことを知っていた。星野の先輩だ。大学二年生だったはずだが、どうして高校にいるのだろうか。
二人は周りの空気を全く気にせず、軽い調子で歩いてくる。
「あれ? なんかこの空気、めっちゃ重くない?」
茶髪のギャルは星野を見つけて手を振っていたが、教室に漂う妙な空気感に気がついた。
「なんか、あったの?」
ピアスまみれの黒髪のギャルが星野に尋ねたが、星野はなにも答えなかった。いや、言葉を考えているようだった。唇を噛んで下を向いている。
すると、見かねた茶髪のギャルが俺に気がついた。
「赤木くんもいるじゃん! おひさー! さては訳あり? お姉さんたちが話聞いたげよっか?」
二人は周りの空気を全く気にせず、陽キャたちに近づいていった。
そして、陽キャのリーダーに目を向けた。
「ねぇ、何があったわけ? よくわかんないけど……その感じならなんか知ってそーだね?」
リーダー格の陽キャは一瞬たじろいだものの、わざと軽い口調で答えた。
「いや、赤木なんかが紗奈のことを口説いてるっぽかったから、釣り合わないんじゃねって話してただけっすよ。別に悪いことはしてないっす」
その瞬間、二人の雰囲気が変わった。
ノリとテンションで喋っていたような二人の瞳が冷たく光り、空気が一気に張り詰める。
「へぇ、そういうこと言うんだ」
「わたし、あんまりそういうの好きじゃないかも」
二人が低い声で静かに口にした。明らかに怒っている。なんか俺に対しては優しい視線を向けてくれてるけど。
「……みんなは紗奈がどんな子か知らないでしょ? あの子に変なこと言うなら、覚悟してよね。あと、赤木くんもあたしたちの知り合いだからさ~」
陽キャたちが顔を引きつらせて黙り込む。
一触即発、そんな雰囲気だった。
しかし、ピリついた空気感を打ち破るようにして、星野が一歩前に出て手を広げた。
ギャルたちの肩を軽く叩いた。
「ちょっと待って、もういいから!」
ギャルたちは怪訝そうに彼女を見たが、星野は微笑みながら教室全体を見回した。
「えーっと……あーし、赤木とは付き合ってないし、そういうのでもない。でも、今は大事な友達だから変なこと言われるのは我慢できない。……だからさ、あーしのことで何か機になることがあるなら直接聞いて? いい?」
教室が静まり返る中、星野は堂々と胸を張って言った。
一転して、ギャルたちは満足そうにうなずき、陽キャたちはバツが悪そうにうつむいた。
皆が居心地が悪そうにしている。黙りこくり、どうすればよいのかわかっていないようだった。
「……」
最中、俺はひっそりと教室を抜け出した。
二人のギャルと星野とは目が合ったので、軽く会釈をして別れを告げた。
向かった先は、校舎裏のベンチだった。
どっかりと腰掛け息をつく。
多分、これで噂話は完全に終息すると思う。でも、払った犠牲は大きかった。星野はああやって宣言したことで、陽キャ連中との確執ができてしまうだろう。
卒業まで残り二ヶ月程度と考えれば、まあそれほど問題ではないかもしれないが。
「……これで正解だったのかな」
膿がなくなった一方で、あまりスッキリしない気持ちもあった。
結局、俺と星野はこれから関わりを持ってもいいのか、果たしてイルミネーションには行けるのか、色々と考えてしまう。
と、俺が思考していると、一つの足音が近づいてきた。
「……赤木」
やってきたのは星野だった。
真剣な顔つきでこちらを見下ろしている。
「星野……大丈夫か?」
「あーしはずっと平気だし、まあ……ここ最近の空気感はちょっとだけ苦手だったけど。それより、赤木は? 元気? 陰口とか叩かれて、悪口を言われて、辛くなかった? ごめんね、あーしがもっと早くなんとかしてあげられるのが一番だったんだけど、やっぱり言い出しにくい感じがしちゃって……」
星野は俺の隣に腰を下ろすし、俺の肩を身を預けると、今にも泣き出しそうな表情で捲し立てた。
「星野が気にすることじゃない。悪いのは変な噂を流した奴らだし、ギャル先輩二人には感謝しないとな」
「……うん」
途端に沈黙が訪れた。
不思議と気まずくはない。
ただ、互いに言いたいことを素直に言えない、そんな空気が流れていた。
「……なぁ」
沈黙を破ったのは俺だった。
「なに?」
「イルミネーション、一緒に見れるんだよな?」
「……もち」
「よかった」
「その感じ、赤木はめちゃくちゃ楽しみにしてくれたってこと?」
「……まあ、うん。そうだな」
「そっか。あーしも楽しみにしてる! 二人にはあーしの口からきちんとお礼しとくから、赤木は今回のことは全部忘れること! なんもなかった! わかった?」
「わかった……またな」
「また!」
星野は言いたいことを言ってわだかまりが消えたのか、最後には爽快な顔つきで立ち去った。
俺たちの間にあった鬱憤はこれでなくなった。そして、明日以降で噂も終息しそうだ。
俺は一瞬、何かがほどけるような感覚を覚えた。
そして、いつの間にかイルミネーションの日が目前に迫っていた。
◇◆◇◆◇
ふわふわとした柔らかな雪が降る中、俺たちは約束通り、街のイルミネーションを見に行った。
いつも教室で見る星野とは違い、私服の星野は少し大人っぽく見えた。
ギャルらしい派手さはそのままだが、どこか落ち着いていて、俺は一瞬言葉を失った。
「このワンピ、赤木がオススメしてくれたやつ。どお?」
「……」
「なに、黙ってるし。似合ってない?」
星野がからかうように言う。
俺は慌てて首を振った。
「いや、似合ってる……すごく」
言った瞬間、星野が驚いたように目を丸くしたが、すぐに照れたように目をそらした。
薄暗いので顔色はよくわからないが、イルミネーションの光に照らされる横顔は少し赤いように思える。
「赤木って、たまーにそういうこと言うよね」
星野は俺を残して先に歩き始めた。
雪を踏みながら、光のトンネルを抜けていく。
イルミネーションは本当に綺麗だった。
きらめく光が通りを埋め尽くし、人々の顔を穏やかに照らしている。星野はそんな風景を見上げながら、ふとつぶやいた。
「……あーし、こういうの嫌いじゃないかも」
「ああ、意外とこういうのも似合うな」
俺がそう言うと、星野は少しむくれたように笑った。
「なにそれ。似合わないとか思ってたの?」
「まあ……ギャルってよりは、黒髪で清楚な子が似合う勝手なイメージだった」
「赤木がやってるゲームだとそうかもだけど、あーしは真夏のチャラい海とかバーベキューとか、真冬のノリノリのスノボとかよりも、こういう落ち着いた場所が好きってこと。ってか、そこ言い方だとあーしが清楚じゃないって言ってるように聞こえるんだけど? どうなの?」
「いや、そう言われても、金髪のギャルが清楚系は少しだけ無理があるんじゃないか……?」
「あーしは清楚だし、誰とも付き合ったことはないし!」
「え? そ、そうなの?」
「うん」
「じゃあ……なんで初対面の俺の腕をホールドしてきたりしたんだよ。あんなの男を弄ぶギャルの仕業だろ」
「あ。あれは、その、衝動的というか。本当に暇つぶしでやってみよーってなったからやってみただけだし! そしたら赤木がたまたまあーしの好み……違う、んー、もういいっしょ! この話は!」
星野は顔を背けて拗ねてしまった。そんな様すら良いなって思えてしまう。
俺なんかに声をかけてくれて感謝しかない。こうして今も楽しい思いでいられるのは、星野のおかげだった。
「……ありがとう」
その言葉に、星野は一瞬何かを言いかけたが、結局黙ったままイルミネーションを見続けていた。
俺たちは肩を並べて歩きながら、たわいもない話をした。星野の笑顔を見ていると、俺の中の迷いが少しずつ溶けていくようだった。
やがて、イルミネーションを見終えると、俺たちは特になにもなく解散することになった。
別れ際に星野は何か言いたげな表情だったが、俺にその真意を尋ねる勇気はなかった。
お互いに少しだけ緊張していたし、上手に話ができていなかったような気がするから仕方がない。
ただ、心は確かに幸せに満ちていた。
多分この思い出を忘れることはないと思う。
◇◆◇◆
イルミネーションの日以来、俺たちの間に流れる空気は確実に変わった。でも、付き合うとか、そういう関係にはならなかった。ただ、それでもいいと思えた。
以前とは違い、教室でもよく話すようになったし、昼休みには一緒にご飯を食べたりした。
クラスのみんなもそれを茶化すことなく、むしろ積極的に話しかけてくれることも増えた。
高校生活の最後の最後に、何人か友達ができたのは素直に嬉しかった。
やがて冬休みに入ると、高校三年生の俺たちは進学や就職に向けてそれぞれの道を歩み始めた。
卒業式まではしばらく学校が休みになるが、指定校推薦を決めていた俺は暇を極めていた。
みんなは忙しいだろうから声をかけられなかったし、結局はまた一人で過ごす時間が増えていた。
星野と出会ってからあまりプレイしていなかったが、俺はまたギャルゲーにのめり込んでいた。
本当は星野と出かけたり、話をしたかった。でも、俺は星野と連絡先を交換していなかった。
彼女から聞かれることもなかったし、俺も聞けなかった。そんな勇気はなかった。
でも、あの時のイルミネーションの光と、隣で笑っていた星野の横顔は、ふとした瞬間に思い出していた。
忘れられない。俺の中で一番の思い出だった。
◇◆◇◆
月日が流れると、俺は慣れないスーツを着て大学の入学式に来ていた。
桜の花びらが舞う四月、俺は大学生になったのだ。
期待や不安が入り混じるキャンパスでの生活。
だが、俺は入学式すらサボって、校舎の隅でギャルゲーをしていた。
出席したら色々と物をもらえるらしいが、強制ではないらしいのでサボることにした。
そもこも人混みは好きではないし、何よりもギャルゲーの続きが気になって仕方がなかった。
「うーん……『笑って誤魔化す』か『想いを伝える』か。ちょっと難しい選択肢だな」
場面は冬のクリスマスイブ。二人でデートを終えた後の公演での一幕だ。ヒロインの好感度は目視不能だが、俺の見立てだとそれほど高くない気がする。
たまにデレたり、可愛らしくツンケンする様子は見せてくれるが、それでも想いを伝えるには早い気がしていた。
「あーーー、どうしよーかー」
悩みに悩み、夢中で画面を見つめえいると、不意に後ろから声をかけられる。
「ここは『想いを伝える』っしょ! チキってないで、こーゆー時はビシッと伝えるのが一番だし! ってか、またそんなところでゲームしてるし。赤木は本当に変わんないね」
「え?」
驚いて振り返ると、そこには星野がいた。
相変わらず派手な格好で、少し笑いながら俺を見ている。
「え? ほ、星野……?」
「入学式は出ないの?」
戸惑う俺を尻目に、星野はケロッとした様子で聞いてきた。
彼女の軽口に、俺はしどろもどろに答える。
「いや、その……ちょっと面倒でサボってただけだ」
俺が笑って誤魔化すと、星野は呆れたようにため息をつく。
「ほんっとに変わんないね。でも、まぁいいや。あーしも入学式すぐ抜けてきたし」
「え、星野って大学受験してたのか? ここに受かったのか? 割と難関だったと思うけど……」
「はぁ? あーしがギャルだからって舐めてんの? あーしだってバカじゃないし、ちゃんとやるときはやるんだから!」
星野の得意げな顔に、俺は思わず笑ってしまった。
まさかのまさかだ。勉強をしているところなんて見たことなかったし、てっきりおバカなのかと思っていた。
嬉しい誤算だ。
星野が同じ大学に進学してきたという事実は、俺にとって予想外だった。でも、また彼女とこうして話せるのが不思議と嬉しいと思った。
「でさ、赤木。このあとは暇?」
「暇だけど」
「じゃ、久しぶりに一緒にどっか行こうよ。って言っても、二人きりで出かけたのなんて買い物の時とイルミネーションの時だけど」
そう言って笑う星野を見て、俺は新しい生活の中で、また彼女との新たな物語が始まりそうな予感を感じていた。
今は大学受験やら就職やらの影響で、学校中が忙しなくなっている。
授業中であろうと静かとは呼べず、誰もがピリピリしながら過ごしている。
そんな喧騒が嘘みたいに、ここは落ち着いている。
まるで別世界に来たかのようなこの場所は、そう、図書室。
俺、赤木斗真が最も気を許せる場所だ。
理由は簡単。誰もいないから。
コミュ障で人付き合いが苦手で、友達がほぼいない俺にとって、高校生活は苦行以外の何者でもなかった。
だから、たまにこうして授業をサボり、図書室に逃げ込むことがあった。
大学進学は推薦で確定させているし、もう授業に出ずとも卒業はできる。あとは残された二、三ヶ月間の高校生活をすり潰して過ごすだけだ。
「ふぅ……」
図書室の隅の隠れたスペースで、家から持ち込んできたゲーム機をいじる。
プレイしているのは、この前セールで買ったギャルゲーだ。
ゲーム内のヒロインが俺に笑顔を向けてくれる。
それだけで、現実の煩わしさを忘れられる。
「選択肢は……『手を繋ぐ』か、『見つめ合う』……か。花火大会のイベント終わりだから、ここは攻めてみてもいいな」
小声で独り言を漏らしながらボタンを押す。
手を繋ごう。二人きりで花火大会に来れた時点で、脈なしというわけではないはずだ。
「……さあ、どうなる」
俺はドキドキしながらヒロインの反応を待った。
ヒロインの彼女は金髪を風に靡かせながら、頬を赤く染めていた。
そして、数秒後。
手を繋いだ効果はテキメン。ゲーム内のヒロインが照れた表情になり、グッと距離を詰めてきた。
よし、選択に間違いはなかったらしい。さすがだ、俺。
こうして授業中をサボって、一人で図書室に逃げ込み、ゲームに興じるのもまた悪い選択ではないのかもしれない。
一種の青春だ。
陽キャの青春はよくわからないが、俺にとっての青春は孤独にゲームと向き合うことだった。
なんて思いながら、次の会話イベントに集中していると、不意に背後から声がした。
「ねぇ、あんたなにしてんのー?」
唐突な声に、俺は反射的にゲーム機を懐に隠した。
恐る恐る振り向くと、そこには金髪の女子——制服のスカートを短くし、ネイルを輝かせた派手な存在が立っていた。
ま、眩しい! 直視できん!
なんだこのギャルは! ゲームの世界から飛び出してきたのか!?
「……どなたでしょうか」
口をついて出た一言に、金髪ギャルはニヤリと笑った。
「星野紗奈だよ? うちの生徒のくせに、あーしのこと知らないとかマジで言ってんの? っつーか、あんたこそ誰? 上靴の色一緒だし、あーしとタメ? 三年だよね?」
グイグイくる金髪ギャルの名前は、星野紗奈。
しらばっくれてとぼけたが、本当は彼女のことを知っている。
だって、一応同じクラスだし、このギャルはめちゃくちゃ目立つし、見た目の派手さと性格の明るさは有名だった。
ってか、こいつ可愛すぎるだろ。
目は大きくてキラッキラ輝いてるし、右の下の泣きぼくろは色気がある。短いスカートの下に見える太ももはしなやかで長い。もうゲームの世界から飛び出してきたキャラクターのようだった。
こんなに近くで顔を見たのは初めてだ。
ゲーム内なら即攻略対象になるが、あいにく俺とは縁遠い存在だ。
「……」
自己紹介をすべきか?
それすらもわからず困惑してしまい、俺は無言で立ち去ろうとした。
しかし、金髪ギャルはそれを許してくれない。
「待ちなー、なんで逃げようとすんのさ。何隠したのか見せなよ!」
「……嫌だ」
「はぁ? お互い授業サボってるくせに生意気なんですけど、先生にチクるよ?」
「っ! それは卑怯だろ!」
先生に言うのは反則だ。横暴だ。同じサボり組ではあるが、俺と金髪ギャルの発言力には天と地ほどの差がある。先生にバレるのはまずい。
「やっとちゃんと喋った。で、あんたの名前は? あーしとタメっしょ?」
「……赤木斗真。一応、三年二組で同じクラスだ」
「まじぃ!? うちのクラスにいたっけ?」
金髪ギャルは飛び跳ねて驚いた。いちいちリアクションがうるさい。誰もいない図書室の静けさを返してくれ。
「で、赤木はこんなとこで何してんの?」
そう言いながら、彼女は遠慮もなく俺の隣の席に座る。
香水だろうか。甘い匂いがふわりと漂ってきて、無意識に少し身を引いてしまった。
良い匂いだが、俺には刺激が強い。
なんかこう……樹液に群がる虫の気分になる。情けないことにクラクラしてくる。
「なんで離れるし!」
星野は尚も距離を詰めてきた。もう諦めよう。こういう性格の人からは逃げられない気がする。
「……それで、なんだっけ? 俺が図書室で何してたって話だっけ?」
「そそそ。何してたん? めっちゃ焦ってたけど、もしかして……やばいこととか?」
「別に、ただの暇つぶしだよ」
適当に答えると、星野の目が俺の手元に注がれる。
「あっ、それゲーム機じゃん! 見せてよ、見せて!」
星野は興奮気味に身を乗り出してくるが、俺は慌ててゲーム機を抱え込む。
「ダメだ! 大事なゲーム機だから見られるのも嫌だ!」
苦し紛れの言い訳を探す俺を見て、星野はさらに面白そうに笑った。
ゲーム機の画面はすでに一度見られているのか、揶揄われるのはわかりきっていた。
「へぇ~、じゃあ教えてよ。どんなゲーム? どうせヒロインとイチャイチャするやつっしょ?」
確信めいた予想だった。
その言葉に、俺は顔が一気に熱くなるのを感じた。
やばい、完全にバレてる。恥ずかしい。
「これは、その……そう、脳トレだ。選択肢を考えて脳を鍛えるやつ!」
「なにそれウケる! あーしみたいな金髪の女の人が画面に映ってたの見たし、しかも、赤木がそれにデレデレしてたのも見てたから、いまさら何言っても無駄だし」
「……はぁぁ」
「ねえねえ、赤木ってもしかしかくても彼女とかいない感じ?」
顔を覗き込むようにしてくる星野。
彼女の髪が俺の肩に触れる距離に、思わず息を飲む。なんかもう抵抗すんのもバカらしくなってきた。完全にお互いの立場がはっきりしてるし。
どうせならとことん冷たくあしらっていなくなってもらおう。グイグイ来られて俺のテリトリーを荒らされるくらいなら、いっそのこととことん嫌われたほうがマシなまである。
「……関係ないだろ。俺に構うなよ。どっかいけよ」
俺はそっけなく返した。
これで星野は、ぷんすか怒って立ち去るだろう……そう思っていたのだが、なぜか彼女は引くどころかさらに距離を詰めてきた。
「ねぇ、さっきのゲームで、金髪の女の子と手ぇ繋いでたじゃん? こういうのって現実の恋愛の参考になるの? たとえば、こんな感じで——」
そう言って、星野は唐突に俺の手を握ってきた。
温かくて柔らかい感触に、思考が飛んだ。
「赤木、ドキドキしてる? どんな気分?」
その挑発的な笑みに俺は完全に翻弄されてしまい、もう何を言うことができなくなっていた。
「……女の子とこんなことしたの、初めて?」
完全に揶揄われている。手を繋いだまま、肩を寄せられ、下から顔を覗き込まれ、挑発的な言葉を浴びせられる。
こんな経験、初めてに決まってるだろうが。
「お前、なんなんだよ……」
俺はようやく絞り出すように言葉を吐くと、星野の手を振り払って彼女から視線を逸らした。
すると、星野はまたクスクス笑った。
「なにって、ただの暇つぶしだけどぉ? でも、赤木もこーゆーのが好きだから、ゲームで女の子とイチャイチャしてたんでしょ? しかも……こういうの、全然慣れてないんでしょ?」
明るい声色と、どこか楽しげな目。
俺の脳内では警報が鳴り響いていた。ゲームないだけならまだしも、現実世界の金髪ギャルなんて、危ないのは確定している。どんなヤンキー男とつるんでるかわからないし、何を考えているのかもわからない。
絶対に関わったら面倒だ——でも、どうしてだろう。この距離の近さが、嫌いじゃない気がする。
俺はもうすでに星野紗奈に魅了されかけているのかもしれない……悲しきかな、純情な俺。
「やば! もう昼休みになるじゃん! あーしもう行くね!」
俺がぼーっと考えに耽っていると、星野は忙しなく立ち上がった。
時刻は昼過ぎ。もうあと五分もすれば昼休みになる。
「赤木、またねー」
「おう」
「なにその返事」
俺は精一杯搾り出した挙げ句こんな返事しかできなかったが、対する星野は楽しそうに笑って立ち去った。
るんるんスキップなのは、彼女の性根の明るさを示している。
まさしく、俺という影とは真逆の存在だった。
◇◆◇◆
星野紗奈という金髪ギャルとの邂逅から数日が経ち、俺は彼女のことなどすっかり忘れたかけていた。
いつもの平穏を取り戻し、今日は校舎裏で昼休みを謳歌していた。
やはりここは静かでいい。
ここは俺にとって図書室の次に落ち着ける場所だ。
今くらいの秋口の季節は気温も天気も何もかもがちょうどいい。大好きだ。
適当にコンビニで買ったおにぎりを、一人で黙々と食べる。
クラスメイトの輪に入る勇気もなければ、必要性も感じない俺には、これくらいの距離感がちょうどいい。
——はずだった。
「うわ、赤木また一人じゃん! どーもー!」
金髪ギャルの声が背後から降ってきた。
聞き間違えであってくれと祈りながら振り向くと、そこには案の定、星野紗奈が立っていた。
今日は長い金髪をポニーテールしている。少し大人っぽく見える。
「なんでここにいるんだよ……」
「んー? たまたま通りがかったら、赤木が寂しそうに飯食ってたからさー! あ、これ何? コンビニのおにぎり? うける!」
星野は勝手に俺の隣に腰を下ろすと、図々しくおにぎりを覗き込んできた。
俺の一人時間が、瞬く間に侵略されていく。
あと、おにぎりを見てうけてるのはお前だけだ。
笑いの沸点が低すぎて、俺が一発ギャグかましても爆笑しそうなレベルだ。
「……なにしにきたんだよ、こんな校舎裏に」
「んー、なんとなく? でか、赤木ってほんとに友達いないんだねー。こんな日陰のベンチで寂しくない?」
悪びれもせず笑いながら、星野は俺の隣に腰を下ろした。
俺を揶揄っているのかと思いきや、星野の表情はどこか自然で、嫌な感じはしない。
本当にたまたまここに来たらしい。
「だからって、いちいち絡んでくるなよ」
「えー? ひどー」
星野は前回と同じく、わざと俺との距離を詰めてきた。
さっきまではひと一人分くらいのスペースはあったのに、今では肩が振れるくらいにまで近い。
やっぱり良い匂いがする。なんだこれ、むさ苦しい男とはまるで違う。
「……」
くらくらして頭がおかしくなりそうだったので、俺はおもむろに数センチ横にずれた。
すると、星野はニヤッと笑う。
「またドキドキしてんのー?」
「別に……」
俺は咄嗟に首を横に振ったが、本当はドキドキしていた。甘い匂いと肩と肩が触れ合う感覚だけで、俺の思考はいっぱいだった。
「嘘が下手すぎるし!」
「嘘じゃない」
「じゃあ、なんで目合わせてくれないの?」
星野の挑発的な声が耳に響く。
明らかに舐められている。
このまま黙っていたら、また図書室での時みたいにからかわれるのがオチだ。
無様に負けて取り残されるのは勘弁したい。ギャルゲーのように強気な選択はできないが、多少なりとも俺だってやる時はやる。
……ちょっと頑張ってみるか。
「別に……ほら、目くらい合わせてやるよ」
そう言って、俺は覚悟を決めて星野の目を見据えた。
彼女の瞳は、思っていた以上に鮮やかで、どこか吸い込まれそうな色をしている。
星野は一瞬だけ「えっ」と目を丸くしたが、すぐにいつもの軽い笑みを浮かべた。
「ふーん、やるじゃん。赤木のくせに生意気だし」
口ではそう言っているが、どこか声の調子が不自然に聞こえる。
気のせいか? 動揺しているのか? いや、まさかな。校内でトップクラスに目立つあの金髪ギャルの星野紗奈が、こんなことで動揺するはずがない。
「……」
俺は目を逸らさないまま、じっと星野を見つめ続ける。
その間、妙に長い沈黙が流れた。
秋風に揺れる木々や草木の音だけが聞こえてくる。
「……な、なに?」
星野が少し首をかしげながら言う。
その動きで、ポニーテールの髪がふわりと揺れた。
「いや、お前が合わせろって言ったから合わせてるだけだ」
「そ、そっか……」
微妙にぎこちない声。
普段の彼女ならもっとテンポよくからかってくるはずなのに、今はなぜか違う。
さらに見つめ続けると、星野が少し落ち着かない様子で視線を泳がせ始めた。
指先でポニーテールの先をいじったり、やけに大きなため息をついてみたり。
「な、なんかじーっと見られると気持ち悪いし!」
「気持ち悪いなら、お前から目を逸らせばいいだろ」
「はぁ? あーしから逸らすわけないし!」
そう言いながらも、星野の頬にほんのりと赤みがさしている気がする。
日差しのせいだろうか。いや、さっきまでそんなことはなかったはずだ。
「……な、なにニヤニヤしてんの!」
「してないけど?」
「してるし!」
星野の声が、少し裏返っている。
ポニーテールを握りしめている手が、どこかそわそわと動いているのが見えた。
——これは、照れているのか?
いやいや、あの天下の星野紗奈がそんな簡単に照れるわけがない。
けれど、その態度はどう見ても落ち着きがない。
ノンデリカシーな俺の推察からするに、星野は尿意を催しているに違いない。動揺ではなく我慢だったのか。目を逸らせば金髪ギャルが根暗男子に敗北してしまうし、かといって我慢を続ければダムが決壊してしまう。
今の星野は、そんなジレンマに立たされているんだ。
可哀想に。だが、この勝負は俺がもらう。
「赤木、もういいし! じーっと見んな!」
「お前が合わせろって言ったんだろ。俺は絶対に目を合わせ続けるからな」
「うっさい!」
結局、最後は半ば投げやりに叫ぶと、星野は急に立ち上がり、俺に背を向けた。
我慢の限界だったらしい。俺が止めるよりも先に、駆け足気味で走り出している。
「じゃ、じゃあね!」
「あ、おい!」
最後、ほんの一瞬振り返った横顔は……赤く見えた。
「……なんだよ、あいつ」
残された俺は、秋風に揺れるポニーテールの残像をぼんやりと目で追っていた。
同時に昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
俺は中途半端に残されたおにぎりを口に詰め込み、教室へと戻ったのだった。
ただ、教室には星野の姿はなかった。先生の話によると、体調を崩して保健室にいるらしい。
悪いことをした。お見舞いに行くようなことはしないが、心の中では”早く良くなるように”と願った。
◇◆◇◆
土曜日の昼下がり。
俺は特に目的もなく、街をぶらぶら歩いていた。
最近気になっているゲームのセール品でも探そうかと、古びた商店街を覗いていた時のことだ。
「——え、赤木じゃん?」
突然、聞き慣れた声が背後から飛び込んできた。
振り返ると、やはりそこにいたのは星野紗奈だった。
ここ数日のうちに三回目の邂逅となる。まるで運命の巡り合わせかのように。まあ、本当に偶然なんだろうけど。
ただし、今日は一人ではなく、派手な二人組のギャルと一緒だ。
星野は金髪で普遍的なギャル。
もう一人は黒髪だがピアスまみれであり、ボーイッシュなタイプ。この人も多分ギャル。
さらにもう一人は、明るすぎるくらいの茶髪に、カラフルなネイルに目立つアクセサリー、お姉さん感増し増しの雰囲気に抜群のスタイル。
正直、俺とは住む世界がまるで違う。
「赤木ってば意外と外出るんだね。ひきこもりかと思ったー!」
星野は駆け寄ってきて肩をバンバン叩いてくる。馴れ馴れしい。プライベートで見かけて声をかけるような間柄でもないのに、とてつもなくフランクに接してくる。
過剰なボディータッチとラフな態度に動揺しそうになったが、俺はバレないように声を取り繕った。
「星野こそ何してんだよ……」
「何って、普通に買い物だけど?」
星野は軽い調子で俺の前に立ち止まる。
その声に釣られるように、お連れのギャル二人も俺を見て興味津々な顔をしていた。
「紗奈、この人誰?」
「友達? にしては地味だけど、まさかこういう系が好みなん? 大学に行ったらもっと良い男いると思うよ?」
そう聞いてきたのは二人のギャルだった。
「んー? ただのクラスメイト」
星野は至って普通のトーンで俺を紹介した。
特に気まずそうな様子もなく、いつもの調子だ。
「クラスメイトなんだ。意外かも」
「そうそう、紗奈ってもっと派手なやつとつるんでるイメージだったけど……意外にも高校では大人しかったりするん?」
ピアスまみれの黒髪ギャルは静かな反応を見せ、明るい茶髪のお姉さんギャルは面白がるように笑いながら、俺をジロジロと観察している。
「別にクラスのやつってだけだってば。ね、赤木?」
「……まあ、そうだな。ただの同級生だ。正直、全然話したことないし。俺は星野のことなんてあんまり知らない」
俺はあっさりと肯定する。事実、それ以上でも以下でもない。
話した回数はたった三回だけ。しかも、直近の一週間のうちに三回だ。三年間全く関わりはなかったし、お互いに気にすることもなかったか間柄だ。
だが、この瞬間、星野がチラリと俺を横目で睨むような視線を向けた。
「……ふーん」
星野の声は平静を装っていたが、どこか刺々しい。
すると、茶髪ギャルがさらに話題を広げるように俺に話しかけてきた。
「ねえ赤木くん、紗奈とは仲は良くないの? あたしってば紗奈の二個上で大学二年生なんだけど、普段の紗奈は高校どんな感じなのか教えてくれる?」
「あー……すみません、よくわかりません。そんなに親しくないですし、あんまり話したこともないです。絡まれたことしかないので」
「絡むって、紗奈が赤木くんに? あはは、なにそれ面白い!」
茶髪ギャルがケラケラ笑い、黒髪ギャルも小さく微笑む。
何が面白いのかよくわからない。
その間、星野は何も言わず黙り込んでいた。
何気なく横を見ると、星野が微妙に不満そうに口をへの字にしているのが目に入る。
「何だよ、その顔」
「……べっつにー? 赤木は絡まれたとしか思ってなかったわけ? 他に何も思わなかったの?」
星野はそっぽを向きながら、気取ったような口調で返した。
何に対して不満なのか分からないが、確実に機嫌が悪そうだ。
「まあまあ、紗奈、そうツンケンしないの。どうせあれでしょ? 紗奈がアプローチしても、思ったより赤木くんが面白い反応をしないから楽しくないんでしょ?」
茶髪ギャルが軽く星野の肩を叩き、俺にウインクしてきた。
「アプローチって、そ、そんなんじゃないし! ただおもしろそーだから、ちょっとだけからかってみて……でも確かに前は見つめられて……」
「見つめられたの? 紗奈が? どうだった?」
黒髪ギャルが食いついた。
しかし、星野は慌てふためいて即座に否定する。
「ちがうし! 急に見つめられたから気持ち悪いって思っただけ! だよね、赤木!」
「お、おう」
よくわからないが、圧に負けて首を縦に振った。
なんか、すごい動揺してて新鮮だ。前は尿意を催してただけだったのだろうが、今回に限ってはあからさまに取り乱している。
「そ、それより、買い物の続きしよっ! あーし、ほしい服あるからさ!」
「……忘れてたー、あたしたち二人で夜とこあったんだったー! ごめんだけど、紗奈は赤木くんと買い物してくれる? 終わったら連絡して? それじゃ!」
茶髪ギャルは黒髪ギャルの手を引くと、脱兎の如く走り去っていった。すごいスピードだ。もう見えなくなった。
というか、星野と二人きりにさせられたんだけど……どうすんの、この状況。
「……星野?」
俺はおずおずと声をかけた。当の星野は肩を落として俯いている。何を考えているのかはよくわからないが、深いため息を吐いているのは見えた。
「赤木」
「ん?」
「……ごめん」
「何が?」
「いや、その……赤木も用事あるんだもんね。なのに変なことに巻き込んじゃってごめん」
「あー、別に気にしなくていい。俺はちょうど暇だったし、茶髪のお姉さんギャルとピアスまみれの黒髪ギャルはノリノリで楽しそうだったし」
本当に暇だったから時間的なことは全く問題ない。
まあ、茶髪のお姉さんギャルのテンションの高さに胃もたれしかけたのは内緒だが。
「二人とも大学二年生で、あーしの先輩だし。しかも、あれは楽しんでるんじゃなくて、あーしのことをバカにしてるだけだし」
「バカにしてたのか? あれ」
「……その話はもうやめた。仕方ないから赤木と買い物するしかなさそうかな」
「トイレにこもってやり過ごせないかな」
「どうせ二人揃って影から覗き見してると思うから無理っしょ。ってか、なんでそんなに行きたくなさそーにしてるわけ? うちの高校でナンバーワンギャルのあーしとデートできるんだよ? もっと喜ぶもんっしょ?」
「はいはい」
俺は軽く返事をした。
「はぁぁぁぁ……ついてきて。せっかくだし、赤木の男としての目線を聞かせな。色んな服着るから感想ちょーだいね」
星野はため息を吐いてから先に歩いていった。
俺の答えに不満があったのか?
正直、星野と話したり、こうして一緒に過ごしたりすることを喜んでいないと言えば嘘になる。
図書室で手を繋がれた時はドキドキしたし、校舎裏のベンチで肩を寄せ合った時も目を合わせて見つめあった時もドキドキした。
ただ、からかわれているのが明白なので、それ以上の感情を持つことはなかった。
更に言えば、今日で三回目の邂逅となるので、俺はそこそこ心の準備ができ始めていたのもある。
結局のところ、俺はギャルゲーしかしたことない恋愛未経験プレイヤーなわけで、現実世界の金髪ギャルとは相容れない存在だ。
当然のように向こうが俺に惚れることもなければ、立場を弁えた俺が靡くこともない。
どうせ高校卒業までの二、三ヶ月間の一過性のイベントだろうし、テキトーに過ごして終わらせるのが吉だろうな。
◇◆◇◆
星野に引っ張られる形で向かったのは、駅前の商業ビル。
三階建ての施設には、若者向けのファッションショップがぎっしり詰まっている。
「……本当に俺、ここに入って大丈夫か?」
「何が? 普通じゃん。むしろあーしと一緒だから安心でしょ?」
星野はあっけらかんとしているが、俺にはこの手の空間は未知の領域だ。
眩しい店内、オシャレなBGM、そして服を選ぶ客たちのキラキラ感。
どれも俺とは無縁すぎて、すでに逃げ出したくなっていた。
「ほら、こっち行こ」
星野に急かされ、意を決して店内に足を踏み入れる。
最初の店は大人びた服が多かった。
星野は慣れた様子で棚から服を選び、次々と手に取る。
「ね、これどう思う?」
星野が持ってきたのはチェック柄のワンピース。
どこか秋っぽい色合いで、落ち着いた雰囲気だ。
「……似合うんじゃないか?」
「んー、じゃあ試着してみるから、ちょっと待ってて」
そう言い残して、星野は試着室に入っていった。俺は促されるまま近くの椅子に座り、視線を彷徨わせる。周りはオシャレな女子ばかりで、完全に場違い感が半端ない。
しかし、試着室のカーテンが開くと、そんな考えは一瞬で吹き飛んだ。
「どう? これ」
星野が出てきた瞬間、言葉を失った。
シンプルなチェック柄のワンピースが彼女に驚くほどよく似合っている。
普段のギャルっぽい派手さとは違い、大人っぽくて、どこか清楚な雰囲気が漂っていた。
「……すごく似合ってると思う」
正直な感想が口をついて出た。
すると、星野は少しだけ照れたように髪を触る。
「そ、そっか。ま、赤木がそう言うなら買っちゃおうかな」
珍しく控えめな反応に、俺は少し驚いた。
その後も、星野は何着か試着を繰り返した。
毎回「どう?」と俺に感想を求めてくるので、なるべく的確に答えるようにした。
「このスカート、どうかな?」
「うん、脚が長く見えていいと思う」
「このトップスは?」
「派手すぎずにオシャレだし、星野らしさが出てる」
俺の言葉に星野は素直に喜んでいた。
いつもの茶化すような態度はどこか影を潜め、純粋にファッションを楽しんでいる様子だった。
「へへ、赤木って意外とセンスあるじゃん。将来、スタイリストにでもなる?」
「いや、ならないけど」
軽口を叩く星野に返しながら、俺は内心で不思議な感覚を抱いていた。
これまで突っかかってくるか、からかってくるかのどちらかの星野が、今日はやけに楽しそうで、しかも素直だ。
もちろん、俺が星野に惚れるなんてことはない……はずだ。そう考えていたし、確信していた。
けど、こうして目の前で色々な服を着て嬉しそうにしている姿を見ると、自然と「素敵だな」と思ってしまう自分がいる。
向こうはこんな態度を見せてくれてはいるが、内心はどうせ俺のことなんて眼中ないと思う。だって、星野は別世界の住人だから。
校内の人気者で見た目も良くて性格も明るい。俺とは到底釣り合わない。
だから俺は惚れてはいけない。決して心を靡かせてはいけない。
「……」
心に思いを決めていると、目の前のカーテンがゆっくりと開かれた。
星野が最後に試着したのは、シンプルなダークブラウンのニットワンピースだった。少しだけ肩が見えるデザインで、普段の星野にはない柔らかさを感じさせる。
色合いも秋冬っぽく温かみがあり、素材感も相まってより一層大人びていた。
「これ、どう?」
「……なんか、すごくいいと思う。大人っぽいし……可愛い」
自分でも驚くほど真っ直ぐな感想を口にしていた。
まずい。あんまりこういうストレートな表現は口にすべきじゃなかった。キモがられるし、もしかしたら周りに吹聴されてしまうかもしれない。
俺は息を呑んで、自分の吐いた言葉を後悔した。
しかし、目の前の星野は、俺の予想とは裏腹に全く違う種類を反応を見せていた。
彼女は、ふいっと視線を逸らして「そ、そっか」と小さく呟くだけだった。
その耳が、ほんのり赤くなっているのを、俺は見逃さなかった。
「……あーし、これ買うわ」
星野は恥ずかしそうにそっぽを向きながら、ニットワンピースの裾を軽く引っ張った。
その動きがどこかぎこちなく、普段の彼女の自信満々な態度とは違う。
なんか、妙にドキッとする。
これ以上見つめたら、変な空気になりそうで、俺は慌てて視線を逸らした。
意識が持っていかれそうだった。誓ったはずの心持ちが変わってしまいそうだった。
「……いいと思うよ。似合ってる」
俺は静かに答えた。
「そ、そっか。じゃあ、これで買い物は終わりだし!」
星野は軽く手を叩いて、自分を無理にでも元の調子に戻そうとしているようだった。
その時、まるでタイミングを見計らったかのように、二人組のギャルが現れた。
「おー、いいじゃん紗奈、そのニット。デートっぽいじゃん!」
茶髪ギャルがにやにやしながら星野に声をかける。
「赤木くんとペアルックにしちゃえば?」
ピアスまみれの黒髪ギャルも、茶化すような視線を俺に向けてくる。
「……ペアルック? あーしがこれを着るからには、相手はもっとちゃんとしたイケメンじゃないとだし!」
星野はぷいっと顔を逸らして、ふてくされたように反論する。
しかし、尚も茶髪ギャルはニヤニヤをやめない。
「紗奈は赤木くんのことイケメンじゃないとダメって言ってるけど、普通にかっこいいクールな顔してない? 地味めな雰囲気はあるけど、話したらけっこー楽しいし、もしかしたら狙ってる女の子もいるかもよ?」
「……優しい系だから意外にモテると思う」
茶髪ギャルが肘で小突いてきた。ついでと言わんばかりに、黒髪ギャルが横から覗き込んでくる。
お世辞なのは分かってるが、顔と性格を良く言われるのは少し嬉しかった。
「……まあ、その辺にいるいけすかないナンパ男よりはずっとマシだし」
二人に乗っかるようにして、星野の反応もそんなに悪くなかった。
「だってさ!」
「……ずっと俺抜きになんの話してるんですか」
魔に受けたら負けるような気がしたので、俺はしらを切って話を流した。
「で、で、で? ペアルックはどうなの? 赤木くん、否定はしてなかったけど、まさかやる気満々だったりする!?」
「そういうのは星野に悪いんでやらないですよ。本人の言うとおり、もっともっとふさわしい人がいると思いますしね」
茶髪ギャルの問いかけに対し、俺は即座に否定した。
断る以外の選択肢はなかった。ギャルゲーの世界なら、ここはグイグイいくべきだが、あいにくここは現実世界だ。
こんなところで攻めてしまったら、ドン引きされて冷ややかな目で見られるのは確実だった。
現に、星野は少しだけ眉をしかめていたが、俺がその返答をしたことですぐに何でもないような顔に戻っていた。
当たり前だが、俺如きが彼女の恋愛面を茶化す真似はよろしくないな。
「ふーん、今はまだそんな感じなんだー。じゃあ赤木くんの出番はここまでかな。ありがとね、色々つきあってくれて」
「あ、はい」
「他に用事あるだろうし、紗奈の服は改めてあたしたちがチェックするから、赤木くんは帰っていーよ!」
「……わかりました。それではまた。星野もまたな」
俺は茶髪ギャルに気圧されるがままに店を出た。
店の外から振り返ると、星野は二人のギャルと何か楽しそうに話しているように見える。
ほっぺたを膨らまし、身振り手振りで何かを伝えているようだった。
「……まあ、これでいいんだろうな」
そう呟きながら、俺は来た道を引き返した。
どこか胸の奥にモヤモヤした感情が残っている気がしたが、それが何なのか、俺にはまだわからなかった。
星野のこと? それとも自分のこと?
なんなんだろうな。この感覚は。
◇◆◇◆
十二月を目前に控え、季節は秋から冬へ移り変わる最中。暖房が入り始めた図書室はぽかぽかと暖かく、休息にはうってつけだった。
午後の授業が自習になったおかげで、俺はここでのんびりできている。静かな空間に身を沈めていたが、ふと入口から軽い足音が聞こえてきた。
顔を上げると、見知らぬ後輩の女子が棚を見回している。困った様子で目を泳がせていた。
そのぎこちなさに、俺はつい声をかけた。
「何か探してるのか?」
驚いた顔で振り返った彼女は、少し赤面しながら答えた。
「あ、はい。一年生の生物の授業で使う参考書を探してるんですけど、どこにあるのか分からなくて……」
「ああ、それならあっちだよ」
俺が指差すと、後輩は顔をぱっと明るくして走り去り、しばらくして本を抱えて戻ってきた。ほんのり頬が赤くなっている。
「ありがとうございます! 先輩、三年生ですよね? お勉強、頑張ってください!」
謎のエールを残し、後輩は小走りで去っていった。
俺はぽつりとつぶやいた。
「……変わった子だな」
後輩女子とのやりとりを終えて机に戻ろうとしたその時、視線を感じて振り向くと、図書室の出入り口に星野が立っていた。
いつもならテンション高く絡んでくるのに、今日は様子が違う。眉を少しひそめ、口元を引き締めている。
「星野? どうしたんだ?」
声をかけると、星野は顔をそむけながら小さく答えた。
「……別に。ただ見てただけ」
どことなく不機嫌そうなその表情に、俺は少し戸惑う。
「さっきの後輩の子、知り合い?」
星野はこちらに近づきながら、軽く尋ねてきた。
「あの子? 全然知らない子だよ。参考書の場所を教えただけだな」
俺がそう答えると、星野はわずかに笑った。
「ふーん。でも、あんまり親切にしすぎない方がいいよ。先輩にいい顔してるだけかもだし」
冗談っぽく言われ、俺は肩をすくめる。
「わかってるよ」
「ほんとにー?」
「……なにを気にしてんだよ」
俺がそう返すと、星野は急に黙り込んだ。
そして、俺の隣に腰を下ろしながら鞄から文庫本を取り出した。
「というか、なんで俺の隣に座るんだよ? 席ならたくさん空いてるだろ」
俺が問いかけると、星野は少しふざけた調子で答える。
「最近、赤木と静かに過ごすのも悪くないって思ってさ。これって大人になった証拠かな?」
「知らんけど。てか、本とか読むなんて意外だな」
俺が思わず口にすると、星野はムッとした表情で睨んできた。
「バカにしてんの?」
「そういうわけじゃない。勉強はしなくていいのか?」
「勉強は嫌いだからしない主義!」
「へー」
俺は淡白に返して話を終わらせた。
星野の学力や進路は知らないが、勉強嫌いなら強制することはないか。人付き合いがうまそうだし見た目もいいから、勉強なんかしなくても大丈夫なタイプだと思う。俺とは違ってな。
それから図書室には静かな時間が流れた。
俺は机に伏せて目を閉じて心を整え、星野は俺の隣でのんびり読書にのめり込んでいた。
「……あ、そういえば」
ふとした拍子に、星野が俺の肩を指で突いてきた。
「どうした?」
顔を上げて星野を見上げた。彼女の視線は図書室の掲示板へと注がれていた。
「ねぇ、赤木。駅前のイルミネーションって見たことある?」
星野が見ていたのは、掲示板に貼られたポスターだった。
どうやら、クリスマスを目掛けて、駅前に大々的なイルミネーションが展開されるらしい。
ポスターにはカラフルな光が散りばめられている。
「イルミネーションなんて、あんまり見たことないな」
俺には無縁だった。
ゲーム内ではヒロインと共に数々のイベントを消化してきたが、現実世界では一度として堪能したことがない。
「ふーん」
「星野は誰かと行く予定でもあるのか? 友達のギャルとか」
「あの二人は彼氏いるし。今んとこ、あーしにそんな予定はないよ。なに、あーしの予定が気になったん?」
「試しに聞いてみただけだ。仮に俺と星野が二人でイルミネーションなんて見てたら、クラスの連中に影でバカにされるだろ。だから俺から誘ったりはしないよ」
自分で言っていて悲しくなるが、俺と星野じゃ全く釣り合いが取れない。
今だって一緒に時間を過ごしているが、誰かに見られるのはよろしくないことなのだ。
変な噂がたったら星野に迷惑がかかる。
「はぁ? そんなこと気にしてんの?」
「……星野だって嫌だろ。普段は陽キャとつるんでるのに、俺と話していても面白くないだろうし……」
「なに言ってんの。赤木だって面白いし! たまーにあーしの胸を見てたり、髪の毛の匂い嗅いでる時はちょっとだけキモって思うけど、それでも悪いやつじゃないのはわかるから! もっと自信持っていいっしょ!」
褒められているのか、暴露して辱めようとしているのか、それははっきりわからない。ただ、星野の言葉に嘘はなさそうだった。本当に俺のことを嫌いではないらしい。変わり者だ。
ギャルのくせに根暗の俺なんかに構う時でおかしいが、こうして対等に話をしてくれるのはもっとおかしい。
「……星野が嫌じゃないならいいんだけど」
「あーしはそんなん気にしないし! むしろ、変なこと言うやついたらぶっとばすからさ!」
星野は手をグーにして素振りを披露した。
決して強そうには見えないが頼りにはなる。俺にはない性根からの明るさを持っているからか、話してるだけで自然と俺の気持ちも明るくなる気がする。
「ありがとう」
「で、話は戻るけど……あーしと行かない? イルミネーション!」
「え? 星野と?」
咄嗟に聞き返す。まさかの誘いだった。
「うん。ダメ?」
「….星野さえ良ければ」
唐突な誘いに俺は一瞬面食らったが、特に断る理由なんてなかった。
イルミネーションが気になるのもそうだし、何よりも今は星野と時間を過ごしたいと思うようになっていた。
恥ずかしいことに、俺はゲーム内だけでは満足できなくなっているのかもしれない。
星野を見ていると……少し気分が高揚してしまう。
「やったー! 今週の日曜、駅前に集合だし!」
星野は静かな図書室に声を響き渡らせると、俺の左腕をがっちり掴んできた。
以前よりも一層強くホールドされているせいで、星野の柔らかい二つのボールがぶち当たる。
キモがられないようにリアクションはしないように心掛ける。
「お供します」
鼻では良い匂いを感じ、左腕には未知の柔らかさを感じ、耳では嬉々とする星野の声を感じていた。五巻の全てを星野に支配されている状態だ。
「お供しますってなに? 桃太郎? 犬とかサルのセリフにある”お供させてください”的なアレ? もしかして、赤木ってドMってやつ?」
「違う。俺は猿じゃなくて人間だし、ドMじゃない。多分、ノーマルだ」
「へー。じゃあ、今度の日曜ね! マジで楽しみだし! 赤木もワクワクして待ってなね!」
星野は俺よ華麗なツッコミを受け流すと、文庫本を片手に図書室から走り去っていった。
二度目の拝見となるルンルンステップだ。
スカートが短いから、後少しふわっとすれば中身が見えてしまう。俺には刺激的すぎる。
「……はぁ……夢か? これ、ゲームの世界に迷い込んだのか?」
取り残された俺はボーッと虚な気分に陥っていた。
まさか、つい数週間前までは話したことすらなかった金髪ギャルと、二人でイルミネーションを見に行く日が来るなんて……全くの予想外だ。
嬉しい反面、これが現実の世界とは思えなくなる。
「来週の日曜、楽しみだなぁ」
昼下がりの図書室で、俺は一人でにやけたのだった。
ちなみに、窓ガラスに反射する俺のニヤケヅラは心底気持ち悪かった。
◇◆◇◆
星野と二人でイルミネーションの話をした翌日。
クラス中で妙な噂が囁かれ始めた。
「赤木が紗奈に手を出したって本当?」
「ああ見えて二人ともノリノリらしいよ」
「マジで?あんな地味男、絶対ないでしょ。俺の方が幸せにできるって!」
噂はどんどん広がり、クスクス笑う声が耳に入ってくる。
俺の名前と星野の名前が同じ会話に出るたび、嫌な汗が背中を伝った。
言い出したのは陽キャの連中だ。
彼らは普段から星野と軽口を叩き合うようなタイプで、俺なんかには話しかけてもこない人種。
そんな彼らの一言一言が教室の空気を変えていった。
だが、対する当人の星野は噂なんて気にしていないように見えた。
むしろ、いつも通り堂々としている。
昼休みになると、彼女は変わらず陽キャ連中と盛り上がっている。
教室では俺に話しかけてくることはほとんどないが、時折視線を向けてくることはある。
今もそうだ。星野は陽キャ連中と話しながらも、ちらちらとこちらを見てきた。まるで捨てられた子犬を見るかのように。
ジレンマがあるのだろう。
友達との付き合いと、俺との交友を天秤にかけて迷っているように見えた。
ただ、そこは俺を優先してほしくはなかった。
確かに、星野は気にしていないのかもしれないけど、俺にはわかる。いつもより視線が泳いでいたり、声が微妙に小さいことに気づいてしまう。
変に俺のことを気にするあまり、いつもの自分を出せていないようだった。
「……くそ」
教室の隅の席で、俺は一人悩み込んだ。
教室の雰囲気も変わり始めていた。
俺が何かをするたびに、笑いをこらえたような声が漏れ聞こえる。
誰も星野本人に噂の真意を聞くことはなく、ただそれに呼応するように遠くから薄ら笑いが返ってきた。
「赤木、なんか調子乗ってない?」
「紗奈って、誰にでも優しいんだな~。あいつには不釣り合いだよ」
そんな陰口が聞こえるたび、俺の心はざわついた。
翌週。
相変わらず、星野は本当に噂なんてどうでもいいと思っているように見える。
実際、彼女は教室のど真ん中を堂々と歩き、陽キャ連中の軽口にも笑顔で返している。
けど、俺にはわかる。廊下でふと視線を伏せる瞬間や、ため息をつく姿が痛々しかった。
昼休みになり、いつものように俺が校舎裏のベンチに腰掛けていると、そこに星野がやってきた。
「赤木、変な噂気にしすぎだよ。あーし、全然気にしてないから! 前も言ったっしょ?」
その無邪気な笑顔に、俺は何も言えなかった。
だけど、それでも俺は悩んだ。
口では気にしていないと言うが、それは彼女が強いからだ。
俺がそばにいることで、星野が居心地悪くなっているのではないか。
それがどうしても引っかかった。
「……少し、距離を置いたほうがお互いのためだな」
俺は自分で自分にそう言い聞かせるように、机に向かった。
次の日から、俺は星野のことを目で追うのをやめた。ごくたまに教室で声をかけてくることもあったが、それすらも適当にあしらった。
そして、何かしら理由をつけて教室を離れるようにした。それが正しいことだと思ったから。
だが、そんな俺の態度に気づかない星野ではなかった。
俺が距離を取るようになっても、星野は変わらず教室で笑っていた。
噂なんて気にしないと強がる姿は、相変わらず堂々としている。それでもその笑顔がどこか空回りしているのも、俺にはわかっていた。
そしてついに展開が変わった。
ある日の放課後になったばかりの時間だった。
星野は人目も憚らず俺の机の前にやってくると、机をバンっと叩いて強く言い放った。
「もうダメ! 我慢できない! あーしが全部終わらせる! 赤木は黙ってていいから!」
星野は自信満々だったが、俺は心配しかなかった。
「そんなことしたら、余計に変な噂が広がるだけだろ」
「いいの! あーしのやり方で、みんなにわからせてやるから!」
星野はそう言ってクラス中を見渡した後、大きく息を吸い込んだ。
「最近、あーしと赤木のことで変な噂が出回ってるけど、何か言いたいこと、聞きたいことがある人いる?」
彼女は余裕を装うように腕を組んでいた。
しかし、その手が微かに震えていることに俺は気づいた。
結局、無理してるんじゃないか。
星野の意気込みに応えられるような器量が、俺にあるとは思えなかった。
俺が黙って見ているわけにはいかない。
星野が噂の矢面に立つくらいなら、俺がその役を引き受ければいい。
それが星野を守る最善策だと考えた。
「はぁぁ……なんでこんなことになったんだ」
俺は机に伏せてやるせない出来事の連続に辟易した。
クラスは静まり返っている。思わぬ宣言をした星野を見て誰もが驚愕していた。
同時に、俺に対する視線は鋭くなっていった。
今しかない。
絶好の機会だった。
これを機に、こんな意味不明な噂は終わらせよう。
「——ありもしない噂をしてる奴らに言っとくけど、悪いのは全部俺だ。星野には関係ない。俺が無理やり星野を遊びに誘ったんだ。星野は優しから断れずに受け入れてくれた。本当は嫌だって思ってるのにな」
瞬間、教室がざわついた。
全ての視線が俺へと集約され、陽キャのリーダー格がニヤッと笑った。
「はぁ? 赤木、お前が何したって? はっきり言えよ。紗奈を口説いてたんだろ? 正直、釣り合ってないって思わないか? まさか惚れたとかいうのか?」
その言葉に笑いが起きるかと思ったが、直後に教室の扉が勢いよく開いた。
「紗奈ー! いるー? 久々に来たわー!」
入ってきたのは、二人のギャルだった。
一人は明るすぎるくらいの茶髪に派手な服装に高めのヒール、キラキラのネイル。
もう一人は落ち着いた黒髪だが、顔やら耳やらピアスまみれ。クールな雰囲気を身に纏っている。
俺は二人のことを知っていた。星野の先輩だ。大学二年生だったはずだが、どうして高校にいるのだろうか。
二人は周りの空気を全く気にせず、軽い調子で歩いてくる。
「あれ? なんかこの空気、めっちゃ重くない?」
茶髪のギャルは星野を見つけて手を振っていたが、教室に漂う妙な空気感に気がついた。
「なんか、あったの?」
ピアスまみれの黒髪のギャルが星野に尋ねたが、星野はなにも答えなかった。いや、言葉を考えているようだった。唇を噛んで下を向いている。
すると、見かねた茶髪のギャルが俺に気がついた。
「赤木くんもいるじゃん! おひさー! さては訳あり? お姉さんたちが話聞いたげよっか?」
二人は周りの空気を全く気にせず、陽キャたちに近づいていった。
そして、陽キャのリーダーに目を向けた。
「ねぇ、何があったわけ? よくわかんないけど……その感じならなんか知ってそーだね?」
リーダー格の陽キャは一瞬たじろいだものの、わざと軽い口調で答えた。
「いや、赤木なんかが紗奈のことを口説いてるっぽかったから、釣り合わないんじゃねって話してただけっすよ。別に悪いことはしてないっす」
その瞬間、二人の雰囲気が変わった。
ノリとテンションで喋っていたような二人の瞳が冷たく光り、空気が一気に張り詰める。
「へぇ、そういうこと言うんだ」
「わたし、あんまりそういうの好きじゃないかも」
二人が低い声で静かに口にした。明らかに怒っている。なんか俺に対しては優しい視線を向けてくれてるけど。
「……みんなは紗奈がどんな子か知らないでしょ? あの子に変なこと言うなら、覚悟してよね。あと、赤木くんもあたしたちの知り合いだからさ~」
陽キャたちが顔を引きつらせて黙り込む。
一触即発、そんな雰囲気だった。
しかし、ピリついた空気感を打ち破るようにして、星野が一歩前に出て手を広げた。
ギャルたちの肩を軽く叩いた。
「ちょっと待って、もういいから!」
ギャルたちは怪訝そうに彼女を見たが、星野は微笑みながら教室全体を見回した。
「えーっと……あーし、赤木とは付き合ってないし、そういうのでもない。でも、今は大事な友達だから変なこと言われるのは我慢できない。……だからさ、あーしのことで何か機になることがあるなら直接聞いて? いい?」
教室が静まり返る中、星野は堂々と胸を張って言った。
一転して、ギャルたちは満足そうにうなずき、陽キャたちはバツが悪そうにうつむいた。
皆が居心地が悪そうにしている。黙りこくり、どうすればよいのかわかっていないようだった。
「……」
最中、俺はひっそりと教室を抜け出した。
二人のギャルと星野とは目が合ったので、軽く会釈をして別れを告げた。
向かった先は、校舎裏のベンチだった。
どっかりと腰掛け息をつく。
多分、これで噂話は完全に終息すると思う。でも、払った犠牲は大きかった。星野はああやって宣言したことで、陽キャ連中との確執ができてしまうだろう。
卒業まで残り二ヶ月程度と考えれば、まあそれほど問題ではないかもしれないが。
「……これで正解だったのかな」
膿がなくなった一方で、あまりスッキリしない気持ちもあった。
結局、俺と星野はこれから関わりを持ってもいいのか、果たしてイルミネーションには行けるのか、色々と考えてしまう。
と、俺が思考していると、一つの足音が近づいてきた。
「……赤木」
やってきたのは星野だった。
真剣な顔つきでこちらを見下ろしている。
「星野……大丈夫か?」
「あーしはずっと平気だし、まあ……ここ最近の空気感はちょっとだけ苦手だったけど。それより、赤木は? 元気? 陰口とか叩かれて、悪口を言われて、辛くなかった? ごめんね、あーしがもっと早くなんとかしてあげられるのが一番だったんだけど、やっぱり言い出しにくい感じがしちゃって……」
星野は俺の隣に腰を下ろすし、俺の肩を身を預けると、今にも泣き出しそうな表情で捲し立てた。
「星野が気にすることじゃない。悪いのは変な噂を流した奴らだし、ギャル先輩二人には感謝しないとな」
「……うん」
途端に沈黙が訪れた。
不思議と気まずくはない。
ただ、互いに言いたいことを素直に言えない、そんな空気が流れていた。
「……なぁ」
沈黙を破ったのは俺だった。
「なに?」
「イルミネーション、一緒に見れるんだよな?」
「……もち」
「よかった」
「その感じ、赤木はめちゃくちゃ楽しみにしてくれたってこと?」
「……まあ、うん。そうだな」
「そっか。あーしも楽しみにしてる! 二人にはあーしの口からきちんとお礼しとくから、赤木は今回のことは全部忘れること! なんもなかった! わかった?」
「わかった……またな」
「また!」
星野は言いたいことを言ってわだかまりが消えたのか、最後には爽快な顔つきで立ち去った。
俺たちの間にあった鬱憤はこれでなくなった。そして、明日以降で噂も終息しそうだ。
俺は一瞬、何かがほどけるような感覚を覚えた。
そして、いつの間にかイルミネーションの日が目前に迫っていた。
◇◆◇◆◇
ふわふわとした柔らかな雪が降る中、俺たちは約束通り、街のイルミネーションを見に行った。
いつも教室で見る星野とは違い、私服の星野は少し大人っぽく見えた。
ギャルらしい派手さはそのままだが、どこか落ち着いていて、俺は一瞬言葉を失った。
「このワンピ、赤木がオススメしてくれたやつ。どお?」
「……」
「なに、黙ってるし。似合ってない?」
星野がからかうように言う。
俺は慌てて首を振った。
「いや、似合ってる……すごく」
言った瞬間、星野が驚いたように目を丸くしたが、すぐに照れたように目をそらした。
薄暗いので顔色はよくわからないが、イルミネーションの光に照らされる横顔は少し赤いように思える。
「赤木って、たまーにそういうこと言うよね」
星野は俺を残して先に歩き始めた。
雪を踏みながら、光のトンネルを抜けていく。
イルミネーションは本当に綺麗だった。
きらめく光が通りを埋め尽くし、人々の顔を穏やかに照らしている。星野はそんな風景を見上げながら、ふとつぶやいた。
「……あーし、こういうの嫌いじゃないかも」
「ああ、意外とこういうのも似合うな」
俺がそう言うと、星野は少しむくれたように笑った。
「なにそれ。似合わないとか思ってたの?」
「まあ……ギャルってよりは、黒髪で清楚な子が似合う勝手なイメージだった」
「赤木がやってるゲームだとそうかもだけど、あーしは真夏のチャラい海とかバーベキューとか、真冬のノリノリのスノボとかよりも、こういう落ち着いた場所が好きってこと。ってか、そこ言い方だとあーしが清楚じゃないって言ってるように聞こえるんだけど? どうなの?」
「いや、そう言われても、金髪のギャルが清楚系は少しだけ無理があるんじゃないか……?」
「あーしは清楚だし、誰とも付き合ったことはないし!」
「え? そ、そうなの?」
「うん」
「じゃあ……なんで初対面の俺の腕をホールドしてきたりしたんだよ。あんなの男を弄ぶギャルの仕業だろ」
「あ。あれは、その、衝動的というか。本当に暇つぶしでやってみよーってなったからやってみただけだし! そしたら赤木がたまたまあーしの好み……違う、んー、もういいっしょ! この話は!」
星野は顔を背けて拗ねてしまった。そんな様すら良いなって思えてしまう。
俺なんかに声をかけてくれて感謝しかない。こうして今も楽しい思いでいられるのは、星野のおかげだった。
「……ありがとう」
その言葉に、星野は一瞬何かを言いかけたが、結局黙ったままイルミネーションを見続けていた。
俺たちは肩を並べて歩きながら、たわいもない話をした。星野の笑顔を見ていると、俺の中の迷いが少しずつ溶けていくようだった。
やがて、イルミネーションを見終えると、俺たちは特になにもなく解散することになった。
別れ際に星野は何か言いたげな表情だったが、俺にその真意を尋ねる勇気はなかった。
お互いに少しだけ緊張していたし、上手に話ができていなかったような気がするから仕方がない。
ただ、心は確かに幸せに満ちていた。
多分この思い出を忘れることはないと思う。
◇◆◇◆
イルミネーションの日以来、俺たちの間に流れる空気は確実に変わった。でも、付き合うとか、そういう関係にはならなかった。ただ、それでもいいと思えた。
以前とは違い、教室でもよく話すようになったし、昼休みには一緒にご飯を食べたりした。
クラスのみんなもそれを茶化すことなく、むしろ積極的に話しかけてくれることも増えた。
高校生活の最後の最後に、何人か友達ができたのは素直に嬉しかった。
やがて冬休みに入ると、高校三年生の俺たちは進学や就職に向けてそれぞれの道を歩み始めた。
卒業式まではしばらく学校が休みになるが、指定校推薦を決めていた俺は暇を極めていた。
みんなは忙しいだろうから声をかけられなかったし、結局はまた一人で過ごす時間が増えていた。
星野と出会ってからあまりプレイしていなかったが、俺はまたギャルゲーにのめり込んでいた。
本当は星野と出かけたり、話をしたかった。でも、俺は星野と連絡先を交換していなかった。
彼女から聞かれることもなかったし、俺も聞けなかった。そんな勇気はなかった。
でも、あの時のイルミネーションの光と、隣で笑っていた星野の横顔は、ふとした瞬間に思い出していた。
忘れられない。俺の中で一番の思い出だった。
◇◆◇◆
月日が流れると、俺は慣れないスーツを着て大学の入学式に来ていた。
桜の花びらが舞う四月、俺は大学生になったのだ。
期待や不安が入り混じるキャンパスでの生活。
だが、俺は入学式すらサボって、校舎の隅でギャルゲーをしていた。
出席したら色々と物をもらえるらしいが、強制ではないらしいのでサボることにした。
そもこも人混みは好きではないし、何よりもギャルゲーの続きが気になって仕方がなかった。
「うーん……『笑って誤魔化す』か『想いを伝える』か。ちょっと難しい選択肢だな」
場面は冬のクリスマスイブ。二人でデートを終えた後の公演での一幕だ。ヒロインの好感度は目視不能だが、俺の見立てだとそれほど高くない気がする。
たまにデレたり、可愛らしくツンケンする様子は見せてくれるが、それでも想いを伝えるには早い気がしていた。
「あーーー、どうしよーかー」
悩みに悩み、夢中で画面を見つめえいると、不意に後ろから声をかけられる。
「ここは『想いを伝える』っしょ! チキってないで、こーゆー時はビシッと伝えるのが一番だし! ってか、またそんなところでゲームしてるし。赤木は本当に変わんないね」
「え?」
驚いて振り返ると、そこには星野がいた。
相変わらず派手な格好で、少し笑いながら俺を見ている。
「え? ほ、星野……?」
「入学式は出ないの?」
戸惑う俺を尻目に、星野はケロッとした様子で聞いてきた。
彼女の軽口に、俺はしどろもどろに答える。
「いや、その……ちょっと面倒でサボってただけだ」
俺が笑って誤魔化すと、星野は呆れたようにため息をつく。
「ほんっとに変わんないね。でも、まぁいいや。あーしも入学式すぐ抜けてきたし」
「え、星野って大学受験してたのか? ここに受かったのか? 割と難関だったと思うけど……」
「はぁ? あーしがギャルだからって舐めてんの? あーしだってバカじゃないし、ちゃんとやるときはやるんだから!」
星野の得意げな顔に、俺は思わず笑ってしまった。
まさかのまさかだ。勉強をしているところなんて見たことなかったし、てっきりおバカなのかと思っていた。
嬉しい誤算だ。
星野が同じ大学に進学してきたという事実は、俺にとって予想外だった。でも、また彼女とこうして話せるのが不思議と嬉しいと思った。
「でさ、赤木。このあとは暇?」
「暇だけど」
「じゃ、久しぶりに一緒にどっか行こうよ。って言っても、二人きりで出かけたのなんて買い物の時とイルミネーションの時だけど」
そう言って笑う星野を見て、俺は新しい生活の中で、また彼女との新たな物語が始まりそうな予感を感じていた。