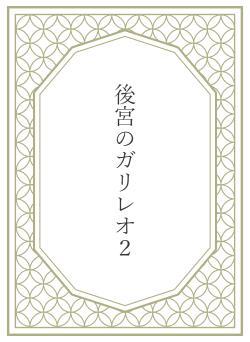≪超新釈≫
クリスマスって特別。一年の中で一番好きなイベントってなあにって聞かれたら、私は絶対クリスマスって答えるよ。特に、恋人とクリスマスを過ごすのって一種の憧れみたいなところがあって。ほら、昔の歌に恋人はサンタクロースみたいなのあるじゃない。小さいころからずっと夢だったんだ。
ピンポーンとインターホンが鳴る。「誰?」と尋ねると「君のサンタクロースです」と言って、恋人が立っている。私は家でケーキやチキンを焼いて、シチューなんかも用意して。シャンパン……はまだ飲めないから、それっぽい炭酸入りの高級ジュースをいい感じのグラスに注いで。乾杯してから二人でご馳走を食べて、クリスマスプレゼントを交換したりなんかして。私だけのサンタクロースとクリスマスを楽しむの。
ザ、王道だし、ちょっと子供っぽい夢かもしれない。
正直自分的にもこじらせてるなって思うところはあるけど、夢なんだからしょうがない。
そして、その夢を叶えるチャンスがついに私にもやってきた……!
恋人の与明くん。同じコーラス部の後輩で、なにかと抜けてて忘れっぽい彼を先輩としてフォローしてるうちに、その、そういう関係になった。高校二年生にして、初めての彼氏ができたんだから、多少浮かれてても許されるでしょ。
私たちの所属するコーラス部は、クリスマス近くになると劇的に忙しくなる。ボランティアで、あっちで歌い、こっちで歌いを繰り返すから、十二月はずっとクリスマスソングを聞きっぱなし、歌いっぱなし。正直、プライベートでクリスマスを楽しめるような雰囲気ではないのだけれど……どんなに忙しくても、私、クリスマスだけは与明くんと一緒に過ごしたい。
好都合なことに、クリスマス当日は朝から夜まで両親は不在だ。
久しぶりに、二人きりでゆっくりクリスマス旅行でもしてきたらって、夏休み中に必死で貯めたバイト代を使って、温泉旅行をプレゼントしたの。もちろん、純粋な親孝行の気持ちだよ。私と与明くんが付き合い始めたのは夏休みが終わってからだから、クリスマス、二人きりでお部屋でデート、なんて当然考えてなかったけれど。結果オーライ、あの時の私、グッジョブ。
そんなこんなで、迎えた十二月二十四日、火曜日。クリスマスイブ。おりしも今日は終業式で、明日からは冬休みだ。
部活動で、高校近くの教会でボランティアとして歌を歌って、へとへとになった帰り道。私と与明くんは一緒に駅までの道を歩いていた。
暮れなずむ空。冬特有の切りつけるような吹きおろしの風が髪の毛をかき混ぜて、去っていく。
「わっ」
あわてて髪を押さえて撫でつけて、そのまま与明くんを見上げると、今にも笑い出しそうな顔をしている。
「鈴森先輩、髪、ぐちゃぐちゃじゃないですか」
「サイアクだよもう」
与明くんはかたくなに私のことを苗字、プラス先輩で呼ぶ。敬語も取ってくれない。
付き合って三か月も経つのに、手もつないでくれないんだ。マジ今どきありえんでしょってくらいプラトニックなお付き合いをしていると思う。
高校から駅までの道はちょっとした商店街になっている。あっちでもこっちでもクリスマスソングがかかっていて、イルミネーションがチカチカしてる。さすがイブ、雰囲気満点。
私は掌をそっと握りしめた。手汗がヤバい。でも、言うなら今しかない。
「あのさ」
与明くんが私を見た。目を柔らかく細めて、「なんですか?」と言う。
「明日から冬休みじゃん」
「はい」
「明日さ……ウチ、来ない?」
「えっ」
与明くんが固まった。私の顔を見て、妙にソワソワと視線を揺らして、もう一度私の顔を見て、視線を外した。
「ウチ、って、先輩の家ですか?」
「それ以外にどこになるの?」
「あー、いえ、そうですか。そうですよね……。でも、いきなりお邪魔したら、ご迷惑じゃ」
「大丈夫だよ、親、夜までいないから。朝からおいでよ」
与明くんは目を見開いた。何か言いたげに一度口を開いて、何か話そうとして、また口を閉じてしまう。さすがに不安になる反応で、思わず彼の顔を伺うように覗き込んだ。
「もしかして、何か予定あった……?」
だとしたら、だいぶショックだ。今日は部活だったから二人きりは無理なのはわかっていたけれど、さすがに二十五日は一緒に過ごせるだろう、与明くんもそのつもりだろうと勝手に思っていたんだ。私だけだったのかな、と思わず落ち込みかけてしまう。
私の顔色に気づいたのか、与明くんは慌てたように手を振った。
「いえ、予定はないです。大丈夫です」
「ほんと? ムリしてない?」
「してないです。大丈夫です。それじゃ、先輩の……家、行き、ますね」
「よかった! 家の場所はわかるよね? それから……」
家でケーキを焼いておくこと、チキンとかも用意するから、基本的には何も持ってこなくて大丈夫だということ。その他のこまごまとしたことを伝える。
与明くんはどこか強張った表情で、「ええ」とか「はい」とかを繰り返している。ちょっと様子が変だったけれど、彼のこういう返答は今に始まったことじゃない。
そうこうしているうちに、駅に着いた。私と彼の家の方向は逆だから、別方向の電車に乗ることになる。
「それじゃ、明日、よろしくね」
「はい」
「あ……それとさ、ひとつお願いがあるんだけど」
厚かましいかもしれないけど、私は兼ねてからの夢を口にした。
「家に来た時にさ、インターホン押すでしょ。私が『誰ですか?』って聞いたら、『サンタクロースです』って……言ってくれないかな……?」
いざ口に出すと、ものすごく恥ずかしかった。
私の夢。ザ・王道の夢。自分からお願いするのはさすがにこじらせすぎかもしれない。顔が熱い。きっと、真っ赤になってる。
勇気を出して告げたのに、与明くんは一向に返事をしてくれない。相変わらず固い顔で、私の頭の上あたりを見つめていた。
ヤバ。引かれたかも。そう思ったときだった。
「はい、わかりました」
「いいの!?」
「いいですよ」
思わぬ快諾に、ガッツポーズしてしまう。ホームに電車が滑りこむ。ここからは別方向だ。私は来た電車に乗り込んだ。
「じゃあ、またね」
「はい」
電車のドアがしまる。軽く手を振ると、与明くんも手を振り返してくれた。体の内側がじんわり温かくなって、嬉しさがこみ上げる。
電車内はそこそこ混んでいて、どこかみんな、浮足立っているように見えた。そこかしこから甘い香りが漂っている。サラリーマンの手に握られた紙袋の中に入っているのは、きっとホールのケーキだな。帰って家族で食べるんだろうな。あっちの親子連れはチキンを買ったのかな。幼稚園児くらいの男の子が、しきりに袋の中を見てニコニコしてる。その子を見つめるお母さんも、目に微笑みをうかべていた。
クリスマスって素敵だ。あちこち、優しい気持ちで溢れている。
さて、忙しくなるぞ。私は心の中であれこれ考える。最寄り駅についたら買い出しして、今日中にスポンジケーキを焼かなくちゃ。薄力粉、まだあったかな。チキンの仕込みもしておきたいし、ちょっと高級なジュースも買っておきたいよね。
自然と口元が緩む。楽しみだなあ、明日のクリスマス!
***
どうしよう、気まずい。
僕は目の前にずらっと並んだご馳走の数々を見つめて途方に暮れていた。
「なんだか、すごいですね」
「……そう?」
声が冷たい。酷く不機嫌だ。僕はなにか、やらかしてしまったんだろうか。
昨日の帰り道。大好きな彼女から突然「明日、ウチ、来ない?」と言われたときは、どうしようかと思ったものだ。
初めてできた彼女。優佳先輩。
しっかりものなのに夢見がちなところのギャップに惹かれて、いつの間にか好きになっていた。告白して、恋人同士になれたときは嬉しすぎて、あまりに信じられなくて、帰り道で何度も電柱にぶつかりそうになったのを覚えている。
そんな大好きな、可愛い先輩の家にご招待だ。しかも両親はいないらしい。
あまりに急なことで、語彙力、思考能力、すべてがふっとんだといっても過言ではない。大混乱を起こしてしまって、先輩の話の内容がすっぽり抜けてしまったけれど、とりあえず朝に先輩の家に行けばいいということは理解した。
おうちデートっていうやつか……。
これはつまり。
いや早まるな。
そんなわけで、翌日の朝。
さしもの僕もそれなりの覚悟と緊張を持ってしてインターホンを押した。
ピンポーンと間延びする音、ガチャっと通話がつながった音。そして先輩の「誰ですか?」という声。緊張がピークに達する。張りつきそうになる喉を何とか開いた。
「あ、与明です」
「えっ……」
暫し無言だ。なにやら反応がおかしい。先輩はどこかびっくりしたような声色で、返事をして、少したってから扉が開いた。
出てきた先輩は、あからさまに不機嫌だ。いや、落ち込んでるのか? わからない。とにかくいつもの朗らかな先輩ではなかった。どうしよう、と思ったものの、直接尋ねるには情報が少なすぎる。
リビングに案内されて、目の前に広がるご馳走の数々を前にして、僕はますます気まずさをつのらせる。先輩が僕にチキンを切り分けてくれている。グラスに注がれているのは僕でも知ってるちょっとお高い炭酸ジュースだ。イチゴの乗ったケーキなんてものも用意されている。
今日は何かのお祝い? 記念日か何かだったのか? いや、でも付き合ってまだ三か月で、記念日もなにも……。付き合って〇か月目、みたいなお祝いも今までしてこなかったし、そもそも日にちがずれている。
日にち……。
サーッと音を立てて、僕の顔から血の気が引くのが分かった。
今日は……クリスマス……だ!
そうだった、クリスマスだ。昨日の部活ですっかりクリスマスは終わった気になってたけど、今日は二十五日。むしろ今日が本番だ。
そして、思い出した。先輩が不機嫌なのは、絶対これが理由だ。先輩はチキンを切り終わり、無言のままシチューをよそってくれている。どうしよう、どうしたらいい。
ええい! もう、正直に言うしかないだろう!
「僕は、サンタクロースです!」
「えっ!?」
先輩がシチューをよそう手を止めた。目を真ん丸にして、僕を見つめている。
「……今?」
「遅くなってすみませんでした! ぶっちゃけ忘れてました! そもそも今日がクリスマスだってことも、忘れてました! 先輩の家にお邪魔するってだけで頭真っ白になって、正直昨日のことも曖昧でした! そんなわけで、プレゼントもありません! ごめんなさい! そして、気づくのも遅くなって、本当にごめんなさい……!」
立て板に水。一度口をつけば止まらずに、僕は先輩に懺悔する。正直に話せば話すほど、本当にどうしようもない彼氏すぎて自分が憎い。
もしかしたらこのままお別れコースもありうるのか。だとしたらどうしよう。やらかしたことの大きさに、焦りが止まらない。
先輩はあっけにとられた顔で僕を見つめている。目を丸くして、口を開き、閉ざして、そして……。
「ふっ……はは、あはは、ヤバ、まじで!?」
笑い転げた。
「あの、先輩……?」
「百歩譲って、私が頼んだこと、忘れてたのはともかく。今日がクリスマスなのも忘れてたの、ヤバすぎん?」
「それは、その。本当にその通りです……」
何も言えない。たしかにどうかしていたとしか思えない。先輩はひとしきり笑うと、目じりに溜まった涙をぬぐった。
「じゃあ、罰として、今日から与明くん、敬語なしね」
「えっ!?」
「私のことも先輩呼びじゃなくて、ちゃんと名前で呼ばなきゃダメだからね」
いたずらっぽく笑う先輩に、期待されたような目で見つめられて、僕は焦った。
「どうしてもですか……?」
「どうしても」
「あー……」
どうしてこんなことになってしまったんだ。敬語を取る? 先輩を名前で呼ぶ? さっきとは違った意味で汗がダラダラと流れるのがわかる。
先輩は期待に満ちた目で僕を見つめている。「呼んでみて」と促され、ますます焦ってしまう。ここで言わなきゃ本当にただのダメ彼氏だ。覚悟を決めろ!
先輩の耳の近くに口を寄せて、限りなく小さな声で名前を呼んだ。先輩はうつむいた。耳がみるみる赤く染まっていく。
そして、僕と同じくらい小さな声で、こう言ったんだ。
「もう本当に、遅いよ、バカ」
【出典・参考文献】
「醒睡笑 全訳注」著 安楽庵策伝/訳注 宮尾與男(講談社学術文庫)
「醒睡笑 (上)」著 安楽庵策伝/訳注 鈴木棠三 (岩波文庫)