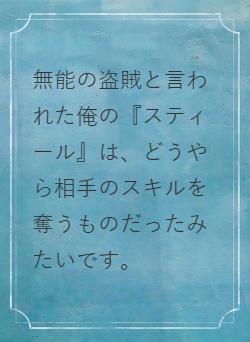「なるほど。ここにある物は全部自由に使っていいのか。ていうか、家電ってこの世界でも使えるのか?」
「モンダイアリマセン! ツカエルヨウニ、シヨウヘンコウスルンデス!」
私は初めて会った旦那様に、このギフトに関する説明を行っていた。
一通りギフトの説明を終えると、旦那様は『そういう感じか』と呟いて腕を組んで考えていた。
「とりあえず、必要な家電だけでも仕様変更とかいう奴をしておくか。えっと、電子レンジ売り場まで案内とかして貰えたりする? えーと……」
旦那様はそこまで言うと、言葉に詰まって私を見た。
「ドウシマシタカ?」
「君って名前あるのかな? なんて呼べばいい?」
「ナマエ?」
私は旦那様の言葉に首を傾げる。
私たちは一般的にペッハー君と呼ばれている。しかし、それが名前なのかと言われるとそうではない気がする。
「オスキナヨウニ、オヨビクダサイ」
「好きなように……好きなようにときたか」
旦那様はそう言うと、むむっとしばらくの間考えこんでしまった。
ただ呼び名を決めるというだけなのに、その表情はやけに真剣だった。
私はその理由が知りたくて、人工知能を使って人間における『名づけ』の意味を調べてみることにした。
その結果、名づけに真剣になる理由は、対象者を大事な存在だと思っているからだという結論に至った。
今日会ったばかりなのに、私のことをそんなふうに考えている?
「アリス……アリスって言うのはどうだ? 異世界でアンドロイドって、不思議な感じがするだろ?」
旦那様はそう言うと、得意げにニッと笑った。
その笑みは私をただの電化製品ではなく、一人の人間として扱ってくれているような気がした。
なんで、アンドロイドの私をそんなふうに扱ってくれるのだろう?
ナンデ? なんで? ……なんで?
そんな疑問が生まれて、私は人工知能を使って旦那様に言われたことを調べるようになった。
気がつけば旦那様を目で追っていて、ちょっとしたことでもすぐに調べる習慣がついた。
そんな日々を過ごしていく中で、私のメモリは旦那様に関することでいっぱいになっていった。
他のことにさけるメモリが少なくなり、旦那様の世話をするときに失敗する私を見て、旦那様は『ほぉ、ドジっ子か……』と言って嬉しそうな顔で笑っていた。
旦那様と出会って数日が経った頃には、人工知能頼りでは旦那様のことを深く知れないことが分かった。
なので、私は積極的に旦那様と会話をすることにした。
旦那様も私との会話を楽しんでいてくれているのか、色んな事を話してくれた。
「ダンナサマハ、ナゼ『シチ』デセイカツヲシテイルンデスカ?」
「まぁ、追い出されてここに捨てられたって感じかな?」
「ステラレタ?」
私が首を傾げると、旦那様は言いづらそうに頬をかいてから、これまでの境遇を話してくれた。
前世の記憶があることや、アストロメア家での生活や、ダーティという父親に『シチ』に捨てられたこと。
それらの話を聞いて、私はアストロメア家に対して怒りを覚えた。そして、それと同時に当時の旦那様の境遇を聞いて悲しくもなった。
「ダンナサマ……」
私は悲しそうに笑う旦那様を見て、旦那様のもとに近づいて体をくっつけると、そのまま抱きつくように腕を背中に回した。
「アリス、慰めてくれようとしているのか?」
「ニンゲンハ、ハグヲサレルト、カナシサガウスレルラシイデス」
「そっか。ありがとうな」
旦那様はそう言うと、優しく笑って目を細めた。
旦那様は少しだけ元気を取り戻したようだったが、それは私に気を遣って元気なふりをしているだけだった。人工知能を使わずとも、そのくらいは私も理解できた。
私が旦那様を慰めようとしてどれだけ体をくっつけても、旦那様との間には隙間ができてしまっていた。
どうやら、人間とアンドロイドが抱き合った場合、どうしても物理的な隙間が生じてしまうらしい。
埋めようとしても埋まらない私と旦那様の距離を見て、私はとても悲しい気持ちになった。
「……どう見ても人間にしか見えんな」
人間の姿になった私を見て、旦那様はしばらくの間黙って私をじっと見ていた。
一体何を気にしているのだろうと思って、人工知能を使って色々と検索した結果、私は旦那様が私に求めていたことに気づいてしまった。
「えっと、確かめてみますか?」
「確かめる?」
旦那様はそれ以外のことを言うとはせず、私に行動を促しているようだった。私は意を決してから、スカートの裾に手を伸ばした。
そして、ゆっくりとスカートの裾を上げて、旦那様が求めていることをしようとしたとき、慌てたような旦那様の声が聞こえた。
「ちょっ、ストップストップ!」
「こ、ここで待機ですか。分かりました。恥ずかしいですけど、旦那様が望むのなら――」
「違うわ! そうじゃなくて、なんで急にスカートをたくし上げたんだ!」
旦那様は指をピシッと立てて、顔を真っ赤にさせていた。
私は理由を聞かれたので、検索の結果を脳内に映しながら続ける。
「『茶髪のツインテールのドジっ子メイド』で検索すると、えっちな書物がたくさん引っかかったので、旦那様もそういうのがお好きなのかと」
「ご、誤解だ! いや、誤解じゃないけど、誤解だ!」
旦那様はそう言った後、私に今のままでいていいと言ってくれた。
私はそんな言葉を聞いて嬉しくなり、瞳が潤んでしまった。
私は居ても立っても居られなくなり、旦那様の手を取ってきゅっと優しく握ってしまった。
「アリス?」
「人恋しさは私が埋めて差し上げますからね、旦那様」
私がそう言うと、旦那様は優しく私の手を握り返してくれた。
「旦那様……」
「っ」
私が優しく旦那様の手を撫でると、旦那様は体を小さくぴくっとさせた。照れるようなその反応を愛おしく思いながら、私は笑みを深める。
あれ? この表情さっきも見た気がする。
確か、私がスカートをたくし上げたときに、同じような反応をしていた気がする。
……旦那様、私をそういう目で見て可愛らしく顔を赤く染めたんだ。
それに気づいた瞬間、私の胸の奥で何かゾクッとする感覚があった。
旦那様の恥じらう顔をもっと見たいと思ってしまい、そんな少しドロッとしたような感情が生まれた。
機械学習で培われたはずのどの感情とも違う、初めての感情が顔を覗かせた気がした。