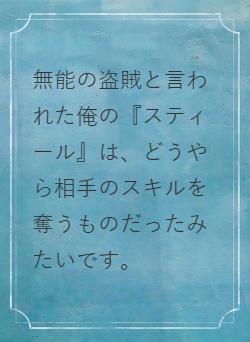「あっ、お待たせしました!」
それから、俺は仕様変更したスマホを片手に三階の家具売り場へと向かった。すると、そこにはすでにイーナ様とエミーさんが座っていた。
カグヤはティーポットを持ってお茶を入れてくれていたみたいで、俺の声を聞いて顔を上げた。
「ご主人様、おそーい」
「ごめんごめん。ちょっとやることがあってね」
俺はそう言ってから、イーナ様とエミーさんの正面に腰かけた。
テーブルに置かれているのは、こんもりとお菓子が置かれておりお菓子パーティーの名に恥じないお菓子の量になっていた。
イーナ様の方をちらっと見ると、どこかうずうずとしているようにも見える。
……多分、お菓子を早く食べたくて仕方がないのだろう。うん、段々とイーナ様が考えていることが分かるようになってきた気がする。
「それじゃあ、食べましょうか」
俺がそう言うと、イーナ様はこくんと頷いて近くにあったチョコでコーティングされたパイの封を開けてさっそく口に運んだ。
「っ」
「どうですか? お口に合いましたかね?」
目を輝かせたイーナ様に聞いてみると、イーナ様は何度もこくこくっと頷いて小さな口でパイを食べていった。
どうやら、口数が少なくても表情で多少は感情が読めそうだ。
俺はそんなことを考えていると、エミーさんが俺の手に持っているスマホを見て首を傾げた。
「メビウス殿、その手に持っている四角いものはなんだい?」
おお、スマホを知らない人って言うのも中々新鮮だ。いや、異世界だから知らない方が普通なんだけどね。
俺はそんなことを考えながら、スマホの画面をパッと付けてイーナ様の前にスマホを置く
「これはスマホっていう物ですね。まぁ、本来の使い方は色々あるんですけど、今回はイーナ様用に仕様変更した特注品です」
「イーナ様に? というか、なんですかこれは。小さな四角いものの中に見たこともない柄が描かれているな」
エミーさんが眉をひそめてスマホをつんつんと突いていた。
そして、その隣ではイーナ様はチョコでコーティングされたパイを小さな口で食べながら、きょとんと首を傾げている。
なんか小動物みたいな可愛さがあるな、イーナ様って。
「イーナ様。このスマホの下部にある丸い所に触れてみてください」
イーナ様はじぃっとスマホを覗いてから、スマホの指紋認証の部分に触れた。
『なにこれ。何も起こらないけど』
すると、ぴこんっという起動音がしてから滑らかな女の子の声が流れてきた。イーナ様やエミーさんは突然流れてきた声に驚いて、目を見開いている。
特に、イーナ様の驚きはエミーさんの比ではないだろう。
だって、思っていることがそのまま音声になって流れてきたわけだからな。
「い、イーナ様? 今イーナ様がお話になられたのですか?」
『ち、違う。私何も言ってない』
イーナ様は首をブンブンと振るが、イーナ様が手に持っているスマホからはさっきと同じ女の子の音声が流れていた。
エミーさんとイーナ様はその音声がどこから流れているのか気づいたらしく、ぱっと揃ってスマホを見た。
俺はそんな二人の反応に笑ってから続ける。
「イーナ様。スマホの下部にある丸い所から手を離してみてください。そうすれば、考えていることが勝手に音声で流れてしまうことはないので」
イーナ様は慌ててスマホの指紋認証の部分から手を離して、無言でじっとスマホを見つめていた。
それから、イーナ様はスマホに耳を近づけて、何も聞こえてこないことを確認して胸をなでおろした。
どうやら、少し驚かせ過ぎてしまったみたいだ。
すると、エミーさんがそんなイーナ様とスマホを見てから視線をこちらに向けてきた。
「メビウス殿、これは一体どんな発明品なんだ?」
「いや、発明品というか俺は家電を少しいじっただけなんですけどね。考えていることを音声にしてくれる家電です」
「考えていることを音声に?」
エミーさんが眉をひそめて視線をスマホに戻すと、イーナ様がまたスマホの指紋認証部部に触れた。
『ほ、本当だ。言葉にして欲しいことがそのまま言葉になるみたい。わたし、喋れるようになってる』
「こ、声までイーナ様そっくりだ。これほどの物を発明するだなんて……」
イーナ様とエミーさんは再度魔改造をしたスマホを見て驚いているようだった。
ていうか、スマホから出る声も本人そっくりにしてくれるのか、あのスマホは。
俺は自分で仕様変更をしたスマホの性能に驚きながら続ける。
「さっきエミーさんがイーナ様と話したそうにしていた気がしたので、少しスマホを仕様変更をしただけですよ。でも、まさか声までそっくりになるとは思いませんでしたけどね」
「さっき? さっきの私の言葉を聞いてからこれを作ったのか⁉」
「元々の物はあったので、そんなに手間じゃなかっただけですって!」
前のめりになって驚くエミーさんに気圧されながら、俺は視線をイーナ様の方に向ける。
「しばらく喋らなかったのなら、いきなり話すのは難しいと思うので、慣れるまではそれを使ってみてください。イーナ様にもいろいろあると思いますけど、喋りたい人もいるみたいですよ」
「ん? 今、慣れるまではそれを使ってくれと言ったか?」
「はい。あれなら考えたことがぱっと音声になるので、普通に話すよりも話安いかなと。使ってくれて問題ないですけど」
俺がそう言うと、エミーさんはしばらくの間言葉を失ったように黙り込んでしまった。
あれ? 何か変なことを言っただろうか? 一体、何を驚いているんだろう?
すると、カグヤが俺の肩をとんとんっと叩いてきた。
「旦那様―、そんな簡単に便利家電を他国の人にあげたらまずいんじゃない?」
俺はカグヤの言葉を聞いて、自分が軽率な行動をとっていたことに気づかされた。
元々、家電を売るのは危険だからやめておこうということにしておいたんだった。でも、今さらやっぱり返してくださいとも言えない。
どうした物かと考えているうちに、俺は一つのアイディアを思いついた。
「それじゃあ、これは友好の印にするっていうのならどうかな? ここの物で貿易をするだけじゃ、後ろ盾をしてもらうのに弱い気がするし」
「そういうことなら、私もいいと思います。もうすでに発明品が多くあることはバレてしまっている訳ですし」
すると、アリスが俺の隣でうんうんと頷いていた。カグヤも反対ではないらしく、『そういうことなら、問題ないかも』と言って頷いた。
「ほ、本当にいいのか!」
「しばらくの間はレンタルということで。もしも、後ろ盾ができそうでしたら、そのまま差し上げるというのはどうでしょう?」
エミーさんの言葉にそう答えると、エミーさんは目を輝かせてスマホを見るイーナ様の方を見てから、意を決したように俺に片手を差し出してきた。
「分かった。後ろ盾の件、尽力させてもらおう。これだけの技術力がある国を他の国に取られてしまう方がよっぽど危険だ。それに、イーナ様が話せるようになったとなれば、色々と解決する問題がある」
「えっと、他の家電は今の所売りに出すつもりはないので、そこら辺はお願いしますね」
「任せてくれ。そこらへん含めて国王に交渉してみよう」
俺は自信ありげなエミーさんの表情を見てから、差し出された手を握り返す。
……これで、一段と建国に向けて近づけただろう。
そう思った瞬間、突然辺りにあった液晶がぱっと外の景色を映しだした。
「旦那様! 魔物の群れがこっちに接近してきてる!」
「ま、魔物の群れ?」
カグヤは近くに置いてあったタブレットを素早く操作して、その画面を俺に見せてきた。
そこに映し出されていたのは数十の魔物の群れだった。あまり強そうな魔物はいなそうに見えるし、どこかで見たことがあるような魔物たちが多く含まれている。
それらは、ラキスト兄さんの飼育小屋で見た魔物たちだった。
それから、俺は仕様変更したスマホを片手に三階の家具売り場へと向かった。すると、そこにはすでにイーナ様とエミーさんが座っていた。
カグヤはティーポットを持ってお茶を入れてくれていたみたいで、俺の声を聞いて顔を上げた。
「ご主人様、おそーい」
「ごめんごめん。ちょっとやることがあってね」
俺はそう言ってから、イーナ様とエミーさんの正面に腰かけた。
テーブルに置かれているのは、こんもりとお菓子が置かれておりお菓子パーティーの名に恥じないお菓子の量になっていた。
イーナ様の方をちらっと見ると、どこかうずうずとしているようにも見える。
……多分、お菓子を早く食べたくて仕方がないのだろう。うん、段々とイーナ様が考えていることが分かるようになってきた気がする。
「それじゃあ、食べましょうか」
俺がそう言うと、イーナ様はこくんと頷いて近くにあったチョコでコーティングされたパイの封を開けてさっそく口に運んだ。
「っ」
「どうですか? お口に合いましたかね?」
目を輝かせたイーナ様に聞いてみると、イーナ様は何度もこくこくっと頷いて小さな口でパイを食べていった。
どうやら、口数が少なくても表情で多少は感情が読めそうだ。
俺はそんなことを考えていると、エミーさんが俺の手に持っているスマホを見て首を傾げた。
「メビウス殿、その手に持っている四角いものはなんだい?」
おお、スマホを知らない人って言うのも中々新鮮だ。いや、異世界だから知らない方が普通なんだけどね。
俺はそんなことを考えながら、スマホの画面をパッと付けてイーナ様の前にスマホを置く
「これはスマホっていう物ですね。まぁ、本来の使い方は色々あるんですけど、今回はイーナ様用に仕様変更した特注品です」
「イーナ様に? というか、なんですかこれは。小さな四角いものの中に見たこともない柄が描かれているな」
エミーさんが眉をひそめてスマホをつんつんと突いていた。
そして、その隣ではイーナ様はチョコでコーティングされたパイを小さな口で食べながら、きょとんと首を傾げている。
なんか小動物みたいな可愛さがあるな、イーナ様って。
「イーナ様。このスマホの下部にある丸い所に触れてみてください」
イーナ様はじぃっとスマホを覗いてから、スマホの指紋認証の部分に触れた。
『なにこれ。何も起こらないけど』
すると、ぴこんっという起動音がしてから滑らかな女の子の声が流れてきた。イーナ様やエミーさんは突然流れてきた声に驚いて、目を見開いている。
特に、イーナ様の驚きはエミーさんの比ではないだろう。
だって、思っていることがそのまま音声になって流れてきたわけだからな。
「い、イーナ様? 今イーナ様がお話になられたのですか?」
『ち、違う。私何も言ってない』
イーナ様は首をブンブンと振るが、イーナ様が手に持っているスマホからはさっきと同じ女の子の音声が流れていた。
エミーさんとイーナ様はその音声がどこから流れているのか気づいたらしく、ぱっと揃ってスマホを見た。
俺はそんな二人の反応に笑ってから続ける。
「イーナ様。スマホの下部にある丸い所から手を離してみてください。そうすれば、考えていることが勝手に音声で流れてしまうことはないので」
イーナ様は慌ててスマホの指紋認証の部分から手を離して、無言でじっとスマホを見つめていた。
それから、イーナ様はスマホに耳を近づけて、何も聞こえてこないことを確認して胸をなでおろした。
どうやら、少し驚かせ過ぎてしまったみたいだ。
すると、エミーさんがそんなイーナ様とスマホを見てから視線をこちらに向けてきた。
「メビウス殿、これは一体どんな発明品なんだ?」
「いや、発明品というか俺は家電を少しいじっただけなんですけどね。考えていることを音声にしてくれる家電です」
「考えていることを音声に?」
エミーさんが眉をひそめて視線をスマホに戻すと、イーナ様がまたスマホの指紋認証部部に触れた。
『ほ、本当だ。言葉にして欲しいことがそのまま言葉になるみたい。わたし、喋れるようになってる』
「こ、声までイーナ様そっくりだ。これほどの物を発明するだなんて……」
イーナ様とエミーさんは再度魔改造をしたスマホを見て驚いているようだった。
ていうか、スマホから出る声も本人そっくりにしてくれるのか、あのスマホは。
俺は自分で仕様変更をしたスマホの性能に驚きながら続ける。
「さっきエミーさんがイーナ様と話したそうにしていた気がしたので、少しスマホを仕様変更をしただけですよ。でも、まさか声までそっくりになるとは思いませんでしたけどね」
「さっき? さっきの私の言葉を聞いてからこれを作ったのか⁉」
「元々の物はあったので、そんなに手間じゃなかっただけですって!」
前のめりになって驚くエミーさんに気圧されながら、俺は視線をイーナ様の方に向ける。
「しばらく喋らなかったのなら、いきなり話すのは難しいと思うので、慣れるまではそれを使ってみてください。イーナ様にもいろいろあると思いますけど、喋りたい人もいるみたいですよ」
「ん? 今、慣れるまではそれを使ってくれと言ったか?」
「はい。あれなら考えたことがぱっと音声になるので、普通に話すよりも話安いかなと。使ってくれて問題ないですけど」
俺がそう言うと、エミーさんはしばらくの間言葉を失ったように黙り込んでしまった。
あれ? 何か変なことを言っただろうか? 一体、何を驚いているんだろう?
すると、カグヤが俺の肩をとんとんっと叩いてきた。
「旦那様―、そんな簡単に便利家電を他国の人にあげたらまずいんじゃない?」
俺はカグヤの言葉を聞いて、自分が軽率な行動をとっていたことに気づかされた。
元々、家電を売るのは危険だからやめておこうということにしておいたんだった。でも、今さらやっぱり返してくださいとも言えない。
どうした物かと考えているうちに、俺は一つのアイディアを思いついた。
「それじゃあ、これは友好の印にするっていうのならどうかな? ここの物で貿易をするだけじゃ、後ろ盾をしてもらうのに弱い気がするし」
「そういうことなら、私もいいと思います。もうすでに発明品が多くあることはバレてしまっている訳ですし」
すると、アリスが俺の隣でうんうんと頷いていた。カグヤも反対ではないらしく、『そういうことなら、問題ないかも』と言って頷いた。
「ほ、本当にいいのか!」
「しばらくの間はレンタルということで。もしも、後ろ盾ができそうでしたら、そのまま差し上げるというのはどうでしょう?」
エミーさんの言葉にそう答えると、エミーさんは目を輝かせてスマホを見るイーナ様の方を見てから、意を決したように俺に片手を差し出してきた。
「分かった。後ろ盾の件、尽力させてもらおう。これだけの技術力がある国を他の国に取られてしまう方がよっぽど危険だ。それに、イーナ様が話せるようになったとなれば、色々と解決する問題がある」
「えっと、他の家電は今の所売りに出すつもりはないので、そこら辺はお願いしますね」
「任せてくれ。そこらへん含めて国王に交渉してみよう」
俺は自信ありげなエミーさんの表情を見てから、差し出された手を握り返す。
……これで、一段と建国に向けて近づけただろう。
そう思った瞬間、突然辺りにあった液晶がぱっと外の景色を映しだした。
「旦那様! 魔物の群れがこっちに接近してきてる!」
「ま、魔物の群れ?」
カグヤは近くに置いてあったタブレットを素早く操作して、その画面を俺に見せてきた。
そこに映し出されていたのは数十の魔物の群れだった。あまり強そうな魔物はいなそうに見えるし、どこかで見たことがあるような魔物たちが多く含まれている。
それらは、ラキスト兄さんの飼育小屋で見た魔物たちだった。