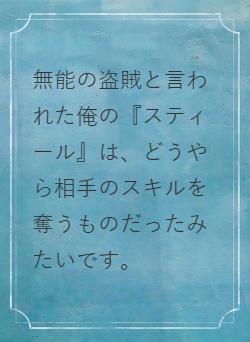「父上、ご報告いたします」
「ふむ、よく戻ったなラキスト! それで、どうだった?」
そして、ラキストは『死地』から帰還するなり、ダーティの元へと報告に向かった。
メビウスが生きていたこと、そのメビウスに取引を断られたこと、侮辱されたこと。それら全てがラキストは許せなかった。
ましてや、メビウスが小国の長になっていたことがダーティにバレれば、ダーティは今から無理やりにでもメビウスと関係を戻そうとする。
そして、そうなってはダーティの後を継ぐのがメビウスになる可能性がある。
そんな未来だけは絶対に回避しなければならない。
ラキストはそうまで考え、その未来を潰すためにいち早くダーティのもとに事の顛末を報告することにしたのだ。
ラキストは悔しさで顔を歪ませる演技をして顔を俯かせる。
「確かに、国はありました。しかし、その国の王が王たる器のある人ではなかった……」
「器ではない? 一体どういうことだ?」
ダーティはよほど続きが気になるのか、体をぐいっと前のめりにして首を傾げる。ラキストは十分ダーティが食いついたのを確認してから続ける。
「アストロメア家如きとは取引をしないと言い、ここでは言えないような罵声を浴びせられました」
「馬鹿にされた? ほほう、『死地』にしか国を構えることができない田舎者が、我がアストロメア家を馬鹿にしてきたのか」
ダーティはラキストの言葉を聞いて、体をぴくっとさせた。それから、ダーティは徐々に怒りで顔を赤くさせていく。
「このままでは、我々ではない他の貴族に先を越され、王へ献上品の品として献上されてしまう。そうなると、我らは『死地』の近くに住んでいながら、何もできなかった無能扱いされてしまいます。きっと、そうなるのを知っていて取引に応じないのでしょう」
「我らに敵対するものか! このアストロメア家を敵に回すなど、舐められたものだ」
ダーティは小さく震えながら、握った拳を机に叩きつける。鈍い音が部屋に響き、机の上に積まれていた書物が宙を舞った。
ラキストは怒りに震えるダーティの言葉に頷いてから続ける。
「全くです。彼ら、数十人くらいしかいないただの移動民族ですよ。なぜ古くからロエン大国に使える割れたアストロメア家を馬鹿にできるのか」
ラキストは肩をすくめるような仕草をして大きくため息を漏らす。すると、ダーティはラキストの言葉を聞いて目を丸くさせた。
「数十? その人数で国だと? ただの貴族崩れごときが……馬鹿にしやがって」
「いかがなさいましょうか、父上」
「殺せ……」
ダーティは顔を震えて俯かせた後、ばっと勢いよく顔を上げた。そして、血走った目でラキストを強く睨む。
「殺せ殺せ! 殺してしまえ! 農地も何もかもぐちゃぐちゃにして、跡形もなく消し去るのだ! 他の貴族たちが手を出せないようにしてしまえば、我らの評価が下がることはない!」
ラキストは想像通りの展開になったことを喜び、慌てて緩んだ口元を手で隠した。それから、ラキストは怒りの表情を作って顔をしかめる。
「そうしましょう。所詮は『死地』。『調教』した魔物たちに襲わせましょう。あとは金で雇った賊でも向かわせましょうか」
「金の糸目はつけない! ウィンスも連れていって、徹底的に潰せ!」
「承知しました、父上」
ラキストは怒り狂っているダーティの表情を見て、満足げに頷く。
ラキストは散々馬鹿にされた仕返しとして、『死地』にある国を潰すことを考えた。
『死地』には城壁もなく、メビウスの隣にいたのは二人のメイドだけ。以上にでかい農園があるということは、基本的に農民しか住んでいない。
こちらに利益が何のなら、他の貴族たちの利益にもならないように潰してしまえばいい。そんなことを本気で考えていた。
しかし、ダーティからのゴーサインがない状態で単独で動くわけにはいかない。だから、ダーティを刺激するように報告する内容を少しか改ざんしたのだった。
ラキストはいち早く馬鹿にされた仕返しをするため、その場を後にすることために回れ右をした。
すると、ダーティが何顔を思い出したような声を漏らす。
「まて、ラキスト。『死地』にいる国王は一体、どんな奴だったのだ?」
「……どこにでもいる、腹の出ている小汚いおっさんでしたよ」
ラキストはそう言い残すと、悪巧みをするような笑みを浮かべてダーティの書斎を後にしたのだった。
邪魔な弟を消すために、ラキストは大きな嘘を吐いたのだった。