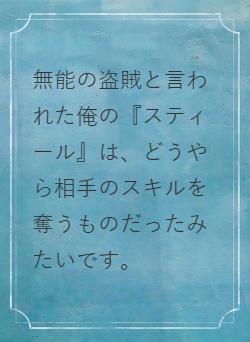それから数週間、俺はグラン大国からの使者が送られてくるのを待ちながら、ひたすら銃の腕を磨いていた。
「よっし。結構腕が上がったんじゃないか?」
俺はストラックアウトコーナーで、7割がた倒れている的を前にそんな言葉を漏らしていた。
ここのストラックアウトコーナーもとい、射撃場には全部で4つの難易度がある。『初級』『中級』『上級』『鬼』といった感じだ。
『初級』は動かない的を相手に、『中級』は動く的を相手に、『上級』は『中級』よりもさらに早い的を相手にする感じだ。
今は『初級』の的をすべて撃ち抜くことができたので、『中級』のモードで挑戦をしている。
ちなみに、まだ『鬼』のモードはやっていない。
『上級』になると的の動く速さが『中級』と桁違いになるので、まだ見たことすらない。なんか色々と怖いしな。
……でも、そろそろどんな感じなのかぐらいは見てみてもいいかな?
「あっ、ご主人様。お客様が来たみたい」
「お客様?」
俺がそんなことを考えてストラックアウトの所にあるタブレットの前で悩んでいると、カグヤが自分のタブレットを見ながらそう口にした。
それから、カグヤは手慣れた感じでタブレットを操作して、バッティングセンターにあった液晶に映像を飛ばした。
どうやら、カグヤのタブレットからは『家電量販店』にある色んな液晶に映像を飛ばせるらしい。
某通販サイトが扱っているような何とかスティックでも搭載されているのだろう。
すると、大きな液晶に走行中の馬車の映像が映っていた。
「あの馬車は……前にエミーさんたちが乗ってきた奴だな。ということは、もうグラン大国の王様に話を通してくれたのかな?」
思った以上に早く話を進めてくれたのかな、エミーさん。
「それじゃあ、今度は入り口で待ってようか。アリスとカグヤは家具売り場でお出迎えの準備をしてから下りてきて」
俺はアリスとカグヤにそう告げてから、エアガンをランドセルにしまってから一階の自動ドアの前に向かうことにしたのだった。
「メビウス殿。度々突然の来訪ですまない」
俺が一階の入口にエミーたちを迎えに行くと、エミーさんたち国家騎士団が数人馬車から下りてきた。
以前よりも人数が大幅に少ないとこから察するに、これから事を構えようとかいうつもりはなさそうだ。
俺は小さく首を横に振って小さく笑う。
「『死地』には手紙を運んでくれる業者とかもいませんから、お構いなく」
「そうかい? そういえば、今回はここに住む者たちも我々が来ることを分かっていたみたいだな。なぜ分かったんだ?」
エミーさんはそう言うと、俺たちに頭を下げているラインさんたちを見て不思議そうに首を傾げる。
「少し設備を整えたからですかね。エミーさんたちが以前乗っていた馬車が通ったのを見て、ここに住む人たちにも前もって伝えておきましたから」
「ほぅ。まったく気づかなかったな……さすがだ」
エミーさんはどこか嬉しそうに笑って俺を見つめていた。
ただペット監視用のカメラを設置しただけで、何か面白い物でも見つけたような顔をしてもらえるとは思わなかったな。
俺は少し意外に思っていると、エミーさんの隣に以前はいなかった眼鏡をつけた男性がいたことに気づいた。
俺の視線に気づいたのか、その男の人はぺこりとこちらに頭を下げてきた。
「お初にお目にかかります。メビウス殿。ステロン・ローアと申します。グラン大国で貿易関係の仕事を任されております」
「初めまして、メビウスと申します。貿易関係ということは……」
俺はローアさんに倣うように頭を下げてから、視線をエミーさんの方に向ける。するとエミーさんは大きく頷いて続ける。
「国王からぜひ貿易をしたいという返事をいただいた。国として後押しする市内の話は、また後日になるが、前向きに検討するようだ。」
「おお、本当ですか!」
俺は思いもしなかったスピードで前向きな回答が返ったことに喜び、エミーさんたちがいるというのにガッツポーズをしてしまった。
慌ててその手を後ろに下げると、エミーさんはふっと小さく笑う。
「今後はより良い関係を築けるようにしていきたい。そんなに畏まらなくてもいいんじゃないか?」
エミーさんは俺に握手をしようと手を伸ばしてから、ピタッと動きを止めた。
「いや、アストロメア家ではなく、次期国王になるということはこの話し方はマズいんじゃないか?」
エミーさんはそう言うと、顔を青くさせて一瞬手を引こうとしたので、俺はその手を優しく包み込む。
「いえ、それこそ気にしないでください。今の俺は貴族でも何でもないんですから」
「いや、そう言う訳には……」
エミーさんは俺の顔を見つめて目をぱちくりとしてから、諦めるように小さく息を吐いた。
「そうか。それじゃあ、国王になるまでは今のままでいさせてもらうとしよう」
エミーさんはそう言うと、俺の手を握り返してくれた。
……ようやく、グラン大国との繋がりを持てることができた。
俺は少しずつではあるが、確実に前に進んでいるという状況に口元を緩めるのだった。