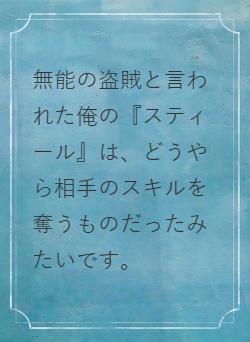「まさか、『死地』に国ができようとしているなんて、思いもしませんでしたね」
「ああ。まったくだ」
『死地』への視察を終えた帰り道。馬車でグラン大国に戻る道中、私エミーは部下のケイドの言葉に頷いた。
とある商人が『死地』に変な建物ができているという報告を受け、調査隊が編成された。
しかし、様子を見に行った先行部隊から、あまりにも規模がでかすぎるという話が上がり、我々国家騎士団が調査に向かうことになったのだった。
正直、初めにあの建物を見たときは蜃気楼でも見ているのかと思った。周辺国に気づかれず、『死地』にあんな高層なものを造ることなどできるはずがない。
そう考えて近づいていくと、蜃気楼のはずなのに徐々に距離が近づいていった。そして、あろうことか『死地』にあるはずがない緑が生い茂っている農園までがあったのだ。
「それにしても、なんで『死地』で農業なんてやろうとしたんですかね。普通に考えれば、一番向いてないでしょ」
「なんだ気づいていないのか。なぜメビウス殿があの地で野菜を作ろうと考えたのか」
私がそう言うと、ケイドは首を傾げてしばらく考え込んでから口を開く。
「理由ですか? もしかしたら、実は『死地』が野菜作りに向いている地だったからとかですか?」
「そんなわけがないだろう。グラン大国も周辺国も開発が無理だから見捨てた地だぞ、あそこは」
歴史を紐問えば分かることだが、『死地』の開発というのは色んな国が試みたことだ。初めは広大な土地だからという理由でどこかの国の領地になっていたが、無駄に広大なだけで草木も水もない場所を開発することができず、領地にもいらないというレッテルが張られた場所だ。
やがて、色んな国で押し付け合うようになり、その後誰も手を付けないどこの国でもない土地となったのだ。
そんな場所で農業をやる理由は一つしかない。
私はやけ気味に笑って、遠ざかっていく七階建ての建物を見つめる。
「理由は単純だ。自分の技術力を見せつけるためだ。国が長年かかって諦めた地でも、再生させることができるということをアピールするためだろう」
「あっ」
ケイドはようやく私の言葉を理解したのか、表情を硬くした。
私はそんなケイドを見ながら、小さくため息を吐いて続ける。
「無理やり自分の力を他国に認めさせる力技だ……あの子、可愛い顔して結構えぐいやり方をしてくるタイプだな」
「そうえいば、館の中に数えきれない発明品がありましたね。もしかして、あれを我々に見せたのは、まだまだ隠している技術があるってことをアピールしているのですか?」
ケイドは重大なことを思い出したようにハッとしてから、額にかいた汗を拭っていた。
私はケイドの言葉を聞いて、さっきまでいた館にあった多くの発明品のことを思い出す。
使い方も全く分からない大きな機械たちは各フロアに置かれていた。おそらく、あの建物のすべてにメビウス殿が発明した物が置かれているのだろう。
あの年齢であれだけの発明をするということは、何かしらそれに関するギフトを持っているのだろう。
一体、どんなギフトを持っていれば、あれだけの発明品を造ることができるのか、全く想像ができないないが。
私はそう考えて、軽度の言葉に頷く。
「もしかしたら、我々が調査に来るのを待っていたのかもしれない。そうすれば、偶然を装って技術力を見せつけることができるからな」
「と、とんでもない御方ですね」
「ああ。でも、初めて接触できたのが我らだったのは幸いだな」
もしも、他の国に接触されていたら、一刻も早く自分たちの自陣に取り入れようと考えるだろう。
私はメビウス殿から渡された土産の入った大きなケースを撫でる。
メビウス殿たちは、これをポータブル冷蔵庫と言っていた。メビウス殿曰く、この大きなケースに入れておけば、野菜が長持ちするらしい。
それでいて、魔法袋の技術を取り入れていため、このポータブル冷蔵庫というものはたくさん物が入るようになっているとのこと。
それはつまり、ただでさえ貴重だと言われている魔法袋に、時間操作系の魔法を組み込んだということになる。
「天才どころの枠じゃ収まらないだろ。さながら、『機械仕掛けの大魔導士』と言ったところか」
私は独り言のようにそんなことを呟いてから続ける。
「これだけの技術力を持つ国だ。敵に回したら厄介だから絶対に囲い込んだ方がいい。いや、そうしなければ、我らの国が危ないかもしれない」
「そうですね。多分、あの野菜とかも貴族連中がいくらでも金出しますよ。なんとかうちに多く流してもらいたいものですね」
「ああ。ただ武力だけでやり合うだけが戦争じゃないってことだな……これが水面下での戦いか。面白くなってきた」
初めはただの辺境地の調査かと思ったが、蓋を開けてみれば一国の取り合いが始まろうとしている。
私は思いもしなかった展開に思わず笑みを浮かべてしまうのだった。