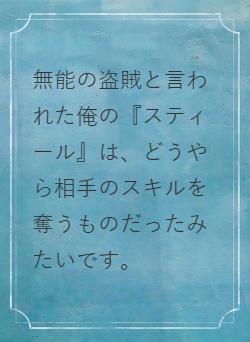「メビウス殿。あの二人は何者なのですか?」
俺が突然舞い降りたビックチャンスに気合を入れ直していると、エミーさんの部下の一人が声を潜めてそんなことを聞いてきた。
俺は質問の意味が分からず首を傾げる。
「といいますと?」
すると、エミーさんの部下二人は顔を見合わせてから各々続ける。
「普通のメイドがあんな殺気出せませんよ。元凄腕の冒険者とかですか?」
「俺本気でブルっちゃいましたもん」
俺は二人の言葉を聞いて、申し訳なさと気まずさを覚えてふいっと視線を逸らす。
……国家騎士団が怖がるくらい殺気を出してたのか、あの二人。
俺はそんなことを考えながら、ふとよく見るテンプレ展開を思い出す。
そういえば、領地経営のテンプレ展開だとよく元最強冒険者みたいな人いるよなぁ。こんなことを聞いてくるということは、この世界でも僻地に飛ばされた子供に凄腕の冒険者が付いてくるのが普通なのか?
「えーと、詳しくは俺も分からないですね。滅茶苦茶強いってことくらいしか、知らないんですよ」
さすがに、元はペッハー君だったことなんて言えないだろう。俺のギフトを詳しく知らない人からしたら、人体錬成とかと間違われそうだし。
「なるほど、一言で言い表せないくらいの猛者ということか」
「い、いえ、そういう訳ではなくてですね」
すると、俺の言葉を聞いたエミーさんが勝手に勘違いをして解釈をしてしまった。訂正しようとしても、『元国家騎士……いや、傭兵や裏ギルドの者だった線も……』などと言って、一人で考えこんでしまって、俺の声が中々届かない。
どうしよう。エミーさんの中で、アリスとカグヤの経歴が凄いことになっていっている気がする。
「旦那様! 冷えている野菜をいくつかお持ちしました!」
「ご主人様、アレを持ってきたよ!」
すると、アリスとカグヤが小走りで俺たちのいる家具売り場に戻ってきた。
そして、二人が帰ってくると、エミーさんたちの背筋が少し伸びたような気がした。
……なんかさっきよりもエミーさんたちの表情が硬くなってる気もするな。
アリスとカグヤは全くそのことに気づいていないのか、さっきと変わらない様子でテーブルの上にカットされた状態の野菜と、箱に入っている酒の瓶とチョコレートを置いた。
「え、なんですかこの新鮮な野菜は!」
「これが、『死地』で採れた野菜?」
エミーさんの部下二人はアリスに出されたカットした色鮮やかな野菜を見て、目を見開いていた。
「頂いていいんだね?」
「もちろんです。どうぞ」
「おいしい。瑞々しく、ジューシーで甘みもある。な、なんだこの野菜は?」
「エミーさんが今食べたのは、トマタですね」
「トマタ? いや、そんなことはないだろう。確かに、見た目は似ているが、旨味がまるで違うぞ」
エミーさんは俺の言葉が信じれらなかったのか、眉を寄せてカットされている他のトマタを見つめていた。
すると、エミーさんの様子を見ていた部下の二人も同じようにトマタを口に運んでいく。
「うまっ! 何だこの野菜!」
「これ、グラン大国の貴族間でも出回らないくらいの旨さじゃないすか⁉」
部下の二人はよほど感動したらしく、皿に盛られたカット野菜をかきこむように食べいた。
ドレッシングも何もかけていないのに、そんなにがっついてくれるとは……よほど美味かったんだな。
俺はそんな二人の反応を見て笑み浮かべながら続ける。
「あとは、こっちにお酒と甘味を用意しました。グラン大国への献上品として、お受け取りいただけますか? 少量ですが、皆様の分もあるので」
俺はその流れに乗るように、カグヤが持ってきてくれた酒とチョコレートをすっとエミーさんたちの方に差し出す。
すると、エミーさんはそれらに視線を落とした後、じっと真剣な眼差しを俺に向けてきた。
「……もちろん、タダで土産をくれるという訳ではないのだろう?」
エミーさんの言葉を聞いて、カットされた野菜を掻きこんでいた二人の手がぴたりと止まった。
どうやら、エミーさんにはこちらの考えが初めからバレていたみたいだ。
俺は小さく息を吐いてから、言葉を続ける。
「将来的なお話をすると、グラン大国に『死地』が国であるということを認めて欲しいんです。大きな後ろ盾が欲しい。でも、メリットがないとそんなことはしていただけないでしょう」
「まぁ、当然そうなるだろうな」
エミーさんはそう言うと、俺の言葉に小さく頷く。
国を作ろうとしてはいるが、今はただ内々で話が動いているだけだ。タダ自称しているだけの状態と言ってもいいだろう。
だから、それを他の国に認めてもらう必要がある。そして、それはできれば隣国の中でも権力が大きな国がいい。
その条件に一番合うのが、グラン大国なのだ。
俺はエミーさんがじっと話を聞いてくれているのを見て、話しを続ける。
「ですので、今は我々と貿易をすれば良い物が手に入るというメリットを提示しているだけです。お土産に色々と詰めていくので、今回は後ろ盾をするに値するかの判断材料にしていただきたいんです。後ろ盾をするのは難しくても、貿易関係だけ続けたいというだけでも構いません」
「……なるほど。先行投資という訳か」
エミーさんは合点がいったのか、大きく頷いてから箱入りの酒を手に取ったり、チョコレートをしばらく観察してから短く息を吐いた。
「分かった。何とか話はつけてみよう」
「本当ですか! ありがとうございます!」
「でも、期待はしないでくれ。あくまで、報告をするときの資料の一つとして王国に提出するだけだからな。副団長の権力はそんなにないんだよ」
エミーさんはそう言うと、仕方なしと言った様子で笑みを浮かべた。
こうして、初めての他国との接触は案外悪くない感じで終わることになったのだった。