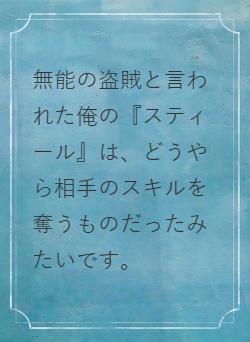「よっし。とりあえず、土は全部巻き終わりましたね」
俺は慣れない畑作業をしたということもあって、息を切らしていた。
しかし、ただ疲れたというだけではない。俺は目の前にできた急増したとは思えない畑を前にして、思わず口角を上げてしまっていた。
まぁ、まだ土を撒いただけの状態だから、畑と呼べるのかは疑問ではあるが。
「旦那様、少しお休みになられては?」
「そうだよ、ご主人様。明日全身筋肉痛になっちゃうよ?」
俺が肩を回して小休憩していると、アリスとカグヤが心配そうに俺の顔を覗いてきた。
俺はカグヤの言葉を聞いて、前世での記憶が一瞬よぎった。
農作業って普段は使わない筋肉を使うから、翌日辺りに変な所が筋肉痛になるんだよなぁ。
でも、今は子供の体なわけだし、筋肉痛になったりはしない気がする。きっと、子供ならではの長回復で何とかなるはずだ。
「だ、大丈夫でっしょ、多分。それに、せっかくならこれも使ってみたいし」
俺はそう言うと、近くにあった仕様変更をした耕運機を手に取る。俺が耕運機を触って使い方などを確かめていると、ラインさんたちが使い方が気になったのか近づいてきた。
「あの、メビウス様。これは一体、どんなものなんですか?」
ラインさんは耕運機を見て首を傾げていた。近づいてきた人たちの顔を見てみると、ラインさんと同じような反応をしていたり、未知の機械を前にワクワクしていたり人たちがいた。
俺はそんな人たちの反応を見て、少しだけ得意げに胸を張る。
「それでは、この耕運機の使い方を教えましょう。まずは『耕す』モードから」
俺が耕運機を軽く撫でて言うと、耕運機がぴこんっという音を上げた。この耕運機はお掃除ロボットの時同じく、ある程度音声認識で操作することもできる。
それから、俺が軽く耕運機を押すと、耕運機は静かな音を立てながら進んでいった。
ショッピングカートを操作するときのように軽いのに、耕す力は力強く簡単に畑が耕されていく。
「「「おおっ!」」」
すると、耕されていく畑を見ていたラインさんたちが声を出して驚いていた。
普段手作業でずっと農作業をしてきた人からしたら、夢のような光景だろうなぁ。
俺はそんなことを考えながら、鼻歌まじりに畑を耕していく。
「まぁ、市販の土ですからそこまで耕さないでもいいかもしれませんけどね。そして、欲しかったのはこっちのモードなんですよね。『畝立て』モード、植える野菜は『トマタ』で」
俺は一度耕すのをやめてから、音声認識でモードの変換を行った。すると、耕運機の形が自動で変形していき、畝を立てるためのアタッチメントを装着した形になる。
畝というのは畑とかにある土が盛り上がっている部分のことだ。畝を作ることで、水はけを良くしたり、根の張りが良くなったりとか、いろんなメリットがある。
野菜によって高さや広さを変えたり微調整をしたりするくらい、畝は畑をやるうえで重要なのだ。
『トマタ』というのは、前世で言うトマトのような野菜のことだ。栽培も難しくはなく、以前にラインさんたちが作ったことがあるとのことなので、一番初めに植える野菜はそれにすることにした。
俺が軽く耕運機を押すと、耕運機が動いて自動で畝を形成していった。俺は振り返ってその光景を確認して、感動して声を漏らしてしまう。
そして、どうやらその光景に感動しているのは俺だけではないみたいだった。
「おい、見ろ! あんなに簡単に畝ができてるぞ!」
「凄いな……あれなら腰を痛めることもなさそうだ」
「これがメビウス様の発明品なのか!」
ラインさんたちは簡単に畝が作られていく様子を見て、また驚きの声を上げていた。
そうなんだよなぁ、畝を作る作業って地味だけど結構疲れるんだよなぁ。俺は前世の実家で農作業を手伝っていた経験を思い出して、ラインさんたちの気持ちにしみじみと共感していた。
俺はある程度畝を作り終えると、耕運機を止めてラインさんたちの方に振り返る。
「こんな感じで畝も作れるので、随分と農作業が楽になると思います。あとは、専門的に農家をやってきたラインさんたちに任せたいんですけど、大丈夫ですか?」
「お任せください! 必ずや、メビウス様のご期待にお答えいたします!」
ラインさんはそう言うと、俺と耕運機の操縦を変わってきびきびと働き出した。そして、それを見ていた周りの人たちも自分にできることを探して働き出す。
「旦那様。『家電量販店』にあった水場からホースを引いてきました!」
そして、少し経った頃にアリスがホースを手に持って現れたので、そのホースをラインさんたちに渡してもらった。
あんまり俺たちにずっといられてもやりずらいだろうし、農業のプロがこれだけいるのだから後は任せた方がいい。
そんなことを考えて、俺とアリスとカグヤは次にするべきことの話し合いをしに一度『家電量販店』に戻ることにしたのだった。